| 芸術に於ける写実の問題(第三回) ――特に演劇におけるそれを中心にして―― 吉田正吉+熊谷 孝+乾 孝 |
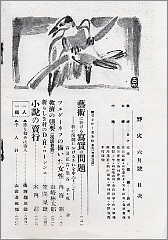 前の二篇によって、私たちは過去の演劇における写実の実践が、その目指す観客層の世界観――従って人間把握――の歴史的な宿命によって限定され乍(なが)ら、その各層の成熟と平行しつつ発展して来た有様を看(み)て来たのだった。そこで今度は現代の演劇のリアリズム論の在り方を同じ方向から検討しなければならない。 前の二篇によって、私たちは過去の演劇における写実の実践が、その目指す観客層の世界観――従って人間把握――の歴史的な宿命によって限定され乍(なが)ら、その各層の成熟と平行しつつ発展して来た有様を看(み)て来たのだった。そこで今度は現代の演劇のリアリズム論の在り方を同じ方向から検討しなければならない。まず、リアリズムが、それとして、はじめての意識的にとり上げられ、論議されたのは、人も知る様に、新劇においてだった。が、その論議そのものの検討に先立って、新劇の発生した史的必然性に遡(さかのぼ)って考えて見る必要があるだろう。 Ⅰ 新劇は、小山内氏史等によって、まず基石をおかれたといってよいだろうが、氏が、或日の事、突然その様な事を思い立ったにしても、これを待ち望んだ一群の人々を前提することなしに、氏の試みが公式に脚光を浴びる訳には行かなかったに違いない。当時、(一九二四年)大戦後の諸状勢に条件づけられて、充分成熟した小市民的知識層が、自分達の為の芸術を待ち望んで模索していた頃だ。 旧態依然たる歌舞伎は、また新派すら、もはや彼らの世界観をもっては容認し難い、封建的モラルと、非現実的な表現とによって、彼等を閉め出していたこの辺の事情について新協の「演劇論」(鈴木英輔氏)の説くところを引けば――まず、団十郎によってひとたびは写実に赴(おもむ)こうとした歌舞伎「『活歴』即(すなわ)ち活きた歴史劇は、従来の出鱈目(でたらめ)な歌舞伎の伝統を排し、全(すべ)て正しい史実に則(のっと)り、その史実の通りに演出する事を特徴としている。それは明治期にまで伝統を残していた、封建主義者達、即ち藩閥政治の為政者達によって多く支持せられたるは当然であった。然(しか)しながらこれらの高尚な歴史劇は、それ自身としては此の時代に勃興せる新興ブルジョアジーの演劇たることが出来ず、かえって後には単にこの封建主義を擁護するという立場に変じて来る」そうして「明治三十年以後の歌舞伎は、遂(つい)に全ての新しい動向を捨て、かつて捨てようとした古典的なものに復帰してしまった。」 また、一方、「日清戦争により勢力の急激な進歩を遂げ、かつ国会の開設等によって確固たる地歩を社会的に占むるに至った日本のブルジョアジーの要求は、明治三十年代の此の新演劇の上に一つの転換をもたらしている。単純な政治思想宣伝劇から、此の新しい演劇形態は次第に進んで新興ブルジョアジーの生活の実現や理想を舞台に具体化しようとしはじめた。」のが新派 のはじまりだが、それも「ブルジョアジーが封建主義と或る意味で妥協し合い、且(か)つ明治三十七八年の日露戦役を境にして、急速な勢の飛躍を遂げるに至って、新派はその飛躍に追随することが出来ず、その帰趨(きすう)に迷いつつ、次第に卑俗化し、その目標を興味本位の追求ということに引き下げると同時に、演目も乱雑、無定見となって行った」。その後「文芸協会」、「自由劇場」「芸術座」など新劇 運動の萌芽はきざしかけてはたおれて行った。「明瞭な支持階級を持たず、気まぐれに変転推移した時代の新劇運動は、遂に確固たる成果をあげ得なかったことはやむを得ない」という次第である。 そうしている内に、世界大戦もすぎ、迷った知識層達にの求める新しい人間把握、新しい世界観を充たす新しい演劇として、小山内氏等の「演劇の実験室」が正に生ずべき機因が必然化したのであった。 副次的な原因として、彼等知識層の優越感、欧風文化心酔なぞもあったろうが、これも同じく彼等の社会的地位に基(もとづ)いているのは勿論(もちろん)だ。 こうして、新劇は発生したが、その方向については、ただ従来の我邦(わがくに)の演劇の在り方にあき足らぬという漠然たる気持はあっても、未(いま)だ正しくかくあらねばならぬ、という規定は齎(もたら)されていなかった。そこで、当時の欧米(特に欧州)の演劇の直訳的輸入がされたのも肯(うなづ)ける話だ。当時の知識層自体が、欧州ののそれと同程度に成熟していたのではないが、とまれ(ともあれ)そこにみられる清新な感じと、全体的に見て、彼等の世界観がほぼ同方向にあったということで気軽に受け入れられたのである。 勿論(もちろん)、当時の欧州観劇大衆と雖(いえど)も、したがって当時輸入された原本たる演劇と雖も、決してリアルな、健康な方向をもっていよう筈(はず)はなかった。むしろ模索期にあったとも云えよう。いや、このことがまた日本新劇の模糊たる出発に際して、むしろ、この共通な混沌さ故に取り入れられ易かったとすら言えるかもしれない。だからこそ、翻訳劇は古典を抜かして一種の飛乗りをやってのけたのだった。また、彼等観客の、生産面から浮き上った性格は、自分達の行き処を正当に発見しえず、芸術至上主義的になり、また知的雰囲気ともいうべきものを憧れたのだった。「桜の園」も滅びて行くものと、来(きた)るべきものを冷静に、しかも温い眼で見つめるチヱホフの正しい史観からは遠ざかり、単に滅び行くものへの感傷的な哀惜として再現されたのである。(小山内氏「演出者の手帖」なぞ)紙数の関係で詳述をさけるが、とまれ、小山内氏は凡(あら)ゆる新しい可能性への開拓者的努力を払い、再三ならずリアリティについて語っているがその帰する所は決して真のリアリズムの追究ではなく、「リアリズム」すら、一つの新しい様式 としての資格でしかとり上げられていなかった、といっても云いすぎではあるまい。 話はとぶが、その後に来たものは左翼演劇の全盛期だった。この場合、さきの芸術至上主義的な雰囲気愛好家の一部は、この傾向をもまた一つの雰囲気として受入れたかもしれぬが、しかし、その中堅層がどこまでついて行けたか、ということは甚(はなは)だ疑問だといわざるを得ない。新劇の流れとして、一概に考えたがる従来の習慣からすれば、ともすれば、この観客層の移行を無視し勝ちだから、一応の注意を喚起しておきたい。尚(なお)、参考までに当時の真面目な新劇理論家の意見として、アイザクの「劇場」の翻訳者、斎藤進氏の、同書跋文(ばつぶん)を引用する。「一九二四、五年来頓(とみ)に盛んとなったプロレタリア演劇も、未だ其(その)『温室』的存在の域内にもがいている。民衆は今や、仄(ほの)かに『何者』かの出現を待望している。それがうまく現代のプロレタリア演劇を『より戯曲化』し、大衆を左旋回に迄(まで)引(ひき)きずって行くか、或(あるい)は名優の『骨董的』演技によって、再び歌舞伎の方へ舞い戻せるか、或は一九一五年前後の如くに欧米の近代的作品の渉猟(しょうりょう)によって所謂(いわゆる)新派劇がインテリゲンチャの自己満足をかい得るか、或は『大衆文芸』的『チャンバラ』の魅力に迄(まで)堕(だ)せうるか、――それは判らない。まさか一部の『幕合(まくあい)』的エロ・レヴュウのみが、飽き易い大衆を掴(つか)んで許(ばかり)も居られまい。」(一九三〇) 左翼演劇のリアリズム論がいかなるものであったかは、今、文献が手元にないので判然と言い切る自信はないが、当時読んだものの記憶からすれば、例えばメイク・アップの指導書の如きものでも、「ダラ幹(かん)の顔は(或はインテリの顔)何番のドーランで地をつくり、頬にかくかくの隈(くま)をつける」という底(てい)の甚(はなは)だ公式的なものだった様だ。これは勿論(もちろん)、当時、ズブの素人(しろうと)達まで動員して速成的に一役やらせねばならなかったという実際的な制約もあったことだろうが、それよりも、当時の彼等の人間把握の在り方を端的に示しているものと見るべきだろう。つまり、ここでは、人間はまたもや、一つ一つの類型として、単にある社会的機構を表現する道具として丁度(ちょうど)能楽における人間 が自然表現の一道具として類型化されていたのと同様に――一つ一つの地位を端的に表すマスクをもって把握されていたのだ。自然主義に於いて、社会的連帯から切り乖(はな)された個性探究に行きすぎた代償として、今度は、環境の動的批判のみが前景に押し出されて人間は再びそれを構成する単子の位置にまで押し下げられたという訳だ。これは何も我国に限った現象でないので、観客大衆の成熟に先立って芸術作品の逆作用を急ぐ場合、ともすれば陥り勝ちな困難に基(もとづ)いている。したがって、この偏(かたよ)りの揚棄(ようき)は、更に観客大衆が成熟し――或は観念的に近づいていた層と換(かわ)るのをまってはじめて問題となり得たのだ。 左翼演劇は、そうした内的な困難ばかりでなく、外的な原因によって、一九三四年の六月所謂「大同団結」論議を契機として、はじめて本格的なリアリズム論争が闘わされたのである。それはまず村山知義(むらやま ともよし)氏の「発展的リアリズム論」に対する松本克平(まつもと かっぺい)氏の反駁からはじまった。 Ⅱ その当時の情勢は、村山氏の描く所を借りれば「政治的文化的な全戦線に亘(わた)っての全般的衰退・演劇部にあってはプロットの解散・積極的部分における方針の混乱と消極的部分における『自由な純粋な芸術』への逃避」がおこり、全面的に見れば「その経済的政治的な将来に対する疑惑と絶望から、彼等(文化担当者・乾註)は不安を哲学化し、絶望を現実化している。(わが国でのシェストフやニイチェの流行を見よ。)彼等は遂に解決を求めないまでになった。紛糾し矛盾する暗い現象から明るい解決を導き出すことの絶望から彼等は遂に解決のあること自身、解決を求めること自身が、ある筈(はず)のないことのように考え出した。」従ってこの芸術は現実の世相なり心理なりの表面的現象のあれこれの記述、描写に過ぎない。覆(おお)い物をはねのけて現実の根拠を全面的に突くことは、不可能である前に彼等の意識においては許されない。」したがって「彼等のリアリズムは表面的な現象記述であり、現実の微小化をしばしばただよわせる。解決のないテーマに戯曲的解決をつけようとして、或いは人情に、遂には神秘化にたよる。」という風だったのである。しかも氏は絶望せず、「芸術的に良心的」な、しかしまだ「部分的にリアリズムの芸術家達が、逃避せずに現実に打ち向う態度」の「積極面を尊重しのばし育てよう」という意図をもって、発展リアリズムの旗を押し立てたのだった。 しからば、その発展リアリズムとはどんなものか。氏はまず「われわれは不安と懐疑との、合理的な解決を確信する。われわれはかかるリアルを芸術的に形象化することをわれわれの任務として担う。」とされ、その「リアリズムはブルジョア・リアリズムとは異(ことな)る。現実のトリビアルな複写、解決なき記述、歪曲と卑俗化と神秘化等とは異る。」そうして「資本主義団[「圏」カ]の芸術はその資本主義的制約性の中に決して或る一定の限度以上の優れた作品は生み得ないというが如き考えをもってはならない。」ので「この戦いの中の人々の典型的なタイプを現すことがわれわれの芸術の課題であり、それ以外にはない。完全に展開した現実の芸術的形象化がわれわれにおいてあり得ないということは、われわれの芸術が一定限度以下の価値しか持ち得ないことでもなく、われわれの手のとどかぬ立派な作品がどこかよそにぶらさがっているということでもない。」そこで、氏のスローガンは、「A、進歩的、芸術的に良心的な、B、観客と妥協せぬ、C、演出上に統一ある演劇の創造と提供」ということになっている。ここで我々によってとりあえず問題になるのは、B、だろう。観客について村山氏はどう考えているか? それは次の章句で明らかだ。 「私は(村山氏)大同団結の提案書において、いい芝居であれば即ち大衆的である筈だ、というような、芸術の大衆化論の卑俗化に抗して『最大多数の大衆は意識的文化的に最低の水準にある』という残念な事実に注意をうながしたのである」とし、この点について、「演劇を愛好する教養ある狭少の観客を対象とすると云う」のは「遺憾ながら審美主義であり――ドグマであり――演劇を形式主義化し卑俗化させる危険をはらんでいる」という松本克平氏の異議に対し「人はこの事実から回避してはならぬ。この事実こそは封建的機構と資本主義機構との重大なる害悪であり、最大多数の大衆を意識的文化的に最低の水準に置くことこそ、それらの機構が自己保存のために全力を尽していることであり、さればこそ大衆とわれわれとの憤(いきどお)りと戦いとがあるのだ」と駁(ばく)しておられる。で、氏は「むろんこういう観客を軽蔑するのではない。ただ、観客の質と量との変化を見落さず、(誤記?乾)かかる観客を急速に量的に拡張してその即時の理解と享受とを期待しようとすれば、われわれは欲すると欲しないとに拘(かかわ)らず卑俗化の危険にさらされなければならない」と注意しておられるのである。 そこで、それについての氏の実際的解決案として本公演と通俗公演――松本氏の所謂「驚くべき二元論」――とを区別(これは「具体的相対的な区別であり、観念的絶対的な区別ではない」のであるが)して行い、「よい芸術品を大衆に示すことが基本的な問題であることはもちろんだが、われわれは更にそれを解りよくし、その成果を定着し、われわれの側に引き寄せ、親切な関係となることにあらゆる努力を払うべきだと説いておられる。(以上の引用は凡(す)べてテアトロ 35.9の村山知義氏論文「進歩的演劇のために」より) Ⅲ 越えて三六年三月テアトロ誌上に書(かか)れた、松本克平氏の「リアリズム強化の為めに」は「再び発展的リアリズムを評す」という傍題にも見られる通り、上述の村山説を、殆(ほとん)ど全面的に批判し不満をのべたものだった。即ち、氏は「歴史の合法則的な発展に対する理解と芸術家の良心を尊重することを以て足れりとしている『発展的リアリズム』をブルジョア的リアリズムのカテゴリーに止まるものとして批判」し、この不満を充たすものとしての氏のリアリズムが「過去から現在までに到るリアリズムの歴史を、社会的経済的諸関係の歴史的な段階の反映という点に見出す。」と規定し、更に「われわれのリアリズムの正しさは、現在の歴史的段階では反資本主義性にあると考える。」「われわれのリアリズムを『現実の真実』のための即ち現実暴露のための『典型的環境における典型的性格』のための創作方法として抽象化してしまうなら、バルザックやトルストイの革命的ブルジョア・リアリズムを凌駕(りょうが)し過去のリアリズムの全成果の上に立ちながら、しかもそれらと決定的に異(ことな)るものとして、われわれのリアリズムの基本的差異を何等みとめていないものと云わなければならない。かかる過去の一切のリアリズムから学びつつ、われわれのリアリズムは『現実をばその……発展の過程において、性格に歴史的に形象化』することを要求すると同時に『勤労大衆を』『改造し教育する』課題と結合されなければならない。」というのである。で結局、村山氏の三項目(前述)についてはAの「進歩的」とか「良心的な」とかいう「抽象的な概括は何等リアリスティックな演劇の基準にはならない」し、B「観客と妥協しない、とは何か? 演劇が観客と不即不離なものである以上、取り立てて観客の問題だけを切り離して妥協するしないを看板にする必要はない。われわれの演劇はそのリアリティの故に、現実の本質に触れている故にリアリスティックな観客層の支持をうけ、」ているのだと駁し、最後に演出の統一については、それはどの演劇においてもあることで何の特徴にもならぬと斥(しりぞ)けておられるのである。したがって、村山式二元公演は松本氏によって、つとに否定しさられたのだった。(この点、上記村山氏よりの引用参照) ご覧の通り、両氏共、観客を意識的に問題としてとりあげつつ、そかもその点において全然対立した結論を来たしているのは何故であろう。リアリズムの意義そのものに対する両者の意見のズレも畢竟(ひっきょう)この点(観客に対する働きかけ)に根ざしているのを思えば、この問題の重大さは言を挨(ま)つまい。尤(もっと)もこれを論ずる前に、われわれとしては当然、何故、あたかもこの時に至って始めてリアリズムの論議がこうした形でまき起こされたのであるか、という根拠を究めなくてはならぬのだが、今、これに就いて詳述すべき自由を持たない。ただ、これを決して単に理論そのものの直進的な発展としては解釈出来ないという事――広い意味での観客の問題であることを指摘するに止める。序乍(ついでなが)ら、こうした論争がその後三八年度における様々のリアリズム論議から姿を消し去ったのも、この問題が、論理的に批判済みとなった為ではなく実は、三八年代における新劇が、既にその観客の構成を異にし、全然一元的な、インテリ観客層を対象とするに至った為だったこともここにつけたしておこう。 話は前に戻るが、村山、松本両氏によって代表される、当時のリアリズム論は、「進歩的インテリ」と「勤労大衆」を倶(とも)に観客として考えなくてはならなかた当時の新劇の、この二層の鑑賞力の乖離(かいり)に対処する悩みの表れだった。で、村山氏は、引用の如く、「意識的文化的に最低の水準にある」「最大多数の大衆」を引上げる手段として、ヨリ大衆的な臨時公演その他を主張し、しかも、これによって進歩的文化層を失望させぬ為の注意をしている。ここに「反卑俗化」なり「観客と妥協しない」なりが重要になってくるのだが、松本氏は「演劇が観客と不即不離なることを指摘して、そこから直(じ)かに村山氏の様々な心づかいを無益有害のことと断じておられる。このことだけから見れば、村山氏の方が観客に対する 看方(みかた)がよりリアルだったと言ってもよかろう。しかし乍(なが)ら、その眼目たる「大衆の向上」と「反卑俗化」に関する限り、松本氏の指摘するのも無理のない割り切れなさがあるのもまた争えない。つまり、臨時公演は或る程度に調子を下げた(文字通りそう書いてはいないが)公演であると解されても仕方がないし、事実またその通りだったのである。これは結局、松本氏と同様リアリズムというものが、観客をまたずして作品に於いて完結し、これを、良質の 観客ならば誰が見てもそのリアリティを把握出来る筈だという――究極において観客の歴史社会的本質を見ずして、その「理解力の高さ」を抽象的・現象的に論じた点では、松本氏から一歩も出てはいないのである。(これが単に高さ ではなく、方向である事、したがってまた、リアリズムなるものが、観客の生活面から切り離して論じ得られぬ事はのちの章でのべる。) Ⅳ 同誌三七年七月に表れた久板栄二郎氏の「リアリズムに就いて」は「問題をより具体的に」と傍題しただけのことはあって、この点非常に卓(すぐ)れた洞察を見せている。即ち、インテリの教養・合理主義が我々インテリゲンツィアに、民衆文化の批判者として、その向上のための代行者としての資格を付与するものであるが、然(しか)し一方両者の間の文化的懸隔のはなはだしさが、ややもすれば我々の仕事を民衆から遊離させる危険を伴いもするのだ。現在の新劇が、広汎(こうはん)な大衆を観客として吸引することが出来ずに、主としてインテリゲンツィア層に限られている根拠は、勿論技術の未熟さとか、外部からの妨害とか観客動員のための組織的手段の欠如等に条件づけられていることは云うまでもないが、他面、我々の演劇そのものが、その題材に於(おい)て、大衆から遊離したインテリ趣味に跼蹐(きょくせき)している点に条件づけられていることも見のがしてはならぬ。 「民衆の低卑な趣味に迎合するのではなく、然し、頭からそれをドヤシつけることもなく、それに即しつつ、それを批判し、徐々に高めて行くことこそが芸術家に課せられた任務なのだ。」「我々は上述した様なハンディキャップを有(も)つ自分たちインテリゲンツィアの狭い趣味性に囚われて『きれいごと』に終始することなく、或場合には、差当り卑俗な悪趣味にまつはられてはいるが、その中にこそ将来の発展性ある健康な、力強い芽生えを宿しているところの、民衆の生活に深く根ざすため、身をもって泥まみれになるだけの覚悟が要るのではなかろうか?」と。これは正に当時のリアリズム論の特記すべき最高点だったと云わなくてはならない。尤(もっと)も、この論述と雖(いえど)も、その主な功績は、専(もっぱ)らそれがインテリの効用の限界性を自覚した点に止まり、真に明らかにすべき課題、大衆化と卑俗化の問題について、苟(いやしく)もリアリズムの芸術たる以上、その問題も、表現技巧も、全て、その観客大衆の生活場面の現状の究明に立ってこそ、はじめてなしえられる事であり、したがって正しく選ばれた中堅観客層の特性を無視して高下を論ずることが、全く趣味論争に畢(おわ)らざるを得ないことを明(あき)らかにする為には必ずしも充分な論考だとは言いきれない。大衆を惹(ひ)きつける為に自ら「泥まみれ」になることが、方便として 合理化されているだけで、その本質的な意義が――即ち、大衆の生活面における問題 を積極的にとりあげることが、決して「調子を落とす」事でない所以(ゆえん)はすこしも自覚されていないのだ。これでは村山氏を超えること余り遠いとはいえない。しかし、氏は「形式と内容が不可分の関係にあることは云うまでもない。我々の作品の平凡さ、低調さというものは、実は我々の現実観察の浅さと結びついていたのである。」「この関係を無視して、様式の解決を急ぐなら、形式主義の誤謬(ごびゅう)に陥るだろう。」という正しい反省をしておられる。これから推して、「泥まみれ」になってよいのは、決して単に表現様式のみではなく、題材・内容共にそうある可(べ)き事を考えておられると見てよかろう。とすればまた「勤労大衆が……芝居を見て、行為と劇的盛り上(あが)りによって感銘を受けるのは、彼等の生活の中で養われた思考方法であり、生活感情である。我々は彼等のこうした心理に即して力強いドラマを構成しなくてはならぬ。」といわれる場合、これが単に表現の技術的な面のみが強調され過ぎる様に思われる。即ち、或る一定の内容を、相手の方言によって伝えよう、という意図だけあって、その訴えるべき題材、従ってまた内容ははじめから永遠不変の真理――とまで行かずともその時代の真実といった様な、誰にでもそのまま通用する抽象的なものが前提せられているかに見える不安がある。次に、「趣味」の高低について氏が言われる所を見るに、先(ま)ず「我が国の一般民衆と我々インテリゲンツィア芸術家との間に横(よこた)わる文化教養上のギャップ」は「単に程度の差だけでなく、質的な喰い違いをもっている。」のを指摘していられるのは卓見であるが、それに続く二三行に於いて、「民衆の日常生活」に「えも云われぬ卑俗低劣な悪趣味」を見出しておられるのはどうも合点がいかない。これでは何か普遍的に通用する「趣味の高下」に関する物尺(ものさし)がアプリオリに前提されている様に聞こえて困る。歴史的年齢を異にした各層における趣味は、その問題 と同様、「質的な喰い違い」があるので、それらを担う各層の歴史的役割を無視して、抽象的な高下を論じられる筋合いのものではない。この点への反省を欠く所にこそ、インテリゲンツィア自らの趣味判断をもって至上絶対の物尺と思い上り、民衆のそれを無条件に「卑俗」断ずるに至る誤謬の因(もと)があるのだ。この様に、観客から遊離した、小部分の者達の趣味判断に基(もとづ)いた卑俗問答と大衆化の問題とがうまく折合いがつく筈はない。従ってまた、「調子を落す」ということ、「泥まみれになる」ということについても、単なる趣味的な印象と把(と)り上げた問題の客観的な価値との混同はむしろ必至という可(べ)きだろう。これは評価軸の恕(ゆる)し難き混乱といわなくてはならない。 Ⅴ 芸術作品の評価の問題は、我国でも古い問題で、私たちの主張もくわしくは一昨年「文芸学への一つの反省」(文学九月・三人共著)に述べたつもりだが、ここに亦(また)問題となるのは、古典再評価の問題である。即ち、久板氏の前掲論文にも「過去の様式からの継承と、新しい内容との弁証法的関係に依(よ)って」古典の「様式からよきものを摂取する努力を惜しんではならぬ」といわれており、「新築地文芸部のもとに持たれているシェークスピア委員会の仕事に」「大きな期待をかけている」と述べておられる。このころからそうした意図をもって、古典を再検討する為に、新しい脚光を浴びせて舞台にのぼせる多くの試みがなされたのは人の知る処だ。ここに、私たちが度々強調した「研究することの価値」の相異が深く反省される必要が起こってくる。 作品を、一身上の立場から鑑賞することと、科学的に、公けの資格において検討することとは全然別のことだ。鑑賞主義者達の常識である様に、ある作品に対する一身上の感想をもって、その研究の方法的前段階におくこと、従って、作品の芸術的価値を、それによって自らが心を打たれた度合から出発して判断しようとすることは、歴史社会的な存在としての、本来の鑑賞者をぬきにして、作品をそれのみによって完結したものとして考察することに基因する誤謬である、ということこそ当時から私たちが極力主張した処である。シェクスピアなり、モリエエルなりの「様式からよきものを摂取」することが現代的意義をもつということと、それらの作品をもって現代の観客層に訴える意義があるということとは、必ずしも恒(つね)には一致しない。古典の上演が、劇団自身の実験的研究として意味を持っていたことは疑うべくもあるまいが、娯(たのし)みの内に人生への認識を深めようとする観客大衆にとって、まず全然娯(たのし)めなかったことの理由は此処(ここ)にあるのでなければならぬ。 とにかく、目指された、観客中堅層の歴史社会的特性を捨象して作品の働きを考察する手落ちが、その「大衆化」論の場合にも、この「古典再評価」の場合にも禍根となっている。松本氏が、さきに引用した様に「われわれの演劇はそのリアリティ故に、現実の本質に触れている故にリアリスティックな観客層の支持を受け」ている、と断じておられる時、リアリティの抽象的な永遠性(?)への妄信が無意識に働いているのは明らかだ。しかし、こういうと、それではお前達は相対主義だといわれるかもしれない。そこで、実証的な調査からの裏書きをしなくてなならない。 Ⅵ 私達は一昨年末から、東童その他の協力を得て、児童の観客としての特性について調査を行っている(第六回日本心理学会・「映画演劇の観客としての児童について」乾報告)。その結果を総括して今にとって重要な点は、「児童の生活の、大人にとってはリアルと思われる再現が、必(かならず)しも恒には児童に訴ええない」ということだった。例えば、東童映画「虎ちゃん日記」にインサートされる日記の文字や絵の「子供らしい」装(よそ)おいは、子供達からは「下手な、デタラメみたいな」ものとして非難されたし、劇「少年部隊」で一つのくつろぎとして使用され、大人観客に対しては成功した「僕のかちゃん女にしちゃ強い方や」という科白(せりふ)のフモールも、子供達からは何の反応も呼びおこしえなかった。後者が、子供達から見ても、ホントにどの子でもが言いそうな――リアルな科白であることは確かだろうが、部分的にリアルなものが必しも登場権をもっているとはいえない。此処で大切なのは、その部分真実が、如何なる文脈で登場しているか、ということだ。この科白のフモールは、大人の眼で見た子供の無邪気さにある――つまり、大人の立場に立って始めて解しうるものなのだ。子供の無邪気な間違い、生意気さ、なぞの、大人的観点からの鑑賞の仕方を、子供に強いて何になろう? また、それがどうして可能だろうか? 「風の又三郎」は、子供のファンタジイをリアルに描いた傑作だが、その面白さは、リアリティとファンタジイとを明確に前提した上でこそ娯しめるものなのだから、子供達が「何だか訳が判らなくて気味が悪くなった」(五年女生の作文)り、「三郎はどうして風が吹くのを知っていたのだろう。ラジオの天気予報でも聞いていたのだろうか?」(六年男生)と疑ったりしているのも無理のないことではあるまいか。それが、手法として如何にリアリスティックな描写をとっているにもせよ、こうした面白さを狙(ねら)いとして持ち、児童に押し売りすることが果してリアリズムだと言いきれるだろうか? 大人に向けて訴えたにしても、子供のリアルな生活に、単に「詩」を感じようとする態度については疑問の余地が大きい。 以上は、児童演劇についての事実だが、同じことを新劇大衆化について、も一度反省する必要はあるまいか。同じ勤労大衆のリアルな再現を意図しても、その感銘の文脈如何によっては、何等大衆をうち得ないのは寧(むし)ろ当然のことだ。「綴方教室」に原作をかりた種々の公演――新築地・新宿再公演・笑の王国・東宝映画の各常設館での調査から見ても、いかに築地のインテリファン・日比谷映劇の山の手人種が深刻がりの思い過ごしに傾(かたよ)っているかということ、一方江東(こうとう)の人々が健康な感情の動きと即物的な判断を有(も)っているかということが判る。 重ねて言うが、私たちは、大衆を、インテリ風深刻がり趣味にひきずることを、彼等の向上と混同してはならない。彼等の内にある健康なモラルを、リアルに発展させることこそ、そうして、その為に、彼等の感受性に最適した表現様式によって訴えることこそリアリズム芸術の課題であることを確認しなくてはならない。それをすることは、何も泥まみれになるという様な悲愴なことではない。最も理性的な、迷う可(べ)からざる大道を歩むことなのだ。 「彼等の感受性に最適した表現様式」なぞというと「調子を落とす」とか「観客と妥協する」とかいうこととして非難される向きもあろうからくどく言うが、例えば児童演劇における観客が、その必然的段階として自己中心的であること、従って、それへの働きかけは、その自己中心性に応じた表現を要請されるということが、何も、彼等を甘やかすことではなく、却(かえ)ってそうした表現によってのみ、彼等の自己中心性を徐々にため直おして社会性ある大人たらしめる様な内容をも、誤りなく訴え得るのと事情は同じことだ。 Ⅶ さて、話は戻って三八年度の論争に移る。この辺の社会情勢については、今更喋々(ちょうちょう)するまでもなく、誰でも知っていることだが、結果したものは、新劇興行成績の未曾有(みぞう)の隆盛と、リアリズム論争の末梢化だった。これは、(先にものべたが、)いろいろの理由で新劇ファンがインテリに一元化したことが、そのリアリズム論の論点移行の最大原因でなくてはならない。また、インテリそのものも変化している事は争えず、同じ新劇とは言い条(じょう)「文学座」なぞはインテリ向新派として観客層を確保しているのである。 「火山灰地」は村山氏の言によれば、画期的なリアリズムの前進だとされているが、それに就いての論議の重点が、炭俵(すみだわら)の大きさの論争に集中(?)されたのなぞは実に悲劇的だが、当時の水準を最もよく示す見本だろう。(帝大新聞 6月より7月にかけて、久保栄氏と布施辰治氏の四回に亘る論争、文芸 刈田新七氏など) こうした瑣末(さまつ)化が決して演劇の分野に限られた偶然の現象でないことは、同年「学芸」誌上に闘わされた芸術一般についてのリアリズム論争をかえり見れば明らかであろう。問題は芸術的真理と科学的真理との一元性に関するすこぶる高邁(こうまい)なものなのだが、偶々(たまたま)石原辰郎氏(学芸 38.4「ありのままにみるということに就て」)が例にとった枇杷(びわ)の雄蕊(おしべ)の数が間違っているのを発見した後のリアリティの低下した話にひっかかって甘粕氏、上野耕三氏などがいろいろ論じ合われたのである。(学芸 38.7「芸術的映画と科学的映画」上野耕三氏、学芸 38.9「芸術の写実について」甘粕石介氏、その他) 甘粕氏の、科学と芸術との違いについての論に対する私たちの不満は今までにも述べたが(文学 37.9「文芸学への一つの反省補遺」)簡単にいえば、氏が理解者側(読者・観客)の積極的な役割を無視して、作品をそれ自体に於いて完結した、その内に不滅の内容(真理)を包含したものの様に考え、「真理を反映する度合」なるものを抽象的に論ぜられる点にかかっているのである。この欠点が、科学的に見て、枇杷の雄蕊が二十本ある以上、芸術的表現に於いても二十本描かれなくてはならぬ、という底(てい)の素朴な「自然科学主義」に陥る因(もと)をつくっているのだ。「二十本」ということが絵画的に表現された枇杷の花において、どういう意味をもつか、という反省がされなくてはならない。二十本忠実に描かれた雄蕊は、それのみでは単に部分的真実にすぎない。部分的な真実を出来る丈(だけ)多く集めれば、それ丈全体としても真実に近くなる、という様な機械的、単子論的な前提がここでは無意識にもせよ無反省に働いているのではあるまいか。いや、それよりも二十本の雄蕊という表現が、直接そのままで科学的真理の位をおかしている点が問題なのだ。科学的に表現された雄蕊の記述も、それを理解するものの体験による裏づけを無視して(これこそ観客を抽象する演劇論議と同じものなのだ)表現された真理を云々するところにこそ、一面甘粕氏の如くデフォルムの合理化への困難を来(きた)し、他方上野耕三氏の如く芸術と科学の対象が異なる とせねばならず、戸坂潤氏の如く、本質が二つある と断じなくてはならないそもそもの禍根があるのだ。 科学的表現は表現の面に徹してその抽象性を自覚してはじめて具体的になること、例えば設計図のようなものだ。シリンダーの断面図は、動きは勿論、その重量感も、立体感さえも直接には包含していない。それなのに、いやそれ故にこそ、その動き、重量、形態を最も精確に理解させ得るのだ。その為には見る者の体験的裏づけが必要である。見る者の表象力を挨(ま)って初めてそれは表現として完成する。その断面図が、他の凡(あら)ゆる要因を捨象したものであるという、その抽象性の自覚によってはじめて具体的な表象を再現しうるのだ。一方、運転しているシリンダーの絵は、その動き、重量感、厚みから物質感に至るまで直接に見る者に訴える。それを見ている者の時空的規定は融通され、全体感として迫るのである。しかし、これも見る者の体験の裏づけなしにはただの絵の具の混乱に過ぎない。動き、その他を感じるのは見る者の側にある。彼等見る者の既得体験を前提して、これを計画的に喚起するのだ。だから、芸術作品においては理解者の生活体験による規定性が、特に大きな役割をもつのである。さてこの絵は、全体感をもって迫るけれども、実はこれ亦(また)抽象的なものなので、或る仮定された一視点からの遠近法に従った一面だけを、或る一瞬において把(とら)えたに過ぎない。しかも、そのシリンダーを、生活的現実面において体験する者は、決して、そうした一点、一瞬の体験として把握する場合はありえない。その時空四次元の渾然(こんぜん)たる現実体験を二次元の画面に再現する場合、画家はいかにしてその捨象次元の補償を行うか? そこに時、空両面におけるデフォルムが要請されるのは当然だ。回転している車輪のヤ(輻)は平板として描かれ、各槓杆(こうかん)の位置は変換されなくては回っている様に見えない。 この場合二十本の雄蕊論はいかなる要求を出すつもりなのだろう。 Ⅷ 芸術的表現は、現実の再現ではなくて、実は移調なのだ。こうした移調によって、その本質を理解者の内に喚起するのでなくてはならぬ。従ってこれを単子論的に追究すれば混乱するのは決まりきった次第なのである。だから甘粕氏(前出)の様に、芸術における写実を「さまざまの点においての現実との近似 である」とされれば芸術は要するに見かけ上のもの(仮象)にすぎない。ありのままを映すといってもこの限界においてのことである」[引用開始の 「 が欠落している。]などということになる。ここで、「学芸」一派の人達が多かれ少かれ単子論的な見方を有(も)っておられるのではないか、という危惧がおこる。と、丁度、38年10月に同誌に山田坂仁氏がゲシタルト心理学の批判をしておられる。横道にそれぬ様に、今の所に直接関係する所だけを論じるが、要するに氏は、ゲシタルトが、単子論的な統覚心理学の立っていた「模写説的立場」を棄てたことにたいして不満をのべておられる。ゲシタルトが観念論的に傾(かたよ)っているのは間違いないが、しかし、単子論的心理学の拠っていた「模写説」とは何んなものか? それは氏も説いておられる様に、機械的な恒常仮定に立っているものだった。つまり、一定の部分刺激が、恒に同じ部分感覚を生じ、その統合が知覚を構成する、という仮定に立っているのである。なんだか先刻の甘粕氏式リアリズム論に似ているではないか。しかし、この仮説はゲシタルトの業績によって完膚(かんぷ)なく撃破されてしまったのだ。ド、ミ、ソという音型はの[「はの」は「の」カ]印象は、ソ、シ、レという――部分的要素に於いては全く異(ことな)る音型に移調され、部分的要素から見れば遙かに同じ部分の多いト[「ド」カ]、ファ、ソなる音型とは全く異る。つまり、同じ部分刺激の有つ意味が、その全体的文脈に規定されて、全く異ったものに転化するのである。 以上から推して、「学芸」の人達の模写説なるものが甚(はなは)だ素朴実在論的なものだ、といっても大した言いすぎではあるまい。対象たる客体を不動の、可分割的なものと仮定し、時間を超えたこの真理に限りなく肉迫すべく、部分真実を積上げようとするのだから。 併(しか)し、客体は動くものなのだ。運動こそ、その存在形式なのだ。だから、真理も前のめりな、動く真理でなくてはならない[「。」カ]客体を運動から切り離し、ある瞬間の真実を永遠の真実とすりかえること(写真を「在りの儘(まま)」の再現だなぞと考える(上野氏)のはこの戯画だ)から、真理は固定し、明日を失ってしまう。だからこそ、こうした立場に於ける写実は、過渡的な矛盾を永遠化するインテリに適(ふさ)わしく、また、現実への批判力を失った現象記述的自然主義に陥り、全体的文脈によるアクセント附[「符」カ]を失った瑣末主義に偏(かたよ)るのだ。 Ⅸ ここに、八田元夫氏の「演出論」は、ブドフキンの「芸術に於て、吾々は、最大の正確さ、最大の深化とその複雑性の最大の包含をもって表現された客観的現実の表現を、リアリズム的形象と称して居るのである」という、若干危険をふくんだ言葉をひき、正当にも次の様に註釈しておられる「――此の最大限度の正確さと云うことは、決して、根本的なものを忘れた現象形態の表面的追究を意味するものではない。もし、そうなれば、自然主義への逆戻りでしかない。与えられた現象の内在的な関係や、全体的関係を忘れた単なる現象の模写、単なる細部の追究は、最早(もはや)、リアリズムの線からの逸脱を意味する」と。で、「デテールの追究によって……「[ 「 不要カ]これを『典型的情勢に於ける、典型的性格』にまで高めて行かねばならない。殊(こと)に生きた個性を構成単位にする演劇に於ては、この典型的性格にまで到達することなしには、リアリスティックな舞台は創出し得ない」と言っておられる。これは寔(まこと)に正しい言葉で異論のあろう筈はないのだが、ただ、この「典型的情勢における典型的性格」について一寸(ちょっと)蛇足をつけ加える。 Ⅹ 前二篇以来論じて来た様に、劇中の人間の把握は、その担い手と共に漸進(ぜんしん)して来ているが、その間、その担い手に対して典型的だった性格も変化して来ている。古(「もと」カ)のは典型的でなかった、なぞとはいえない。その典型が客観的に見て進んで来たのは、彼等の世界観の進歩による人間把握の深化なのだ。例えば、現代に於いて考えて見ても、少女歌劇の男役のリアリティはどうだろう。私たち成年男子が見れば、あんな嘘っパチな男性の表現はないにもかかわらず、あれは少女諸君にとっては、真物(「ほんもの」カ)の男性よりも、よりホントの男性なのだ、というという事実を疑う訳には行かない。女性解放の中段にブラ下(さが)っている彼女たちの男性認識の浅薄さがここに反映しているのだ。大衆映画の主人公の類型についても同じことが云える。彼等大衆が嘘を承知で満足しているのではなく、彼等の現実生活における人間把握がそうなのだ。しかし、ここでも、私たちインテリゲンツィアの個性鑑賞主義的な人間把握こそ最も深い(或いは高い)ものだ、という様な自惚(うぬぼ)れを出してはならない。誰が、その生活において最も本質的な特性を見ぬいているか、という反省が第一になされねばならぬ。 ところで亦、性格は恒に或る情勢への或る反応として具現するのであって、抽象的な性格それ自体 なぞというものはない。だから、性格を描くということは、真義においては情勢を描くことと一つなのだ。そうしてまた、ある層にとって典型的と把握される性格が顕現する様な情勢が即ちその典型的な情勢なのでなくてはならない。 こう考えを進めれば、ある観客大衆に最もリアルに訴えるには、その層の現実生活において最も典型的な情勢を――例えば社会的矛盾を表すにしても、それの、彼等にとって、正に典型的な情勢において現れている所を把(とら)えなくてはならないのは当然だろう。ここでも亦、観客の生活面が大きく前景に出てくる。 最後に、それでは、いかなる芸術も、その中堅鑑賞者層にとっては、一応ホントだとおもわれるとすれば、リアリズム論はやはり相対主義に陥るのではなかろうか。そうではない。作者や、観客にとって主観的にはリアルなるが如く感ぜられる事柄そのものが、その層のもつ歴史的役割に従って、客観的にはリアルにもその逆にもなるのだ。 武田武志氏も謂(い)われる様に(学芸 38.7)「対象世界の客観的に正確な反映という性質が、芸術・美術の特質であり、芸術価値の規準である」ことは確かだが、この場合、「反映」とひと口に言っても、それが、理解者をぬきにして、抽象的に考えられている限り、観念論的な独断と、なんら選ぶところはない。「反映」とは、理解者――その作品において目指された享受者中堅層に、直接訴えることでなくてはならない」、また、ここに言う「対象世界の客観的に正確な」という言葉も、その層からの遠近法に従っての正しい文脈規定を無視して理解してはならない。これから抽象する時は、「客観的正確さ」も、忽(たちま)ち相対的な、それのみでは水かけ論的な、区々たる部分真実に墜(お)ちるのは当然だからである。 要するに、芸術における写実を、単子論的恒常仮定に立って考えてはならない。芸術表現は、客体の模写であるにしても、それは、その享受者中堅層にとっての真理を、対象の仮象的本質の移調によって、準体験として与える手段であって、これによって、彼等に正しく生きる為の正しい認識へとかり立てるものでなくてはならない。科学における本質と芸術における追究するそれとは、理解者の理解を挨(ま)って初めて一元化されるものなので、その表現が、一は規定性の面に徹し、他は融通性の面に極まっていることからくる、表現手段における仮象的本質においては異るのが当然である。(戸坂氏の本質二元論も、かく解釈すべきであろう。) 演劇におけるリアリズムも、まず、観客大衆の感受特性のリアルな認識にはじまり、その生活面における、彼等にとって典型的な性格の典型的情勢における顕現を、正しく彼等に反映する様に努めることによってこそはじめて実践されうるのでなければならぬ。 |
| ――三九・四・一〇 |