| 芸術に於ける写実の問題(第一回) ――特に演劇におけるそれを中心にして―― 吉田正吉+熊谷 孝+乾 孝 |
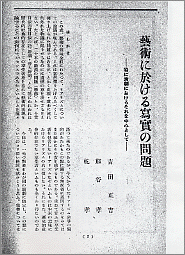 は し が き この処、芸術の領域全般にわたって、リアリズムについての論議が旺(さか)んである。これは当然択(と)り上げらるべくして択り上げられた問題ではあるが、とかく皮相・瑣末に流れ的外れな物議に陥りがちなのには遺憾の意を表せざるをえない。たとえば、二十本の雄蕋の問題(学芸)とか、十貫目俵(じっかんめだわら)四貫目俵の話。(新潮・帝大新聞)とか。既にわれわれは歴史社会的存在としての享受者層を忘れて芸術的表現を論ずることの如何にナンセンスであるかということを屡々(しばしば)語って来たのであるが、今又こうしたリアリズム論争の偏向があたかもこの点に関する無反省に基因するのをみてはまた秘(ひそ)かにその責(せめ)を感ずるものである。重ねて言うが享受者を包含しないリアリズムなぞというものは本来の意味におけるリアリズムの名に値しない。それにまた、歴史社会的存在でない享受者というものも全くあり得ないのである。 今回は、一先(ひとま)ず対象をわが国の演劇に限定し、この点についてのヨリ深い検討を試みようと思う。[第一回]能楽については吉田、[第二回]歌舞伎・浄瑠璃については熊谷、[第三回]現代演劇については乾がそれぞれ之(これ)を担当し、連作の形式を採るが、各部分いずれも共同の責を負うものである。尚(なお)、この連作を通じての実例は総(すべ)て現代演劇における写実論のための資料として役立たすことを目的として選ばれた。 能楽における写実 室町時代の土地領有制度は、衆知の如く幕府を中心とした庄園制度であった。しかし、この時代は既に織田・豊臣の時代への過渡期として、地方豪族の勢威が著しく旺んとなりつつあった頃で、従って小領主(御家人級)と大領主(地方豪族)との懸隔というものが非常に大きくなってしまうような時勢、つまり封建武士から封建領主への過渡の時代であった。ところで、経済的にはめぐまれていた豪族達も、政治的には極(ご)く限られた範囲での支配権しか与えられていなかったので、その奢侈(しゃし)品への要求は到底貢物という手続では満すことが出来なかった。こういうきっかけが地方特産物の交換を促し、手工業の発達を招き、市場の発達、小都市の発生商業資本の発生・発展、小市民の台頭と成った。一方、南北朝の頃から公家と武家の関係は一応単なる対立から離れて来たが、二朝の合一によって武家の公家への接近が一層緊密となったことは争えない。で、将軍をその主体とする足利幕府は、それ以前にみられたよりもヨリ一層貴族化されて行きつつある武家によって組織されていたものと見做(みな)すことが出来る。ところが、前述のような地方豪族の台頭は亦(また)それら諸侯と幕府との対立となって現われ、幕府は兎(と)もすれば逆に牽制されがちであった。そして、この時代こそは実に武家相互間に戦乱が繰り返されていた時代でもあった。(三代義満の治政下に於ける応永の乱、義政時代の永享の乱、下って嘉吉の乱、更に応仁の乱、及びそれ以後織田氏迄の複雑無数の戦乱)。 さて、能楽は、このような慌(あわただ)しい時代を背景として所謂(いわゆる)中世芸術の極致を展開したのであったが、その初めは人も知るように三代将軍義満の時、その絶大な庇護の下に、見事観世父子の手によって成就されたのであって、「従来の猿楽の舞に、田楽の能及び諸(もろもろ)の舞を折衷(せっちゅう)して舞ぶりを定め幾多の新曲を作為して、謡曲を興し、太鼓(タイコ)、大鼓(オオツヅミ)、小鼓、横笛等を楽器と定め、其の名称は旧に拠りて猿楽と唱(ヨ)べるも、古来より専(もっぱ)らとしたる可咲態(オカシキワザ)は、狂言として区別」(「歌舞音楽略史」・岩波文庫版)せられたのであった。「猿楽の能」は「田楽の能にむかへたる称」(前掲書)であって、発生的にはこれらの能が、もともと民衆的な動機からのものであり、それの貴族的娯楽への移行としてみられようとも、兎にかく、これから生まれ出でた観世父子の「能楽」は、鎌倉――室町時代における庶民階級と武士階級との完全な乖離(かいり)という社会情勢の下に、全(まった)き武士階級の娯楽の芸術として新しく成立したのであって、それ以前の猿楽や田楽の能が一方に未だ庶民階級を振り離さずにいたのとは全然趣(おもむき)を異にしていたという点に注目しなければならない。従って、この能楽は最初から当時の支配階級のための娯楽――幕府の御用芸術として打ち建てられたものであって、その意味で一つの絶対的な枠の中に身を狭めなければならなかった。それ故にひとたび将軍の忌諱(きい)に触れれば、世阿弥のような優れた芸術家も忽(たちま)ちにしてその最高の御用芸術家としての地位を失って、遠流(おんる)ともなりかねなかったということは別段怪しむに足りない消息なのである。「さりながら申楽(さるがく)は貴人の御出(おんいで)をほん(本)とすれば、若(もし)はやく御出ある時は、やがて始めずしては不[レ点]叶(かなわず)」(花伝・問答条々)とか「殊更、その貴人の御心(みこころ)にあひたらん風体(ふうてい)をすべし」(同)というような心構えをすら演能に際して必要としたのは、当時の能楽者――芸術家の社会的な位置を窺(うかが)うに足る一例であろう。そして、「貴所・大庭などにて、あまねくのう(能)のよからんは、めいばう(名望)長久なるべし」(花伝・花修)という風に制約されていた当時の能楽は、しかし、このような中世的限界に堰(せ)かれながらも、同じ時代からの産物 御伽草子などとは対蹠(たいせき)的な位置に在る芸術であったという点を見遁(みのが)してはならない。 先(ま)ず、世阿弥は、「遊楽の道は一切物真似なり」(申楽談義・序)と言って、芸術が物真似即ち写実であることを規定し、「一さいの物まねに、いつはるところにて、あらくもよはくも、なると、しるべし。(中略)まづ、よはかるべき事をつよくするは、いつはりなれば、これあらきなり。つよかるべき事つよきは、これつよき也[。]あらきにはあらず」(花伝・花修)と述べて、あらき 能、とよはき 能とを悪しき能として区別し、これが能楽の目標とする幽玄と相反するものであることを指摘し、これこそ実は、物真似=写実への不忠実(いつわり)に基因するものだということを戒めつつ、「およそ何事も残さずよく似せんが本意なり。」(同)と迄言い切っている。これは、実に、能楽なる芸術が一応は明らかに写実の上に立っていたということを物語るものに他ならぬが、にも拘(かか)はらず、われわれは他方において世阿弥が又、「けりやう(仮令)、木こり、草刈、炭焼、しほくみ(塩汲)なんどの風情にもなりつべきわざ(態)をば、こまかに似すべきか。それよりなほくはしからん下職(げしょく)をば、さのみには似すまじき也。これ上方(うえつかた)の御目に見ゆべからず。もし見えば、あまりにいやしくて、面白きところあるべからず。」(花伝・物学条々)と戒しめて、「似事(にせごと)の人体(にんてい)によりて浅深あるべき」(同)ことに言葉を強めているのを見落すワケには行かない。ここに中世芸術・能楽が有(も)ち得た写実の限界が見出される。これは、今日われわれの目ざしているような写実とは自(おの)ずとその趣を異にするものであることは言う迄もないが、何よりもわれわれは、こうした隔(へだた)りが何であるかを知らなければならない。 さて、ここでわれわれは一応、当時の能楽者自身がこの芸術を如何なる意欲において発展せしめようとしたかをみよう。世阿弥は、「問。能に花を知る事、この条々を見るに無上第一なり。肝要也。又又不審なり。是(これ)何として心得べきや。答。此(この)道の奥義(おうぎ)をきはむる所なるべし。一大事とも秘事とも、ただ此一道なり。先、大方、稽古(けいこ)、物まねの条々に、くはしく見えたり。時分の花、声の花、ゆふげん(幽玄)の花、かやうの条々は、人の目にも見えたれども、そのわざよりいでくる花なれば、又やがて散る時分あり。されば、久しからねば、天下に名望少なし、ただまことの花は、咲く道理も、散る道理も、人のままなるべし。されば久しかるべし。」(花伝・問答条々)と説いているが、この場合、又、「花ハ見ル人ノ心ニメヅラシキガ花」(花伝・別紙口伝)なのであり、「されば、ぬしの心には随分花ありとおもへども人の目に見ゆるこうあん(公案)なからんは、田舎(でんじゃ)の花、やぶ梅などの、いたづらに咲きにほはんがごとし。」(花伝・問答条々)であって、まことの花は決して独りよがりのものであってはならないというワケである。だから、能楽者がその芸の精進の上で対象としたのは、貴人の中の目利きなのであって、彼の一方で、「乱酒の時、俄(にわ)かに能などのあらん時の能、貴人の機嫌を伺うべきこと、またかくの如し。」(申楽談義)を初めとして、前の引例にみられるような一にも二にも貴人貴人と口にして卑屈な態度を示しているのは、この点から考えて、決して単なる卑屈とのみは言い切れないのである。さて、世阿弥の観客への配慮というものは非常なもので、「神事、貴人の御前などの申楽に、人群集(ぐんじゅ)して座敷いまだしづまら」ざる時には云々とか、夜の申能と昼の申能とのやり方をちがえねばならぬというような心尽しがみられるかと思うと(花伝・問答条々)、又、「時折節ニタウセイ(当世)ヲ心得テ、時ノ人ノ好ミニ品ニヨリテ、ソノ風体ヲ取リイダス。コレ時ノ花ノ咲クヲ見ンガゴトシ。」(花伝・別紙口伝)と述べてもいる。野上豊一郎氏も亦、申楽談義「……まさしくその座敷にての時の調子はあるものなり。此座敷にてはいかほど成るべきがよかるべきと、考へ見るべし」の註において「……それには歌う場合の事情環境というものが支配するのである」(岩波文庫版)という風に解説していられる。更に、又、「マズ、コノ花ノ口伝ニ於イテモ、タダメヅラシキ花ゾト、皆人知ルナラバ、サテハ、メヅラシキコトアルベシト、思ヒマウケタラン見物衆ノ前ニテハ、タトヒメヅラシキコトヲスルトモ、見手ノ心ニメヅラシキ感ハアルベカラズ。見ル人ニタメ、花ゾトモ知ラデコソ、シテ(仕手)ノ花ニハナルベケレ。サレバ見ル人ハ、タダ思ヒノホカニ、オモシロキ上手トバカリ見テ、コレハ、花ゾトモ知ラヌガシテ(仕手)ノハナ(花)ナリ。サルホドニ、人ノ心ニ、思ヒモヨラヌ感ヲモヨホス手ダテ、コレ花ナリ。」(花伝・別紙口伝)と世阿弥が言い、「人の心も、気をつめて見る時もあるべし。唯あら面白やと見る時もあるべし。気をつめてあは、止(と)むるよ止むるよと、満座思ふ気色(けしき)あらば、そと止むべし。大かた面白しと悠悠と覚ゆる気色あらば、きと気を持ちて、きと止むべし。当座の人の気に違(たが)へて止むれば面白し。」(申楽談義)というのは、貴人への阿諛(あゆ)から離れて、尚(なお)観客に意を注いだという半面が窺(うかが)えるのである。 また、能の「立合」という場合についても、観客の心理に対して非常に行届いた顧慮が払われているのを見る。(例えば特に花伝・問答条々条々、別紙口伝など)しかしながら、「時」の分析が、陰陽説的原理に拠り、「陰陽の和する所の堺を成就と知るべし」(花伝・問答条々)と言ったり、「因果ノ花ヲ知ルコト、キハメナルベシ。一サイミナ因果ナリ。」(花伝・別紙口伝)というような見解をとっているのは注目すべきである。ここに殊更陰陽説に準拠したような物言いをしているのは、外でもない彼等が自己の芸術を一般庶民には手の届かぬ神秘的なものであるかに偽装し、虚しき権威を誇示(?)してその生活内容の欠如を胡魔化(ごまか)そうとの悪足掻(わるあがき)なのである。これは同じ時期の貴族が、「和歌の神聖を強調する事に依って、その一手制作者たる貴族の神聖をも強調せんとする事以外には」「途(みち)が無かった」こと、しかも「その神聖化の最有効な方法は、」「和歌の宗教的解釈」であったことと同様の文脈において理解さるべき事柄なのだ。古典、たとえば源氏物語に対する中世仏教的解釈などなど。 茲(ここ)でわれわれは、世阿弥があのように深刻な注意を払った、当時の観客というものは如何なるものであったかを、もう一度振り返ってみよう。例えば、「歌舞音楽略史」の図解(岩波文庫版一二〇頁)は或時の上覧能に際して主なる観客の指定席(?)の按配(あんばい)を示すものであるが、これをみても容易(たやす)く感ぜられることは、彼等が、初頭に述べたような歴史的状勢において、既に自らの歴史的役割を果し、後退期にある層であったということである。もとより、がかる場合その中には、やがて幕府に弓引いて応仁の乱をなしたような地方豪族も打ち混っていたことであろうし、又事実上新興商業資本と結びついていた者たちもいたであろうが、兎(と)まれ、既に例上した世阿弥の言葉に現われているように、能楽者が芸の上で目標としたのは、「目利き」たる貴人であり、その世界観が、飽く迄、彼等の不生産的な、又退嬰(たいえい)的な生活面に裏づけられたものであったことは明らかである。この点を反省すれば先きに挙げた写実における世阿弥の限界も亦容易に理解することが出来よう。 彼等にあっては、木こり、草刈なども、「風情」のある限り、又、近藤忠義氏も指摘しておられるように、戦(いくさ)すら、「軍体の能姿、仮令(けりょう)、源平の名将の人体(にんてい)の本説ならば、ことにことに平家の物がたりままにかくべし」(能作者)とか、「よくすれども、おもしろき所まれなり。さのみはすまじきなり。ただし、源平などの名ある人の事を、花鳥風月につくりよせて、能よければ、何よりもまたおもしろし。是ことに花やかなる所ありたし。」(花伝・物学条々)の如く、唯風流なものとしてのみ看做(みな)された。更に、当時の社会的悲劇である子買・人買(例えば隅田川、自然居士)も、決してその客観的に社会的な根拠に触れず、単なる人情悲劇的シチュエーションとしてのみ採り上げられているし、又、中央集権の微力化による訴訟処理の遅延に基(もとづ)いて当時屡々(しばしば)発生した夫婦生別れのような事件も亦同様の取扱いによって初めて貴人たちの観賞に供されたものである。社会的には、既に後退期に在った貴人たちが、当時の社会的現実を在るがままに見つめようとは欲しなかった故にこそ、能の作り方も亦、こうした行き方を採らざるを得なかったのは当然であろう。茲において、われわれは、前に述べたような、写実における世阿弥的限界が決して彼個人の偶然有(も)って生れた天分の限界であったのでもなく、況(ま)して、能楽という芸術の形式そのものにのみ負わされた限界でもなく、実に、歴史的社会的存在としての当時の観客層によって規定された必然的限界に他ならなかった、ということを知るのである。 それだから、世阿弥における写実は、決して在るがままの姿をもって観客に迫る態(てい)のものではなかた。それは、むしろ、面白い物真似 なのであって、所詮は、「らしきこと」が狙い であった。而(しか)も、そのらしさ は、貴人の好みに投ずるような、従って又、彼等の観念した限りでの炭焼らしさであり、鬼らしさでしかなかったのである。(「鬼は、まことの冥途の鬼を見る人なければ、ただ面白きが肝要なり。」(申楽談義 二)。ここに、能楽における人間の類型化がみられ、同時にそれの中世的な特性が見出されるのであるが、この点については、近世の歌舞伎における人間の類型化と比較して次号に熊谷が評説する予定である。 更に言えば、その本当らしさ を写すことすら、実は能楽の目的 とするところではなかった。「しかれば、よきのう(能)と申すは、ほんせつ(本説)ただしく、めづらしきふうてい(風体)にて、つ(詰)め所ありて、かかりゆうげん(幽玄)ならんを第一とすべし。」(花伝・花修)なのであって、幽玄の花こそ、目指す最極の目的であったのである。そして、この点についてはも早(はや)深く説明する迄もあるまいが、ここで注意しなければならないのは、この「幽玄」が、当節、日本的なるものへの性急な模索の故に陥りがちな回顧趣味的・鑑賞主義的解釈によって捏造(ねつぞう)されたような、所謂(いわゆる)「幽玄」ではないという点である。そういう、現代人が、歴史的・社会的段階を無視して、直接古典作品を鑑賞した場合に体験された印象を加工してような、「幽玄」ではなくて、歴史的・社会的存在としての彼等武士貴族・公家が、その時代の感覚によって呼吸した限りでの「幽玄」でなければならなかったという点が大切である。 兎も角この幽玄を追求するための手段としてのみ、写実が意味を有ち得たのであって、「されば、ゆう(遊)女・びなん(美男)などの物まねを、よくにせたらば、をのづから、ゆうげんなるべし。ただ、にせんと斗(ばかり)おもうべし。」(花伝・花修)、とある如く、似せんとするのは、つまるところ、幽玄ならんがための方便としての心構えに過ぎなかった。だから、本来、幽玄でないものは、深く似せてはならなかったのである。 只管(ひたすら)に、幽玄なるものにのみその視野を限り、既に彼等を置き去りにして進んで行く冷めたい現実に眼を塞(ふさ)ごうとした彼等、武士貴族、公家たちの世界観は、このように能楽の在り方を規定していたのである。この点を看逃(みの)がして徒(いたず)らに幽玄 を論ずるのが如何にナンセンスなものであるかを知るべきであろう。(以下連載) |