| |
| |
|
全国学校図書館協議会刊「学校図書館」174 1965年4月号 掲載 |
|
| <巻頭言> 文学教育の視点--(巻頭言)-
|
|
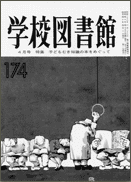 自我をぬきにしては文学(文学体験)は成り立たない。文学は究極において自分でわかるほかないし、わかり方がまためいめいに違っている。ひとりの読者における文学(文学作品)のつかみ方が、それぞれの時点において必ずしも同一ではないように、それぞれの読者は、それぞれの仕方でその作品を理解するのである。 自我をぬきにしては文学(文学体験)は成り立たない。文学は究極において自分でわかるほかないし、わかり方がまためいめいに違っている。ひとりの読者における文学(文学作品)のつかみ方が、それぞれの時点において必ずしも同一ではないように、それぞれの読者は、それぞれの仕方でその作品を理解するのである。ところで、これまでの学校文学教育は、この自明の事実を忘却して、一律に、紋切り型に、全部をわかったことにさせてしまうブンガク教育だったような気がしてならない。「絵というものは、それを描いた当人にもわからないところがあるものだ」とマティスはいったが、文学の場合も同じことだろう。読者の側からいっても、読み返すたびに新しい発見はあるが依然わからないところが残る、というのが作品鑑賞の実際ではないのか。それをたかが五時間か六時間のクラス授業で、すっかり一律にみんなにわからせることができると考える、その神経を疑うのである。 たとえば『裸の王様』や『五つのエンドウ豆』のようなアンデルセン作品だが、それを小学校三年生や四年生に読ませて、全部わかれ、というのは無理な注文だ。本筋のところでそれを面白いと感じるようになるのは、いっぺん成人文学の世界をくぐった上のことだろう。ではないのか。 だが必要なことは、アンデルセンならアンデルセンとの出会いを小学生のうちに経験させることである。大人になってから初めて読むというのでは、ああいう文学はやはり自分のものにならないように思うのだ。それと同時に、育った心でもう一度読み返す、というかたちにならないと、本当には自分のものになりきらないのである。文学教育は、さしずめ、その点をおさえた、子どもたちの未来へ向けての教育活動にならなければならないだろう。
|