サム.H.白川 (藤原啓介、加藤功泰、斎藤静代 訳) 『フルトヴェングラー――悪魔の楽匠』(上巻)より =アルファベータ 2004.11= 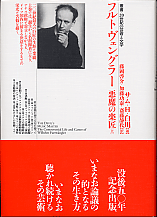 |
一九三五年四月下旬、二十五日に予定されている冬の慈善公演でベルリン・フィルハーモニーを指揮するため、フルトヴェングラーはウィーンから戻った。(中略)演奏会の切符は、売り出されてから数時間のうちに完全に売り切れた。思えばフルトヴェングラーはヒンデミット事件[(ドイツを代表する現代音楽作曲家ヒンデミットの作品は頽廃音楽としてナチスからマークされていたが、それをフルトヴェングラーはベルリン・フィルの演奏会で取り上げ指揮をした。熱狂する聴衆を前にナチスは直接フルトヴェングラーに手を下すことができなかったが、新聞は執拗な攻撃キャンペーンを展開した。)]以来初めてベルリンで姿を現したのだった。留守の間、フルトヴェングラーはオーストリアに留まっていた、スイスに亡命して保護を求めた、アメリカに行っていた、あるいは強制収容所にいた等々、さまざまな噂が流れていた。この行事の飾り付けはすべて国の式典並みだった。政府の最高位の役人も、ほとんどすべての大使館の外交団も臨席した。 フルトヴェングラーが登場すると聴衆は激しい喝采を送った。フルトヴェングラーは感謝の気持ちをこめて会釈した。しかし、それは今では義務的になっているナチ式敬礼ではなかった。彼はオーケストラの方を向いて指揮を始めた。プログラムはすべてベートーベンの作品で、《エグモント》序曲から始めて交響曲第五番および第六番で終わった。演奏会が終わると拍手喝采は鳴りやまず一時間も続き、フルトヴェングラーは十七回も舞台に呼び戻された。 一週間後、再び冬の慈善公演がおこなわれることになった。本番の直前になってヒトラーの臨席が発表された。フルトヴェングラーは激怒して、楽屋にある暖房器から木のカバーを引きはがし、割ってしまった。しかしヒトラーは非政治的な演奏会に来るのだ。それを妨げるために彼ができることなど何もなかった。フルトヴェングラーは私人として指揮するのであり、ヒトラーは聴衆の一人として参加するのだ。そこで問題となるのがナチス式敬礼だった。これまで彼は「ヒトラーに感謝する必要はまったくない」と、そう繰り返せば解決策が見つかるかのように言い続けていた。ここに至ってフルトヴェングラーは以前よりも状況がよく分かってきた。今ではフルトヴェングラーもヒトラーを文化面でも支配者として認めている以上、帝国の指導者が臨席するとなれば、敬礼はしないわけにはいかない。さてどうしたものか。 オーケストラの中で何でも屋として有名だったフランツ・ヤストラウが遂に解決策を見つけた。「指揮棒を手にして登場したらいかがでしょう。そのままナチス式の敬礼をしたら、まるでヒトラーを叩こうとしているみたいに見えますよ」。フルトヴェングラーは提案をありがたく受け入れた。指揮棒を右手に持って指揮台にのぼった。そそくさと聴衆にお辞儀して、それからすぐさまくるりとオーケストラの方を向いた。演奏者は《エグモント》序曲の始まりを告げる不吉な和音を鳴らしたが、拍手は依然として激しく鳴り響いていた。息詰まるような気分が会場全体に走った。ヒトラーは何か報復行為のような動きを示すだろうか。大臣か誰かが演奏会を中止させるだろうか。ヒトラーはただ演奏会の終わりまで座り続け、それぞれの作品で聴衆に加わって拍手喝采していた。演奏会が終わると、フルトヴェングラーは恒例の歓迎を受け、普通の礼で応えた。(「第十二章 もう一つの事件」p.330-331) (中略) フルトヴェングラーにとって、仮に自分のチケットの売り上げが限りなくゼロに近付いていくことに絶望して、怒れる巨人トスカニーニの前で身をすくめる者として描かれたとしても、それほど激怒することではなかった。しかし、自分の利益のためにドイツに残っているとか、政府と利己的な取り引きをしているといった非難を繰り返されることは、耐え難いことだった。このような噂が誤りであることを証明しようとしても、彼はほとんど何もできなかった。ともかくも彼は、何千人という人々が今そこから逃れようとしている国に自分の意志で残ったのだ。しかも彼は外国から重要な、金になる仕事の申し込みを受けていた。彼はまた、自分がナチスによって見せかけの飾り物として利用されていることも知っていた。このため、彼は長い間親密な関係が続いていたベルリン在住の若い医師マリア・デーレンに、このように板挟みになっている苦悩を打ち明けた。 毎日お手紙やお葉書を受け取っています。おかげで自分が好むと好まざるとにかかわらず受諾せざるをえない仕事よりもすばらしいものが、この世に存在することを実感できますから、たいへん嬉しいことです。正直なところ、相変わらず動いている政治に翻弄されている真只中にあって、第九や《ヴァルキューレ》を指揮することは、まるでそれがみんな[「第三帝国で指揮をする者は誰でもみんなナチスなのだ」という]トスカニーニの非難を証明しているみたいで、私には耐えらえません。でも、見てご覧なさい、トスカニーニは政治の世界で小役人のように利用されるままになっています。芸術家は自主的でなければないません。 パリ、一九三七年(日付なし)それでもなお彼は、何が起ころうとドイツに残らなければならぬ、そしてそれがどうなろうと自分の国民と運命を共にしなければならぬと決心した。ゲーテの「私が役に立つところは、それがどこであろうと自分の故郷である」ということばを思い出していた。フルトヴェングラーはナチスがその目的のために恥ずかしげもなく自分を利用していたとはいえ、外国では自国ほどには自分が「役に立つ」ことができないと明らかに感じていた。[音楽と政治の分離を固い信念をもって主張してきたフルトヴェングラーも]今では音楽家としての自分の使命が、たしかに政治的なものだと意識するようになった。どのような形でも、できるだけナチスに抵抗を続けることが彼の運命だった。しかしその戦いはますます苦しくなっていく。 何十年も後になって、[妻の]エリザベート・フルトヴェングラーが語っている。「多くの人にとって、彼の立場を理解することは難しいでしょう。単に黒と白が反対だというようなことに基づいていないからです。それから抜け出す簡単な方法は出ていくこと、つまりドイツから出ていくことでした。しかし簡単な方法は決してフルトヴェングラーの選ぶものではありませんでした。百回も指揮している曲でさえそのつど、まるで初心者のように初めからやり直して、曲を徹底的に調べて取り組む。これが彼のやり方ですから、それと同じようにドイツに残ったことで、いっそう困難な道を選択したことになりました。しかし当時は自分が取るべき道はそれしかないと確信していたからこそ、その道にとどまっていたのです」([1989年4月22日、パリで、筆者に直接語った話。])(「第十三章 精神の対決」p.371-373) (中略) フルトヴェングラーのナチスとの一九三五年の合意により、彼はフリーランスの指揮者としてドイツに残ることが許された。このため、多かろうが少なかろうが彼が望むだけ指揮ができたと推測される。ドイツ国外にいた人たちは、彼がある程度の自由を得ていたように見えたためか、ある種の特別な取り引きをして、あらゆる種類の余禄を手にすることができたに違いないと考えた。実際は枢密院顧問官の肩書きに対して与えられていた鉄道のフリーパスは別として、まったく逆だった。フルトヴェングラーがあの不安定な和睦に同意したその瞬間から、ゲッベルスはこの合意を無効にしようと執拗に工作を続けていた。[フルトヴェングラー自身の要求が辛うじて容れられた結果として、]公式の、あるいは国の主催する行事でフルトヴェングラーが指揮を免除されたことは、ゲッベルスや他のナチスの権力者にとって、きわめて腹立たしい和解条項だった。そこでゲッベルスはフルトヴェングラーに応分のお返しをさせようと決意した。ポーランド、フランス、ベルギー、オランダおよびノルウェーがナチスに制圧されると、ゲッベルスは第三帝国の文化的威信を宣伝するために、全力を注いでフルトヴェングラーに協力させようと試みた。しかし、フルトヴェングラーはゲッベルス宛に「以前自分が客演指揮者だった国々に、侵入する戦車の後をついて行く気持は毛頭ありません」と手紙を書き、断固として拒絶した。ゲッベルスは副官たちに語った。「フルトヴェングラーが党員であるかないか、それはどうでもいい。彼が好きなだけ我々のことを批判しても本官はかまわない。ところが今や彼はトラブルの種となっている。彼は政治的な役人である必要はないが、我々の看板でなければならないのだ。」 フルトヴェングラーは、自分で宣言したとおり、外国での指揮の仕事は個人的招聘だけを受け入れた。フランスが降伏した後、ナチスはシャルル・ミュンシュに、フルトヴェングラー宛に個人的に手紙を書いてフランスで指揮するよう説得してほしい、と「要請」した。ミュンシュは、一九二〇年にフルトヴェングラーがライプツィヒ・ゲヴァントハウスの指揮者だったとき、そのコンサートマスターであり、二人はよき友人だった。ミュンシュは後にボストン交響楽団の優れた音楽監督になるが、このときはナチスが口述筆記させた通りに手紙を書いた。しかし手紙が発送される前に辛うじて「ドイツ占領軍当局との協定により」という文言を乱暴に走り書きして、追加することができた。フルトヴェングラーは、ドイツ占領軍当局が演奏会と無関係であれば招聘を受諾すると返事した。結局彼はフランスには行かなかった。 このようにしてフルトヴェングラーは、ナチスの工作した厄介な事態を、薄氷を踏む思いで逃れていた。しかし、ナチスを巧みに避けることは、そう長くはできなかった。(「第十四章 おぞましい任務――その一」p.376-377) (事柄の意味をよりわかりやすくするため[ ]内に若干の言葉を補いました。なお、本文に添えられている脚注は省略しました。) more(同書下巻より) |
◇ひとこと◇ ドイツの指揮者・作曲家ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1886-1954)と作家エーリヒ・ケストナー(1899-1974)は、同時期、ともにナチスの支配するドイツ国内に留まりながら、それぞれの芸術活動を続ける道をあえて選び取った。むろん、政治から自立した音楽の絶対的優位を愚直なまでに信じ、宣伝相ゲッベルス、内相ゲーリング、総統ヒトラーたちを相手どって果敢に渡り合おうとしたフルトヴェングラーと、自ら歴史の証人となるべく、自身の著書をも含む数多くの「有害書」が抹殺される焚書の現場に立ったケストナーとでは、状況に対する認識や立場のとり方に違いはあろう。しかし、国外亡命をした人たちとはまた別種の困難を引き受けて自己の分担課題を誠実に果たそうとした姿に、両者の共通点を見る。著者のサム・H・白川氏は「著者略歴」によれば、アメリカの捕虜・敵性外国人収容所で生まれ、フィラデルフィアで育つ。テンプル大学に学び、ロンドン大学に留学、英語学・英文学博士号を取得。芸術一般についての著作多数。 (2005.2.9 T) |
|