|
|
| 国土社刊「教育」№64(1956.10)掲載---
|
画期的な児童文学史 『日本の児童文学』が刊行されてから半年近くなる。この半年ほどのあいだに、この本をめぐっていろいろの論議がかわされてきているらしいが、それもそのはずなのであって、これはいわば日本ではじめての児童文学史なのである。文学史らしい文学史の大系をそなえた本、しかも最初のものということで、各人各様の視点からこの本がマナイタの上にのせられるようになるのは、だからむしろ当然のことだといっていい。 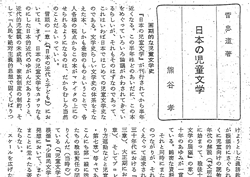 冒頭の一章(『日本の近代と子ども』)においては、まず、日本の児童文学をカタワなものにした日本的近代のゆがんだありようと、近代的児童観の未成熟、家族制度の制約、そして「人民を絶対主義的思想で固くしばりつけようとした義務教育の整備」等々の諸問題が根源的にさぐられている。年代的には、とくに児童向けの読物といってなかった明治十年代の解説(『文明開化と少年の読書』の項)に始まって、戦後十年の現在(『戦後の児童文学の展望』の章)に至るまでの児童文学七十年のあゆみが一貫して体系的に跡づけられている。綿密な資料に裏うちされてである。 それと同時にまた、学校教育や教育運動とのつながりが、それぞれの時期にわたって深くえぐって追求されている。たとえば、明治三十年代における『教育界と課外読物』(第三章)、大正期における『文芸と教育』(第五章)、そしてプロレタリア教育運動や生活綴り方運動などと児童文学運動との関係(第六章・第七章)等々である。さらに、その間に、こんにち第一線に活躍する現役の児童文学者たちの戦犯責任の問題が、「抵抗と転向のいりくんだ(当時の)様相」のもとにさぐられている(『児童文学者の戦争観』『聖戦意識の根源』『少国民文学をめぐって』などの項)。発想において、またそのスケールにおいて、まことに堂々たる著作であるといわなくてはならない。 スケールを広げたことが、またしかし同時に、世上一般の児童文学作品研究や評論の未熟さ、低調さ、底の浅さを敷写しに反映した、或種の弱さを露呈する結果となっていることも確かである。だから、その点に批判が集中するようになっていくのも当然のことだろう。さきごろ、児童文学者協会の研究例会の席上で、この本に示された巖谷小波への評価(第三章『おとぎばなしの確立』その他)をめぐって活発な討論がかわされたのなども、理由は右のような点にあったと見ていいだろう。 が、そうした論難も、この本が“方法的に処理された児童文学史の最初の礎石”であるということは充分みとめたうえでの批判・反論である。『日本の児童文学』にたいする高い評価は、すでに動かぬところと見ていい。わたしも、また、そうした評価を前提とし肯定したうえで、いわばそのさきのところで、二三感じたことをここに書きつけてみることにしたい。 新しい文学史への方法的礎石 これまでに児童文学史らしいものが一冊も書かれていない、というのは、考えてみると不思議なことである。その点について、この本の著者は、「子どもの本は消耗度がはげしい」から、という理由をあげておられる。(『はしがき』の項)。つまり、子どもの本は、よく読まれるものほど、はやく屑屋の手にわたってしまって、資料を集めるのがむずかしいから、ということらしい。 が、それは半分はうそだ。戦災でなくした手持ちの資料には、二度と手に入れることのできないようなものもあって……という著者その人の嘆きとしてならわかるが、これまでなん十年かのあいだに、見とり図ふうのものさえ一冊日本に生まれなかったという理由を、屑屋のせい(?)にするわけにはいかない。たんに資料がどうのという性質の問題じゃないという意味だ。 それは、むしろ、全面的に課題意識の問題である。というのは、これまでに、全般の雰囲気として課題意識のまともな方向づけがおこなわれていたら、すくなくとも人びとがいま困惑を感じているような、本筋の資料まで散佚してしまうというふうなことは起りえなかったであろうからである。菅氏は、むろん、そのことを百も承知の上で、あえて右のようなひかえめないい方をしておられるに違いないのだが、事実は児童文学者自身に課題意識に欠けるところがあったし、一般文学史家がまたそのとおりであった。 後者の場合についていえば、児童文学面を素通りにして文学史が成り立つと考えていたところに、これまでの日本文学史の方法的な欠陥があったわけである。児童文学を素通りするということは、児童文学による一般成人文学の基盤の形成を無視するということであり、読者をぬきにして文学評価するということにほかならない。読者の質や、読者へのはたらきかけの質を度外視しておこなわれる、作品論・作家論そして文学史が、文学の創造・発展にはなんら役だたない非実践的なものに成り終るのは当然のことである。そして、これがじつは日本文学史の現状でもある、ということは銘記しておく必要がある。 という際、菅氏がここでとられた方法は注目にあたいする。作品の認識や表現を読者の側からさぐろう、というかまえを見せておられるのである。森田思軒訳の『十五少年』が「日清戦争後の海外発展熱に迎えられて、原作の趣きとはかなりちがったところで少年の人気をあおった」ことの指摘(九〇ページ)などが、それである。もっとも、指摘の仕方そのものは表面的にすぎるし、また、この本の叙述(体系)を一貫する方法として“読者によって理解された作品の表現”の分析がおこなわれているわけでもない。『十五少年』のそれのように、たまたま、従来の文学史の方法では処理のつかないような現象面にゆきあたった際に、右に見るような分析方法が結果としてとりあげられることになった、といった程度である。問題の指摘が皮相的で彫りが浅い、というのも、方法が自覚的なものになっていないからである。 矛盾する二つの方法の混在。その点にこの本の体系そものの混乱もあるわけだが、それにしても、そうした矛盾をそこに示すことで、この本は、従来の文学史を大幅にのりこえ、新しい文学史への見とおしを用意するものになりえているのである。 文学認識論に疑問がある 「まとまった児童文学史のないことが遺産のうけつぎを困難に」していた、と菅氏はいわれるが(『はしがき』の項)、事実は、文学遺産の受けつぎを必要としないような、非創造的・非発展的な場面でしか人びとがしごとをしていなかったから、児童文学史が生まれなかったのである。 じつは菅氏自身の手で、この点をハッキリさせていただきたかった、とわたしは思う。それを百も承知のはずの氏が、どうして、あからさまに、そのことをいってくれなかったのか。というのは、問題は『はしがき』だけのことではなくて、気がねしいしいものをいっているようなところがこの本の随所に見られ、そのことがこの本全般の論脈を幾分もたついたものにしているからである。 さらに、もたつく・もたつかないの問題ではなくて、本筋のところで気になるのは、この本全体にみなぎる、辞典ふうの解題口調である。「わたしが関心をそそいだのは、人と情勢と時代の関係であった」(同上)と氏は言われるのだが、その関係が文学内面の問題としては受けとめられていない。それが文学現象のただの“背景”として扱われているというにとどまる。「それぞれの時代の資料に、ものをいわせようとした」氏のここでの試みも、だからたんに、現物提示の資料解説に終っているきらいがなくはないのである。 これもそうした事例の一つになろうが、片上伸の文学教育論の原文を引用しながらも、それをただ「人間的な道徳教育論」にほかならない、というような“解題”で片づけてしまっているのなどは(一一七ページ)、ちょっとひどすぎる。片上が文学の内面から問題を提起し、それをあくまで文学内面の問題として処理していっていることは、氏が引用された原文の範囲からでも明らかではないか。 読者の質と読者へのはたらきかけの質、そこをハッキリとつかみとることで、リアリズムを主体の問題として展開した片上の文学論。そうしたリアリズム文学論の、いわば必然的な論理的帰結としてもたらされたのが彼の文学教育論であった、ということになるのだと思うが、どうか。(そうした“帰結”を現実にもたらした社会的契機が、強化された教学精神への抵抗にあったことは、いうまでもないけれど――。) これも右の解題・解説調と関連することだが、「当時としては珍しい児童心理の描写」であったとか「これでも当時は珍しかったので」といった調子の説明の仕方はとくに気になる。ここまでくると、もう文学史の叙述ではない。叙述のスタイルが、ではなくて、方法そのものが文学史的でないのである。文学の発展やその評価ということを、氏はどう考えておられるのか、或いは単純に発展イコール進歩というふうに解しておられるのではないか、とさえ思われてくるのだ。 文学の発展ということは、いわゆる意味の進歩ということではない。もし、進歩ということをいうならば、それは読者の現実認識の進歩(またそれにつながる作者の認識の進歩)ということでなければならない。文学の表現そのものの進歩というようなことはありえない。その点が科学の認識や表現と異なるところであり、文学のそれが典型の認識であり表現であるといわれる理由である。だから「当時としては」ではなくて、その当時における読者との相対関係において、その作品の認識・表現が、典型の認識、典型の表現になりえていたかどうかが評価されねばならぬのである。――率直に言って、菅氏の文学認識論そのものに若干問題がありそうに思われるが、しかしこれは文学史家全般に通じる問題でもある。 (文京区本郷一ノ十五・大月書店刊・本文三二五ページ・三八〇円) |
| (文中、今日の人権感覚に照らして適切でない表現があるが、文章の歴史性を考慮し、そのままとした。) |