|
|
|
| 三一書房刊「日本児童文学体系月報」№1 1955年6月 掲載---
|
|
| 十代の読書 「十代にどんな本を読みましたか」とお訊ねしたら、あなたは、なんとお答えになられるだろうか?  この問いに対する答えは、ひとによってきっとまちまちに違いない。 たとえば、秋田雨雀先生(作家・児童文学協会長・七十二歳)などは、十代前期(明治三十年代末)において『少国民』や『えいさい新誌』を、そして博文館の『おとぎばなし』(巌谷小波)などを愛読されたということだし、十代後期から二十代にかけては、『バイブル』、藤村の『若菜集』『一葉舟』『落葉集』、『透谷全集』、蘇峰の『文学断片』、二葉亭の『浮雲』などを読んだのを思いだします、というふうに語っておられる。あなたはさっそく、それをあなたご自身の読書経歴とおくらべになってみて戴きたい。大きなジェネレーションの差異を、そこにきっとお感じになられることだろう。 この問いに対する答えは、ひとによってきっとまちまちに違いない。 たとえば、秋田雨雀先生(作家・児童文学協会長・七十二歳)などは、十代前期(明治三十年代末)において『少国民』や『えいさい新誌』を、そして博文館の『おとぎばなし』(巌谷小波)などを愛読されたということだし、十代後期から二十代にかけては、『バイブル』、藤村の『若菜集』『一葉舟』『落葉集』、『透谷全集』、蘇峰の『文学断片』、二葉亭の『浮雲』などを読んだのを思いだします、というふうに語っておられる。あなたはさっそく、それをあなたご自身の読書経歴とおくらべになってみて戴きたい。大きなジェネレーションの差異を、そこにきっとお感じになられることだろう。また、たとえば末川博先生(立命館大学総長・六十三歳)のように、「農村で育ちましたので、小学校の教科書以外に読んだものはありませぬ」とご自分の空白の少年期について語っておられる方もあれば、また、「おとなのものでもなんでも乱読した」という佐木秋夫氏(宗教学者・四十九歳)のような方もいる。世代により、環境により読書の体験・経歴はさまざまである。 右のような読書から何をえたか? 「国民的・人間的認識」をというのが、秋田氏のばあい。末川氏は、「革新的な教育者になろうとする意欲を」えられたという。もっとも、これは青年期の読書からである。佐木氏もまた「少年期のものはあまり効果がなかった。正しい指導がほしかったと思う。青年期のものが現在の自分を決定した」といわれる。ところで、あなたは、あなたご自身の読書から何をえられただろうか。 私は、さきごろ、卒業を前にした女子高校生諸君とこの〝読書からえたもの〟について語りあうことができた。何を読んでいるか、読んできたか、ではなくて、もっぱら〝何が自分の成長の糧(かて)となったか〟という点についてである。このことに併せて〝読書からえたもの〟について語りあった、というわけだ。現在の時点に立って、 Ⅰ 小学生時代 Ⅱ 中学生時代 Ⅲ 高校生になってから という三つの時期についての思い出を、まずカードにメモしてもらい、すこし間を置いてから、こちらの質問に答えてもらうことにした。また、自由に自発的に発言してもらうことにした。以下、その折のメモを繰って、問題点を二三拾ってみることにしよう。 相手は東京山の手の某私立女子高校の生徒。その大多数が経済的に豊かな環境に育った生徒たちである。早い話が、その九割方が家庭に電話をもっている。女中のいないという家は二割そこそこ。会社の重役が三割、一流の大会社や官庁の部課長級が二割、その他商店経営といったところ。極めて特殊な環境に人となった生徒たちだが、しかし健康でスナオな心を持っている人たちばかりだ。自分たちの生活の特殊性を自覚することで、遂に環境による制約を乗りこえ、目隠しされた箱入り娘にだけはなるまいと絶えず努力しているような、好もしい若者たちである。こんにちの十代の一つのケースを示すものとして、お読みになって戴きたい。報告は〝文学的読書〟に絞っておこなうことにする。 高校時代は日本の作品が 高校生になってから何を読んだか、という問いに対して、七十八名のこの生徒たちは二六一の作品名をあげた。一人当たり三~四冊の書名を書きつけたわけだ。やはり、日本の作品のほうが多い。外国の作品との比率は、だいたい六対四というところ(第一表参照)。 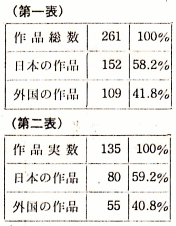 ところで、むろん、各人の書きつけた作品名には重なり合うものがあるわけだ。殊にこの学校は学校全体の生徒会活動に関心が深いし、クラブ活動やサークル活動がさかんだから、教師・生徒のタテ横の交流がかなり徹底しておこなわれている。したがって、同じ本を読み合って話すとか、感銘の深かった本は友人にもすすめるというようなことが、高学年になるにつれて〝傾向〟というより〝雰囲気〟にさえなってきている。この〝重なり合いの大きい〟理由だ。 それで、あげられた作品数は二六一だが、実数は半減して一三五という結果になっている。が、それでもやはり、六対四という比率は動かない(第二表参照)。 ところで、むろん、各人の書きつけた作品名には重なり合うものがあるわけだ。殊にこの学校は学校全体の生徒会活動に関心が深いし、クラブ活動やサークル活動がさかんだから、教師・生徒のタテ横の交流がかなり徹底しておこなわれている。したがって、同じ本を読み合って話すとか、感銘の深かった本は友人にもすすめるというようなことが、高学年になるにつれて〝傾向〟というより〝雰囲気〟にさえなってきている。この〝重なり合いの大きい〟理由だ。 それで、あげられた作品数は二六一だが、実数は半減して一三五という結果になっている。が、それでもやはり、六対四という比率は動かない(第二表参照)。何が心の糧となったか――高校時代―― 右の〝心の糧(かて)となった作品〟として挙げられたものを、同一作家の作品は作家別にまとめて高順位に第一〇位まで拾ってみると、次のようになる。 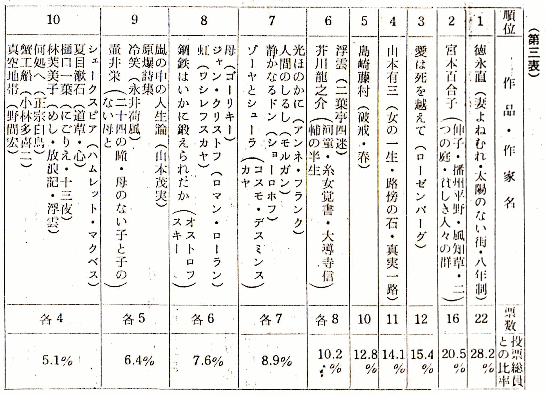 これを作家別でなしに、純粋に作品別に第五位までの順位を辿ってみると、次のようになる。 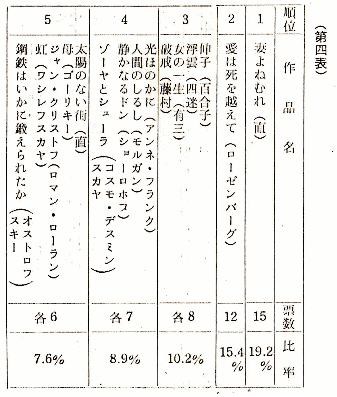 ということになるが、いずれにしても彼女たちの関心が、いわゆる〝古典〟よりは現代に、外国作品も日本の現実に問題を投げかけるようなものに集中していることが知られよう。 なお、『「妻よねむれ』が第一位を占めているのは、彼女たちが前に読書会のテキストにこの作品を選んだことと関係があり、また百合子が初期のものから晩年の作品にわたって読まれていることには、さいしょの項に記したような、彼女たち自身の〝良家そだち〟という特殊環境と深く関係している。 教科書の問題 ところで、右[左]の第四表をデータとしていうかぎり、『ジャン・クリストフ』を唯一の例外として、彼女たちの愛読書の系列は国語教科書のそれとほとんど無関係だということになる。むしろ、教科書の系列とは背中合わせだといったほうがあたっているのだ。(第四表に示された作品中、その断片だけでも教科書に載っているものは、右のロマン・ローランの作品だけである。) 百合子にしろ直にしろ、また多喜二にしろ、いまの教科書では敬遠されている。プロ文学と名のつくものや、それにつながる作品は、すべて教科書ではタブーなのである。 それだけではない、漱石の作品にしても、『草枕』や『坊ちゃん』などの初期のものがほとんどで、『三四郎』がチラッと顔をのぞかせる程度だ。龍之介の作品についても、同じようなことが言える。『地獄変』以前のおさない龍之介が姿を見せているだけだ。 外国文学で〈は、英・米・仏・伊・独その他総花式に作品の断片が掲載されているが、中国やソヴェートの作品は一篇も見当らない。近代ロシアの作品さえツルゲーネフのものを例外として皆無である。誰やらが言っていたが、民族的関心をどこかへ置き忘れた拝外主義と排外主義がいまの教科書の編集だ。 つまり、右に示されているような生徒たちの読書傾向は、民族的なものを見失なったこの拝外主義と排外主義とへの抵抗とさえ考えられるくらいのものだ。 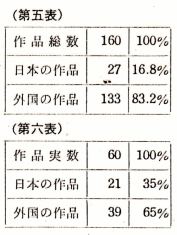 小学生時代にはアンデルセンを 高校卒業のいまの時点に立って、おさない自分の心を培ってくれた作品として回想されるのは高校時代と違って、おもに外国の作品であるという(第五・六表参照)。数多く読んだのは、むしろ日本の童話や少年・少女読み物だが、なつかしいのはしかしアンデルセンやグリムだというのである。 順位を追ってみると、次のとおりである。 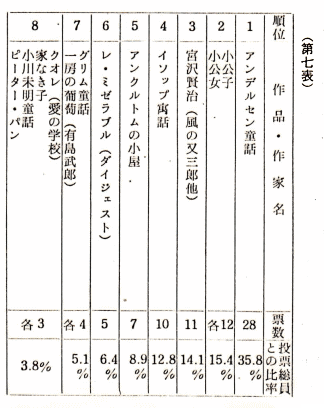 便宜上、三人以上の生徒が指名している作品を右[左]に掲げたわけだが、その中にあげられている作家が僅か三名にすぎず、しかもそれが児童文壇の文壇的傾向(生活童話へのかたより)から自由であった宮沢賢治や、本来的な児童文学者ではないところの有島武郎などであることは何を示しているのであろうか。 便宜上、三人以上の生徒が指名している作品を右[左]に掲げたわけだが、その中にあげられている作家が僅か三名にすぎず、しかもそれが児童文壇の文壇的傾向(生活童話へのかたより)から自由であった宮沢賢治や、本来的な児童文学者ではないところの有島武郎などであることは何を示しているのであろうか。日本の作品を耽読した中学生時代 中学生時代になると、日本の作品が圧倒的に多く読まれるようになる。数多く読まれるというだけではなく、感銘の深いのも日本の作品だったというのだ(第八・第九表参照)。 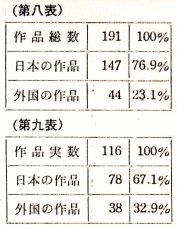 この時期における日本近代文学への関心の深まりは、どこの学校にも見られる一般的なあらわれのようだが、彼女たち自身の語るところでは、自分たちの生活や生活感覚に直接ふれるものを日本の作品の中に多く見いだしたからだという。いま一つには、文学教育がほとんど国語教室の一手専売のような形でおこなわれたことにもよるという。他の教科、たとえば文学とのふれあいの多い英語の授業などでは、しかしせっかくの文学教材も単に語学のための演習教材として扱われがちだっとことにも関係がある、と彼女たちは言っている。文学教育を国語教育の枠内において考えがちな、私たちにとって、一つの反省の資である。 右の関係を、さらに次の順位表についてごらんになって戴きたい。 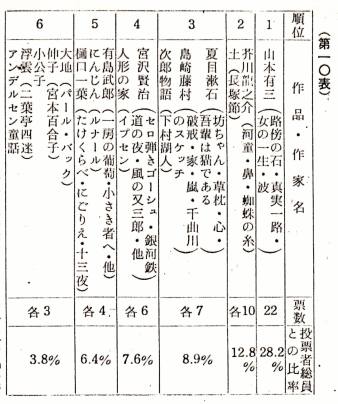 これを作家別にしないで、作品別で順位を辿ると、有三の『路傍の石』と湖人の『次郎物語』がそれぞれ票数七で第一位、『人形の家』が六票で第二位、『破壊』『河童』がそれぞれ四票で第三位ということになるが、ところで有三や胡人の作品への傾倒から何をえたであろうか?――「おおまかな意味でのヒューマニスティックな正義感と人生への意欲を」と彼女たちはいう。「あの時期に『路傍の石』や『真実一路』に親しんだことは、ともかくプラスだった」としみじみと語るのである。 これを作家別にしないで、作品別で順位を辿ると、有三の『路傍の石』と湖人の『次郎物語』がそれぞれ票数七で第一位、『人形の家』が六票で第二位、『破壊』『河童』がそれぞれ四票で第三位ということになるが、ところで有三や胡人の作品への傾倒から何をえたであろうか?――「おおまかな意味でのヒューマニスティックな正義感と人生への意欲を」と彼女たちはいう。「あの時期に『路傍の石』や『真実一路』に親しんだことは、ともかくプラスだった」としみじみと語るのである。が、また、たとえば、『次郎物語』の世界のような「架空の人生を、現実のそれと思い誤まったまま今に至ったとしたら、それは大きな問題だが」とも彼女たちは語るのだった。そこに望まれるのは、とくに中三から高一の時期へかけての精神の成長期における、問題意識喚起の積極的・計画的な文学教育の指導である。 問題は、文学と教科書のあり方 ところで、ここに問題があるのは、高校卒業の現在の時点において、一般の生徒たちがそれをもはや薄手なものに感じてきているような、たんにヒューマニスティックな作品に、今に至ってようやく親しみはじめたというふうな生徒たちのことである。 このケースの生徒たちの愛読してきた作品というのを、小学生時代からずっと辿って見てみると、たとえば、 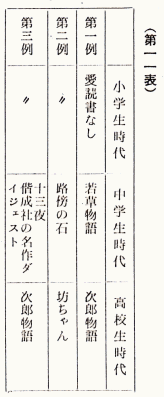 というようなことになっている。小学生時代の読書生活のブランクが補いのつかぬまま現在に至っているといういきさつらしいのだ。 が、その到達点は、方向として健康なものであり、それとして充分意欲的であるとさえいえる。前途について悲観的な観測をくだすのはだから必ずしもあたらないが、この生徒たちがこれで学校生活と縁が切れて、〝家の娘〟に還元されてしまうという点に問題がある。進学組は別として、この十九の娘たちの大部分にとっては、学校生活だけが社会に向って開かれたほとんど唯一の窓であるからである。 が、それはそれとして、『次郎物語』や『路傍の石』のような、そのかぎり意欲的で明るくタクましい作品が一般に人気があるのは、近代から最近代に至る日本文学一般の暗くじめじめした否定的性格への嫌悪とふかく関係している。 また、末梢神経で書いたような視野の狭い作品や、人肌のぬくもりのない傾向的な作品の氾濫しているこの現状にも、彼女たちは彼女たちなりにあきたりぬものを感じているのだ。またたとえば、お色気を売り物にした巨匠某々氏や中堅作家某々氏の作品などは、なおさら彼女たちの潔癖さがそれを受けつけぬのである。問題はこの一点では文学自体の問題にかえってしまうのだ。 それと同時に、さきほどもふれた今の学校教科書のコスモポリタニズム(拝外主義=排外主義)と〝お稽古ごと〟的教養趣味・文化主義のあの編集ぶりである。未熟ではあるが潔癖で意欲的な生徒たちは、教科書の文学教材と文壇的文学作品との双方に背中を向けて、右に見てきたような〝架空の人生〟に逃避(?)する。もっと手の悪いものになると、少女小説から母物小説へ(通俗少女雑誌から『明星』『平凡』へ)へというコースを辿っている。 文学教育と読書サークル けれど、また、第一〇表にそのことが示されているように、中学生時代に『伸子』や『人形の家』『河童』『破戒』などに傾倒し、大きく自分を成長させて行っているケースもある。その中核は、中三 ― 高一の時期に読書サークルをつくって、生活の幅を加えていった生徒たちである。 サークルで何人かの先生を囲んで読みあったのは、はじめ田中千禾夫の『おふくろ』だったという。次いで、『可愛い女』(チェホフ)・『地獄変』(龍之介)・『河童』(同)・『土』(長塚節)・『外套』(ゴーゴリ)などを読んだという。が、『外套』まで読んできて気づかされたのは、「文学的読書が、しかし文学作品だけの読書にとどまっていたのでは、けっきょく文学もわからない」ということだった。 そういう自覚が生まれたところから、彼女たちの飛躍的な成長がはじまった。理論的なものへの関心、そして理論的関心、歴史への関心である。それが同時に、自分たち自身の生活の基盤や周囲への関心と実践的意欲をよびさました。生徒会の組織が彼女たち自身の手によってこの学校に誕生したのも、或いはその一つのあらわれだったかも知れない。そして、この時点において、文学は、新たな意味で彼女たちの心を奮い起こす生きた力になった、というのが、彼女たちの指導者である教師諸君の観測。 学校における文学教育活動の中心の場は、なんといっても教室であるが、教室がそのすべてではない。むしろ、課外の指導やサークル活動に大きな期待がかけられる。課外やサークルの活発な活動の成果が教室に撥ね返ってきて、クラス全体の活動がいきいきとしたものになる、というのが実際だ。そこに他教科との緊密な横のつながりが望まれるし、何よりも学校自体(とくに教職員組織)の真の民主化をそこに期待しなくてはならない。――これが、彼女たちや彼女たちの先生である教師諸君と話しあってえた結論めいたものの一つであった。
|