| 批評精神の喪失――文学界月評子の「批判」に応える―― 熊谷 孝 |
| 「文芸復興」1-1(1937.6)掲載--- |
|
|
| *漢字は原則として新字体を使用した。 *引用部分以外は現代仮名遣いに替えた。 *傍点の部分は太字・イタリック体に替えた。 *明らかに誤植と判断できるものは訂正した。 *難読語句(文字)には適宜、読み仮名を添えた。 |
|
|
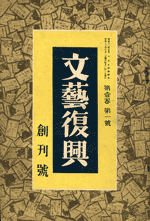 はじめに学問というものの性質について考えてみる必要があるのだと思う。趣味と学問との区別をはっきりしてかからなくては不可(いけな)いのだと思う。これはもう何遍もいったことなのだが。そうしてまた、至極わかりきった事柄であるのだが。その判り切っている筈(はず)のことを、もう一度開き直って言って置かなければならない様な場合に、いま私は行き当っているのだ。 はじめに学問というものの性質について考えてみる必要があるのだと思う。趣味と学問との区別をはっきりしてかからなくては不可(いけな)いのだと思う。これはもう何遍もいったことなのだが。そうしてまた、至極わかりきった事柄であるのだが。その判り切っている筈(はず)のことを、もう一度開き直って言って置かなければならない様な場合に、いま私は行き当っているのだ。柴生田稔氏は、文学界五月号(文化月報・古典文学欄)において、拙稿「西鶴論断章」(国語と国文学・三月号)および近藤忠義氏「能楽論に於ける中世的世界」(文学・二月号)の二論文を引合いに出しながら専(もっぱ)ら歴史的方法の「欠陥」「誤謬」を発(あば)き出すことに腐心して居られる。 氏によれば、『歴史的方法の問題の如きは、一般的にはもはや事新しいものでなく』したがって『二篇の論文にこれだけ集中するのは如何(いかが)とも思はれるが』それにも拘(かかわ)らず『現在の国文学界の情勢に於いては無関心たり得ぬ問題であり、――現に文学四月号の予告には古典評価の規準の問題(熊谷孝)の題目が載つている――また取扱はれた内容も注意すべきものであるから』『取上げたの』だといわれる。そうして、殊更(ことさら)拙稿を槍玉に挙げたのも『熊谷氏は近藤忠義氏とともに、鑑賞を絶対に排斥する客観的歴史的研究方法の主張者であ』り、『この論文も「文芸の偶発生の問題にふれて」と題註にあるように、大いに方法論上の問題を論じてゐるが、兎に角ひとつ具体的な応用 を示したものであるから、理論の功過を窺ふに都合がいい』(圏点 引用者)からだそうである。鑑賞主義者 柴生田稔氏が、一挙歴史学派の陣営を陥れるべく眼(まなこ)を皿にしてアラ探しを企てられるに至った所以(ゆえん)である。 ところで、その批評のしかたが問題なのだ。アラ探し以上のものではないからである。アラをアラとして指摘するのならいい、揚げ足取りのための揚げ足取りでもまだ許すところはある。ところが、氏のアラ探したるや一時代前の、姑(しゅうとめ)の嫁に対する態度とちっとも違ってはいないのだ。つまり、批評精神を欠いた(だからまた批評の名に値しない)「批評」だというのだ。趣味と学問とをゴチャゴチャにした物言いでしかない、というのだ。その子細をこれから順を追って明かにしていこう。 拙稿の所論を一部分引用したあとで、氏はまずこう云われるのである、『文学史上の重要な問題に触れてゐるが、全体を通じて常識的・公式的の色彩が強い。』『論者は方法論の強調に騒がしく、事象の認識と検討とを疎(おろそ)かにして、理論への引合せに急いでゐる傾きがあ』り、『科学的な精到を欠いてゐる。』 要するに、氏が拙稿の論旨の『全体を通じて』そういう印象 を受けられたという丈(だけ)の云い分なのだから、私としては何もいうことはない。私が『方法論の強調』に勉めたのは事実だが、それがまた氏にとって『騒がしく』感じられた、という報告に過ぎないのだし、その他『事象の認識と検討とを疎かにして』いるとか、『理論への引合せに急いでゐる傾きがあ』るとか、『科学的な精到を欠いてゐる』といった云い分もすべて氏の感想 の範囲を出ていないものなのだから、それらを批評として受取らない限り(また絶対に批評として受取り得る筋合いのものではないのだが)、やはり私としてはなんら応答すべき義務はないわけだし、第一個人個人の直感的なあれこれの感想にいちいちムキ になってはいられないし、またムキ になりようも無いわけである。ただ、こうした言い捨てな・無責任な感想を批評だなどと履き違えていられないことを氏のために切に切に望む次第である。 とはいえ、そういう判断をもち来たすに至った理由を全然説明していられないわけではない。部分的には兎も角一応の解説を試みているのである。ただ、その説明が説明になっていない、というのだ。そうしてまた、その説明のしかたが非論理的だというのだ。つまる処、批評以外の何かではあっても、批評でだけはない、というのである。ということの次第はおいおい判ってくる。 『文学的現象が歴史的社会的に制約されてゐるのは今更言ふまでもないことだが、問題はその奥にもある……』(圏点 引用者) 『奥にも ある』、いや、そうではあるまい。「奥に ある」のだろう。この種の、いざという時の逃げ道をこしらえて置いて、半ば逃げ腰の、しかし口だけは達者な云い方をするというやり口は世の鑑賞主義者諸賢の最も愛好せられる所である。例えば、誰でも知っている様に、「文芸が当該時代の歴史的社会的条件によって規定されている」一面 をカッコ付の形で認めて置いて、「しかもかかる歴史的限界を超えて普遍人間 に通じる」一面をも 見遁(みのが)しえない、といい、そうして結局のところ、その「歴史的制約から自由な」後(あと)の一面こそ 「文芸の本質」をいいあらわすものなのだ、といった云い方は鑑賞主義者のひとしく口にする合言葉なのである。 文芸現象の『歴史的社会的に制約されている』一面を認めるにも拘らず、『問題はその奥にもある』といった風な論理の運び方をするのは、実は「文芸の研究にとってはその本質(文芸の本質)を究めるのが目的であるのだから、歴史学派の連中の云う様な歴史的価値の追求など、(まあ一応は認めてやってもいいが)第二第三の問題だ」と云う結論を導き出すための伏線に外ならないのだ。氏自らをして語らしめよう、『所謂(いわゆる)歴史的価値の設定を〔私たちの歴史学派が〕究極の目的とすること自身がそもそも問題である。』氏はまたこうも云われる、『西鶴の個性を無視 して、作品の現実相を論じ、現代人としての評価 を離れて近世町人文芸を理解することなどにどれだけの意味 があらうか。さういふ方法によつて成立する科学性 といふものは結局文学の本質 とは遥(はる)かなものである。』(圏点 引用者) そこで、『文芸現象が歴史的社会的に制約されてゐるのは今更云ふまでもない』などと知った風な顔をして、つまる処、それを文芸のもつ単なる一面だとして蔑(ないが)しろにし、文芸の本質をいまひとつの「歴史的制約から自由な」一面に覓(もと)める、というやり方は、所詮は文芸の意義そのものに対する無理解を、「文学の本質」なるものを全然履き違えて理解しているということを暴露する以外のものではないのである。そうして、それはまた氏の依拠せられる鑑賞主義方法論の非方法性・非科学性の自己暴露に過ぎないのである。なぜかというに、――氏および一般に鑑賞主義者諸賢が『文学の本質』を、謂(い)うところの、「普遍人間」的な面にのみ閉されている「神秘」の中に探り覓(もと)めようとするのは、文芸作品〔古典〕が啻(ただ)に製作された時代にあって鑑賞されるばかりでなく、時空を超越して現代の吾々の芸術感にまで迫ってくるということ、いや在りし日の「評価」以上の「評価」を現在がもちきたしている場合さえもあるということ、その事ゆえであるだろう。「この事実をどうして呉れる」と氏らは開き直るだろう。事実氏は昂然(こうぜん)としてこういうのである、『現代人としての評価を離れて近世町人文芸を理解するなどということにどれだけの意味があろうか』と。 いかさまむかしむかしにつくられた作品が、いまの私たちにも充分興味をもって読める、充分鑑賞に堪えるというような場合も決して少(すくな)くはない。けれども、そのことからして直ぐさま、その作品の制作された時代の読者が受取ったところの作品の表現と、現代の私たちがその作品〔古典〕から読みとったところの表現とが、同質 のものである、という風に考えるのは早合点というものである。考えて見るがいい、電車が走って居ない大昔の人間の生活を、私たちは、たとい理解 することは出来ても、身を以て追体験することなど断じて出来はしないのである。文芸の場合とてもおなじことなのだ。「源氏物語」の表現を身を以て(吾がものとして)「文芸的」に享受し得るためには、紫式部との共通体験が予想されねばならぬのだ。文芸が、作家と読者との共軛(きょうやく)した体験の面に於いて場を構成するものである限りそうなのである。「洒落」というものがある。「洒落」は相手に通じなければ洒落にはならない。洒落が洒落として成立つためにはお互の間に共通の体験が予想されなければならない。話の筋はこれと全く同じことなのである。古典を生ける文芸として文芸的に鑑賞し得るのは、当代の、しかもその作品の世界と共通の世界に住むところの読者に限定されるのだ。(これはまだまだ粗雑ないい方でしかないが、当然「層」の問題が考慮されなければならないのだが、――この問題についての詳細は拙稿「古典評価の規準の問題」〔文学・四月号〕参照。)鑑賞を方法とする限り、ひとは、『文芸の本質』を把握するは愚か理解することさえも遂になし得ないであろう。 ところで、『現代人としての評価』の立場に立って『近世町人文芸を理解』した筈の柴生田氏は次のような結論に到達されるのである、『仮名草紙や貞徳のやうに文学性の希薄なもの に対しては論者の方法は余り破綻を見せてゐない云々』(圏点 引用者) 私の『方法が破綻を見せてゐ』るか如何(どう)かは大方の批判に俟(ま)つの外はないが、仮名草紙や貞徳の文芸を『文学性の希薄なもの』だとする判断に対しては一言しないわけにはいかないのである。ここにも「歴史」を無視した氏の「鑑賞主義」が悪く作用しているのである。仮名草紙の制作に際して予想された当時の読者の「鑑賞」と二十世紀の空気を呼吸して生活していられる柴生田氏の「鑑賞」とを同質なものだと履き違え、氏御自身それらの作品を「文学性の希薄なもの」として感じられたということからして直ぐさま「当時の読者にも仮名草紙なんか面白く無かつたに違ひない、」という風にお考えになってか、或は「彼ら無知大衆がそれを娯(たの)しんだか娯しまなかったかは別問題として兎に角文芸としてくだらない」という風に思われてか遮二無二(しゃにむに)それらを『文芸性の希薄なもの』と断定していられる。しかしこれは独断というものである。ここでは、過去現在(敢(あ)えて未来といわざるも)の文芸に対する恒常普遍の最も優れた読者としての柴生田氏がたち現われているのである。しかし、「文学性」の『希薄』「濃厚」ということは歴史を無視した鑑賞者としての「私」の立場からは絶対にいい得ないことなのである。対者の芸術感にしっくり訴え得た場合、その作品は充分『文学性』に浸透したものであるだろう。仮名草紙は、当時の読者に対しても芸術的享受を与えなかった、とは一概には云い切れない(たとい今日の私たちにとって面白くなくともこれは如何しようもないのである)。なおこの点に関しては前掲拙稿「古典評価の規準の問題」を熟読せられんことを特に柴生田氏におすすめしておく次第である。 こう見て来ると、氏の云われるところの『現代人としての評価』とは、実は「現代人としての、一身上の立場からの鑑賞」以外のものではない、ということなどは、も早(はや)自ずから明かであろう。『現代人としての評価〔鑑賞〕を離れて近世町人文芸を理解する』ということは、実は非常に『意味』のあることなのである。 ついでにいま一つ氏の近世町人文芸論を紹介し、併せて批判を加えて置くことにしよう。 芭蕉の『外面的には 隠遁流離の消極的生活は』氏によれば『近世社会の矛盾、漸(ようや)く経済的勢力を失つた武士支配階級と政治的自由を拒否されて経済生活・好色生活にのみ生きた市民階級と、それら多くの矛盾を含んだ社会生活に対する積極的な捨身の抗議で』あるのだそうである。そうしてまた、『熊谷氏は多分それを時代に取り残された芭蕉の前時代的世界観に帰せられるのであらうがさういふ考へ方は結局公式的である』(圏点 引用者)といわれる。 『時代に取残された』という云い方は、可成(かなり)誤解を招き易いものではあるが、そういう穿鑿(せんさく)は別として、おっしゃる通り、私が『芭蕉の前時代的世界観』を問題としているのは事実だ。そうして、かかる前時代的世界観の所有者の存在し得た、そうしてまた、かかる旧世界観によって貫かれた文芸が兎も角も町人文芸の一翼として存立し得たことの根拠を、私は近世社会の否定的な歴史的構造のうちに覓(もと)める。こうした考え方がなぜ『公式的』なのだろうか。氏はこの時評論のいちばんはじめの所で、私を『公式的』だといわれた。その公式的であるといわれる所以(ゆえん)を氏の論文の全体に渉(わた)って探し覓(もと)めたが、結局「公式的だ、公式的だ」というだけでその理由は遂に明かにされてはいないのだ。ついでだから云うが、前の『文学の本質とは遥(はるか)なものである』という個所の直ぐあとで『さういふ〔歴史学派の〕立場としてもこの論文は初めに述べたやうに 精到を欠い』(圏点 引用者)たものだと批難していられるが、さっき引用した通り無責任に『科学的な精到を欠いてゐる』といったきりで『精到を欠いてゐる』所以を一向説明しては呉れないのだ。そのくせ『初めに述べたやうに』などと、さも説明し尽くしている様な顔をしていられるところを見ると、氏はこういう無責任な・思いつき的な感想 (漫想)を並べたてることを以て批評 だという風にお考えになっていられるらしい。氏の「批評」が批評以外の何かではあっても、批評でだけはない、と云ったことの第一番目の理由である。(『空虚感』を伴うとか、『常識的』だとか、『芭蕉に対しては特に鑑賞上の欠陥が目立つ』とか、『感傷的な「自然詩人芭蕉」の崇拝者達の鑑賞と径庭な』いものだとか、『「炭俵」の軽みの境地の解釈なども一部の素人意見と同様の誤謬に陥ってゐ』はしないかとか、その他いろいろ言いたい放題の悪口を理由も明かにしないで言い捨てにする、という無責任なやり口は、氏の、いやおしなべて鑑賞主義者 たちに共通した悪い癖である。) さて、氏の、『芭蕉の外面的には隠遁流離の消極的生活』が『実は』『矛盾を含んだ社会生活に対する積極的な捨身の反抗』なのだ、という論であるが、芭蕉のそういう『消極的生活態度』が、たとい彼自身にとって『積極的な捨身の反抗』の表現であったとしてからが、芭蕉流のそうした行き方が、事実『隠遁流離の消極的生活』としてあったという事実に、彼の文芸が「町人の生活意識・感情をひたすら消極的退嬰(たいえい)的なものに組織する」「反歴史的のものであった」(拙稿「西鶴論断章」)という事実に変りはないのだから、彼の主観にとって『捨身の反抗』であったといったことは、この場合 (かかる問題の限りに於いては)、問題にすること自体、全く意味ないことなのである。いかさま『捨身の反抗』の揚句、ああした退嬰的な文芸を生み出すことにもなっていったのだとか、そういう結果、ああした伝統的な文芸ジャンルにその身を打ち込むに至ったわけでもあったのだ、という様な解釈 も或は可能かもしれない。それが当っているかいないかは別問題として。だが、芭蕉の動機 が『捨身の反抗』にあったにしろ、そうでなかったにしろ、彼の作品のありかたが「退嬰的消極的」なものであるという事実は、彼の作品が現実に対して分け有(も)ったところの役割が「反歴史的なもの」であったという事実は、動かぬところである。このことは、歴史を正視し、『芭蕉の作品そのものに尋ね』(柴生田氏)てみれば判ることなのである。私たちが問題にして意味のある、作家の「動機的なもの」というのは、「作品そのもの」への理解を確かなものにする為に役立つ、その様な「動機」だけなのである。そして、動機を云々することも、かかる理解をヨリ確かなものに導くための資料として 役立てよう、という目的の下に語られてこそ、そうしてこそはじめて意義も生じて来るというものである。 ところが、柴生田氏の場合は、それとは凡(およ)そうらはらなものなのだ。芭蕉の生活が『外面的には 隠遁流離の消極的』なものに見えるが、彼の本質 は『矛盾を含んだ社会生活に対する捨身の反抗』にある、というのだ。殊更「内面」と「本質」とに問題を分けて、「内面」が「本質」がこうだから、といって事実をさえも歪めようとしているのだ。「作品そのもの」を理解しようがために「内面」を探ろうというのではなくて、「内面」をあれこれと解釈して娯しもうがために作品を読む、という丈のことなのだ。氏は、繰返し繰返し、作家の『個性を無視して』は不可(いけな)い、といわれる。作家の個性を読みとることが恰(あたか)も文芸研究の究極の目的ででもあるかの様にいわれる。そして、その為には、やはり「鑑賞」が必要だ、という処に氏の論は落着くらしい。ところで、「鑑賞」を方法として獲得されたところの氏の町人文芸論は、実に『仮名草紙や貞徳』の俳諧が『文学性の希薄なもの』であったり、芭蕉の俳諧が『矛盾を含んだ社会生活に対する積極的な捨身の抗議』を表現するものであったり、また『……芭蕉の作品はその外形伝統的趣味と混同せられ易く、第一芭蕉自身未だ自覚を欠いてゐた点』(圏点 引用者)があったり、なかなかヴァラエティーに富んだものなのである。「鑑賞」を方法とした柴生田氏の所論が正しいか、それとも『極く一般的な粗雑な鑑賞過程を通過してゐるといふに過ぎぬ』(柴生田氏)私の、『素人意見』(同上)にもひとしい『西鶴論断章』の所論が正しいかは暫(しばら)く大方の批判に俟(ま)つことにしよう。 私たちは、作家の個性だとか性格だとかいうものを決して無視はしない。創作心理を探るということも、場合によっては必要だとさえ考える。ただ、それが何のために必要なのか、ということが問題なのだ。作品を鑑賞しながら、憶測を逞(たくま)しゅうしながら作家の創作心理を、或は個性を性格をあれこれと「解釈」して娯しんでいるのでは不可(いけな)い、とういうのだ。個性などなどの探究も「鑑賞」のためにするのでは意味がない、というのだ。問題は解釈することにあるのではない。解釈は、学問の一操作として行われてこそ、意義をもってくるものなのだ。そして、学問というものは、もう何遍も繰返してきたように、自分の娯しみにするものでなどあっては不可いのだ。歴史が私たちに課しているところの課題(現実の課題)に正しく応答するための、そうした目的のためのヨリよき認識の整理であらねばならぬのだ。評価も、かかる目的のための評価として行われてこそ評価の名に値するものででもあり得るのだ。 柴生田氏が、「鑑賞」を評価だなどと考えてのんびりしていられる太平振りこそは、実は評価の軸への混乱を身を以て体現していることを指し示す以外のものではないのである。いいかえると、学問というものの性質がわかっていない証拠なのである。氏が趣味と学問とを混同していられる、と敢えて云ってのけた所以である。 私はさきに「古典評価の規準の問題」において、私たち歴史学派に向けて浴びせかけられている批難の中で、とりわけ「歴史学派の主張は、文芸を文芸として扱わないものなのだから、それは本来文芸 学の名に値しない」と云った種類の批難がいちばん多い、という意味のことを述べ、そうしてそういう論は、もっぱら鑑賞主義の建前からおこなわれ、また遮二無二鑑賞必要論に導くための伏線に外ならぬものである、ということについて語り、この種の愚劣極まりない・蒙昧な論議が、ひとえに評価の意義(何のための評価か、ということ)・学問と趣味との区別をはっきりしてかからない処に由縁するものである、ということなどを論証したのであった。 ところで、またもやかかる妄論が、殊更威儀を正し虚勢を張りながら、文芸性の把握こそ文芸学の使命だ、文芸性を無視しては文芸学は成立たない、といった言い廻しで蒸し返されている。言い廻しは違っても、言おうとしているところ(言うところ)は結局同じことだ。私たちは文芸性を無視しはしない。唯、鑑賞主義者諸賢の様に、自己の鑑賞を規準として文芸性を云々しないだけのことだ。「歴史」を無視して文芸性を論じない、というだけのことなのだ。そして、文芸性の把握を文芸学の究極の目的だ、などといわないだけのことなのだ。これらの事に関して私はこれ迄しかしもう何遍も語っている。 * 評価の意義についてはなお「文学」四月号・拙稿[「古典評価の規準の問題」]を参照ありたい。 |
|
|