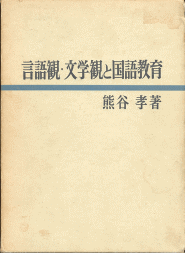| 熊谷 孝 著 |
| 言語観・文学観と国語教育 |
| |
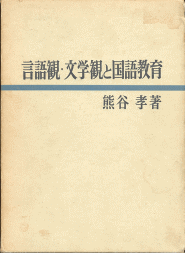
1967年2月
明治図書出版株式会社 発行
A5版207頁
定価720円
絶版 |
|
――文章の中にある言葉は辞書の中にある時よりも美しさを加えていなければならぬ。(『侏儒の言葉』)
わたしの考える国語教育は、芥川のことばを口移しにしていうと、辞書の中にある時よりも美しさを増し加えている、そのような生きた日本語の教育である、ということになります。いいかえれば、わたしたちの民族が、その生活と歴史の闘いの中でつかみとった外界の法則(環境の論理・対象の論理)の第二信号系への反映である国語帽の教育である、ということなのであります。
つまりは、そのような対象の論理の反映として、民族の歴史の中で煮つめられ洗練され、民族の主体性におけるもっとも有効な外界認知の基礎手段の体系として生産されたのが民族語、国語にほかなりません。国語教育は、したがって、そのような民族的体験の共通信号の系としての国語の、生産的・実践的な信号操作のための教育活動以外のものではない、ということになるでありましょう。国語自体の成長と発展のためにも、国語教育はそのようなものとして組まれなければならないという意味です。(本書「まえがき」より)
|
著者:熊谷 孝(くまがい たかし)
1911年東京に生まれる。1938年法政大学大学院修了、法政大学助教授を経て、現在国立音楽大学助教授。
著書に『芸術とことば』(牧書店) 『文学教育』(国土社)など。共著『文学の教授過程』『中学校の文学教材研究と授業過程』(明治図書)など。[奥付による] |
| |
| ◆ 内 容 |
まえがき
Ⅰ 言語観・メディア観の変革と国語教育
1 第二信号系の理論と国語教育
(1) 信号と記号、信号の記号化
(2) “ことば”は実体か媒体か
(3) 国語教育とは何か――民族的体験の共通信号の系
(4) 教科書構造論の前提となるもの
2 国語教育としての文学教育
(1) 勤評体制下の国語教育――たえず問題を原則に返して
(2) 部分と全体、方向分析
(3) 文法教育と文学教育と
(4) 学習指導要領の問題点
3 汎言語主義的メディア観からの解放(一)
(1) メディア観とは何か? 汎言語主義とは何か?
(2) 読解指導的発想の基底にあるもの
(3) わく組みによる認知
(4) “概念”中心主義的指導観との対決
4 汎言語主義的メディア観からの解放(二)
(1) 教科構造論と言語観の問題
(2) J・デューウィの汎言語主義批判
(3) 国語教育の新段階
(4) 第一信号系と第二信号系の間――国語教育こんごの課題
5 総合よみの確立のために
(1) 教育の方法体系における総合法の位置づけ
(2) 三層よみか総合よみか
(3) 描写文体の総合よみは過程をたいせつに
(4) 送り意図と作品の主題
(5) “ことば”の融通性ということ
6 主題把握と教材化の視点
(1) 読むべき時期に読むべき作品を
(2) 主題とは何か、その指導
Ⅱ 文学観・芸術観の変革と国語教育
1 課題について
“伝え”の物質的基礎/客観主義と主観主義/反映論の視点で
2 文学と教育
(1) 創造と鑑賞の統一的視点
(2) 鑑賞の起点
(3) 感情の素地・別個の感情――文学教育の課題
(4) 先行体験の形成――国語教師への提言
3 鑑賞指導の前提となるもの(一)
(1) 表現理解を規制するもの――解きくちの問題
(2) 本来の鑑賞者
(3) 鑑賞と創造の接点
4 表現と理解の間――鑑賞指導の前提となるもの(二)
(1) 意味形象――文学史の、文学教育への媒介
(2) 表示と表現の弁証法
(3) 無意識の意識化――形象的認識の本質
さくいん
|