| 荒川有史 著 | ||
| 文学教育論 | ||
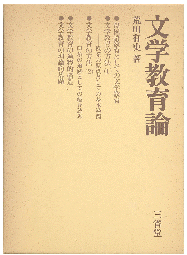 1976年12月10日 三省堂 発行 A5判 247頁 定価1900円(税込) 絶版 |
教育の荒廃が叫ばれてから実に久しい。そして、教育現場の核ともなるべき授業が小・中・高校各段階において、それぞれ特有の現象を呈しながら、まさに成り立たないという状況になってきている。 どうすれば授業を授業らしく、一時限毎に教師が疲労感を訴え蓄積させることなく、教室の子どもたちの眼が学ぶことの喜びに光り輝くようになるのか。――授業運営の、あるいは授業方法のテクニック的側面にのみその起因があるのか。否とすれば、教材の素材・題材性の善し悪しにのみあるのか。それもまた否と言わざるをえないであろう。荒川有史氏(国立音大・明星学園高)の新著『文学教育論』(三省堂刊)を手にするとき、まさにその感を深くするのである。 国語教育=母国語教育に長年従事してきた氏の現場実践を踏まえた〈文学教育〉のとらえ直しはそのまま現在の日本の教育状況への真摯な警鐘、提言となっているのだ。〔中略〕 小・中・高現場の実践を踏まえた氏の、とりあげた教材の基本的作品把握の論はまた優れたひとつの作品論として息づいている。文学研究者へ本書をすすめたい所以でもある。〔以下略〕(「文学と教育」第99号 「新刊紹介」より) |
|
| 著者:荒川有史(あらかわ ゆうし) 1930年、宮城県生まれる。1956年、法政大学日本文学科卒業。国立音楽大・明星学園講師、文学教育研究者集団事務局長。著書に『文学教育の構造化』(共著、三省堂)『芥川文学手帖』(共著、文教研出版部)などがある。 |
||
| ◆ 内 容 | ||
まえがき Ⅰ 母国語教育としての文学教育 1 母国語教育の原点は何か (1) 母国語による思索と行動への準備 (2) “母国語”概念の確立を (3) 母国語教育の必然的な展開 (4) 多民族国家におけるも国語の問題 2 文学教育的発想の復権 (1) 自主編成へ向けて (2) 基礎学力の新しい見なおし (3) 言語活動主義批判の視点 (4) 「文学教育」と「文学作品の読み方指導」のあいだ Ⅱ文学教育の方法 (1)――授業の原点としての基本過程 1 基本過程とは何か (1) 人間的感動と教育労働者的自覚との接点 (2) 教材体系構想の基礎過程 2 現代史への問いかけ (1) 文学史における自己の再発見 (2) 近代主義的批評との対決 (3) 過去と現代との対話 Ⅲ 文学教育の方法 (2)――印象の追跡としての総合読み 1 読みの過程的構造 (1) 印象の追跡としての総合読み (2) 読みの三層構造 2 総合読みの方法原理 (1) わく組みによる認知を成り立たせること (2) 文体的発想の変革をめざす読み (3) 読みの方法の自己規制 (4) 文体的特性をふまえた立ちどまり Ⅳ 文学教育の過程的構造 1 主題的発想の視点に立つ教材体系 (1) 読むべき時期に読むべき文体の文章を (2) 授業の構造化の第一歩 (3) 国語教育教材としての視点から 2 小学校段階の総合読み―― 『太陽は四角!』を中心に (1) 『太陽は四角!』の世界 (2) 経験主義的発想を超える (3) 虚構的現実の準体験 3 中学校後期を現在像として――『最後の授業』の読み (1) 感情の素地――表現理解を規制するもの (2) 総合読みのねらいを保障する第一歩 (3) 作品との出会いの場をたいせつに (4) 読み手の凹凸率を調節する (5) 主題的発想の変革に焦点を (6) 基本テーマの言語化 4 高校生の眼からみた総合読み――『正義と微笑』を中心に (1) 授業をふりかえって (2) 『正義と微笑』の展開 (3) 進君に対する温かい眼と冷たい目――ある日の討論 (4) テストについて (5) レポートの中から (6) 中学時代の授業と高校の授業 Ⅴ 文学教育の理論的基礎 1 文学とは何か――基軸としての読者論 (1) 国語教科書における評論の位置 (2) 「小説の読みかた」――その構成と文体的特徴 (3) 準体験的発想によるイメージづくり (4) 第一次的足場をどうきずくか (5) 未知と既知とのバランスシートを確かめながら (6) 日常性と非日常性のあいだ (7) “文学の眼”“虚構の眼”による追跡――読者である民衆に学ぶこと 2 文学の認識と表現 (1) 言語と文学 (2) 形式と内容 (3) 芸術的認識の過程的構造 3 文学にとって主題とは何か (1) 主題把握を明確に (2) 主題把握の変革 (3) 実践に有効な概念とは (4) 授業の構造化に向けて 4 歴史と文学 (1) 史実と真実 (2) 歴史小説の方法 (3) 鴎外における歴史小説 5 文学史の方法 (1) 現代史としての文学史 (2) 大正デモクラシーにおける文学体験――芥川文学の再評価 (3) 二十年戦争の文学体験を通路に |
||