| 荒川有史 著 | ||
| 母国語ノート 〈国語教育叢書 20〉 | ||
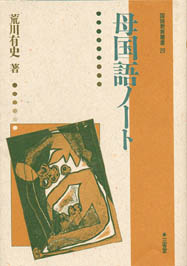 |
創造の契機において母国語を考えるという視点は、母語と母国語を機械的に区別し「母国語イコール国家権力から強制された言葉」と一義的に規定する立場からは、決して、生まれえないものであろう。 「故郷の発見は、自己の誕生と成長の歴史の確認であり、未来の展望をたしかめる作業の一環である。幼い生命をいとおしみ、幼い生命の幸せを願って語りかける母親の一語一語は、同時に母親の民族の一員としての存在証明であり、自己確認につながっていく」。「母親はそういう意味で、ある〈言語共同体〉の中で生きている。しかし、母親の言葉は、、彼女の既往現在の体験の総決算を反映しているのであり、完結した〈母語〉一般を担っているわけではない。彼女の言葉の生産性は、民族の共通信号として機能したときに発揮される。私たちが、母語を母国語として考えるゆえんである」。(中略) 〈母国語〉概念が、言葉を、その実際のありように即して場面との関係・関連の中で動的に把握していこうとする発想に基づいていること、そして、母国語文化の基盤となるもの、母国語文化の真の担い手は誰なのかということをも含みこんだ、豊かな広がりをもつ概念であることが見えてくる。(「文学と教育」№164掲載の山口章浩氏の書評より) |
|
| 1993年9月20日 株式会社三省堂 発行 四六判 200頁 定価 2000円 絶版 |
著者:荒川有史(あらかわ ゆうし) 1930年 宮城県に生まれる。1956年、法政大学日本文学科卒業。 国立音楽大学教授、文学教育研究者集団事務局長。著書に『文学教育論』(三省堂)『西鶴世代との対話』(近刊)『文学教育の構造化』(共著、三省堂)『芥川文学手帖』・『井伏文学手帖』・『太宰文学手帖』(共著、みずち書房)などがある。 |
|
| ◆ 内 容 | ||
第一部 母国語発見への道筋――〈内なる仲間〉との対話を基底に 第一章 母国語教育としての英語教育
第二部 母国語奪還 第一章 母語と母国語
あとがき |
||