坂口安吾『ラムネ氏のこと』を読む
文教研のNです。
メールを定期的に出すぞ! と決意を述べたとたん、次の例会まで一週間しかないことに気づき、あらためて気を引き締めておるところです。
先日の例会では坂口安吾『ラムネ氏のこと』(ちくま文庫・坂口安吾全集14、他)を音読し、印象の追跡をしました。
この作品は確かに面白いけど、難しい。
その語りかけようとしている読者の幅が広いというか、逆に選ばれていて狭い、というか。
ともかく、私が例会に出て、そうか、と思わされた点を「上」を中心にご紹介します。『ラムネ氏のこと』はまだ青空文庫で作業中のようなので、以下に「上」の概略を述べます。
小林秀雄、島木健作、三好達治、そして、安吾の四人で「鮎を肴に食事のうち、談たまたまラムネに及んで」ラムネとはいったい誰が発見したかという話題になる。三好はラムネー氏なる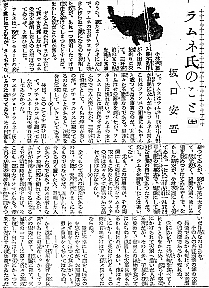 人物が発見したというが、辞書にはない。後日「プチ・ラルッスル」を調べてみるとフェリシテ・ド・ラムネーという「絢爛にして強壮な思索の持ち主」であったという哲学者の名前が載っていた。もしこの人物がラムネの玉を発見したとすれば「ラムネの玉はますますもって愛嬌のある品物」だ。全てのものは天然自然のままにはない。「誰かしら、今あるごとく置いた人、発明した人」があったのだ。フグを料理として通用するようになるまでも、暗黒時代があった。何人もの人がそのために命を落とした。その中には「爾来この怪物を食ってはならぬと遺言した太郎兵衛」もいただろうが、俺は死ぬがこの肉の甘味は子々孫々忘れるな、必ず血を絞って食え、と言い残した頓兵衛、それに続く「幾百十の頓兵衛」がいたのだ。 人物が発見したというが、辞書にはない。後日「プチ・ラルッスル」を調べてみるとフェリシテ・ド・ラムネーという「絢爛にして強壮な思索の持ち主」であったという哲学者の名前が載っていた。もしこの人物がラムネの玉を発見したとすれば「ラムネの玉はますますもって愛嬌のある品物」だ。全てのものは天然自然のままにはない。「誰かしら、今あるごとく置いた人、発明した人」があったのだ。フグを料理として通用するようになるまでも、暗黒時代があった。何人もの人がそのために命を落とした。その中には「爾来この怪物を食ってはならぬと遺言した太郎兵衛」もいただろうが、俺は死ぬがこの肉の甘味は子々孫々忘れるな、必ず血を絞って食え、と言い残した頓兵衛、それに続く「幾百十の頓兵衛」がいたのだ。
まず登場してくるそうそうたるメンバーが他愛もないラムネの話に興じるところが面白く読み出されていくのが自然でしょう。
しかし例会に出てみて、そこからして場面規定がずれると、読者によってそのイメージの持ち方が少しずつ違っていってしまうことを感じました。
当代きっての知識人たちの、打ち解けた雰囲気。そんなことを最初思っていましたが、「この時期の小林、島木、三好、と言えば、もう転向している時期ですよね」と念を押され、そうか、と歯止めがかけられました。1941年11月20日から三日間の都新聞一面に連載。実名が挙げられている以上、そこには読む人によってその時点の具体的なイメージが重なってくるはずです。
 また一方で、太宰の『十二月八日』(1942年2月)に出てくる「ぬぬ百年」の描写、紀元二千六百年を風刺したあの亭主たちの会話に通じるものがある、という指摘もされました。 また一方で、太宰の『十二月八日』(1942年2月)に出てくる「ぬぬ百年」の描写、紀元二千六百年を風刺したあの亭主たちの会話に通じるものがある、という指摘もされました。
一見、不真面目。しかし、世の中が異常になってきたとき、真正面からではやっていられない。
それをはずすことで、状況を風刺していく。
そうした「武器としての笑い」があるという問題提起でした。
風流に鮎を肴に、というなら、『日本文化私観』で言及されたタウトのように、もっと幽玄な日本美の世界へ入っていってもいいかもしれないのに、話題はラムネ玉なんていうものにいたる。
そこにも風刺的な笑いがあるだろうという指摘でもありました。
面白く読んでいくこと抜きにこの作品は読み出せないけれど、そこにはいくつもの仕掛けがあって、それを読み込んでいく面白さと同時に、自分勝手に肩に力を入れすぎると読み間違ってしまう危うさがあるようです。
仕掛けがたくさんあるという点では、例えばフェリシテ・ド・ラムネーという人物の取り上げ方などについても、話題になりました。
1940年版の「プチ・ラルッス」によると、カトリックの自由主義の青年を組織し、やがて教会と決別、社会主義的で神秘主義的な人道主義に傾斜していった人物らしい。(大修館・精選現代文指導資料・2007年4月)そんなところをこの作品を読んだ読者の中には知っている人もいるだろうし、調べてみる人間もいるだろう。そこからさらに様々なイメージの重なりの中に、時局の批判もできる可能性もでてくるだろうし、読者の裾野も広がっていくだろう。
安吾の読者層。笑いの中に様々な読者を取り込みながら、実は、精選され、そしてまた、広がっていく。
やはり今の実感では、面白くなってきたけど難しい。
でも前回『日本文化私観』をやったことで、人間に、その生活の要求に可能性を見続ける安吾の一貫した姿勢は、ますます強く見えてきました。
「中」の終わりはこうなっています。茸とりの名人が自らの茸に当たって死んだ話の後です。
つまり、この村には、ラムネ氏がいなかった。絢爛にして強壮な思索の持ち主がいなかったのだ。名人は、ただいたずらに、静かな往生を遂げてしまった。しかしながら、ラムネ氏は必ずしも常に一人とは限らない。こういう暗黒な長い時代にわたって、何人もの血と血のつながりの中に、ようやく一人のラムネ氏がひそみ、そうして、常にひそんでいるのかも知れぬ。ただ、確実に言えることは、私のように恐れて食わぬ者の中には、決してラムネ氏がひそんでいないということだ。
人間の知恵が伝えられなかった村、しかし、そこにも可能性を見る眼を捨てない安吾の姿勢。
生活の欲求を忘れた知識人として、あえて自分自身をも対象化し批判する。
民衆がそこにいる限り必ずラムネ氏は出てくる、という安吾の人間の可能性にかけた発想が実感されてきました。
さて、今週の例会(会場は渋谷・大向会館)も『ラムネ氏のこと』です。「下」のところをもう少し検討し、益田勝実氏の教材化の視点の検討などをふまえ、今の我々としてはこの作品を高校段階で教材化するべきかどうか、など、トータルに話し合う予定です。
【〈文教研メール〉2007.6.27 より】
 ‖Nさんの例会・集会リポート‖前頁‖次頁‖ ‖Nさんの例会・集会リポート‖前頁‖次頁‖
|