坂口安吾『日本文化私観』を読む
文教研のNです。
コンスタントにメールをお送りできないでいます。
しかし、初心にもどれば、例会を身近に感じていただこうと始めたことで、コンスタントに出ないことは致命傷でもあります。
ここは一つ、自分の生活習慣を見直し、ご飯を食べたり(お酒を飲んだり)するように、欠かすことなく様子をお伝えしよう!
と前向きに心に誓ったところです。
先日の例会は、坂口安吾「日本文化私観」(ちくま文庫・坂口安吾全集14、他)を音読し、読みきりました。
これは1942年3月に発表されたものです。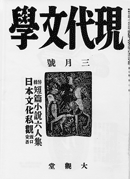
正直言って、最初一人で読んだときは面白いエピソードが入っているし、文学について語られているところなど胸を打つのだけれど、なんだかよく分からない、という感じでした。
高校時代、「ラムネ氏のこと」(1941年)をはじめて読んだときもこんな感じだった気がする、と思い出されました。
とはいえ、やはりそこは文教研で場面規定の重要さを学んできた身。
「これは1942年時点の表現であるはず」という思いでは読んでいったのですが……。
さて、例会に出るとその点が具体的に見えてきたし、当然、ぐんと深まりました。
文教研では今まで取り上げたことのない作品なので、少々長くなりますが本文を引用します。
最終章、「四 美に就いて」の最後の部分はこんな感じです。
見たところのスマートだけでは、真に美なる物とはなり得ない。すべては、実質の問題だ。美しさのための美しさは素直でなく、結局、本当の物ではないのである。要するに、空虚なのだ。そうして、空虚なものは、その真実のものによって人を打つことは決してなく、詮ずるところ、有っても無くても構わない代物である。法隆寺も平等院も焼けてしまって一向に困らぬ。必要ならば、法隆寺をとりこわして停車場をつくるがいい。我が民族の光輝ある文化や伝統は、そのことによって決して亡びはしないのである。武蔵野の静かな落日はなくなったが累々たるバラックの屋根に夕陽が落ち、埃のために晴れた日も曇り、月夜の景観に代ってネオン・サインが光っている。ここに我々の実際の生活が魂を下している限り、これが美しくなくて、何であろうか。見給え、空には飛行機がとび、海には鋼鉄が走り、高架線を電車が轟々《ごうごう》と駈けて行く。我々の生活が健康である限り、西洋風の安直なバラックを模倣して得々としても、我々の文化は健康だ。我々の伝統も健康だ。必要ならば公園をひっくり返して菜園にせよ。それが真に必要ならば、必ずそこにも真の美が生れる。そこに真実の生活があるからだ。そうして、真に生活する限り、猿真似を羞《はじ》ることはないのである。それが真実の生活である限り、猿真似にも、独創と同一の優越があるのである。(電子図書館「青空文庫」より転載、以下同じ。)
とてもショッキングなイメージ。
しかし、この文章全体にこうした表現がちりばめられています。
そうした表現を貫いているものとして、例会の中で明らかにしてもらったことは次のようなことでした。
人がいて生活があって、その生活の必要、生活に応じた欲求によって、モノや観念が生まれてくる、という安吾の一貫した姿勢がそこにあること。
日本精神、という観念が先にあって日本人がいるのではない。
自分たちの生活の欲求、そこにこそ日本人の日本人としての独創性も優位性もあるのだ。
バラック屋根がすばらしいとか、法隆寺より停車場がいいといっているのではないでしょう。
しかし、法隆寺や平等院が、今の自分たちの生活の欲求とどう関係しているのか。
物資を輸送する停車場や、生きるための菜園が、今私たちの生活の必要にあるならば、それをどうして否定できるだろうか、だいたい、そういう生活事情に追い込んだのは誰なのか。
この文章は実にこうした逆説的表現に満ちています。
まだまだつかみきれませんが、1942年という時点の表現が少しずつ見えてきました。
長くなりついでに、もう一部分、心に残ったところをご紹介します。
安吾が文学に就いて語っているところです。
叱る母もなく、怒る女房もいないけれども、家へ帰ると、叱られてしまう。人は孤独で、誰に気がねのいらない生活の中でも、決して自由ではないのである。そうして、文学は、こういう所から生れてくるのだ、と僕は思っている。
「自由を我等に」という活動写真がある。機械文明への諷刺であるらしい。毎日毎日日曜日で、社長も職工もなく、毎日釣りだの酒でも飲んで遊んで暮していられたら、自由で楽しいだろうというのである。然し、自由というものは、そんなに簡単なものじゃない。誰に気がねがいらなくとも、人は自由では有り得ない。第一、毎日毎日、遊ぶことしかなければ、遊びに特殊性がなくなって、楽しくもなんともない。苦があって楽があるのだが、楽ばかりになってしまえば、世界中がただ水だけになったことと同じことで、楽の楽たる所以《ゆえん》がないだろう。人は必ず死ぬ。死あるがために、喜怒哀楽もあるのだろうが、いつまでたっても死なないと極ったら、退屈千万な話である。生きていることに、特別の意義がないからである。『自由を我等に』という活動写真の馬鹿らしさはどうでもいいが、ルネ・クレールはとにかくとして、社会改良家などと言われる人の自由に対する認識が、やっぱり之《これ》と五十歩百歩の思いつきに過ぎないことを考えると、文学への信用を深くせずにはいられない。僕は文学万能だ。なぜなら、文学というものは、叱る母がなく、怒る女房がいなくとも、帰ってくると叱られる。そういう所から出発しているからである。だから、文学を信用することが出来なくなったら、人間を信用することが出来ないという考えでもある。(「三 家に就いて」)
今の自分は本当に自分の生活の欲求に根ざした生き方をしているか。
今の日本は本当に日本人の欲求に根ざした日本であるだろうか。
叱られて、そして、そこから、もう一度考えていく。
安吾の言葉が表現する世界は、確かに叱る力を持っていると感じました。
次回は6月23日(土)、そして、4月第二例会が休会になった分を6月30日(土)に行います。
どちらも坂口安吾「ラムネ氏のこと」、会場は二回とも渋谷・大向会館です。
【〈文教研メール〉2007.6.19 より】
 ‖Nさんの例会・集会リポート‖前頁‖次頁‖ ‖Nさんの例会・集会リポート‖前頁‖次頁‖
|