| ▼1991/01/12 №461~№464 12月冬合宿(12/26~28) S.N.&K.A.&N.T. 12月26日 S.N. 12月26日、午後2時、例年のとおり、冬の合宿が始まった。熊谷先生がご病気で不参加との報が入り、心配でたまらない合宿の幕あけだった。(その後、先生は入院されたが経過は順調とのこと) (1) 予定されていた、第一部オリエンテーション「階級論としての世代論(作品を読む視点)」は、チューターの熊谷先生がいらっしゃらないので、予定を変更して、テキストを皆で読みあうかたちで進めた。「文学と教育」№115「座談会 西鶴の発見」がテキストである。 討論のなかで重要と思われることを項目をあてて、メモふうに……。 ① 西鶴文学の時期区分論が、座談会のなかで話題になっているが、時期区分というのは、西鶴のある作品になら作品の、ある鑑賞が成立していないかぎり、できないものだ。「時期区分論の成立には作品の鑑賞が先行する」ということが実例としてわかった。 ② 典型というのは、普遍の中の個として描かれた人間像のことだ。普遍の中の個にも、ある作家(読者)にとって意味のある普遍と、意味のない普遍があるが、どの普遍の中の個に意味を感じて、描くか(読むか)というところにその作家(読者)の階級的立場(視点的立場)があるのだ。 ③ 西鶴文学の時期区分で一期から二期を、常の町人二代目(新興町人二代目)の視点的立場の自覚の過程とみるわけだが、「新興町人」という概念を何か固定化してみてはいないか。新興町人を都市部にだけみられる身分としての町人と同一に考えてはならない。身分概念ではなくて、階級概念なのである。農産物の商品化に伴い、農民の商人化(町人化)など、農村部まで含んだ問題として考えるべきだし、新興町人の階級分化(上層新興町人の御用商人化、下層者への転落の不安にたえずおびやかされている新興町人中間層)を含んだ階級概念として考えるべきだろう。 ④ 世代ということに関して――自己の精神形成期にあるショックな歴史的体験を体験し、それにこだわりながら、そのことを思考し、ショックを持続し続けている人々のことを同じ世代というのだろうし、そこに、固有の視点的立場も生まれる。ショックというからには、ある大きな歴史的事件でも経験しないと、という議論もあったが、歴史的な事件、歴史的な転換期というのが何か特別にあるのではなくて、日々、日常が歴史的転換点なのだ。日々の体験を歴史的事件だと感じ得るかどうかが決定的だといってよいという反論があった。ここでも、まさに主体が問われているのだと痛切に感じた。(現代を生きる主体としての自己の問題として) 12月26日 K.A. 合宿の2日目、27日の朝、機関誌「文学と教育」の合評が1時間ほど行われた。 (2) 続いて「芥川龍之介『芋粥』から『秋』へ」の検討。 [略] 『芋粥』との関連(階級的な人間把握の視点)をふまえたうえで、次の二点が特に強調された。 ① 『秋』において芥川は自分の属する階級である中流階級に焦点をしぼり、自分と同世代の人間たちの問題にはっきりと視点を定めていること。また、たとえ同じ階級にあっても、その世代形成が違っていること。登場人物それぞれの顔のちがいが見事に描かれた作品であり、これは『雛』や『大導寺信輔の半生』へとつながっていくものであること。 ② 『秋』は信子サイドの目を通して描かれており(『地獄変』と同じ特質)、この点を落とすと、一般の『秋』論にみられる「悲劇の主人公である信子、その救いようのない絶望は龍之介の挫折をあらわす」といった読み方になってしまう。 以上の二点加えて、自分自身の属する階級の「他人の愚であると共に自分の愚であるところの、自他の愚」を徹底的に問題にしていこうとしている芥川の姿勢が、1919年11月11日の海軍学校時代の教え子への手紙[*]の中にもうかがえる。『秋』はその目で丸ごとつかみなおされた人間が描かれていることが話された。 [*芥川龍之介の小田寿雄宛手紙こうした話題提供をふまえ、以下1章~4章にわたって印象の追跡が行われた。 [略] 最後に、まとめの方向でいくつかの意見が出された。この作品では、人間が階級的な視点で丸ごとつかまれていること。俊吉は芥川世代の一人であり、冬の時代を意識し、倦怠の思いを持続し、その生活感情・メンタリティーを共有している世代の一人であること。いちばんやりきれない思いをしている俊吉の中に、ある明るさを感じるが、これはあそびの精神につながるものであること、などなど。 [話題提供者の]S.T.氏は最後に、『尾生の信』を引きながら、「芥川も書きたいから書いている。わが属する階級、ひどい面はいっぱいあるけれど、俊吉の姿、これで良いんだよ、というものを感じる。何か、来るべき不可思議なものを待ち続けながら、未来を求め、その可能性、可変性を求めて書く。そこに芥川のロマンチシズムを感じる。」とまとめられた。 12月28日 N.T. (3) 階級論としての世代論――西鶴 初日に読んだ「西鶴の発見」をもとに、ここでは、時期区分で第二期にあたる『二代目に破る扇の風』(『永代蔵』)を読んでいった。[略]各部分少しずつ重なる形で、全体を4パートに分け、音読し、話題提供した後、意見を出し合うことにした。が、時間の関係で②の途中までとなった。 ① 始め~生れ付たる長者なり ② さればかぎり有る命~彼男、返事もせずおとがひにてをしへける ③ 此一歩只かへすも思へばおしき心ざし、出て~身の程を謡うたひて一日暮しにせしを ④ まんまと此道にかしこくなって~終わり [略] ▼1991/01/26 №465 1月第一例会(1/12) Y.R. “明けましておめでとうございます。”委員長のあいさつで、今年初めての例会が始まった。そして、念頭にふさわしい嬉しいニュース。熊谷先生が11日に退院、しかもその次の日であるにもかかわらず、この例会に出席して下さった。予定よりずいぶん早い退院とのこと。「鍛え方が違うんですよね」とは、委員長の弁。 さて、まずはN.T.氏の「10分コーナー」から。“主題概念”についての報告である。[略] この“重要基礎概念”のとらえ返し、おさえ直しは、個人としても例会としても、大事に位置づけたいものだ、という関そうがあちことで聞かれたことを付け加えたい。 西鶴『二代目に破る扇の風』の印象の追跡 冬合宿の続きである。③、④パート(ニュース№463参照)を中心にということであったが、熊谷先生の助言を受けて、もう一度、全体を大きくとらえ直すことになった。ここでは、いくつかの論点を、“ひとつ書き”ふうに記してみたいと思う。 ○ ここに描かれている初代について 「惣じて大坂の手前よろしき人、代々つづきしにはあらず、大方は吉蔵三助がなりあがり……是皆大和、河内、津の国、和泉近在の物つくりせし人の子ども、惣領のこして末々を丁稚奉公……次第送りの手代分になって」云々。(『永代蔵』) こう書かれているような、典型的な初代新興町人なのではないか。三井高利などとは、出自からして違うのである。そうおさえることで、「其身一代に二千貫目しこためて」のイメージも確実になってくるのではないか。 ○ 「若い時ならひ置きし小謡を、それも両隣をはばかりて、地声にして我ひとりの慰みになしける」 ここをどう読んだか。近所迷惑になるからとか、つつましく、というのではないのではないか。謡も、仲間を作ってやると出費がかさむ。「四条の橋を東へ渡らず、大宮通より丹波口の西へ行かず」。つまり、危険なこと(出費がかさむこと)には、徹底して近づかないのである。謡をたしなんでいる、ということを近所に知られないよう、こっそり謡っているのだ。 ○ 「めしつれたる年切女」について “年切女”、これは注にもあるように、期限を切って雇っている下女のことである。臨時雇いである。期限が切れたら、はいそれまで、なのだ(私も年切女・年切男だ、という声あり)。初代の場合、ケチでそうした形態をとっていた訳ではなく、それがせいいっぱいだったのである。しかし、二代目には、そうする必然性があるのだろうか。 また、この時期が封建制の解体期であることが、ここにも出てきている。町屋からも、こういう形で主従関係が崩れていく。“下女”ではなく、“年切女”であることに注目したい。 ○ 第3パート(③)について( I .H.氏の話題提供から) 手紙を読んで、二代目なりに心を打たれているのではないか。また、渡す相手を探し歩く姿に、この男の誠実さのようなものが感じられる。人のお金で遊ぼうとするせこさ。初代に較べていかにも不徹底。しかし、どこか、お金だけではないもの、そのメンタリティーを感じる。「一度はえ一度は衰ふると、身の程を謡うたひて一日暮しにせしを」と、自分の人生を後悔しているようにも見えない。この男の存在に、利左の生れてくる可能性をどこか感じるのだが。 ○ 第4パート(④)について(Y.R.の話題提供から 塵も灰もなく、というほどに使い果たしてしまった二代目。その姿に、どこか爽快さのようなものを感じる。最後の鎌田屋の何がしが、子どもに、こうなっちゃあおしまいだと教訓的に語るその言葉を、そのままには聞けない。 ▼1991/02/09 №466~№467 1月第二例会(1/26) M.M. 熊谷先生は大分お元気になられたが、用心のため外出を控えておられる。お大事に。 西鶴文学にみる階級論としての世代論 冬合宿・前例会を承けて、今日の話題提供者A.Y.氏から、『二代目に破る扇の風』後半部分を中心に一読者としてのまとめと、『小判は寝姿の夢』の魅力について話したい、とあって始まる。 ① 新興町人の経験と経験主義――『二代目~』に即して この作品の初代は、裸一貫から身をおこした。しかし二代目の教育については失敗者だったのではないか、という前回のT.M.氏の意見に共感。きびしい身分制社会にあって、彼らがそれに対抗し、人間を解放しうる途を求めるとすれば、それは金の獲得・蓄積によって、人間としてのある保障をかちとる以外にはない。その手段であるはずのものが、人間形成において、やがて目的が変わっていく。 初代が成功者であればある程、自分の体験を絶対化し、経験主義へと傾斜してゆく。自分と同じ発想の子供を育てることに重点がおかれる。どういう視点に立てば、変化する現実に対処しうる人間に育てうるのか。成功した初代には、それが見いだしにくくなっている。その問題が、今作品の親子に介在しているのではないか。初代の背中を見ながら成長した二代目が、父親のすることはすべて正しいと受取ったとき、そこにある種の問題がつみ重なる。子が、どういう経験のしかたをした時に、先輩や親たちの経験が継承されていくのか。単なる経験重視ということとの違い、経験主義に傾斜した初代と、二代目との係わりの問題を、形象的思索を通して描いている。これを大事な問題として位置づけたい。 ② 『西鶴の発見』の“時期区分論”ともっと真剣に取り組む必要がある。『二代目~』を読むうえでも、『一代男』の鑑賞体験の捉え直しが不可欠。『二代男』『胸算用』、利左の魅力を自分のものにするためにも。 『五人女』巻一あたりから、初代を二代目の視点から捉え直し始めている。その視点は清十郎の視点ではない。この場合の新興町人二代目の視点とは何か、深めるべき課題であろう。どういう作品に魅力を感じ、あるいは反発し、どこに一貫性を見いだすか、を詰めていった時に、初代、二代目のありようが見えてくる。 ③ 多様に描かれている二代目 この作品の二代目の、金を拾ってからの悩み、迷いなどの心の動きは、単にダメな人間の弱さのあらわれというものではなく、人間的なものを求める二代目のある思い、二代目の中に形成されている非人間的なものとの相剋、矛盾と捉える。 読者の視座からみると、利左が吉州を発見したようにはいかなかったこの男に、ある悲哀を感じることがある。しかし、それを二代目自身が内なる探究をするようには描かれていない。そういうモメントを持っているかどうかも、形象化の対象になっていない。清十郎の場合、みな川が、吉州に値するかけがえのない女であることに気付かぬまま、お夏と“もやもや”になる。しかし、お夏の内部に形成された清十郎の姿には、新興町人二代目の、ある緊張した生き方が反映されている。金が金を儲ける世の中に、人間らしく生きるとは、という問いかけを、西鶴は人間喜劇という形で描き続けていることが、この作品の検討を通して見えてきた。 なお、鎌田屋の某の発言を西鶴自身のものとする読みには同意できない。身を持ち固めた初代的存在からみると、二代目のすることが、阿呆くさく、おかしいということなのだろう。新興町人二代目を中堅とする西鶴文学の読者の眼からすると、そのバカバカしい事自体が、どう問題になってくるのか。多くの読者は、そういう遊びさえできない現実の中で生きている。西鶴が投げかけていることを、読者自身が対話し、批判し、対決する。そうしうる言葉として位置づけられているのではないか。 ④ 「人情ばなし」をこえた作品(『小判は~』) 「『世間胸算用』に夫婦愛にふれた短編がありますね。一見人情ばなしみたいなんですが、よく読んでみると、どうしてどうして人情ばなしなんてものじゃない。まさに人間的な愛情の世界なのですね。」―― これまで“人情ばなし”を歴史的系譜において捉えていなかった事に気づく。 ある落語家は、人情ばなしについて、“長編小説を何回かに分けて口で語ったもの、人情・世態・風俗をリアルに追跡する時に生れる世界で、ホロリとするところも出てくるが、ホロリにアクセントがあるわけではない”と言っている。今取り組んでいるリアリズム志向のロマンチシズム、階級論としての世代論を考える時、“人情ばなしをこえている”という指摘は重要。この作品は、人間一般のあわれを描いたものではない。真剣に生きる二代目の、ダメなところも多く、時には衝動的に生きる時もある、が、これだけは譲れないというところで、大切なものを持って生きている人間を等身大に描いている。そこに“人情ばなしをこえるたもの”ろつながるものがあるのではないか。 〈話し合いの中から〉 [略] ○ 「新興町人」というのは階級概念。「新興町人二代目」というのは、世代的把握。階級一般があるのではない。その階級の階級的な世代として新興町人二代目を捉えている。西鶴の文学的イデオロギー(視点的立場)として、新興町人二代目の立場がある。その眼を通して見たとき、この若旦那は、新興町人二代目とは違うものとして映る。作品タイトルの「二代目」は、年代論に立ってのそれなのであろう。新興町人二代目の人間像が典型として描かれているというより、こうではないという方の典型。ありうべき二代目、その人間の可能性・可変性を、一つ一つそこに追求している。一つのプロセスにある作品。 単なる写実主義の意味で言われるものと典型思考のリアリズムとはちがうものだ。後者が本当のリアリズム。西鶴の姿勢こそ、そのリアリズムとよびうる。典型思考のリアリズムは、人間の可能性が追求される。そのプロセスで生み出された作品であり、人間の姿を通しながら、ある方向性が、読者の視座において見えてくるのだ。 ○ この作品の初代は、裸一貫から身をおこし働いた人。「常の町人」初代のイメージであり、二代目も、大店の旦那とか、非常に豊かであるというイメージではない。 この二代目は、お金に変に執着してはいない。サバサバしていて(さわやかで)後悔しているふうもない。遊女と二三の手紙のやりとりに感動するだけではなく、変に理屈をつけずに行動していく。初代とちがう面を探りあてている。読者の視座において、何か父親とちがった生き方がつかめてくる。新興町人二代目の可能性につながる何かを、かすかに探りあてている。 しかし、彼の感動は持続していかないそこに弱さが……。虚構性において弱い作品ではないか、ということがつきまとう。 典型とは何か。『長刀はむかしの鞘』のような、ヒーローのいない、しかし面白い作品を読んできた。ヒーローを描くことが典型だという確認はない。 [略] 〈次回に向けて論点の整理――話題提供者の発言より〉 読者の視座からみた時、この作品の作中人物(二代目)が自覚的、意識的に初代を超えて生きていこうとしているようには描かれていない。(この点、意見一致) その一致をふまえて――二代目に、ある瞬間瞬間の魅力的な言動とか思いとかはあるにしても、そこに一貫性はないのではないか、という意見と、一貫性がないと見えるなかに、ある共軛する心情が感じられるのではないかという意見に分かれている。 末尾の鎌田屋の某の発言にこの作品の結論があるのではなく、作品の展開に即した思索過程に、この作品の魅力があるのではないか。 残された課題――“典型とは何か”“新興町人二代目の現実態と理想態との関係、関連”“虚構性のありよう――虚構性の弱い作品か”“『小判は~をどう読んだか” ▼1991/02/23 №468~№469 2月第一例会(2/9) Y.R. (1) 10分コーナー 問題別研究会の内容紹介 K.K. 信号としての言葉、記号としての言葉。私たちは記号主義(汎言語主義)に陥っているのではないか。そこから自分を解放しなければならない。 記号は、とりもなおさず、概念の記号化されたものである。地図にあるいろいろな記号、たとえば神社を表すのは鳥居の記号だが、その鳥居を見て描くイメージは人さまざまである。 言葉で、概念を表すわけだが、そのとき大切なのは、その概念内包である。それを組みかえ、明確にし続けることが必要になってくる。〈リアリズムとロマンチシズム〉〈階級と世代〉……、それぞれの概念を、その必要があるからこそ、今、とらえ直そう。 (2) 10分コーナー 世代概念について A.Y. 世代というのは固定化されたものとしてあるのではなく、たえず再生産過程の中で形成される。個々の変革のプロセスを通して、理想がとらえ直されていく。実践を志向する、動的なものとして世代をつかむ必要がある。 民族体験としての個の体験を追跡していったとき、その世代の体験のありようがはっきり見えてくるのではないか。 芥川世代、井伏世代、太宰世代、……との対話を通して、自身の世代とは?を見直すきっかけを持ちうる。 プチブル文学、ブルジョア文学、という枠組みではとらえられない文学創造、創造の完結(鑑賞)とのかかわりをとらえ直すきっかけとして、世代概念が私たちに提起されているのではないか。 (3) 『二代目に破る扇の風』についての話し合い 登場してくる二代目に可能性があるのか、ないのか、この作品は虚構性の弱い作品なのか、どうなのか、etc. と、少々混乱してしまった話し合いだったように思うので、とりあえず確認されたと思われる点のいくつかを……。 ○ 「西鶴の発見」において熊谷先生が「正も負も含めて二代目に特徴的な個性が追求されている」と書かれているわけだが、これが作品の鑑賞をしてきた今、納得できるのか、どうなのか。 ・ たとえば“五七度も分別かへけるが……”の部分には、人間と非人間との葛藤が単純化した形で描かれているわけだが、それは西鶴世代の葛藤、疎外からの回復という問題意識の中で描かれているのである。 ・ 二代目のひ弱さ、不徹底さをえぐり出す、というのだが、ここに出てくる二代目も、実は西鶴世代の内側に存在するからこそ、みつめ直し、自己変革しなければならない、そうした存在として描かれているのではないか。根っこにあるのは、我々は疎外された人間、ということなのだ。その疎外のされ方、表れ方はいろいろである。それをみつめ、それと対決していく中で、自分自身が直面する疎外状況、また自己疎外からの回復、可能性の発見、ということになっていくのではないだろうか。 ・ 私たちの内にも、この二代目の弱さ、不徹底さにつながるものを感じるのではないか。徹底して突きはなされて描かれたとき見えてくるものがあるだろう。 (私Y.R.個人、最後の場面でこの二代目に“爽快さのようなものを感じる”という発言をしたのだが、そのとらえ方は、この二代目に全く自分を感じないような、どこか傍観者の目で読み、しかも部分だけを読んでしまったところがあった。ここで改めて撤回したい。) つぎに『小判は寝姿の夢』に話が進んだのだが、時間がなくてまとめられませんでした。どうか、お許しを。次回以降に回します。 ▼1991/02/23 №470 2月第二例会(2/23) D.H. 『世間胸算用』巻三の三「小判は寝姿の夢」 前回にこの作品を朗読し、若干の意見が出された。今回はそれを受けての話し合いという形であったが、作品の印象の追跡といった性格の例会になった。それだけに様々な意見の中から新しい発見や、各自の読みの軌道修正がなされた。全員が発言する程の活発な話し合いだったが、ここではそうした話し合いの過程を追って紹介したい。 ○ 「左夜の中山にありし無間のかねをつきてなりとも、先此世をたすかりたし」という言葉の中に、来世よりもこの世を生きることに懸命な、どん底の人々の思いがある。また、この男(さる貧者)は、自分では何もせず、「一足とびに分限に成事を思ひ」という考えがある。前回にこの夫婦が通じ合っているかということが話題になったが、こうしたところに女房との微妙な違いがある。 ○ 今の意見につながるが、男は金の無さを一発で解決しようとする発想の弱さがあるが、女房は「けふの日いかにたてがたし」というように、日々の生活の中で貧しさを直視している。 ○ 冒頭の長者の言葉について。これは長者でさえも、夢でも生活を思わなければならない現実の厳しさを感じさせる言葉だろう。 ○ 男と女房の関係についてだが、夫にしてみれば、一足とびの分限でも夢見なければやっていけない現実なのだろう。弱さは弱さだが、夫のこの弱さは、それとして女房にも理解されているようだ。 ○ 二人の間には貧乏にありがちなカサカサした夫婦関係は見いだせない。そういうことでの「通じ合う」なら理解できる。 ○ 題名の「夢」、長者の「夢」、そして男の「夢」……此の展開を面白いと感じた。 ○ そのことについて。俳諧性、ということなのだと思うのだが、初期の西鶴のそれとは違って、それぞれの現実を喚起していく文体となっている。そうした厳しい文体なのだろう。また、「こちの人」という呼び方などに、この夫婦のジェネレーションの共有を感じるが。 ○ 厳しい文体という言葉が出たが、これは、何も眉間にシワをよせて読むということではないだろう。笑ったりしながら読者が文体に引き込まれるものだと思う。 ○ その、引き込まれるということだが、はじめから眼が貧者の側にあるのではなく、展開の中で引き込まれていくのではないか。 ○ 「人置のかか」について。彼女は相手に選択の道をあたえないで、どんどんことを進める。非人間的な人物として明確にイメージされる。 ○ 彼女もこうしなければ生きてゆけない現実であるわけだが、そうした中で疎外されつくしている。隣のかかたちにしても、「いい人達」なのであろうが、「お内儀様は果報。さきの旦那殿が綺麗なる女房をつかふ事がすきぢや」云々、といった言葉を男に言ってしまうところなど、やはり疎外された人間を感じる。男や女房とはメンタリティーが違う。階級は同じでも世代は違うということを実感する。 ○ 女房は、「我が手前を思召して、さぞ口惜しかるべし」というように、夫への言葉を、気持をくぐる中で選択している。女房の夫に対する信頼を感じる。 ○ 夫婦の関係をとらえてきたことで、かんばし二ぜんを焼くところが、より感動する。女房の夫の対する思いということが出されてきたが、この場面は夫の女房への思いが出ている。夫婦で正月を迎えることを楽しみにしていた二人の思いを感じる。単なる感傷でないと思った。 ○ 感傷でないということは、一人でかんばしを焼く男の中に感傷がないということか。 ○ 自分としては、「新玉の春に二人あふこそ楽みなれ」という言葉の、女房への愛情について使ったつもりだった。 ○ 男は隣のかかの話を聞く中で、自分にとって大事なものは何かということに気づいていく。 ○ 長屋の女房たちは、人置のかかとは違うやさしさがあるが、金の論理に乗っかっていってしまう。こう見ると、この二人の夫婦の可能性は大きなものと映る。しかしだからといって、経済的な苦しさから彼らが解放されるわけではない。 ○ 人置のかかも、この男も、金へのある呪いの思いがある。しかし、そこでの「行動の選び方」が重要な点なのであろう。 春合宿プログラム テーマ《リアリズムとロマンチシズム――階級的世代ということ》 ◎ 階級的世代ということ 熊谷先生 1. “君死に給ふことなかれ” 世話人:N (テキスト:『日本人の自画像』) 2. 二つの芥川論 世話人:S (テキスト:『日本人の自画像』『芸術の論理』) 3. 西鶴世代とは何か 世話人:A (テキスト:「西鶴の発見」「芭蕉文学への視角」「近世文学における異端の系譜」、および、上記論文中で問題になっている西鶴作品) ▼1991/04/13 №471~№473 春合宿(3/27-29) 報告 I.H. & N.T. №471 春合宿1日目 I.H. 熊谷先生は具合があまりよくないところを、今回の合宿には無理をして参加して下さった。心から感謝するとともに、負担をかけないでしっかり学び合いたい、という委員長からの言葉で合宿が始まった。また、嬉しいことに、S.S.さん、A.Y.さんがお元気になられ、合宿に参加された。 1.委員長からの報告 1) 湾岸戦争についての文教研の声明を、というD氏からの要請あり。平和教育としての文学教育という視点で、次号機関誌の巻頭言などで姿勢を明らかにする。(今後ともこういう要請・指摘はしてほしい、とのこと。) 2) 全国集会に向けて。[略] 2.第40回全国集会のプランの提案 熊谷先生から、下記のような具体案を含んだ構想が示された。
プランについての熊谷先生の説明・補足 次のようなことをふまえて、プランを作りたい。 〈統一テーマ、及び1. 2. 3. について〉 芥川研究を例にとると、私たちは、その都度の必要性と感動をもとに、時間をかけて集団で研究し、様々なものに書いてきた。その各々の芥川論は、統一された全体像(芥川論)とはなっていない。その具体例をあげれば、『日本人の自画像』と『芸術の論理』の芥川像は異なっている。『自画像』では扱わなかった『秋』という作品を『論理』では取り上げた。その作品は、蔵原惟人氏の把握では、「悪しき小市民文学」となってしまうのであろう。が、私自身は,「作家志望の青年、そのかつての恋人、その妹という人間のからみ合いの中で、秋という題にシンボライズされる人生というものに正面から取り組んだ、リアリスティックな作品であり、そこにはすぐれたロマンチシズムがある」と考えている。この『秋』も含めての芥川文学の全体像について私たちの共通の視点・理解を作りあげる必要がある。このように、文学史あるいは文学の理論の問題として、いろいろな角度から検討してきたものを総ざらえして、芥川文学、太宰文学、井伏文学などの私たちなりの全体像をつかみ、その基本的な押さえを、それぞれのドラエモン・ポケット[バラバラなままの蓄積ではなく、必要に応じて必要なものを取り出せるような、ひとまとまりのもの。実践的に有効な体系]にすること、それが準備集会の狙いであり、その総決算を全国集会で行いたい。 二つの基調報告で打ち出される、私たちの文学史の根本命題、基調概念(キイ・コンセプト)としてのリアリズムとロマンチシズムを、今次集会の目的に沿ってとらえていく中で、統一テーマが明らかにされる。その後、4以降で少しずつ具体化していきたい。 〈4. について〉 1) 初代と二代目の問題が西鶴においては決定的。西鶴のリアリズムとロマンチシズムをめぐりながら、その仕事が世代概念(意識)によって成立したものであることを明らかにする。 2) 近松は、どのような世代のどのような文学をどのように受け継いだのか。以貫やその師匠たち(古学派)の学統・研究・芸論と近松のリアリズムの結び付き。また、その違い。以貫と出会う前と後のリアリズムの想念、近松自身の世代的変容。 〈8/6 以降について〉 扱う頃柄だけを並べた。ドラエモン・ポケットにするために、どんな作品をどういう方向で取り上げたらいいか一人一人の意見を出してもらいたい。 〈全体像の把握についての補足〉 “文学史1929”、井伏文学にとって、日本近代文学史にとってエポックメーキングな年。『屋根の上のサワン』『山椒魚』『炭鉱地帯病院』などによって初めて実現した文体、文体的発想。その人間把握、歴史のつかみ方は、漱石や芥川にも到達しえなかった、後追いした太宰さえもその面では追いつけなかったもの。このことは、『自画像』の検討だけではつかめなかった。『井伏鱒二』において井伏文学に焦点をあて、内在的に追求していった時に初めてつかめるのが、“1929”の想念である。ここに作家論の必要性がある。全体像をつかむには、この両側面の統一が必要なのである。 「現代史としての文学史」の提案理由、『自画像』の「あとがき」を、もう一度読んでみてもらいたい。 №472 I.H. 〈リアリズムとロマンチシズムについての補足〉 リアリズム志向のロマンチシズムは精神構造の問題であり、リアリズムとロマンチシズムは、マルクスのいう「意識と存在」の問題のように、相互に支え合う。ここをもとに、『自画像』p.71「(新詩社の)リアリズム」という問題を考えたい。これは、リアリズムとは何か、ロマンチシズムとは何かを考えることでもある。これをはずすと、『This is 読売』の三浦朱門['91年4月号「三浦朱門の教科書検定」]のように、「晶子は、がりがり亡者の商人、前近代(封建)思想の持ち主」という論になる。勝本清一郎氏の研究の、新詩社は「八分が前垂掛」というのは、20%がそうではない点の押さえが大事であり、「存在が意識を決定し、意識が存在を決定する」というのは矛盾ではないことをきちんととらえたい。たまたまプロレタリアートの子息に生まれなければ弁証法的唯物論者の立場に立てないのか。教育は意識変革の営みである。 3.全国集会のプランについての話し合い 〈1. 2. 3. あいさつ、基調報告に関して〉 統一テーマの意義、全国集会の課題を明らかにする発言が続いた。以下その要約である。 ○ 湾岸戦争[日本時間1991年1月17日、アメリカを中心とする多国籍軍がイラクに対して攻撃を開始し、湾岸戦争が始まった。]を目のあたりにして、プシコ・イデオロギーの動揺としての思想の混迷、外部と内部がつながりきれていない自己を感じた。現代のテーマとして本当の対話を現実と切り結ぶとき、文学史の問題が「現代史としての文学史」の問題として実感されてきた。 『自画像』では、日本の近代の本当のリアリズムとは何だったかということが、世代の受け継ぎという形で追いかけられている。 ○ リアリズムとロマンチシズムは一体のものでありながら相互規定しているということを、具体的な文学史の中で、また、それを武器としながら考えていくこと。これが基調概念としてのリアリズムとロマンチシズムのいみだということがつかめてきた。 「君死にたまふことなかれ」での先生の指摘。「新詩社のリアリズム、ロマンチシズム」。リアリズムは、一般性ではなく、普遍性の中で考えられてくる概念。このおさえがないと、「客観主義的」なリアリズム論にとらわれてしまう。自分自身の人間主体の在り方をぬきにしてはありえないもの。そこを明確におさえることで、現代史としての文学史への視点が主体化してくる。これまでの研究をさらに発展させるプランだ。 ○ 芥川すら到達できなかった井伏の文体という視点をもつことで、さらに、今回のテーマは、はっきりしてくるのではないか。また、世代論の視点をはっきりすえることで、“1929”は私たちのものとなるように思う。 〈4. について〉 主に4の2について、熊谷先生に講演をお願いしたいという要望が多く出されたが、体調不振で、十分な研究のできる状態でなく、講演に責任を持ちきれないとのこと。ソコデ、S.M.氏やT.M.氏の提案もあり、共同研究者による座談とシンポジウムという形にし、そこへ体調に応じて先生に参加して頂くことをお願いした。 4への意見としては、近世リアリズムと近代リアリズム、近世文学と近代文学の接点を明らかにしつつ、世代の受け継ぎ、リアリズムとロマンチシズムを考えたいということが出された。また、熊谷先生には談話の形か何かで、私たちの欠けている面やタイムリーに取り上げなくてはならないことなど自由に話して頂きたいという要望が出された。 〈8/6 以降のプログラムに関連して〉 いくつかの具体的な作品が出されたあとで、熊谷先生から作品を選ぶ視点についての整理があった。 ○ (熊谷) 「読者中心の文学史」ということが世間でも話題になっているが、文教研の理論は、鑑賞ということを、どう位置づけるかという点が違う。読む(鑑賞する)というのは、創造のすぐれた完結のためのもの。作家は読者の立場をくぐることでこれまでの完結の方向が違っていたことに気づき、別の作品を創造してゆく。(井伏『幽閉』→『山椒魚』)読者においても同じ。読む主体が変化していれば、鑑賞(創造の完結)も変わる。どういう完結を導くために読むのか、なぜ自分がその作品を読みたいのかを明らかにしてほしい。 この整理の方向で、出された意見の中からいくつかを紹介しておきたい。 ○ 湾岸戦争の起こった現在、文学を学ぶ自分の課題は何かということがつきつけられている現実。そういう現実と対決してゆく人間の受け継ぎの問題を考えるという点で、『秋』をやってみたい。信子のフィルターを通して見えてきた俊吉像を大切にしつつ、信子のフィルターにまどわされない自分に鍛えていきたい。 ○ 『井伏鱒二』を読み返す中で、湾岸戦争を「階級疎外の極致」として主体的にとらえられた。例会では、西鶴文学での近世の世代と芥川文学での近代の世代を自分の中で統一してつかんでいなかった。その弱さを補強する『秋』。そこには同じ階級でありながら違う世代が描かれている。 (熊谷) 出発点が違うと一緒の仕事も生まれ得ない。「君死に~」は反戦思想の産物ではないという点や、蔵原理論について発展的に受け継ぐ面と、何かに足元をすくわれている面とを明らかにする視点など、しっかり確かめ合い、押さえたい。 №473 春合宿2日目 N.T. 〈「君死にたまふことなかれ」〉 このパートは、 1) 新詩社のリアリズムとロマンチシズム 2) 現在の「君死に~」の評価をめぐって の報告が行われました。 1)についてN.T.氏より報告 ・資料『日本人の自画像』に即したまとめ(A) ・新詩社の“二分”の人々の紹介資料(B) Aに基づいて『自画像』の近代主義の規定、日本近代文学の成立、および透谷・晶子の両世代とその受け継ぎ――透谷が文三のつぶやきをどう受け継いだか。晶子が透谷から受け継いだものは何か。また藤村は……、という各々の世代で追求された近代的自我解放の思索と実践、ロマンチシズムとリアリズムのありようが報告された。[略] 報告の概要――晶子が受け継いだ透谷は日本近代という「実世界」と闘った透谷である。晶子世代の場合、自我解放の契機として観念のの網の目をくぐった「想世界」の本能が、内的世界を外的世界に分裂した透谷世代をのりこえて、内部と外部の通路となった。それは新詩社の“八分”の前垂掛の合理主義に基盤をもつ故だ。さらに“二分”の人々(平出修・大石誠之助・春夫・啄木ら)の文学的イデオロギーとして、世代の課題を先取りする精神に触発されたこの詩は、晶子の複数の弟たちへの呼びかけであり、当時の意識的な人々の支えとなっただろう。そのロマンチシズムとそれを支えるリアリズムは前垂掛のリアリズムを超えたはみ出し方であり、高山樗牛のいう「美的生活」を妨げるものへの「本能」による抵抗であった。大町桂月の危険思想という非難に即座に反論した晶子と晶子を支えた新詩社の対応は、文学に自己の存在証明を求めた“二分”の人々の精神の自由を語るものだ。文三の問いが、透谷を受け継いだ晶子において、近代主義の克服の可能性として示されたのではないか。 報告の後、藤村の受け継ぎについて若干の質疑が行われ、その後、熊谷先生の「自分の読み、晶子論をどうとらえているか率直に」という呼びかけをうけて、話し合いを行った。 ○ 晶子の観念を再評価している『自画像』に共感。前垂掛のリアリズムをはみ出し、リアリスティックな世界を創造している新鮮さを感じた。 ○ 新詩社の“二分”の精神の何を受け継いだかが大切。はみ出していったものに大切なものがある。また氏の発表後、大町桂月の非難に即座に反論対応した晶子の本能が「人間の全人的な社会的行為の本能」であるという厳密な思索に共感と感銘を覚えた。 ○ この詩は反戦イデオロギーの詩ではない。晶子の文学主体を通してこの詩が創造されてくる内在的展開を透谷の受け継ぎとして主体をふまえた指摘に共感。晶子の前垂掛リアリズムからのはみ出し方に、西鶴や教養的中流下層階級者の異端者、はみ出し方とのある共軛を感じる。 ○ 寒川道夫氏は反戦詩としてとらえていた。この詩を非難する側と反戦と評価する側に共通した問題を感じる。 2)についてH.M.氏より報告 ・資料 「This is 読売」'91年4月号「三浦朱門の教科書検定」(A) 「朝日新聞」百人一語 梅原猛 '91年2月11日付(B) 『みだれ髪』からこの詩に至る内在的発展をとらえて媒介の仕方を考える。 文学の理論としてどうおさえるのか、という視点から、ユーモアを交えてご自身の実践をまじえながら報告された。 まず、Bの梅原氏の晶子の詩の評価について――自分の戦争体験のなかで「君死にたまふなかれ」と呼びかけてくれる人は一人もいなかった。今は、中東へ行く自衛隊に捧げるべきだとする発想を批判。次に三浦論文については、教科書左傾批判の一環としての晶子の詩評価であるとして、各出版社の社会科教科書の三浦分析の検討から話された。戦後の日本の高度成長を自由と繁栄の時代と規定し、否定面に目をむけた教科書を非難する氏の発想から、晶子の詩も「前垂掛の実利主義に基づいて、国家を度外視する遅れた前近代的意識の反映」と決めつけていることを指摘。そこから明治時代は進歩と繁栄の時代であり、漱石も作品の中で明治時代を肯定的に取り上げているとして、大方の国民はこの戦争に賛成であったとまで主張する氏の歴史意識が、大々的に宣伝されていくことに危惧を感じること、何より晶子の詩を文学をふまえない立場で評価する氏の姿勢に疑問を感じることなどが語られた。 以下話し合いの内容です。 ○ H.M.氏に同感。読売もサンケイなみになってしまっている。三浦氏は国語の先生は読み書きだけ教えればよいという人。晶子に関しては、マスコミでもその実生活面からアプローチする傾向があり、肝心な詩歌論評価がない。『自画像』は、その面でも画期的だ。 ○ 三浦氏の発想には、個の主張成立の叫びという発想がなく、素材主義的把握がある。大町の危険思想非難のやき直しだ。近代主義者としての氏の自己証明をみる。 ○ 現在のマスコミの論調に同調した三浦氏の晶子の前近代性、国際的視野の欠如という非難に、まやかしを感じる。この詩は今を生きる心棒になる詩であり、文学として楽しめる詩だ。 ○ 三浦氏の敗戦の意味をくぐらない発想では、文学を文学として楽しめない。 ○ に浦発言は時代錯誤。晶子世代の存在証明としてのこの詩の意義を見いだすべき。 ▼1991/04/27 №474~№476 春合宿(3/27-29) 報告(続き) T.K. & Y.A. №474 春合宿2~3日目 T.K. Y.R. K.T. 両氏の話題提供をうけ、西鶴文学に即しつつ世代概念を明らかにすること、そしてまた、世代論の観点から西鶴文学をつかみ直すことを目標として検討が進められた。 〈話題提供 1 Y.R.〉 西鶴は『二代目に破る扇の風』『小判は寝姿の夢』『人には棒振虫同然におもはれ』などの作品ごとに新興町人二代目のいろいろな顔を描いていく。そこに私たちは、西鶴の我が世代についての思索の深まりをうかがうことができる。 『二代目に破る扇の風』においては、対象(後に「恋風様」とよばれる男)を笑いとばしながらも、そこに自らの姿を感じとり、自己否定の契機を見出している。 『小判は寝姿の夢』では、決定的瞬間における「男」の行動選択のありようが描かれる。そうした彼の前途に待ち受けているものは、現実からの転落であり「はみ出し」であろう。新興町人社会内部での階級分化が顕著になっていく中で、自身、転落の危機にさらされているがゆえに、この「男」に「明日は我が身」と感じざるをえない人、そしてまた、「男」の行動選択に驚きと共感を感じる人こそが、この作品本来の読者たりうるのであろう。 この^「男」のはみ出していく方向に、私たちは『人には棒振虫同然におもはれ』の、あの利左衛門の徹底したはみ出し方を想い浮かべる。転落の瀬戸際で、自身と吉州たち母子を辛うじて支えていた利左衛門は、友人たちとの再開から生じた新たな危機に際して、徹底した逃亡の道を選ぶことで彼の人間としての証を立てようとした。このように、はみ出すことによってしか「人間」を守れないようにしてしまっているものに対して怒りを感じる人々こそ新興町人二代目としての西鶴世代と呼びうるのではないか。 このように見てくると、西鶴文学の展開は、どう生きることが人間らしい生き方なのか、それを探る筋道であったことが分かる。 作品一つ一つの中に描かれたはみ出し方、そこに西鶴のリアリズムとロマンチシズムの問題を探ることができよう。 〈話題提供 2 K.T.〉 (Y氏の話題提供につなげて) これらの作品にはそれぞれ「生きている人間」が描かれている。それは「階級的世代の人間」が「個」として描かれているということだ。このように西鶴文学においては、「階級」が外側から規定されるのではなく、個々の人間のプシコ・イデオロギーにおいて描かれている。マルキシズム以前の西鶴が階級的人間を生き生きと描きえているのだ。 熊谷先生の「西鶴文学地図」は、通常なされる素材による西鶴文学の分類でなく、新興町人二代目の視点的立場の深まりの過程を主軸として提示されている。しかもそれは、客観主義的、固定的なものとして捉えられるのではなく、西鶴文学読者としての鑑賞体験の総括として描きだされた「地図」であることに注目したい。 第一期 西鶴の自己の階級的視点がまだ弱い。当然そうしたところから出発せざるをえなかったということだが、しかし、そのような中にも、後の西鶴につながっていく側面を見過ごすことはできない。じっくり現実を見ていこう、類型的把握でなく対象を凝視していこう、とする姿勢がうかがわれる。 第二期 初代新興町人の姿が見えてくることで、二代目としての自分たちがどういうものであるのかということが見えてくる。むろんまたその逆の関係もあって、西鶴の階級的世代の視点が深まっていくのである。自己の世代に対しての西鶴の見方は厳しい。そのひ弱さ、こずるさなどマイナス面からも目をそらすことはしない。それは芥川龍之介の、例の、他人の中の愚だけでなく自分の中の愚も徹底して見ていくという姿勢に通じるものである。このように、凝視の中で自分の世代のつかみ直しが進んでいく。 とすると、私たちの世代概念は、蔵原惟人が「階級的人間以外に生きた人間はありえない」というときの「階級的人間」とちょっと違うのではないか。確かに「人間性一般というものは現実には存在せず、存在するのはただ個々の階級の個々の人間の性質である」(蔵原)としても、蔵原が階級的人間を「型」において捉えようとしているかぎり賛同しかねるのである。真に「階級的に描く」とはどういうことなのか。その問に答えようとするとき、単に階級という枠ぐみだけでは足りずに「世代(階級的世代)」概念が、不可欠のものとして要請されてくるのではないか。西鶴は彼自身の創造の営みの中で「階級的人間」を固定的、類型的にではなく生きいきとつかんでいった。それは現実の疎外状況の中で真の仲間を発見していく過程でもあった。 第三期 現実からのはみ出しが問題になってくる。それは晶子の「はみ出し」ともつながるが、元禄期特有のはみ出しの徹底した姿を、私たちは利左衛門に見る。これは、西鶴世代がどういうものであるかを考えるうえで大切である。「はみ出したその先に待ち構えているものは、やはり封建の世の中」(「西鶴の発見」)なのだ。近代と別個のはみ出しなのだが、しかし近代の異端の文学系譜に西鶴世代の姿がつながってくる。その根底に貫くものは、人間を人間でなくするものへの怒りだ。 〈討論から〉 ○ 新興町人初代が「大方は吉蔵三助がなりあがり」(『永代蔵』 だとして、では二代目を文教研の世代概念からいってどう定義づけたらよいか。二代目とは何かという世代的規定をしてほしい。 ○(熊谷) (直接的には、M.M.氏の、「世代」とは何か、もう一遍はっきりつかみたいということに対して)初代新興町人については、「西鶴の発見」(機関誌№115)9~10頁参照。新興町人二代目については、同10頁を参照。1675年江戸に進出して越後屋呉服店を開業した三井高利は、いわゆる二代目だが、彼はやがて黒い手の性格をはっきり見せていく(1683年、両替店開業)。巨大資本の成立である。 一方にそうした金融資本の支配のもとで痛めつけられていく人たちがいる。中下層町人の、明日への希望を失っていく姿。70~80年代、これが新興町人の新しい姿がある。 この時期、たとえば芭蕉の弟子の多くが巨大資本につながっていく。そのような現実からの「逃亡」として、芭蕉の、市中日本橋を去っての深川村草庵入りがある。ここに私たちが、芭蕉世代の「二代目性」を見る。このようなことがわかれば、こと改めて論議することもなかろう。 ○ 私たちの世代論は、蔵原の所論と「ちょっと」だけ違うのか。 ○ (K.T.)根本的に違う、と言い換えたい。 ○ 「普遍につながる個=典型」という私たちの考え方と、蔵原の、芸術家の任務を「現実の再現」であるとし「階級的型」において階級的人間を描こうとすることとは、決定的に違う。 ○ 蔵原は、「階級――層――集団……」と考えるわけだが、階級を「一つの型」で考えないところは柔軟性を感じさせるとしても、しかし「層」といったところで、しょせん輪切り。そこのはそれぞれの型が見られるにすぎない。こうした蔵原理論を超えるところに熊谷先生の階級的世代論がある。 ○ ある時期、西鶴文学は上層町人の文学だという見解があった。真に古典と対話するということはどういうことなのか。今、そのことを文教研が先頭に立ってやっているのだ。 ○ (K.T.) 型(タイプ)ということで西鶴文学はつかむことはできない。そうした外枠によってではなく、プシコ・イデオロギーの問題として捉えていくべきであろう。「世代」はダイナミックな概念だ。二代目とは自分という読者にとってどういうものなのかということが、本当は話題提供で話したかったことだ。古典と真に向かい合うということは、「現代の実人生を私たちがポジティヴに生きつらぬいて行く上の、日常的で実践的な生活的必要からの既往現在の文学作品との対決ということ」(『日本人の自画像』 「あとがき」)だからである。 ○ 西鶴世代、そして西鶴世代の課題をいかに明らかにしていくかというところから、熊谷先生の時期区分論が出てきていると思う。西鶴における二代目新興町人の視点的立場の確立を1690年の時点とするご指摘も大切にしたい。 ○ 新興町人二代目と、新興町人二代目の視点的立場とをはっきり区別して考えていきたい。たとえば、プティブル二代目にもいろいろな意識(リッチとか……)があるのだから。 ○ 『二代目に破る扇の風』の「恋風様」、『小判は寝姿の夢』の「男」、『人には棒振虫同然に思はれ』の利左衛門らは、存在としては皆「常の町人二代目」といえる。そのことと、「常の町人二代目の視点的立場に立つ西鶴」とは区別したい。また、視点的立場に立ちうるということは、「教養的」ということと関わってこないか。 ○ 「世代を同じくする者」ということを、通じ合える仲間・対話できる仲間というように考えたい。決して固定的なものではないということだ。 ○ 典型(Vorbild)を描くということは、可能性を求めての営みだ。 ○ 真に「世代」をつかめるかどうかは、教養のあり方に関わってくるのではないか。自己の世代を抉っていこうとする中に、自己の世代をつかんでいく契機がある。「人は化物」と押えることで、その中でプシコ・イデオロギーが見えてくる。 ※ニュース部より 春合宿での芥川論の部分、そして前回(4/13)の例会分(『道化の華』)が都合で次回まわしになってしまいました。お許し下さい。 №476 Y.A. 〈二つの芥川論〉 以下は、春合宿二日目の午後から夜にかけて、上記のテーマで話し合われたパートをまとめたものです。本来ならば4月第一例会に出るはずのものが、まるまる一ヶ月おくれたのは、全く、このパートのまとめを担当したY.A.の責任であります。[略] ◇I .M.報告 要旨 『現代文学にみる日本人の自画像』(以下、『自画像』と略記)の芥川論と『芸術の論理』の芥川論を、トータルにおさえたい。その「あとがき」に書かれているように、『自画像』は、近代文学史を〈現代史としての文学史〉の視点から叙述されている。それは、作中人物に関して、人間主体の精神の系譜としてとらえていこうとするものである。『自画像』では、芥川は〈近代主義と対決した作家〉としておさえられ(近代主義の克服)、『大導寺信輔の半生』(以下、『信輔』と略記)がとりあげられている(大正デモクラシーの文学体験――孤独に堪える性情)。信輔と『浮雲』の文三や『破戒』の丑松らとの連続・不連続の問題が検討されている(『一九二八年三月一五日』では、竜吉と信輔との関連もとりあげられている)。『自画像』の叙述は、近代主義との対決という視点から、作中人物の精神の系譜としてダイナミックに展開されている。そうした〈現代史としての文学史〉の視点による近代文学史の大きな流れの中に、『信輔』が位置づけられている。一方、『芸術の論理』の芥川論は、芥川文学の展開そのものに密着して、作家論的視点から追跡されている。そこで明らかにされていることは、芥川文学の内在的発展として『信輔』という作品が実現したということ、また『芋粥』が『信輔』につながる作品として位置づくこと、などなど。このような芥川文学の内在的発展の過程を追跡していくなかで、芥川文学が、井歩一歩何を実現していったのかが綿密にあとづけられている。同時に、〈二人の芥川〉ということが指摘され、芥川文学のどういう可能性に目をむけたとき、芥川文学をトータルにとらえられるのかということも提起されている。こうして見てくると、『自画像』の芥川論と『芸術の論理』の芥川論は、どちらが上でどちらが下ということでなしに、その全体像をつかむために、二つの側面から芥川文学を追究したものだといえるだろう。 A 近代文学史の流れの中で、芥川文学がどのように生まれてきたのか、また、そ れはどのように位置づけられるのか、を検討すること。この、A・B両側面を相即的に追究することで芥川文学がトータルにとらえられるのだろう。 ◇話し合いで話題になったこと ○ 『自画像』の芥川論と『芸術の論理』の芥川論とはバラバラではなく、相互にささえあう関係だ。『自画像』では、世代のうけつぎ・近代主義との対決の視点から、自己の階級主体を凝視し、つきはなしたところで階級疎外を見つめていったのが芥川文学だと位置づけられている。そうした芥川文学の内在的発展を追究したエポック・メーキングな作品として『信輔』を取り上げ、問題を深く抉りだしている。 ○ 『芸術の論理』では、芥川文学を初期からたどり、『秋』についても触れられている(p.243)。幻の『偸盗』をさぐる営み――作品の可能性をさぐる営み――と信輔のその後を竜吉に見ていくという把握のしかたと方法的には一つだ。『自画像』の芥川論と決して矛盾しない。 ○ 『秋』は『芸術の論理』では〈男と女〉という角度からとりあげられているが、切り口を変えてみるとまたちがった面が見えてくるだろうし、それができる豊かな作品だ。例えば、自分なら信子と照子のどちらを選ぶかといった点でも楽しめる。また、俊吉に目を向けると、そのある側面――旧制高校から以後の時期――が焦点をしぼって『信輔』で描かれているという面もあるのではないか。 ○ 『秋』という作品――やや冗漫なところはあるが、短編として見事に整っている。信子と照子を登場させることで、プチ・ブルの女性の弱さや何やが実によく描かれている。これは他の登場人物では駄目だろう。これ以外ないという感じだ。信子の亭主(高商出の)にしてもそうだろう。選び抜かれた(設定し抜かれた?)人物が描かれている。こういう所に芥川のリアリズムとロマンチシズムの相互の支えあいがみえてくるのではないか。血(血縁)が同じなら、あるいは、階級が同じなら、みな同じだと俗には考えられがちだ、血は同じでも、階級は同じでも、世代が違えば人間は違うということ(俗論に対する反論)が見事にとらえられている。『秋』という作品は、位置づけるときのテーマによって、いろいろなコースが考えられる豊かな作品だ。 ○ 教養のありかたということについて、その世代の教養とはどういう教養なのか(その世代を形づくっている教養とは何か)、大きな問題だ。そういう点から見たとき、芥川が、一高での蘆花の講演を聴いているに違いないという、熊谷先生が出された仮説の持つ意味は大きい。第四次新思潮を形づくった人々のほとんどが、蘆花講演を聴いている。熊谷先生の提起されたことはすでに仮説の域を越えている。 ○ 世代、世代形成の問題は、まさに、文学と教育の問題だ。『秋』の俊吉に芥川世代を感じる。自己の世代形成に大逆事件が色濃く影をおとし、いまだにそこから抜け出せず抱え込んでいる人。文学的事象としての大逆事件を、自己の世代形成過程で体験し、抱き続けた人。それが俊吉なのではないか。まさに、芥川でなければ描けない。 ○ 血縁、地縁ということが問題にされたが、世代論的な意味で、芥川はたぐいまれな〈東京っ子〉ではないのか。〈江戸っ子〉では断じてない。俊吉もやはり〈東京っ子〉だろう。一高生というのは、いろいろな地方から集まってきた人々だが、その中にいい意味で〈東京っ子〉になりえた人々がいた。なかでも芥川はたぐいまれな〈東京っ子〉になりえた。俊吉――〈東京っ子〉の――のような人はもうでて来ない。そういう〈東京っ子〉を芥川は見事に描いた。芥川――断じて〈江戸っ子〉ではないし、また〈本所っ子〉でもない(本所生まれだが)。世代論としての話だが、俊吉は、文学に描かれた〈東京っ子〉の自画像ではないのか。芥川はどう見ても〈下町っ子〉ではないが、むきになって〈下町っ子〉のふりをしようとする。そこがやはり〈山の手っ子〉なのだろう。こんなふうに考えていくと、ふくよかに世代論を考えられるのではないか。 ※ この後、蔵原惟人の『芸術的方法についての感想』がとりあげられ、話しあわれた。まとめるべきなのだが、紙面もつきたし、なにより、私の手に余る。今少し、態勢を整えてから、ということにしたい。 ▼1991/05/11 №477~№478 ※ ニュース部より――4月第一例会分のニュースが都合により出せませんでした。 『道化の華』の第一回目。S.T.氏の司会、T.M.氏の報告。綿密な報告に基づき、話し合いが行われました。そして、この際『道化の華』の印象の追跡をきっちりやって見ようではないか、という提案がなされ、冒頭の部分から読み進めることになったわけです。本来、T.氏の優れた報告や、話し合いの内容をお伝えするべきなのですが、今回のニュースがかなり前回を含み込んだものとなっていますので、それでお許しいただきたいと思います。 4月第二例会(4/27) Tan.M. 〈前回の話題の確認〉 ○ 作品の中に出てくる「ぼく」がフィクショナルな形で出てきてはいるのだろうが、どこまで成功しているのか。あるメンタリティーとか、プシコ・イデオロギーとして成功しているのか。 ○ 冒頭の言葉「ここをすぎて悲しみの街」が、『葉』における冒頭のような、大きな役割を果しているのか。 ○ 普遍に通ずる、という形で表現されているか、という点では、はなはだ疑問であるが、ある面、怒濤の葉っぱの世代の代弁たりえているところもあるのではないか。 〈話し合いから〉 ―― 冒頭の部分に関して、前回の例会でS.M.さんの出した「太宰の気迫を感じる」ということについて、どういう意味で使ったのか、はっきりさせてほしい、という要望も出た。 ○ (S.M) 「おかしいか、なに、君だって」などのところに、『葉』の口調と似ているものを感じる。「酒でない、ほかのもっと強烈なものに酔いしれつつ……主人公のただならぬ気魄を象徴して……」などの表現。新しい小説の形を見いだそうとしている作家の心意気に気迫を感じたのだと思う。 ―― ここで、熊谷先生のほうから、第一ブロックを素直に読んで、印象の追跡しよう、という提案がなされた。 ○ (熊谷) 第一ブロックに限って気迫を感じる、というっことなのか、先まで読んでいって、トータルとして書き出しのところに強い訴え、叫びなどが響いてくるのか、ということをはっきりさせる必要があるのではないか。 ○ 「ここをすぎて悲しみの……」が、なぜここにいきなり出てくるかわからない。『葉』や『めくら草紙』の冒頭とはどこか違う感じがする。 ○ ぐっとひきつけられていく、というのではない。どこかしっくりこない。出だしから練られた形象的な文章として実現しているとは思えない。 ○ 付いていけない文調だ。語り口が空転している。ひとりよがりではないか。展開がわかりにくい。読者である自分の位置が見えにくい。 ○ 「ぼく」が、井伏の狂言まわしや、芥川の『羅生門』にみられるものとは違うのではないか。空振りを感じる。作者の意図がどう実現しているか、ということで言えば、文体として定着していないのではないか。 ○ 『女の決闘』における「私」などとは違い、『道化の華』においては、作者「ぼく」登場の必然性を読者には納得させえていない。 ○ 作者「ぼく」について、『道化の華』では成功していないが、それが、『女の決闘』で花開いていくのではないか。冒頭のところは、太宰の意図は別として、文体的弱さは否めないのではないか。 ―― 『ボヴァリー夫人』を誰が読んでいるのか、という点について。 ○ 文章を主語は、述語は、というふうに読んでいくと、い号室の女性が読んでいる、ということになる。しかし、その女性が読んでいるとすると、100ページの中からよい一行を見つける、というのがイメージと結びつかない。罪は太宰にあるのかなァ……。 ○ 葉蔵が『ボヴァリー夫人』を読んでいると、ずっと思っていた。 ○ この女性が読んでいるとしたら、ちぐはぐな感じを受ける。 ○ サナトリウムだから、結核で長期入院している20歳を越え、恋などに思いをはせる女性、というふうにも思える。だとしたら、『ボヴァリー夫人』に、ある共感をもって読んでいるのではないだろうか。 ○ なぜ読んでいるのが葉蔵だと思ったか。ここでは、葉蔵の人間像、同じ世代の人間、メンタリティーとつながるものを思いうかべて読んでいた。しかも、この女性は希薄な感じでしか描かれていないのではないか。 ○ この部分に、葉蔵のことば、その思いを描く言葉につながるリズムを感じる。それでやはりここは葉蔵のイメージで読んでいたように思う。 ○ 「エンマはたいまつの……」に強烈な印象を受ける。この女性が読んでいるという必然性は感じられない。 ○ (熊谷) 「エンマは……」というところはずっと響いていた。葉蔵が読んでいると読んでいた。今も葉蔵に主眼がある。どういうつもりだったのか、太宰本人に聞かなければわからないようなことだ。しかし、リズムやその他、前からの関連からいっても、やはり葉蔵が読んでいるというのが自然だろう。「よい一行」を選ぶ、というのも、この読者が前々から読んでいた、ということが前提になっている。だからこそ、命になるような一行が明確に引き出されてくる。どう見ても、葉蔵的人間――怒濤の葉っぱの世代、暗い谷間の世代の人間でないとそこへ目がいかないような表現ではないか。太宰の書き損ない、というか不正確な表現になっているのではないか。太宰の鋭さと欠点が始めからある作品ではないか。もし、い号室の女性が読んでいるとしたら、失敗としか言いようのない作品に思える。作品の構成、組み立てがまずい、という感じ。S.F.さんの、「葉蔵が読んでる、というほうが面白いよね」という意見に、全面賛成。 ○ 『日本人の自画像』の『道化の華』論に尽きている、と改めて感じる。優れた再創造なのである。それでは、『君死にたまふことなかれ』を私たちはどう再創造するのか、そうした問題としてつながってきたように思う。 ――かなり書き落としていると思います。また、『ボヴァリー夫人』のところについては、「葉蔵に読ませたい」という点で、皆一致していたように思います。話し合いのあと、S.N.さんの持ってきてくださったテープで、吉田隆子さん作曲の「君死にたまふことなかれ」の歌を聴きました。 ▼1991/05/25 №479 5月第一例会(5/12) Y.R この例会で、40回全国集会の最終プランが出された。第40回――ある節目になる全国集会として、各自のこれまでの総括が要請される、そんなプランだと思う。そして、参加者にとってなにより嬉しいニュース。昨年に引き続き、sくまが井先生の〈談話〉が実現した! そのプランについての企画部からの説明があったわけだが、それに先立って、5月5日に行われた問題別学習会について、10分コーナーとしてK.K.氏から話された。その内容と、全国集会プランについての話し合いの中で熊谷先生から話されたこととは密接につながっていると思うので、箇条書きふうにまとめたいと思う。そのことが、何より全国集会についての話し合いの骨子であると信じて。 5日の問題別では、〈西鶴文学にみる世代意識と虚構精神〉ということについて考えあった。そこで熊谷先生から出されたのは、世代意識――それは誰の世代意識なのかが問題にされなくてはならないだろう、ということである。 1. 作者の世代意識――彼の虚構精神を刺激し、その反応として作品が生まれる。 2. 本来の読者の世代意識 3. 創造の完結者としての読者の世代意識 4. 現代史としての文学史の視点 ――それは、読者が文学作品から受け継いできた世代意識、虚構精神。 1~4は、バラバラのものとしてではなくとらえられねばならない。 作品との対話で、自分の世代が見えてこないか、深まってこないか。 〈「歴史社会学派」について〉 一枚岩だと思っていたが、さにあらず。実はバラバラだった。その原因は、世代論にあった。世代論の欠如。のっぺらぼうの「階級論」。そしてそれは、階級論の欠如ということだった(歴史社会学派の理論的限界)。 しかし、歴史社会学派、とひとつものとして呼ばれた理由はあった。つまり、階級論を持たなければ文学史は成り立たない、というふうな考え方をしていた、ということだ。だからこそ蔵原惟人氏の業績、近代文学――ブルジョア文学、実はプチ・ブル文学だ、という明確な押さえ、そこに注目しえた。中世文学においては永積安明氏である。彼にも世代論は皆無である。しかし、藤原定家――中層貴族者の文学、鴨長明――下層貴族者の文学、として中層者の文学こそ、“中世文学”(“中世の文学”ではなく)たりえている、とした。これらが、歴史社会学派の成し遂げたことといっていいだろう。 〈普遍の中の個〉 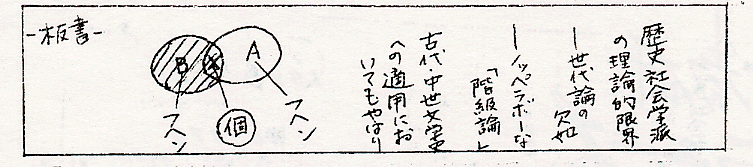 そこにあるそのもの、その人、その考え方、それをヘソの印で表してある(板書の×印)。ある普遍の中の個として位置づけられたときに意味をもってくる。そして普遍の中の個こそが、典型と呼ばれるべきものである。 例えば、[西鶴『人には棒振虫同然におもはれ』の]月夜の利左である。彼は、読めば読むほど、血筋の上では特権門閥町人である。しかし、彼はそこから抜け出ていった。新興町人意識にむけて。また、そういう生活の在り方にむけて逃亡していったのだ。三人の友人からも。返り咲きからも。敢えて苦しい生活を選んでいったのである。逃亡の先には、もっと苦しい生活があるだけである。けれど、本当に人間らしい生活がある。それを選んだ利左の姿が描かれている。 これは、どこにでもいる新興町人二代目ではない。世にも類い稀な二代目である。しかし、そんな利左の姿がリアリティーをもって存在していることの素晴らしさ。そんな利左を描けた西鶴。その西鶴は、家を手代に譲って雑階級者の道を選んだ人間なのである。そんなふうに、西鶴自身のとった行動、意識の変革。そんな中から、利左という人物形象が生まれた。そしてそのことがまた、西鶴自身に働きかけていく。 〈近世のリアリスト近松門左衛門〉 (『二代目に破る扇の風』の二代目は二千貫目を使い果たすわけだが、二千貫目とはどれほどの額なのか。換算すると、三万三千三百両。石高では五万石。大石内蔵助の取り高は千五百石。四公六民なので、年収は六百石。大石内蔵助の年収の83年分。大石家三代がかりなのである。そんなとんでもない金額を使い果たす二代目。そんな二代目を描くことで、初代がコケにされているのではないか。) そういった普遍の中の個という問題を取り上げていったときに、今度は、そのヘソ(=個)を近松門左衛門にとるわけだ。その近松をはっきりと支え、近松をして近世リアリズムの先頭に立つ一人に押し上げていった人、それが、古学派の穂積以貫である。片や学問の領域の人、もう一人は芸能の領域の人である。それが、この図形のようなからみあいの中から、違った個として、近松らしい近松を生み出していった。こういった意味において近松のリアリズムをとらえていってこそ、近松を、現代史としての文学史におけるリアリストとして評価できるのである。この評価をもたらすものは、世代論だ。近松は初めからリアリストだったわけではない。リアリズム文学を生み出していく新興町人二代目の精神を貫いた近松をここに導き出すのである。文学でなければできないことを近松は成し遂げた。古学派の学問領域とのタッチ、ドッキングのあったことだけが、それを可能にしたのである。 ▼1991/06/08 №480 5月第二例会(5/25) S.F. 10分コーナー(今後の研究の予告編) ◇ゼミナール『炭鉱地帯病院』について K.K. 文学史1929を明らかにしたい。 [略] ◇『君死にたまふことなかれ』について N.T. 晶子の歌をつくる姿勢と詩をつくる姿勢とは別のものではない、という視点を提示した『日本人の自画像』に学びながら、「明星」と、そこに集う文学者たちについて基礎的な面から調べてみたい。 [略] ◇『愚者の死』(佐藤春夫) 『墓碑銘』(石川啄木)について S.F. 世代形成期に、大逆事件のおよぼした影響。文学事象として大逆事件をおさえることで見えてくるもの。 [略] ▼1991/06/22 №481 6月第一例会(6/8) D.H. 6月第一例会は、熊谷先生の著作『文学教育』(1958年 国土社)の第二章を光村図書出版『現代国語大系』(全16巻 来年夏刊行予定)に収録したいという依頼があった、という嬉しい報告から始まった。 次いで、H.M.氏の広島での講演の報告もなされた。講演の題目は「自他の変革と文学の授業」。作品をまっとうに完結させるということをH.氏自身の経験にふれながら語った、ということだった。同行したK.K.氏によると、「主観性を切り捨てるところに読みの客観性が生じるのではなく、問われるべきなのは、主観の質である、ということを強調しながら、「創造の完結者としての読者」ということをキチッと位置づけていた。感動した。」とのことであった。 熊谷先生の文章や、広島での講演などを通して、一人でも多くの仲間ができることを願わずにいられない。 [このあと、全国集会プログラムにしたがい、芥川『秋』、太宰『右大臣実朝』についての報告、話し合いが行われた。話し合いの中から熊谷先生の指摘・助言の部分を摘記する。] ○ (熊谷) なぜ今度の全国集会で、『秋』や『右大臣実朝』などの作品を選んだのか、今回のテーマから見て、なぜ『河童』ではなく『秋』なのか、ということの詰めが甘いのではないだろうか。現代に「創造の完結」を行う自分の本音から初めて、考え直すべきなのではないか。ここでいわゆる『秋』論や『右大臣実朝』論を行うのではない。自分自身の問題を解決するために、自分のヘナチョコな階級論・世代論を生き生きとした行動的なものにするための場なのだ、という基本をおさえなければ何もならない。〈1929〉の後に『右大臣実朝』を取り上げるということは、〈1929〉の発展として、という一本がそこに入ってくる。その一本を自分自身の問題としてどうつかむのか、ということなのだ。 ○ (熊谷) [ 『右大臣実朝』の]近習が実朝と共に世代形成期を送り、自己の世代感覚を身につけていったことは確かだろう。そのことを角度を変えてみるならば、ある意味で別個の世代意識にゆきつく近習であるという作品展開なのではないだろうか。世代のうけつぎ・発展とはそうしたものであろう。その意味で、この作品は、普遍の中に個をとらえた、典型の認識の見事に成り立っている作品なのだ。 今回の例会は、「現代史としての文学史」というテーマと「世代論・階級論」の問題とのつながりが、明確になった例会だった。「自分自身の課題を解決するため」という基本のところをあいまいにしていたので、私自身のそうした姿勢への厳しい反省がせまられた思いがした。ともあれ、全国集会への大きな方向性が示された例会であった。 ▼1991/07/13 №483 6月第二例会(6/22) T.K. 全国集会プログラム10.ゼミナール『炭鉱地帯病院』のチューター提案については5/25の例会で既にK.K.氏から報告があった。今例会の課題は、この作品の総合読みを通して〈文学史1929〉の意味を明らかにするということである。報告は三つのパートの分けて進められた。以下はその要旨である。 Ⅰ 「私」とケーテーを中心に [略] Ⅱ 「私」と「おやじさん」を中心に [略] Ⅲ 「私」と看護婦を中心に [略] 【討論から】 ○ 語り口の問題が大切。「その人の語り口」を通して「その人」がつかめる、そんな作品だ。語り口が強烈な刺激となって読者に迫ってくる。ここは看護婦の生き方を問題にするパートではないだろう。「生命五匁説」でケーテーが見えてくるという方向だ。 ○ 確かに、看護婦は看護婦ということではだめだなと思う。読者は、ケーテーの言→おやじさんの言→看護婦の言、と見てきているわけだから。 ○ 表現の重層性ということが見えてきた。誰の言にしろ、最初から結論があって語っているのではなく、その語りの中にひとりひとりの思索過程が描かれている。処理し切れない内面の葛藤だとか、倦怠の思いだとか、言うことによってまた自分に返ってくる問題だとか、それらが重なりあいながら進行している感じだ。個々人の生活の実際と屈託の心情が、訪問記者の「私」殿関わりの中で出てくる。「私」は「通路」を作ってくれているのだ。だから、「私」は分をわきまえて出来るだけ作中人物の言葉を、あるときにはそのまま、あるときには雑報風に翻訳して媒介しようとする。だが、それにとどまらず作中人物としても行動し、それが批判される、という最後の場面になる。だから、単に事実的に読んでいく姿勢からはこの作品の表現は自分のものになっていこない。自己との対決の中で初めてこの作品の表現が表現としてアピアしてくるのだなと、感じている。 ○ (報告者、K.K.) 「民衆的現実に即し民衆個々人の生活の実際と屈託の心情・実感に即して」(『井伏鱒二』p.188)というところで、この作品は芥川の『秋』とつながっていくと思う。日常性にまで下りてきた作品として『秋』を捉えた私たちだが、ここでは更に民衆の現実にそれぞれ分け入ってきめ細かく形象化されている。が、そこに世代の問題という視点からもう一歩切り込んで行かなくてはならないと思っている。 ○ (熊谷) 『秋』との比較をするということは、すなわち表現の比較だ。文学でなくても言えるし、文学でないほうがかっちり言えるというものもある。そんな中でこれ(『秋』『炭鉱地帯病院』)は文学でなければ言えない表現だ。狂言回しの何のといっても、結論が出ていてそれに合わせていくのではないのだ。自然そうなっていくしそれしか道がない、というふうな辿り方をしている。ある意味で こさえもの 過ぎるという感じがあるかもしれない。文学でなければ言えない、文学だからこそ言えること、それが表現というもの。 この作品、狂言回しとか語り手とか、その両方を兼担している人とか初めから決まっているわけではない。こうしなければ文学にならない、ということを文学的に突き詰めている。つまり表現の究極のもの、といったものが自然と出ている。 存外ひとりひとりの人がみんな自分の感じていること・思っていること・訴えたいことを勝手に自分の生活を通して、それから目の前で、事実としては共通に経験している事実に向きあいながら、しかも自分の世代が実感しているもの、それを最後まで頑張りぬいている。そして、巧まずしてある自分の世代の主張のようなものを最後に出してきている。妙な作品だと思うが、そのことは例えば、最後の部分を見てほしい。「人々のテンダネスを虚偽として……」、これは百姓じいさんの本音だ。彼は今、洋酒を飲んで頭がしびれているという自覚があるが、普段は何かにしびれっぱなしの人物。そのしびれた感覚でものを見ることで終始一貫している。そして最後にもっともらしくでてくる言葉の中身は、「おめぇのは贋造紙幣だよ」。そういって探訪記者はやっつけられる。 読者の世代というのは、この探訪記者の世代ではないのか。この探訪記者である「私」の世代の目というのが最初から最後まで一貫して通っている作品だ、と言ってはいけないか。この「私」が、あるところで言う。この看護婦のことを、こういうの大嫌いなのだと。看護婦の世代の持つある基本的な感覚というものとは、どうにも握手できない。やりきれない。そういうものが一貫しているような感じなのだが、どうだろうか。「私」は、その世代の感覚で通している。それを通して見ている。その目に映った看護婦はどうだ。百姓じいさんはどうだ。ケーテーはどうだ。その場合また、ケーテーは異人さんなのだが、ある意味ではいちばんぴったりときている。イデオロギーの面では違うものを感じる。案外こいつ古いよと思ったりもする。しかし、ある感覚――プシコ・イデオロギーにおいては一致がある。これは終始変わっていない。 看護婦というのはどうしても好きになれない。苦しい生活をしている、辛い生活をしている、そういう苦しんでいる人の目に映る出来事とか、話題とか蹴飛ばさないで、ちゃんと描いている、というのは、報告者の指摘のとおりだと思う。にかかわらず、「私」は永久にこの感覚にはなれない。それを紹介している。そこのところ、案外大事なのではないか。プシコ・イデオロギーの、「私」の世代感覚へ向けての翻訳、そういう作品になっていないか。 「雑報的」ということ――これは論文でもない、小説でもない、まさに雑報なのだ。日常性に下りてきたのだ。しかもそれには新聞記者としての視点というものが入っている。一つ一つに「私」という人間のプシコ・イデオロギーが息づいている。それを通して対象が捉えられている。そうすることで、ふつう正確には見えてこないこと・聞こえてこないことが見えてくる・聞こえてくる、ということではないか。ケーテーのプシコ・イデオロギーもそうだし、看護婦もそうだし、百姓じいさんもそうだし……。 「ラメンテーション」という言葉に翻訳することで、百姓じいさんの幾世代にもわたる農民の長い長い歴史の持ちえているもの・持ったものが表明されている。そしてそれは形式は違っても、坊主の、僧侶哲学と内容において全く同じものである、という問題があるのではないか。だから、「生命五匁説」も、はたしてここに登場してくる人物によって肯定されるべきものなのか。その人物が看護婦でないことはもちろんだ。 ・そしたら父が……「同じことを何度もやっても、面白くも何ともない。」考えてみれば、それは私の初めての演技……一番厳しい観客に向かってやっちゃった……。(岸田今日子)井伏は、われわれが「1929」と名づけている新しい表現の仕方を、あの時点で実現した。これはまさにこの人の個性が生み出したもの。この「1929」を、本当の意味で「説明」すべきだ。 ▼1991/07/13 №485 7月第一例会(7/13) H.M. 初めにA.Y.氏から、基調報告(1)「〈現代史としての文学史〉の根本命題」の骨子が話された。 ① 茨木のり子の「わたしが一番きれいだったとき」を読んで、“私たちは幸せ”と言う若い人たち。障害者が放置されて飢え死にをする現実。全教に大会会場を貸そうとしない三鷹市当局。――こうした事実を踏まえて、私たちにとって〈現代〉とは何か、真の〈現代文学〉はどういうものでなければならないか、考え合いたい。 ② “新しい文学史”とか“文学史の書きかえ”とか言って、フランスやドイツ渡りの「文学史」が横行している。自分の主体と切り離して「文学史」を構想するというのではなく、作品との主体的な対話・対決の中からこそ文学史を構想すべきである、と強調したい。 ③ 『日本文学言論』(近藤忠義)の頃、文学史の方法を8つに分けたり5つに分けたり、いろいろな人がいた。そういう中で、いわゆる歴史社会学派の人々が最もまっとうな文学史論を提唱した。しかしそこには、階級論としての世代論が欠如していた。私たちの考える文学史というものを、『コシャマイン記』などに即して話したい。 A.Y.氏の報告に関連して、「機関誌の論文で〈直覚〉〈直観〉を強調しておられることとどうつながるのか?」「〈主体的〉と〈主観的〉とは同じことか?」といった質問や、「なぜこれらの作品を取り上げるか、にも触れてほしい」という要望が出された。 続いて、『秋』(芥川龍之介)の検討に入った。四氏が第一章から第四章までを丁寧に報告された。ここでは報告内容の要約はせず、話題になったことのみを、熊谷先生の発言を中心に列記するにとどめたい。 ① 信子のいた〈女子大学〉をどうイメージするか、この作品にとって重要だ。これは目白の日本女子大学校だろう。1901年(明治 34)の開校で、この頃は大学令(大正 8)に則った女子大学として唯一のものだった(東京女子大学は名称のみ「大学」だが、実は専門学校)。東京っ子よりもむしろ地方の豪農・良家の子女が多く入学していた。地方出身だったからこそ東京風へのあこがれも強かった。言葉も風俗も。そこで彼女たちの寮を、早稲田の学生たちは「“あそばせ”長屋」と揶揄したりもした。 ② 俊吉の〈大学〉とは当然、東京帝国大学のことだ。だから俊吉は“赤門派”の文学者であり、その点で芥川につながる作家ということになる。 ③ 〈高商〉とは高等商業(一橋大学の前身)のことで、当時、一流中の一流であった。〈女子大〉よりは上であり、そこの出身者を信子は結婚相手に選んだ(あるいは選ばされた)というわけである。 ④ 「殊に俊吉を知らないものは(滑稽と云ふより外はないが)一層これが甚だしかつた。」という部分の()内の言葉について、これは読者に向けての作者のコメントだとの指摘が報告が者からあった。ところでこれを、万事お見通しの作者が顔を出して作中人物を評価している、〈文学史1929〉以前の表現だ、として否定すべきか。むしろ、俊吉に自分を見ている作者芥川が、俊吉という人間は憧れるような大した人間ではないと言っている表現といえるのではないか。この時期の芥川らしさのある表現として見るとおもしろい。〈1929〉以前はみなダメ、というのではまずいだろう。 ⑤ 芥川の眼は、俊吉に対する場合と信子に対する場合とでは異なっている。信子に対する眼は温かいが、そこには必要な突き放しがある。信子をリアリスティックに描いている。そしてそういう眼が、俊吉への眼につながっている。 ⑥ 人間必ずしも最愛の人と結婚しているとは限らない。結婚できてめでたしというメルヘンで片の付かない問題、大人の世界の問題がここにある。だから『秋』なのだろう。 ▼1991/09/14 №486 ◎報告 第5回 民教連交流集会 全国大会を終えた各団体が交流し、今後の展望を探ろうというのが趣旨。国語関係の団体は今回が二度目。「文教連」「児言研」「日文協」「文芸研」「教科研」「日作」「到達度研(全国到達度評価研究会)」、それに「文教研」の8団体。文教研からは、福田・荒川が参加しました。全国集会を要約し福田が報告。荒川さんが、質問・意見という形でバックアップ。というより、荒川さんの質問・意見が、話し合い全体をリードしました。[以下略](福田記) ◎文教研 ’91体制 ・委員長 福田隆義 ・副委員長 夏目武子 ・事務局長 荒川有史 ・常任委員[人名略、以下同じ] ・準常任委員 【研究企画部】 【編集部】 【組織部】 ◎訃報 金内美智子さん 8月24日、ご逝去。謹んでご冥福をお祈りいたします。 ▼1991/09/28 №487~№488 9月総会(9/14) Y.H 去る9月14日、91年度文教研9月総会が、烏山区民センターでもたれました。 はじめに、常任委員会を代表して、福田委員長殻一部提案を含む報告がありました。 まず、夏の全国集会の熱気を受けとめ、8/30 常任委員会および研究企画部会がもたれ、熊谷先生を中心に91年度第一期研究計画(別表)が練り上げられたこと、そして、これを、この総会の最重要議題として、提案するので充分深めてほしい旨の訴えがありました。 第二に、組織・運営の問題として、① 常任委員会でのない要検討の一貫性を保持するために、準常任委員の欠席者にも、文書でその討議内容を伝達することとした点、② 年三回の合宿における会計・宿泊の係について、偏りのないよう“回り持ち”であたりましょうという点、③ その他、組織運営について、改善する点があれば、それを改めるために、この冬合宿に検討する場を設けるということなどが報告され、了承されました。 さらに、④ これまで合宿の際に集めていた〈私の大学〉の授業料、2500円については、これを前納制にしたいという提案がされ、了承されました。文教研の現在の財政状態からして、どうしても、この〈私の大学〉の授業料による補填が必要になっているからです。 第三は会員に関するもので、[以下、ご逝去、怪我入院、女児出産など、略]。 つぎに研究企画部をはじめ各部から計画・方針案が提案され、原案通り了承されました。 ◎ 研究企画部 提案 N.T. 氏 〈文学史事象としての大逆事件〉を統一テーマに、現代史としての文学史の視点を貫き、印象の追跡の方法で、『謀叛論』前後の徳冨蘆花の作品を中心に研究し、勉強していこうという計画です。 N. さんは、この夏の第40回全国集会で深められた〈世代概念〉〈世代意識〉を、今期の研究活動で、とりわけ意識し、検討作品の中から、今の私たちの課題を探っていこうではないかと訴えられました。 中心におかれる検討作品は、『灰燼』『思出の記』『黒い眼と茶色の眼』『謀叛論』で、作品それぞれの文体的特性を踏まえて、追跡、対話していこうという研究企画……。例えば、『謀叛論』。私たちは、これまで、これを「説明文体」としての特性を意識して読んできたろうか。感動の保障においてつかむという方法意識で、自己の印象を追跡してきたろうか。単なる「説明文」として扱っていたのではないか。そうした問題提起も含みつつ、今回の研究企画が、提案されました。 この提案をめぐり、会員からこもごも賛成意見が開陳されました。 [略] №488 企画部提案が了承確認された後、次回以降の例会のために、〈印象の追跡〉とは何かという問いが、あえて提起され、この機会にあらためて検討されました。その重要性にたいする認識が、最近、薄れてきていると判断されたからです。 そこで「〈印象の追跡〉は、「刺激にたいする全人格的な反応」を前提としているから、結論があって読んでいく、あの解釈学の読みとは根本的に異なるのだ、とN. さん。 それを受けて、熊谷先生から、「自身が自覚していない自分を発見していく読み、自己否定の読み、自己を越える読み、これが〈印象の追跡〉ではないのか。戸坂理論を拠り所にしてはいるが、これは戸坂さんは、言っていない」(……これを聞き、文教研理論として達成されている大切なところを気付かされました。) 「〈ゆがみとひずみをもった文体〉と〈ゆがみとひずみをもった読者〉が対決する、その中から自己(読者)のゆがみを正していく、これが読みというものだろう。……ところで、ものにはすべて“ひずみ”がある。この“ひずみ”がなければ、“反映”もない。したがって、ひずみは当然あるとして、しかし“ゆがみ”は正されなければならないだろう。また、この自己の“ゆがみ”をみつめていくこと、これが世代論なのだろう」云々。 たしかに、まともな方向に自己の発想をつくり変えていく過程、自己の中にすぐれた世代を育む過程、それが読みのはずだった。そうした本来の読みを保障する方法原理が〈印象の追跡〉なのだという点の理解がいっそう深められる機会に、これは、なりました。 さらに先生は、ある年配研究者のTV発言を引きながら、〈印象の追跡〉における、プシコ・イデオロギーやリズム感覚など、神経の末端にまでかかわらせた問題をも、展開されました。 「ニュー・ミュージックの歌詞は、それだけ見たら私たちの世代は気恥ずかしくてとてもついていけない。彼ら若者の気持に、その歌詞は正直なのかもしれないが、しかし、どうも……と思う。ところが、あのニュー・ミュージックのリズムにのせると、そういう自分でも乗れてしまう」云々、というTV発言からの展開でした。 「自分のリズムに頑固になるのも困るが、しかしどのリズムにも乗ってしまえるのも困った“自己”ではないのか。私は浪花節のリズムは生理的にダメ。ニュー・ミュージックにはのれる。しかし、のれるからといって、そのまま自己肯定にはならない。では、リズムにのるとはどういうことなのか。むずかしい問題だ。ところで、あのニュー・ミュージックのリズムでしか、ものを考えられない若者というのもいる。そうした若者とは何なのか、考えあいたい。……読みの問題にもどせば、自分というものを見据えなければ、何を何十遍読んでも何にもならないのではないか」と述べ、ここではなしを結ばれました。 自分のつかみかたを、十分に突きつめないタチの私には少々痛みの走る話題でしたが、ここには、準体験と追体験の問題、大衆性と通俗性の問題、鑑賞の自己規制の問題など、日常体験の個人的な狭さを克服する上での課題を視野にいれた展開となっているのは感じました。 S.T.さんが「相手のリズムに単純にのるということは、これは単に自分の身を置き換えているに過ぎない。自分の持っているリズムに気付いていくことが本当に大切だと思う。逆にいえば、共軛性を持ちえないものに気付いていくこと、つまりは、階級論と世代論の問題なのだ。しかも、それを絶対化しないためには、感動において、自己をくみかえていくほかない……」と言ったことばも印象に残りました。 ◎ 編集部 提案 S.T. 氏 [略] ◎ 組織部 提案 A.Y. 氏 [略] ◇財政報告 M.Mik. 氏 [略] ▼1991/10/12 №489~№491 乾孝氏からの手紙 [熊谷先生から紹介がありました。以下は、その最初の部分です。] 文教研のことをずっと見守ってくれている乾孝、個人的には友人であります。彼から数日前手紙をもらったんですが、原稿のことで頭がいっぱいで、持ってくるのを忘れちゃいました。皆さまによろしくとのことでした。毎号、彼は「文学と教育」を愛読しておりまして、折りにふれて電話などをくれるんですが、再び最近手紙をもらいました。そして、それには「思想の科学」の比較的最近号に彼が頼まれて書いた見開きの随想的なもの、そこで文教研のことをにしておりまして話題にしておりまして……「思想の科学」に書いたことと関連して自分の意見を述べてました。文教研のことに関して、そして、国際的な意味での世相一般に関してであります。僕が代わってしゃべってしまっては、彼独特の面白みがないんですが……。 私は最近の状況――社会主義はもう死んじゃったみたいな、そして、生き残っている部分はくたばれ、みたいな、そういう文章に接して非常に怒りを覚えていた。そして、その怒りを正面からぶつけるような自分ではない、腹を立ててもニヤッと笑ってごまかすようなところがあったと。しかし、もうそういう時期ではないことを感じる。「思想の科学」の抜き刷りを送るけれど、そこにも書いてあるように、もう今は恥ずかしがったりなんかしている時期じゃない。で、社会主義論、言い換えれば社会主義なしに何で世界の、またしたがって日本の未来があるだろうかということを私は言い続けると。社会主義は我々の理想であり、それをめざしてこそ日々の営みが出来るんだ、ということを私は「思想の科学」に書いたが、このことはこれから臆面もない調子で、恥知らずになって言うんだと。[以下略](ニュース部 編) 9月第二例会(9/28) M.M. 徳冨蘆花『灰燼』の印象の追跡 〈上〉 “印象も追跡”とは何かを意識した読みをめざしたいとの発言が、司会・報告者の両方からあり、一部音読をもとり入れて報告がなされた。これに触発されて活発な話し合いが行われた。以下、内容を摘記する形で。発言は順不同。 【作品の冒頭をめぐって】 ○ 緊張したリズムで描かれている。そのリズムは、作者の発想・描写の対象と緊密に結びついている。「勝てば官軍負けては賊の名を負わされて」という一句は、作者の思想的立場をうかがわせる注目すべき書き出しである。誰が賊の名を負わせるのか。そこをしっかりつかんでいる人の表現になっている。 ○ (熊谷) 官軍が正しいとはかぎらない。正義は必ずしも官軍を自称するものの方にはない。勝った方が正義で、負けた方が悪いというのは蘆花の発想とはまるでちがうものだ。官軍―明治政府―天皇を支持するものを正義とする、これとは違う正義論を蘆花はもっている。後にトルストイアンになっていく彼の、その兆しが初めから出ているのではないか。 【冒頭の文の長さ、その意味】 ○ (熊谷) ここは描写文体だが、説明文体を同時に考えてみると、昭和戦前期のそれは、殆どといってよい程、息の長い文であった。短くなったのは戦後のことである。波多野完治氏を先頭にした人々のセンテンスを短くしようという運動があり、作文教育がこれに歩調をあわせた。ヨーロッパの論文は、原文では長文なのであるが、それを区切り、短文に訳すこともはやった。 口言葉においても、ある長さを持たなければ、思考の流れが中断され、リズムが狂ってしまうことがある。この冒頭の文も、短文(的思考)に慣らされた(変化の時代を生きた)私達には、長いと感じられようが、当時としては、とりわけ長いと感じられるセンテンスではなかった。思考(思索)形式の特徴が出ている。 ○ 二月の鹿児島出立から八月にいたる経過を一気に一文として描きあげることによって緊迫感が増している。南州と死を共にすることに自己の存在証明を賭けた人々の姿が鮮明に迫ってくる感動的な文になっている。この長さに必然性があることがわかる。 ○ 戸坂論文は文が長いため、判りにくいという印象をうけてきたが、思考の形式にかかわるということを教えられた。上の一の第二段落は一転して短文で始まる。文の長短を固定化して考えるのではなく、リズム・内容との関連でおさえたい。 【「活動写真」的描写】 ○ 目に見えるような視覚的表現。だんだんに焦点を絞り込んでゆく描き方など、映画のショットを見るようである。「六百の草鞋さながら『明けむ間に、明けぬ間』と囁き」には蘆花のユーモアも感じられる。また、これ以上そぎ落とせないと思えるほどの表現である。 【青年(群)像】 ○ 西郷軍は、洋装の兵士から「賊」と呼ばれている。学校で習う日本史では、西南戦争は歴史を逆行させる反動的な不平士族の叛乱とされていて、ずっとそう考えてきたが、今回『自画像』を読み返し、また『灰燼』を読むことで、「自由民権運動との微妙なかかわり」が捉えられ、眼を開かれた(同様の発言が他にもあった)。 この青年は死を賭けて、自分の生き方として戦に参加し、一人になってなお戦っている。どういう気持で参加しているのか。青年の口言葉が、普遍性のある、よくこなれたものになっている。 ○ 「さっき……ああもう夜明けだ」「……三田井というは何方か知らん」など、青年の若さ、清新な人間像をほうふつさせる。新鮮な口言葉である。 【「我此翁」の読みの質問に応えて】 ○ (熊谷) 私にとって敬愛措くあたわざる西郷南州先生、の意で、文調(文体)・リズム感覚からいっても、我(ワレ)でなく、我(ワガ)と読める。 ○ 自分の意志でこの戦いに参加している隊士たちの気迫が冒頭からすでに感じられる。そしてこの冒頭と呼応して、こうした表現が随所に見える。「賊」軍とはちがうイメージで描かれている。 〈中〉 【独特のリズム・文調】 ○ 中学一年の夏休みにこの作品に出会い、興奮を覚えつつ読んだ。文章のリズムにも依るのだろうが、俗世間に対する抵抗意識、天下国家を憂うる心を刺激する部分があり、茂に憧れ、茂の死に心が痛むのを覚えた記憶がある。 熊谷先生の「活動写真だ!」という指摘に同感。とすれば、どこか活弁調であったり、民俗芸能など、日本語特有のリズムを響かせていることがうなずける。また、「青葉落葉をかき分け踏み分け、次第に上り上り上り――」(上)などという特徴ある蘆花の文調・文体とも関係するのであろう。地の文におぶさることなく、生き生きとした会話を多用することで場面が展開し、人柄が捉えられている。反面、会話の全くない中の三などが加わることで、作品全体のリズムも生まれている。 【民衆を多角的に形象】 ○ (熊谷) 西郷さんを「疫病神」と言う民衆の声を描く一方で、南州に従った人達の、民衆の叫びの行動化を形象していく、というように民衆を多角的にとらえている作品。 ○ 戦争についてのお菊の母親の言葉、また農民たちの会話から、それぞれの実感として響いてくるものがある。が、そこには彼らのある限界も同時に表れている。 ○ 民衆は生活に密着しているからこそ見通しがきく面と、であるからこそ見えない面――青年達が何ゆえに情熱をかけてゆくのか――とがあり、結局のところこうすればよかった式の結果論に陥りがちだ。堅実さとずるさの両面を描ききっている。 ○ 民衆精神につながる発想と、民衆性を自ら否定する面と、それがきとっと分けられなくて、一種の生活の知恵のように出てきている面とがあると思う。『さざなみ軍記』の中にもみられる(『井伏鱒二』p.54~参照)。報告者は「庶民の実感が表現されている」と言ったが、全面肯定になってはいないか。また、「庶民の倦怠」という言い方は妥当か。目先の生活の利益――彼のもつ生活の知恵とはどう重なるのか。彼らに茂のような抽象的思想への情熱がないことは明らかだ。 ○ 民衆のもつ二面性については『かるさん屋敷』にも描かれている。映画『七人の侍』で落人狩りをする農民が出てくるが、全面肯定されてはいない。 【『灰燼』の読者層/芦花の階級論・世代論】 ○ 「西郷先生を逆賊?――逆賊と云うのは、役人です、大久保の奴です」。茂は自分たちを逆賊とは思っていない。冒頭の緊張した文体によって三百余人の思いは伝わってくるのだが、茂のこの言葉が、それの明確な裏付けになっている。 ○ 読者の視座からみると、若い茂に人間としてのある可能性を感じるのだが、「……未だ乳臭き口に……年も行かぬに憂国三昧……」など、その描き方に、茂を噂話のタネにしている中津の人々の思いも同時に表現されているようだが、どうなのか。 ○ (熊谷) 読者にみえてくるという時の、その読者とは? まる 「民衆」の方ではなく、茂の中に自分につながる何かを見いだし、そこに共感をよせている読者、日々飼い慣らされまいとしている人々。 ○ (熊谷) 茂も民衆。蘆花は、誰に理解されなくともよい、この人達には理解する条件があるという人を読者として予想し、期待をかけ、内なる読者として温めている。その人達が、この作品形象の人物造型における読者――内なる読者達を含めた――になっている。 ○ (熊谷、他) 蘆花の階級論・世代論は、読者論として、また前記のような描写形象として実現している。また、リアリズムは、作者の世界観・人間観そのものであって、表現方法の問題ではない。蘆花のリアリズムに支えられたロマンチシズムに注目してほしい(特にこれは、このパートの報告者に)。 【プチブル・インテリゲンチャの視点】 ○ (熊谷) 〈文学の科学〉は、〈鑑賞体験の科学〉ともいうべき側面をもつ。そこで〈読者論〉につながる。理論と鑑賞とは別個のものではない。文章表現(作品形象)の内側から理論をるくり、検証していく必要がある。 今、理論面にアクセントをおいていうと、――文学者徳冨蘆花(内なる読者群に支えられた蘆花という作家)の考えの中に、この人達にだけは判ってほしいという訴えがある。その訴えをもつ蘆花は、インテリゲンチャ、階級論の用語でいえば、プチブル・インテリゲンチャ(明治30年代の)である。 蘆花の場合、言葉として整理ができているわけではないが(蘆花もまた当然時代の子である)、大筋で、この作品において予想する、期待をかける読者群(複数の蘆花、内なる読者を含めた)は、プチブル・インテリゲンチャであった。蘆花自身もプチブルの視点でものを言っている。これは、明治大正文学史にとって大事なこと。その辺を統一的に扱ってほしい。 つまり、高倉テル氏、蔵原惟人氏が言われるように、日本近代文学は、ブルジョア文学ではない。積極的な意味で日本の近代文化を創造的に担った集団は、プチブル・インテリゲンチャであり、文学においてもプチブル文学なのだ。 今日、乾孝の手紙を通じて日本共産党を話題にした。何かその辺のことをおさえたい。そうすれば、近代文学を近代文学たらしめた階級集団・意識における階級集団が、そういうもの存在が、『灰燼』の検討を通して九分九厘まで実証できる。それが実現できれば、理論と鑑賞体験が別問題ではないのだということをはっきり定位できる。そういう局面にさしかかっている。 故 金井美智子さんを偲ぶ [略] ▼1991/11/09 №492 10月例会(10/26) Y.R. 前回の例会(10月12日)は台風の為に中止。前代未聞のことで、多少混乱があった様子。一度例会がふけたのでほぼ一カ月ぶりということになるわけだが、その十分な準備期間を見事に生かして(?!)、『灰燼』の〈下〉を I .M. 氏が報告された。前回の熊谷先生の問題提起にぴったりとつながる形で、しかもふっくらと作品の印象の追跡をされたので、「これで例会は終わりにしてもいいですね。」という感想があちらこちらから出たほど。そんな優れた報告をどこまで媒介できるか不安だけれど、その報告を中心にまとめてみようと思う。話し合いの部分は、大きな問題点と思われるものだけを。 ☆ I .M. 報告 前回の例会で、『灰燼』においての民衆の描き方が多面的だ、と言うことが指摘されたが、その多面的な人間把握をもたらしたのは何なのか。そこで、前号にニュースにもまとめられた蘆花のプチブル・インテリゲンチャとしての視点、ということが問題になってくるのだろう。 そうしたことをふまえてこの作品を読み返してみると、今までは、例えば家族制度・家と家の観念が茂をしに追いやっていく、というようなことを、どこか図式的にとらえ、読んでいたようなのだ。 猛は封建的な道徳を徹底的に身につけて、家のため、ということで自分のありかたを考え行動していく。したがって、いわゆる家の論理・倫理ということで言えば、猛は決してまちがったことをしているとは思っていない。「『孝行者』の役割を買って出ている結果 にもなっている」のである。(『自画像』p.53) それにひきかえ茂は、「自由の民権のと言い罵り」「年も行かぬに憂国三昧」という日常であり、その点から言えば、むしろ上田の家にとってははみ出しもの、困った存在であるはずである。しかし、両親は、猛をではなく、そんな茂を愛している。財産も「少なくも二分せられて、両親は茂に倚るならむとは、何人も信じたりき。」……というのが現実なのだ。 つまり、家族制度、そこに家の論理・倫理は生きているわけだけれど、実際そこに生きている具体的な人間像を見ていくとどうか。家の当主であるからといって、家のためになるからと猛にすべてを任せるかというと、ぶしろそこでは、自分たちに人間として愛着をもってかかわってくれる存在なのかどうかで、ひとつの行動選択が行われていっているのである。 しかし、結局、家の存続があやうくなるといったときはには、茂を犠牲にせざるをえなくなる。いってみれば茂は肉親に殺されていくのだ。 けれど、母親のお由はその後、茂の「阿母あなたも?」と言った最後の言葉に――というより自身の茂に対する仕打ちに苛まれ、狂っていく。茂の最後の言葉はまた、茂がどんなに母を愛し信じていたかを物語った言葉でもあるのだ。それをふみにじらざるをえなかったお由。 上田の家が焼けていく。「道具は如何した? 大切な物は皆出したか?」という猛。そんな猛のありように、何故あの両親が茂を愛したのか、ということも自ずとわかってくる。……「上田の家は灰燼に帰した。が、家と家の観念そのものは滅びはしない。……久吾やお由が身をもって感じたような『家』の制度と観念の自己矛盾を、やがてその跡継ぎたちも感じる日が来るだろう。……」(『自画像』p.53) 家族制度、家の論理・倫理がどういうものであるかということが、そこに現れる人間と人間とのメンタリティー、ひとりひとりのありよう、その絡まりあいの中に描かれているのである。 蘆花自身、家族制度の中で苦しんでいる。また、彼の年譜などを見ていっても、この時期、インテリゲンチャとしての視点の基盤の形成、自己形成がなされたことがわかる。そんな作家としての立場からまた、家の問題、家族制度の問題を、自己の世代の問題としてとらえ直していったとき、こうした人間把握が、また描写がなされていったのだろう。 ☆話し合いの中で 猛には、家族制度をも越えるような野望・欲望があるのでは、といった意見が出されたことに対して、熊谷先生が、次のようなことを話された。 「今、文部省や厚生省が押しつけてきているのは『弱肉強食』のケモノ的児童館です。そこへソビエトや東欧の問題を横滑りさせ、社会主義は人間の欲望を充たせないなどとの俗説が広がり、生物学主義的発達観が子どもたちを脅かしています。……」(「思想の科学」9月号 いぬい・たかし「マルクス主義の燈を守ろう」) ―― この欲望云々ということ、これはけっこう幅をきかせている考え方なのだ。人間の欲望というものを絶対的な一つの軸として、それに対立させて別の軸を立てる。人間は欲望から離れ得ない生き物なのだ。また、欲望を生産し、その欲望に従って生きる。――全国集会のある参加者もまた、そうした考え方をしていた。欲望が人間の根本なんだ。このことをごまかしているだけだ。欲望プラスアルファだったり欲望マイナス去るファだったり、それが人間だ、とおっしゃる。この考え方こそ、わりに普遍的な論理なのだ。 わたしたちの中にも、そうした二元論がないか。今日の話し合いで言えば、家族制度は家族制度、それ以外に人間というものが、人間の気持というものがある。家族制度を越えたものがどこかにあるとか、それ以前のものがあるとか――人間が人間であるかぎり、普遍的に流れる人間という存在がある。その人間はたとえ社会主義社会の人間であろうと、資本主義社会の人間であろうと、封建主義社会であろうと、この二元的なものによって支えられているのだ……。そうした考え方にすべっているところがないだろうか。そして、 I .氏の報告は、そうした二元論に対する反論になっていたのではないのか。 こうした問題提起を受けていくつかの発言が続いたが、 I .氏の次のような発言を記すことで、まとめにしたい。 ―― ともすると、制度は制度、人間は人間、という発想になってしまう。欲望という何か根源的なものがあって、それにいろいろな色づけをするのが社会性なのだ、歴史的・社会的な制度プラス人間とすることが、歴史社会的に人間を把握することだ……というような発想に陥る危険性がある。人間と人間との係わりを根本的に規定している、そういうことをぬきにして、家族制度というものがあるのではない。そこが統一的に描かれているところに『灰燼』の素晴らしさがあるのではないのか。 ▼1991/11/23 №493~№494 11月第一例会(11/09) I.H. 〈『思出の記』の印象の追跡 第一回〉 N.T. さんから、『思出の記』が連載されていた『国民新聞』についての資料の説明と、印象の追跡の進め方の確認がされた後、まず始めに、熊谷先生が〈『『思出の記』についての私の思出の記〉を語って下さった。先生自身の生い立ちや少年時代のエピソードを交えながらの楽しいお話の中に、『思出の記』を読むうえでの大切な視点が示唆されていた。そのお話の楽しさはとても伝えきれないが、私自身がつかめたこと、後の報告や発言とのつながりを理解できたところを記しておきたい。(以下、1-①②とは、一の巻の一、二を表す) 熊谷先生のお話 かつて自分の文学との出会いは(若き日の)藤村だと思っていた。あとになって、ある自覚が生まれた自分が生涯を通じて一番親しんだのは、この『思出の記』だっとということである。知らぬまに覚えてしまうくらい繰返して読み続け、笑ったり涙を流したりしながら抱いた感動は持続性を持っていたのである。 人は、出会いの仕方で相手の顔が違って見える。この作品との出会いが、どういうものだったからなのか。 『思出の記』の慎太郎は、温かく仲の良い、そして時には夫婦喧嘩もあるような恵まれた家庭に生まれるが、父の破産で零落し、村人たちから手のひらを返すように(あるいは心ならずも)そっぽを向かれた。慎太郎が経験した、「素封家」から零落した生活と、その苦しみ、それは、この作品と出会った時の自分自身が、過去から現在において経験しつつあるものだった。ある暮らしから零落した貧乏の特殊なところ、根っこからどん底というのとは違う苦しみ、そこに自分のおかれた環境との重なりを感じつつ読み続けてきた。 『徳冨蘆花全集』(日本文学全集/集英社)に、荒正人氏が詳細に論じた解説がある。蘆花の作品論としては、とりわけ優れたもの。しかし、自分と決定的に違っているのは、一生をかけて読んできているというところ。この作品論は理屈が先にたち、それだけではこぼれてしまっているものがあると思う。 報告・発言 ○ 零落した人間の貧乏、そこでの慎太郎の様々な思い、その意味に目が向けられてきた。それを、本当の意味での言文一致とは何か、ということとのつながりでとらえ直したい。[具体例、略] ○ 〈零落した人間における貧乏の特殊性〉、その視点から、あるパースペクティヴを持って読み返してきた時、この作品の文章の新しさが見えてくる。[具体例、略] 熊谷先生からの補足 旧制中学の上級、プロ文学を読み出した頃、慎太郎に対する村人たちの変化は無理ないな、という関そう・理屈が出てきた。今まで尊敬していたわけでもないのに、「素封家」の息子だということで、立場上ある態度を強いられていた下積みの人々にとっては自然なことであり、そこがえぐられていないのは「ブルジョア文学」「しょせんは否定されるべきもの」とした時期があった。そして、もとの読み――〈田舎〉のあるいやらしさ、〈田舎人の純朴〉の本質とは何か、というところへ帰ってきている。 1-③ 「なぜこのとおり叔父が迫害を加えたか。僕は今にいたるまでその故を知らぬ。」 子どもの自分にはわからないことだと言い切りながら、母の美しさや、その母が叔父を嫌っていたこと、さらに人づてに聞いた話しとして、祖父は愛情を父に注ぎ、叔父を疎んじたことが語られる。わからないことはわからないとし、言い切らない。しかし、普通の感情を持っている人間ならこう感じるほかないというところを指摘し、読者に推測を促す文章になっている。井伏のつかみ方との関連をおさえたい。 1-⑦ 「幸いにも誤解したもうな。」「今も記憶している、――版がまっ黒になったことを。」これらはヨーロッパ語の文脈。 引き続き、二の巻、西山塾のパートをY.A.さんがイメージ鮮やかに報告された。特に兎狩りの場面やでは、ご自身の故郷の自然への思いも伝わってきて、それぞれが懐かしい故郷の風景や記憶を語り合った。ここでは、報告の骨子、発言のいくつかだけを。 Y.A.報告―西山塾― 西山塾の活気が感じられ、とても面白く読めた。思い出している慎太郎の中に、その頃の忘れられない強烈なものが甦っているからだろう。 西山塾。近代的学校の失ってしまったものが、そこにはある。何よりも「主脳たる一人の人格」西山先生の型やぶりの面白さが大きな魅力だ。それは、「士族根性を打ちつぶすと共に、……士族魂はどこまでの維持させ」ようとする、西山先生の一貫した精神から生み出されている。 2-⑤ 「秋収が済む。霜が降る。裏山の楓が染める。と兎狩りの季節がそろそろ始まる。」 当時そして今の慎太郎の思い、それに塾生たちのはずむ気持を映し出した文章のリズム。慎太郎の気持の高まりと共に読んでいく中で、自分自身が秋の野山のひやりとした空気にふれ、川面の光を目にし、一緒に野山を駆け回ったような感じを受ける。 発言 ○ 零落した者の視点から見えてくる〈都市と農村〉〈都会と田舎〉。そのどちらでもない、いわば第三の地、西山塾でいきいきと生きている姿が描写されている。 ○ 西山先生の潔さと面白さ。『思出の記』の世代形成期の魅力は、この得がたいすばらしい師との出会いと大きく関わっている。 ○ にしやな塾には、男の子の世界の特徴が出ている。少年あるいは青年だけの世界、そこにはいやな面ももちろんあるが、その世界の面白い部分がすくいとられている。これは『思出の記』論において、あたりまえすぎるためか忘れられていること。しかし、それが、お敏さん登場の印象にも関わっている。 ▼1991/12/14 №495~№497 11月第二例会(11/23) S.F. 〈『思出の記』の印象の追跡 第二回〉 1) 前回のまとめ ニュース№493、№494による。 読者の視座の問題――熊谷先生の体験の否定的媒介。 零落した人間の苦しみのひずみから現実を反映した作品。 読者のひずみ―私達は教養的中流下層階級者の視点というひずみと共軛するものとして共感。 このひずみの自覚。 2) 「関西学院」のよみ 全集(昭3)、改造社円本(昭3)では「カンサイ」。 現実の関西学院は「カンセイ」。 3) 西山塾の教育精神 (熊谷先生) 前回のY.A.報告にあったように、西山塾の西山先生は「よき意味の士族精神を今日(明治)に生かせ、あしき意味の士族根性をつぶせ」という、一見相反するような二つのことを基本において教育に打ち込んでいた。そこで、わたしの言いたいのは、次のようなこと。 その1――西山先生の教育のあり方、実践は非常に個性的なものであった。西山先生の個性が西山塾に貫かれていた。その精神こそ、近代の精神であり、近代主義の否定であり、前近代主義の否定でもある。つまり、士族根性の否定と同時に古きよきものもすべて否定してしまい、新しいものはすべて否定してしまい、新しいものはすべていいとする近代主義に立ち向かっていく。そういうなかで、菊池慎太郎は育まれていく。この精神がこの作品の一貫した姿勢ではないか。 育英学舎の駒井先生の個性、個性的発想も、近代主義でないし前近代主義でもない。このような西山先生や駒井先生のものの考え方、感じ方は慎太郎のよき面につながっていく。それを、教育史一般に返したり、明治近代とはこういう時代だということで、この作品を解釈するのは間違いだ。 その2――西山塾のあり方がおもしろい。今日の私達の学校教育のなかで失ってはならないもの、失ったものが基本的に出ている。真の意味の教養・文化が西山塾の教育に生きている。また、裁判のいくつかがあり、いわゆる大岡裁きである。そこには裁判の本来のものが息づいている。 その3――全般に息づいているのは、真の意味の教養・文化である。そこででっけぇ面して学んでいるつもりでいる慎太郎たちは、何も知らないことを思い知らされるのである。松村清麿の郷里へひと月ほど行くが、その後、西山塾は閉塾する。その時のスピーチ「老生のような……」の中に西山先生の教育精神がある。それは真の意味の教養・文化に満ち満ちている。その教養・文化にとっては、古典、書物が問題となる。太閤記・八犬伝など。それらが生活に息づいている。[略] #恒春園を訪ねる# 11月23日、定例研究会の前に、12名の一行が徳冨蘆花の住まいだった恒春園(会場に近い)を訪ねました。楽しい会でした。 №496 4) 育英学舎の魅力 報告と話し合いの中から ○ 社会への窓。目を輝かしている学生達の姿がみえる。それは、〈私の中の私達〉の拡大につながる。○ 自由平等も、以前に西山塾の生活があってこそ、理解できた。 ○ 駒井先生の精神は、西山塾で育まれた慎太郎にどのように受け継がれていくのか。 ○ 見た目にはヤサ男のようであるが、意志の強い駒井先生が印象に残る。そして、慎太郎の成長をじっと待ち続ける駒井先生の姿。 ○ 駒井先生の魅力、それは駒井先生の別れのことば「諸君も自分も共に真理の一平卒として……書生の精神を忘れず……」などの感じる。西山先生とのつながりもあり、印象深く読んだ。 ○ まず初めに、駒井先生が橋本左内のようだ、というところに魅力を感じた。押しつけるのではなく、孤立のなかで節を曲げずに待ち続けて青年の心をつかんでいく。そして一挙に逆転していくなかで権威を確立する。現実にこのような先生達を知っているだけに、感動的に読んだ。すごい男が登場してきたのだ。 ○ 該博な知識が単なる知識にとどまらず、教養として身についている。駒井先生は自由・平等の理想に燃えている教室の場面としては、疑似国会の場が印象に残る。書生的な妥協を排していく姿勢。真に学生一人一人を大切にする姿があり、そこから怒りも出てくる。「一平卒として」訴えるというところに、『謀叛論』のルーツをみることもできる。 №497 ○ 「一眼は書巻の上に、一眼は世間の上に、……学校の窓から社会を望むで居た。」とあるが、実践へ向けて内と外との通路を見付けようとしている。行動の系に結びつけていく教育。「真理へ向かっての一平卒」の意味が明解だ。 ○ 熊谷先生の指摘した、明治の諸制度に位置づけてだけ読むのは誤りだということを受けて考えているが、学校制度の確立以前の、私塾的な〈やりたいから、やらねばならぬから〉という思いがあって、青年を教育していく姿に、教育の原点をみる。 ○ 〈自由〉を求める者が〈国賊〉とみなされるような世の中で、政治家になりたいと考えるのは、駒井先生の影響であり、政治家を志すのは天下のために尽くすのであり、〈自由・平等〉を実践していくことなのだ。 ○ 青年期らしい青年期を過ごすことを育英学舎は保障している。今の学校に欠けていることだ。 5) 関西学院 報告と話し合いの中から ○ 生き生きしている学園生活。独立の精神。自由な討論。演題のすばらしさ。 ○ 雑階級者である学生の精神形成に大きな影響。学校を横断、学級の区別。学校を縦断、精神の区別。精神のありようによる区別の分類が面白い。人物批評になっている。 ○ 矢吹周三との出会い。矢吹の自殺で知る苦しみは、世代の苦しみとなっている。 ○ 矢吹の問いかけ。人生とは何か。矢吹の死後、それは慎太郎の内面に定着し、自身への問いかけとなる。慎太郎の成長。 ○ 兼頭との再会。思索の相手としていつまでも生き続ける。 ○ 派閥の争い。現実と理想のはざまで苦悩する。 ○ 菅先生が去っていく。慎太郎も退学して東京へ。西山先生に育まれ、それ以後の生活の中で育てた精神の自由、言論の自由を大切に。 ○ 西山塾や育英学舎は、西山先生や駒井先生の影響、縦の線による先生の影響が大きいのに対し、関西学院は、種々雑多な人々の中で横の線による、たとえば、矢吹や兼頭らとの相互のつながりの中での成長の面が大きい。 ○ 慎太郎にとって、関西学院は反面教師。反抗することで、自分の求めていたものが明確になっていったのではないか。 6) 帝国大学 報告と話し合いの中から ○ 成績優秀で総代となる。海外留学の話もことわり、自らの「出世」の道を求めず、私立学校の教師となる。行動選択のもとは、西山塾や育英学舎での教育だ。 ▼1991/12/26 №498~№500 12月例会(12/14) S.F. 冬の合宿プログラム [略] 〈『思出の記』の印象の追跡〉 (A) 慎太郎と学校 前回までのつづき (B) 慎太郎と基督教 (A) 慎太郎と学校 N.T. この作品の最初のところで立ち止まることにより、読みの構えをつくった。つまり、零落した人の哀しみ、苦しみという視点をもった。その上で、こんどは「慎太郎と学校」とタテワリの切り口で考えてみることにした。 関西学院は基督教系の学校であり、宗教を別にして話すのは難しいのだが、あくまでも学校という側面から考えていく。慎太郎はこの学校を、卒業半年前にもかかわらず、退学してしまう。理由は、菅先生の辞職にある。先生は「迷信と信仰」という講話が物議をかもし、異端者として排撃された。慎太郎にとって菅先生は、宣教師である前に、英文学をやったほうがいいと勧めてくれた人である。 慎太郎が食堂に張り出した「檄」に呼応して、「基督教、思想の自由、言論の権利のため……」と燃え上がった学生の運動も、校長の涙で収束させられてしまう。「己に対し同輩に対し校長に対し〈売られた〉という」感情を抱き、慎太郎は、このような学校に残る意味なしとして退学を決意。これは、学校の体制との訣別であって、背教ではない。関西学院は、最も肝心なところで慎太郎のハートをとらえることができなかった。19歳の〈自我〉をもった慎太郎として、成長の跡がイメージできる。 話し合いの中から ○ 塾という小規模な場で可能だったことが、学校という中規模の場ではうまくいかなかった。組織とは一体何か。 ○ もはやここは自分の学ぶべき場所ではない、と決断する慎太郎に、小気味よさがある。精神の自由の問題である。 ○ こうした慎太郎を育んだのは、やはり西山先生や駒井先生だったと思う。 ○ 菅先生との食事の場面、文学に向いているのではないか、と示唆されるところが印象的。菅先生との出会いの意味は大きい。 ○ やはり長編なのだな、と思う。慎太郎の精神形成のありようが描かれていくのも長編なればこそ。6-⑤の最後に「ああ僕は若かった」とあるが、物事を自分に返して考えていく姿があり、慎太郎の精神のあり方を示す。それぞれの場で培われてきたものがあり、そのかかわりで教師の存在が問われる。 №499 (B) 慎太郎と基督教 S.S. F.T. 6-④ キリスト教における門閥。金閥、官閥、職閥……地域閥。伝道師として、内側からみることでいろいろのことが見えてくる。金満家の寄付金の少ないのに驚く。もし、自分ならば「生活費だけを残して余は尽く施してしまう。」と考える。 6-⑤ では、貧民窟へ伝導にはいる。貧しさと病苦による、あまりに悲惨な状況。それをも痛めつける役人たち。慎太郎は怒りを感じる。「黒塗馬車に爆裂弾でも投げつけたくなる」ほどの怒り。苦しみの中で死んでいく人々に対して、「彼等の罪にあらず」という怒り。貧民を教会に連れてきたときの信者たちの反発。醜い姿。たとえ財産をなげうったとしても、少数の者しか救えない、と考える。 慎太郎がキリスト教に近づくのは、道太郎との関係によってである。それは、慎太郎の育ちからして、偶然がもたらした必然であったように思える。道太郎の松山行きに同行して、はじめ反発を感じながらも、道太郎の人となりに惹かれその話に感動していく。関西学院時代の矢吹の自殺。「何のために」生きるのかという矢吹の残した疑問を慎太郎は自ら問い続ける。解決を聖書に求めようとするが、求め得ず、聖書への疑問として残る。そうしたときの道太郎との出会い。 比叡山での道太郎の落雷による急死。苦悩の中で慎太郎は、自分のために道太郎は死んだ、と思う。小基督を思い、道太郎は生きている、とつかみ直しをする。そうして道太郎は慎太郎の中で生き続ける。 慎太郎は、このように紆余曲折を経て信仰の道にはいっていき、キリスト教を自分のものにし、実践の力としていく。 「基督教の公義を維持せんとしてたおれた一種の殉教者」として、公義を守るため、東京へ。 話し合いの中から ○ 「国民新聞」連載の様子が、コピーをとってみて初めて分かった。休載の場合、一日くらいだと「本日休載」の断りが載るが、何の知らせもなく二ヶ月くらい休載している。これが二回ある。 ○ (熊谷) 初出と現行本文との異同についての調査が基礎作業として必要。二ヶ月も休載しているのは、長編小説としてあたためているからだろう。その間に文章の変化があるはず。長編の構想から出発しているので、休載なしにはすぐれた文学にはなりえない。長編小説ならではのことだ。改稿による文体の変化を知るため、改稿過程の追究はぜひとも必要だ。蘆花文学についての研究は必須。 長編の場合、タテワリで読んでいるのが普通。自分で楽しみながら読む場合、タテワリになっているはず。研究ではそれを体系的意識的にやるわけだ。 慎太郎は背教者ではない。(私の場合は背教者。教会の偽善に嫌気がさしたため。) №500 ○ 貧民窟へ伝導に入った時、人々が、信仰ではなく、衣食を求める。そこで悩む慎太郎がいる ○ 関西学院を捨ててもキリスト教は捨てない。自分の内なるものを大事にする。実践的。キリスト教に新しいものを求めていく姿勢は、藤村や透谷にもつながる。透谷世代につながるものとして考えてはどうか。 ○ (熊谷) キリスト教一般ではなくて、これは思想の問題。透谷、藤村、蘆花。キリスト教でなければならなかったもの、その必然をこの作品はつかんでいる。 (熊谷三兄弟のあり方。長兄―教会に我慢ができず、内村鑑三の無教会主義へ。次兄―部落解放運動から賀川豊彦のキリスト教社会主義へ。先生―キリスト教そのものに問題ありと、否定。背教。) ○ 蘆花のリアリズムは、明治元年生まれの慎太郎の生き方で探っている。苦しみぬいた生き方の典型がある。 ○ 主題的発想を一貫して通していこうとするとき、休載の期間をおかざるをえなかったのではないか。 ○ 通俗小説ではない。一見弱点のように見えるところも、弱点ではない。必然的な構成がとられている。 ○ 蘆花と自由民権運動との関係を考えていくことも大事だ。 (C) 慎太郎と彼をめぐる女性たち(母親も含めて) 各自考えておくようにということでした。 #ちょっと楽しいニュース# 委員長がオジイチャンになりました。初孫です。性別は慌てて聞き忘れました。 |