| ▼1992/01/11 №501~№505 冬合宿(12/26~28) Y.R.&T.K. №501 Y.R. 明けましておめでとうございます。 冬合宿は、思いもかけず雪景色の中で行われました。部屋の中で見ているぶんにはきれいでも、寒さと、宿舎と会場との行き来における足場の悪さに、皆閉口しました。それでも、前回(昨年)の冬合宿は熊谷先生が入院されていたことを思うと、嬉しい合宿でした。 〈「文学と教育」№157「―てい談―虚構論へのひとつの視点」についての話し合い〉 ★p.8~ 「裏ばなし一、二」に関連して ○ (A.Y.) ご存じない方もいらっしゃると思うのでご紹介したいと思います。9ページの下段。はっきりものをいうことの必要性と、その後のとばっちりの大きさ。そういう中で、先生がご自身のお考えを述べられた意味ですね。例えば、恩師の方の、太平洋戦争下の発言。「国防教育としての国語教育」という論文が岩波の「文学」に1941年(昭和16年)段階で載っているわけですが、その論文を書いた方が、戦後は、「国防教育としての」ということをカットして、「言語活動主義としての」と書き換えた。しかし発想の基本は変わっていないということを、先生は1955年段階で、三一書房から出された『文学教育の理論と実践』の中で批判されているわけですね。その2、3カ月後に、その先生のてい談を先生は司会されておりまして、その本をその方が読まれていたかどうかははっきりしないのですが、そうしたすれすれのところで司会を担当されて、大変おつらい状況だったんだな、ということを今にして思いました。ですから、わたしたち自身が、文教研で学んだことを職場の中で主張することの様々な厳しさがあると思いますけれども、そういう厳しさどう受け止めながら問題を切り開いていったらいいのか、ということなども、この「裏ばなし一、二」を通してあらためて感じました。 ○ (熊谷) A.Y.さんの話につなげて。9ページの下段、終わりの方です*。ある大家――もう出してもいいでしょう。活字にしない限り。N.M.先生[ここでは実名を伏せる]です。「体制内知識人のオポチュニズム」、彼はオポチュニストにすぎなっかた、ということをはっきり言っちゃったんですね。そのことを今お話しして下さったと思うんです。N先生をご存じない方はいらっしゃらないと思うんですけれど、晩年、国立国語研究所の初代の所長さんです。そして、日本女子大学の文学部国文学科の教授でもあられました。それから法政大学の文学部の講師、そして岩波の「文学」の編集長をずっとやられてました。 *熊谷 辛いところなのでして、以前に、たしか戦後十年ぐらいの時分に文学教育小史みたいなものを書きましてね。[略]その小史の中でその道の或る大家の戦争下(太平洋戦争下)の業績を、体制内知識人のオポチュニズムの産物だとして酷評してしまったのですよ、僕は。その方は僕の恩師に当たる方なのでして、いまだに寝覚めの悪い思いをしております。(「文学と教育」№157、p.9)そして、11ページの上段、後ろから4行目、K教授、K先生。この方は、私の最大の恩師、戸坂先生への敬意と同時に敬意を表しているところの、近藤忠義先生のことです。歴史社会学派のオピニオン・リーダーであられました。そして、戦後、日本文学協会を発足させた、日本の文学研究史、文学教育研究史、その徒にとって、記憶から抹殺してはならない方です。 つまりこれはひとつの文学研究史、文学教育研究史の大事な点にふれているつもりなんです。 それから、山本健吉さん。この方のお父さんが、石橋忍月さんです。その当時の「俳句研究」は、編集者が同時に文学者である素晴らしさが現れた雑誌だったんですね。僕にとっては忘れられないんです。明日締め切り、っていう日におしかけてきて、布団をもってっちゃうんですから。……実はこうした文学史の裏話――裏話のない表話もないんで――こういう、さもないようなことから、山本健吉さんの息吹をしみじみ感じて、長いおつきあいになった、そんなことなんです。 11ページ下段「急場しのぎの肩代わり」*、これ、肩代わりということと同時に、若い僕を、一流雑誌に書かせてやろう、そんな温かい面でもあったんです。ほんとに、温かい先生でした。かわいがって下さいました。非常に感謝しております。卒論の何編かも、いろんな所に推薦してくださいました。 *熊谷 K教授、K先生。「俳句研究」の編集部から先生のところに「洒落風俳諧」云々、という同題の原稿の執筆依頼が舞いこんだわけ。ところで当時、先生は、歴史社会学派のリーダーとして学会に旋風を巻き起こしつつあった、時の人でした。それを少し俗な言いかたをすると、ジャーナリズムの売れっ子だった。いきおい、諸方から原稿の依頼が殺到して、なかなかさばき切れない。「俳句研究」の場合もOKは出したものの、原稿締切りの数日まえになっても手が着かない。№502~№504 Y.R. そして、もう一点、ここに書き落としたことがあります。僕は西鶴が専攻じゃない、とここで書いてありますね。むしろ専攻は文芸学理論のつもりだったんです。そして、最初の文芸学の論文、乾孝と連名のものですが、それを岩波の「文学」に載せてもらったんです。その時の「文学」の編集長がN.M.先生なんです。そういうふうに、恩恵を蒙っている方を、どこかでたたかなくてはならなかった。論理は論理、正は正、負は負、というところで。今回、こうした温かい面というのを、紙面の都合上とはいえカットしてしまったこと、残念に思うんです。 ★p.17~「実験と実証、虚構の実験的機能」*について ○ (熊谷) 虚構のどういう側面を問題にしているのか。虚構精神、虚構の機能、こういう点を少しでも具体的に――ということはすぐれた抽象を一歩でも二歩でも前進させたい、と思ったんです。 17ページ上段のところ。経験のつかみ直し――説明科学として文学の科学を、或いは鑑賞理論を話題にする場合、経験のどういう側面が問題なのか、ということが説明されなくてはならない。科学は、学問は説明です。それを明確に、説明に値する説明を、経験ということについてやってみようとしたんです。“経験”――それは経験内容のことでしょう。“つかみ直し”――それは再組織のことですね。これはそういう試み、科学用語として、そういうことなんです。例えば宗教、信仰について。自己の信仰について語る場合、説明になっていなければ通じない。信仰内容を説明する、ということが必要なのだ、ということです。 信仰、それは信仰内容のことです。それは社会現象としての信仰の中身なんですね。徳冨蘆花『思出の記』の場合、菊池慎太郎の信仰の問題、道太郎さんの信仰の問題、そこに必死にくいさがっているから、説明ができている。僕みたいな不信心なものが読んでも、なにか考えさせられるモメントを提供してくれている。これだけのことをやった作家は近代にどれだけいるのか。 *熊谷 実証とは何か、ということから始めますと……何かを実証するというのは、その何かについての自他の経験、直接間接の経験、それらの経験内容を、批評の否定的媒介の機能においてつかみ直す、ということでうね。つかみ直し、つまり経験内容の再組織というこということですね。批評のもつ、この否定的媒介の機能に背を向けていたのでは実証も何もあったものではない、ということを重ねて言いたいわけです。そして、説明という問題。どこかひからびたものという誤った理解がある。説明ぐらい具体的で生き生きしたものはないんです。我々が感動した文学現象がある。それを説明する。本当に説明できないようでは、わかっちゃいない、ということですよね。どこまで、何を、説明できるのか。それは社会現象としてのそれを説明する。それは反映論の立場です。そして、それには客観的なものが欲しいし、自分のあやふやなところを確かめたいから、 第二信号系の理論と取り組んだんですよね。 準体験と説明。何を説明するのか。文学の。準体験をしつつ説明する。説明する、というのはコミュニケーションなんですね。追体験じゃないんです。伝える、ということは伝えあう、ということです。慎太郎の、道太郎の信仰をわかる、というのは何も追体験するんじゃないんです。準体験ですよね。その準体験にたっての説明なんですね。 ★p.19「文学を解釈するのではない、文学という社会現象を説明するのが〈文学の科学〉の任務なのだ」*にふれて ○ (熊谷) 我々のいう〈文学の科学〉は、文芸学――解釈学、精神科学、それを否定するところから始まっている。文芸学批判、ですよね。文芸学と文学の科学とは、語源的には同じですよね。けど、次元がまるで違う。 「文学現象を現象せしめる、鑑賞の機能や役割……」これは、スーザン・ランガーの考え方とイコールです。アピアランス、ということです。アピアするのは鑑賞によってである。しかし、「文学という社会現象」、社会現象であるところの文学現象、という押さえ方はまったくランガーとは違ってくる。これはわれわれ文教研の視点です。 宗教(現象)、それもまた社会現象として我々はとらえているのではないのか。思想として。思想になると信仰と折り合いがあわないようなものなのだとしたら、信仰、犬にくわれろ、ですよね。 *夏目 西鶴作品に見られる虚構の機能のメインになるものが〈実証へ向けての実験〉の機能だ、というこのご指摘の前提になるものとして、このあいだの部会では、まず、〈文学的実証としての小説文学の虚構〉、〈文学的実験としての小説文学の虚構〉という問題設定のかたちで熊谷さんから提案があったわけでしたね。実証や実験という概念がもっぱら科学の領域の主要な概念として用いられているが、それは同時に〈文学の科学〉の視点から、虚構精神や虚構の機能を説明 する概念としても考えられてよいのではあるまいか、という問題提起を含んでいたように思います。戸坂潤先生が〈印象の追跡〉の必要を主張された際に、〈印象〉概念の再検討について語られた事例などが前回の部会で話題になりました。№505 T.K. 9月以来継続して来た蘆花の三作品――『灰燼』『思出の記』『謀叛論』をひとまず終えたところで、高倉テル『日本国民文学の確立』(「思想」 1936.8)を読み合うことになった。筆者の指摘する『不如帰』の読者層の問題と、それに関連する蘆花文学の文体的特質について一歩突っ込んで考えてみようというのがその狙いである。 [略] 《熊谷先生の話から》 読者層の問題を、「実証とは何か」ということを踏まえて考えてほしい。全女子労働者の何パーセントに読まれたかなどということは調べ尽くされているわけではない。実証とは「批評の否定的媒介の機能においてつかみ直す」ことだ。 勉強したくても、教養を身につけたくても、それの叶わなかった女子労働者が、工場の痛めつけられた生活の中でそれを回し読みしたのだ。彼女らの何パーセントかは知らぬが泣きながら読めた、そして病を得て農村に帰される女工がそれを心の支えとした、という事実に眼を向けたい。学歴のない女工たちにも読んで泣いたり笑ったりできる文体であったということだ。この作品を偶然に読んだ女工がいたということではなく、この作品の文体が、小学校四年ぐらいまでは学校に通えた、その人たちに読めるような文体になっているという点の押さえが肝腎だ。 「実証的」文学史があるとすれば、こうしたもの以外にはないはず。「実証的」文学史と「実証主義的」文学史とは真反対のものだ。「実証主義」は物事をつかむ決定的な瞬間を捉え得ずに流してしまう。それとは反対に、間違うかも知れぬが今やらずに入られない、というものがあるだろう。そういうものと取り組むのが我々の基本の姿勢ではなかったか。いま『不如帰』の読者層を把握しようとするに当たってもそのような「実証精神」が必要なのだ。「実証主義」は切って捨てられなければならない。「読者層をつかむとは?」「実証とは?」これらの問題を統一的に考えていきたい。 [略] この高倉論文は、1936年、大学院一年の時、毎号愛読していた「思想」誌上で読んだ。そのときそこに、文学史の原理と方法、文体論の原理と方法を指し示された思いがした。 小学校四年で身売りの対象とされる女子労働者。平均一年から一年半という短い労働期間を経た後、彼女らの多くが胸を病み馘になっていく。そして死を待つために故郷へ帰っていく……。そういう状況にある人間のメンタリティー、プシコ・イデオロギーに、この『不如帰』の文体は訴えることができた、ということだ。どういうふうに作品論は組立てるべきか、どういう方向で文学史は組立てるべきか……。その拠りどころとすべきものを、この高倉論文の中に見た。 この論文に加えて、もう一つ拠りどころとなったものに蔵原惟人の論文があった。日本近代文学の中軸をなすものは、断じてブルジョア文学などではない、プチ・ブル文学だ、という叫びがそこにはあった。高倉、蔵原らは周知のごとく戦前の日本共産党の文化面を支えていた人たちだ。それにひきかえ、戦後の党はどうだ。宮本百合子の文学を最高の文学と賛美したりしている限り、文化面においては支持できないと思う。 ▼1992/02/08 №506~№507 冬合宿(12/26~28) つづき H.M. 例会や合宿の場で『謀叛論』を読み合うのは、今回が初めてであった。しかし、「文学と教育」107号(1979年2月)の内貴和子氏のレポートで紹介されているように、熊谷先生は既に、「日本近代文学における異端の系譜――鴎外・芥川・井伏・太宰――」と題する講演(1978年11月5日/国立音楽大学)で、この『謀叛論』うぃ大きく位置づけられた。内貴レポートによれば、熊谷先生はそこで、「芥川文学を直接的に触発したもの」として『謀叛論』を再評価し、「芥川が実際その場にいたかどうかはまだ立証できないが、当時全寮制だったことや、恒藤らが参加していたことを考えると、仮にその場にいなかったにしても、あの感動をよんだ講演のことが芥川の耳に入らなかったとは思われない。」との判断を示されたのだった。 その後、佐藤嗣男氏が、「『大導寺信輔の半生』の場面規定」と題する論文(「文学と教育」113号/1980年8月)で、芥川の旧友西川英次郎の談話に「芥川もこの芦花講演を聞いたいたはずです」との一節があることを紹介された。佐藤氏の資料踏査はさらに続けられ、「芥川文学と『謀叛論』」(「文学と教育」127号/1984年2月)でさらに緻密に整理された。その結果、芥川文学を民衆の側へ奪還しようとする私たちの営みは、よりたしかな裏付けを得ることができた。 また、大逆事件や蘆花文学に直接触れた講演や論文として、私たちは次に挙げる貴重な財産をも共有している(機関誌掲載のみ)。 芝崎文仁「日露戦争から大逆事件へ」(№126/1983年11月) 荒川有史「文学事象としての大逆事件――徳冨蘆花『謀叛論』を中心に」(№126、127) 佐藤嗣男「蘆花と龍之介――近代散文成立への一つの道すじ」(№140/1987年5月) 芝崎文仁「幸徳事件前後」(同上) 佐藤嗣男「蘆花と龍之介――新文体創造への胎動」(№141/1987年7月) 高田正男「『灰燼』から『思出の記』へ――徳冨蘆花の、新しい言文一致への模索」(№142/1987年 11月) 冬合宿における『謀叛論』の検討は、こうした研究成果を『謀叛論』を踏まえつつ、『灰燼』や『思出の記』とのつながりや説明文体の特質を押さえて印象の追跡をすることを目標にしたものであった。 [略] 話し合いの中で、蘆花の天皇観が話題になった。その過程で、「浅しとて」の歌の作者が天皇であるか皇后であるかが問題にされた。そして、こういう問題が生じるのは〈悪文〉ゆえだとの指摘が熊谷先生からあった。 [略] 最後に、熊谷先生から次のような発言があった。 『謀叛論』は今、まともな評価がなされていない。私たちは全国集会に向けて共通の概念を持ち、『灰燼』『思出の記』『謀叛論』の三つを集会プログラムに組み入れたい。〈蘆花と芥川文学〉〈大逆事件と芥川文学〉ということをも含めて。その際、首をかけて芦花講演を支持した新渡戸稲造のようなインテリ・プロテスタントにもぜひ目を向けていきたい。 ▼1992/02/22 №508~№510 1月第一例会(1/11) T.K. ■《10分コーナー》では熊谷先生が、1月6日付朝日新聞朝刊「声」欄に載った本多立太郎氏(77歳)の「『革命』で得た権利どうなる」と、その文章の中に割り込む形で位置づけられた「かたえくぼ」をめぐって話された。私自身ある種の感動を覚えながら読んだ文章ではあったが、熊谷先生の、これは後世に残るほどのすごい文章だという指摘に接したことは驚きであった。 先生のお話と、それを伺って出された参会者の感想の中からその内容をかいつまんで書き留めておく。 ☆ 乾孝氏が書いていることだが、法政心研で学び保育者として立った、坪田譲治の息子さんは、「おとなの立場で世の中や人生を見るからまちがうんだ、もっと子どものように素直に人生を見なくてはならぬ。おとなの眼からはちっぽけでな家が子どもにはでっかく見える。つねに子どもにかえって世の中を見直したい」と保育者としてのものの見方を説き、自らもその趣旨を貫いて今日まできた、という。 「声」の本多さんの文章を読んでみてどうか。子どもとおとなの話ではないが、ここはものを見る視点、私たちが失いかけている視点が明確にでているのではないか。その視点に立つことが実は正当で健康なことなのだが、いまやそこに立ってものを言おうとすればオズオズとした表現でしか言えなくなっている。妙に改まってしかものが言えなくなっている。われわれが共通に訴えている問題に、「社会主義「社会主義ははたして滅び去ったのか、もう社会主義はいらないのか。やっぱり資本主義だよね、という考えでいいのか。」ということがあるわけだが、そうした「社会主義」観についてももっと素直に語れないものか。 人生にも、子どもの日あり、老年の日あり、その中の「現在」だ。それなのに私たちは他の時と関係なしに単なる「現在」からしかものが見られなくなってきている。そんな中でこの文章の見方はどうだろう、近来にないすごい朝日の投書の一つだと思って読んだ。 「私」の質問に答えてシベリアの老人たちは言う。「――とても良くなったことが一つある。現在は子供の教育と老後の生活は国家が保障してくれる。革命前は考えられないことだ。」そういう自由をいま我々社会主義によって獲得している、そのことを目を輝かして彼は語った――。それで彼らの言葉はいまどう次の世代に、さらにその次の世代に伝えられているであろうか、受け継がれているであろうかという問題を本多さんは出している。そして終わりの段落。「ゆりかごから墓場まで」の人生と社会システム・国家のシステムとがどのような関連にあるか、という問題が語られている。 我々が我々の時代において獲得した社会のあり方、それが私の幸福をもたらし、我々の子孫の幸福をもたらした。私の未来を約束してくれている。しがないものであろう、でも、皆が苦しむときに自分も苦しんでいる。自分が苦しいときは他のひとも苦しい。そういう中の苦しみは耐え得るし、また耐えることに喜びを感ずる。教育は子供の時代に始まる。その教育が自分や自分の後の世代を育んでくれている。――そういう喜びを語っている。 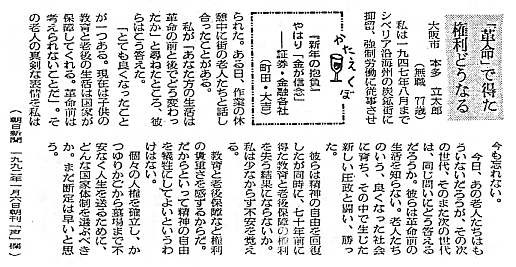 一方、そこにある「かたえくぼ」を見てほしい。「ああ、永遠なるかな資本主義。絶対なるかな自由社会。」それをリードしている証券・金融各社。その新年の抱負。このようなことの中に喜びを感じている人々。その中で人はどう考えるのか。私の場合は老年者だから(老年者にもピンからキリまであるが)自分自身の問題として語ることができる。けっして老後は保障されていない。では子どもの時代・青年の時代は保障されていたか。保障されていなかった。それが保障されているといわれている社会の中で保障されていなかった。そして、知らずしらず「金が信念」だ――、そっちへ傾きかけてはうしろへ戻り、傾きかけてはうしろへ戻り、という暮らしの中で生きている。そういう目でこの文章を読み、何の解説もいらないすごい文章だと思った。四百字とちょっとでこれだけのものを――。 無駄がなく、気取り・はったり・借り物のない文章だ。また、いかつい面も一つもない。後世に残る文章ではないか。こういう文章を書きたい。説明文体かくありたし、だ。「自然と人生」を感じさせる文章だ。自分が特別のところにいるのではなく(いや、抑留ということでいえば特別だが)、その場面をきっちり押さえて、そこでどういう人と会話しどういうことを考えたのか、いままたどう考えているか、実に緻密な文章だ。感動した。 この投書の文章と、この「かたえくぼ」との組み合わせの妙。くだらぬ新聞にますますなりつつある朝日だが、そこにはまだ同じ思いでいる記者・編集者も存在するのだ、編集に苦労しているのだな、と思わされる。 [略] ■続いて熊谷先生から「歴史と文学の会」の研究活動と関連し、「仮説」「実験」の重要性についてお話があった。 ☆ 「歴史と文学の会」は、一昨年秋以来すでに17回を数える。西鶴作品を中心とするそこでの読書量は大したものだと自画自賛に値するが、では、どう読んでいるのか、総括の仕事をやってみたいという願望を持つ。何が感動的なのか、どういう点が読み返さずにいられなくするのか、どういう点を後の世代に伝えていかなければならないのか、そうしたことの再検討の機会を今年はぜひ持ちたいと思う。 「仮説」を安っぽく考えてはいけない。文教研の仕事は仮説(Hypothese)を打ち立てること。それはまた、「実験」ということと大きくかかわる。全般的一般化の段階における「実証」などできない。できる条件もない。条件のないところには何もない。できるのは「実験」、「実験」の緻密化だ。「仮説」をつくるための「実験」だ。「実証」はできない。 「実証」を、というなら、投書の本多さんは何も残さずに死んでいくしかない。だが、現に「実験」において我々をこれほど感動させているのではないか。子どものころを、子どものためを忘れないこと、意味のある人生を送りうる条件を創り出していくことを――、というように、方向を誤ってはいない。 文教研が持っているつもり の財産目録を提出したい。わずかの財産を大切にしよう。 [略] ■蘆花『自然と人生』の検討の中での熊谷先生のコメント。 ☆ 旧制中学時代、教科書・副読本に名文として必ず載っていた。 ☆ 読みやすい文章だという発言もあったが、「読みやすい」ということの重層性の問題を、よく考えてみたい。 読みやすい・読みにくい、といっても一律には言えない。明治の人にとってどうだったのか。大正になるとまた違ってくる。昭和ではぐっと違ってくる。二葉亭四迷によるツルゲネフのすばらしい翻訳は、たぶん読みいいものだった。あの読みやすさ・親しみやすさで育った人種にとって、『自然と人生』は「読みにくかった」のではないか。 ☆ 『自然と人生』全編の中で焦点をどこに置いて扱おうとするのか、我々はまだ確かめていない。〈兄弟〉も、あるジャンルの代表作だ。〈国家と個人〉もそうだ。「愛国、忠君、其は君が説くに任す。願くば陛下の赤子をして餓えるしむる勿れ。」――この辺を焦点と考える人もいれば、〈此頃の富士の曙〉に焦点を感じる人もいよう。趣旨がはっきりしなくて、ややモタついているようだ。骨子・趣旨を明らかにして次回に臨みたい。著者自身「自然と人生」とはいっても、はっきりしない、シドロモドロのところがある。我々がいまどき『自然と人生』を取り上げる意味を証明できるように持っていきたい。 [※1月第二例会(1/25)は(拡大常任委員会のため?)中止となった。] ▼1992/02/22 №511~№513 2月第一例会(2/8) I.H. 〈徳冨蘆花『自然と人生』の報告と討論〉 前回の例会で、熊谷先生が「この作品集は、カオスとも言えるわけで、いろんな要素を持っている。どういう焦点、切り口を取るかで様々な問題が見えてくる」と指摘してくださった。その指摘を受け、切り口をはっきりさせつつ、この作品集の内包している可能性を中心に、N.H.さん、 I.M.さんが報告された。 [略] ▼1992/03/14 №514~№515 2月第二例会(2/22) M.M. 《1/25,2/11の拡大常任委員会の討議報告―全国集会に向けて―をめぐって》 入試と感冒に直撃された会でしたが、西鶴文学研究にとって画期となる提案がなされ、密度の高い話し合いが行われました。 以下、熊谷孝先生の問題提起を中心に。 〈二代目=今日の自分たちの世代=階級としての世代〉 (1) 西鶴は、自分の属る世代が生物的にも階級的にも二代目であり、自分が扱うのは、自分たちの世代のこと――自分たちの世代の意識、感情を通してみた我が世代のありようであり、そこから逆照射して、我々の世代の、我々の眼に映ってきた我々のご先祖(初代)のありようと我が世代とのかかわりを問題にする。〈二代目〉とは、その意味においてであることを確認してほしい。 (2) そこでは、自分たちの世代が問題なのであり、それなしには〈現代史としての文学史〉にならない。今日を生きる人間である自分たちから振り返っての過去である。その自分たちは、はたしてまともに自分自身をつかみ得ているか。様々の誤認や誤った感情のあり方をしてはいないかどうか。また、ご先祖をこえた新しいものを持ち得ているかどうかの検討が必要であろう。 (3) わが西鶴世代は、我々とちがってマルキシズムもヘーゲルもくぐってはいない。当時、階級という語は存在していなかったが、彼らの世代は、純粋な意味での階級としての世代、本質的に階級とよべるものではないか。したがって、〈二代目〉とは、単に二代目なのではなく、生粋の階級的なもの、我々の用語でいえば、〈常の町人二代目〉(西鶴自身の自己規定、階級概念)ということになる。新興町人としてスタートした集団が分化(階級化)する。その時、経済的な覇者への道を求めるのではなく、明日はより一層ひどい経済状態になっていく、しかしその一面で、初代とはまた違った意味で、明日といういう日を今までにないものとして築かざるをえず、築こうとしている、そうした世代である。 (4) 西鶴の作品は、“昔ばなし”ではない、“浮世咄”になっていく。“仮名草子”は、生物学的には西鶴の世代にタッチしているが、「我が世代」的なものではない。それを超えようとして生み出されたのが浮世草子である。 〈新興町人=商業ブルジョアジー〉 (5)〈新興町人二代目〉という言い方を今後やめようと思っている。西鶴はマルキシズム以前の人だから、階級論にせよ、その理論構造にせよ、身分概念、階級概念がゴッチャになっている面がある。しかし、我々はもっと整理できるはずなのではないか。 利左は、三井高利のようでありたかったのに、そうなれなかったのではない。意識的にふみきって、人間としてかくありたい、そうしか生きようがないという生き方を求めて、逃亡の道を選んでいる。“逃げる”ことでしか自己の存在証明のしようがない中で、その道を選んでいるのだ。――それは封建社会の庶民大衆の叫びにもなってくる。 その事をきっぱりと言い出したのが西鶴という文学者であり、彼の天才性をそこに見出す。 (6) 西鶴は、初代からの受け継ぎを全部拒否しているわけではない。受け継ぐに値するものを見つけている。 (7) 新興町人という言葉は、〈商業ブルジョアジー〉の訳語。つまり前期資本の金貸資本や、商業資本の担い手という意味。古代にも商人(あきうど)は存在したが、それとはちがって、前期資本の誕生をもたらし、前期資本の発展とともに覇権を握っていった〈商業ブルジョアジー〉、その訳語ととってよい。 〈商業ブルジョアジー、確立へのプロセスとその後) (8) 商業ブルジョアジーとして成功し、大きな利益を懐に入れていった連中、そして高利貸資本として庶民大衆――一般町人大衆、一般農民大衆、職人衆――を苦しめていった連中と、それはどう関わるのか。逃亡を重ねつつある利左は、グランブルではないとして、商業ブルジョアジーか? プチ・ブルか? 産業資本の段階と同じではない。 言い方を変えなければ混乱が起こるのではないか。 (9) 西鶴の書いた作品に即してみてもそうなのだが、本来的な意味で特権町人と書きならわしてきたのは、ヨーロッパ社会に現存した都市門閥貴族の訳語である。その特権町人に搾られてきた庶民大衆の中から、鎖国という形の抑圧に抗して、反抗の旗印をかかげ、行動を選んだ人達の中から、苦労を重ねて新しい特権町人になった三井・鴻池がでてくる。 身分は町人であるそういう人達の、成功へ向けての欲望充足のための苦心努力のプロセスを二代目である西鶴は、その中から拾って書いていった。『永代蔵』の始めの部分はそれであり、三井高利もその中の一人。艱難辛苦して地歩を築き上げるプロセスに我々の眼が向く。その事を西鶴はどう評価しているのか。作品の鑑賞過程に即してみていってほしい。 (10) それをみていく時に、次の①、②をゴッチャにしないように。 ① 親の譲りを受けず、あるいは少しばかりの譲りをフルに活用して自立していく彼らの姿――商業ブルジョアジーとして自己を確立していくプロセス。 ② 彼らの到達した目標は何であったか。搾取の形態はどうであった。――商業ブルジョアジーになった彼らが、搾取の根源となって猛威をふるう。幕藩権力に彼らはどう取り入り、握手したか。 (11) 商業ブルジョアジーが庶民大衆にやってのけた非人間的行為の典型例が、こよし、利左夫婦の場合であろう。商業資本にもいいところがある、という発想でなく、近世文学におけるさまざまのヒーロー、ヒロインを西鶴や芭蕉たちがクリエイトしたと見るべきではないか。 #「西鶴の発見」を読む会 へのお誘い# 4月5日(日)午後1時半から、烏山区民センターでにおいて、[熊谷先生の論文]「西鶴の発見」を読む会を行います。“新興町人”概念のとらえ直し、という課題が提示された今、改めて読み返したいと思います。何度も読んでいるわけですが、それでも読み飛ばしたり、分からない部分をそのままにしてきているところなど、率直に話し合えれば、と考えます。三人寄れば文殊の知恵。いかがですか。(呼びかけ人 Y.R.) ▼1992/03/27 №516~№517 3月第一例会(3/14) D.H. 今回の例会は熊谷先生が体調をくずされて欠席されるという残念な状況のもとで開かれた。まず、3/1に開かれた特別研究会の報告がM.M.氏によってなされ、その報告と当日配られたニュース(514,515号)をもとにして、前回の例会で熊谷先生が提出された文教研の西鶴文学研究にとって画期となる提案を、全員のものとしようとするための話し合いがおこなわれた。 ここでは特別研究会の報告と、それを受けての話し合いを、合わせてまとめる。 (1) 二月二十八日づけの朝日新聞の「予備校もつらいよ」という記事について。この記事は、今年の東京大学の国語の入試問題に関してのものだが、ここで触れられている問題は、まさに西鶴文学を考えるうえにおいても、現代のインテリを考えるうえにおいても、非常に重要なものではないかということが、熊谷先生のほうから提起された。 「インテリというのは自分で考えすぎますからね、そのうち俺は何を考えていただろうってわかんなくなってくるんです。テレビの裏っ方でいいますと、配線がガチャガチャにこみ入っているわけなんですよね。その点私なんか線が一本だけですから、まァいってみりゃ空っポといいましょうか、たたけばコーンと澄んだ音がしますよ。」(渥美清)(2) いわゆる「西鶴世代」を、新興ブルジョワジーとしての「新興町人二代目」と位置づけることができるのか。広い視野で再度西鶴文学をとらえ直す時期にきている。 (3) 旧特権町人を打ち倒し、巨大な商業資本家となりえた三井。かれは商人として、自己の才覚と努力によりある種の成功をおさめた。だが、商人としてやりくりがうまく優れているということと、民衆の先頭にたつということとは別のことである。現に三井たちは、農業ぬきでは成り立たない時代に、多くの土地を手に入れ、地主となって農村生活者を支配していく。このことはこの時代においては、経済の実質的な支配者ということである。そしてそのように移行していく決定的な時期が元禄期である。 (4) こうした商業ブルジョワジーのあり方は、利左やよしたちとは敵味方ほど違っている。利左たちは新興町人の上層者になろうとしたが失敗してしまったので今の立場に甘んじているわけではない。三井たちとは根本的に、階級的に、ちがっているのである。 (5) こう考えると、西鶴文学はまさに優れた抵抗文学 たりえているのだといえるのだろう。 (6) 逃亡の世代ということでは、同時代の芭蕉と切り離すことはできない。芭蕉はみずから逃亡の道を選び、西鶴は虚構において逃亡を描いた。このちがいはジャンルのちがいによるものなのであろう。しかし、この精神の共軛は重要な問題である。 (7) 西鶴文学の「配線」はゴチャゴチャしているのではなく、「コーンと澄んだ音のする太い線」があるのである。 (8) 近代の小説家と近世の小説家 近代の小説家――ある見通しの中で人間を描いている。 近世の小説家――見通しということよりも、書かずにはおられないことを、筆のほうが先に動くとでもいうように描くことで成功している。 [略] ※ 特別研究会でもたびたび話題になったという古島敏雄氏の著書として、『日本農業技術史』と『近世日本農業の構造』が紹介された。 ▼1992/04/11 №518~№522 春合宿(3/27~29) I.H. Y.R. I.M. H.M. & D.H. I.H. 今回の合宿には、熊谷先生が、体調を崩しておられるところ無理をして参加して下さった。先生は前日から、セミナーハウスに泊まって体を慣らしていらっしゃったが、初日は、どうしても起き上がれないほど具合が悪く、部屋で休んでいて頂き、回復を願いながらの合宿の始まりとなった。 まず初めに、M.M.さんから、ニュース№514,№515をもとに、ここ数回の例会で提起された〈新興町人〉と〈西鶴世代〉のとらえ直しの問題が整理して媒介され、今回の合宿の課題を確かめ合った。 その後、早速、①のパートに入り、作品に即して、課題の検討をした。以下その報告、補足発言、討論のメモである。 ① 『永代蔵』「初午は……」「浪風静に……」(3/27) [略] ② 『好色五人女』「姿姫路清十郎物語」(3/28午前) Y.R. 司会のA.Y.氏から用意された資料について話された。森村学園女子部で熊谷先生が学生たちに媒介するために作られた、『西鶴作品集』の中の「姿姫路……」である。一章から四章のあらすじと、終章の写しとで構成されている。学生に向けての、優れた西鶴入門であり、いわゆる好色ものと片付けられてしまう傾向をシャットアウトする要約である。今、西鶴の何を問題にするのか、ということのより所として使わせてもらいたい、という意味をこめての紹介だったように思う。 [略] ③ (28日午後の部では、急きょ教師館の会議室に会場を移して、熊谷先生を囲んでの話し合い、という形をとることになった。) I.M. 午後の部で話題になったことをについて、私なりの要約を書いてみると、次のようになる。 1. 西鶴世代と私たちが言う場合、それは、「戸籍上の存在」を指しているのではなくあくまで、文学史上の、精神史上の存在である。つまり、文学創造の主体としての西鶴、西鶴の視点的立場によってのみ創造(発見)された存在として、西鶴世代を把握する必要がある。 2. 西鶴の視点的立場とは、前期資本の人的表現としての商業ブルジョアジー(新興町人)の立場ではない。出身階級が新興町人であったとしても、自己の教養を媒介にそれを乗り越え、脱新興町人階級という立場において獲得されたものが、西鶴の視点的立場である。 3. 芥川文学の視点的立場が、「教養的中流下層階級者の視点」であるというのも。芥川龍之介が実際に中流下層階級者として生活していて、アンジッヒにそのような視点を身につけたということではない。彼の生活条件は、むしろ、中流中層ぐらいであろう。だが彼が、自己の文学創造の過程において獲得したのは、「教養的中流下層階級者の視点」だったのである。西鶴文学の視点的立場を把握するためにも、こうした観点が必要だ。 4. 文学的な視点的立場としての階級的立場は、世代的立場と不可分であり、むしろ、明確な世代意識によってこそ、このような階級的立場が獲得されるのだ。 5. 以上のような点が不明確だと、他の歴史学に対する文学史研究の独自性が把握できなくなる。 [略] ④ 『万の文反古』「代筆は浮世の闇」(3/28夜) H.M. [略] 4人の報告を受けて、話し合いは自心の精神構造をめぐって進められた。「商業ブルジョアジーの持っていた誠実さの受け継ぎが自心にはない」というN.T.氏の発言が呼び水となって、次のような意見が相次いだのであった。 ○ 受け継ぎの問題とだけ限定できないだろう。フレッシュな感覚の町人大衆もまた、あるところでつまづくことがある。20代と60代で変わっていくこと――精神のありようが不健康になっていくこと――もある。そういう人の感覚で受け止めると、この作品はどうなるか。(熊谷孝氏) ○ 受け継ぐも受け継がないも、自分の問題だ。個々の人間の世代意識を問わなければ文学にならないだろう。 ○ 「衣食住の三つに楽しみを極めん」と考える自心には夢がない。 ○ 自心の言葉は、普通の感覚の人間が読んだらおかしいと感じざるをえないような見えすいたものだ。(熊谷氏) ○ 幽霊の怒りや叫びの方がよほど人間らしい。自心の姿は、大事なものを自分の生活の中に求めないとこんなにもなる、という感じを与える。 ○ 自分の中に自心につながるものを見つける時、この作品は無縁のものではなくなる。生活の中に人間として大切な何かを求め続けている限りわたしたちは美しくもなりうるものだ、と思えてくる。 こうして、自心の人間像が浮き彫りにされ、幽霊登場の虚構的必然性も話題にされる中で、話し合いは〈近世小説と近代小説〉の問題にも及んだ。「熊谷先生は、近代小説につながるモメントがこの作品にあること、これは意識せざるエゴイズムを初めて描いた作品であること、を指摘しておられる。」という発言(A.Y.氏)を機に、熊谷先生から概ね次のようなコメントがあった。 「基本として、近世小説と、近代小説の違いと特徴をきちんと押さえなければならない。その上で、この二つを分離させずに考える必要がある。日本の近代小説は西洋の影響によって成立した、という考えは間違いだ。西鶴たちが用意したもの(土壌)があって初めて近代小説が生まれ育ったのだ。」云々。「学問はくどいものです。」と念を押されながらの、貴重なご指摘であった。 また、人間の可変性に関連して、「自心も初めからこういう人間ではなかったろう。それがこのように転落するところにリアリティを感じる。」という発言があったが、 「これは自心の転落の過程を描いた作品なのか?」 「この短編集では自己凝視を徹底している人間と全くしていない人間とを描き分けているが、自心は後者であろう。」 「救いようのない自心、というところにポイントがある。」 といった発言が続いた。 そして、「精神的に不健康になった自心を、対決すべき者として西鶴は描いている。」という方向で落ち着いた。 さらに、自心の出自をめぐっての発言もあったが、機関誌118号掲載の井筒氏の論文と重なる内容であったので割愛させていただく。 最後にS.T.氏が、熊谷先生の時期区分論を踏まえることの重要さを強調しながら、「敵として闘わねばならない人間を見据えて描いている」この作品の性格や、〈近世小説と近代小説〉の問題などに触れて話し合いをまとめられた。 ⑤ 『日本永代蔵』「二代目に破る扇の風」(3/29午前) D.H. [略] 報告者と報告グループのメンバーからのコメントのあと、話し合いに移った。話し合いでは、拾った銀を返そうかと迷う場面などをめぐって、そこを二代目の健康的な面とする意見が出され論じられた。A.Y.氏が、「迷うことのモメントに目を向けたとき、確かに自心とは違った人間的な何かを感じるが、それが主体化された人間の行動ではない。」という発言をされ、この件は、ひとまずおさまった。しかし、「商業ブルジョアジー」とうい言葉を安易に使うと、大切な概念のはずなのに、解釈の道具になりかねないのだという感想を私自身感じた場面であった。 つづいて熊谷先生から、この作品形象でなければ訴えられないものは何かなのかを論じるべき、という助言があり、その問題に移った。 ○ この二代目とお夏・清十郎との違う点はわかるが、共軛点は?(熊谷) ○ 初代とはちがったところに自分の生き方を求めようとしている点。 ○ この作品固有の面白さは、社会的存在としての町人身分の特徴を余すところなく描いているところではないか。この「恋風様」は逃亡世代ではない。社会的存在としての人間の運命を、利左を描くよりも正面から描いている。そうなると当然描き方はカリカチュアとなる。(熊谷) この熊谷氏の意見により、この二代目像が大きくつかみ直されたような気がした。 「巨大な歯車とそれに翻弄される人間というつかみ方ではなく、二代目の感じ方や行動を通して、この時代の社会的存在としての人間が描かれている」(A.Y.氏)、「この二代目の姿は単なる特殊なのではなく、社会的存在の必然、こうなってゆかざるを得ない姿を描いている」( I .M.氏)など、この熊谷氏の意見に触発されての発言があった。 ⑥ 『西鶴置土産』「人には棒振虫同前に思はれ」(3/29午後) D.H. [略] 報告に続いて、話し合いに移った。その中での熊谷氏のコメント。 この作品でなければという側面からの追究がされるべき。 利左にとってこの三人の友人たちからのすすめは、「狂い咲き」のすすめである。「普通」の生活をおくることが、他者を疎外に追い込んでしまう。逃亡世代の問題が見事に描かれていないか。 ▼1992/04/25 №523~№525 4月第一例会(4/11) Y.H. 例会は、「現代史としての文学史――世代意識と虚構精神」の視点から、〈春季合宿研究会〉を総括しようという会でした。 [略] 熊谷先生から貴重な助言、私たちがこの合宿で押さえ忘れてきてしまっていた点の指摘があり、ここであらためて、そこから学び直すかたちで総括がされました。 それは、西鶴文学が、近世封建社会(文化・経済)史の構造との密接な関連・統一において追跡されきれなかったのではないか、文学現象と社会史とを統一的にとらえないと〈現代史としての文学史〉にはならないのではないか、という指摘でした。 確かにわたし自身を振り返ってみても、この指摘は当たっていました。当然、押さえておくべきであった私たちの財産としての〈西鶴地図〉(『近世文学における異端の系譜』 1981.8.6全国集会熊谷講演レジュメ)をもとに、感動の質を検証することはほとんどありませんでした。自己の実感を大切にすることと、実感を甘やかすこととの混同を避ける、唯一の方法原理としての「場面規定を押さえる」ことをおろそかにしていたということになります。 Y.R.さんは、そこのところを次のように問題をつかみ直すかたちで発言しました。……春合宿では西鶴地図に沿った作品群を読んだ。一本勝負では見えてこないものが見えてきた。でも、『西鶴の発見』(「文学と教育」№115)で述べられている「新興町人社会の現実と現実の推移を、自分の文学主体の問題として西鶴がどう受けとめているのか、その受けとめかたの変容・深化がおのずから作品の展開にある区切りをあたえている。その区切りを文学現象の中に事実に即して見つけていくのが、時期区分論の課題」というのを正面にすえて照射してみると、本当には読めてなかったことに気づいた。とくに「現実の推移」があるということ、その推移を読みとるために、どれだけ『異端の系譜』の年表と注を通し作品を追跡しえたかと、いま反省が生まれている。…… 「時期区分の問題を正面にすえてここの西鶴作品の位置づけや評価について一緒に考えあってもらいたい」という熊谷先生の提案を、私たち会員がどれだけ「正面にすえ」ていたかという反省でしょう。 N.T.さんが、それを受け『異端の系譜』の年表とその注記の重要さを強調しつつ、とりわけ、重要な点として「元禄期が封建制動揺期の端緒的段階」というところをあげ、「第3表・注9で示されているように、小規模農業経営に危機が出てきているということ、そこをキッチリ押さえて西鶴論を展開しなければならないと思う。その時代を生きていた生活者はそれをビンビン肌で感じとめていたと思う。その〈何か〉を感じている読者を、西鶴も内にあたためて格闘しているのではないか、その点をさぐり、深めたい」と発言。 つづけて熊谷先生が、小規模農業経営の危機の深化と、地主富農経営から寄生地主的経営へと変貌していく動揺期の端緒的段階の動態について、『近世文学における異端の系譜』の第1表、第2表をつかって説明、具体的に証明されました。 さらに、先生は、解体へむけての動揺期にもふれ、その収奪の凄まじさを、“二村に質屋一軒冬木立”と詠んだ蕪村を通し、封建動揺期の深化を、その文学現象と社会史との統一において話されました。 これらの発言を受け、あらためてA.Y.さんによって、〈西鶴地図〉を組み込んだ整理・総括がなされました。 ……私たちは『西鶴の発見』や『近世文学における異端の系譜』に学びながら、西鶴の世代とか西鶴を取り巻く人々の苦悩の根源や近世特有の矛盾といったものを押さえなくてはいけないのではないか。とりわけ『異端の系譜』の第3表(年表)とその注記は、私たちの西鶴論、西鶴世代論を検討していくときの基本的な文献、出発点として確認しておきたい。そのために、 ① 「新興町人」の概念を考えるときに、同表注1に示されている「鎖国の問題は避けて通れない」という熊谷先生だけが提示している、このテーゼを大切にしたい。(林基さんのような歴史学者といえども、特権門閥町人と新興町人との交替は指摘していても、そこで交替していく新興町人の変化とその質を解明しているとはいえない。)このテーゼに立った西鶴論を展開したい。 ② 注7、8にある「……親よりゆづりなくては富貴にはなりがたし。……今は銀が銀を儲くる時節」を先ほど引用し、そういう「時節」における西鶴世代の自己凝視ということを問題にしたが、初代新興町人の上昇過程が一応のピークに達した、そのメルクマールとしての三井呉服店創業(1675)、そして1683年三井の両替店開業という新興町人内部における階級分化、固定化の現象とを結び付けて問題を提起しなかったという弱さを反省したい。 ③ 注2、3,4,6の指摘、「近世的小規模農業経営ないし地主富農経営」これこそが近世封建体制の基本的な生産関係、人間関係、階級関係なのだが、その端緒的な動揺期において、西鶴の主体的な文学活動が行われていたんだという、そういうダイナミックな問題のつかみかたが、春合宿では弱かった、という総括・反省を、きょうここでしておきたい。 これは私たち全会員の反省であり、春季合宿の総括として全体で確認されました。 さらに熊谷先生は、西鶴の実際の読者についてイメージ豊かに話されましtた。 ……西鶴の実際の読者、実は大百姓の労働力としての家族、譜代奉公人、年季奉公人たち、都会地では大店の丁稚たちであった。富農地主や大店の主人は、奉公人を夜間外出させない、その代替娯楽として、それはまた労働力の再生産のためにではあるが、一定の楽しみを提供しなければならなかった。そこで貸本なのである。貸本による回し読み、読み聞かせがそこでなされた。時には連雀商人[連尺商いをする人、行商人]を介して高価な西鶴本も地主や大店の主人ならば買い取ることもあったろう。こうして寺子屋以外でも文学教育がなされたのだ。岡山藩に保存されていた西鶴本にしても、奥女中が読者であったこと見落としはならないのではないか。奥女中、実は奥へ勤めにあげられた町娘である。 西鶴の読者とは、こういう具体的な問題なのである。そういうつかみ方をしていかないと、変に高度のインテリゲンチャ向けの文学、西鶴論にすりかわってしまう。ほんの一握りの人だけに読まれた西鶴といった誤解を恐れる。 また、西鶴文学の読者は、その内容から、古典の素養を持った階層に限られるという論に対しても、実は、徒然草や能など中世の古典が、民衆の中に広がっていくモメントとしての“仮名草子”を視野にいれてみれば、その論の狭さが明らかにされよう。むろん、仮名草子の読者がすべて“浮世草子”の読者、西鶴の読者になったわけではないが、そうした基盤は見落とせない。 なお、こうしたつかみかたは、近代における文学の民衆基盤の広がりについて考えるときにも有効である。多くの女工さんに読まれた『金色夜叉』や『不如帰』を通して、文学が農村に拡がっていったということへも、つなげて考えてみてはどうか。…… 西鶴の実際の読者を見誤っては、その本来の読者、西鶴の内なる対話の相手をも、見誤ってしまうだろう、それはまた、西鶴世代の問題と深く関わるわけだ、ということなど、ここへ来てさらにダイナミックに西鶴地図が理解されてきました。重要な指摘、貴重なお話でした。 以上。 ▼1992/05/09 №526 4月第二例会(4/25) T.K. 第41回全国集会プランの検討を行った。(第二部に予定されていた春合宿の総括の続きは、時間切れのため割愛。) 首都圏会員について担当者の割振りを決めた後、集会プログラムに従い、各パートの責任者から基本的方向についての説明があった。 ■蘆花文学――『思出の記』 (N.T.) [略] ■『謀叛論』 (S.T.) [略] ■西鶴 (A.Y.) [略] ■『日本人の自画像』の「近代」「教養的近代」「反近代」等の概念について (熊谷) 幕末から明治へ。近代がまだ実現していなくて、その中で必死に近代を理想化していく想念が生まれてくる。それの実現へむけての行動が自由民権運動だ。これは真に具体的・臨床的な実践であった。近代は未だないが想念として見えてくる。これが本来の近代主義である。 ところが、やがて曲がりなりの近代が上から作られてくる。反動的なものにすり替えようとする明治政府、それに引きずられていく文壇(という形ではまだないが)との闘いが、反近代主義の闘いである(『謀叛論』の蘆花、芥川……)。芥川はっもはやわれわれの求めているのは近代ではない、と言っている。 #会員動静# ☆ 佐藤嗣男 「芥川龍之介――“王朝のヴェールをかぶった”短編――」 「国文学解釈と鑑賞」1992.5に掲載 ▼1992/05/23 №527~№528 5月第一例会(5/9)S.F. 初めに、全国集会の役割分担についての、常任委員会の報告を聞く。 次いで、熊谷先生の『太宰治 〈右大臣実朝〉試論』(増補版)の検討に移る。熊谷先生は、この著書の内容をさらに深めたい、それについて夏の全国集会でもぜひ話したい、という意向をお持ちだとして、常任委員から、その話された内容が紹介された。 ① 〈印象の追跡〉を意識的に行っている団体は文教研だけだ。鑑賞は印象を追跡し続けることで是正される。また、鑑賞は、研究・批評によって裏打ちされていなければならない。その研究・批評も、それ自体印象の追跡の対象となる。この関係をきちんとつかむ必要がある。解釈は追体験主義に基づくが、鑑賞は準体験による。両者の区別をはっきりさせるべきだ。 ② 三首の問題(『太宰治』p.234)。京都体制へのかかわりについての印象の追跡をすること。「明ルサハ、ホロビノ姿デアロウカ」は、礼賛か。マチ針の問題を考えること。口先だけで言っていないか。 ③ アマチュアリズムの問題。アマチュアリズムはいわゆる素人芸とは全く違う。精神の自由の問題だ。プロとしての意識を持つこととは矛盾しない。その意味で、アマチュアリズムは学問・研究の本道である。 ④ 研究姿勢。懸命に取り組むほどに、その対象作品を最高のものとしてしまいがちだが、それには要注意。そもそも報告とは何か。少しノンキに、しかし、本気で。 ⑤ 太宰文学のすばらしさは「水たまり……」(「太宰治語録」15〈私にとって小説であるもの〉*)にある。現実の反映像である意味を、形象的に描いている。文学者の立場は、美と英知による創造。(「語録」23〈曳くかれものの小唄〉*)美と英知を規準にした倫理の創造。倫理とはプシコ・イデオロギーだ。倫理を樹立することが文学者の仕事である。 *15 私にとって小説であるもの⑥ 蘆花文学とは何か。西鶴文学とは何か。方向感覚を確かめることである。 ⑦ 『太宰治』を現在の達成点とみるが、〈右大臣実朝〉試論があることを忘れないでほしい。 [略]
▼1992/06/13 №529 5月第二例会(5/23) Y.R A.Y.氏から、熊谷先生のことをめぐって、いくつかのことが報告・提案されました。今度発行される「文学と教育」の巻頭言に代えて、福田委員長による追悼の文章が載ること。それを、A.氏が全文読み上げられ、紹介されました。また、熊谷先生の蔵書を処分するにあたって、会員の財産にするためにも、そして熊谷先生の奥様に少しでもお役に立てるように、競売(?)にかけるのはどうだろう、という提案。文庫にするにはスペースの問題があるので無理。先生の書き込みは皆の情報交換がなされることを前提にして。……などなど。蔵書目録が作成されつつある状況です。いろいろなご意見をうかがって、よりよい方法を考えたい、ということでした。 全国集会の初日は、熊谷先生の追悼集会とすること。そこでは、乾孝氏、伊豆利彦氏が「熊谷孝、人と学問」ということで話してくださること。また、奥様も参加して下さるということです。夜の部は懇親会とし、8月5日の分は、6日以降に詰めていくことにしたい、ということで提案、了承されました。 〈『思出の記』の印象の追跡〉 [略] #教育基礎講座# 去る6月6日、広島の婦人教育会館において、広島市民間教育サークル会議主催の第十五回教育基礎講座が行われ、A.Y.氏が「文体づくりの国語教育」ということで講演されました。 #広島のN.さんからの手紙――嬉しいご報告。地方会員として四名入会!! # 前略 今年の基礎講座も、A.先生を初め福田委員長、S.S.先生、Y.R.さんに駆けつけていただき、充実した時を持つことができました。ありがとうございました。 さて、今回、入会を希望された四名は、広島・文学と教育の会(広島文教研)の重要なメンバーとして、長年活動を共にしてきた仲間です。広島で行う例会や教育基礎講座、さらに夏の全国集会への参加を重ねる中で、これからの文学教育を考えた時、文教研の理論しかない、との確信を深めて、入会を決意されました。 いよいよ、これから……と思っていた矢先の、熊谷先生のご急逝。無念。いえ、だからこそ、やはり、みなさんと一緒に歩みたい。広島の会員一同の思いでもあります。どうぞ、よろしく、お願い致します。 [4名の氏名、勤務校 略] ▼1992/06/27 №530~№531 6月第一例会(6/13) Y.H. 〈例会全段の報告二、三〉 1. 広島・教育基礎講座(6/6)講演の報告 ……熊谷先生、ご急逝の哀しみを受け止めての、緊張した集会でした。40名の出席。A.さんは講演内容を急遽組み替え、先生との出会いから、第1部〈なにを学んだか〉、第2部〈母国語意識の自覚〉という組み立てで話されました。 講座終了後の「文学と教育の会」のつどいでは、先生への黙祷を捧げ「こういう時だからこそ頑張らなければ」という意思が表明されました。(福田委員長) ……加えて、講演は福田さんの『かさじぞう』論とS.S.さんの『走れメロス』論があり、緊張した中にも楽しい雰囲気が生まれました。(Y.R.さん) 2. 地方会員の入会承認 地方会員として、O. K. M. Y. の方々の入会が、常任委員会で承認されました。(4人の方の氏名、勤務先はニュース529号に) 3. 第41回全国集会プログラムの内容と日程の一部変更について (企画部) ① 集会第1日の8月5日は、熊谷先生を偲び、その「人と学問」を改めて振り返る日とし、乾孝氏、伊豆利彦氏にご出席いただき、夜には懇親会を持つという企画で、今年は、この日だけの1日会員(1万円、含 懇親会費)も募ることにしました。……了承。 ② それに伴い、集会第2日以降のプログラムの日程に若干の変更が生じます。 [略] 〈『灰燼』の印象の追跡〉 [略] ▼1992/07/11 №532 6月第二例会(6/27) M.M. 6月21日、光母寺で熊谷孝先生の納骨式がおこなわれた。文教研からの出席者は、F.T. N.T. A.Y.の三氏。 例会の席上、夫人と福田委員長連名の挨拶状が手渡され、葬儀に弔意を寄せられた方々について、概略報告された。 〈基調報告「文学史の中の近世と近代――西鶴と蘆花に即して」の検討〉 [略] #お知らせ# ☆ 報告が遅くなりましたが、去る6月7日の「民教連の強化・発展をめざす懇談会、シンポジウム」に、一般参加者として、M.Mik. さんに出席していただきました。 ☆ 「近・現代作家の文体――川端康成と井伏鱒二――」(「明治大学人文科学研究所紀要」第31冊1991年度)を佐藤嗣男氏が、河村清一郎氏との共同研究の形で発表されています。 ☆ すでにご存じでしょうが、アサヒグラフ別冊『井伏鱒二の世界』という雑誌が出されています。二千円なり。 ▼1992/07/26 №534 7月第一例会(7/11) Y.R. ■ A.Y.氏から、M.M.氏のダンナサマのご協力によって、法政大学新聞に載った熊谷孝先生の未公開のご論考が発掘されている旨、報告されました。そのうちに、機関誌やニュースで紹介したい、とのことです。お楽しみに。 ■ A.Y.氏はまた、 I.M.氏と一緒に、乾孝先生にお会いになり、いろいろなお話をうかがった、ということで、そのお話のなかのいくつかを紹介されました。 「文芸学への一つの反省」を書かれるときに、乾先生と、熊谷先生と、吉田正吉さんの三人が、二、三行ずつ書いては、次は君、というふうに分担された。それが岩波の「文学」に載るときに、縮められたのだが、その切り貼りした残りの原稿がきれいなままで保存されているとのことで、その復刻版を出したい、ということが一つ。 それから、パブロフの理論を熊谷先生に媒介したのは乾先生ですか、という問いに対して。 ……多分私でしょう。まだ日本で翻訳が出ていない段階で東大のソヴィエト医学研究会の翻訳を紹介しました。波多野完治さんは機械 論者でね。大久保忠利さんは、本来プラグマティストで、必ずしも弁証法的な紹介者ではないでしょう。 パブロフ自身がまた、機械論者。「水曜日」というエッセイがあって、ゴーリキィは第一信号系型で、自分は第二信号系型だ、というような発言がある。彼もそういう意味では機械論的ですね。…… 当時の民科(民主主義科学者協会)の果たした役割。民科芸術部会、民科哲学部会が果たした役割。いろいろな自然科学系、社会科学系の学者が一緒に仕事をして、その仕事のなかで自分の専門分野を見直すきっかけを得た。…… 《 I.M.氏からの媒介》 ・ パブロフは哲学的知識のない人である、と。そういう意味で放言が飛び出すことがある。その放言的な類のことを、日本的教条主義で持ち込むと、たいへんなことになる。摂取のしかたを考えないと。 ・ 優れた学者同士の学びあい方。乾氏と熊谷氏とはもっと一緒にいろいろ創っていった、というふうに思っていたが、また、結果としてはそうなのだが、実際は、それぞれが自分の場で追求していることが、共軛していく。ウーン、凡人にはまねができない。 (八月五日が楽しみになってきました。一日会員の参加を呼びかけましょう!) 〈基調報告「文学史の方法意識――印象の追跡について」の報告、検討〉 [略] #執筆活動# ○ 佐藤嗣男氏の論文。「日中戦争下の井伏文体――『へんろう宿』を中心として」(「明治大学教養論集」通巻251号、「日本文学」1992.3) ○ 『乳幼児の保育』(野呂アイ編、日本文化科学社 2500円)の10章「仲間はずれは子どもの性格によるのか」を荒川由美子さんが執筆されています。 ▼1992/09/26 №535~№537 9月総会(9/12) S.F. 1) 開会 あいさつ 福田委員長 今までも「私が文教研」といってきたが、これからは、熊谷先生を頼ることができないので、この精神を今まで以上に発揮しよう、という呼びかけがあった。 [略] ■ 研究の方向 当面、熊谷理論の再学習を中心としていく。 ① 文芸認識論――第二信号系の理論とコミュニケーション理論との再学習を進め、文芸認識論を確かめ合う。 ② 文学史――現代史としての文学史の視点に立ち、異端の文学の系譜をさぐることで、教養的中流下層階級者の文学の成立を確かめる。 ③ 文学教育――文学教育意識、母国語の奪回、読者論について。児童文学に位置づけ。読者論については、他に対する批判活動を、熊谷理論との関連で展開することも必要。 [略] ■ 第42回全国集会(統一テーマ:現代史としての文学史――創造の完結者の視点から)を見通しながらの、例会・合宿プラン [略] 提案されたプランの検討のなかで、A.Y.氏から以下のような発言があった。 ……熊谷理論における読者論を、読者論の「先駆をなすもの」と言う人もいるが、むしろ、まだそれを超えたものがないという事実を、押さえておきたい。 母国語教育の問題、異端の文学の成立過程の問題も同様である。 [略] ▼1992/09/26 №538~№540 9月第二例会(9/26) Y.H. 9月第二例会のテーマは、全国集会総括(その1)としての、『南部の人が見たも真言』(他の西鶴パートをも含む)の検討。 [略] #会員動向# 1. 佐藤嗣男さん:「週刊読書人」(1992.9.28)に、関口安義著『芥川龍之介』を書評。「市井人と作家の交点が探られている叙述、楽しい」と評価。 2. 井筒 満さん:第六回日本民教連交流研究集会(1992.10.18 一橋大学国立校舎)に出席。〈母国語教育と対話精神の創造〉というテーマで報告。 ▼1992/10/24 №541~№543 10月第一例会(10/10) K.K. 10月第一例会のテーマは、全国集会総括(その2)として、『謀叛論』を中心に蘆花のパートを深めることでした。 [略] ▼1992/11/07 №544~№547 10月第二例会(10/24) S.F. 〈活動報告〉 民教連交流集会 井筒氏が、文教研を代表して報告。標題「母国と教育の創造」。 国語分科会に参加した団体は、児言研・演教研・文教連・文教研の4団体。井筒氏の報告が、全体をリードした。熊谷先生や乾先生のいう「私の中の私たち」という内部コミュニケーションの発想が、言語観・文学観の根底に欠かせないことが、あらあためて痛感された。 会員が高齢化してきており、若い井筒氏は、その点でも注目された。 〈本日のテーマ〉 文学史の方法原理――児童文学史と成人文学史と 報告・討論[略]を通じて課題が明確になり、次のようなことが確認された。 ① 児童文学史を、文教研として考えていくうえで、基本となるのは機関紙76号の熊谷論文「〈資料〉児童観の推移と日本児童文学」である。熊谷論文は骨太に方向を示しているので、その検証も含めて考えていくべきだ。 ② 成人文学史とのかかわりで、つまり教養的中流下層階級者の視点でつめていくことが必要である。文学史「1929」や「1936」との関係をぬきにしてはならない。 ③ その点から、児童文学史の画期としての作品『杜子春』をどう位置づけるか。『杜子春』の以前と以後の問題について、近代主義の観点からアプローチできるのか。 ④ 坪田譲治と、その文学の検討も必要である。 ⑤ 当然、児童観の問題も考えなければならない。その変遷を作品との関連でとらえていく。プロレタリヤ児童文学の功罪も問題になる。 児童観の変遷では、太宰治の「人間みなおなじものではない」を、児童文学のなかでどうみたらよいのか。当然「創造の完結者としての読者」の問題もある。 ⑥ 新しい児童文学として、『牛づれ兵隊』や『空気がなくなる日』の検討、研究。 ▼1992/11/21 №547~№549 11月第一例会(11/7) T.K. 〈芥川龍之介『杜子春』の印象の追跡〉 10月第二例会の「文学史の方法原理――成人文学史と児童文学史と」を受け、芥川の児童文学『杜子春』を検討した。 [略] ▼1992/12/12 №550~№553 11月第二例会(11/21) I .H. 〈冬の合宿の日程〉〉 [略] 〈常任委員会から――冬合宿の日程について〉 ・熊谷理論の〈継承と発展〉を意識し、文芸認識論と文学教育を核にしてすすめる。 ・「文学と教育」160号【熊谷孝 人と学問】の検討は、この合宿で行う。 [略] 〈編集部から〉 ・160号の第Ⅳ部に1938年(S.13)法政大学新聞に熊谷先生が書かれた文章[「古典の現代的意義」]を入れる。M.M.さんの御夫君のご尽力によって入手できたもの。心から感謝したい。 〈事務局から〉 ・熊谷先生の、学問的なことに関する手紙などがあったら、紹介してほしい。 [略] 〈本日のテーマ〉 1) 芥川龍之介『杜子春』 残された課題について [略] 2) 芥川龍之介『羅生門』の印象の追跡 [略] ◎ 『羅生門』の検討に際して H.M. 《文教研関係の『羅生門』研究史》 [一覧表と解説 略] ・熊谷氏をはじめとする文教研の仕事は、従来、学会で取り上げられることは少なかったが、佐藤嗣男氏の『謀叛論』とのかかわりに関する研究や、関口安義氏の紹介なども一つの大きなきっかけになり、最近しだいに取り上げられるようになってきた。 《学界における『羅生門』研究の現状と課題》 ・石割透氏の発言。文教研の仕事が目に入っていない。これは『羅生門』研究の一つの現実であり平均的なものといえるのではないか。 ・関口氏の『羅生門』論。吉田精一氏や三好行雄氏らの従来のエゴイズム論=「暗い」『羅生門』を「明るい」積極的な『羅生門』論に変えていくというのが基本的立場。 ・初稿=戒律からの自己解放・反逆。決定稿=読者が創造に関わる余地をつくり、そういう意味で作品の完結性は高まった。――というように、別の軸で、初稿と決定稿を評価。倫理的是非ではなく、迷っていた下人が盗人となる下人へ、そこに可能性を感じるという。同じ「可能性」ということばを使うが、文教研でいっているものとはかなり方向が違う。これはひとり関口氏の問題ではなく、かなりそういう論は多い。 ・佐藤嗣男氏の最近の論文。改稿によって、一義的な人間観を脱した。人間の可能性・可変性をもとめるところに芸術・文学の命があるとすれば、まさにその点において芥川は芸術家として自己を確立した、ということを強く打ち出している。その辺がこれから表舞台で話題になっていくことを期待したい。 ◎ 『羅生門』の印象の追跡 [略] ▼1992/12/26 №554~№555 12月第一例会(12/12) M.M. 芥川龍之介『羅生門』の印象の追跡(続き) [略] |