| 作家コーナー ■ケストナー (Erich Kaestner 1899.2.23-1974.7.29) | |
|
ケストナー文学への言及 |
|
| |
|
…略…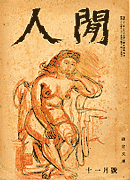 (第一次世界大戦後の)賠償問題、経済的危機の永続を、人口過剰、失業問題、精神的敗北感、生活苦、残存する軍部の勢力、国際的劣等感――こういう諸条件こそまさに「現実からの逃亡」・「現実蔑視、現実憎悪」を合言葉とする表現主義を正当化したものに他ならぬ。のみならず古い世代の内面の途への勧告と、たとえば「ドイツ民族が絶対に理解することなく、また永い間に亘っては堪えることのできぬものが二つある。議会政治を民兵システムだ。」というルーデンドルフの言葉にうかがわれるような「ドイツ民族精神」の側からの暗黙の保証は、「われわれに外的現実として与えられているものが真となるものでありえぬことはわかり切っている。現実はわれわれ によって創られねばならぬ。……世界の姿は歪曲されず汚されずに写されねばならぬ。ところでそれはただわれわれ自身の中にあるのだ。」という果敢な宣言(カジミール・エトシュミット)を可能にした。こうして感性的世界の彼岸にある領域、非現実的・超現実的な極端なもの、反合理的なもの、神秘的・異国的・魔力的世界が追求された。ベルグソンの直観哲学、フッサールの現象学的本質直観、クラーゲスの性格学、フロイトの無意識世界・意識下世界への分析下降、構造心理学等が表現主義の学問的根柢となる。現実の「現実」は顧みるに足らぬ。より現実的な「現実」の把握こそ新しい課題であった。それは、物理学において新しい物質の単位・エレクトロンやイオンが考えられたのと隠秘な関連を保っているように思われる。こういう個人中心的パースペクチーヴにつれて、社会的なパースペクチーヴも変転する。普遍妥当的な人間愛や正義感が、盗賊や売笑婦の頭上にも永遠に人間的なるものの聖光を輝かしめる。すべてを魂の中から取ってくる「おお、人間よ」(。)文学としての、怒号と陶酔の表現主義文学は、まさしくラーテナウの人生哲学の文学的等価物であった。 ところが既に一九二〇年頃、早くも表現主義文学陣営内に、表現主義の稀薄な空気を厭う声が生まれる。「混沌を! 血のしたたる心臓を! 魂の歌声、轟々たる情感の叫びよ、響きわたれ!」と叫んだ同じパウル・コンフェルトは、ほとんど謙遜にこう要求し始める。「戦争、革命、世界救済はもう真平だ。謙遜にしていよう、そして、別の、小さな事物に献身しよう。……少しばかり遊び、眺め、もしできたら少しばかり笑ったり、ほほえんだりしようではないか!」同じくかつての表現主義者ヴェルフェルは表現主義を欧州のペストと罵り始める。現実よりの逃亡は、人間から肉体的なものを締め出そうとした。しかも肉体と現実の悲惨は依然として眼前にあるではないか。むしろ肉体を精神の領国の中に組み入れるべきではあるまいか。むしろ現実を素直に見つめるべきではないか。こうしてブレヒト、ブロンネン・レーフィッシュ等によって、「意識的に非感傷的に、可能性の限界まで進んでただ事実のみを捉える」新即物主義の運動が起った。「現実の事物をはっきりつかめ! 理想を捨てろ! 事実に把みかかれ!」(ケンター)「あてどもなく相対主義と懐疑主義の叢の中をさまよって自己を見失いはすまいかと懼れるのをやめよう。知識と能力の一切の流れを解放したのちに、われわれは動揺の精神体系の中に生きている。今こそ結晶の体系を求めるのだ。……法則と訓練とへの意志のみがこの世界過渡期を通してわれわれを担ってくれるのだ。……もはや感傷的であることをやめよう。……世界をはっきりと見つめて、われわれの探りえぬ死や彼岸の世界にたいしては無関心でいよう。しかし生への愛と、文化への意志を捨ててはならぬ。」(オイゲン・ディーゼル)「芸術家は学者と同じように客観的でなければならぬ。」(H.J.ヴィレ) 一九三〇年に出版されたキンダーマンの「現代文学概観」は、要約の関係上、上に引用した文章の中に隠見する全く新しい一つのモメントを、表現主義への反措定としての写実主義的モメントと併せて「新即物主義」の範疇に入れ、時代傾向的と超時代的という二様の概念でその差異を説明しようとしている。彼は前者にブレヒト、リンゲルナッツ、パンター、ケストナー、ブロンネン、レン、ルマルク、グレーザー、グリム等を数え、後者にホイシェレ、メル、ツックマイヤー、ルート・シャウマン、ビリンガー、ハウスマン、ヘッセ、ビンディング、カロッサ、グリーゼ等を数えている。しかしながら後の範疇に属する詩人たちは、表現主義へのアンティテーゼとしての新即物主義とは見なしがたく、むしろブロックドルフ=ランツァウや「渡り鳥」運動の中に生きのびてきたドイツ浪曼主義や神秘主義の代表者として見られねばならぬであろう。それらの詩人の内部には「民族精神」とのきわめて複雑な反発と牽引との関係が存している。しかし前者の把握した即物的世界はどのようなものであったか。 ――世間の男たちはみんな一定の職業を持って出世をし、結婚して子供をこしらえ、それが人生の目的だと信じている。それなのにこの男は自分の自由意志からとはいいながら、ひとり垣根の外に立って、じっと眺めて、月給を貰うたびに絶望している。ヨーロッパは今大きな休暇に入った。教師は去ってしまった。時間表は消されてしまった。古い大陸は教室の目的を果さなくなってしまった。如何なる目的をも果さなくなってしまった。――こういう目的喪失の意識。 ――自分を支配人の位置につけてくれて、百万ドルもらい、気に入った女房の世話もしてもらう、この三つが一緒になったところで、そんなものは何にもならぬという、「みんな実に無意味だ」という意識。 理性と権力とは決して相会うことはあるまい。今日の状態で人類に残された途は、自分の運命に満足せず境遇を改善するために互に殴り合って殺しっこするか、あるいは逆に自己と世間とに満足して退屈のあまりに自殺するかであって、人間が豚にすぎぬかぎり、どんなに完全な社会組織をもってみたところでなんのたしにもならぬという絶望感。 これがエーリヒ・ケストナーの「ファビアン」の精神風景であるが、しかしファビアンはなんといおうと生きている以上はあるプラスに支えられている。「楽天家は絶望するでしょうよ。しかし僕みたいな厭世家は平気なんです。僕には功名心ってものがないんですからね。僕はむしろじっと眺めて待っているんです。」(たとえば「深尾正治の手記」の作者(椎名麟三) などと不思議に符合するものがここにはありはしないか。「ファビアン」は一九三二年(ママ)の作品である。)ファビアンは予感を嫌う。「ベッドの掛け蒲団をそっとまくって見るように、未来を覗き見する」習慣を嫌う。それを卑しいことだと考える。彼は運命に堪える。これは謙虚な傲慢ともいえるような、神経的で、しかも勁い態度である。事実、生きているかぎりは、このプラスがなければならない。ところがファビアンは死ぬのである。その友ラブーデのように現実との対決に破れて自殺するのではない。生れ故郷の町に帰って、橋から河中に子供の墜ちたのを見て、救けようとファビアンは身を躍らせる。幸い子供は泣きながらも泳いで岸にはいあがった。しかし泳ぎを知らぬファビアンは溺死した。文学史家が新即物主義(ノイエ・ザハリヒカイト この合言葉は本来は絵画の新しい傾向をいいあらわすために考えられたものである)と呼んでいるところの潮流は、こういうケストナーの線を、彼よりもリルケ的に深いカフカなどに延長した部分にあるといえる。カフカも、橋から河中に飛び入って自殺する若い男の短い物語を書いている。男は、たとえば自然主義のシュニッツラーの動機ずけに見られるような意味での明白な動因をもって身を躍らせるのではない。男は家をとびだし、家の傍の橋へ行き、欄干から河に飛びこむが、これらの動作の関連は普通のマクロスコピックな因果関係をもたぬ。この三つの動作はいわばばらばらに捉えられている。しかもその各々の意味が、自然主義的な因果関係などにおけるよりも遥かに明確に、むきだしにされているように受けとられる。なぜ河に飛びこむかではなく、河に飛びこむことの意味が不思議にわれわれの眼前にぽかりと浮びあがってくる。いわばマイクロスコピックな意味関連ないしは因果関係がカフカの筆に捉えられようとするのである。このような世界が幾多の地下の水路を流れて三三年の革命に結晶した運動と無関係でしかないことはいうまでもあるまい。しかしまたその意味においてこそファシズムと関係を結んでいるのである。しかもファシズムは滑稽にもこの「無関心」にたいして感謝する代りに追放をもって応えた。 キンダーマンの小冊子より一年前に刊行されたパウル・フェヒターの「現代ドイツ文学」(一九二九年)は、当時のドイツ文学の特長として、新旧両勢力の併存・対立、文芸作品の生産過剰、文学芸術愛好の大衆化、戦後世代が指導者と見なされるべき人々をもっていなかった事実、作家と読者との平均化、両者の疲労、殊に小説の分野における徹底的なパーティキュラリズム・個人主義・私小説的潮流等を挙げているが、これまでに見てきたような数々の点を考えてみると、第二次大戦後の日本の現状は、あたかも第一次大戦後のドイツの諸事情のくり返しであるかのように思われぬこともない。しかしそれはあくまで酷似にすぎないであろう。第一次大戦後のドイツがたどった途から幾くつの(ママ)厳しい示唆を見出す今日のわれわれの判断と努力が、それを証明するに違いなかろう。グーチがその「ドイツ」の最後に書いている言葉、「こうしてドイツの将来はヨーロッパの運命と離れがたく結びついており、勝者と敗者との運命は、それによって支配者と諸国民とがわれわれの共通の文化の真の諸関心を認識し評価するであろうところの知見に依存しているのである。」は、今日のわれわれに何か特に切実な 響きを伝えているように思われてならぬ。 |
|
| (筆者は北大教授・独文学) |
|
|
|
|