| 四つの文学論 熊谷 孝 |
| 岩波書店刊「文学」第十九巻第四号(1951年4月号)掲載----- |
|
|
一 「文芸学は可能か」の問題 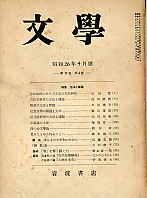 加藤周一著『文学とは何か』(角川新書、五〇年八月刊) 福田恒存著『芸術とはなにか』(要選書、五〇年六月刊) 桑原武夫著『文学入門』(岩波新書、五〇年五月刊) 中野重治『文学論』(ナウカ講座、四九年一二月刊) 与えられた課題は、現在、文芸学が採っている方法(ないし文学研究の方法)の盲点を突きとめるための、右の四つの文学論の方法の吟味ということだが、課題の趣旨からいって、とくに問題を孕(はら)んでいると思われるのは、加藤の『文学とは何か』と、福田の『芸術となにか』とである。 というのは、(一)それぞれ別の視点、別の角度からではあるが、この二つのエセイが、始発点にさかのぼって、文芸学は可能かという問題(或いは、芸術の研究に科学の方法が適用され得るかという問題)を吟味しなおしたものであるからだし、また、(二)そうした吟味の結果が、文芸学の否定に(加藤の場合)、さらに一歩突き入って科学そのものの否定にまで至っている(福田の場合)という点に、並々ならぬこんにち的な意義が看取されるからである。 さらにまた、(三)文学というものの性格からいって、それの本質は客観的方法によっては捉えようのないものだと福田も言い、加藤もけっきょくそう言うのだが、そういう文学の性質というものが、客観的方法以外のいったいどういう方法によって突きとめられたものであるのか、という点が興味であるし、また、(四)そうした科学的方法の適用を拒む論拠としてそこに挙げられている、いくつかの事がら(たとえば、文学の内面的規定としての「美」や「才能」「文学的体験」の特殊性 etc)は、文芸学者たちのあいだでも、ほんとうには吟味し尽されていない問題であるだけに、むしろ、これら著者たちの解決に期待するところが大きいからである。――等々を含めたいくつかの理由からして、この稿では、加藤・福田の論旨を軸として、そらにその交差する箇所で桑原・中野の労作に言及したい、と考えている。 が、そのまえに、福田・加藤の評論が、いわば文学的知識人ともいうべき人たちを相手の問題の提起であるのに対して、中野の「文学論」は、産別その他おもに組織労働者の人たちに向けて語られたものであり、また、桑原の『文学入門』も、学生、教師、労働組合の人々を相手に、「お互に社会人として」問題を考えようとして書かれたものである(はしがき)ことを言い添えておかなくてはなるまい。誰を相手に書くかということは、けっきょく、誰の立場――どういう立場に身を置いて問題を考えるか、ということであるのだから。そういう相手の選びが、それを書く人の思考の道筋に制約(方向づけ)を与えないはずはないのだから。それはアクセントの置きどころの違いということもあるが、しかしそれだけにとどまるのではない。 二 文学論の起点 なるほど、たとえば、「いい小説だけれども、あれは学者の生活を書いたんだから、労働者の生活を書いたものにくらべれば値打ちが低いのだとかいうふうな、そういうせまい考え方」に落ち込んではいけない、という中野の言葉(二八ページ)には、労組の人たちを目の前にしての幾分のアクセントがあるかも知れない。また、たとえば、その反対に、こんにちの日本の現実から問題をさぐろうとする作家は、当然、組織労働者を描かなくてはならぬはずだ、という加藤の言葉(一二八ページ)にも、むしろ、語ろうとする相手が小市民的知識人であるところからくる、或る種のアクセンチュエーションが考えられなくてはならぬのかも知れない。だが、けっしてそれだけではない。 中野について言えば、『新日本文学』の誌上座談会あたりで「進歩的」知識人を相手に談論風発している時のかれなどより、労働者あいてに語っているこの中野のほうが、ずっと階級的立場にも徹しており、意見も建設的で具体的であるということだ。さっきのあの「せまい考え方」というのも、労働者独善のせまい考え方というふうな意味ではなくて、それこそまさに小市民的な考え方のせまさであることを指摘して、それがインテリを描いたものであろうと、戦争未亡人の生活に取材したものであろうと、およそ「平和のために、あるいは今日の生活の苦しさからのがれ出ようとしてもがいているものであるかぎり、……援護するという立場で、その欠点やまちがいをも正していく、という方式をわれわれはとらなければならない。」(三一ページ)と述べている。そういう方式によらない限り、民衆の自由と平和のためのたたかいを徹底的に支持するという労働者階級の歴史的任務は遂行され得ない(三〇ページ)、というのだ。 労働者階級のそういう現実的な文学の創造・育成という立場から、「われわれとしては、文学というものを、まずもってひろい意味で考える必要がある」ことを述べている最初の一章は、とくに光っている。中野は、そこのところで、「ひろい意味での人間の表現の仕方の一つとして、文学があるのであって、自分を表現するには、言葉、文字を使うやり方としては、新聞記事もあれば法律の条文もあるのですから、そういうものすべてをひっくるめて文学というものは考えられ、そのなかでそこから専門的なものとして出来てきたものをせまい意味での文学というという、ことになるでしょう。」といい、詩や小説が「それ一つでポツンとあったのでもあるものでも」ないこと、「こういう関係は、歴史的にもそうであり、個人の立場の場合にもそう」であると語っているが、すべての文学論は、ここを起点として始められるべきだ。人間の生活のいとなみの一つとして(また人間の生活のために)文学があるのでなくて、文学のために人間があるというような、まるでそれ一つがポツンとあるみたいな文学論の横行しているさい(次章参照)、中野のこの指摘にはふかい意味がある。 だが、たとえば、ヘタでたくみでないが人を感動させるというようなのが「文学としてはほんとうに値打ちのある文学だ」(一五ページ)といった式の粗雑な言い方はヤメたほうがいい。「よい本とは、初めからしまいまですべて正しい本という意味ではなく、多少の錯覚があっても、正しいところはひどく正しい、という本のことである。」(「文学入門」)という桑原の整理された表現に学ぶべきだろう。 三 実存的孤独 ところで、組織労働者を描けと説いている加藤のほうは、中野とは反対に、むしろ階級的な文学観や人間観を否定する立場から、そのことを提唱している。  加藤の考えでは、小説は必ずしも人間を社会的な相のもとに描く必要はないのであって、社会的に孤独な、もしくは「社会的身分や歴史的条件に本来かゝはりない人間の孤独(非社会的な孤独=絶対的孤独)を追求」することで、かえって日本社会の後進性を超越することもできる(一一五,一三五ページ)、というのだ。「人間性の変らざる部分に対する信頼と黙示録的現実の体験」の必要がそこに説かれ(一三三ページ)、さらに、ついで、「もしわれわれが自己の内部へ深く降りてゆくことによって一般に人間的なものを探りあてれば、……小説に如何なる社会を背景として用ひようと普遍的な文学をつくることができるはず」だ(一三五-六ページ)、という願望がそこに語られている。 加藤の考えでは、小説は必ずしも人間を社会的な相のもとに描く必要はないのであって、社会的に孤独な、もしくは「社会的身分や歴史的条件に本来かゝはりない人間の孤独(非社会的な孤独=絶対的孤独)を追求」することで、かえって日本社会の後進性を超越することもできる(一一五,一三五ページ)、というのだ。「人間性の変らざる部分に対する信頼と黙示録的現実の体験」の必要がそこに説かれ(一三三ページ)、さらに、ついで、「もしわれわれが自己の内部へ深く降りてゆくことによって一般に人間的なものを探りあてれば、……小説に如何なる社会を背景として用ひようと普遍的な文学をつくることができるはず」だ(一三五-六ページ)、という願望がそこに語られている。じつにハッキリしているではないか。組織労働者を描くということも、それは、個人としての組織労働者の意識に内在する、超階級的・普遍的人間を主人公とするということなのであって、社会的人間としての現実の労働者は、そういう内在的人間(普遍的人間)をキワ立たせるための「背景」にすぎない、というのだ。(そこに描かれるものは、つまり骨抜きにされた組織労働者だ。)だから、描く相手はなにも組織労働者に限るわけのものではないのだが、なるべくならニュー・ルックでいこう、というわけなのだろう。「孤独な精神の構造に(社会的孤独と非社会的孤独との)二面があるとしても、……一面だけ現れる場合は少い。リルケの孤独(非社会的孤独)も純粋に絶対的なものでは」なかった、と加藤がいっているのは、語るに落ちた感じだ。ともかく、人間――現実の生活をいとなむ社会的人間のよりよき生活のために文学があるのではなくて、逆に、普遍的な文学の創造と栄誉のためにのみ人間が存在理由を持つ、ということになるのだ。人間のレーゾン・デートルは、然(しか)り而(しこ)うして、歴史的時間を超えた「永遠なるもの」に合致する実存的孤独(絶対的孤独)においてのみ保障される(一三五ページ)、というのである。 こうして、加藤にとっては、「世代の交替する社会の、無数の人間の一人としての自己が問題なのではなく、ただ一人の、一回的な存在としての自己が問題である」のだが(一三四ページ)、かれが文学的体験を「一般化されない一回的なもの」として客観的方法の適用を拒むのも、つまりはこうした立場からであるし、『明暗』を孤独の文学として手放しでホメちぎっているようなのも(一三四ページ)、やはりまたこの立場においてである。 四 あぐらをかいたニヒリズム(?) 福田は、加藤のように、「人間性の変らざる部分に対する信頼」というようなことを、直接口に出して言ってはいない。けれど、さかんにベルグソンの口移しみたいなことを言ってみたり、また、生哲学ふうの概念を援用して万事(?)生哲学流に問題を処理しようとかかったり、またたとえば、「古典がつねに新しいゆえんは、それが人間性の本質に通じたカタルシスの効用をもっているから」だ(一四一ページ)、と語っているような点からも、福田もやはり、普遍人間的なものへの信頼感にもたれかかってものを言っていることは明らかだ。 福田によると、現代こそ呪術の時代であるというのだ。ジャーナリズムとう「呪術的秘儀の場所」において、「右から、左から、中立の立場から、呪文の放射線」が交錯している(二一-二五ページ)。つまり、現代においては、何もかもが呪文である。それで、「われわれは正しい認識をもって現実に処するにしくはない」のだが、正しい認識だの正しい実践なんてものは、むろんあるはずがない(一〇五ページ)、というのだ。科学もまた、呪文の一つにすぎない。 科学が「観察し実験し検証し説明し組織しうるものは、つねに過去である」にすぎぬ。「この過去から経験主義 的に帰納しえた方法によってのみ 未来をとらへよう」(圏点=太字斜体 筆者)とする科学は、しかし「人間精神のいとなみを、その全領域にわたってうしろむきにして」しまっただけである(一〇四ページ)。 ところで、芸術は――芸術は「演戯」なのだ。「演戯といふのは、自分で自分を位置づけること」である(三八ページ)。つまり、いっさいが呪文と化してしまった現代にあっては、演戯することによってだけしか、人間は生きがいを感じることができないし、また、自由を自分のものにすることも出来ない。「人間の自由とは、演戯の自由のほかのなにものも意味しません。」(四四ページ)芸術だけが救いだ、という声が、どこからか聞えて来そうである。 芸術だけが救いだ、――そう思うのは当人の自由だ。それもいいだろう。だが、救いである芸術は、福田の言うとおり、自分で自分を位置づけする以外に成り立ちようがないのだ。一切を否定することで自分自身をも否定してしまった人間に、いったいどう自分を位置づけすることができるというのか。「人間は――個人は――つねにまちがひを犯す存在であります。」(一〇五ページ)なぞと居直ってみたところで、それはそれだけの話で、問題の解決になりはしない。 福田は、また、「芸術とはなにかを知ろうとすれば、芸術作品につく」ことだ、と言っているが(一八八ページ)、芸術作品につく――芸術作品を享受するということは、享受者自身、作者(演戯者)といっしょに演戯する(自分を位置づける)ということだろう。そのことによって、当然、享受者は、自分自身に対する自分のこれまでの位置づけ方を改めることになるのだろう。それは、新しい体験(準体験)によって精神の内容が変るということである。ところが、福田にしたがえば、「医者は病気をなほすのが目的であって、その肉体がなにに使用されるかは、問題にしないやうに」芸術によって人間はその精神を強壮にするだけだ、というのである(一六〇ページ)。「精神は変る必要もなければ、変ることもできない。」(同)それを、病気をなおすこともしないで、「病躯をひっさげて投票場へ駆けつけること」を説くような医者が今は多くて困る(一六一ページ)、というのが福田の言い分である。福田の言おうとするところも、ここまで来れば歴然である。 真意が明らかになったところでダメを押しておくと、芸術は精神を強壮にするだけだというのはウソだ、ということだ。いや、精神が強壮になるということは、それの内容が変る――位置づけが変るというのと一つことである。それを変らないといって、妙なリキみ方をするのは、人間の精神が変化するものだということになっては、例の普遍人間性への信頼感にヒビが入って不都合だからだろう。ともかく、「芸術はカタルシスであり、カタルシスの本質はくりかえしにある。」(一四五ページ)なぞとヤニ下(さが)ってみたって、それで問題が解決されたことにはならないのだ。 問題は、それから、科学についての福田の考え方だ。 五 現代非合理主義 福田の言うように、科学が人間精神のいとなみをうしろむきにしているかどうかは大方の判断に待つとして、それが「経験主義 的に帰納しえた方法によってのみ 未来をとらへよう」とするものだというのは受け取れない。科学の方法は経験的ではあっても、経験主義 的でなんかけっしてないからだ。(科学史の過去の一コマを捉えて、だから科学というものは……というのはナンセンスだ。) 同様のことは加藤の場合についても言えるのであって、「文学史を作る人の、『文学とは何であるか』が、『文学とは何であったか』を決定する」はずであるのに、文芸学では「文学とは何であったかといふことから……文学とは何であるかを定め」ようとしている、これはおかしい(一二ページ)、という加藤の言葉は、素朴実在論的な客観主義の文芸学――それは、むろん文芸学の昨日の姿だ――に対する批判としては当っているところもあるのだ。が、問題は、いま、この客観主義ないし経験主義の否定ということが、加藤や福田の場合、客観的方法・経験的方法そのものの否定にまで突き抜けてしまっているという点にある。 ところで、また、科学は現象の解説者・説明役としては有能だが、「生そのもの」「芸術そのもの」については全く発言権を持たない、と福田は言うのだが(一七三ページ)、この考え方の底にあるものは、「生は生によってしか理解され得ない」という、生哲学流のあの問題の立て方であろう。そして、それは、生の自己同一性・超時間性ということを前提としている限りにおいて、文学的体験の一回性による科学的方法の適用拒否という、加藤のあの考え方につながるものを持っていることが知られよう。 それで、けっきょく、過去の或る時期において、新カント派や生哲学の一派が、機械論(客観主義)の盲点をさぐり当てることで、客観的方法(科学)そのものの限界をきわめ得たかのようなウヌボレを持ったのと同じように、いやそれをさらに下回って(というのは二番煎じだから)、客観主義をたてまえとするのが科学の立場だ、とひとりぎめにきめ込んで、いまさらのように機械論のアナを眺め回してアゴを撫でているのが、福田であり加藤であるということになろう。 六 「美」とインタレスト そこでまた、福田や加藤が、不易の美にささえられた芸術の永遠性への感激を口にしている根拠が、生の自己同一――普遍人間性への信頼にあることは繰り返すまでもあるまいが、しかし不易の美云々というのは具体的にはどういうことなのか。 加藤によると、何が美しいかということは時とところによって違っても、「美しい」という言葉は、いつどこの国においても用いられている、それは「何を美しく感じるかはちがっても、美しく感じるという人間の精神のはたらきには共通のものがある」からだし、またそれだからこそ、「美しさのなかには時やところを超えて変らないものがある」のだ(三六-三七ページ)、というのである。これは、ひどい。 なるほど、美という「言葉」は一つかも知れない。けれど、この言葉がコンミュニケート(伝達)する実質的な内容は、必らずしも一つではない。造形美術の歴史にかえりみれば明らかなように、いわばそれを荘厳とか宏大というふうに感じた気持(或いはそう感ずる精神のはたらき)を、「美しい」という言葉であらわしていたような時代もあったわけだ。また、たとえば、有閑的で装飾的なものに対してしか美を感ずることの出来ないような精神のはたらきと、実用的なものほど美しいと感ずる気持(精神のはたらき)とを、加藤のように、共通だ、一つものだといって、あっさり片付けてしまうことが出来るだろうか。 美という言葉は、こんなふうに規定性の乏しい、ひじょうにあいまいな言葉だ。だから、桑原が、「  美という言葉を持ち込むことは一方的解釈におち入るおそれがあり、むしろ避けた方がよい」として、インタレストという言葉(概念)により文学を説明しようとしている(一二-一三ページ)のは賢明である。「インタレストは『興味』であると同時に『関心』であり、さらに『利害感』でさえあって、それは行動そのものでは決してないが、何ものかに働きかけようとする心の動きであって、必然的に行動をはらんでいる。……人生を表現した文学に面白さを感じるということは、そこに人生的なインタレストをもつことではなかろうか? もし文学に心ひかれるということが、人生に対してインタレストを失い、人生から逃避することであるならば、どうして文学が人生に必要などということができよう。」と桑原は語っている。また、「おのおのの文学者は、自己の作品創作という苦悩にみちた経験によってようやく到達した、彼独自の諸インタレストの調整の仕方 を示すのであって、そのことによって彼は、人生いかに生くべきかという問いに、彼としての答えを出しているのである。」(圏点筆者、五七-五八ページ)とも語っている。こうして、いわば文学の内面規定であるインタレストが「利害感」でさえあり、行動を孕んだものであり、文学者の体験が諸インタレストの調整において成り立つものであることが具体的に明らかにされた場合、加藤の、文学的体験と日常的体験および科学的体験との形式的な区別(分類)や、福田のあのカタルシスがいかに無内容なものであるかがバクロされて来るのである。 美という言葉を持ち込むことは一方的解釈におち入るおそれがあり、むしろ避けた方がよい」として、インタレストという言葉(概念)により文学を説明しようとしている(一二-一三ページ)のは賢明である。「インタレストは『興味』であると同時に『関心』であり、さらに『利害感』でさえあって、それは行動そのものでは決してないが、何ものかに働きかけようとする心の動きであって、必然的に行動をはらんでいる。……人生を表現した文学に面白さを感じるということは、そこに人生的なインタレストをもつことではなかろうか? もし文学に心ひかれるということが、人生に対してインタレストを失い、人生から逃避することであるならば、どうして文学が人生に必要などということができよう。」と桑原は語っている。また、「おのおのの文学者は、自己の作品創作という苦悩にみちた経験によってようやく到達した、彼独自の諸インタレストの調整の仕方 を示すのであって、そのことによって彼は、人生いかに生くべきかという問いに、彼としての答えを出しているのである。」(圏点筆者、五七-五八ページ)とも語っている。こうして、いわば文学の内面規定であるインタレストが「利害感」でさえあり、行動を孕んだものであり、文学者の体験が諸インタレストの調整において成り立つものであることが具体的に明らかにされた場合、加藤の、文学的体験と日常的体験および科学的体験との形式的な区別(分類)や、福田のあのカタルシスがいかに無内容なものであるかがバクロされて来るのである。触れなければならなぬ問題は、なお数多くある。たとえば、文学の創作には才能(あるいは素質)が必要だという当然の指摘が、しかし桑原の場合、その実質的な内容についての説明を欠いているため、旧い観念論美学の天才論から一歩も出ていないものになってしまっており、また、福田の場合、「才能とは精神と技術との出あう場所」だというようなことでお茶を濁しているにすぎない、といった点である。また、たとえば、ジャンルの問題・言語法の問題その他についての加藤への質疑などである。一二具体例を挙げると、――「世界を、言葉を通して眺め」るのが散文で、「言葉を媒介とせずに(世界を)感じ、その感じと等価値的な言葉を探」すのが詩である(七四-七五ページ)、というような、常識をひとひねり捻ったにすぎない問題の解決(つまり問題の放棄)や、詩精神の枯渇から生まれてくる中世日本の「本歌取り」の形式を、反対に詩精神の躍動の結果とする非歴史的な理解や、また、「風の上に星のひかりはさえながらわざともふらぬ霰をぞ聞く」という藤原定家の詠歌を、「移りゆく時を超えて、われわれの前におかれてゐる」詩であるといい、「それが詩といふもの、大理石のやうにかたく、動かしがたい作品」だといっているような主観的な、あまりに主観的な古典の把握(八六-九一ページ)等々々。さらに、これは福田とも共通した映画芸術にたいするプリミティヴな理解の仕方であるが、映画の表現というものを、ぶっつけに(つまり無前提に)事物のリアルな客観的な再現である、ときめ込んでいるような点、たんに説明不足からくるアナとだけはいえないものがある。(それで、加藤の場合、芸術として見て、映画のほうが文学よりも格が落ちるという口ぶりだし、福田に至っては、「映画は芸術ではありません。」と言いきるのだから、ひどいものだ。「あとがき」でいっているように、福田は、「日ごろぼくはよく反語的」なものいいをし、「ぜんぜん反対のことを平気で放言する」のだそうで、「そんなことからなにかと誤解されることもある」そうだが、ぼくのこの理解も「誤解」の部類に入るのだろうか? ともかく、あとで弁解しなくてはならないような放言ならヤメたほうがいいし、反語で呟くほか手がないような深刻なことを言っているのでもないのに、思わせぶりな言い回しをすることは、この批評家のためにも採らないところである。) |
|
|