| 丂丂 | |||
| 丂丂擣幆偵偍偗傞庡娤惈偲媞娤惈丂丂丂丂丂愳惣丂堦 乮孎扟岶偺昅柤偲悇掕偝傟傞乯 | |||
| 丂丂丂 | |||
| 乮惓丂侾乣係復乯丂桞暔榑尋媶夛敪峴乽桞暔榑尋媶乿俆俁 (1937.3乯宖嵹丂 ---丂乮懕丂俆乣俇復乯丂桞暔榑尋媶夛敪峴乽桞暔榑尋媶乿俆係 (1937.4乯宖嵹丂 |
|||
|
|
|||
| 仏娍帤偼尨懃偲偟偰怴帤懱傪巊梡偟偨丅 仏壖柤尛偄偼怴壖柤尛偄偵嫆偭偨丅仏朤揰偺晹暘偼懢帤丒僀僞儕僢僋懱偵懼偊偨丅 仏柧傜偐偵岆怉偲敾抐偱偒傞傕偺偼掶惓偟偨丅仏擄撉岅嬪乮暥帤乯偵偼揔媂丄撉傒壖柤傪揧偊偨丅 仏榑暥枛旜偺乽晅婰乿偱掶惓偑巜帵偝傟偰偄傞晹暘偵偮偄偰偼丄掶惓屻偺杮暥傪傕帵偟偨丅俁復偍傛傃係復偺壓慄晹乮仸嘆乣仸嘍乯偑偦傟偱偁傞丅 |
|||
|
|
|||
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂侾 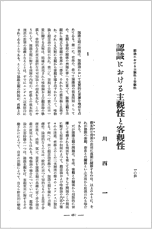 丂丂擣幆庡娤偺栤戣偼丄擣幆榑偵偍偄偰杮幙揑偵廳梫側抧埵傪愯傔偰偄傞丅戞堦偵丄揘妛偺丄廬偭偰擣幆榑偺崻杮栤戣偲偟偰偺丄庡娤偲媞娤偺娭學偺栤戣偵摎偊傞偵摉偭偰丄擣幆庡娤傪庡娤偐傜撈棫側媞娤偺悽奅偺堦晹暘丄偦傟偐傜偺攈惗暔偲尒橍乮側乯偡偐丄偦傟偲傕斀懳偵庡娤偐傜媞娤傪摫偒弌偡偐偵傛偭偰丄桞暔榑偲娤擮榑偺嵎暿偑惗傟丄戞擇偵丄媞娤偲庡娤偺堦抳枖偼晄堦抳偵娭偡傞尒夝偼丄柧妋偵昞尰偝傟偨桞暔榑偍傛傃娤擮榑偺偺妛攈偲丄拞娫揑側愜拸庡媊揑側晄壜抦榑偲偺憡堘傪惗傓丅偙偺傛偆偵偟偰丄擣幆庡娤偵懳偡傞棟夝偺撪梕偑丄揘妛忋偺崻杮揑側棳攈偺嵎暿偺婎慴偲側傞偙偲偼丄偡偱偵僄儞僎儖僗埲棃柧敀偵偝傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偲偙傠偱擣幆庡娤偺栤戣偑丄揘妛忋偺崻杮揑側棳攈 偺嵎暿偵捈愙偵娭楢偡傞偺偼丄埲忋偺傛偆偵丄偦傟偑擣幆偺媞娤丄懚嵼偲偺娭學偲偄偆曽柺偐傜庢埖傢傟傞応崌偱偁傞丅 丂偩偑擣幆庡娤偺栤戣偼丄側偍丄媞娤偲偺娭學偐傜憡懳揑偵愗棧偟偰峫嶡偝傟傞懁柺傪傕桳偟偰偄傞丅偦偟偰栤戣偺偙偺懁柺偵懳偡傞夝摎偺擛壗偵傛偭偰丄娤擮榑媦傃桞暔榑偺撪晹偺 庬乆偺彫棳攈丄揘妛忋偺偙偺擇戝挭棳偺庬乆偺僯儏傾儞僗偑敪惗偡傞丅椺偊偽丄摨偠娤擮榑揘妛偱傕丄擣幆庡娤傪桪傟偰巚堃丄棟惈丄榑棟揑側傕偺枖偼堦斒揑偵塢偭偰抦揑側傕偺偲尒橍乮側乯偡崌棟庡媊偲丄姶忣丄婥暘丄堄梸傪擣幆庡娤偺婎慴偵抲偔旕崌棟庡媊偺嬫暿偑偁傜傢傟傞丅桞暔榑偺応崌偵偮偄偰偄偊偽丄媽桞暔榑偺庡梫摿挜偺堦偮偼丄擣幆庡娤傪偽丄媞娤悽奅偵懳偡傞偦偺摥偒偐偗偵傛偭偰丄帺恎偺妶摦偵傛偭偰丄帺傜傪楌巎揑偵曄壔偣偟傔傞傕偺偲偟偰攃埇偟側偐偭偨偙偲偱偁傝丄偙偺揰偱偦傟偼曎徹朄揑桞暔榑偺擣幆榑偐傜崻杮揑偵嬫暿偝傟傞丅媽桞暔榑偼懳徾傪捈娤偺宍幃偵偍偄偰攃埇偡傞偩偗偱丄偦傟傪庡娤偵傛偭偰曄壔偣偟傔傜傟傞傕偺偲偟偰懆偊側偐偭偨偲偄偆偙偲偼丄媽桞暔榑偑庡娤傪乽懳徾揑妶摦乿偲偟偰懆偊側偐偭偨偲偄偆帠幚偺敿柺偵奜側傜側偄丅 丂偲偙傠偱壛摗惓巵偺応崌偺擛偔丄媞娤悽奅傪曄壔偝偣傞恖娫亖庡娤乮巵偺偄傢備傞乽庡懱乿乯偺堄媊傪擣傔側偑傜傕丄偙偺乽庡懱乿傪擣幆庡娤乮巵偺偄傢備傞乽庡娤乿乯偐傜婡夿揑偵愗棧偟丄曎徹朄揑桞暔榑偵偍偄偰偼擣幆偼乽庡懱惈偺婯掕乿傪娷傑偢丄愱乮傕偭傁乯傜乽庡娤乿偺乽弮悎巚堃乿偵傛偭偰妉摼偝傟偨帺慠偺婯掕偱偁傞偲偡傞尒夝傕丄棟榑偲幚慔偺暘棧偺尒抧丄媽桞暔榑偺捈娤揑乮娤徠揑乯尒抧傪丄扐偟愻楙偝傟偨宍懺偵偍偄偰丄戙昞偟偰偄傞傕偺偩偲塢偆偙偲偑偱偒傞丅壛摗巵偺尒夝偼丄尰戙桞暔榑偺擣幆榑偺崻杮柦戣偺堦偮乗乗庡娤揑峔惉偱側偔偰丄帺慠偺斀塮偲偟偰偺擣幆偵娭偡傞乗乗偵埶嫆偟丄偙傟傪堦柺揑偵揥奐偡傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺傕偆堦偮偺崻杮柦戣乗乗幚慔偵傛傞棟榑偺旐婯掕惈偵娭偡傞乗乗傪榗嬋偟丄寢嬊偵偍偄偰斲掕偡傞偲偄偆棫応傪埲偭偰堦娧偟偰偄傞丅庡娤庡媊揑側暉杮僀僘儉傗嶰栘揘妛偵懳偡傞懳峈暔偲偟偰婲偭偨壛摗巵偺偙偺尒夝偼丄扨偵庡娤庡媊偲偼媡側拪徾揑媞娤庡媊偺岆昑傪揟宆揑偵戙昞偟偰偄傞偽偐傝偱側偔丄摿偵尰嵼偵偍偄偰偼丄幚慔偐傜梀棧偟偰偄傞屷乆偺揘妛揑尋媶偵丄棟榑揑丄擣幆榑揑婎慴偯偗傪梌偊偰偄傞揰偱丄屷乆偑帺暘帺恎偺娮偭偰偄傞偐偐傞梀棧乗乗偦傟偼埆偟偒幚慔傊偺曭巇枖偼偦傟偲偺峈憟偺曻婞偩偑乗乗傪僲儖儅儖乵惓忢乶側傕偺丄揘妛偺慜恑偺偨傔偺尨懃揑偵 惓偟偄搑丄偲偟偰岞尵偟摼側偄尷傝丄屷乆帺恎偺帺屓斸敾偲偄偆堄枴偱傕丄廩暘偵斸敾偵壙偡傞傕偺偱偁傞丅 丂偦傟偱丄埲壓丄庡偲偟偰乽桞尋乿戞巐廫擇丄巐廫嶰崋偵偍偗傞壛摗巵偺榑暥乮乽亀僼僅僀僄儖僶僢僴偵偮偄偰亁戞堦僥乕僛偺堦夝庍乿乯偲戞巐廫嬨崋偵偍偗傞壨搶惓巵偺榑暥乽庡懱惈偺栤戣乿偵偍偄偰採婲偝傟偰偄傞棟榑揑栤戣傪丄擣幆庡娤偺栤戣偺嬦枴偲偺楢娭偵偍偄偰庢埖偄丄屷乆偲壛摗乮偍傛傃壨搶乯巵偲偺堄尒偺憡堎傪柧椖側傜偟傔丄偦傟傪捠偟偰巵偺崿棎傪斸敾偡傞偙偲偵偟傛偆丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俀 丂傑偢庡娤偺夝庍偵偍偗傞媽桞暔榑偲尰戙桞暔榑偺憡堎偺栤戣偐傜巒傔傞丅 丂偙偺栤戣偵偍偄偰壛摗巵偺庡挘偡傞偲偙傠偼丄師偺揰偵婣拝偡傞丅 丂(1)丂乽廬棃偺桞暔榑偺恖娫娤傪専偟偰尒傞偲丄拞乆傕偭偰丄恖娫傪偨乁惷偐偵娤徠偡傞偺傒傪擻帠偲偡傞庡娤偲峫偊傞傛偆側偍忋昳側傕偱偼側偐偭偨乿乮戞巐廫擇崋丄堦巐巐暸乯丅乽乧乧懳徠偵懳偡傞扨側傞娤徠傕壗摍偐偺堄枴偱偦傟偵懳偡傞幚慔揑摥偒偐偗偲楢棈偑偁傞丅偟偐偟丄偙偺偙偲偑廬棃偺桞暔榑偵傛偭偰堄幆偝傟偰嫃側偐偭偨偲峫偊傞偙偲偼岆傝偱偁傞乿乮摨忋堦巐擇暸乯丅 丂(2)丂偟偐偟媽桞暔榑偼丄恖娫偺偙偺幚慔傪棟榑偺懳徾偲偣偢丄偦偺桞暔榑揑側慡柺揑攃埇傪梌偊側偐偭偨丅偦偙偱偼乽帺慠偺傒偑擣幆偺懳徾偱偁偭偨乿乮摨忋堦巐擇暸乯丅 丂(3)丂慠傞偵曎徹朄揑桞暔榑偼庡娤丄乽幚慔偡傞恖娫乿傪棟榑偺懳徾偲偡傞偙偲偵傛偭偰丄乽懳徾椞堟傪奼挘乿偟偨丅 丂(4)丂偦偙偱丄恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔傪擣傔偰偄傞揰偱偼丄媽桞暔榑偲尰戙桞暔榑偼壗摍堎乮偙偲側乯傞傕偺偱偼側偄丅乽巚峫偺尰幚惈傪岅傞尷傝偼丄幚慔偵偍偄偰尰幚揑懳徾乮幚嵺偵摉浧乮偁偰偼乯傔傞偙偲偵傛偭偰偙傟傪専徹偟側偗傟偽側傜偸丅偦偺尷傝偵偍偄偰廬棃偺桞暔榑傕儅儖僋僗偺偦傟傕壗摍偺嵎暿偑偁傞栿偱偼側偄乿乮摨忋堦巐嶰暸乯丅 丂(5)丂乽嵎暿偼丄幚徹揑宱尡揑側尋媶丄尰幚偵懄偟偨尋媶偺懳徾偲偟偰 丄恖娫妶摦偦偺傕偺傪幏乮偲傜乯偊偨偙偲偱偁傞乿乮摨忋堦巐嶰暸乯丅恖娫妶摦偺朄懃傗忦審傪偙偺傛偆偵偟偰恀偵桞暔榑揑偵懆偊傞偙偲偵傛偭偰丄偦傟偼幚慔傊偺巜恓偲側傝丄幚慔揑桞暔榑偲側偭偨丄偲壛摗巵偼峫偊傞丅 丂塃偺庡挘偺拞偵偼恀幚偲岆昑偑棈傒崌偭偰偄傞偲塢偆偙偲偑偱偒傞丅壛摗巵偺塢傢傟傞擛偔丄恖娫偼愱傜帺慠傪娤徠偡傞傕偺偱偁偭偰丄怘偄丄堸傒丄楯摥偟丄惗妶偡傞偙偲偼恖娫偵偲偭偰嬼慠側帠暱偩漌乮側偳乯偲峫偊偨桞暔榑幰偼屆棃堦恖傕側偄丅偦偟偰丄恖娫偺偙偆偄偆幚慔傪媽桞暔榑幰偑巚嶕偺懳徾偲偟側偐偭偨偲峫偊傞乮壛摗巵偺擛偔乯偺傕丄傓傠傫惓偟偔側偄丅廫幍悽婭偺桞暔榑幰偼恖娫偺惗妶傪埥乮偁傞偄乯偼椣棟妛偺尒抧偐傜乮僗僺僲僓偺乽椣棟妛乿傪尒傛乯丄埥偼惌帯揑尒抧偐傜乮摿偵儂僢僽僗乯峫嶡偟丄偙偺揱摑傪姰惉偟偨廫敧悽婭偺僼儔儞僗偺桞暔榑幰偼恖娫偺幚慔傪摴摽榑揑丄惌帯妛揑丄嫵堢妛揑摍乆偺尒抧偐傜峀斈偵庢埖偭偨丅僼僅僀僄儖僶僢僴偼乽僉儕僗僩嫵偺杮幙乿偵偍偄偰丄乽廆嫵偺杮幙揑棫応偼幚慔揑棫応偱偁傞乿偲婯掕偟丄廆嫵傪恖娫偺幚慔偺帺屓慳奜偲偟偰朶業偟偨丅偩偐傜媽桞暔榑偵偲偭偰偼帺慠偺傒偑 擣幆偺丄棟榑偺懳徾偱偁偭偨偲偄偆偺偼娫堘偄偱偁傞丅 丂恖娫偺幚慔偺栤戣偵偍偄偰丄媽桞暔榑偑尰戙桞暔榑偲堎傞揰偼丄寛偟偰偦傟偑幚慔傪棟榑偺懳徾偲偟側偐偭偨偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄戞堦偵丄幚慔傪庡偲偟偰帺慠庡媊揑偵乮儅儖僋僗揑偵偄偊偽儐僟儎恖揑尰徾宍懺偵偍偄偰乯懆偊丄偦偺楌巎惈偵偍偄偰桞暔榑揑偵 懆偊摼側偐偭偨偙偲偱偁傞丅媽桞暔榑偼丄恖娫傪丄帺慠偵摥偒偐偗丄偦傟傪曄壔偣偟傔偮偮丄帺暘帺恎偺帺慠傪傕丄帺恎偺惗妶忦審丄幮夛揑惗妶忦審丄幮夛宍懺傪傕曄壔偣偟傔傞傕偺偲偟偰棟夝偣偢丄帺慠偵摥偒偐偗丄憡屳偵摥偒偐偗傞恖娫偺幚慔傪恖娫幮夛偺偐傛偆側楌巎揑曄壔偲偺岎屳嶌梡揑側楢娭偵偍偄偰峫嶡偣偢丄傓偟傠屌掕揑丄宍帶忋妛揑偵昞徾偝傟偨恖娫偺帺慠揑梸朷丄梸媮丄徴摦傪幮夛惗妶偺堦斒揑側晄曄揑婎慴偲尒橍乮側乯偟丄廬偭偰幮夛偺楌巎揑曄壔偺愢柧偵摉偭偰偼丄偐偐傞堦斒揑丄晄曄揑側婎慴偲偼堎偭偨娤擮揑丄怱棟揑乮埥偼偦傟偲暲傫偱抧棟揑乯偺梫場偵慽偊偞傞傪摼偢丄偦傟偑偨傔偵恖娫偺幚慔丄幮夛惗妶偺棟夝偵傑偱桞暔榑傪娧揙偝偣摼側偐偭偨丅偩偐傜丄傕偟壛摗巵偑丄媽桞暔榑幰偵偲偭偰偼恖娫揑妶摦偼桞暔榑揑攃埇偺懳徾 偱側偐偭偨偲塢偆偺側傜丄偦傟偼惓摉偱偁傞丅偩偑巵偵偁偭偰偼惓妋偵偦偆偱偼側偔偰丄堦斒偵桞暔榑偺怴媽擇偮偺宍懺偺憡堎偼丄棟榑偺懳徾 偑慜幰偵偍偄偰偼帺慠偱偁傝丄屻幰偵偍偄偰偼恖娫丄恖娫揑妶摦偱偁偭偨丄偲偄偆揰偵媮傔傜傟偰偄傞丅 丂壛摗巵偵偍偄偰偼丄曎徹朄揑桞暔榑偼乮儅儅乯恖娫偺妶摦傪乽尋媶偺懳徾乿偵偟偨偲偄偆偙偲偼丄偙偺桞暔榑偵偲偭偰偼恖娫偺妶摦偑惓偵懳徾揑側傕偺丄懳徾揑妶摦偱偁傞偲偄偆帠忣偐傜昁慠揑偵婣寢偝傟傞傜偟偄丅壗屘側傜丄恖娫偺幚慔偼丄巵偵傛傟偽丄恖娫偺奜偵懳徾偲偟偰懚棫偡傞偑屘偵偙偦丄恖娫偺擣幆偺懳徾偲側傞偐傜偱偁傞丅偙偙偐傜偟偰丄屷乆偺擣幆偐傜撈棫偵丄偦偺奜偵懚嵼偡傞帺慠丄媞娤悽奅偼幚偼恖娫偺幚慔側偺偩丄偲壛摗巵偼峫偊傞丅偩偐傜巵偼丄乽恖娫偺妶摦傪懳徾揑偵幏乮偲傜乯偊傞偙偲偲暿偺偙偲偱偼側偄乿乮戞巐廫擇崋堦巐嶰暸乯偲偐丄乽摥偒偐偗偺懳徾偦偺傕偺偑幚偼帺慠偵偁傜偞傞恖娫妶摦偱偁傞乿乮摨忋堦巐屲暸乯偲抐掕偟丄恖娫偺奜偵懚嵼偟丄恖娫偺摥偒偐偗偺懳徾偲側傞媞娤悽奅偼幚偼乽恖娫妶摦乿偱偁傝丄乽恖娫偺妶摦乿偑恖娫偺乽幚慔揑側摥偒偐偗偺懳徾乿偱偁傞偲庡挘偡傞丅偦偙偱帺慠壢妛偺懳徾偲側傞帺慠偼丄乽恖娫偺幚慔偑恖娫偺廃埻偵妋棫偟偨慡懳徾悽奅偺丄偦偺媞娤揑懁柺丄堦墳恖娫偦偺傕偺偐傜堷棧偟偰峫偊傜傟傞懁柺偲偟偰乿幏偊傜傟偨傕偺偵奜側傜側偄乮摨忋堦屲堦暸乯丅壛摗巵偑丄儅儖僋僗偺桞暔榑偼恖娫偺妶摦傪棟榑偺懳徾偵偟偨偲塢偆偺偼丄傑偝偵偐傛偆側堄枴偵偍偄偰偱偁傞丅 丂傕偪傠傫丄恖娫偺幚慔偼柍懳徾揑側傕偺偱偼偁傝摼偢丄幚慔偲偼庡娤偺懁偐傜偡傞庡娤偲媞娤偺岎屳嶌梡偱偁傞偐傜丄偦傟偼偦傟偵傛偭偰曄壔偣偟傔傜傟傞懳徾偺拞偵奜壔丄乽帺屓慳奜乿偡傞懳徾揑側妶摦偱偁傞丅偩偑丄偦傟偩偐傜偲偄偭偰丄幚慔傪懳徾揑悽奅偲摨堦帇偟丄幚慔偺懳徾偑幚慔偱偁傞偲寢榑偡傞偺偼丄庡娤偲媞娤偺摨堦惈傪愢偔儖僇僢僠庡媊偱偁傝丄庡娤庡媊偱偁傞丅恖娫偺妶摦偺懳徾偼愭峴偡傞妶摦偵傛偭偰曄壔偣偟傔傜傟偨帺慠丄奜奅 偱偁傝丄偙偺奜奅偼恖娫偺妶摦偐傜尦棃撈棫偵懚嵼偟丄偦偟偰擛壗側傞楌巎揑抜奒 偵偍偗傞恖娫楯摥偵偍偄偰傕恖娫偺妶摦丄楯摥偐傜撈棫側帺慠椞堟偑栶妱傪墘偠傞偙偲偼乽帒杮榑乿偵塢傢傟偰偄傞強偱偁傞丅廬偭偰恖娫妶摦偺夁掱偵偍偄偰擣幆偝傟傞帺慠偺楢娭偼丄恖娫偺幚慔偵傛偭偰 乽妋棫乿丄乽憂憿乿偝傟偨傕偺偱偼側偔偰丄恖娫偺懚嵼埲慜偐傜丄恖娫偐傜撈棫偵懚嵼偟偰偄傞媞娤揑楢娭偱偁傝丄惓偵偙偺揰偵偍偄偰帺慠偺桪墇惈偵娭偡傞桞暔榑揑娤擮偼惉棫偡傞丅慠傞偵壛摗巵偺柦戣偼慡偔恖娫妛揑丄庡娤庡媊揑偱偁偭偰丄偦偙偱偼幮夛壢妛偵偍偄偰峫媶偝傟傞恖娫妶摦偲丄帺慠壢妛偵偍偄偰峫媶偝傟傞丄恖娫妶摦偐傜撈棫側帺慠楢娭偲偑崿摨偝傟丄帺慠壢妛偼恖娫偺幚慔傪炄濿乮偙偆偐傫乯偲偟偰敪揥偟丄帺慠傊偺摥偒偐偗偺強嶻偱偁傞偲嫟偵丄偦偺尋媶偡傞朄懃偼幚慔偐傜撈棫偵懚嵼偡傞傕偺偩偲偄偆偙偲偑柍帇偝傟偰偄傞丅壛摗巵偼儅儖僋僗偺僥乕僛偺帤嬪偺夝庍偺柤偵偍偄偰丄儅儖僋僗偺桞暔榑傪斲掕偟偰偄傞傕偺偺擛偔偱偁傞丅偙傟偼丄媽桞暔榑偵偁偭偰偼尋媶偺懳徾偼帺慠偱偁傝丄偙傟偵斀偟偰儅儖僋僗偺乽桞暔榑偵偁偭偰偼恖娫妶摦偑乮廬偭偰偦傟偵傛偭偰乽妋棫乿偝傟傞帺慠傕乯尋媶偺懳徾偱偁偭偨偲偡傞巵偺尒夝偲怺偔寢傃偮偄偰偄傞丅偩偑偙傟偙偦偼丄儅儖僋僗偵偁偭偰偼曎徹朄揑攃埇偺懳徾偼乽楌巎揑=幮夛揑尰幚乿偱偁偭偰丄僿乕僎儖乮偍傛傃僄儞僎儖僗乯偵偍偗傞擛偔帺慠偵傑偱偼墑挿偝傟摼側偄偲偄偆儖僇僢僠偺庡挘偲崌抳偡傞傕偺偱偼側偄偐丅 丂梫偡傞偵丄幚慔偺栤戣偵偍偄偰偺丄廬棃偺桞暔榑偲儅儖僋僗丄僄儞僎儖僗偺桞暔榑偲偺戞堦偺憡堎偼丄幚慔偺夝庍偺撪梕偱偁偭偰丄偦傟偑尋媶偺懳徾偱偁偭偨偐斲偐偲偄偆偙偲偵偁傞偺偱偼側偄乮拹乯丅師偵丄椉幰偺戞擇偺廳梫側憡堎偼丄曎徹朄揑桞暔榑偼幚慔傪擣幆榑 丄榑棟妛偵摫擖 偟偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅偩偐傜乽巚峫偺尰幚惈傪岅傞尷傝偼丄幚慔偵偍偄偰尰幚揑懳徾傊幚嵺偵摉浧傔傞偙偲偵傛偭偰偙傟傪専徹偟側偗傟偽側傜偸丅偦偺尷傝偵偍偄偰廬棃偺桞暔榑傕儅儖僋僗偺偦傟傕壗摍偺嵎暿偑偁傞栿偱偼側偄乿偲偄偆壛摗巵偺庡挘偼惓摉偱側偄丅
丂栜榑丄懳徾揑恀棟偼娬嫃惷巚偡傞偙偲偵傛偭偰妉摼偝傟傞偲偼丄搶梞偺揘妛幰払偼暿偲偟偰丄彮側偔偲傕偡偱偵僼儔儞僗偺桞暔榑幰偼峫偊偰偄側偄丅斵摍偼丄擣幆偼惗妶偵昁梫側傕偺偱偁傝丄傑偨幚尡偑帺慠擣幆偵偍偄偰廳梫側堄媊傪帩偮偙偲傪擣傔偰偄傞丅偦傟偵傕峉傢傜偢丄斵摍偵偁偭偰偼偦傟偼堦斒揑側尒夝 偲側傞偵摓傜偢丄斵摍偼奣偟偰塢偊偽擣幆庡娤偲幚慔偺庡娤 偲傪曎徹朄揑摑堦偵偍偄偰懆偊摼側偐偭偨丅帺慠偵摥偒偐偗傞恖娫偺妶摦丄楯摥丄嶻嬈偙偦偑丄帺慠傪擣幆偡傞巚堃偺摥偒偺婎慴偱偁傝丄擣幆妶摦傪婯掕偡傞傕偺偱偁傞偙偲傪棟夝偟側偐偭偨丅惗妶丄幚慔傪擣幆榑偺弌敪揰偲尒偨僼僅僀僄儖僶僢僴偼僼儔儞僗偺桞暔榑幰傛傝偼堦曕慜恑偟偰偄偨偲偼偄偊丄偦偺惗妶丄幚慔偼斵偵偁偭偰偼楌巎揑偵懆偊傜傟側偐偭偨偨傔偵丄斵偼擣幆偺夁掱傪丄偙偺夁掱偵偍偗傞幚慔偺栶妱傪丄嬶懱揑偵夝柧 偡傞偵摓傜偢丄偦傟屘擣幆榑偵偍偗傞幚慔偺婯弨偼斵偵偁偭偰偼僼儔乕僛乵寧暲傒側尵梩丄偁傝偒偨傝側暥嬪乶偨傞偵巭傑偭偨丅壛摗巵偺塢傢傟傞傛偆側丄恖娫偼妶摦揑側傕偺偩偲偄偆媽桞暔榑偺乽恖娫娤乿偼丄枹偩寛偟偰擣幆榑偵偍偗傞幚慔偺婯弨偺棟夝偱偼側偔丄擣幆庡娤 傪妶摦揑恖娫丄恖娫揑妶摦偲偟偰懆偊傞偙偲傪堄枴偟側偄丅 丂僄儞僎儖僗偑乮乽僼僅僀僄儖僶僢僴榑乿乯丄晄壜抦榑偺斀敐丄懄偪巚堃偺尰幚惈偺徹柧偲偟偰偺幚慔丄懄偪幚尡偲嶻嬈偵偮偄偰岅傞偵摉偭偰丄晄壜抦榑偺斀敐偺偨傔偵寛掕揑側偙偲偼娤擮榑偵偍偄偰壜擻側尷傝偱偼僿乕僎儖偵傛偭偰岅傜傟丄僼僅僀僄儖僶僢僴偑偦傟偵晅壛偟偨桞暔榑揑側傕偺偼乽怺崗偲偄偆傛傝傕婡抦揑乿側傕偺偩偲塢偭偨偺偼丄惓偵曎徹朄揑桞暔榑偵偍偄偰偙偦恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔偼柧妋偵丄惓摉偵棟夝偝傟偰偄傞偙偲傪巜偟偨傕偺偲塢偊傞丅乽揘妛僲乕僩乿偺僿乕僎儖榑棟妛偺晹暘偵偼丄乽惗柦 傪榑棟妛偵曪妵偝偣傞乿僿乕僎儖偺巚憐偼乽揤嵥揑乿偩偲彂偐傟偰偄傞丅傑偨偦偙偵偼乽幚慔偼僿乕僎儖偵偁偭偰偼擣幆夁掱偺暘愅偺拞偵堦娐偲偟偰埵偟丄惓偵媞娤揑恀棟傊偺堏峴偲偟偰埵偟偰偄傞丅廬偭偰丄儅儖僋僗偼丄擣幆榑偵幚慔偺婯弨傪摫擖偡傞偲偒丄捈滲偵僿乕僎儖偵壛扴偟偰偄傞丅僼僅僀僄儖僶僢僴偵娭偡傞僥乕僛傪嶲徠偣傛乿偲傕彂偐傟偰偄傞丅 丂儅儖僋僗帺恎偵偮偄偰偄偊偽丄斵偼偡偱偵乽恄惞壠懓乿傊偺壓彂偒乮乽宱嵪妛揑=揘妛揑憪峞乿偲偟偰慡廤斉偵敪昞偝傟偨傕偺乯偺拞偱丄乽庡娤庡媊偲媞娤庡媊丄桞怱榑偲桞暔榑乿偺懳棫偼乽幮夛揑忬懺乿偵偍偄偰弶傔偰揚攑偝傟丄乽棟榑揑懳棫偺夝寛偡傜偨乁幚慔揑側 巇曽偱偺傒丄偨乁恖娫偺幚慔揑僄僱儖僊乕偵傛偭偰偺傒丄壜擻偱偁傝乿丄乽偦傟屘偦偺夝寛偼寛偟偰扨偵擣幆偺壽戣偱側偔丄尰幚揑側 惗妶偺壽戣偱偁傞乿偙偲丄慠傞偵廬棃偺乽揘妛 偼偙偺壽戣傪扨偵棟榑揑壽戣偲偟偰偺傒懆偊偨偑屘偵丄偙傟傪夝寛偟摼側偐偭偨乿偙偲傪弎傋偰偄傞丅 丂偙偺傛偆偵偟偰丄棟榑揑壽戣偵嵟屻偺寛拝傪梌偊傞傕偺偼幚慔偱偁傝丄幚慔偵傛傞専徹丄徹柧偱偁傞偲偄偆巚憐丄恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔 偲偄偆娤擮偼丄娤擮榑偵偍偄偰壜擻側斖埻偱偼僿乕僎儖偵傛偭偰丄偦偟偰桞暔榑偵偍偄偰揙掙揑偵偼儅儖僋僗丄僄儞僎儖僗偵傛偭偰弶傔偰帩偪崬傑傟偨傕偺偱偁傞丅偲丄彮側偔偲傕尰戙桞暔榑偺僋儔僔働儖乵揟宆揑側恖丄嫄彔乶払偼擣傔偰偄傞丅恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔偵娭偡傞柦戣偺恀偺堄媊偼丄壛摗巵偺塢偆擛偔乽擣幆偺懳徾偑幚慔偵傛偭偰巟偊傜傟偰偄傞乿乮戞巐廫擇崋昐屲廫堦暸乯偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄愭峴偡傞幚慔偺惉壥偲偟偰摼傜傟偨擣幆乗乗帺慠偺楢娭偵偮偄偰偺堄幆乗乗偑丄怴偟偄幚慔偵傛偭偰怴偨偵奐斺偝傟偨帺慠偺楢娭偲偺懳斾偵傛偭偰妋徹丄惀惓偝傟傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄幚慔偐傜撈棫側帺慠偺楢娭偑幚慔傪捠偟偰恖娫偺堄幆偵忋偭偰偔傞 偲偄偆偙偲偱偁傞丅恖娫偺幚慔偵傛偭偰憂憿偝傟傞楌巎偺擣幆偵偍偄偰傕丄婛摼偺擣幆傪楌巎揑尰幚偵偮偄偰専徹偡傞幚慔傪捠偟偰堄幆偵岦偭偰尰傟傞尰幚偺楢娭偼丄偦偺幚慔埲慜偵丄偦傟偐傜撈棫偵乮埲慜偺幚慔偵傛偭偰憿傝弌偝傟偰乯懚嵼偟偰偄傞傕偺偱偁偭偰丄偙偺怴偨側丄専徹偡傞幚慔偵傛偭偰懳徾偵壛偊傜傟偨曄壔偼丄偦偺屻偐傜擣幆偝傟傞偙偲偵側傞丅擣幆榑偵偍偗傞幚慔偺婯弨偲偄偆偙偲偼偲傝傕捈偝偢棟榑偵懳偡傞幚慔偺桪埵 偱偁傝丄幚慔傊偺棟榑偺廬懏偺彸擣偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俁 丂摨帪偵丄恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔偺彸擣偼丄妶摦偡傞恖娫丄恖娫揑妶摦偲擣幆庡娤偲傪摨堦惈偵偍偄偰懆偊傞 偙偲偱偁傝丄惗妶偟丄峴摦偡傞慡恖娫 偐傜擣幆庡娤傪暘棧偝偣側偄偙偲偱偁傝丄恖娫偺堦晹暘乮巚堃丄抦揑擻椡乯偺傒 傪擣幆庡娤偲偟側偄偙偲偱偁傞丅奧乮偗偩乯偟丄恖娫偺擣幆偺尰幚惈丄恀棟惈偺徹柧偲偟偰偺幚慔偼丄扨側傞巚堃丄抦揑妶摦丄棟榑傛傝埲忋偺傕偺 偱偁傝丄幚慔偼恖娫偺惗懚偺帠幚偦偺傕偺偩偐傜偱偁傞丅偲偙傠偱桞暔巎娤偵傛傟偽丄恖娫堦斒偼懚嵼偣偢丄恖娫偼楌巎揑側傕偺偱偁傝丄帺恎偺懳徾揑妶摦傪捠偟偰楌巎揑偵帺恎傪曄壔偣偟傔傞傕偺偱偁偭偰丄奒憌暘壔偵棫媟偡傞幮夛偵偍偄偰偼恖娫偼奒媺恖偱偁傞丅偮傑傝擣幆庡娤偼僋儔僢僙儞僴僼僩乵奒媺揑乶側杮幙傪桳偟偰偄傞丅偦傟偼丄恖娫偺妶摦偑僋儔僢僙儞僴僼僩偱偁傝丄幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶傪傕偭偰娧偐傟偰偄傞偙偲偺拞偵昞尰偝傟傞丅 丂恖娫偺幚慔偵偼帺慠傊偺摥偒偐偗偲恖娫憡屳偺摥偒偐偗偑偁傝丄椉幰偑屳偄偵怹摟偟崌偭偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄楯摥丄惗嶻偼偮偹偵堦掕偺惗嶻娭學偺壓偱偺傒塩傑傟傞偲偄偆帠幚偵傛偭偰柧乆敀乆偱偁傞丅偩偐傜丄僋儔僢僙儞丒僇儉僾乵奒媺摤憟乶偺擛偒丄恖娫懳恖娫偺峴堊偑恀棟偺婯弨偲偟偰偺幚慔偲偼暿暔偱偁偭偰丄屻幰偼愱傜 楯摥丄懳帺慠妶摦偱偁傝丄彮側偔傕帺慠擣幆偵娭偡傞尷傝偱偼慡偔 偦偆偱偁傞丄漌乮側偳乯偲峫偊傞偺偼柧偐偵岆昑偱偁傞丅 丂偦偙偱丄幚慔偵傛傞擣幆偺婯掕偺庬乆偺宊婡偵堦墳棫偪擖偭偰傒傞昁梫偑偁傞丅 丂戞堦偵丄恖娫偼幚慔偵偍偄偰懳徾偲偺岎屳嶌梡偵擖傝丄擣幆偺懳徾丄嵽椏偼幚慔偵傛偭偰梌偊傜傟傞丅偦偺応崌丄偳傟偩偗偺懳徾斖埻偑擣幆偺懳徾偲偟偰恖娫偺娽慜偵傕偨傜偝傟傞偐偼丄婎杮揑偵偼幮夛偺暔幙揑惗嶻椡偺悈弨 偵傛偭偰婯掕偝傟傞丅 丂偩偑戞擇偵丄惗嶻椡偼偮偹偵堦掕偺惗嶻娭學偺壓偱塣摦偡傞傕偺偱偁傞偐傜丄惗嶻椡傪巟攝偡傞奒媺偺棙塿偼惗嶻偵丄惗嶻椡偺塣摦偵丄塭嬁偟丄偦偺偙偲偵傛偭偰懡偐傟彮側偐傟擣幆嵽椏偺斖埻偺峀嫹愺怺偵塭嬁偣偞傞傪摼側偄丅偙傟傪嵽椏傪庴庢傞庡娤偺懁偐傜塢偊偽丄屄乆偺庡娤偼丄偦偺帪戙偺惗嶻椡偺忬懺偵傛偭偰擣幆偺嵽椏偨傜偟傔傜傟摼傞慡懳徾斖埻傪丄帺屓偺尋媶懳徾偲偡傞偺偱偼側偄偟丄傑偨偦偆偡傞偙偲偼晄壜擻偱偁偭偰丄尋媶壠偼偮偹偵懳徾偺惂尷丄嵽椏偺慖戰傪梋媀側偔偝傟傞丅偦偟偰偐乀傞惂尷丄慖戰偼昁偢傗偁傟偙傟偺奒媺揑棙塿偵傛偭偰惂栺偝傟傞丅摿偵幮夛壢妛偺応崌偵偍偄偰偼丄妛幰偑帺屓偺奒媺揑棙奞姶偺偨傔偵丄堦掕偺尰徾丄帠徾偵懳偟偰娽傪暵偠傞偙偲偡傜婬偱側偄丅 丂師偵丄戞嶰偵丄偙偺傛偆偵偟偰庴庢傜傟偨嵽椏偼丄偦偺嵼傞偑傑乀偺巔偵偍偄偰堄幆偵斀塮偡傞偐偲偄偆偵丄昁偢偟傕 偦偆偱偼側偄丅傕偪傠傫丄姶姱偺峔憿偐傜丄媞娤揑幚嵼偺堄幆傊偺揔墳揑斀塮傪斲掕偟偨傝丄愭揤揑側捈娤宍幃傗斖醗傪憐掕偟偰柾幨榑傪斲掕偡傞偺偼丄晄壜抦榑擳帄乮側偄偟乯娤擮榑偱偁偭偰丄桞暔榑偲偼柍墢偱偁傞丅偩偑堄幆偼庴摦揑側嬀偱偼側偔丄堦楢偺僕僢僌僓僢僌傪宱偰媞娤偺擣幆偵摓払偡傞傕偺偱偁傞丅捈娤揑偵妉摼偝傟偨昞徾傪壢妛揑奣擮偵巇忋偘傞巚堃 偼丄偦偺婡擻偺屘偵弌棃傞偩偗惗妶忋偺棙奞娭學傗恖娫偺婅朷偐傜撈棫偟偰丄媞娤傪偦偺嵼傞偑傑乀偵懆偊傛偆偲偡傞梫媮傪帩偮偲偼塢偄側偑傜丄寛偟偰偐傛偆側惗妶忋偺婅朷傗棙奞姶偐傜慡慠夝曻偝傟偰偄傞偲偄偆堄枴偱乽弮悎乿側傕偺偱偼偁傝摼側偄丅擣幆庡娤偦偺傕偺偼惗妶偟丄屳偄偵峈憟偡傞幮夛揑恖娫偱偁傝丄奒媺恖偩偐傜偱偁傞丅偦傟偱丄椺偊偽丄擛壗側傞壢妛揑巚堃傕寛偟偰偦傟側偟偵偼嵪傑偣側偄偲偙傠偺憐憸丄嬻憐 偺拞偵偼丄偡偱偵庡娤揑側傕偺乗乗偦傟偼偮偹偵媞娤偲晄堦抳偩偲偼尷傜側偄 偑丄乗乗偑擖傝崬傒丄婅朷傗奒媺杮擻偵傛偭偰惂栺偝傟偨娤擮偑擖傝崬傓丅屷乆偼帺屓偺擣幆偺惛枾惈傪屩傞暔棟妛幰払偑丄擛壗偵棟榑揑栤戣偵偍偄偰廆嫵揑嬻憐偵曔傢傟偰偄傞偐偺懡偔偺椺傪抦偭偰偄傞丅 丂乽屄乆偺暔偵懳偡傞惛恄乮恖娫乯偺懺搙丄偦傟偺柾幨乮亖奣擮乯偺庢摼偼丄扨弮側丄捈愙揑側嬀偺條偵巰傫偩嶌梡偱偼側偔偰丄暋嶨側丄暘楐偟偨丄僕僢僌僓僢僌條偺傕偺偱偁偭偰丄惗妶偐傜偺嬻憐乮僼傽儞僞僕乕乯偺旘隳偺壜擻惈傪丄偦傟偽偐傝偱側偔丄拪徾揑奣擮丄娤擮偺丄嬻憐 乮寢嬊偵偍偄偰恄乯傊偺揮壔 乮偟偐傕栚棫偨側偄丄恖娫偵傛偭偰堄幆偝傟偰偄側偄揮壔乯偺壜擻惈傪丄帺傜偺拞偵曪娷偟偰偄傞 丅壗屘側傜丄嵟傕扨弮側奣妵丄嵟傕尨弶揑側堦斒揑娤擮乮乽婘乿堦斒乯偺拞偵傕丄嬻憐 偺堦掕偺抐曅偑偁傞 偐傜偱偁傞丅乮斀懳偵丄嵟傕尩枾側壢妛偵偍偄偰傕嬻憐偺栶妱傪斲掕偡傞偺偼攏幁偘偰偄傞丅楯嶌傊偺 巋徴偲偟偰偺丄桳塿側嬻憐偲嬻嫊側嬻憐惈偲偵娭偡傞僺乕僒儗僼偺尵傪嶲徠偣傛乯乿丅偙傟偼乽揘妛僲乕僩乿偵偍偗傞廳梫側巚憐偺堦偮偱偁傞丅偦偙偱偼丄拪徾丄奣妵丄奣擮宍惉偺拞偵偼偡偱偵嬻憐偺宊婡偑偁傞偙偲偑岅傜傟偰偄傞丅壢妛揑擣幆偺曽朄榑亖榑棟妛偑丄傑偨偦偺揔梡偑丄嬻憐偐傜慡慠撈棫偱偁偭偰丄偦偺拞偵偼恖娫偺幮夛揑懚嵼丄幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶丄傾儞僞僑僯僗僥傿僢僔儏乵懳棫揑丒揋懳揑乶側棙奞偑丄偡偙偟傕斀塮偟偰偄側偄偲峫偊傞偙偲偼丄擣幆庡娤傪僇儞僩庡媊揑堄枴偺乽弮悎巚堃乿丄枖偼僿乕僎儖揑棟擮偲尒橍乮側乯偡応崌偐丄擳帄偼擣幆庡娤傪幚慔偺庡娤偐傜丄惗妶偡傞恖娫偐傜愗棧偟丄擣幆傪幚慔偐傜愗棧偡応崌偵偺傒壜擻偱偁傞丅偩偐傜椺偊偽僄儞僎儖僗偼丄尰徾偲杮幙丄尨場偲寢壥偲傪愗棧偡宍帶忋妛揑榑棟傪乽僽儖僕儑傾揑忢幆偺梈捠偺偒偐偸攏幵攏乿偲屇傃丄偙偺傛偆側曽朄榑偺僽儖僕儑傾揑奒媺惈傪巜揈偟偰偄傞乮乽帒杮榑乿偵偮偄偰偺昡榑乯丅 丂嵟屻偵丄戞巐偵丄偐傛偆偵偟偰巇忋偘傜傟偨擣幆偺恀棟惈傪嵟屻揑偵専徹偡傞幚慔傕丄傕偪傠傫丄擣幆偺庡娤揑旐惂栺惈傪慡慠攔彍偟摼傞傕偺偱偼側偔丄媞娤揑恀棟傪姰慡偵 尕乮傕偨乯傜偟摼傞傕偺偱偼側偄丅乽幚慔偺婯弨偼帠懺偺杮幙偦偺傕偺偐傜偄偭偰丄寛偟偰擛壗側傞恖娫偺昞徾傪傕姰慡偵偼 妋徹枖偼榑敐偟摼側偄傕偺偩偲偄偆偙偲傪朰傞傋偒偱偼側偄丅偙偺婯弨傕傑偨丄恖娫偺抦幆偑亀愨懳幰亁偵揮壔偡傞偺傪嫋偝側偄掱搙偵亀晄妋掕揑亁偱偁傝丄摨帪偵娤擮榑傗晄壜抦榑偺偡傋偰偺垷庬偲偺柍帨斶側摤憟傪峴偆掱搙偵偼妋掕揑偱偁傞乿乮乽桞暔榑偲宱尡斸敾榑乿丄戞擇復戞榋愡乯丅幚慔偺婯弨偼丄恖娫偺擣幆偑恖娫偐傜撈棫側媞娤揑恀棟傪撪梕偲偡傞傕偺偱偁傞偙偲傪妋掕揑偵徹柧偡傞偲嫟偵丄偙偺媞娤揑恀棟偼奺乆偺楌巎揑抜奒偵偍偄偰偮偹偵乽晄妋掕乿偵擣幆偝傟傞偙偲丄懄偪恖娫偺擣幆偼憡懳揑恀棟偱偁傞偙偲傪巜帵偡傞丅擣幆偺偙偺憐掕惈丄晄妋掕惈偺斖埻偼丄媄弍傗嶻嬈偺恑曕偵偮傟偰師戞偵弅彫偝傟丄擣幆偼師戞偵愨懳揑恀棟偵嬤敆偡傞丅偩偑奺乆偺堦掕偺楌巎揑抜奒偵偍偄偰偼幚慔偵傛傞擣幆偺恀棟惈偺専徹偵偍偗傞壗傜偐偺掱搙偺乽晄妋掕惈乿偼偮偹偵巆懚偡傞丅偦偟偰偙偺乽晄妋掕惈乿偺斖埻偙偦偼嬻憐 偺廧傒壠偱偁傝丄墲乆偵偟偰斀壢妛揑側壢妛揑壖愝 偺嫆傝強偱偁傞丅媞娤揑側丄惛枾側幚尡偵傛傞専徹傪摿怓偲偡傞帺慠壢妛偵偍偄偰傕丄旕忢偵幤乆乮偟偽偟偽乯廆嫵偲懨嫤偡傞壖愢偑懪偪寶偰傜傟傞偺偼丄幚偼偙偺幚尡偵傛傞専徹偦偺傕偺偺楌巎揑偵惂栺偝傟偨尷奅丄晄妋掕惈偵傛傞偺偱偁傞丅偩偐傜幚慔偵傛傞専徹偼丄壗傜擣幆偺僋儔僢僙儞僴僼僩乵奒媺揑乶側惈幙傪彍嫀偡傞傕偺偱偼側偄丅摿偵幮夛壢妛偵偁偭偰偼丄専徹偡傞幚慔偦傟帺恎偑偡偱偵恖娫懳恖娫偺妶摦偱偁傝丄乮仸嘆壓慄晹偼屻偵捛壛仺乯捈愙偵奒媺惈偁傞傕偺偱偁傞偐傜丄偙偺偙偲偼堦憌慡柺揑偵懨摉偡傞丅 丂栜榑丄嬻憐偼偮偹偵 斀壢妛揑側偺偱偼側偄丅偦傟偼丄帠忣偵傛偭偰偼丄壢妛揑敪尒偺宊婡偲傕側傞偙偲偑偱偒傞偟丄堦斒偵媞娤揑恀棟偺塀暳傗榗嬋偵嵄彮偺棙塿傪傕帩偨側偄恖乆偺摦岦偵傛偭偰摫偐傟傞応崌偵偼擣幆偺壢妛惈偲嫤摨偡傞丄偲偄偆偙偲傪柫婰偟側偗傟偽側傜側偄丅扨偵丄幚嵺惗妶忋偺棙奞傗摦岦傪捈愙偵斀塮偝偣摼傞嬻憐枖偼憐憸偺傒偱側偔丄傑偨堦斒偵幚嵺惗妶丄幚慔偦偺傕偺偵偮偄偰傕偦傟偲摨偠偙偲偑妋擣偝傟傞丅幚慔偼帠忣偺擛壗偵墳偠偰丄扨偵壢妛偺恑曕偺悇恑椡偨傞偺傒偱側偔丄傑偨媡偵偦偺瀪瀲乮偟偭偙偔乯偲傕側傝摼傞丅偦傟偱丄擛壗側傞幚慔丄幚慔揑棙奞偑壢妛恑曕偺瀪瀲偲側傞偐偼丄幚慔偡傞奒媺揑庡娤偑抲偒崬傑傟偰偄傞楌巎揑抧埵偵埶懚偡傞丅椺偊偽僽儖僕儑傾僕乕偺楌巎揑抧埵偵傛偭偰婯掕偝傟傞斵摍偺棫応丄棙奞丄幚慔偑丄擛壗偵壢妛揑宱嵪妛偺巇忋偘傪晄壜擻側傜偟傔偨偐傪儅儖僋僗偼嵞嶰岅傝丄傑偨擛壗偵偦偺悽奅娤傪楌巎偺椞堟偵偍偄偰娤擮榑揑側傜偟傔偨偐丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺戜摢偲嫟偵廆嫵偵揮岦偣偟傔偨偐傪僄儞僎儖僗偼岅偭偰偄傞丅 丂曎徹朄揑桞暔榑偑丄擣幆偵偍偗傞堦愗偺僽儖僕儑傾揑惂尷傪巭梘偟丄媞娤揑恀棟傊偺搑忋偵偍偗傞楌巎揑偵惗惉偣傞庡娤揑忈奞暔傪幓乮偙偲偛偲乯偔惔憒偟偰偄傞偲偟偰傕丄偦偺偙偲偼寛偟偰偙偺揘妛偑幮夛揑懚嵼偵傛傞旐婯掕惈偐傜夝曻偝傟丄乽庡懱惈偺婯掕乿傪壗傜娷桳偟側偄偲偄偆偙偲傪堄枴偟側偄丅媝乮偐偊乯偭偰丄偙偺帠幚偼僾儘儗僞儕傾乕僩偺楌巎揑抧埵丄偦偺幮夛揑棫応偐傜愢柧偝傟側偗傟偽側傜側偄丅斵摍偺悽奅娤偑擣幆偺壢妛惈偵懳偡傞儅僀僫僗偲偄偆堄枴偺丄擳帄偼媞娤揑恀棟傪榗嬋偡傞忦審偲偄偆堄枴偺乽庡懱惈偺婯掕乿傪帩偨側偄偲偄偆偙偲偼丄偦傟帺恎斵摍偺乽庡懱惈偺婯掕乿偺慠傜偟傓傞偲偙傠偩偲偄偆偙偲傪峫椂偡傋偒偱偁傞丅壗屘偵僾儘儗僞儕傾乕僩偺楌巎揑抧埵丄偦偺惗妶丄幚慔偼尰幚偺揙掙揑側壢妛揑擣幆偵棙塿傪帩偨偟傔傞偐偲偄偆偙偲偼丄偦傟帺恎廳梫側僥乕儅傪惉偡傕偺偱偁傞偑丄堦尵偵偟偰偙傟傪塢偊偽師偺揰偵婣拝偡傞偱偁傠偆丅 丂戞堦偵丄偦偺楌巎揑抧埵偺屘偵丄斵摍偼尰懚儗僕乕儉乵惌帯懱惂乶偐傜偺帺屓偺夝曻傪梸偟丄偦傟偵懳偟偰斲掕揑丄斸敾揑偲側傞丅 丂戞擇偵丄偙偺夝曻偺壜擻惈偼丄尰戙幮夛偦偺傕偺偺敪揥偵敽偆斵摍帺恎偺惉挿偺拞偵梌偊傜傟偰偍傝丄廬偭偰偦偺幚尰偼愱傜斵摍帺恎偺椡偵埶懚偡傞丅 丂戞嶰偵丄斵摍偼丄斵摍偺壓偐傜夝曻偝傞傋偒幮夛梫慺傪帺傜偺壓偵桳偣偢丄廬偭偰帺屓傪夝曻偡傞偲嫟偵恖娫偵傛傞恖娫傊偺壛埑偺堦愗偺宍懺丄忦審傪惔嶼偡傞丅 丂偙偙偵偁偘偨戞堦偺揰偼丄搝楆傗擾搝偵傕丄傑偨埥傞掱搙枠偼晻寶惂壓偺僽儖僕儑傾僕乕偵傕嫟捠偱偁傞丅偩偑搝楆傗擾搝偼丄愱傜 帺恎偺椡偵傛偭偰夝曻偝傟摼傞傕偺偱傕側偔丄傑偨斵摍偑搝楆擳帄擾搝偨傞偙偲傪巭傔偨怴偟偄幮夛揑娭學偺壓偱傕斵摍偺埑搢揑懡悢偼埶慠偲偟偰旐廂庢幰偱偁偭偨丅偩偐傜斵摍偼恄傗揤崙偵媬嵪傪媮傔傞孹岦傪扙偟摼側偐偭偨丅晻寶惂偲愴偆僽儖僕儑傾僕乕偼怴偟偄拋彉偺乽庡恖乿偲側傞傋偒抧埵偵偁偭偨偲偼偄偊丄偙偺摤憟偵偍偄偰斵摍偼擾搝揑擾柉傗搒巗楯摥幰偺暔幙揑椡傪摦堳偣偹偽側傜偢丄懠柺偵偍偄偰偼晻寶惂偵懳偡傞斀懳偲偄偆堄枴偱偼擾柉傗楯摥幰偺棙塿傪僽儖僕儑傾僕乕偼埥傞掱搙枠戙昞偟偨偑屘偵丄傑偨摨帪偵僽儖僕儑傾揑娭學偼彜昳惗嶻偺敪払偲嫟偵晻寶惂壓偱埥傞尷搙枠偼帺惗揑 偵丄惗挿偟偨偑屘偵丄斵摍偼乽崙柉乿丄塱媣恀棟丄晄曄揑恖尃丄乽帺慠揑乿乮僽儖僕儑傾揑娭學偼帺惗揑偵惗挿偟偨偑屘偵乽帺慠揑乿偲尒橍偝傟偨乯拋彉偺柤偵偍偄偰晻寶惂傪斸敾偟偨偵巭傑傝丄幮夛敪揥偺媞娤揑崌朄懃惈偺攃埇傪帺屓偺摤憟偺晄壜寚側忦審偵帩偨側偐偭偨丅傑偨斵摍偼怴偟偄拋彉偺乽庡恖乿偲側傞傗丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺堄幆偺惗挿丄偦偺壢妛揑側幮夛擣幆偺宍惉丄嫮壔偵懳偟偰旛偊傞昁梫偵敆傜傟偨丅偮傑傝丄塃偵偁偘偨戞擇偍傛傃戞嶰偺揰偱丄僽儖僕儑傾僕乕偼僾儘儗僞儕傾乕僩偲憡堎偟丄偙傟傜偺憡堎偼慜幰偵偍偗傞宍帶忋妛揑悽奅娤丄廆嫵惈傪惂栺偟丄屻幰偵偍偗傞壢妛揑悽奅娤傪惂栺偡傞丅乮仸嘇壓慄晹偼屻偵曗懌仺乯僾儘儗僞儕傾乕僩偼乽慡懱偲偟偰偺幮夛敪揥偺扴偄庤丄嬤戙幮夛偺柕弬偺夝寛幰偨傞傋偒楌巎揑忦審偺壓偵抲偐傟偰偄偰丄斵摍偺奒媺揑棙塿偼幮夛敪揥偺棙塿偲崌抳偟丄偟偐傕帒杮庡媊偺戀撪偵僂僋儔乕僪 乵宱嵪惂搙乶偲偟偰帺惗揑偵敪堢偟摼側偄惗嶻娭學偺憿弌 偑偙偺幮夛敪揥偺媞娤揑婣寢丄媞娤揑栚昗偱偁傝丄摨帪偵斵摍帺恎偺奒媺揑摦岦偺婣偡傞偲偙傠偱偁傞偐傜丄偙偙偱偼楌巎偺朄懃丄幮夛偺敪揥孹岦丄乧乧偵娭偡傞偁偔傑偱壢妛揑側丄慡柺揑側擣幆偑昁慠揑偵梫媮偝傟傞乿乮塱揷峀巙乽桞暔巎娤島榖乿嶰榋巐暸丄朤揰偼昅幰乯丅傕偪傠傫丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺悽奅娤偑巇忋偘傜傟傞偵偼丄偦偺偨傔偺僀僨僆儘僊乕揑忦審乮揘妛丄幮夛壢妛摍乆偵偍偗傞廬慜偺払惉乯傕晄壜寚偱偁傞丅偟偐偟偦偆偟偨僀僨僆儘僊乕揑忦審偐傜惓偵僾儘儗僞儕傾乕僩偺悽奅娤偑宍惉偝傟偨偲偄偆偙偲偼丄屻幰偺楌巎揑抧埵偺慠傜偟傓傞偲偙傠偱偁傝丄傕偟斵摍偺摦岦丄婅朷丄棙塿偑偦傟傪梫媮偟側偄側傜偽丄寛偟偰偦偆偟偨壢妛揑悽奅娤偼巇忋偘傜傟側偐偭偨偱偁傠偆丅斵摍偺僜僔儍儕僗僠僢僋側乽孹岦惈乿偙偦偼丄偦偺擣幆偺壢妛惈傪曐徹偡傞庡懱揑忦審丄乽庡懱惈偺婯掕乿側偺偱偁傞丅 丂偙傟偵斀偟丄尰戙偺僽儖僕儑傾僕乕偑廆嫵惈丄恄旈庡媊丄庡娤庡媊丄旕崌棟庡媊摍乆傪摿挜偲偡傞斀壢妛揑悽奅娤丄榗嬋偝傟偨壢妛傪帩偭偰偄傞偲偡傟偽丄偦傟偼尰戙偵偍偗傞斵摍偺惗懚偺幮夛揑忦審丄斵摍偺奒媺揑棙奞偺拞偵丄偦偺楌巎揑丄幮夛揑崻尮傪桳偟偰偄傞丅 丂偙偺傛偆偵偟偰丄擣幆夁掱偵偍偗傞幚慔偺栶妱偺桞暔曎徹朄揑棟夝偼丄擣幆丄壢妛丄悽奅娤偺僋儔僢僙儞僴僼僩乵奒媺揑乶側惈幙偵娭偡傞娤擮傪丄擣幆庡娤偲偟偰偺奒媺偵娭偡傞娤擮偲偺晄壜暘側楢娭偵偍偄偰曪娷偡傞丅偦偟偰擣幆庡娤偑奒媺偱偁傝丄奒媺揑恖娫偱偁傞偲偄偆偙偲偼丄奺乆偺奒媺偼媞娤揑恀棟傪攃埇偟摼側偄偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄奺乆偺奒媺偼帺屓偺幚慔揑昁梫丄棙奞偑梫媮偡傞尷搙撪偵偍偄偰媞娤揑恀棟傪攃埇偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄庬乆偺奒媺偺憡堎偭偨幚慔揑昁梫偼偦傟傜偺奒媺偺悽奅娤丄擣幆懱宯偺憡堎傪惂栺偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺偙偲偼丄傕偪傠傫丄壛摗巵偑嬋夝偡傞擛偔乽擣幆偵偍偗傞曽朄偺桪埵乿乮戞巐廫嶰崋堦擇堦暸乯偲偄偆庡娤庡媊揑尒夝傪惓摉壔偡傞傕偺偱偼側偄丅擣幆偑恖娫偺堄幆傊偺媞娤揑恀棟偺斀塮偱偁傞偲偡傟偽丄擣幆偵偍偄偰桪埵傪帩偮傕偺偼惓偵幚慔傪攠夘偲偟偰堄幆偵尕乮傕偨乯傜偝傟傞媞娤揑幚嵼偱偁傝丄偦偺捈愙偺斀塮 偱偁偭偰丄巚堃曽朄 丄曽朄榑偼堗傢偽婯惂揑側傕偺偲偟偰丄偙偺捈愙偺斀塮偺棟榑揑巇忋偘偺嵺偵栶妱傪墘偠傞傕偺偱偁傞丅偩偐傜丄擣幆偺奒媺惈偲偄偆偙偲偼丄擣幆偼偡傋偰偁傟偙傟偺奒媺偺帺堄幆偩偲偄偆偙偲偱偼側偔丄奺乆偺奒媺偵偼堗傢偽愭揤揑側屌桳側巚堃斖醗偑偁傝丄偙偺斖醗偺拻宆偵傛偭偰媞娤揑幚嵼偲偼慡偔帡偰偄側偄擣幆偑峔惉偝傟傞偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄擣幆偑偦偺捈愙惈偐傜師戞偵攠夘傪宱偰奣妵乮堦斒惈乯偝傟偰峴偔夁掱偵偍偄偰丄憐憸椡偑栶妱傪墘偠丄偦傟偑偨傔偵幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶偑偦偙偵斀塮偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅傕偟乽曽朄乮巚堃曽朄乯偺桪埵乿偑塢堊乮偆傫偄乯偝傟傞偲偡傟偽丄偦傟偼擣幆偵偍偗傞 桪埵傪堄枴偡傞偺偱偼側偔偰丄巚堃曽朄偼憡堎偭偨奒媺偺擣幆懱宯傪憡堎偣偟傔傞 宊婡 偲側傞偲偄偆偙偲傪堄枴偡傞傕偺偵奜側傜側偄丅偲偙傠偱庬乆偺奒媺娫偵偍偗傞擣幆懱宯偺憡堎偼憡懳揑偱偁傝丄偙傟偵斀偟偦傟傜偺擣幆偑媞娤揑恀棟偺戝側傝彫側傝嬤帡揑側斀塮偱偁傞偲偄偆偙偲偼愨懳揑偱偁傞 丅姺尵偡傟偽丄巚堃曽朄偼丄媞娤揑恀棟偑恖娫偺堄幆偵梌偊傜傟傞偲偄偆愨懳揑側帠幚偺婎慴偺忋偱丄憡懳揑側堄媊傪帩偮偺傒偱偁傞丅柾幨榑偐傜弌敪偟偰棟榑偺僷儖僞僀儕僸僇僀僩乵搣攈惈乶傪寢榑偟偨桞暔榑偼惓偵偙偺傛偆偵庡挘偟偨偺偱偁傝丄偦偟偰偙偺揰偱儃僌僟乕僲僼庡媊丄嶰栘揘妛丄儖僇僢僠庡媊摍乆偲崻杮揑偵憡堎偡傞乮偙偺憡堎偼桞暔榑偲娤擮榑偺憡堎偩乯丅慠傞偵壛摗巵偑僷儖僞僀儕僸僇僀僩偺榑幰偵偍偗傞乽曽朄偺桪埵乿傪抐掕偡傞偲偒丄偙偺憡堎偼尒棊偝傟偰偄傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂係 丂東乮傂傞偑偊乯偭偰丄擣幆榑偵偍偗傞幚慔偺宊婡偵偮偄偰偺壛摗巵偺尒夝傪嬦枴偡傞側傜偽丄偦傟偼師偺擛偔梫栺偝傟傞丅 丂乽堦丄恖娫偺壢妛揑堄幆偼懳徾揑恀棟偺恖娫堄幆傊偺慟師揑斀塮乿偱偁傞偙偲丄乽擇丄偙偺斀塮偼恖椶偺幚慔偺峬掕偺拞偱偦傟偵攠夘偝傟偰崌棟壔偟丄怺壔偟偰峴偔偙偲丄嶰丄懳徾揑恀棟傪恖椶偺堄幆偵攠夘偡傞幚慔偼丄偦偺憤懱偵偍偄偰楌巎揑幮夛惗妶偺慡彅娭學傪宍惉偟丄屻幰偼偦傟帺恎傑偨懳徾揑恀棟偲偟偰攃埇偝傞傋偒偙偲丄巐丄恖椶偺壢妛揑堄幆偼丄懳徾揑夁掱偵偮偄偰幚徹偝傟偨尰幚揑楢娭傪帺屓偺拞偵曪愛偡傞偙偲偵傛偭偰偺傒 敪揥偡傞偙偲乿乮戞巐廫嶰崋堦擇堦=堦擇擇暸乯丅 丂偙偺戞巐偺柦戣偑丄師偺傛偆側堄枴偵丄懄偪丄壢妛揑堄幆偼幚慔偵傛偭偰専徹偝傟偮偮暔偺媞娤揑楢娭傪傑偡傑偡峀偔怺偔懆偊偰峴偔帠偵傛偭偰偺傒敪揥偡傞丄偲偄偆堄枴偵夝庍偝傟傞偲偡傟偽丄壛摗巵偺埲忋偺巐偮偺柦戣偵懳偟偰偼擛壗側傞桞暔榑幰傕摨堄偡傞偵堘偄側偄丅偩偑偙偺偙偲偼寛偟偰埲忋偺柦戣偵偍偄偰擣幆榑偵偍偗傞幚慔偺堄媊偑廩暘偵惓偟偔攃埇偝傟偰偄傞乗乗壛摗巵偺塢偆傛偆偵乗乗偲偄偆偙偲傪堄枴偟側偄丅尰戙桞暔榑偼丄偦偙偐傜堦曕恑傫偱丄奒媺偺懚嵼偡傞幮夛偵偍偄偰偼恖娫偺幚慔偼僋儔僢僙儞僴僼僩乵奒媺揑乶偱偁傝丄偙偺偙偲偺婎慴偺忋偱擣幆傕傑偨僋儔僢僙儞僴僼僩偨傜偞傞傪摼側偄偲峫偊傞丅慠傞偵偙傟偙偦偼惓偵壛摗巵偺斲擣偡傞偲偙傠偱偁傞丅 丂壛摗巵偵偁偭偰偼丄擣幆偺夁掱偵偍偄偰丄摿偵恀棟偺婯弨偲偟偰丄恖娫傊偺恖娫偺摥偒偐偗偼壗偺堄枴傕桳偣偢丄幚慔偵傛偭偰妋徹偝傟偨擣幆偺撪梕偵偼幮夛揑丄奒媺揑棙奞偼斀塮偟側偄傜偟偄丅巵偑擣幆偺楌巎揑旐惂栺惈傪擣傔傞偺偼丄傂偲偊偵乽擣幆偝傞傋偒懳徾丄乧乧偺慡懱偑丄恖娫偺幚慔偺敪揥抜奒偵墳偠偰尷掕偝傟偰偄傞乿偲偄偆堄枴偵偍偄偰偱偁偭偰丄峏偵偦偺忋偵 丄偙偺恖娫幚慔偵偍偗傞幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶偑擣幆偵斀塮偟丄偦偺撪梕傪惂栺偡傞偲偄偆堄枴偵偍偄偰偱偼抐偠偰側偄丅塢偄偐偊傟偽丄惗嶻娭學傪敳偒偵偟偰庢忋偘傜傟偨拪徾揑側惗嶻椡偑丄擣幆傪婯掕偡傞傕偺偲偟偰擣傔傜傟偰偄傞偺偱偁偭偰丄惗嶻娭學偵偍偗傞傾儞僞僑僯僘儉偼擣幆偵懳偟偰撪揑娭學傪桳偟側偄偲尒橍乮側乯偝傟傞丅壛摗巵偼丄幚慔偼乽偦偺憤懱偵偍偄偰楌巎揑幮夛惗妶偺慡彅娭學傪宍惉乿偡傞傕偺偩偲塢偄側偑傜丄偙偺乽慡彅娭學乿偑堦掕偺楌巎揑帪戙偵偍偄偰偼恖娫娫偺傾儞僞僑僯僘儉傪傕偭偰堦娧偝傟丄偦偺偙偲偑擣幆偵怺偔塭嬁偡傞偲偄偆偙偲偼擣傔傑偄偲搘椡偡傞丅 丂巵偺偐傛偆側尒夝偼丄戞堦偵丄擣幆榑偵偍偄偰栶妱傪墘偠傞尷傝偺幚慔偼挻奒媺揑側傕偺丄幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉傪挻墇偟偨傕偺偱偁傝丄戞擇偵丄偦傟偵娭楢偟偰擣幆偺庡娤偼乽弮悎巚堃乿偱偁傞偲偄偆庡挘偺拞偵昞尰偝傟偰偄傞丅 丂傑偢戞堦偺揰偵偮偄偰偄偊偽丄壛摗巵偼柧敀偵乽媞娤揑幚嵼傊偺摥偒偐偗偵偍偄偰偺傒幚慔傪岅傞尷傝偼恖椶偺幚慔堦斒乮亀恖椶惗妶偺偁傜備傞宍懺偐傜撈棫亁偣傞楯摥峴掱乯傪岅偭偰偄傞偺偩乿乮戞巐廫嶰崋堦擇幍暸乯偲偐丄乽偙偺揘妛揑擣幆偺棫応偼偨偩慡懱偲偟偰偺恖椶幚慔偺巎揑惂栺偩偗傪尰幚揑 惂栺偲偟偰抦傞偺傒偱偁傞乿乮摨忋堦擇敧暸乯偲偐丄乽恖椶偺慡幚慔偺尰幚揑宱尡偑丄擣幆偺婎慴乿偱偁傞乮摨忋堦擇嶰暸乯偲抐掕偟丄恖椶惗妶偺堦掕偺楌巎揑宍懺偑丄偐乀傞宍懺偺壓偵偍偗傞傾儞僞僑僯僘儉偑乽壢妛揑擣幆乿偺乽尰幚揑惂栺乿偲側傞偙偲傪斲擣偟偰偄傞丅 丂偮傑傝丄巵偵偁偭偰偼丄恖娫偺帺慠傊偺摥偒偐偗偺傒偑擣幆偺尰幚揑側乽巎揑惂栺乿偱偁偭偰丄恖娫偺恖娫傊偺摥偒偐偗丄幮夛傊偺摥偒偐偗丄僋儔僢僙儞丒僇儉僾乵奒媺摤憟乶偺擛偒偼傕偼傗偦偆偟偨傕偺偱偼側偄丅偲偙傠偱恖娫偼帺慠偵懳偟偰偼慡幮夛 偲偟偰摥偒偐偗傞偺偱偁偭偰丄椺偊偽僽儖僕儑傾僕乕偲僾儘儗僞儕傾乕僩偼暿乆偵 帺慠偵摥偒偐偗傞偺偱偼側偔丄偙偺椉幰偼帺慠傊偺摥偒偐偗偺庡懱偨傞幮夛偺撪晹偵偍偗傞暘楐偵奜側傜側偄偐傜丄偙偺幮夛撪晹偺暘楐偼擣幆偺乽巎揑惂栺乿偲側傞傕偺偱偼側偄偲擣掕偡傞壛摗巵偼丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺棟榑偺壢妛惈傪偙偺斵摍偺幚慔偲偺楢娭偵偍偄偰峫嶡偡傞尒抧傪庡娤庡媊偲峫偊傞偙偲偵側傞丅椺偊偽僾儘儗僞儕傾乕僩偺棟榑偼丄偦偺婎慴偲側傞幚慔偑僽儖僕儑傾揑幚慔傛傝傕慡柺揑 偱偁傞偑屘偵丄傛傝壢妛揑偱偁傝摼傞丄偲庡挘偡傞偺偼丄巵偵傛傟偽乽恖椶偺慡幚慔偺尰幚揑宱尡偑丄擣幆偺婎慴偲側偭偰偄側偄偱丄枹棃偺惗嶻椡 偺崅搙側堢惉偺扴摉幰偲偟偰婜懸偝傟傞奒憌偺幚慔偲偄偆尷掕偝傟偨幚慔偑擣幆偺婎慴偵側偭偰偄傞偙偲傪堄枴偡傞丅尰嵼傛傝傕亀峀偄亁彨棃偺尰幚 乮偮傑傝尰幚揑偱側偄傕偺乯偑擣幆偺棟擮偲側偭偰偄傞偙偲傪堄枴偡傞丅乿懄偪乽懳徾揑尰幚偲偟偰偺恖娫幚慔偍傛傃偦偺惉壥傪擣幆偺婎慴偲偡傞嵺丄偦偺慡柺揑側愯桳傪庡娤偺堄幆偺撪晹偐傜尷掕偡傞愭尡揑婯掕乿丄乗乗埥偼丄乽擣幆庡娤偵撪嵼偟偰丄巚堃偺懳徾偺峔惉晹暘傪側偟偰偄側偄幚慔丄懳徾偵椪傓偙偲偼抦偭偰偄傞偑丄懳徾偺婯掕偺壓偵帺屓傪幏乮偲傜乯偊傞偙偲偺偱偒側偄亀幮夛揑帺変亁乗乗偑丄擣幆偺惂栺偲偟偰峔憐偝傟偰偄傞偙偲傪堄枴偡傞乮戞巐廫嶰崋堦擇嶰=堦擇巐暸乯丅 丂側傞掱丄帺慠傊偺恖娫偺摥偒偐偗偺庡懱偼丄堦斒揑丄拪徾揑偵偼慡幮夛 偱偁傞偲塢偆偙偲偑偱偒傞丅偩偑嬶懱揑偵偼幮夛偼楌巎揑偵堎偭偨峔惉傪桳偟丄偦偟偰峔惉忋偺偐乀傞楌巎揑憡堎偼恖娫懳恖娫偺娭學偺憤懱偺憡堎偲偟偰昞尰偝傟傞丅塢偄偐偊傟偽丄幮夛偺撪晹揑側傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶偺庬乆偺宍懺偑庬乆偺幮夛峔惉傪摿挜偯偗傞丅偙偆偟偨楌巎揑偵屳偄偵憡堎偡傞峔惉偺榞撪偱偺傒帺慠偵懳偡傞妶摦丄楯摥偼峴傢傟傞偺偱偁傞偐傜丄楯摥偺宍懺傗慻怐偵偼丄懄偪帺慠傊偺恖娫偺摥偒偐偗偺巇曽偵偼丄幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉偑斀塮偡傞丅偩偐傜傾儞僞僑僯僘儉偵棫媟偡傞幮夛偵偍偄偰偼丄拪徾揑偵偼慡幮夛偑楯摥偺庡懱偲塢偄摼傞偲偟偰傕丄嬶懱揑偵尒傟偽楯摥乗乗暔幙揑惗嶻偲偟偰偺乗乗偐傜梀棧偟偨婑怘揑暘巕偺僌儖乕僾偑懚嵼偡傞丅戝側傞搝楆庡丄擾搝庡偍傛傃偦偺僀僨僆儘乕僌偺擛偒偑偦傟偱偁傝丄偦偟偰暔幙揑楯摥偐傜偺惛恄揑楯摥偺偙偺暘棧偑娤擮榑偺敪惗偺堦斒揑側 楌巎揑忦審偱偁傞偙偲偼乽僪僀僣丒僀僨僆儘僊乕乿偵偍偄偰偡偱偵柧敀偵巜帵偝傟偰偄傞丅乮偙偙偵丄乽戝側傞乿搝楆庡丄擾搝庡偲偄偆偺偼丄堦恖丄擇恖偺搝楆傗擾搝傪帩偭偨強偱丄楯摥偐傜梀棧偡傞偙偲偼偱偒側偄偐傜偱偁傞乯丅僾儖僕儑傾僕乕傕傑偨丄撈愯帒杮庡媊偺抜奒丄嬥梈帒杮偺僿僎儌僯乕偺妋棫偺抜奒偵偍偄偰偼丄婑怘揑惈幙傪懷傃傞偙偲偼乽帒杮庡媊嵟崅抜奒偲偟偰偺掗崙庡媊乿偺拞偱徻榑偝傟偰偄傞偲偙傠偱偁傞丅偙偺抜奒偵偍偄偰偼僽儖僕儑傾僕乕偵偲偭偰偼棙嶥愗傝偑戞堦偺惗妶忦審偲側傝丄惗嶻偺巜摫偼偦偺戙棟恖偵埾戸偝傟丄偐偔偰僽儖僕儑傾僕乕偼傑偡傑偡楯摥偐傜梀棧偟丄傑偨斵摍偺僩儔僗僩傗僇儖僥儖偼帺屓偺棙塿偺偨傔偵惗嶻傪抁弅偟偨傝丄怴偟偄媄弍揑敪柧丄壢妛揑敪尒傪晻偠偨傝偟偰丄幮夛偺尰懚惗嶻椡偵傛偭偰壜擻側傜偟傔傜傟偰偄傞懳帺慠妶摦傪慡暆揑丄慡柺揑偵揥奐偡傞偙偲傪傗傔傞丅偙偺傛偆偵偟偰帺慠傊偺摥偒偐偗偼楌巎揑偵堎偭偨宍懺傪偲傞偲嫟偵丄傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶偵傛偭偰娧偐傟偨幮夛峔惉偵偍偄偰偼丄摿偵偦偺壓岦揑敪揥婜偵偼丄偮偹偵楯摥偡傞幰偲婑怘幰偲偑懚嵼偟丄偦偟偰晉偲尃椡偲娬壣偲傪撈愯偟偰偄傞偑屘偵惛恄暥壔偺惗嶻傪巟攝偡傞婑怘幰孮偺婑怘揑惗妶丄幚慔偼摨帪偵偙偺惛恄暥壔丄僀僨僆儘僊乕偵戅攑揑丄斀壢妛揑怓嵤傪晩梌偡傞丅尰戙偺僽儖僕儑傾壢妛偵偍偗傞戅攑揑孹岦傗丄斀媄弍庡媊偺擛偒偼丄偙偆偄偆帠忣偲偺楢娭傪敳偒偵偟偰偼愢柧偝傟摼側偄丅 丂僾儘儗僞儕傾乕僩偵偮偄偰偄偊偽丄斵摍偼帒杮庡媊偺壓偱偼帒杮壠偵屬梡偝傟傞偙偲偵傛偭偰偺傒帺慠偵摥偒偐偗偰偄傞偲塢偆偙偲偼偱偒側偄丅偩偑楯摥偵傛偭偰惗妶偡傞斵摍偼丄乮仸嘊壓慄晹偼屻偵扙棊曗擖仺乯堦斒偵帒杮庡媊偺偁傜備傞僼傽乕僛乵抜奒乶傪捠偠偰旐廂庢幰偲偟偰壛埑偝傟傞偽偐傝偱側偔丄摿偵壓岦揑敪揥偺僼傽乕僛偵偁傞僽儖僕儑傾僕乕偵傛偭偰巜椷偝傟傞丄帺慠傊偺摥偒偐偗偺曃嫹壔乗乗惗嶻椡偺悈弨偵斾妑偟偰偺乗乗偺偨傔偵嵟傕擸傑偝傟傞奒媺偱偁傝乮仸嘋屻偵壓慄晹偺傛偆偵掶惓仺乯擳帄婏宍壔乮椺偊偽戝廜偺徚旓傪栚摉偰偵偣偸孯廀岺嬈偺堎忢側斏塰偺擛偒乯偺偨傔偵偨偊偑偨偔丄廬偭偰斵摍偼僽儖僕儑傾揑惗嶻偵懳偡傞斸敾幰偲側傝丄傑偨偐乀傞惗嶻偺婎慴偺忋偵棫偮僽儖僕儑傾帺慠壢妛偵懳偟偰偝偊傕斸敾揑偲側傝摼傞丅斵摍偼帺慠壢妛傊偺廆嫵揑悽奅娤傗恄旈庡媊偺摫擖偵偼壗摍偺棙塿傪桳偣偢丄廬偭偰斵摍偺帺慠娤 偼丄帒杮庡媊壓偱偼枹偩僽儖僕儑傾帺慠壢妛偲尐傪暲傋傞枠偵嬶懱壔 偝傟側偄偲偟偰傕丄屻幰傛傝傕堦憌壢妛揑 偱偁傝摼傞偟丄尰偵偦偆偱偁傞丅 丂偙偺傛偆偵丄帺慠擣幆偵偍偄偰尰戙僽儖僕儑傾僕乕偑戅攑揑孹岦傪帵偟偰偄傞偙偲偼丄惗嶻椡偺尰敪揥悈弨偵斾偟偰偺丄斵摍偺棙塿偑愝掕偡傞懳帺慠妶摦乮惗嶻乯偺尷奅偺嫹瑗壔偺帠幚偲枾愙偵寢傃偮偄偰偄傞偟丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺帺慠娤偺壢妛惈偼丄斵摍偺尰戙偺懳帺慠妶摦偑傛傝慡柺揑偱偁傞偲偄偆偙偲乮壛摗巵傕塢偆傛偆偵丄偙傟偼枹棃偺偙偲偩乯偐傜偱側偔丄斵摍偑僽儖僕儑傾揑惗嶻偺桷攑乮仸嘍屻偵壓慄晹偺傛偆偵掶惓仺乯嬊尷惈偵懳偡傞斸敾幰偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜婣寢偝傟傞丅偮傑傝帺慠傊偺摥偒偐偗偺庡懱偼慡幮夛丄慡恖椶偱偁傞丄偲拪徾揑偵婯掕偡傞偙偲偱偼側偔偰丄偙偺摥偒偐偗偵偍偗傞庬乆偺奒媺偺楌巎揑偵摿庩側抧埵丄惗妶忦審傪嬶懱揑偵妋擣偡傞偙偲偑丄弶傔偰帺慠擣幆偺婎慴偵墶乮傛偙偨乯傢傞幚慔偺堄媊傪柧妋側傜偟傔傞丅懄偪丄恖娫傊偺恖娫偺摥偒偐偗丄恖娫娭學傪奜偵偟偰丄帺慠傊偺偦偺摥偒偐偗傪拪徾揑偵庢傝偩偟丄偦傟偩偗傪擣幆敪揥偺婎慴偲偡傞壛摗巵揑尒夝偼堦柺揑丄宍帶忋妛揑偱偁偭偰丄擣幆偺楌巎傪揔墳揑偵夝柧偡傞偙偲偑偱偒側偄丅 丂壛摗巵偵偲偭偰峏偵搒崌埆偄偙偲偼丄恖娫娭學偑擣幆偺懳徾偲側傞幮夛壢妛偵偍偄偰偼丄擣幆夁掱偺炄濿乮偙偆偐傫乯偨傞幚慔丄乗乗僋儔僢僙儞丒僇儉僾乵奒媺摤憟乶乗乗偑丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺懁偵偁偭偰偼丄幮夛敪揥偺媞娤揑孹岦傪戙昞偟丄偙偺敪揥偵懳偟偰僽儖僕儑傾僕乕傛傝傕傛傝儔僕僇儖偵丄傛傝崻掙揑偵 嶌梡偡傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅慡幮夛偺敪揥孹岦傪戙昞偟丄偦傟偵崌抳偡傞偑屘偵丄偦傟傪傛傝崻掙揑偵梙傝摦偐偡斵摍偺妶摦偼丄僽儖僕儑傾壢妛傛傝傕傛傝崻掙揑側丄怺偄丄慡柺揑側幮夛擣幆傪梫媮偟丄壜擻側傜偟傔丄嶻弌偡傞丅偩偐傜僾儘儗僞儕傾乕僩偺悽奅娤偑嵟弶偵幮夛擣幆乮偍傛傃偦傟偲偺晄壜暘側楢娭偵偍偄偰丄偦偺曽朄榑偲偟偰偺揘妛乯偺椞堟偵偍偄偰妋棫偝傟丄僽儖僕儑傾幮夛壢妛乮偍傛傃揘妛乯偲暲傫偱丄偦傟偵懳偡傞桪埵傪偝偊帵偟側偑傜丄嬶懱揑偵揥奐偝傟偰偒偨偙偲偼丄寛偟偰嬼慠偱側偄丅偲偙傠偱丄幮夛娤傗揘妛偼帺慠娤偲岎屳偵塭嬁偟偰丄摑堦揑側悽奅娤偑宍惉偝傟傞偺偱偁傞偐傜丄尰戙幮夛偵偍偄偰偼惓偵擇偮偺懳岦偡傞壢妛丄擇偮偺悽奅娤偑懚嵼偡傞偺偱偁傞丅 丂偙偆偄偆尒夝偑壛摗巵偺嬋夝偡傞擛偔丄擣幆懳徾偨傝摼側偄乽幮夛揑帺変乿偩偺丄乽彨棃偺尰幚乿偩偺偐傜尰戙桞暔榑偺悽奅娤偺桪埵惈傪墘銏偡傞傕偺偱側偄偙偲偼丄傕偼傗帺柧偱偁傠偆丅偙偺桪埵惈偑丄尰嵼偺尰幚偺拞偵丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺尰嵼偺惗妶偺拞偵偦偺幮夛揑婎慴傪帩偭偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄傕偼傗偙傟埲忋偺愢柧傪梫偟側偄偲巚偆丅 丂壛摗巵偺寚娮偼丄恖娫傊偺恖娫偺摥偒偐偗傪丄擣幆榑偵偲偭偰柍墢側傕偺偲偟偰柍帇偟偨揰偵偁傞丅巵偺榑棟偐傜偼丄僽儖僕儑傾揑悽奅娤偲桞暔曎徹朄揑悽奅娤偵偮偄偰丄屻幰傪傛傝榑棟揑偵忋埵偺抜奒偵偁傞傕偺偲婯掕偡傞偙偲偼偱偒偰傕丄壗屘偵慜幰偼惓偵僽儖僕儑傾僕乕偑屌幏偟丄屻幰偼僾儘儗僞儕傾乕僩偵傛偭偰庴梕偝傟傞偐偼愢柧偝傟摼側偄丅壛摗巵偼丄偙偆偄偆帠幚偺愢柧偼巎揑桞暔榑偺巇帠偨傞偵巭傑傝丄擣幆榑偵偲偭偰柍娭學偩偲峫偊傞偩傠偆偐丠丂偩偑擣幆偺楌巎揑敪揥偵偍偗傞偙偺堦戝帠幚傪夝柧偟側偄傛偆側擣幆榑偼壢妛惈傪帩偪摼偢丄壢妛偺晄曃晄搣惈偵娭偡傞僽儖僕儑傾揑娤擮偵曭巇偡傞傕偺偵偡偓側偄丅 丂傕偪傠傫丄屷乆偼壛摗巵偑偙偆偟偨僽儖僕儑傾揑娤擮偵壛惃偟傛偆偲堄恾偟偰偄傞偲偼巚傢側偄丅媝乮偐偊乯偭偰丄巵偵偁偭偰偼丄曎徹朄揑桞暔榑偺棟榑揑桪埵丄偦偺媞娤揑恀棟惈傪嫮挷偟丄偦傟偼壗傜偐偺庡娤揑惂尷偵傛偭偰惂尷偝傟偨傕偺偱偁傞偲偄偆尒夝偵懳偟偰丄偦偺媞娤揑恀幚惈傪梚岇偟傛偆偲偡傞椙偒堄恾偑尰戙桞暔榑偺撪梕傪僾儘儗僞儕傾乕僩偺幚慔揑棙奞偵寢傃偮偗傞乽孹岦惈乿偺攔彍傊偲巵傪扙慄偣偟傔偨強埲乮備偊傫乯偺傕偺偱偁傞丅偩偐傜巵偼丄尰戙桞暔榑偑帠暔偺揙掙揑偵媞娤揑側攃埇傪摿挜偲偟丄恖椶偺宱尡偺憤懱傪偐乀傞媞娤揑攃埇偵晅偡偲嫟偵丄傑偨僾儘儗僞儕傾乕僩偺妶摦偦偺傕偺傪傕媞娤揑擣幆偺懳徾偨傜偟傔傞壢妛揑側揘妛偱偁傞偙偲傪丄偔傝曉偟嫮挷偟偰偄傞丅偙傟偼屷乆傕嫮挷偡傞偙偲偱偁傝丄屷乆偲偄偊偳傕尰戙桞暔榑偑媞娤揑恀棟傪尨棟揑偵榗嬋偡傞庡娤揑梫慺偵寢傃偮偄偰偄傞偲偐丄慡恖椶巎偐傜愗棧偝傟偨僾儘儗僞儕傾乕僩偺宱尡偩偗偺暘愅傪帠偲偡傞偲偐丄幚慔偼棟榑偺懳徾偨傝摼側偄埥傞忚梋傪桳偡傞偲偄偆堄枴偱棟榑乽傛傝埲忋乿偺傕偺偩偲偐庡挘偟偰偄傞偺偱偼側偄丅偨偩僾儘儗僞儕傾乕僩偺幚慔偼丄恖椶偺慡宱尡偺暘愅偵摉偭偰傕丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺幚慔偦偺傕偺偺暘愅偵摉偭偰傕丄屭椂偡傞偲偙傠側偒棪捈側壢妛惈傪壜擻側傜偟傔丄妿偮梫媮偡傞傕偺偩偲偄偆枠偱偁傞丅偦偟偰壢妛惈傪梫媮偡傞偙偺幚慔偑偦傟帺恎傑偨棟榑偺懳徾偱偁傞偙偲偼丄屷乆偑偦傟偵偮偄偰偐偔傕塢堊偟偰偄傞尷傝丄帺柧偺慜採偱偁傞丅梫偡傞偵壛摗巵偼丄擣幆庡娤偲偟偰偺僾儘儗僞儕傾乕僩偺楌巎揑抧埵偐傜婣寢偝傟傞偦偺乽庡娤惈偺婯掕乿傪丄斵摍偺棟榑偺媞娤揑恀棟惈偺曐徹偲尒橍乮側乯偡戙傝偵丄偁傜備傞媞娤揑恀棟惈偼乽庡懱偺婯掕乿偲椉棫偣偢丄乽堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧乿偐傜夁掱傪乽昡壙乿偡傞偙偲偼尨棟揑偵 擣幆偺媞娤惈偲椉棫偟摼側偄偲抐掕偡傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺庡娤揑堄恾偲偼斀懳偵丄壢妛偺晄曃晄搣惈偺僽儖僕儑傾揑娤擮傪媞娤揑偵偼曎柧偡傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅乮埲壓師崋乯 乲埲壓乽桞暔榑尋媶乿俆係 (1937.4乯宖嵹乴 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俆 丂擣幆夁掱偺婎慴偲側傞幚慔偐傜恖娫憡屳偺摥偒偐偗傪彍奜偟丄擣幆庡娤偺僋儔僢僙儞僴僼僩乵奒媺揑乶側惈幙傪斲掕偡傞側傜偽丄偙偺庡娤偼惗妶忋偺棙奞傗摦岦偐傜撈棫偲偄偆堄枴偺乽弮悎側乿丄僄乕僥儖揑側傕偺丄巚堃堦斒丄堄幆堦斒傊偲忲棷偝傟傞偙偲偼摉慠偱偁傞丅偩偐傜壨搶巵偼丄擣幆庡娤傪惗偗傞幮夛揑恖娫乮巵偺偄傢備傞乽庡懱乿乯偐傜愗棧偝傟偨乽弮悎巚堃乿丄乽棟榑揑乮堗傢偽弮悎乯巚堃偲偟偰偺堄幆乿偲偟偰婯掕偡傞乮戞巐嬨崋敧敧暸丄敧嬨暸乯丅偦偙偱丄恖娫偺幮夛惗妶偼傕偪傠傫丄姶忣傗堄巙傕擣幆庡娤偺寳奜偵愃乮偟傝偧乯偗傜傟丄乽庡娤乿偵偲偭偰奜揑側傕偺偲婯掕偝傟偰偄傞丅 丂傕偪傠傫丄恖娫偺堄幆傊偺懳徾偺斀塮偲偟偰偺擣幆偼丄巚堃偺宍懺偵偍偄偰嵟傕揟宆揑偵梌偊傜傟傞丅偦偟偰巚堃偼丄懳徾傪偦偺媞娤揑楢娭偵偍偄偰懆偊傛偆偲偡傞摦岦傪摿挜偲偟丄偦傟偵娭楢偟偰媞娤揑恀棟傪戝側傝彫側傝偺掱搙偵帺傜偺撪梕偵帩偮丅偦偆偄偆堄枴偱偼巚堃偼乽弮悎乿偱偁傝摼傞丅乮壨搶巵傕尵梩偺忋偱偼乽弮悎巚堃乿偺偐傛偆側堄枴傪彸擣偼偟偰偄傞乯丅僄儞僎儖僗偺塢偭偨乽弮悎巚堃乿偲偼丄惓偵偐乀傞堄枴偺傕偺偱偁傞丅偩偑偙偺偙偲偼乽弮悎巚堃乿偺傒 偑擣幆庡娤偱偁傞偙偲傪堄枴偣偢丄乽弮悎巚堃乿偑恖娫憡屳偺幮夛揑娭學偵傛偭偰惂栺偝傟丄惗偗傞恖娫幚慔丄惗偗傞恖娫亖庡懱偺婡擻偲偟偰丄偦傟偵傛偭偰惂栺偝傟傞偙偲傪攔彍偟側偄丅懄偪丄偦偺偙偲偼丄擣幆庡娤傪惗偗傞慡恖娫偲偟偰丄枖偼偙偺慡恖娫偲偺摑堦偵偍偄偰丄峫嶡偡傞昁梫傪攔彍偟側偄丅慠傞偵壨搶巵偵偁偭偰偼乽弮悎巚堃乿偼乽庡懱惈偺婯掕乿傪桳偣偢丄偨偩乽擣幆偝傞傋偒懳徾偑乧乧恖娫幚慔偺敪揥抜奒偵墳偠偰尷掕偝傟偰偄傞乿乮戞巐嶰崋堦擇擇暸乯偙偲偵傛偭偰丄塢偄偐偊傟偽擣幆偝傟摼傞懳徾斖埻丄嵽椏偑惗嶻椡偺悈弨偵墳偠偰尷掕偝傟偰偄傞偙偲偵傛偭偰偺傒楌巎揑偵惂栺偝傟傞傕偺偵偡偓偢丄偡偱偵愢柧偟偨傛偆偵丄偦偺楌巎揑旐惂栺惈偼惓偵乽弮悎巚堃乿偺撪梕偑幮夛揑娭學丄恖娫娫偺傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶偵傛偭偰惂栺偝傟傞揰偵偁傞偲偄偆偙偲偼斲掕偝傟丄廬偭偰乽弮悎巚堃乿偼偙乀偱偼恖娫偺幮夛惗妶偺棙奞傗摦岦偵懳偟偰晄曃晄搣偲偄偆堄枴偱丄僇儞僩庡媊揑堄枴偱乽弮悎乿側傕偺偲側傜偞傞傪偊側偄丅 丂尦棃丄巚堃枖偼抦揑擻椡傪擣幆庡娤偲偡傞尒夝偼丄屆戙偵偍偄偰丄恀棟偺栤戣丄擣幆偺媞娤惈偺栤戣偑採婲偝傟偨偲偒偐傜丄偦傟偵懳偡傞夝摎偲偟偰偁傜傢傟偨偺偱偁偭偰乮僜僋儔僥僗=僾儔僩儞乯丄抦揑擻椡埲奜偺宊婡偑擣幆夁掱偵撪嵼 偟丄擣幆庡娤偺峔惉梫慺偲側傞偲偄偆尒夝偼丄嬤戙偵側偭偰弶傔偰柧妋偵採婲偝傟偨丅廫幍=廫敧悽婭偺宱尡榑幰偲桞暔榑幰偼幚尡丄宱尡偺擣幆榑揑堄媊傪柧妋側傜偟傔丄僿乕僎儖偼娤擮榑揑偵丄帺堄幆偺楯摥偲偟偰棟夝偝傟偨恖娫妶摦傪擣幆榑偵摫擖偟丄偐乀傞妶摦偺庡懱傪擣幆庡娤偲偟偰棟夝偟丄傑偨偄傢備傞怱棟庡媊幰偼堄巙傗姶忣偑擣幆偵媦傏偡塭嬁傪妋擣偟偨乮偩偑怱棟庡媊幰偼丄柾幨榑偺尒抧偺寚擛偺屘偵丄恀棟偺栤戣偵偍偄偰憡懳榑偺埫徥偵忔傝忋偘偨乯丅僼僅僀僄儖僶僢僴偼丄恖娫偺梸媮丄惗妶傪擣幆榑偵擖傟崬傒丄梸媮偟丄惗妶偡傞恖娫傪擣幆庡娤偲偟偰懆偊丄嵟屻偵桞暔巎娤偼丄恖娫偺梸朷丄惗妶丄摦岦偑幮夛揑丄楌巎揑偵惂栺偝傟傞偙偲傪柧敀側傜偟傔丄擣幆庡娤傪幮夛揑丄楌巎揑恖娫丄奒媺揑恖娫偲偟偰懆偊傞偲偙傠枠摓払偟偨丅尰戙桞暔榑偺擣幆榑偼丄惓偵桞暔巎娤偵傛偭偰妋棫偝傟偨偙偺恖娫娤偐傜弌敪偡傞偺偱偁傞丅 丂傕偪傠傫丄尰戙桞暔榑偺擣幆榑偼丄恖椶妛偱傕丄桞暔巎娤偱傕丄堦斒偵幮夛壢妛偱傕側偔丄傑偨怱棟妛偱傕側偄偐傜丄偦傟偼惗偗傞恖娫偺慡柺揑尋媶偵廬帠偡傞傕偺偱偼側偄丅偦傟偼傗偼傝丄僄儞僎儖僗揑堄枴偺乽弮悎巚堃乿偺曽柺傪尋媶偺拞怱僥乕儅偲偡傞傕偺偱偁傞丅偩偑乽弮悎巚堃乿偼惗偗傞恖娫偺婡擻偱偁傞尷傝丄偦傟偼偙偺恖娫偺慡幚慔偲偺楢娭偺壓偵丄屻幰偲偺摑堦偵偍偄偰峫媶偝傟側偗傟偽側傜側偄丅偦偆偟偰弶傔偰丄乽弮悎巚堃乿偺婎慴偵墶乮傛偙偨乯傢傝丄偦傟傪惂栺偡傞幮夛揑娭學丄慡恖娫妶摦偺堄媊偼攃埇偝傟摼傞丅 丂偲偙傠偱擣幆庡娤傪幮夛揑恖娫偲尒橍乮側乯偟乮偙偺偙偲偼傕偪傠傫丄庡娤偑帺屓帺傜傪傕棟榑偺懳徾偲側偟偆傞偙偲傪攔彍偟側偄丅庡娤偲媞娤偺嵎暿傕傑偨憡懳揑偱偁傞乯丄巚堃傪偦偺婡擻偲偟偰峫嶡偡傞偵摉偭偰偼丄桞暔巎娤偺搚戜偺忋偱丄恖椶偺擣幆偺敪払巎 傪媶柧偡傞偲嫟偵丄屄乆偺恖娫偺堄幆撪偵偍偄偰巚堃偑婡擻偡傞応崌偺怱棟夁掱 傪媶柧偡傞偙偲偑昁梫偲側傞丅擣幆庡娤偑扨偵乽弮悎巚堃乿偵娨尦偝傟傞傕偺偱側偔丄恖娫偺慡摦岦偑丄廬偭偰姶忣傗堄巙傕擣幆夁掱偵偍偄偰栶妱傪墘偠傞埲忋丄擣幆榑偼怱棟妛側偟偵偼嵪傑偣側偄 丅愭偒偵尵媦偟偨嬻憐丄憐憸偺栶妱偺擛偒偼丄奜側傜偸怱棟妛揑尋媶偵傛偭偰嬶懱揑偵夝柧偝傞傋偒傕偺偱偁傞丅擣幆偺怱棟揑夁掱 偐傜傒偰嬻憐擳帄憐憸偲屇偽傟傞梫場偼丄恖乆偺楌巎揑偵宍惉偝傟偨悽奅娤 偑丄傛偭偰傕偭偰擣幆偺怴偨側憂憿妶摦偵夘擖偡傞偲偙傠偺怱棟揑偺宍幃丄忦審偱偁傞偲塢偆偙偲偑偱偒傞丅偲偄偆偺偼丄姶惈揑昞徾傪壢妛揑擣幆偵巇忋偘傞応崌偵丄偙傟傜偺昞徾傪婛摼偺悽奅娤枖偼曽朄榑偺壓偵曪愛偡傞巚堃偺摥偒偼丄憐憸乮枖偼乽峔憐椡乿偲塢偭偰傕傛偄偩傠偆乯偺宊婡傪曪娷偡傞偐傜偱偁傞丅偦偟偰偡偱偵弎傋偨傛偆偵丄偙偺宊婡傪捠偟偰恖娫偺幚慔忋偺棙奞傗摦岦偑擣幆撪梕偵斀塮偟摼傞偺偱偁傞偐傜丄擣幆夁掱偺怱棟妛揑尋媶偼惗偗傞恖娫亖庡懱丄偦偺慡摦岦偑擣幆偺宍惉傪惂栺偡傞夁掱傪夝柧偡傞丅乮怱棟庡媊偼丄偙偺応崌丄戞堦偵丄擣幆偑媞娤偺柾幨偱偁傞偙偲傪柍帇偡傞偙偲偵傛偭偰丄戞擇偵丄擣幆傪惂栺偡傞庡娤揑亖怱棟揑梫慺傪恖娫偺幮夛惗妶偺嶻暔偲偟偰懆偊側偄偙偲偵傛偭偰丄庡堄榑丄忣堄庡媊偵揮棊偡傞乯丅 丂慠傞偵壛摗亖壨搶巵偺強榑傪堦娧偟偰偄傞傕偺偼丄恖娫妶摦丄庡懱傕傑偨擣幆偺懳徾偲偟偰媞娤揑偵暘愅偝傟側偗傟偽側傜側偄乮偙偺偙偲偵屷乆偑斀懳偟偰偄傞偐偺擛偔壛摗巵偑鎤乮偟乯偄傞偺偼晄摉偱偁傞乯偲偄偆庡挘偩偗 偱偁傝丄姶忣傗堄巙偼惓偟偄擣幆偵攠夘偝傟偰傛傝媞娤惈傪妉摼偡傞偲偄偆庡挘偩偗 偱偁偭偰丄偦偺斀柺偺恀棟乗乗懄偪惗偗傞恖娫偺妶摦丄摦岦丄婅朷偑乽弮悎巚堃乿偺摥偒偵夘擖偟丄擣幆夁掱偵撪嵼偟丄擣幆偺撪梕偵幮夛揑傾儞僞僑僯僘儉乵懳棫丒揋懳娭學乶乮偐乀傞傕偺偑懚嵼偡傞尷傝乯傪斀塮偣偟傔丄恖娫偺忣堄偑巚堃偲棈傒崌偄丄巚堃偵嶌梡偟丄偦偟偰忣堄偼偦偺惈幙偺擛壗偵傛偭偰擣幆偺悇恑偺宊婡偲傕側傟偽媡峴偺宊婡丄瀪瀲乮偟偭偙偔乯偲傕側傞偲偄偆恀棟乗乗偺彸擣偼娤擮榑偲偟偰愃乮偟傝偧乯偗傜傟丄廬偭偰乽弮悎巚堃乿偲堄巙傗姶忣偲偺娫偺岎屳嶌梡 偺尋媶丄恖娫偺慡惗妶丄慡摦岦偑乽弮悎巚堃乿偵媦傏偡嶌梡偺媶柧丄堦岥偵偄偊偽擣幆偺怱棟揑夁掱 偺媶柧乗乗奒媺杮擻傑偱傕峫椂偵擖傟偰偺乗乗偺巇帠偼丄擣幆榑偵偲偭偰柍梡側傕偺偲偝傟傞丅 丂偦偙偱乽弮悎巚堃乿偼丄恖娫偺惗偗傞惗妶傗丄偦傟偵傛偭偰婯掕偝傟傞奒媺怱棟偲偺楢娭偵偍偄偰峫媶偝傟傞昁梫偼側偄偙偲偵側傞丅偩偐傜壛摗巵偑擣幆榑偵懳偡傞巎揑桞暔榑偺乽峷專乿傪擣傔丄恖娫妶摦偺擣幆偵懳偡傞堄媊傪擣傔傞偲偟偰傕丄偦傟偼扨偵偙偺妶摦偑乽弮悎巚堃乿偺奜晹偱 丄擣幆偵懳偟偰懳徾傪乽妋棫乿偡傞偲偄偆堄枴偵偍偄偰偱偁偭偰丄乽弮悎巚堃乿偺摥偒偦偺傕偺偵塭嬁偟丄擣幆夁掱偺撪嵼揑宊婡偲側傞偲偄偆堄枴偵偍偄偰偱側偄偙偲偼塢偆枠傕側偄丅偦偆偩偲偡傟偽丄偙偺応崌丄乽弮悎巚堃乿偺尋媶偑丄擣幆榑揑尋媶偑丄榑棟庡媊揑 孹岦傪懷傃傞偙偲偼帺柧偱偁傞丅偙偺榑棟庡媊偼丄壛摗巵偵偁偭偰偼丄巵帺恎偺嫮挷偡傞柾幨榑 偐傜奜傟偨娤擮榑偵傑偱摓払偡傞丅 丂乽揘妛偺懳徾偼丄堦斒偵岆夝偝傟偰偄傞擛偔丄慡懱偲偟偰偺悽奅偺堦斒朄懃側偳偱偼側偄丅揘妛偼丄壢妛偐傜偦偺撪梕傪幪徾偟偨偁偲偵巆傞婯掕丄壢妛偺宍幃丄弮悎巚堃偺婯掕傪懳徾偲偡傞乿乮戞巐嶰崋堦擇榋暸乯丅 丂乽壢妛偼幚嵼悽奅傪擣幆偡傞丅揘妛偵傕偟尋媶偡傋偒懳徾偑巆偭偰偄傞側傜幚嵼悽奅偱側偔丄偦傟傪擣幆偡傞壢妛偦偺傕偺偑懳徾偱偁傞丅幚嵼偺塣摦朄懃傪尋媶偡傞偺偑壢妛偱偁傝丄壢妛偺塣摦朄懃懄巚堃傑偨偼恖娫摢擼偺慡塣摦偺朄懃傪尋媶偡傞偺偑揘妛乮榑棟妛曎徹朄乯偱偁傝暿柤擣幆榑偱偁傞乿乮乽桞尋僯儏乕僗戞榋巐崋乯丅 丂偙乀偱壛摗巵偑丄乽恖娫摢擼偺慡塣摦偺朄懃乿偺尋媶傪塢堊偟偨偲偙傠偱丄偦傟傕幚偼惗偒偨恖娫亖庡懱偐傜暘棧偣偟傔傜傟偨乽弮悎巚堃乿偺尋媶偵婣拝偡傞偙偲偼丄愭偒偺愢柧偵傛偭偰柧偐偱偁傞丅偲偙傠偱偙偺乽弮悎巚堃偺婯掕乿丄乽壢妛偺宍幃乿丄乽壢妛偺塣摦朄懃乿傪乽悽奅偺堦斒朄懃乿偐傜丄乽幚嵼悽奅偺擣幆乿偐傜愗棧偟丄偦傟偲婡夿揑偵嬫暿偡傞揰偵丄娤擮榑丄僇儞僩揑榑棟庡媊丄柾幨榑偺斲掕丄傊偺揮棊偑偁傞丅尦棃丄壛摗巵偵偁偭偰偼丄乽庡懱惈偺婯掕乿偐慠傜偞傟偽乽媞娤惈乿丄乽悽奅偺堦斒朄懃乿偐慠傜偞傟偽巚堃朄懃丄偲偄偭偨晽側宍帶忋妛揑側擇幰愶堦偑摿挜揑偱偁傝丄偙傟傜偺懳棫暔傪曎徹朄揑摑堦 偵偍偄偰尒傞娤揰偑寚擛偟偰偄傞偙偲偑摿挜揑偱偁傞丅偦傟偑偨傔偵丄乽悽奅偺堦斒朄懃乿偼丄堦搙傃攃埇偝傟傞傗丄巚堃偺朄懃丄斖醗偲偟偰摥偔偺偱偁傝丄廬偭偰曎徹朄乮擣幆榑丄榑棟妛乯偺懳徾偲側傞巚堃偺朄懃傕幚幙忋幚嵼悽奅偺堦斒朄懃偱偁傝丄偦偺柾幨偱偁傞乮傕偪傠傫丄柾幨偡傞摥偒偦偺傕偺偼巚堃偵屌桳偱偁傞偲偼偄偊乯偲偄偆柾幨榑偑愃偗傜傟傞偺偱偁傞丅慠傞偵僄儞僎儖僗偼曎徹朄傪婯掕偟偰丄乽奜奅暲傃偵恖娫巚堃偺塣摦偺堦斒朄懃偵娭偡傞壢妛乿側傝偲偟丄偙偺擇偮偺朄懃宯楍偼乽昞尰忋乿偱偼堎傞偑乽幚幙忋乿偱偼乽摨堦乿偩偲塢偭偰偄傞乮柾幨榑偵廬偭偰丅乽僼僅僀僄儖僶僢僴榑乿乯丅摨偠偔乽揘妛僲乕僩乿偺挊幰傕丄乽曎徹朄偼恖娫偺屽惈偺拞偵偁傞偺偱偼側偔丄亀棟擮亁偺拞偵丄懄偪媞娤揑尰幚偺拞偵偁傞乿偲塢偄丄乽暔偦偺傕偺丄帺慠偦偺傕偺丄帠徾偺恑峴偦偺傕偺偺曎徹朄乿偵偮偄偰岅傝丄乽榑棟妛偼奜揑側巚堃宍幃偵娭偡傞妛偱偼側偔偰丄乧乧悽奅偺慡嬶懱揑撪梕偲偦偺擣幆偲偺敪揥偺朄懃偵娭偡傞妛偱偁傞乿偲婯掕偟偰偄傞丅 丂壛摗巵偑丄偙偺傛偆偵丄曎徹朄偑悽奅偺堦斒揑塣摦朄懃偺妛偱偁傞偙偲傪斲掕偟偨偨傔偵丄巚堃朄懃傪偦傟偲慡偔暿屄偺傕偺偲抐掕偟偰乮偩偑椺偊偽懳棫暔偺摑堦偺朄懃丄幙偲検偺岎屳揮堏偺朄懃丄偦偺懠偺曎徹朄偺朄懃傗斖醗偑乽悽奅偺堦斒朄懃乿偱側偄偲偼丄壛摗巵偲偄偊偳傕塢傢側偄偵堘偄側偄乯柾幨榑偵攚斀偟丄僇儞僩揑亖榑棟庡媊揑乽擣幆斸敾乿偺懁傊孹幬偟偨偺偼丄悽奅偺楢娭傪巚曎揑偵峔惉偟偨媽揘妛偺巰柵偵娭偡傞僄儞僎儖僗偺柦戣傪丄乽堦偮偺扨弮側悽奅娤 乿乮乽斀僨儏乕儕儞僌榑乿戞堦曆丄戞敧復乯偺斲掕丄懄偪悽奅偺堦斒朄懃偺棟夝偲偟偰偺曎徹朄偺斲掕丄偲偄偆堄枴偵夝庍偟偨偐傜偱偁傞丅偙偆偄偆夝庍偵偍偄偰丄壛摗巵偼幚徹庡媊偺曃岦偵偝偊娮偭偰偄傞丅巵偼塢傢傟傞乗乗 丂乽恀棟偼丄恀偺抦幆偼丄偨乁堦偮偟偐側偄乗乗偦傟偼幚徹揑宱尡揑側壢妛偱偁傞丅懄偪 桞暔榑偱偁傞乮戞巐嶰崋堦嶰巐暸乯丅 丂乽幚嵺丄宱尡揑側帺慠擣幆偲偟偰偺帺慠壢妛偺敪揥傪慠傞偑傑乀偵懳徾揑偵暘愅偡傞偙偲傪抦傞傕偺偼丄僄儞僎儖僗偲嫟偵丄乧乧帺慠壢妛偺擣幆曽朄埲奜偵偦傟傪曗懌偟偨傝丄嫥惓偟偨傝丄巜摫 偟偨傝偡傞揘妛揑棟擮傪愝掕偡傞昁梫偺側偄偙偲傪丄彸擣偣偹偽側傜側偄乿乮摨忋堦嶰擇暸丅朤揰偼昅幰乯丅 丂乽偙偺攈偺榑幰乮強堗乽僷榑庒乿乗乗昅幰乯偼丄尰幚偵柾幨榑偺棫応偱悑峴偝傟偮偮偁傞帺慠偍傛傃楌巎偺宱尡壢妛傪暘愅偟側偐偭偨摉慠偺寢壥偲偟偰丄宱尡壢妛偺撪晹偵偁傞傕偺偲偟偰榑棟擳帄曎徹朄傪钁柧乮偣傫傔偄乯偟摼偢丄揘妛偲偟偰偺偦傟傪偙偺宱尡壢妛偺奜 偁傞偄偼忋偵愝掕偡傞乿乮摨忋堦嶰擇暸丅朤揰偼昅幰乯丅 丂僄儞僎儖僗偼丄廃抦偺偛偲偔丄乽撈摿側壢妛偺壢妛乿乮乽斀僨儏乕儕儞榑乿丄戞堦曆戞敧復乯丄乽懠偺壢妛偺忋偵埵偡傞揘妛乿丄乽憡懳揑楢娭偵娭偡傞摿庩側壢妛乿乮摨忋彉愢乯偺巰柵偵偮偄偰岅傝丄乽堦偮偺扨弮側悽奅娤乿偲偟偰偺乽尰戙桞暔榑乿偼偦偆偟偨媽揘妛偲堎偭偰乽尰幚揑側彅壢妛偵偍偄偰妋徹偝傟幚徹偝傞傋偒乿傕偺偩偲塢偭偰偄傞丅偙傟偑丄壛摗巵偺塃偵堷梡偟偨彅柦戣偺墖梡偡傞偲偙偲偱偁傞丅偩偑僄儞僎儖僗偼丄尰幚揑壢妛偺拞偐傜榑棟揑側傕偺傪拪弌偟丄奣妵偡傞戙傝偵丄悽奅偺乽楢娭傪摢偺拞偱埬弌乿乮乽僼僅僀僄儖僶僢僴榑乿乯偟丄偦傟傪尰幚揑娭楢偵抲偒戙偊乮偙偺偙偲偼尰幚揑楢娭偑晄廩暘偵偟偐柧妋偵偝傟偰偍傜側偐偭偨帪戙偵偼晄壜旔揑偱偝偊偁偭偨乯丄峏偵偦傟傪尰幚揑壢妛偺墴偟偮偗偝偊偡傞媽偄帺慠揘妛傗楌巎揘妛偺巰柵傪岅偭偰偄傞偺偱偁偭偰丄尰幚揑壢妛偵偍偄偰妋徹偝傞傋偒丄廬偭偰懠柺偱偼偦傟傜偺壢妛偐傜愅弌偝傟拪弌偝傞傋偒拪徾揑丄堦斒揑側乽扨弮側悽奅娤乿丄悽奅偺堦斒朄懃偺棟夝丄懄偪堦斒揑丄拪徾揑婯掕惈偵偍偗傞悽奅偺棟夝丄懄偪曎徹朄丄偑堦屄偺壢妛丄揘妛揑壢妛偨傞偙偲傪斲掕偟偰偄傞偺偱偼側偄丅偨偩乮僿乕僎儖揑側乽壢妛偺壢妛乿偲偟偰偺揘妛丄乽懠偺壢妛偺忋偵埵偡傞乿乗乗懄偪懠偺壢妛偐傜奣妵偝傟傞戙傝偵屻幰偵帺屓傪墴偟偮偗傞乗乗壢妛偲偟偰偺揘妛偺巰柵偵偮偄偰岅偭偰偄傞偩偗偱偁傞丅偩偐傜斵偼桞暔榑揘妛傪乽幚徹揑宱尡揑側壢妛乿偵娨尦乮枖偼偦傟偲摨堦帇乯偣偢丄媝乮偐偊乯偭偰揘妛傪柍帇偡傞乽宱尡揑帺慠壢妛乿丄幚徹庡媊偑棟榑偺椞堟偵偍偄偰柍椡偱偁傞偙偲傪嵞嶰嫮挷偟乮椺偊偽壛摗巵偑偦偺朚栿幰偱偁傞偲偙傠偺乽帺慠曎徹朄乿傪尒傛乯丄宱尡壢妛傪曽朄偺忋偱乽巜摫乿偡傋偒曎徹朄偺曽朄榑揑堄媊傪嫮挷偟丄扨偵宱尡壢妛偺傒偱側偔傑偨揘妛 偺敪払巎偺媶柧偑曎徹朄偵偲偭偰昁梫偱偁傞偙偲傪庡挘偟偨丅偙偺応崌僄儞僎儖僗偑帺慠揘妛幰傗楌巎揘妛幰偲堎傞揰偼丄宱尡壢妛偺拞偵丄偦偺懳徾偺曎徹朄揑杮惈偺屘偵丄帺惗揑 偵娧偒丄撪嵼偟偰偄傞曎徹朄傪丄揘妛巎 偵偍偗傞曎徹朄揑尋媶偺惉壥偺斸敾揑愛庢偵婎乮傕偲偯乯偄偰偺丄宱尡壢妛偺敪揥偦偺傕偺偺暘愅偵傛偭偰堄幆壔偟棟榑揑偵奣妵偡傞傕偺偱偁傞偐傜偙偦丄棟榑偲偟偰偺曎徹朄偼曽朄榑揑偵栶棫偮偺偩偲峫偊偨偙偲偱偁傝丄巚曎揑曎徹朄傪宱尡壢妛偵岥庼偟傛偆偲偟側偐偭偨偙偲偱偁傞丅壛摗巵偺斀懳幰払偑屄暿揑宱尡壢妛偺奣妵偲偟偰偺揘妛偵偮偄偰岅偭偨偺傕丄偙傟偲摨偠堄枴丄宱尡壢妛偵撪嵼偡傞曎徹朄偺棟榑壔偲偄偆堄枴偱偁偭偰丄寛偟偰壛摗巵偺岆夝偡傞擛偔幚嵼悽奅偺楢娭傪乽摢偺拞偱埬弌偡傞乿揘妛丄偦偺埬弌暔傪傕偭偰宱尡壢妛傪曗懌偟偨傝嫥惓偟偨傝偡傞揘妛偵偮偄偰岅偭偰偄傞偺偱偼側偄丅 丂壛摗巵偑僄儞僎儖僗傪幚徹庡媊揑偵嬋夝偟偰偄傞偙偲偼偡偱偵柧敀偱偁傞丅桞暔榑偼幚徹壢妛偱偁傞偲偐丄偦傟偼宱尡壢妛偺乽奜乿偵偼惉棫偟摼偢丄愱傜宱尡壢妛偺撪偵懚嵼偟偰偄傞乮偩偑揘妛 偺拞偵偍偄偰偼乗乗媽偄揘妛偵偍偄偰傕乗乗曎徹朄偼宱尡壢妛偵偍偄偰傛傝傕堦憌堄幆揑偵丄慡柺揑偵揥奐偝傟偨偺偩丅椺偊偽僿乕僎儖乯偲偄偆巵偺庡挘偼丄幚徹庡媊偱偁傝丄杮幙忋偱偼揘妛偺斲掕偱偁傞丅偦傟偼丄僄儞僎儖僗偺媽揘妛巰柵愢偐傜丄乽儅儖僋僗庡媊偲偼壢妛偩乿丄屘偵揘妛偱偼側偄丄偲抐掕偟偨儈乕僯儞傗乿丄乽儅儖僋僗庡媊幰偵偲偭偰偼壢妛偐傜暿屄側寢榑偱偁傞乿偲塢偭偨僗僥僷乕僲僼偺柦戣傪憐傢偣傞丅偨偩偙偺乽尰戙壢妛偺乧乧堦斒揑側寢榑乿偑丄壛摗巵偵偁偭偰偼乽幚徹揑宱尡揑側壢妛乿偦偺傕偺偲側偭偰偄傞偩偗偺憡堎偱偁傞丅 丂壛摗巵偺偙偺傛偆側榑棟庡媊揑偍傛傃幚徹庡媊揑堩扙偼丄乽弮悎巚堃乿偼扨偵恖娫妶摦丄恖娫偦偺傕偺傪擣幆偡傞偽偐傝偱側偔丄傑偨幚偵偙偺惗偒偨恖娫偵傛偭偰丄恖娫妶摦偵傛偭偰婯掕偝傟丄撪揑偵惂栺偝傟傞偲偄偆偙偲傪斲掕偟偨寢壥偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俇 丂擣幆偺乽媞娤惈乿偲乽庡懱惈偺婯掕乿偲傪曎徹朄揑摑堦偵偍偄偰懆偊側偄壛摗巵偼丄棟榑偺僷儖僞僀儕僢僸僇僀僩乵搣攈惈乶偺栤戣偵偍偄偰幚偵柧妋偵偦偺寚娮傪業掓偡傞丅 丂棟榑偺僷儖僞僀儕僢僸僇僀僩偲偼丄棟榑揑懳棫偺攚屻偵偼恖乆偺幮夛揑懳棫偑偁傝丄恖乆偼堄幆揑偵偐柍堄幆揑偵偐棟榑妶摦偵偍偄偰堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺棙奞偵傛偭偰惂栺偝傟傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄桞暔榑幰偼堄幆揑偵堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偐傜帠徾傪乽昡壙乿偣偹偽側傜偸偲偄偆偙偲偱偁傝丄棟榑偼幚慔偵曭巇 偟丄幚嵺忋偺栚揑 偺偨傔偵尋鑢偝傟偹偽側傜偸偲偄偆偙偲偱偁傞丅偩偑偙偺偙偲偑尨棟揑 偵媞娤揑怱棟偺攃埇傪晄壜擻側傜偟傔傞偲峫偊傞偺偼僾儔僌儅僠僗僩偱偁偭偰丄桞暔榑幰偱偼側偄丅屷乆偼偡偱偵丄僾儘儗僞儕傾揑側乽尒抧乿丄乽庡懱惈偺婯掕乿偑丄擣幆偺庡娤揑榗嬋傪梌偊傞傕偺偱側偔丄媝乮偐偊乯偭偰偦偺媞娤惈偺忦審偱偁傞偺傪尒偨丅偙偙偱偼丄乽堦掕偺幮夛僌儖乕僾乿乮僾儘儗僞儕傾乕僩乯偺乽尒抧乿偐傜帠徾傪乽昡壙乿偡傞偙偲偼丄壛摗巵偑嬋夝偡傞傛偆偵乽楌巎乿偺乽媞娤揑側愢柧傪愃偗乿乮戞巐嶰崋堦擇敧暸乯傞偙偲偱偼側偔偰丄悽奅傪扨偵愢柧偡傞偺偱偼側偔偰峏偵偦傟傪曄夵偡傞栚揑偺偨傔偵丄悽奅偺崌朄懃惈傪媞娤揑偵懆偊傞偙偲偱偁傞丅 丂壛摗巵偼乽桞暔榑偼乧乧偁傜備傞弌棃帠偺昡壙偵摉偭偰棪捈妿偮岞慠偵堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偵棫偮偙偲傪媊柋偯偗傞乿偲偄偆僀儕僀僢僠偺尵梩偼丄乽帺屓偺尒抧懄偪幚慔忋偺棫媟抧傪懳徾揑側攃埇偵偍偄偰钁柧乮偣傫傔偄乯偝傟偨堦掕偺幮夛僌儖乕僾傊抲偔 丄埥偼媊柋偯偗傞乿偲偄偆堄枴偱偁傝丄乽尒抧偵棫偮乿偲偄偆偙偲偼乽摦偒偮偮偁傞堦掕偺僌儖乕僾偺幚慔偵嶲壛偡傞乿乽幚慔偺栤戣乿偱偁偭偰乽擣幆榑偺栤戣乿偱偼側偄偲抐掕偟偰偄傞乮戞巐嶰崋堦擇敧暸乯丅偙偙偱傕摿挜揑側偙偲偼丄椺偵傛偭偰丄桞暔榑幰偑帺屓偺乽尒抧乿傪偦偙偵抲偔幮夛僌儖乕僾偦偺傕偺偑乽懳徾揑側攃埇乿偵晅偣傜傞傋偒傕偺偩偲偄偆恀棟偩偗偑堦柺揑偵嫮挷偝傟丄偙偺幮夛僌儖乕僾偺乽尒抧乿偑媡偵桞暔榑幰偺棟榑傪惂栺偡傞偟丄傑偨桞暔榑幰偼堄幆揑偵偙偺乽尒抧乿偐傜棟榑妶摦傪揥奐偡傋偒偩偲偄偆傕偆堦偮偺廳梫側恀棟偑婃屌偵愃偗傜傟偰偄傞偙偲偱偁傝丄乽弌棃帠偺昡壙乿偵摉偭偰堦掕偺僌儖乕僾偺乽尒抧偵棫偮乿偙偲偼愱傜乽幚慔偺栤戣乿偱偁偭偰丄棟榑偺栤戣丄乽弌棃帠乿偺擣幆偺栤戣丄棟榑妶摦偺栤戣偱偼側偄偲婯掕偝傟偰丄乽昡壙乿偡傞棟榑妶摦偦偺傕偺偑幚慔忋偺栚揑偺偨傔偺傕偺偲偟偰幚慔偵巜摫偝傞傋偒偙偲偑柍帇偝傟丄棟榑偲幚慔偑暘棧偟偰偄傞偙偲偱偁傝丄棟榑傊偺幚慔丄幚慔揑尒抧偺摫擖偼偦偺媞娤惈傪彎偮偗傞偲峫偊傜傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅 丂傕偪傠傫丄桞暔榑幰偑堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偵棫偮偙偲偼丄懡悢僾儘儗僞儕傾偺乽帺屓堄幆乿偺尒抧偵棫偮偙偲偱偼側偄丅偙偺乽帺屓堄幆乿偵偍偄偰偼壨搶巵傕庡挘偡傞傛偆偵丄乽偦偺奒媺偺媞娤揑懚嵼條幃偑昁偢偟傕堄幆偝傟偰偄傞偲偼尷傜側偄乿乮戞屲嬨崋嬨幍暸乯丅帠幚丄懡悢偺僾儘儗僞儕傾偼僽儖僕儑傾丒僀僨僆儘僊乕偺塭嬁壓偵偁傝丄帺屓偺楌巎揑埵抲偵偮偄偰惓偟偄擣幆傪桳偟偰偄側偄丅偩偑僼傽僔僘儉偺媞娤揑杮幙偺壢妛揑夝柧偑僼傽僔僗僩偵傛偭偰愃偗傜傟傞乮奧乮偗偩乯偟僼傽僔僘儉偼斀壢妛揑棟榑偱偁傞偐傜乯偺偲偼斀懳偵丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺媞娤揑惗妶忦審丄偦偺惗挿偺曽岦偺壢妛揑夝柧偼丄斵摍偵岝偲婓朷傪梌偊傞偑擛偒惈幙偺傕偺偱偁傞偑屘偵丄師戞偵懡偔偺僾儘儗僞儕傾偵傛偭偰傢偑傕偺偲偝傟傞丅偦傟偼丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺帺惗揑側杮擻傗摦岦乗乗僾儖僕儑傾丒僀僨僆儘僊乕偺偨傔偵偦偺揔墳揑側敪揥傪慾巭偝傟偰偄傞乗乗偵搳崌偟丄偦偺揔墳揑側揥奐傪懀偡傕偺偱偁傞偐傜丄斵摍偵偲偭偰惓偵暉壒偲偟偰庴梕偝傟傞偺偱偁傞丅尰戙桞暔榑偼偙偆偄偆堄枴偱丄懄偪僾儘儗僞儕傾乕僩偺摦岦丄棙塿傪揔墳揑偵戙昞偟偰偄傞偲偄偆堄枴偱丄僾儘儗僞儕傾揑偱偁傞丅偩偐傜偙偺揘妛偺憂巒幰偑夝曻塣摦傊偺嶲壛偺幚慔揑夁掱偵偍偄偰偙傟傪憿傝忋偘偨偙偲偼嬼慠偱側偄丅僾儘儗僞儕傾乕僩偺棟榑偼楯摥偟昻朢偡傞懱尡傗丄楯摥幰偺帺屓夝曻偐傜暘斿偝傟傞偺偱偼側偔偰丄斵摍偺夝曻偺棙塿偺偨傔偵丄偙偺夝曻偺昁慠惈偲忦審傪擣幆偡傞偙偲偵傛偭偰宍惉偝傟傞丅尰戙桞暔榑偺楌巎傪偄偔傜偐偱傕抦偭偰偄傞幰偼丄偦傟偑僾儘儗僞儕傾乕僩偺塣柦偵懳偟偰柍娭怱側丄擳帄偼揋懳揑側妛幰偵傛偭偰揥奐偝傟偨傕偺偱側偔丄斵摍偺夝曻偺偨傔偵摤偭偨恖乆偵傛偭偰丄偙偺夝曻塣摦偺採婲偡傞傾僋僠儏傾儖側栤戣偺棟榑揑夝柧傪捠偟偰慜恑偝偣傜傟偨偙偲傪抦偭偰偄傞敜偱偁傞丅懄偪偙乀偱偼丄棟榑偼僾儔僋僔僗乵幚慔乶傊偺廬懏偵偍偄偰丄僷儖僞僀儕僢僸乵搣攈揑乶側尒抧偐傜揥奐偝傟偰偄傞丅偟偐傕偐乀傞夝曻偺棙塿偼丄尰幚偵偮偄偰偺朞偔傑偱壢妛揑側擣幆傪梫媮偡傞偑屘偵丄偙乀偱偼乽堦掕偺幮夛揑僌儖乕僾偺尒抧乿傪擣幆妶摦偵摫擖偡傞偙偲偑丄偲傝傕捈偝偢擣幆偺媞娤惈偺曐徹偱偝偊偁傞偺偱偁傞丅媝偭偰丄棟榑傪幚慔偐傜暘棧偟丄傾僋僠儏傾儖側栤戣偺媶柧傪懹偭偨僨儃乕儕儞妛攈偑丄偦偺偨傔偵娤擮榑偵揮棊偟偨偙偲偼丄堦掕偺幮夛忋丄幚慔忋偺乽尒抧偵棫偮乿偙偲傪愱傜乽幚慔偺栤戣乿偲偟偰棟榑偺栤戣偲偟側偄尒夝偑丄壗張偵惗挿偟偰備偔偐傪椺夝偡傞傕偺偱偁傞丅 丂慠傞偵堦掕偺奒媺揑庡娤偺尒抧偐傜帠徾傪昡壙偣傛偲偄偆応崌偵偼丄庡娤偼乽懳徾揑彅忦審偵傛偭偰攠夘偝傟偨懚棫乿偨傞偙偲偑柍帇偝傟丄偦偺幚慔偼堗傢偽乽僇僥僑儕僢僔儏丒傾僋僠償傿僥乕僩乵抐屌偨傞峴摦惈乶偲偟偰昞徾偝傟乿偰偄傞偲偄偆庡挘乮戞巐嬨崋堦乑乑=堦乑堦暸乯偼丄僾儘儗僞儕傾揑側僷儖僞僀儕僢僸僇僀僩乵搣攈惈乶丄庡娤丄幚慔偑惓偵尰幚偺媞娤揑擣幆偵攠夘偝傟傞偙偲傪梫媮偟丄偦傟偲晄壜暘偵寢傃偮偄偰偄傞傕偺偱偁偭偰丄壢妛惈偲乽庡懱惈偺婯掕乿偲偼偙乀偱偼曎徹朄揑摑堦偵偁傞傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偺斲掕乗乗乽昡壙偵晅偡乿偙偲偼昁偢傗 壢妛揑偵婎慴偯偗傜傟偰偄側偄庡娤揑乽帺屓堄幆乿偺尒抧偐傜帠徾傪嵸抐偡傞偙偲偱偁傞偲偄偆撈抐丄乗乗偐傜婣寢偝傟傞傕偺偱偁傞丅 丂壨搶巵偼偙偺応崌丄椺偊偽塱揷偺乽楌巎偵偍偗傞庡娤揑忦審乿偺拞偱丄庡娤偺憡懳揑偵愊嬌揑側栶妱偺榑媶偵偍偄偰丄堦掕偺栚揑偺幚尰偺偨傔偺乽媞娤揑忦審偺尰懚偵娭偡傞擣幆偺恀婾偼廔嬊揑偵偼 偐乀傞峴堊偦偺傕偺偵傛偭偰専徹偝傟傞乿乮乽桞暔榑揘妛偺偨傔偵乿丄擇嶰嶰暸乯偲塢偭偨尵梩傪丄師偺傛偆偵嬋夝偡傞丅塃榑暥偺昅幰偵偍偄偰偼丄懳徾偺媞娤揑擣幆偵傛偭偰攠夘偝傟偞傞庡娤偺擻摦惈偑乽帺桼慖戰揑偵乿怳晳偄丄峴摦偑媞娤揑忦審偺擣幆偵棫媟偡傞偺偱側偔偰丄媡偵媞娤揑忦審偺懚嵼偑峴摦偺屻偵柧偐偵偝傟傞偺偩丄偲丅偮傑傝斵偵偁偭偰偼乽愭偢 傗偭偰尒傞丅傗偭偰尒偰偆傑偔偄偭偨傜丄偦偺偨傔偺媞娤揑忦審偑懙偭偰偄偨栿側傫偩丅乧乧偙偆偄偆 擻摦惈傪敳偄偰峫偊傞偲丄媞娤揑忦審偑懙偭偰偄傞偺偵丄偦傟偵婥偑偮偐偢丄堩偟偰偟傑偆偙偲偵側傞丄偲乿丅乽慠偟丄堦偮偺攠夘揑宊婡乮壜擻惈乯傪堄幆偟摼傞偐斲偐偼丄乧乧宱尡揑側埥偄偼棟榑揑側敾抐椡偺栤戣偱偁傞乿乮戞巐嬨崋丄堦乑乑=堦乑堦暸乯丅塃榑暥偱偼乽廔嬊偵偼乿傗偭偰尒偰暘傞乮恀棟偺婯弨偼幚慔偩偐傜乯偲塢偭偰偄傞偺偵丄壛摗巵偼偙傟傪乽愭偢傗偭偰尒傞乿偲偄偆傛偆偵榗嬋偡傞丅偙偺榗嬋偑側偄偲堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偐傜帠徾傪昡壙偣傛偲偄偆採尵偵偍偄偰偼庡娤偼媞娤揑擣幆偵攠夘偝傟偨傕偺偱偁傞偙偲偑柍帇偝傟傞偲偄偆壨搶巵偺庡挘丄懄偪乽昡壙乿偲擣幆偺乽媞娤惈乿偺旕榓夝惈偺庡挘偼惉傝棫偨側偔側傞偐傜偱偁傞丅偟偐傞偵偙偺乽廔嬊揑偵偼乿偲乽愭偢乿偲偺憡堎偼壢妛揑僜僔儍儕僗儉乵幮夛庡媊乶偲傾償傽儞僠儏儕僗儉乵惌帯揑朻尟庡媊乶偺憡堎偱偁傝丄桞暔榑偲庡娤庡媊偺憡堎偱偁傞丅尰懚偟偰偄傞媞娤揑忦審傪堩偟偰偟傑偆偺偼丄媞娤揑擣幆偺晄懌偲偐丄惉岟偵懳偡傞婋湝丄晄埨偺擮摍乆偺傛偆側丄庡娤揑忦審偵偍偗傞摿掕偺帠忣偱偁偭偰丄擣幆偵愭棫偭偰乽愭偢傗偭偰尒傞乿擻摦惈側傫偐偱偼側偄丅偦偟偰堦掕偺峴摦偺惉岟偺偨傔偺媞娤揑忦審傪堩偟偰偟傑偆偐斲偐偲偄偆偙偲偼丄媞娤揑 偵慬掕偝傟偨慖戰乮乽帺桼慖戰乿偱側偔乯偺栤戣偱偁傝丄壗傪慖傇偐偼庡娤揑忦審偵埶懚偡傞丅椺偊偽庡娤揑忦審偑枹弉偱偁傟偽丄埥偼媞娤揑壜擻惈傪擣幆偣偢丄埥偼擣幆偟偰傕棙梡偟摼側偄偙偲偵傛偭偰丄楌巎偺媞娤揑峴掱偦偺傕偺偵傛偭偰梫媮偝傟傞慖戰乗乗廬偭偰昁偢偟傕慖戰偲偟偰堄幆偝傟傞偲偼尷傜側偄慖戰乗乗偺栤戣偼丄壜擻惈傪尰幚惈傊偲揥奐偟側偄曽岦傊夝寛偝傟傞丅偙傟偼娤擮榑偱側偔偰丄桞暔榑偵夝柧偝傟偨楌巎揑帠幚偱偁傞丅傕偟慖戰偺栤戣偑側偔丄楌巎帠徾偼偡傋偰庡娤偐傜撈棫偵堦媊揑偵寛掕偝傟偰偄傞側傜偽丄僞僋僥傿乕僋乵愴弍乶偺栤戣偵偮偄偰夁岆偲偄偆傕偺偼偁傝摼偢丄憤偠偰庡娤偺妶摦偼柍堄幆側傕偺偲側傞偩傠偆丅壛摗巵偼乽昡壙乿偑媞娤惈傪攔彍偟丄堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偐傜偺棟榑栤戣偺張棟偑偮偹偵庡娤庡媊偱偁傞偙偲傪愢柧偡傞偨傔偵偼丄乽廔嬊揑偵偼乿傪乽愭偢乿偲曄偊側偗傟偽側傜側偄掱偺鎘曎傪昁梫偲偟偨偺偱偁傞丅 丂埲忋偺傛偆側尒夝丄乽帠徾偼堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺尒抧偐傜偱側偔丄媞娤摼揑偵攃埇偝傞傋偒偱偁傞堦掕偺幚慔庡懱偺庡娤偐傜偱側偔媞娤揑偵丄偦偺庡懱傪傕娷傓幮夛娭學偺憤懱偵偍偄偰丄攃埇偝傞傋偒偱偁傞乿乮戞巐嬨崋堦乑嶰暸乯偲偄偆丄壗乆偱乽側偔偰乿壗乆乽偱偁傞乿偲偄偆宍帶忋妛揑擇幰愶堦偺尒抧乮拹乯偐傜偼丄桞暔榑幰偵懳偟偰偼丄棟榑傪堦掕偺幮夛僌儖乕僾偺幚慔忋偺栚揑丄棙塿偵栶棫偨偣傛偲偐丄庡戣偺傾僋僠儏傾儕僥傿偲偐偄偆梫媮偼丄棟榑揑偵偼柍堄枴 偲側傝丄愱傜棟榑偺尷奅奜偵偁傞惌嶔偺栤戣偲側傞丅偩偐傜棟榑偼棟榑丄幚慔偼幚慔偲偄偆晽偵暘棧偝傟丄幚慔偺庡懱亖慻怐偑摨帪偵棟榑偺憂憿椡 偱偁傝丄棟榑妶摦偺殞摫乮偒傚偆偳偆乯幰 偱偁傞偙偲偼斲掕偝傟丄偦傟偼壗張偐奜晹偱挷惢偝傟偨棟榑傪庴梕偟偨忋偱乽嫵堢揑慻怐揑妶摦乿乮戞巐嬨崋嬨敧暸乯傪傗傟偽傛偄偲偄偆偙偲偵側傞丅壨搶亖壛摗巵偵偁偭偰偼乽棟榑揑棟擮乮擣幆乯偲幚慔 偺摑堦乧乧偙偺摑堦偼惓偵擣幆榑偵偍偗傞傕偺偱偁傞 乿乮乽揘妛僲乕僩乿乯偲偄偆恀棟偼幏漍偵斲掕偝傟乮戞巐嬨崌嬨敧暸乗乗乽僷榑攈偺彅孨偼丄棟榑偲幚慔偲偺摑堦偺栤戣傪擣幆榑偺栤戣偩偲峫偊乿塢乆偺嬪傪傕嶲徠乯丄偙偺摑堦偑擣幆夁掱丄棟榑妶摦偵偍偗傞 寛掕揑側婎慴偱偁傞偙偲偼斲掕偝傟丄棟榑偺僷儖僞僀儕僢僸僇僀僩乵搣攈惈乶偺栤戣偼擣幆榑偐傜曻拃偝傟丄廬偭偰扨偵僷儖僞僀儕僢僸僇僀僩偲偄偆尵梩偼岥偵偝傟偰傕丄偦偺杮幙偼斲擣偝傟丄棟榑偲幚慔偺摑堦偼桳婡揑摑堦 偲偟偰偱偼側偔丄奜揑側楢愙丄撪揑暘棧偲偟偰攃埇偝傟偰偄傞丅
丂偩偐傜巵偑墖梡偡傞丄幚慔揑桞暔榑幰偵偲偭偰娞梫側偺偼悽奅傪夵曄偡傞偙偲偩偲偄偆柦戣偼丄巵偵偁偭偰偼幚偼丄幚慔揑桞暔榑幰偵偲偭偰娞梫側偺偼悽奅傪夵曄偡傞偙偲傪娤徠偡傞 偙偲偩偲偄偆捈娤揑桞暔榑偺怴曄庬偵曄幙偟丄幚慔揑桞暔榑偲偼恖娫偺幚慔傪尋媶偡傞桞暔榑偱偁傝丄堦愗偺 懳徾傪幚慔偲偟偰峫嶡偡傞桞暔榑偱偁傞偲偄偆恖娫妛揑亖庡娤庡媊揑曃岦傪傕偭偨僗僩儖乕償僃揑媞娤庡媊偵曄幙偡傞丅壛摗巵偺棟榑偼丄庡娤庡媊丄榑棟庡媊丄幚徹庡媊摍乆傊偺恟偩偟偄曃岦傪昁慠揑偵曪娷偣傞怴斉偺捈娤揑桞暔榑偱偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亊丂丂丂丂丂丂丂丂丂亊丂丂丂丂丂丂丂丂亊 丂埲忋傪梫栺偟偰偄偊偽丄壛摗巵偺崻杮庡挘偼丄幚慔揑桞暔榑偲偼幚慔傪棟榑偺懳徾偲偟偰捈娤偟娤徠偡傞桞暔榑偱偁傞丄偲偄偆揰偵偁傞丅偙偙偐傜偟偰媽桞暔榑偲尰戙桞暔榑偺嵎暿偵娭偡傞岆偭偨尒夝傗丄尰戙桞暔榑偵偁偭偰偼恖娫偺幚慔揑摥偒偐偗偺懳徾偼幚慔偦偺傕偺偩偲偄偆偑擛偒庡娤庡媊傗丄巚堃偵懳偡傞尰幚惗妶丄幮夛揑棙奞偺塭嬁偺斲掕傗偑婣寢偝傟丄偐乀傞尰幚揑棙奞偐傜撈棫偲偄偆堄枴偺巚堃偺乽弮悎乿惈偵娭偡傞庡挘偼丄悽奅偺塣摦朄懃偐傜偺榑棟揑側傕偺偺梀棧丄榑棟庡媊偵傑偱堩扙偟丄摨帪偵悽奅偺堦斒揑塣摦朄懃偵娭偡傞妛偲偟偰偺揘妛偺斲掕偼幚徹庡媊偵摓払偡傞丅偙傟傜偡傋偰偺堩扙偼丄梫偡傞偵丄幚慔揑桞暔榑偲偼恖椶偺慜恑揑僋儔僗乵奒媺乶偺幚慔偺棙塿偺偨傔偵帺慠傪傕恖娫偺幚慔傪傕巚堃傪傕棟榑偺懳徾偲偡傞桞暔榑偩偲偄偆恀棟偺嫅斲丄幚慔揑桞暔榑偲偼幮夛揑棙奞傪挻墇偟偨乽弮悎巚堃乿偺棫応偐傜恖娫偺幚慔傪娤徠偡傞桞暔榑偩偲偄偆庡挘丄偲怺偔寢傃偮偄偰偄傞傕偺偱偁傞丅丂丂丂乗乗廔乗乗
|
|||
| 丂
|