| 1 運動の実践形態として 文学教育の歴史は、同時に文学教育運動の歴史である。すくなくとも、それが運動の様相を呈するにいたったときに、文学教育のいとなみは、みずからの機能と役割とについて自覚的なものになりえた、ということだけはいってよさそうである。いいかえれば、すぐれた運動意識が明確な文学教育意識をつくりあげ、みのり多い実践的・理論的成果をもたらしている、という関係がそこに見られるのである。 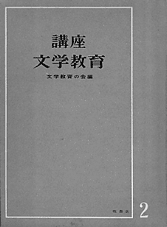 ここに文学教育意識というのは、文学教育を欠いて人間形成のいとなみはありえないとする意識、文学教育を必要とする意識のことである。さし当って、そのことを意味している。指導の成功を偶然に賭けるのではなく、むしろ、この偶然をさえ必然に変え、成果を持続的なものとして発展させていこうとする態度――それこそ、すぐれた文学教育意識のもたらすところのものである(1)。 ともあれ、それが運動意識にささえられたいとなみとなったときに、その活動が自覚的なものとなり、真に実践的なものになりえた、ということを、歴史の事実ははっきりと裏書きしている(2)。とくに、戦後の文学教育運動は、いわば運動そのものの実践形態というかたちをとって開始され、また展開していっているという点で特徴的である。 さて、戦後十余年の文学教育運動は、次の三つの時点においてみずからの進路をえらびとった、と見てよさそうである。すなわち、 (1) 児童文化雑誌『子供の広場』(3)の創刊(一九四六年四月)前後 (2) 日本文学協会・一九五二年度大会(一九五二年六月)前後 (3) 文学教育の会成立(一九五七年四月)前後 の三つの時点においてである。 このようにして、また、民間教育運動の視点から見て、戦後文学教育の展開については、 (1) 児童文学者を中心とした、文学教育の提唱と実践の時期(一九四六~五一年) (2) 学習指導要領ラインの、上からの文学教育・国語教育(そのコスモポリタニズム・プラグマティズム) 。。。。への抵抗を底流とする、学校文学教育の研究・実践の時期(一九五一、五二年~) (3) 文学教育関係者の大同団結による、対立の統一が意図された時期(一九五七~) の三つの時期を、過去に考えてみることができそうである。 もっとも、それを、たんに、過去といいきってしまえないものがある。戦後のそれぞれの時期においてかかげられた課題なり問題提起のいずれをとりあげてみても、そのほとんどすべてが未解決のままに終っている。問題のほとんどすべてが未解決のまま、多少かたちを変えただけで、こんにちに持ち越されている、といっていいのである。 だからして、また、上記の三つの時期区分も、その意味では、しょせん年次を追っての便宜的な構図――ピークとピークをつなぐ便宜的な構図によるもの、というほかないのである。戦後はまだ終結していない。戦後は現在なお継続しているという意味で、戦後文学教育史は明確な時期区分をもつというところまでは至っていないのである。 じつをいうと、こうして戦後が終結を見ないうちに、早くも(?)戦前の天皇制臣民教育への復帰がたくらまれ、ほとんどそれと紙一重のところまで学校教育――学校文学教育が追い込まれてきているのが、こんにちこの唯今の時期にほかならない。 それは、もはや、注記するまでもないかと思う。ごく最近の出来事だけについてみても、例の教育二法・三法このかたの教員の政治活動に対する大幅制限、教科書国定化への動き、教育委員のアマクダリ任命制の実施、そして勤務評定の一方的強行。さらに、この勤務評定の施行を前提とした、「道徳」の時間特設と、国家基準の制定というかたちをとっての学習指導要領の全面改訂、等々。 「道徳」を、いわば全教科の核として特設し、それを施行規則によって強制すると同時に、各教科のカリキュラムを戦前の臣民教育の方向に改訂することで、天野文相このかたの歴代の文相のもとにおいて意図された「修身」の復活は、ある程度実質的に具現された、と見ていいのである。 このようにして、くちぐちに子どもたちに「君が代」を歌わせながら(4)、「国民的自覚」をそこに促がしたり、その「道徳性を高め」たりという、現政府筋の期待するような国語教育や文学教育というものが、その方向と内容においてどういうものであるかは説明を要しないであろう(5)。 また、すでに、「道徳」の時間のほうでは、「読み物の利用」というかたちで、“道徳教育のための文学教育”とでもいうべきものが行われている。文学作品のなかから、道徳的要素――いわゆる道徳的要素だけを抜きだしてきて、それを教育に「利用」しようというのである。あるいは、文学作品を教訓読み物・教訓咄にすり替えて扱おう、というのである。ともあれ、文学作品は、そこでは「道徳」教育に利用すべき読み物の一種に過ぎない(6)。 文学ほんらいの感動(文学的感動)を疎外した、この文学学習(?)が、文学固有の感動・文学的思考を生命とする国語科文学教育を破壊にみちびくものである、という点については、すでに小・中学校の教育の現場から批判が巻き起こっている(7)。 教育および文学教育への、このような上からの破壊工作・破壊活動に対して、こんご、文学教育の会や日文協国語部会その他民間諸団体がどう対処し、どう対決していくかは、直接教育の現場の動向につながる問題である。と同時に、それはまた、上記三つの時期のあとを承けた今後のこの時期が、文学教育史上の輝かしい時期として記録されるか、大きな汚点をそこにとどめるかという分れ目でもある。 上記、第三期において意図された“対立の統一としての大同団結”が、とくに、こんにちのこの段階において、どの方向にむけての大同団結とならねばならないか、――ともあれ、今までにない困難な時期にさしかかってきている、といわなくてはならない。 註 2 児童文学運動とともに 戦後の児童文学運動ないし文学教育運動は、子どもを守る文化運動の一環として、敗戦の荒廃のただなかで活動が開始された。児童文学者協会(一九四六年三月創立[創刊を創立に訂正])結集し、上記『子供の広場』のささえとなったような、一連の民主的な児童文学者や文化人たちの手によってである。 戦後文学教育史の第一期は、このようにして、児童文学者を中心とした活動の時期である。『子供の広場』『コドモノハタ』『赤とんぼ』(以上、一九四六年四月創刊)、『銀河』(同年十月創刊)、『子どもの村』(一九四七年六月創刊)、『少年少女』(一九四八年二月創刊)などの良心的な児童雑誌が、国民各層の子どもたちに、自然なかたちで、すぐれた文学環境と文学学習の場を提供した、と見ていいだろう。なかでも『子供の広場』の発刊は、戦後の文学教育運動に大きな道標をうちたてたものといっていいかと思う。 ――「“子供の広場”は諸君の広場だ。諸君が自由に集って、勉強し、議論をたたかわせ、計画をたて、実行を進める楽しい広場だ。ほんとうのことをまなび、物事を根本から考える力をねり、文化を、平和を、人類を愛する心をきたえる明るい広場だ。全日本の少年少女諸君、子供は子供で、しっかり腕をくもう。そうして、どんな困難でも乗りきって、文化の国、平和の国、民主日本をつくりあげよう。」これは、同誌の“創刊のことば”である。また、この創刊号の“あとがき”には、 ――「“広場”は、うそっぱちの読みものは、いっさいのせない。そのかわり、ほんとうに明るく平和で、ゆたかな日本をつくる。美しい詩、たのしい創作、正しい科学的な読みものなどを、どしどしのせる」うんぬん。と、その編集方針を明らかにしている。この雑誌のいだく文学教育的意図を示すものである。ちなみに、創刊号の目次をくってみると、創作欄に小川未明の『兄の声』、上林暁の『弘君』の二つの短編、与田準一の詩作品『貨車と赤牛』があり、赤松俊子のさし絵で山村房次の物語『コーリヤとめんどり』、文学教室の欄に渡辺順三の『石川啄木』などがかかげられている。その他、『世界を一つに』という標題の国際連合の解説(松本慎一)や、世界の窓欄『中国のお友達』、生活教室欄『子供壁新聞』などである。表紙は、村山知義のタッチによる、児童雑誌としてはかなり思いきったものであった。 また、たとえば、川崎大治氏や国分一太郎氏による小学校国語教科書批判(1)(『日本児童文学』一九四七年十月号)や、大久保正太郎氏の文学教育論(2)(『文学教室刊行のことば』同年三月)などについて見ると、学校文学教育の進路が、そこに実にはっきりと示されていたことが知られるのである。 ――「文学については、いままで多くの誤解があった。たとえば、文学は少年や青年の心をだらくさせる以外には、なんの役にもたたないものだという迷信がおこなわれていた。……もちろん〔文学が〕そういうふうに嫌われるだけの理由もあった。だが、それは、文学そのもののせいではなく、若い人に、すぐれた文学をあたえず、文学のただしい読みかたを教えなかったからである。教室で、国語の時間などに、文学作品のきれはしが教えられることはあった。しかし、その大部分は、少年や青年のわかわかしい心をとらえる、生きた文学ではなかった。……生活する人々の、なまなましいよろこびや悲しみを、そっちょくにうったえた、力づよい文学ではなかった。かびくさい、老人じみた、上品にきどった、そうでなければ、国体のそんげん、日本のありがたさを頭からおしつけるようなものばかりだった。ちょっぴりでも真実をえがいた、ほんものの文学は、ぜったいに持ちこまれなかった。外国のりっぱな文学にたいしては目かくしも同然だった。」引用は、上記大久保氏の文章からのそれであるが、このようにして、次の時期において盛りあがりを示す、学校文学教育(教室における文学学習指導)への確実な手がかりはこの時期において用意された、といっていいのである。 その手がかりは、たんにこの種の文章のなかに示されているというだけでなく、たとえば右の『刊行のことば』が示しているような意図にもとづいて、「ほんとうの文学を、ただしく読む方法を」子どもたちの「身につける」ことをめざした、片岡良一の『有島武郎と夏目漱石』他数編の文学教室シリーズが刊行されることで具体化されている。 また、たとえば、次の第二期の学校文学教育において、その主要教材として全般的にとりあげられるにいたった、すぐれた作品のかなりの部分は、この時期の児童雑誌が明確な編集意図のもとにうちだした、その掲載作品にほかならなかった。二、三例をあげれば、岩倉政治『空気がなくなる日』、壺井栄『あたたかい右の手』(以上、「広場」)、竹山道雄『ビルマの竪琴』(「赤とんぼ」)、国分一太郎『雨ごいの村』(「銀河」)などである。 と見てくると、評論(文学教育の原理・方法の提示)の面でも、また実作(教材の提示)の面でも、それは、かなりにみのり多い時期であった、ということになろう。 さらに、これは今のところ推定以上のものではないが、ジャーナリズムとの結びつきがないため、活字になった報告こそ持たないけれど、かなり多くのすぐれた文学教育の実践が、それぞれの教室において行われていたことが、そこに考えられるのである(3)。現場教師による、そうした直接の媒介とささえなしには、上記の諸雑誌や単行本(したがってまた、上記の諸作品)の児童・生徒への浸透ということは、とうてい考えられないのである。ともあれ、この時期における現場の教育実践面の実態を掘り起こすしごとは、戦後文学教育史のこんごの課題の一つである。 注 3 第二期の運動へ よその国のことは知らない。すくなくとも、わたしたちのところでは、児童文学運動や文学教育運動は、いつも、“子どもを守るため”の運動として終始している。すでに一定水準の文化がそこにあって、それを向上させるために運動が展開されるというのではなくて、それは、いわば、最低線の生活文化を守るための運動であった。戦前における童心主義の文学運動・文学教育運動が、すでにそうしたものであった。それは、「世俗的な下卑た子供の読み物を排除して、子供の純正を保全開発するため」のもの(『赤い鳥』創刊号・巻頭言)にほかならなかった。 が、ひとしく“子どもを守るため”とはいっても、戦前の童心主義の場合は、せめて子どもだけはゆたかな文化的環境のなかに、という、おとなの夢がそこに託されていたわけである。そうしたおとなの夢が、おとな自身、追い詰められた社会的シチュエーションのもとにあることで生まれた夢であるにしても、しかしその意味では戦後のおとなは、もっと追い詰められている。あるいは、追い詰められかたが違う、といったらいいだろうか。 「文化どころか、子供の最低の生活さえまもり得ない、同じ“せめて”にしても、“せめてウチの子だけは、浮浪児にしたくない”の“せめて”になってしまった(1)」のである。 『肉の火』(舟橋聖一――「新潮」一九四七年三月号)の女主人公も語っている。「戦争にまけた以上、何もかも変るのが、当り前でございましょう。美樹子だけに変るなと申しましても、無理でございます。だから、私は何ごとも、娘次第と考えて、やかましいことをいうのは、やめました。何もかも変ったじゃございませんか。人の心は、申すまでもございません。富士山の形まで、変ったような気が致しますのですが、そうはお思いになりません?」と――。 何もかも変った、そのなかでの“せめて子どもだけは”である。美樹子だけに――子どもにだけ変るなといっても無理である。むしろ、変ってくれなくては困るのである。が、問題は、その変りかたである。その方向づけである。 子どもを守る、ということは、彼らを温室のなかへとじこめて外気にふれないようにさせる、ということではない。そうではなくて、悪現実にめげずに、むしろ現実の新しい息吹きのなかで、すくすくと成長していけるような批判力と抵抗力とを、子どもたちの身につける、ということでなければならない。『赤い鳥』時代のそれとくらべて、運動が生活に根をおろした、幅と深まりのあるものになっていったのは、当然といえば当然であろう。 右の関係は、すでに、いちおう、前項において見えてきたところである。 ところで、それと同時に、戦争直後のあの野放図な解放感――占領軍を解放軍と見誤ったような、あの解放感が、現実の暗さを裏切った、一種観念的な明るさをそこに漂わせていたことも否みえないように思われる。それは、子どもの現実、子どもたちのリアリティーそのものとも矛盾するものだった、といわなくてはならない。 片足は、たしかに、しっかりと地面を踏まえている。けれど、もう一方の足は、いつか宙に浮いている、といった、何かふっ切れない、跛行的な不統一さがそこにあったように思われてならないのである。童心主義とは方向を異にしていたにしろ、それを裏返しにしたかたちの一種の文化主義が、結果としては、やはり、そこに作用していた、といわなくてはならない。 『少年少女の広場』や『赤とんぼ』『銀河』『少年少女』その他一連の良心的な児童雑誌が、つぎつぎと姿を消しさり、朝鮮戦争が開始される前夜には、運動がすでに挫折を経験しなくてはならなかったということには、直接間接の政治の圧力やら資本攻勢やらさまざまの外的条件が決定的な要因としてあげられるだろう。むろん、それに異論はない。が、それと同時に、子どものリアリティーを疎外した、一種観念的な雑誌編集の方針や創作態度にも、挫折の理由の一つがあったことが、かえりみられなくてはならないように思う。 このようにして、後に、「私たちは、児童文学を口にしながら、意識の底では、子どもたちを忘れ去っていたこと。私たちは、児童を置き去りにして、“文学”の形骸を追い求めていたこと。……要するに、無意識の裡に、生活的にも意識的にも、子どもから遊離してしまっていた」ことの反省が、ほかならぬ児童文学作家たちによって語られることにもなっていったのである(2)。 そこで、これからは「今日の子どもたちの心をみたす“文学”の勉強を本気になってしていきたい。」それは「児童文学を志すものとして、きまりきったこと」ではあるが、「私たちにしてみれば、このきまりきった方向に到達するだけでも大変だったのである。さらに、それを実践に移すとなれば、一層の困難」を覚悟しなくてはならない(3)、とも一群の作家たちは語っているのである。 ところで、また、右に見るところの運動の停滞・挫折は、そこに同時に、いっそう強力な文学教育運動への要求を生むにいたっている。「多数の児童は指導者がその自覚を引きだすことなしには、こまやかな感受性や思考の努力を要する文学作品を、争って読むということはない。十年の戦争期間中の教育の低下、戦後の荒廃せる環境ではなおさらである。だから、現在必要なのは強力な文学教育の運動である。文学教育が広く行われるならば、読者が育つだけでなく、児童文学作家の思想や技術も、逆にまた教育され高まることはたしかである。」と、その当時(一九五一年)において関英雄氏は語っている(4)。 また、右の関氏の発言と前後して、児童文学者協会・第五回総会(一九五〇年十二月)は、年間運動目標の一つとして、“文学教育運動の強力な展開”を決議している。一方、児童文協の中堅メンバーである菅忠道・国分一太郎・さがわみちお・与田準一・福井研介・金沢嘉市その他の諸氏による、文学教育関係の研究・評論が、一九五〇~五一年の各種の雑誌や講座物の紙面を賑わしている(5)。 一九五二年、五三年あたりからジャーナリズムと結びついて急テンポに活発になっていく、学校文学教育の研究・実践活動は、けれど直接的には、こうした児童文学者の運動を受けついでおこなわれたものとはいえないようである。すくなくとも、日本文学協会ラインのそれは、児童文協ラインの運動とは別個のところから出発していた。そこに一種の断層があった。 断層があった、というより、児童文協は児童文協、日文協は日文協、実践国語は実践国語というふうにお互いがお互い、自分のセクション以外のところへは目が届いていなかったのである。 セクショナリズムがそこにはたらいていた、というのではない。そうではなくて、周囲に目が届いていないために、結果としてそれぞれに自分の狭いワクのなかでの判断にもとづいてしか仕事が行われえなかったということにほかならない。 が、それはそれとして、右に見てきたような、この第一期における文学教育運動や、その教室実践による基盤の開拓を前提とすることなしには、戦後第二期の学校文学教育のいとなみも、そこにみのり多い成果を期待しえなかったことは明らかである。 それは、たんに、小・中学校の文学学習面についてだけ、いえることではない。また同時に、高校その他における実践部面においても指摘されることなのである。第一期における小学生は、第二期の段階においては中学生・高校生に成長している。この第一期の文学教育活動にはぐくまれた小学生が、である。第三期における文学教育の実践活動が、まず高校の分野において盛りあがりを示したというのも、あながち偶然ではなかったように思われるのである。 注 4 言語教育か文学教育か 「文部省の教科書『国語』は、どうも文学くさみがこすぎる」という点を批判して、国分一太郎氏は、上記『詩について』(一九四七年)という論文のなかで、 ――「国語読本が、もっぱら文学読本となることに、わたしは反対である。コトバとモジの教育をするテキストが国語の教科書である。もし文学のよみかたや創作について指導したいならば、べつに“文学科”をおき、“文学読本”をつくればよいのである。なにも国語読本に、そんなにおもいフタンをしょわせる必要はない。そうでなくてさえ、日本の言語教育は、基本的な母国語の教育と、近代的な文字表現の指導に効果をあげていないのだ。もっとも、言語や文字が、いちばん、ふくざつに、高度に、総合的に、芸術的に、センレンされてつかわれたカタチが、文学の形であるという考えかたからすれば、“文学作品”も、国語教科書のあるページをしめることはゆるされるだろう。けれども、それは、ほんの一部でなければならない。」また、西尾実氏は、その著『言語教育と文学教育』(一九五〇年一月)において、「いままでの国語教育は、文学教育であった。すくなくとも、文学教育でありすぎた。それをわれわれの日常生活における、話し・聞き・書き・読む言語生活教育である」ことの必要を力説した。 ついでまた、時枝誠記氏は、(1)「日常の言語生活ということと、文学を主体とする文学言語の生活とは……平行の関係においてその教育が進められなければならない」ことや、(2)「文学教育は、書物を読む方法と能力を養う言語教育とは別のものではない」ことを指摘していた(『国語科文学教育の方法』所収『国語教育と文学教育』一九五二年二月)。 と、こんなふうに年次を追ってみてくると、一方で児童文学者その他による文学教育運動のつづけられていた時期は、国語教育“論”の面では、むしろ、文学教育への傾斜を示したこれまでの国語教育(?)への反省として、 (1) 文学教材は、国語教科書のなかの「ほんの一部でなければならない」こと、 (2) 文学教育は、「話し・聞き・書き・読む言語生活教育」の部分と考えられねばならぬこと、 あるいは、 (3) 文学教育は、「書物を読む方法と能力を養う言語教育」の部分であること、 などが語られ、けっきょく文学教育を、言語教育ないし言語生活教育のワク組みのなかで考えていこう、という方向に動いていた時期であったことが知られるのである。 が、右のような考えかたに対しては、(1)「言語教育か文学教育か。国語教育は確かに生活言語としての国語教育でありましょう。しかし、もしわれわれの歴史がたたかって来ており、たたかいとりつつある文学の精神を教えないならば、一体他のどの学科がそれをしてくれるでしょうか。」というかたちで、益田勝美氏による批判(『文学教育の問題点』)が、日本文学協会・一九五二年度大会においておこなわれた。 また、(2)国語教科書に文学教材は不要だというに近い、国語科を言語教育一本にという考えかたに対しては、石田宇三郎氏による国分批判(『国語教育の基本的方向』――「教師の友」一九五三年七月号)に端を発し、国分氏による反論(『国語教育の実践的課題』――「教師の友」五三年三月号)と、さらに片岡並男氏(『国語教育の階級的観点』――「教師の友」五四年八月号)・水野清氏(『言語教育と文学教育』――「教師の友」五五年六月号)などの論争への参加によって、問題のありかが、方向的にかなりはっきり、ときとめられた形である。 まず、益田氏による批判について見てみると、 ――「私の問題提起は次の如く要約できます。というのである。 益田氏による右の問題提起にふれて、鴻巣良雄氏は、つぎのように語っている。その問題提起のなかで、「とくに注目しなければならないことは、いままでの“言語教育か文学教育か”という、二者択一の考え方ではなくて、両者を止揚し、統一して“言語と思考”との関連のうえで文学教育を考えていこうとする態度である。いいかえれば、言語と思考がいつでも相関関係をもっているように、文学教育も言語教育との関連においてとらえ、しかもそのうえで、独自なはたらきを追求していこうとすることである。」(『文学教育の発見』一六一~二ページ)と。 益田氏の意図するところは、鴻巣氏の指摘しているとおりのことなのだが、しかし言語教育を主張する側からは、「ともすると、近年の“言語教育”を目のかたきにしているような傾き」として批判されることにもなっていった。 ところで、ここにいう「近年の言語教育」というコトバが直接何をさしているかは別として、当時、支配的であったのは「アメリカ直輸入の言語技術主義」であった。「現場における文学教育の理念的探求は、ほとんど放置の状態にあったが、『学習指導要領』はこの隙に乗じて、言語教育のプラグマティズムと表裏一体をなすコスモポリタニズムを注入してきた。……このような文学教育のコスモポリタニズムは、現実を隠蔽し、植民地的退廃を見て見ぬふりをし、これと野合したものとならざるをえない。われわれはこのような文学教育に反対し、人間に働きかけ、生徒の心のなかに真実を求めようとする意欲を呼び覚すような文学教育を主張しようとした。しかしわれわれのこの主張は、大方に文学教育への関心が高まっていなかったためと、われわれの理論的弱さ、実践の不足から、文学教育の提唱が、戦後の言語教育にたいする単なる対立意識から生じているかのように、うけとられた。」(『国語教育の十年』――「日本文学」一九五五年六月号)という、森山重雄氏による一九五二年代への回顧は、そこで問題のありかをよくいい当てていたように思われる。 ところで、また一方、二年の余にわたってくりひろげられた、上記“国分・石田論争”の焦点は、どこにあったろう? 水野清氏(前掲『言語教育と文学教育』)のすぐれた整理・要約にしたがえば、それは、「国語科を用具教科と見て、国語(文芸作品をふくむ)で教育する前に、まず国語を指導すべきだという国分氏と、文学的作品(すぐれた文章一般をふくむ広義の文学)を教え、日本国民としてふさわしいモラルを学ばせつつ、その文章の《外被》としての語い・文法を指導すべきだという石田氏との対立」であった。 したがって、「石田氏にあっては、文学的作品は国語科の《血肉》的要素となるし、国分氏の場合は、文学教育を国語科の外へ出し別に文学科を特設する。」(水野氏・同上)ということになる。 そこで、つまり、石田氏にいわせると、文学作品や文学教育を疎外した、国分方式の国語教育は「一種の通訳養成の仕事にすぎない」ということになるし、また、それを国分氏からいわせれば、「石田氏のいうようなしごとをする以前に、しなければならぬことがたくさんある……つまり《国語で教育する》より先に《国語を指導する》こと」(前掲『国語教育の実践的課題』)、だというわけである。 この点に関して、水野氏は、つぎのように語っている。 ――「さきの論文中の《国語で教育する》より先きに《国語を指導する》ことが大切だ、という国分氏の意見はきわめて機械 的である。また、石田氏の考えを《国語で》の中で《国語を》指導するものと規定して、それを《計画的な順序をへた過程》の無視であり、理想論を述べたものと非難したのは一考を要しまいか? 問題は、“で”“を”の助詞の使いわけではない。石田氏の考えは、思想と言語の不可分性をいうにあり、国分氏の非難するように言語と思想の混同をしているのではない。国分氏こそ、形式と内容を区別するのあまり、両者を分離してしまったのである。」また、国語科を言語教育一本にして別に文学科を設ける、という点については、「当分、国分氏のいわゆる“国語科”は、むしろ文学教育をふくむ国語教育のなかに包摂・吸収され、文章を読みつつ、文章を書いて行く、その作業のなかで行われるべきではなかろうか? それらの指導の体系ができあがったのち、その成果を“国語科”の教科書として編集することができよう。」という意見を水野氏はのべている。 それは、暫定的に、国語教育のなかに文学教育をふくめて考える、という以上に、文学科と国語科(言語科)との分離は、「文学教育をふくむ国語教育」の統一的な「指導の体系ができあたったのち」のこと、という意見のように思われる。筆者の個人的な意見を加えることが許されるならば、筆者自身は、この点に関しては、水野氏と(方向的にいって)だいたい同じような考えかたをしている、ということをいい添えておきたい。 とくに、時間特設の「道徳」のほうで、文学を疎外した文学教育(「運動の実践形態として」の項参照)がおこなわれ、さらに国語科文学教育そのものが、改訂指導要領の示すところにしたがって、作品の表現全体(つまり内容そのもの)を扱うよりは、部分的な表現の切れっぱしについての詠嘆的鑑賞に向かおうとしている現在、文学教育を正常なルートに乗せるために必要なことは、むしろ、国語教育のなかに文学教育を明確に位置づけることであるからだ。(表現の切れっぱしについての詠嘆的な鑑賞?――つまり、表現の全体からきりはなされた部分について、「ここのところの修辞や修飾のしかたはすばらしいですなあ」式の、自己陶酔の鑑賞である。) ところで、当の国分氏自身、五四年七月に発表された論文『文学教育の問題点』(「国語教育」)にいたって、国語科の外に文学科を設けることが望ましいが、しかし「現状では、教師たち自身があらゆる創意を発揮して、文学教育を実践」するほかない、という考えかたに変ってきている。そして、この論文では、言語教育か文学教育かなどとうるさくいわないで、「大きな必要に立って、あっさりと文学教育をおこなえばよい」というところまで割り切って考えているのである。 大きな必要に立って、あっさりとやればいい。 で、多分、大きな必要に立って、というこのコトバを、“言語教育か文学教育か”の問題の、さし当っての解決策と考えていいだろうと思う。が、あっさりと、それがおこなえるようになるためにも、国語教育の体系のなかに文学教育を明確に位置づけ、それの機能的本質と役割とをはっきりつかんでおく必要がある。そのことが、はっきりつかめたときに、それこそ“あっさりと”文学教育にたち向かうことも、できるようになれるのではないか、と思う。 5 “問題意識の文学教育”前後 言語教育か文学教育か? そこのところから日文協国語教育部会の文学教育への動きが活発になっていった。学習指導要領ラインの、上からの文学教育の経験主義・実用主義、そのコスモポリタニズムの否定としてである。 その運動の起点となったのが、上記、益田勝美氏による一九五二年度大会報告であったが、さらにそれを古典教育の面にしぼって批判の焦点をはっきりさせたのが、翌一九五三年度大会における荒木繁氏の『民族教育としての古典教育』という報告であった。 ――「日本民族がこのようなすぐれた文学遺産をもっていることに喜びと誇りを感じさせるということは、生徒たちに祖国に対する愛情と民族的自覚をめざめさせるということになります。私は古典教育の究極の目標をここにおきます。……国語の教師は、古典に対するできるだけ正しい評価をもち、どのような古典を生徒に与えるべきかについても考慮して、民族の遺産として真にすぐれた作品を教材として用いなければなりません。そうしてこそ生徒も古典から豊かなものを学び、民族に対する愛情と誇りの感情もつちかわれてゆくのです。ここに文部省の『国語科学習指導要領』がありますが、幸いにしてその中に、高等学校第一学年の単元の例として、「古典はわれわれの生活とどんなつながりがあるか」というのがあります。しかし、その目標が二〇ばかりならべられている中にも、残念ながら民族という言葉は全くありません。……民族という言葉がないということについては、この場合の古典というのは、なにも日本の古典のみにかぎらないといわれるかもしれませんが、民族の古典に学ぶということは、古典一般の学習に解消されてはならない独自の目標をもつべきだと思うのです。こういうところに、国語科指導要領のコスモポリタニズムがはっきりあらわれています。」と、氏はそこで語っている。そして、 ――「私が古典教育の意義を力説することは、すぐれた古典を正しく教えよということであって、決して授業の上で古典偏重になれということではありません。むしろ近代の文学には十分力点をおかねばならないのであって、そうしてこそ、生徒たちも現実のきびしい問題を正面からうけとめることができるのであり、それによってかえって古典から豊かなものを学びとることができるのです。逆コースの風潮とは勿論たたかってゆかねばなりませんが、それは逆コースをおそれて民族的契機を国語教育から失い、コスモポリタニズムに堕することによってではなく、国語教育の上に正しく民族の観点をすえることによってのみ可能であろうと思います。」と語ることで、古典文学学習と近代文学学習との関係や関連にふれていき、「国語教育の上に正しく民族の観点をすえること」の必要を主張している。 問題は、そこでは、もはや、“言語教育か文学教育か”ではなく、古典文学学習をふくめた文学教育が、それとして正しい民族的視点に立つ国語教育そのものでなければならないことが語られているのであった。 国語科で文学教育を締めだしにして、いったいどこでそれをやるというのか、文学教育を疎外した生活言語教育が、だいいち国語教育といえるかどうか、というにも近い益田氏の批判を、その批判の方向において問題の整理をおこなったのが、荒木氏のこの古典教育論であった。一九五二~一九五三年度は、戦後文学教育史上の画期的な時期であった、と思う。益田・荒木両氏の、したがってまた日文協国語教育部会のこの時期において果した役割、その業績は十分高く評価されてよいかと思われるのである。 ところで、右の報告は、益田氏の場合にせよ、荒木氏の場合にせよ、高校国語教室における実践をふまえての報告であった。そこで、荒木氏の場合、まず、「私が中学のとき受けた国語の古典授業は、なぜそれらが学ぶに値するすぐれた作品なのかということは全く説明されずに、解釈や文法をおしえこまれたり、あるいは私たちの全く理解できぬままに、頭からすぐれた作品であるという前提のもとに教えられました。そこには、一方的に教えこむ立場と、一方的に教えこまれる立場はありましたが、生徒の意見とか感じ方は全く問題にされなかった」ことへの回想から報告がはじまって、そのことへの反省として、「私は万葉を通じて生徒の感じ方・考え方をつかまえようと努め」あるいは「万葉をなかだちにして生徒と話しあおうとした」ことが語られ、ついで氏の指導した高校二年の国語教室のそのおりの模様が語られていっている。 そうした上で、また、氏は、つぎのように主張している。 ――「私たちの学習は生徒の関心から出発しなければならないということが、指導要領などでもしばしばいわれています。しかし、それは生徒の関心のおもむくままに引きづられることではないでしょう。ある場合は、生徒が失い忘れかけている貴重なものを思いおこさせる必要があります。ことに植民地化の危機にあり、青少年の頽廃化が問題となっている現在において、教師は生徒をどのような人間像にむかって教育してゆくかについて、はっきりした目的意識をもつべきです。」文学教育の方法に関するこんにちの問題点が、原理的・原則的には、ほとんどそこで尽くされているように思われるのである。すなわち、 (1) 文学の学習指導は、教師の生徒に対する上意下達の、一方通行の指導方式では実現されえな 。。。いこと、 (2) それは、あくまで生徒の感じ方なり考え方をだいじにした指導でなければならないこと、 (3) けれど一方通行方式にかえある対面交通方式の学習が、「生徒の関心のおもむくままに引きづら 。。。れる」ことであれば、それは指導の放棄以外のものではないこと、 (4) 教師は、あくまで、はっきりした目的意識と指導目標をもって、「生徒が失い忘れかけている貴重 。。。なもの」を彼らのあいだに喚起させる必要があること、 等々である。あえていうが、方法上の原則的な問題処理として、荒木氏によるこの提示を、その後の文学教育論はまだ越えていないように思う。 ところで、右に見る荒木氏の問題提示(とくに(4)の主張とつながる氏の教育実践)が、後の西尾実氏によって“問題意識喚起の文学教育”として方法的に定位されるにいたったものであるが(『文学教育の問題点』――「文学」一九五三年九月号)、何を問題意識とし、また何をもって問題意識の喚起と考えるか、という点において、じつは、すでに、両氏のあいだに基本的な見解の相違があった、と見なくてはならないようである。 ややきっぱりしたいい方をすれば、文学教育に対する目的意識そのものが、方向を異にしているのである。上記、荒木氏のいう「生徒をどのような人間像にむかって教育してゆくか」という、そこに理想像として考える子どもの人間像も、かなり基本的な点でくいちがっていたように思われるのである。問題意識といい問題意識の喚起というコトバが同じなだけで、このコトバによってあらわそうとしているものは、お互いにまったく別であった。 だから、それが西尾氏によって“問題意識喚起の文学教育”というコトバ(概念)でつかまれることによって、荒木氏の提起した問題は、西尾氏独自の理論のペースにおいて再整理され、当初のねらいとは別のものになって人々のまえに姿をあらわす、ということにもなっていったのである。 西尾氏にあっては、問題意識喚起の文学教育とは、鑑賞者がこれまでの生活経験によって、すでに蓄えていたところの“問題意識”を、作品に接することによって“喚起”する、ということ以外ではないのである(前掲『文学教育の問題点』に拠る)。このようにして、また、氏によれば、「作品によって喚起された生徒自身の問題そのものを取り上げるのが問題意識の指導だ」というのであり、「小学校・中学校・高等学校を通じた文学教育の方法としては、その作品の理解・評価ということとは別に、生徒自身に喚起された問題意識をどう指導したらいいかということを、……鑑賞指導の問題として考えるべきだ」(日文協・一九五四年度大会、総合討論)、ということになるのである。 それは、作品の表現理解において、「生徒が失い忘れかけている貴重なものを思いおこさせる」(前出・荒木氏)という意味での“問題意識の喚起”ということとは、まるで方向が違っている、といっていいかと思われる。荒木氏の場合も、「究極の目標は作品を鑑賞することにある」わけだが、その指導の手つづきは「鑑賞する場合、自分の生活と結びつけて味わおうとするように仕向ける」のであり、作品から「逆に歴史への関心をもつという主体的方向」をみちびくのであり、そしてたんに「自分の中にあるもの」に気づかせるだけでなくて、作品の表現を媒介として「ないもの、失われたものを見出して感動」させることに目標があったのだ。 両者のめざすところでは、こうして方向をまったく異にしていた。荒木氏によって修正意見や反批判が展開されたのは当然である(『文学教育の課題』――「文学」五三年十二月号、『文学教育の方法』――「岩波講座・文学の創造と鑑賞」Ⅴ――五五年三月刊)。 そこにおこなわれた論争や、その後の展開については、鴻巣良雄氏の前掲著書『文学教育の発見』(一六五~一八六ページ)においてすぐれた整理と批判がおこなわれているので、それについて見ていただくことにして、(1)荒木氏たちが高校の国語教室でおこなった指導方法を小・中学校の現場に移して、というところから鴻巣氏たちのすぐれた現場の実践がはじめられたらしいことや、(2)こんにちの現場の有力な指導理論である西尾氏の鑑賞論は、数十年来一貫して変らぬ氏の所論の展開であるが、それが戦後、教育の現場に大きな指導性を発揮するようになったのは、直接的にはこの“問題意識喚起の文学教育”の提唱にはじまるものである、ということを、ここではいい添えておきたい。 |
|
|
|
|