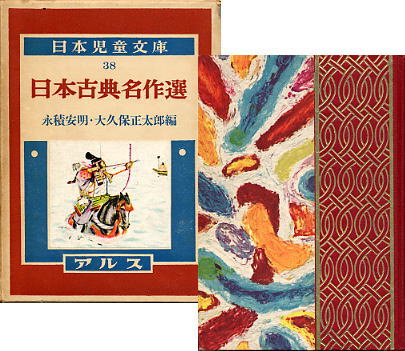目 次 ◆ りくつっぽい子(徒然草) ・りくつっぽい子だね ・ばけネコ ・おに ◆ しおやき文正(文正草子) ・しょうじき文太 ・れんげ ・みやこからきたものうり ◆ 芭蕉の俳句 ◆ 出世景清(浄瑠璃) ・平家のおちゅうど ・あれやうちくびに ・どうしうちはやめよう ・大義にいきる ◆ 町人の世のなか(日本永代蔵) ・大江戸のまんまんなかに ・みんなでうでをくんで ◆ せんりゅう(川柳) りくつっぽい子 りくつっぽい子だね こどものころのことを、ときかれましても、こまごましたことは、すっかりわすれてしまいました。なにしろ、四十年も、それいじょうもまえのことになりますから――。 こどものじぶんというと、五十のさかをこしたわたしには、もう、とおい、とおいむかしになってしまっているのですよ。おもいでをたどることのすきなわたしなのですけれど、少年時代のじぶんのすがたを、いま、ここで、おもいうかべることは、むずかしいのです。 でも、そうですな、父のことは、ときおり、おもいだします。やさしかった父のことをなのです。 父は、そのころ、治部省という役所の役人をしておりました。治部省輔という、この役所の次官のような役をしていたのですが、それが、たいへんいそがしいしごとであることは、こどものわたしにも、よくわかっていました。 父が役所からかえってくるのは、たいてい、もう、わたしがねどこにはいってしまってからのことなのです。それで、たまに家にいるかとおもうと、いつもお客さまのあいてをしているのです。なにしろ、つぎからつぎと、人がたずねてくるのです。 「ご用がすんだのなら、さっさとかえればいいのに……。」 客間のほうからもれてくるわらいごえを耳にしながら、わたしは、よく、そうおもい、おもいしました。人がきていると、父にあそんでもらえないのです。ながっちりのお客が、こども心ににくらしかったのです。 でも、父は、ひまがあると、わたしのよい話しあいてになってくれました。学問もおしえてくれました。そういうとき、父は、目をほそくしてわらいながら、 「りくつっぽい子だね。」 と、口ぐせのように、よく、そんなことをいいました。わたしが、なにか、ものをたずねると、きまって、あとで、この「りくつっぽい子だね。」をくりかえすのです。 でも、ほかのこどもにくらべて、とくべつりくつっぽかったわけではないのです。いま、こうやって、おもいかえしてみても、じぶんで、じぶんが、りくつっぽいこどもだったとはおもいません。こどもが、みんなそうであるように、つじつまのあわないことにたいして、「うん。」とはいえなかっただけのことです。説明をきいても、わからないことは、やはりわからないのですから、 「なぜ?」 「どうして?……」 と、父にそのさきをたずねたというだけのことだったのです。 こんなことがありました。 たしか、わたしが、七つか、八つのころのことだったとおもいます。 「ほとけさまって、いったいなんなの?」 と、父にきいてみたことがあるのです。 父や母が、朝夕おがんでいるほとけさま。わたしも、手をあわせさせられるほとけさま。だれにだって、あたまをさげたこともない大臣や関白のような人たちさえおがむというほとけさま。だから、きっと、えらい、えらいかたにはちがいないのですが、いったい、なんなのでしょう? 「もとは人間さ。人間がほとけになったのだよ。」 なんだ人間なのか。人間がなったのか。 「でも、どうすれば、ほとけさまになれるの?」 「ほとけさまのおしえを、しっかりまもればなれるのさ。」 それはわかった。よくわかった。だが……? そこで、また、きいてみることにしました。 「そうやっておしえてくださるほとけさまは、どうやって、ほとけさまになったのでしょう?」 「べつのほとけさまがおしえてくださったのだろうよ。」 わかたような、わからない気もちです。 「それでは、いちばんはじめに、ほとけさまになったのは、どういうかたなのですか。それは、人間ですか。それとも、はじめから、ほとけさまだったのですか?」 父は、わたしの質問にこたえるかわりに、にっこりとして、そして、こういいました。 「りくつっぽい子だね。」 ばけネコ こんな話をききました。 名まえは、つい、ききもらしましたが、なんとかいうぼうさんが、ある日、ともだちのところへ、あそびにいったのだそうです。ちょうど、そこへ、なん人か、話ずきの人がきあわせていまして、なんだかんだと、せけん話をしているうちに、夜になってしまいました。 「さあ、そろそろおいとましよう。」 ということになって、みんながたちかけると、 「山おくへいくと、ネコマタというものがいて、人をくうそうだ。」 と、そのなかのひとりが、きゅうに、そんなことをいいだすのです。すると、また、べつの人が、 「山おくでなくったって、このへんにもいるそうですよ。ネコが年をとってくると、ネコマタにばけて、人をとってくうことがあるのですね。」 というのです。 ぼうさんは、かえり道のことを考えて、すっかりこわくなってしまいました。一条通り(京都の町の名)のお寺まで、くらい夜道を、ひとりでかえらなくてはならないのですから。 「ネコマタがでたら、どうしよう!」 お寺までは、二キロそこそこの、ちかい道のりだったのですが、そのときのぼうさんには、それが、五キロも一〇キロもある、とおい、とおいところのように感じられました。寺のそばをながれているお川のほとりまでの、三〇分たらずの時間は、その夜は、一時間にも、それ以上にも感じられたということです。 でも、そこのかどをまがれば、もうすぐお寺です。 ぼうさんは、ほっと、ひといきつきました。 「もう、だいじょうぶだ!」 が、あんしんするのは、すこし早すぎたようです。くらやみをついて、とつぜん、ネコマタがあらわれたのです。 ネコマタは、ぼうさんめがけて、まっしぐらにかけてきました。 そして、いきなり、くびすじにとびつこうとしたのです。 「たすけてくれ! ネコマタだ! たすけて、たすけてえ……。」 こしをぬかしたぼうさんは、よろめいて、川のなかへころがりおりました。 そのこえに、ちかくの家々の人たちは、手に手に、たいまつをともし、こんぼうを片手にして、かけつけてきました。 が、おそろしいネコマタのすがたを、だれもみることはできませんでした。人々の目にとまったのは、ひざぐらいまでしかない、あさい小川のなかを、ずぶぬれになって、ころげまわっているぼうさんのすがたと、このぼうさんが、ふだんかわいがっていた、コイヌのすがただけだったそうです。 あとはお話ししなくてもわかるでしょう。主人としって、とびついてきた、かいイヌを、ぼうさんは、ネコマタとまちがえたのです。 おに あれから、もう、二十年ぐらいになるでしょうか。いせの国(伊勢国 いまの三重県)から、おにがやってきたといううわさが、京都の町じゅうに、ぱっとひろまったことがあります。なんでも、そのおにというのは、もとは、人間の女で、それを、だれかが、京都につれてやってきたというのです。 いまになって考えてみると、ほうとうに、ばかげたことなのですが、そのときは、たいへんなさわぎでした。 「きのうは、西園寺へいったそうだ。」 「おに女は、いま、一条室町へきているそうだ。」 そういううわさがたつたびごとに、そのふきんは、おすなおすなのさわぎになるのです。そのあげく、人ごみのなかで、足をふんだとか、ふまれたとかで、なぐりあいのけんかがはじまるのですから、まったくあきれた話です。 むろん、だれひとり、おにをみたものはないのですが、そのはつか間ぐらいというもの、町の人たちは、しごともしないで、ただもう、おにのあとをおいまわしていたわけです。いもしないおにのあとをですよ。 でも、まだ、それはいいのです。そのころ、たまたま、かぜがはやりまして、ふつか、三日と、ねこむ人が多かったのですが、 「おにのつくり話は、あれはきっと、こんどの病気のまえぶれだったのだね。」 というようなことを、もっともらしい顔をしていう人が、でてきたのです。でたらめなうわさに、さんざんひきずりまわされても、まだこりないで、こんどは、じぶんから、でたらめなことをいいだすのですね。そして、それが、でたらめだということに、いいだした本人も気がつかないのですね。 (「徒然草」による。) 「枕草子」とならんで、日本のずいひつ(随筆)文学ちゅうの名作といわれている「つれづれ草(徒然草)」は、いまから六百年まえぐらいに、兼好というぼうさんがかいたものです。どうやったら、人間はしあわせになれるかということを、兼好は、この作品のなかで、いっしょうけんめいになって、考えています。 すみよい世のなかにするためには、めいしん(迷信)にとらわれたり、根も葉もないうわさにひきずりまわされたり、じぶんがさきにたって、そんなうわさをふりまくようではだめだ、と、兼好はいっているらしいのです。「ばけネコ」や「おに」の話には、兼好のそういう考えが、はっきりとでています。 また、そのためには、りくつっぽいといわれるぐらいに、りづめに、こまかく、くわしく、ものごとを考えてみるひつようがあると、「りくつっぽい子だね。」のお話で、兼好は、かたっているようです。 なんべんよみかえしてみてもおもしろいのが、この「つれづれ草」です。 《目次へ戻る》 しおやき文正 しょうじき文太 いつのころのことか、よくはわかりませんが、ひたちの国(常陸国 いまの茨城県)に、しおやき(塩焼き)文正という長者がおりました。もとは、鹿島大明神の宮司の家にめしつかわれている下男でしたが、おもいがけないことから、長者とよばれる、いまの身分にしゅっせしたのでした。 そのころ、文太という名まえでよばれていた、この文正は、根っからのしょうじきもので、あけてもくれても、主人のことを、だいじにおもって、いっしょうけんめいにはたらいていました。ところが、あるときのこと、主人の宮司は、文太にむかって、 「わたしは、なんだか、おまえが虫がすかないのだよ。どこが気にいらないかときかれてもこまるけれど、ともかく、気にいらんのだから、でていってくれないか。」 と、いいました。 とつぜん、どうしてそんなことをいいだしたのか、文太には、わけがのみこめませんでしたが、なにしろ、主人のいうことですから、しかたなく、その日のうちに、宮司の家をでていきました。 どこへいくというあてもなく、足にまかせてあるいているうちに、つのがおかという海べにつきました。つかれてはきたし、日もとっぷりくれましたので、しお(塩)をやいてつくる家へいって、 「たびのものですが、どうか、こんやひとばん、とめてくれませんか。」 と、たのんでみることにしました。すると、さいわい、主人は、なさけぶかい人でしたから、すぐにしょうちしてくれました。 ぐっすりねて目がさめた、あくる朝、 「これだけのたきぎでは、とても、きょうのしごとにはたりないな。山へいって、たきぎをはこんでこなければならんが、あいにく、せがれはでかけてしまったあとだし……。」 と、主人が、ひとりごとをいっているのを、文太は、ねどこのなかでききつけました。 「わたしがいって、とってまいりましょう。」 そういって、朝ごはんをかきこむと、文太は、すたすた、山へでかけていきました。うまれつき力のある文太のことですから、びっくりするぐらいたくさんのたきぎをかついで、ひるには、もう、家へかえってきました。 「いや、ごくろう、ごくろう。」 主人は、おおよろこびです。 「むすこさんがおるすでは、おひとりで、たいへんでしょう。わたしにも、手つだわせてください。」 しょうじきで、しんせつものの文太は、ひとりで、きりきりまいをしている主人をみかねて、こんどは、しおをやいてつくる手つだいをはじめました。 主人は、文太がすっかり気にいりました。いそがぬたびなら、しばらく、しごとの手つだいをしていってくれないかと、そのばん、主人は文太にいいました。文太もよろこんで、このしお屋ではたらかせてもらうことにしました。 一年たち、二年たちました。もうじき三年になります。文太は、ある日、主人のまえへいって、あらたまって、こういいました。 「ご主人さま。わたしも、そろそろ、じぶんで、しおやきの商売をはじめてみたくなりました。どうぞ、しおやきがまを一つ、わけてくださいませんか。」 三年ちかく、かげひなたなくはたらいてくれた文太のねがいですから、主人も、こころよく、しょうちしてくれました。一つとたのんだのに、二つも、しおやきがまをくれました。 そのかまで、しおをやいてうったところが、文太のしおは味がいいというので、ひょうばんです。これをたべると病気はしないし、わかがえるというので、だいはんじょうです。それで、三年たったころには、文太は、いままでの、小さな家をひきはらって、大きな家にすむようになりました。十年たったころには、長者といわれるような、おおがねもちになりました。そうなると、文太という名まえでは、もう、おかしいというので、文正常岡と、名をあらためました。 文正のやしきのひろいこと、りっぱなことは、これは、とても、ことばではいいあらわせません、ほりをめぐらしたやしきのなかには、九十むねの家がたちならんでいるのです。その四方には、くらが八十三もたっています。三百人からのけらいがいることは、たしかですが、下男や女中たちのかずまでかぞえたら、さあ、どのくらいになるでしょう。千? 千五百? いや、そんなことではききません。なにふそくないくらしというのは、このことでしょう。文正の、たった一つの、そして、いちばん大きな不幸は、しかし、こどものないことでした。 れんげ 話かわって、文正をおいだした、もとの主人の宮司です。宮司は、なにも、文正が気にいらなくて、おいだしたわけではなかったのです。しょうじきものだし、人なみいじょうの才能のある人間だとおもったので、 「かわいい子には、たびをさせろ。」 というような気もちで、わざとじゃけんに、 「でていけ!」 と、そういってみせたのでした。ですから、もしも、文正が、ほんとうにこまるようなことがあったら、たすけてやろうと、とおくから、いつもじっとみまもっていたのでした。ところへ、こどもがなくて、かなしんでいるといううわさを、耳にしたものですから、宮司はさっそく、文正のもとへ、手がみをもたせたやることにしました。 その手がみには、子だからをさずかるように、明神さまに願をかけたらと、かいてありました。 文正は、おどりあがってよろこびました。おこっているとばかりおもっていた宮司が、じぶんのことをしんぱいしていてくれたのです。 文正夫婦は、すぐにその足で、宮司のところへあいさつにでかけました。そのまま、七日のあいだ、精進して身をきよめ、鹿島大明神に願をかけました。 「どうか、わたくしどもに、こどもをひとり、おさずけくださいませ。」 すると、七日の満願の夜のことです。つかれがでて、おもわず、とろとろとまどろみました。と、本殿のとびらがあく音がして、 「なんとでも、ねがいをかなえてやりたいとおもって、七日のあいだというもの、あちこち、くまなくさがしもとめたが、おまえたちのこどもになるものが、どこにもいないのじゃ。だが、せっかくのねがいだから、これをつかわそう。」 という、けだかいこえがしました。はっとおもって、目をさますと、文正の妻の手には、レンゲ(蓮華)の花のひとふさがのこされていました。 八月、九月、十月たって、それはそれはうつくしい、かあいらしい女の子がうまれました。 手のまい足のふむところをしらないというのは、そのときの文正のことでしょう。もう、じっとしてはいられないのです。人がなにをいっても、耳にはいらないのです。あう人ごとに、 「うまれたんだよ、かわいいむすめがうまれたんだよ。」 と、いってあるきました。 女の子は、れんげと名づけられました。 それから十年たち、十五年たちました。れんげは、いまでは、もう、一人まえのむすめになりました。ほのぼのと光りかがやくような、うつくしい、うつくしいれんげです。れんげは、顔かたちがうつくしいだけでなくて、心もうつくしいむすめでした。どんなに、心にくったくのある人でも、れんげと話していると、ふしぎに、気もちがなごんでくるのです。れんげは、そんなむすめでした。 うつくしいれんげのうわさを耳にした、関東八国の大名たちは、さきをあらそって、 「ぜひ、わたしのおよめさんにください。」 といってきました。このごろ、めっきり、年をとってしまった文正は、大名のおつかいが、そういってくるたびごとに、 「まことに、家のほまれでございます。」 といって、しわくちゃの顔をほころばせました。ほんとうに、うれしくて、うれしくてたまらなかったのです。 ある日、むすめをよんで、きいてみました。 「どのおかたを、おまえはえらぶかね。」 このかたは、むさしの国(武蔵国 いまの東京都。埼玉県・神奈川県にもまたがっている)のお大名で、たいそうなおかねもちだとか、こちらのかたは、こうずけの国(上野国 いまの群馬県)のお大名で、武勇にひいでたかたであるとか、文正は、いろいろと話してきかせました。 「どなたのよめになることも、わたくしはいやでございます。」 文正は、びっくりしてしまいました。こんなへんじってあるだろうか? あいてはお大名がたなのに……。きっと、むすめは、じぶんのきりょうのいいことにうぬぼれて、もっといいところへ、およめにいきたいと考えているにちがいないと、おもいました。そこで、こんなふうに、きいてみました。 「れんげや、おまえは、お大名がたよりも、もっとりっぱなおかたのおよめになりたいと、考えているのではないかね。」 「はい、おとうさま。れんげは、もっと、もっと、りっぱなかたのおよめになりとうございます。」 お大名がたからの話をことわったということをきいて、こんどは、鹿島大明神の宮司のおつかいがきました。 「れんげを、わたしのむすこのよめにくれないか。」 まえのことがあるので、文正は、すっかり考えこんでしまいました。 「ご恩のある宮司さまのおことばに、どうしたってそむけない。むすめが、もし、いやだといったら、どうしよう?」 が、文正のしんぱいが、ほんとうになりました。 「ご恩はご恩でございます。およめにいくことが、ご恩がえしになるなんて、わたくしには、考えられないことでございます。」 と、きっぱり、れんげがいったからです。 しょうことなしに、文正は、宮司のところへいって、そのとおりのことを話しました。宮司は、かんかんになって、おこりだしました。 「いやとはなにごとだ。なまいきな。いやなら、いやでもよい。文正、そのかわり、おまえを、ろうやへいれるから、そうおもいなさい。」 文正は青くなって、はあはあいいながら、家へかえってきました。そして、むすめに、そのとおりのことを話しました。 「死んでもいやです。どうしてもと、おっしゃるのなら、川へ身をなげて死ぬだけのことでございます。」 そういったきり、顔をおおったまま、れんげはじぶんの居間にかけこんでしまいました。文正は、むすめがふびんになってきました。このかわいいむすめのためなら、ろうやへはいってもいいと、そうおもいました。いくら恩人だからといって、むりをいう宮司が、にくらしくもなってきました。 「ご恩はご恩でございます。」 といったむすめの気もちが、すこしわかりかけたような気がします。それとどうじに、お大名がたのよめにはならないという、むすめの気もちの、ほんとうのところが、ぼんやりとですが、わかってきたような気がします。 「れんげは、やはり、気のやさしい、すなおなむすめだったのだ。おもいあがっていると考えたのは、わたしのあやまりだったにちがいない。あの子にはあの子で、きっと、なにか考えていることがあるのだろう。おとがめをうけたって、しかたがない。そうだ、宮司さまに、きっぱりとおことわりしてこよう。」 そのとき、文正のやしきの門前で、 「みやこからまいった、ものうりでございます。こまもの、けしょう品、ふで、すみ、そのほか、いろいろなものをもっております。一ど、ごらんくださいませ。」 とよぶこえがしました。すんだ、ふくらみのある、わかい男のこえでした。 みやこからきたものうり ものうりは、文正のまえに、とおされました。なにかめずらしいものをもっていたら、それをかって、宮司のところへ、おみやげにもっていこう、ほしいものがあるなら、むすめにも、かってやろうと、おもったのでした。れんげも、よばれて父のまえにまいりました。 ものうりは、ぜんぶで七人でした。年のころは二十二、三の、気だてのやさしそうな、しかし、きびきびした感じのする、わかい男の人が、みんなの主人らしく、ほかの六人のものうりたちは、たいそううやうやしく、そのわかものをあつかっていました。みんなのちゅうもんをきいて、そちらのつつみをあけなさい、あの品を、お目にかけなさいと、さしずしている、そのわかものをみているうちに、文正は、じぶんがわかかったころのことをおもいだしました。 「旅をしていると、いろいろ、つらいことが多いだろうね。」 「いいえ、こうして、みんなで力をあわせて、はたらきながら、旅をしているのは、たのしいものでございます。みやこをはなれてから、かれこれ、もう、二年になりますが、まえにいったことのある土地へ、二ど、三どと、いくことがあります。そんなとき、お客さまが、まえにかった品ものは、つかってみて、たいへんよかった、こんどもかってあげようなどと、おっしゃってくださることがあります。そんなときは、ほんとうにうれしくなりますね。」 文正がたずねたのにこたえて、わかものは、そういいました。まじめなあきないをしているものだけがいえることばです。 「でも、みやこへかえりたいと、おおもいになるときがあるでしょうね。」 と、れんげも、おもわず、口をはさみました。そのことばに、ふかいおもいやりと、したしみがこもっていました。わかものは、ちょっと、くらい顔をしました。が、すぐに、もとの、あかるい顔にかえって、れんげに、ほおえみかけました。 「みやこが、こいしくなることもあります。でも……。」 そういいかけたとき、めしつかいが、 「宮司さまが、おみえになりました。」 といって、文正に、とりつぎました。文正も、れんげも、ぎくりとしました。と、あんないもまたずに、宮司が、その場へあらわれました。 「いや、すまなかった、すまなかった。あとで、しずかに考えてみたのだが、わたしのわがままだったよ、きょうは、わびにきたのだよ。」 そういって、にこにこしているのです。 「おわびのかわりに、れんげのおよめいりには、できるだけのことはしよう、れんげ、そなたは、どういう人のおよめになりたいのだね。」 れんげは、それにはこたえないで、庭さきにたっている、ものうりのわかもののほうに、目をやりました。わかものも、だまって、ほおえんでいました。 れんげは、このわかもののおよめさんになることに、きまりました。れんげは、このわかものといっしょに、ものうりをして、はたらくつもりだったのです。わかものも、そのつもりで、よろこんでいたのでしたが、それができなくなりました。むかえの人がきて、わかものは、みやこへかえらなくてはならなくなりました。 というのは、わかものは、ほんとうは、ときのみかどの皇子で二位の中将という人だったのです。そのころ、宮中では、みんなが、たかい位や、たかい役めにつこうとして、みにくいあらそいが、まい日のようにくりかえされていました。それがいやになって、皇子は、こっそり、旅にでてしまったのでした。 でも、いまはまた、みやこへかえらなくてはなりません。宮中へかえっていかなくてはならなくなったのです。しかし、これからの宮中のくらしは、いままでのような、ひとりぼっちのくらしではありません。れんげという、やさしい、そしてしっかりしたおよめさんといっしょなのです。それに、文正たちも、いっしょにみやこへいって、すまおうといっているのですから。(「文正草子」による) 心のうつくしい、よい人たちが、みんなしあわせになれたというのですから、しおやき文正のものがたりは、ほんとうにたのしいお話です。しょうじきにはたらいているものが、しあわせになれるような世のなかを、という、百しょうや、職人や、商人たちのねがいが、きっと、こういうたのしいものがたりをうむことになったのだろうとおもいます。この「文正草子」や「物臭太郎」のような、おとぎ草子といわれているものがたりがうまれたのは、十六世紀のころです。そのころ、日本の百しょうや、職人や、商人の人たちは、「はたらくもののしあわせな世のなか」をつくりあげようとして、いっしょうけんめいになっていました。山城国一揆のような、百しょうの、かたいだんけつの力や、堺の町のような、商人だけの自由都市がうまれたのも、この時代のことでした。おとぎ草子は、つまり、文学の世界にうちたてられた自由都市のようなものだったのではないでしょうか。 《目次へ戻る》 旅にいき、旅に死んだ 芭蕉の俳句 名月や 池をめぐりて 夜もすがら 十五夜のまんまるいお月さま。雲ひとつない、はれてすんだ空。まひるのようにあかるい、池のほとり。でも、ひるまとはちがって、しいんと、しずまりかえった、あたりのけしきです。どことなく、しっとりとした気分です。 ふと、われにかえりました。夜もだいぶふけてしまっていたのでした。 夏草や つわものどもが ゆめのあと 中尊寺で名だかい平泉(岩手県)には、三代のおごりをほこった藤原氏のしろあとがあります。なん十年かにわたって東北地方の王者であった藤原氏。京都の文化や芸術を、東北のこの地にうつしうえた藤原氏。そして、さいごには、義経をかくまったというので、源頼朝にほろぼされてしまった藤原氏。平泉のしろあとは、そういう藤原氏のおごりのあとであり、血なまぐさい古戦場です。けれど、いまは、夏草がおいしげり、風にゆれているだけです。いまから二百八十年ほどまえ、このしろあとをおとずれた芭蕉は、いろいろなことをおもいだして、なみだをながしました。 さみだれの ふりのこしてや 光り堂 芭蕉は、しろあとの高台をおりて、中尊寺にむかいました。中尊寺には、あの名だかい光り堂があるのです。おりから、さみだれの季節で、道はぬかっていますが、そのぬかるみを、期待にむねをときめかせて、あゆみをすすめます。 光り堂! これが光り堂であるのか。いく百年ものあいだ、雨や風にもまけないで、藤原氏のおごりのあとをのこしている、この光り堂をまえにして、芭蕉のむねは、ふかい、ふかい感動でいっぱいです。しろあとの夏草に、武士どものゆめしかみることのできなかった、すぐあとのことであるだけに、その感動は、いっそう大きかったのでした。 さみだれを あつめて早し 最上川 まい日ふりつづくさみだれに、川はばをまし、にごった、ものすごいながれのうずまく最上川。おそろしい早さで、ものをおしながら、ながれていく最上川の、力にあふれた、すばらしいながめ! 山路きて なにやらゆかし スミレ草 ひとりたびの、さびしい山みちで、ふと、目にとまった、かわいらしい一本のスミレの花。おもわずたちどまって、じいっと、みいったことでした。 ウメが香に のっと日のでる 山路かな ひえびえとする山の空気です。ウメの花のなんともいえない、よいかおりが、ぷうんと、はなをつきます。と、目のまえの山のおねから、のっと、朝日がでたのです。ほんの、みじかいあいだのことでした 旅にやんで ゆめはかれ野を かけめぐる もくてき地までは、まだほどとおい旅のとちゅうで、病気にたおれてしまったじぶんが、うらめしい。こうしてねていてみるゆめは、きまって、かれ野をたびしてあるいているじぶんのすがたなのですよ。 ――ところで、この句をよんだ五十一さいの芭蕉は、それから三日あとの一六九四年の十月十一日に、なくなりました。ですから、これは、芭蕉のさいごの句だということになります。でも、これは、死ぬことをかくごしてよんだ辞世の句ではありませんでした。おでしさんたちが、「辞世の句を」といったのにたいして、「ふだんつくっている句が、わたしにとっては、みんな辞世の句なのだよ。」と、芭蕉はこたえたということです。 《目次へ戻る》 出世景清 平家のおちゅうど 「こら、げろう! ほどなく将軍さまがおみえになろうというのに、ほおかむりなんかしているやつがあるか。」 本田の二郎というさむらいが、年のころ四十ぐらいの人足をつかまえて、しかりつけています。 二郎の主人の畠山重忠は、将軍頼朝のいいつけで、奈良の東大寺の大仏殿の改修工事をかんとくしているのでした。きょうは、工事のすすみぐあいをみようというので、頼朝が、ひるすぎに、ここへくることになっていたのです。それなのに、こんな、れいぎをわきまえない人足が、うろうろしていたのでは、主人のおちどになります。二郎は、それで、顔をまっかにして、どなっているのでした。 そのこえをききつけて、重忠が、まくのそとから顔をだしました。その重忠の目と、人足の目がぱったりあいました。 「あっ、景清。」 人足のすがたの、そのおお男は、門のほうにむかって、さっと、はしりだしました。 「景清があらわれた。悪七兵衛をつかまえろ!」 壇の浦に平家がほろびてから、もうなん年になるでしょう。なく子もだまるといわれた、つよくていさましい平家のさむらい大将、悪七兵衛景清も、いまでは人目をしのぶおたずねびとでした。「草の根をわけても。」といって、源氏がたでは、ひっしになって景清のゆくえをさがしもとめています。それは、ただ、平家の残党だからというだけでなくて、頼朝のいのちをつけねらって、景清が、これまでになんどか、頼朝が、そとへでかけたときなどに、矢をいかけたりしたことがあって、あぶなくてしようがなかったからです。 「いま、頼朝公の身のうえに、もしものことがあったら、それこそ一だいじだ。頼朝公という中心がなくなったら、せっかくこうしてまとまった全国の武士たちも、また、もとの、ばらばらのじょうたいにかえってしまうにきまっている。もしも、そんなことにでもなったら、じぶんたちのことしか考えないような、あの公家どもが、また、いい気になってのさばりだすのは、みえている。こまったことだ。」 畠山重忠は、そのことをおもうと、しんぱいで、いても立ってもいられなくなりました。ことに、こんどの大仏殿のできごとがあってからというものは、重忠のあたまかのなかは、そのことでいっぱいでした。なんとしてでも、景清をつかまえなくてはと、考えました。まい日、まい日、考えに考えぬいたあげく、 「そうだ。これにかぎる。かわいそうだが、いたしかたない。」 と、あることをおもいつきました。そして、さっそく、ウマの用意を命じました。 あれやうちくびに 本田の二郎をせんとうに、重忠の手ぜい十騎は、ウマにむちをくれて、熱田へいそぎました。おわりの国(尾張国 いまの愛知県)の熱田には、景清のいいなずけの小野のひめが、景清の身をしんぱいしながら、熱田神宮の宮司をしている、年おいた父といっしょに、くらしておりました。 だいぶ夜もふけたので、小野のひめが、もう、そろそろやすもうかと、父に「おやすみなさい。」をいっていたところへ、ずかずかと、わらじばきの土足のままでふみこんできたのは、本田の二郎たちでした。 「宮司どのじゃな。こちらは、小野のひめどのか。それ、なわをうて!」 ふたりは、そのまま、京都の六波羅の役所に、ひきたてられていきました。 なにを考えたのか、重忠は、けらいたちに命じて、六条河原にたけやらいをはりめぐらさせました。そこへ、小野のひめと宮司のふたりをひきずりだして、わざと、おおぜいのけんぶつ人のみているまえで、それはそれは、じゃけんないじめかたをするのです。 「景清のかくれているところをいえ。いわぬあいだは、いたいめをみせるぞ。」 にくにくしげに、そういって、さむらいたちは、弓やむちで、ぴしっ、ぴしっと、ふたりをなぐりつけるのです。三十分もすると、気をうしなってしまいます。すると、水をかけて、いきをふきかえさせて、「さあ、いえっ!」と、せめたてます。とても、みてはいられません。ものみだかいけんぶつ人たちも、さすがに、目をそむけるしまつです。 そういうしうちが、二日、三日、四日とつづけられました。 「あのおなさけぶかい畠山さまが――。」 といって、京都の町の人たちは、いつもとちがった、重忠のむごいしうちに、あきれかえりました。きょうは、小野のひめたちも、もう、いきもたえだえです。 重忠は、顔をこわばらせたまま、じっと、それをみています。そして、ときおり、目をちらっ、ちらっと、たけやらいのけんぶつ人のほうに、するどくそそぎます。 「はくじょうせんなら、もうよい。うちくびにするから、さよう心えろ。みなのもの、用意!」 重忠が、つめたく、そして、こわだかに、そういったときでした。 「まってくれ。」 たけやらいを、めりめりっとやぶって、おお男があらわれました。いかりと、にくしみと、かなしみをまじえた、血ばしったまなこです。 「さあ、わしをしばってくれ。そのかわり、ふたりをたすけてやってくれ。」 重忠のけいりゃくは、みごとに成功しました。景清が自首してでたのです。なさけにあつい景清が、ふたりのくるしみを、だまってみているはずはないと、重忠は、きょうのこの日をまっていたのでした。 どうしうちはやめよう 宮司と小野のひめは、それから、重忠や二郎たちのはからいで、手あついかんごをうけました。ふたりの、いたいたしいすがたをみる重忠の目はうるんでいました。 「ゆるしてくれ。ほかに手だてがなかったのだ。」 重忠は、また、まい日のように、ろうやへでかけていって、おなじことばをくりかえしました。 「景清どの。あなたの気もちは、わたしにはよくわかる。かりに、たちばをかえて、わたしが平家がたのさむらいだったなら、やはり、あなたとおなじように、頼朝公をかたきとつけねらったことでしょう。武士のいきじです。義理です。武士は義理にいきなければなりません。」 「…………。」 「だが、景清どの。義理にも、小さな義理と、大きな義理がありましょう。わたしが源氏がたの人間だから、いうのではありません。頼朝公をうたなくてはならないというのは、これは、小さな義理かとおもいます。源氏がたの、平家がたのと、せまく考えるからいけないのです。どちらも武士です。いままで、わたしたちは、どうしうちをしていたのです。いや、させられていたのです。」 景清は、目をとじて、ろうやの板かべによりかかったまま、重忠のことばがきこえているのか、いないのか、わからないようなようすです。いつも、そうだったのです。 「保元のいくさも、そうでした。平治のかっせんのときもおなじでした。こんどの源平のあらそいにしても、やはりおなじことだとおもうのです。それは、ほんとうの敵にむかってながした血ではなくて、敵である公家どもにだまされてながした、みかたどうしの血であったのです。わたしは、それを考えると、くやしくて、くやしくてたまらなくなるのです。二どとふたたび、わたしたちが、どうしうちの血をながさないようにするのには、武士と百しょうの政府――幕府をもりたてるほかありません。景清どの。あなたに、そこのところを考えてみていただきたいのです。」 景清は、しかし、だまって、目をとじたままでした。 大義にいきる それからひと月、ふた月と、月日がながれました。景清の気もちも、このごろでは、だいぶほぐれてきたようです。でも、くらい顔つきです。くるしんでいるのです。 重忠のいうことはもっともだと、おもうのです。りくつは、そのとおりだと、おもうのです。でも、壇の浦の、あのみじめな平家一門のさいごをおもうと、頼朝にたいするにくしみが、また、むらむらと、こみあげてくるのでした。 「景清は、どうしている?」 ひさしぶりに、鎌倉から京都へでてきていた頼朝は、その日、六波羅の役所のおくの間で、茶をすすっていましたが、重忠にむかって、ふと、そうたずねました。そして、きょうは、ひとつ、景清にあってみようというのです。 なわをうたれたまま、景清は、庭さきへまわされて、頼朝のまえにひきすえられました。あいかわらず、目をとじたままです。目をとじたまま、頼朝にむかって、しずかに一礼しました。 「悪七兵衛か。重忠からも、いろいろときいたであろうが、いまは、だいじのとき。この頼朝のいのちは、頼朝ひとりのものではない。わかってくれるか。」 「はっ、はい!」 景清のほおには、ひとすじ、なみだが光っていました。 「わかってくれたか。わかってくれてよかった。重忠、景清のなわをといてやれ。」 「えっ!」 重忠は、じぶんの耳をうたがいました。いや、重忠だけでなしに、景清も、そして、なみいる一座の人たちも、ききちがいではないかと、頼朝の顔をみあげました。頼朝は、ほおえんでいました。 「景清、そなたに、宮崎の庄をとらせよう。が、この頼朝につかえよというのではない。宮崎の庄司(荘園をおさめる役人)として、鎌倉幕府のためにつくしてくれというのだ。武士と百しょうの、このあたらしい世のなかのために、はたらいてもらいたいのだ。」 「はっ!」 といったきり、景清は、その場になきふしました。なわをとかれても、まだ、しゃくりあげていました。が、しばらくして、 「おそれながら、頼朝公をおうらみもうしあげる気もちは、けそうとおもっても、きえませぬ。心のどこかに、頼朝公をうてといっているものが、いるのでございます。が、もはや、景清はまけませぬ。心の、そのこえにうちかって、大きな義理に、武士の大義にいきるかくごでございます。この景清は、きょうから、うまれかわって、小義をすて大義にいきる、武士らしい武士になろうとぞんじます。」 と、なみだながらに、かたりました。 「景清どの!」重忠は、おもわずよりそって、景清の手を、かたく、かたく、にぎりしめました。 「景清どの、おたがいに力をあわせて、あたらしい時代のためにたたかおうではありませぬか。」 (近松門左衛門作「出世景清」による。) 「出世景清」は、人形劇の台本です。いまからおよそ二七〇年ぐらいまえの、一六八六年に、大阪の竹本座という人形劇専門の劇場で上演されました。近松門左衛門が台本をかいて、竹本義太夫というじょうるり(浄瑠璃 さみせんにあわせてかたる一種のものがたり)かたりが、さみせん(三味線)のばんそうで、それに、ふしをつけてかたったのでした。たいへんな人気だったようです。お客は、おもに町人や百しょうたちでした。 この劇が、ひょうばんをよんだのは、作者の近松のねらいをよくつかんで、人形つかいは人形をつかい、義太夫は義太夫で、じょうずに、じょうるりをかたったからです。近松のねらいは、景清を、百しょうや町人たちの代表者として登場させることでした。すがた、かたちは武士でも、心は町人、百しょうというふうな景清を、この作品でえがこうとしたのでした。ですから、「出世景清」にでてくる景清は、「平家物語」や謡曲(うたい)などにあつかわれている景清とはちがって、つよく、ただしく、いきようとする民衆のねがいをあらわした人物になっています。 《目次へ戻る》 町人の世のなか 大江戸のまんまんなかに すこし手びろく、商売をしようとおもうなら、それは、なんといっても、江戸にでることでしょうな。これが三十年、四十年まえの、あのじぶんでしたら、なにも、江戸にかぎったことはなかったのですが、島原のいくさのあと、鎖国のおふれがでてからというものは、江戸ででもなければ、商売らしい商売は、できなくなってしまいましたからね。 いくら江戸でも、青い目の異人さんをあいてにするような、大きな商売はできませんが、でも、いまでは、やっぱり江戸ですね。 江戸には、将軍さまのおられる千代田城を中心に、なん百、なん千という大名やしきや旗本やしきがあります。そこには、十万をこえるお武家がたが、おかねをつかういっぽうのくらしをしているのです。ひと口に十万ともうしますが、これは、たいした人数ですよ。たいしたお客の数ですよ。お客? ……ええ、そうです、わたくしたち町人にとっては、お武家がたは、だいじな、だいじなお客さまですからな。 ですから、大阪や京都の町人で、すこし手びろく商売をしているような人たちは、いまでは、みんな、江戸に出店をもつようになりました。江戸で一りゅうの商店といったら、それは、大阪町人がやっているとおもえば、まず、まちがいはありますまい。わたしのみたところでは、いまのお江戸は、天下の町人のうでくらべ、ちえくらべのひのきぶたいというところでしょうか。町人の戦場、――それも関が原というところでしょうな。 これは、いまから十四、五年前の延宝のころ(一六七〇年代)のことですが、そういう大江戸のまんまんなかの日本橋、本町一丁めに、あたらしい家ぶしんが、はじまりました。本町一丁めといえば、江戸でも、一りゅうの商店街です。大きな店がまえの、ゆびおりの大商店だけが、のきをつらねている、この本町でも、これはまた、ずばぬけて大きなふしんでした。なにしろ、表どおりに面した店の間口が九間(十六、七メートル)もあるのです。それで、おくゆきが四十間(七〇メートルあまり)というのですから、ずいぶん大きなつくりです。 新築のできあがった日には、その店さきに「越後屋」とそめだした、まあたらしいのれんがかけられました。越後屋ごふく店というのです。三井八郎右衛門という、いせ(伊勢 いまの三重県)松阪の町人がはじめた店なのです。 八郎右衛門が、こんど、江戸でごふく屋をはじめるについては、大きな兄、なかの兄、下の兄、そして、したしいともだちみんなのはんたいをうけました。 「ほかの商売はべつとして、ごふく屋だけは……。」 みんながはんたいしたのも、むりはありません。八郎右衛門の身をおもえば、はんたいせずにはいられなかったのです。そのころ、江戸のごふく屋というごふく屋が、かたっぱしから、ばたばたつぶれていっていたからです。 「いまどき、ごふく屋なんか、はじめたりして……。」 ですから、これは、八郎右衛門の身よりや友人たちでなくとも、そういいたくなるところでしょうな。しっぱいするのが、みえているからです。 それというのは、ひと口にいって、お大名がたが、びんぼうになってきていたからです。いまだって、そのとおりなのですが、そのころは、とくに、幕府では、大名がたが、おかねをつかうように、つかうようにと、しむけていました。一年おきに、江戸へでかけてこなくてはならないような、参勤交代のきまりをこしらえておしつけたり、木曽川や信濃川のような大きな川の堤防工事をいいつけたり、ほうぼうのおしろの修理をやらせたり、おかねのたくさんいるようなしごとばかり、お大名がたにいいつけました。それで、いっぽうでは、貿易はしてはいけないというのですから、お大名がたのくらしむきが、くるしくなっていくのは、あたりまえでした。 ですから、お大名がたや、そのごけらいしゅうは、かいたいものも、おもうようにはかえなくなってきましたし、かっても、代金ははらえないのです。町人のほうからもうしますと、品ものはうれないし、うれても、おかねがふところにはいらないというわけです。これじゃあ、商売はなりたちません。 江戸の商売も、だいぶ、つまってきたわけです。 なかでも、いちばんこたえたのは、ごふくものの商売でした。なにしろ、ごふくものは、ほかの品ものとちがって、しいれのもとねが、たかいのです。うれさえすれば、もうけが大きいかわりに、うれなかったら、もう、おしまいです。品ものは、お客の手にわたっても、代金をはらってもらえないのでは、これは、店をしめるよりほかありません。それで、大名やしきや旗本やしきを、おとくいさきにしているような、大きなごふく屋から、店じまいをはじめるようなことになりました。 大きなごふく屋といったら、それは、たいがい、大阪あたりの問屋の出店でした。損ばかりしていて、もうからない、江戸の出店をいつまでもつづけていたのでは、そのうちには、本店のほうがつぶれてしますでしょう。そこで、つぎつぎと、店じまいということになったのです。店じまいまではしなくとも、商売がえをするごふく屋は、ざらでしたよ。だから、ひところは、十けんからあった、本町の大きなごふく屋も、八郎右衛門の越後屋が店びらきするじぶんには、たった二けんか三げんになってしまっていたのでした。 「こじきでも、きものはきております。人間のくらしのことを、ひと口に衣・食・住ともうしますが、すむところをもたぬ、くうやくわずのこじきでさえも、きものはきているのです。きもの……ごふくものは、人間がいきていくうえに、どうしてもいりような品でございます。その、ひつような品がうれないどおりはありません。うれないのは、うりようがわるいからかとおもいます。」 はんたいする兄たちのまえで、そう、きっぱりといいきって、八郎右衛門は、いま、あこがれの江戸へでてきたのでした。はたちまえの、わかいじぶんから、二十年も、二十五年も、いや三十年ちかくかかってたくわえた、労働のあせのかたまりのような二千両あまりのおかねをもとでに、八郎右衛門は、いま、こうして、江戸いちばんの商店街に、大きなかまえの店をだしたのです。 越後屋――それは、三井の家が、おうみの国(近江の国 いまの滋賀県)にあったじぶんから、つかっていた屋号でした。 みんなでうでをくんで 「うれないのは、うりようがわるいからかとおもいます。」 なるほど、これなら、うれるはずです。越後屋の商売のしかたは、ほかの店とは、まるきりちがいます。 だいいち、品ものが、そろっているのです。上州(上野国 いま群馬県)産の日野絹がほしいといえば、二つへんじで、お客の目のまえに、それがはこばれてきます。甲州(甲斐国 いまの山梨県)の郡内絹をみせてくれというお客がありますと、すぐに、でっち(こぞうさん)が、くらへいって、それをとってきます。 「おくさまには、それは、すこし、おじみなようにおもいますが、おなじ郡内でも、こちらの、おはでながらのほうが、よくおにあいのようにぞんじます。……お気にめしませんか? ……がらは、おすきずきでございますからな。それでは、べつのがらを、ごらんにいれましょう。ほかに、いろいろとございますから……。」 手代のいいつけで、でっちが、また、おくのくらへかけていきます。 「越後屋には、ないものはない。」 「あの店へいけば、なんでもまにあう。」 そんなひょうばんが、ぱっとたちました。 これが、ほかの店ですと、 「おあいにくさまで。ごちゅうもんなら、とりよせますが……。」 ということで、すこしめずらしいものですと、すぐには、まにあわないことが多いのです。ちゅうもんしたらしたで、半月ひと月と、産地から品もののとどくのをまっていなくてはなりません。おまけに、とりよせたたんもののがらが、気にいらなくとも、ちゅうものした手まえ、いやいやかうということになります。八郎右衛門の店では、そういうしんぱいはいりません。品ものの種類も、がらも、いろいろなのがそろえてあるから、べんりです。 べんりといえば、たんものを三尺、五尺(一メートル、二メートル)と、お客のいりようなぶんだけうってくれる点も、たいへんべんりです。ほかの店ですと、一反(やく九メートル)よりすくなくはうりませんから、手ぬぐい一本ぶんのきれがほしいときでも、一反のもめんをかわなくてはなりません。それが、越後屋へいくと、まあたらしいたんものに、おしげもなく、はさみをいれて、じょき、じょき、きってうってよこすのです。 「こぎれでうるんで、わたしたちみたいなびんぼう人には、もってこいだね。」 「ほんとうにそうだよ。いりもしないものを一反、二反とかわされるんじゃあ、たまらんからな。」 「でも、越後屋では、かけうりはしないね。玉にきずという感じだが――、」 「なあに、そのかわり、ねだんは、ほかよりぐっとやすいし、三尺、四尺のきれをかうぶんには、現金がいだって、たかがしれているよ。」 そんな話が、おふろ屋のながし場で、とこ屋で、まちかどで、みんなのあいだにかわされています。 品ものは、ちゅうもんのあったときにお客にわたして、代金は、ぼんまえや、年のくれにうけとるという、これまでのかけうりのしきたりを、越後屋ではやめたのでした。それが常識になっている、せけんいっぱんの、ながいしきたりを、じぶんのところだけやめにするというのですから、八郎右衛門も、ずいぶんおもいきったことをやったものです。あいてが、お大名だろうと、旗本やしきだろうと、かけうりはしないのです。越後屋では、いっさい現金がい、現金うりなのです。そのかわり、町の人たちが、そういっているように、ねだんが、ほかの店より、ずっとやすいのです。ですから、おやしきすじには、ひょうばんがわるいが、その日ぐらしのびんぼうな人たちや、ごく、ふつうのくらしをしている町の人たちのあいだでは、かえって、それが、ひょうばんのようです。 みょうに、きかざった、気ぐらいがたかくて、お上品ぶった大名やしきのおく女中なんかが、しょっちゅう、ではいりしていると、気おくれがして、その店へははいりにくくなりますが、越後屋へは、そういうお客は、たまにしかきません。越後屋は、ですから、はいりいい店、かよいよい店、大衆の店なのです。 そして、越後屋が、ひょうばんをよんだのは、店のなかを、いくつにも、いくつにも、うり場をしきって、そのうり場、うり場に、かかりの手代がなん人かいて、かいものの、しんせつなそうだんあいてになってくれるというようなこともあります。そこには、四十人からの、おおぜいの手代がいるのですが、それがみんな、きびきびした感じの手代なのです。そして、そのうり場のひとつびとつが、これは絹のうり場、こちらのほうは、もめんのうり場というふうにわかれているのですから、その点でも、越後屋は、ほんとうに「かよいよい店」です。 「うら長屋にいる浅野さんというご浪人――あんたもしってるだろう、寺子屋をやっている、あのおとなしいお武家さんだが、こんどいいぐあいに、九州のお大名に、おめしかかえということに、話がきまったんだ。」 「ふうん、そりゃあよかった。ながい浪人ぐらしで、あのかたも、ずいぶん、くろうしなすったようだからな。」 だいくの九助と、うえ木屋の与吉は、しごとをしながら、そんな話をしています。 「うん。それはいいんだが、あす、とのさまにお目みえだというのに、きていくのしめ(かみしもの下にきるもの)がないといって、こまっていなさるんだ。」 「大家さんにでも、かねをかりて、したて屋にあつらえたらいいのに……。」 「かねのほうは、くめんがついたんだが、したて屋のほうが、うまくねえ。三げん、四げんと、したて屋をまわってみたが、ちゅうもんがつかえていて、とても、あすには、まにあわないというあいさつなんだ。」 「そうかい、それは浅野さんもおこまりだろうな。」 と、与吉は、こくびをかしげ、うでをくんで、しばらく考えていましたが、 「うん、いいことをおもいだした。越後屋へたのんでみな、越後屋へ……。」 といって、にっこりわらいました、 「いますぐいってたのめば、あすの朝には、きっと、まにあう。だいじょうぶ、まにあわせてくれるよ。」 「なにかい、越後屋では、きもののしたてもやるのかい。」 九助は、いがいそうです。与吉は、まるで、じぶんが越後屋の主人ででもあるかのように、とくいそうにいいました。 「ああ、うでのいい職人を、そうさ、ざっと六十人がとこ、かかえてあるんだ。一けんの店で、なんでもまにあうようにね。また、早く、やすくというわけさ。うでのいい職人も、いまはしごとにあぶれてこまっているからね。これも商人と職人のたすけあいというわけのものさ。」 浪人の浅野さんも、きっと、こおどりして越後屋へかけつけたことでしょう。 八郎右衛門の商売は、お大名あいての商売ではありませんでした。町のどこにでもいるような、ごくふつうの商人や職人、それから江戸のちかまわりの村々のお百しょうをあいての商売でしたよ。お百しょうたちが、ときたま江戸へでてきたとき、野らぎにするたんものやきれを、気らくに、そしてあんしんしてかえるごふく屋といったら、それはやはり越後屋でしたからな。 「かう人の身になって商売しなくては――。」 八郎右衛門は、いつも口ぐせのように、こういっていましたっけ。また、 「ものをつくる人たちの身にもなってみなくては……。」 とも、いっておりましたよ。 「越後屋さんのお店は、品ものがそろっている。どうやっておあつめになるので?」 とたずねる人があると、八郎右衛門は、いつもきまって、こう、こたえました。 「日本国じゅうの村々に、なかのいいともだちがなん百人、なん千人といるのですよ。はた(機)をおらなくては、くらしのたたないような、まずしいお百しょうさんがたと、わたしは、なかよしなのですよ。江戸へでてくるまでの三十年のあいだに、そういう、いいともだちが、たくさんできたのです。いまでも、わたしは、なるべく、じぶんででかけていくようにして、そういうともだちと、おたがいにとくなようなとりひきをしています。まえには、くらしのくるしかった、あの人たちも、それで、いまはどうやら、いきをついているようですよ。いまにきっと、もっともっとらくなくらしになれるでしょうよ。早く、そうなってもらいたいものですね。」 (井原西鶴作「日本永代蔵」による) 江戸幕府が、外国との貿易やゆききをきんじたため、そのあとしばらくのあいだ、日本の産業や商業は、おとろえるいっぽうでした。くらしをつめるにも、かぎりがあります。商売のしかたをかえるほか、町人たちは、いきていけなくなりました。品ものをしいれるにも、それをうるのにも、あたらしいくふうがいります。ちえをしぼって、いきぐるしい世のなかを、根かぎりいきようというのです。くらしのたてなおしに、いっしょうけんめいになっている、そういう町人たちのすがたを、いきいきとえがきだしたのが、井原西鶴の「日本永代蔵」です。「永代蔵」には、三十編の短編小説がはいっていますが、その主人公たちは、生活のくるしみにまけない、つよい人たちです。とちゅうで根まけしたり、あきらめたりしてしまうような人はいません。越後屋の三井八郎右衛門も、そういうつよい人間のひとりでした。こんにちの三越百貨店や、三井銀行のもとをつくったのが、この八郎右衛門です。「永代蔵」は、一六八八年に、しゅっぱんされました。 《目次へ戻る》 せんりゅう(川柳) 朝寝する 人をおこすは ひるという 「いいかげんにおきなさい。もうじき、おひるになりますよ。」 ところで、ほんとうは、まだ、十時にもなっていません。 男の子 はだかにすると つかまらず まだ二つか三つの男の子です。おふろはいやだといって、あっち、こっちへ、にげまわっています。ぬがせたきものを手にしたまま「ぼうや、いけませんよ。」といいいい、おかあさんが、おっかけまわしていますが、なかなかつかまりません。 山ぶしに たびたびばけるは 源氏がた 源頼光や、坂田金時たちは、山ぶしすがたに身をやつして、大江山へむかいました。義経と弁慶たちも、東大寺のきふ金をあつめに国々をまわってあるく山ぶしだと、関守をいつわって、安宅の関をこえました。源氏の人たちは、どうも、山ぶしにばけるのがすきらしかったようです。 山ぶしを たのんでばかに してもらい この山ぶしは、インチキなしかけをしておいて、おがんで、人をだます商売の、山ぶしです。はらのなかでは、ぺろりと、したをだしながら、しかつめらしいつらつきで、「アブランケンソワカ」などとやっています。まるで、じぶんがばかにされるために、わざわざ、山ぶしをたのをたのんだようなものです。 めしびつを かくすが母の おおおこり 「そんなおいたをすると、ごはんをたべさせませんよ。」いけないというのに、おざしきですもうをとって、ふすまに大きなあなをあけたりしたぼうやたちが、おかあさんに、しかられています。 役人の 子はにぎにぎを よくおぼえ まあ、このお子さんったら、にぎにぎがおじょうずですこと。えっ! お役人のお子さまですって? どうりで、おじょうずだとおもいましたわ。おとうさまもおじょうずですものね、そでの下(わいろ)をにぎにぎするのが――。 江戸時代の幕府の役人たちは、わいろを、おおっぴらにとったものです。 十八世紀のなかばすぎごろから、町人たちのあいだにはやった、こっけいな句が、せんりゅう(川柳)です。柄井川柳という、こっけいな句をつくるのがじょうずだった作者の名まえをそのままとって、「せんりゅう」といいならわしたのです。俳句ににていますが、俳句のような、こむずかしいきそくがありません。だれにでもつくれて、だれでもたのしめる、これが、せんりゅうのとくちょうです。生活のくるしみや、かなしみを、わらいにまぎらせてうったえたような句もあります。世のなかにたいするいきどおりを、わらいにつつんで、かたっているような句も、たくさんあります。「役人の子は」の句などは、そのいい例です。右の六つの句は、柄井川柳があんだ「柳多留」という、せんりゅうをあつめた本からとりました。 |
|||||||||||