| 文学と教育 第32号 1964年3月15日発行 |
||||
|
||||
| 〈学習指導体系案〉 岩倉政治『空気がなくなる日』(小学校・六年) 福田隆義 | ||||
| 一、『空気がなくなる日』の歴史的・現代的意義 1 主題的展開の軌跡 ――かなりいぜんのことである。日本のどこから、あんなばかばかしいうわさがひろがったものか? その年の七月二十八日という日に、ほんの五分間ほどのことだが、この地球上から空気がなくなってしまうそうだという話がやかましくなったものだ。」 村にこのうわさをもち帰った学校の小使いさんは、「町のほうは空気のなくなる話でたいへんですぞォ」と、おびえたように目をまるくしていった。けれど、先生たちは、笑って相手にならなかった。「べんきょうしている先生たちにとって、そんなばかげた話は、てんでうけとれなかったから」である。 ――「ところが、そのつぎの日になると、こんどは校長先生が大さわぎをはじめた。」県庁のお役人も、そういっているし、どうもほんとうらしい、というのだ。 ――「わがハイの、まなんだ学問からいえばじゃねえ……」といって、校長先生は、「つまり、この地球よりも、ずっとでっかくておもたい、たいへんな天体が……つまり星がじゃ、わがハイらの世界へ、デーンと近よってくると見たね」と、“学問的”な説明をはじめた。 青くなった先生たちのひとりが、「すると、地球のいんりょくが、そいつのいんりょくにまけて?」と口をさしはさむと、こっくりうなづいて校長先生は、さらにその“学問的”な説明を、不安と得意をごっちゃにした表情で続けていくのであった。 七月二十八日までには、あと一週間しかない。 ――「校長先生は子どもたちをたいへん愛していた。」 だから、校長先生は、自分がさきにたって、どうすれば五分間呼吸しないで生きていられるかというけいこを、子どもたちにさせることになった。 だが、いくら練習を重ねてみても、人間は二分間と息をしないではおれないものだ、ということがわかった。そこで、 ――「いよいよこれは、よういならんもんだいだ。」 ということになった。 ――「けっきょく、だれいうともなく、いちばんたしかな方法は、ゴムのふくろのなかへ、空気をつかまえておいて、いよいよのときに、すこしずつはなからすうほかないらしい、ということにきまった。」 ところが、「これは多くの人々にとってはたいへんざんこくな話であった。」というのは、氷ぶくろにした自転車のチューブにしろ五分間も息をするための空気を入れるのには、たくさんの品がいるわけだし、それを買うための金など、貧乏な百姓にあるはずがないからだ。そうこうしているうちに、一筒一円二十銭だった氷ぶくろが、百円、二百円だしても手にはいらぬ、ということになってしまった。 ここまでが、まず話の半分だ。それから、八人家族のまずしい農民のうえに話が進められていく。 ――「うちのもんが、みんな死んでゆくのに、おらだけ生きのこっておられるかい。」 これは、せめて末っ子にだけでも借金して氷りぶくろを買ってやろうか、と親たちがいいだしたときの子どものことばだ。 ――「かわいそうにな。おまえら、こんな家にうまれずと、地主のだんなのところへうまれたらよかったに……」 ――「そうしたら、おら、おのウスノロの大三郎ときょうだいちゅうことになるんけ?」と、子どもは吐き出すようにいった。大三郎は、自分のことしか考えない、いやなヤツだ。おまけにウスノロで、から威張りのいやなヤツだ。子どもは、親たちが、あんなヤツの家を羨ましげにいったことさえ、腹立たしくてならなかった。 ――「みんな死んでやらあい。」子どもたちは、口々にそういって、表へとびだしていった。 七月二十八日 ――「このぶきみな日は、空ぜんたいを血のようにそめた、みょうな朝やけのなかに明けはなたれた。」 子どもたちは、先生や友だちと最後のお別れをするために学校に集まった。ウスノロの大三郎だけが、自転車のチューブを六本も肩にかけて、南洋の陸軍大将みたいな恰好をしているきりで、校長先生をはじめ、だれもかれも一つのゴム袋さえさげていなかった。 ――「子どもたちは、しかし、このありさまをみて、世の中に金もちというものの、思ったよりかすくないのにびっくりした。」 そして、だれひとり大三郎のことを羨ましがったりする者はなかった。どころか、「こんなウスノロの大三郎などといっしょに生きのこったりしたら、それこそたまらないと思った。」 空気のなくなるウワサは、むろんデマだった。ゴムを高く売りつけて、もうけようとたくらんだ連中の、たちの悪い“つくりごと”だということも、あとでわかった。 そのときがきても、生きている自分を見つけると、「子どもはふいと大三郎の南洋の陸軍大将をおもいだした。そしていまは、おかしいというよりも、なんだかかわいそうな気がしてならなかった。」(熊谷孝著『文学教育』から引用) 2 この作品に反映された民族の体験 ○ 素材と背景 「一九一〇年(明治四十三年)ハレーすいせいが地球に近づくというので、さわがれたことがあります。それが、この作品のもとになっています。ここには、さわぎのばかばかしさが、こっけいにえがかれているだけではありません。生きるか死ぬかというさわぎのなかで、こどもや村の人たちが、なにを見、なにを感じたかを、ひとつ考えてみてください。」以上は、アルスの『児童文庫』に掲載されている作品解説の一節である。 この作品が『子どもの広場』に発表されたのは、一九四七年十一月、例の二・一スト禁止直後である。当時、この『子どもの広場』を中心に、民主的・芸術的な児童文学の珠玉の幾編かをうんだ。そのなかの、まさに珠玉の一編がこの『空気がなくなる日』だと思う。かつては、映画化され、文部省選定のなったし、テレビで放送されたこともある。 ○ 登場人物 「こどもや村の人たちが、なにを見、なにを感じたか」ではなく、子どもや村の人たちのなかに、読者はなにを見、なにを感じたかが問われなければならない。 そこには、権威に対しては疑うことさえ知らない、おかしな学識・善意だけの愛情をもった校長をはじめ、先生たちがいる。いくらだまされようと、おこることをわすれた、無気力で貧しい村の百姓たちがいる。そして、彼等は、地主のダンナに“こび”、ダンナを“羨む”ようなおとなたちである。 いっぽう、村のおとなたちの“こび”のうえにあぐらをかいている人がある。自分だけが生きのびようとする、いわゆる地主のダンナ一家がそれである。しかし、それも結局は、悪どいゴム商人の計略には、おどらされてしまう存在である。無学で、おひとよしという意味では、百姓たちと同じ人間でしかない。 こうした、校長的な知性を欠いた善意や愛情では、どうしようもない世の中である。「せめてこの子だけでも……」というようなゆがめられた愛情、また、自分だけは生きのびようとするような考え方では、どうすることもできない世の中である。そうした愛情や考え方にたつかぎり、真けんになればなるほど、こっけいにならざるをえないのである。 こうした、おひとよしのおとなたちに対して、生死のドタン場にたたされたこどもたちは、実に勇敢である。自覚はしていないにしろ、そこには連帯感の芽ばえがある。ある方向を探りあてている。おとなたちの、あきらめきった、いくじなさとは、まったく対照的である。こうした、こどもたちにとっては、親たちのいくじない生き方は、はらだたしくさえ感じるのである。また、日ごろはいじわるでげじげじと思っていた大三郎でさえも、同情すべき存在となってしまうわけである。 ここにでてくるこどもたちこそ、善意だけでは、また、自分だけは、という考え方では生きることさえできない時代の、あすを切りひらく可能性をひめた人間として、期待されていると思う。 二、 発達からみた学習過程 1 この作品と子どもたち 六年生の子どもたちは、自分と生活を共にしている父母とか、接する機会の多い、担任の教師や、専科の教師に対しては、かなり批判もし抵抗もする。しかし、接する機会の少ない校長・区長・知事、あるいは、警察の人たちなどの発言に対しては、無批判になりがちである。つまり、自分たちの身のまわりにいる人に対しては、その弱点、欠点を見ぬくことが可能なわけだが、直接交渉のすくない、地位のたかい人たちに対しては、わりに従順である。そこには、まだ子どもたちの権威主義がのこっている。 ところで、ここに出てくる校長の“学識”や“盲愛”あるいは“権威主義”を、そのまま受けいれるほど、子どもたちはチョロくはない。笑いとばせるだけの批判力は育っている。作中の校長や先生たちを笑いとばすことで、今までは見えなかった、自分たちの生活とは直接ふれあうことのすくなかった人たちへも、批判の目を開かせたい。また、そうすることが、意識しなかった、自分自身の権威主義にも気付くことになると思う。 いっぽう、子どもたちは、互にひはんはするが、それは正面きって批判しあうというより、むしろ、かげ口や、つげ口の形をとってあらわれる場合が多い。また、そのなかには、他人を批判することで、自分が、いい子になろうとする、自己弁護的な要素が多分に感じられる。つまり、自分のなかにすむ、大三郎的なエゴや、おとなたちの弱さに気づいていないわけである。互に、自分の弱さ、みにくさをカバーしたおつきあいでは、本当の仲間意識は育たないと思うし、学級集団としての成長も期待されない。 校長や大三郎、あるいは、村のおとなたちを批判するなかで、自分自身の弱さ、みにくさを自覚させたい。そうした自覚にたって、互に交流・交換することが、子どもたちの連帯感をうむことになると思う。そして、その連帯感が、クラスの中の大三郎的な存在に対する批判・抵抗となると思うし、みんなに共通の加害者である、現実のゴム商人的な存在にも気づくことになると思う。 2 展開の視点 (1) デマが広まった経緯をつかむ イ. デマは、誰が、なんのためにつくったか ロ. さわぎが大きくなったわけ ・ 校長や、先生たちの“権威主義” ・ 校長の学んだ学問、知性を欠いた善意のおろかさ ・ 自分の校長観と作中の校長とのちがい (2) デマを信じた人たちはどうしたか イ. 校長の対処にしかた――そのおろかさと結末―― ロ. 村のおとなたちと、こどもたちの対処のしかたのちがい ・ 貧富の矛盾と、その対処のしかた ・ 親とこどもの考え方・対処のしかたのちがい ・ 自分自身がここにいたらどう対処したか ・ こどもたちは、このさわぎで何をつかんだか ・ このさわぎで得をしたのは誰か、損をしたのは誰か (3) 大三郎像はどうかわったか イ. 大三郎自身はどうかわったか ロ. こどもたちのみかたはなぜかわったのか 〈補説〉 展 開 例 1 子どもたちの反応 この作品は、五年生のときに一度読んで聞かせたことがある。従って、自分で読むのは初めてであっても、子どもたちにとっては二度めの出会いである。 子どもたちは「空気がなくなるなんて、そんなバカな」と思いながらも、やっぱりおもしろいと思ったらしい。バカなうわさだということは、わかっていながら、ついついひきこまれてしまうというのである。 ① ところで「どこがおもしろかった? いちばん印象に残っている場面は?」という問いに対して、子どもたちは
② 次に、感想めいたことを話させてみた。発言の順に列記してみると
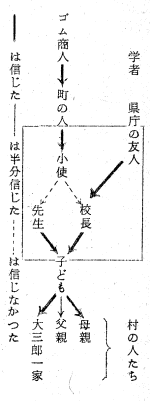 2 読みをたしかめる意味で 子どもたちの発言イ・ホ.ヌ.などから考えて、デマがどういう経路で広まったか、また、そこではたした、校長や先生たちの役割(権威主義)については、あるていど、共通な感じとりかたをしていると思う。従って、その点については、読みをたしかめる意味をふくめて、ざっと左(右)のような図式で整理をした。なお、校長や先生たちについては、先へいって別の視点(愛情)から、もう一度ふり返ってみたい。 太線にするか、細線にするか、点線にするかを考えさせながら、読みをたしかめていった。むろん、こうした図式ではあらわせない複雑な伝わり方をしただろうということを確認したうえで、特にワク内に重点をおいて話しあった。 3 大三郎像について こうしたたしかめのうえにたって、ハ.ト.チ.のように、ちがった反応をしめした、大三郎像をまず問題にした。
① はじめ……にくらしい (ばかいばりにいばっていた) ② 次に ……おかしい (南洋の陸軍大将) ③ いまは……かわいそう (?) “ずるい”といった子は、むろん②①を中心にして考えていたし“かわいそう”といった子は③②を中心に考えていたわけである。だが、かわいそうな大三郎のイメージは、どうもはっきりしないらしい。そこで
① チューブを買って損をした。 ② 小使いさんやみんなにいじわるをされたり、わらわれたりした。 ③ どうせひとりでは生きていけないのに、死ぬ決心ができなかった。 ④ ほんとうはみんなといっしょに、死にたかったのにチューブをもってこさせられた。 ⑤ チューブをわけてやりたい気持はあったかもしれない、だが、親が「絶対にやってはいけない」といったのではないか。 ⑥ 自分の思いどおりには、なにもできない子ではないか。 などなど、結局は、大三郎も根っからの悪人ではないらしい。みんながしんけんにれんしゅうしているところや、死ぬ決心をしたのをみて、だんだんかわってきている。むしろ、悪いのは大三郎の親のほうではないか、という整理をした。そうした整理から、「これからさき、きっと大三郎もみんなと友だちになったと思う」とか「みんなも、大三郎をのけ者にはしないだろう」などという見とおしまでつけた子もいた。 4 おとなたちについて 「大三郎の親のほうが悪いのではないか」という整理から、いきおい話しあいは、おとなたちの生き方、考え方に発展していった。ここでは次の三名を比較しながら話しあいをすすめた。 ① 大三郎の親について ② こどもの親について ③ 校長・先生たちについて ①は直接表面にでていない。従って、大三郎を通して、あるいは、子どもたちの発言や、こどもの親たちの発言からイメージ化していくよりしかたがない。が、子どもたちは、それらの発言から「へいにかこまれた大きな家に住んでいる」とか、「デップリ肥ったおじさんで、眼鏡をかけてツンとしたおばさんらしい」、あるいは「きっとヒゲをつけて、いやな目つきの人だ」などと想像していった。 ②については、 イ.地主のダンナに対する態度を、こどもたちのそれと比較しながら考えさせた。また、 ロ.米一石十四、五円と、氷りぶくろ二百円を対比したり、現在価に換算してみたりした。そのことで、貧富の矛盾を明確にすると同時に、①のダンナのイメージ化もより確かにすることができると思ったからである。さらに ハ.その貧しさからでてくる愛情のゆがみを、こどもたちの考え方とくらべながら問題にした。こうした話しあいのなかで「私のおかあさんも、きっとこどもの母親のようにするだろうと思うし、私もいやだけど、そんなおかあさんになりそうな気がする」という発言もあった。つまり、子どもたちは、こどもの母親を通して、現実の母親や、自分自身をみつめていたわけである。 ③校長や先生たちの“権威主義”については、すでに感じとっていると判断し、ここでは「校長先生は、こどもたちをたいそう愛していた」という、その愛情のあり方を中心に話しあいをすすめた。「校長先生は、ほんとうにこどもを愛していたのだろうか? こどもたちを愛したことになるだろうか?」という視点、つまり校長のつもりと、結果のズレを問題にしたわけである。そのことは、校長や先生たちの“権威主義”にもつながると思う。 5 まとめとして 以上の学習のまとめとして、最後の時間に次のような二つのことをおこなった。 ① 登場人物と自分とをくらべてみる ② 登場人物をグループにわけてみる ・二つのグループにわけると、どうわかれるか ・三つのグループにわけると、どうわかれるか ①では、ポツポツでていた「いやだけど、私もこどもの母親のようになりそうだ」などという方向で、自分を見つめさせたわけである。案外「大三郎に似ている」とか「大三郎と似たところがある」という自己批判が多かった。 また、ここでは単に自己批判ということにとどめず「校長のように、自分では、自分のことがわからないことだってある。友だちの意見も聞いてみよう」ということにして、自己批判を、さらに、友だち同士で批判するというかたちをとった。 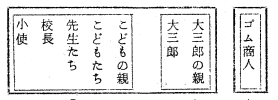 ②二つのグループにわけるのは、容易であった。が、三つにわけるわけ方には、いろいろな視点があった。 たとえば イ.デマをつくった人 ロ.デマを伝えた人 ハ.デマにまよわされた人、あるいは イ.自分のことしか考えない人 ロ.こどもたちのことを心配した人 ハ.心配された人 などがそれである。 そこで、上記(右)のようなワクをはめて、ワクづけの理由を考えさせた。ここでも、考え方は二つあった。 イ.もうけ主義の人 ロ.損をした人 ハ.死ぬかと心配した人、というのと、 イ.もうけ主義の人 ロ.生きようとした人 ハ.死を覚悟した人たち、というのである。教師は後者のわけかたを予想していた。 (筆者自身の訂正書き入れ本により、表現を変えたところが数ヶ所ある。) |
||||