| 「文学と教育」第24 1962年5月31日発行 |
|
| デューイの芸術理論と文教研理論の対応するところ 小枝木昭定 | |
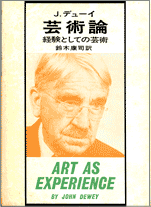 ルーズベルト大統領の時代、いわゆる「ニューディール政策」がアメリカで実施された、その翌年、一九三四年に、デューイは『経験としての芸術』を世に出している。 一、認識論の角度から デューイは、その第三章の中で、彼が問題として、とりあげようとしている「経験」の概念を、哲学の立場から言われる「単数の経験」とも区別して、「完成された経験」あるいは、「一つの経験」というコトバで表現している。 つまり、この場合の経験とは、統一性を持つものであり、完結・終局に向って進む、まとまった一つの経験だというのである。 そして、さらに「知的経験にして、それ自身、完全なものであるためには、美の刻印を帯びなければならない。」(経験としての芸術 P45)といっているが、これは「認識」が認識として成立する一つの条件を、いい表わしているものと考える。 註 以後「経験としての芸術」から引用した個所は、Kという略記号を用いる。熊谷さんは「体験は体験として、体験される限り、それだけでまとまった全体的なものだ。」(源平盛衰記論序章)といっている。 両者のこのような発想は、認識の成立を反映論をとおして、知性と感情の統一という視角からみていこうとする。つまり、「まるごとの認識」と、われわれがいっている考え方と相通じるものがある。 デューイは、また、デューイなりの科学的根拠から、認識の基礎的条件について述べている。 第六章の中で、デューイは次のようなことをいっている。「実験室内の最も画一的な条件の上でさえも、“単”色は複合的で、その端は青みがかっている。」(K・P121)つまり、視・聴覚ならびに、触覚や味覚ですら、それらは実際には単独に作用するのではなく、複数の感覚が相互に作用し合って、美的性質を帯びるのだということである。このような感覚的素材に関する科学的成果にもとづきながら、「“純粋”または“単一”な性質の経験はない。また、その性質が単一な感覚だけに限られた経験はない。」(K・P121)そして、感覚的なものと、知的なものを対立させるのではなくて、「両者の相互浸透」によって、芸術性の真価が認められるのだといっている。 二、創作と鑑賞 デューイは“芸術的”というコトバと、“美的”というコトバとを、同時に意味するようなコトバが英語にないことを不幸だといっている。このことは「創作と鑑賞」の問題についての、極めて、明解な問題提起である。 あわせた意味を持つコトバがないということは、デューイが彼自身の芸術論を展開するのに、不便なことなのだという意味が含まれている。「芸術的」と「美的」が別々にあるということは、「芸術が、なにか美的素材の上に積み重なったものと考えられ」(K・P47)たり、鑑賞活動は「創造活動と何ら共通点がない」(K・P40)とまで考えられてしまう危険があるからであろう。 デューイが、このようなことを不幸だといったり、危険なことだと感じるのは、すでに、そのこと自体が、デューイの芸術理論の展開の方向を示している。つまり、「芸術の創作の面と、享受としての認識、鑑賞の面と互いに支持し合う関係」(K・P47)をいかにしてつきとめようかという、彼の基本姿勢が、うかがえるからである。 デューイの芸術論の基礎には、二つの土台がある。 一つは「経験」を受動と能動の関係としてとらえ、他の一つは、「認識」をそれらの相互作用の調和したものとしてとらえる、とらえ方である。 このことを、作家の創作活動の面にあてはめてみれば、作家は「自己の中に鑑賞者の態度も兼ねそなえて」(K・P57)いなければならないし、同時に、鑑賞者は作家の置かれているこのような関係をもちながら、「鑑賞者自身の経験を創造しなければならない」(K・P64)ということなのである。 しかし、このことは、作家の経験と読者の経験とが文字どおり同一というわけではなくて、鑑賞者、つまり読者の中で「再創造の活動なくしては、ものが芸術品として、認識されることはない。」(K・P65)ことをいっている。 デューイのこういう考え方は「鑑賞主義のエセ科学的な“方法”の基礎づけに悪用された“追体験”の神秘作用」(文芸学への一つの反省)を信じていた、いわゆる、三十年代の日本の鑑賞主義者に対する熊谷さん及び、そのグループの理論と相通じるものがある。 熊谷さんたちは、さらに、古典の問題にふれながら、甘粕石介氏の「芸術学」を批判している。つまり、その批判の中で、作家と作品と読者の関係について、「どの時代の、どの層の人々が読んでも、一つの作品は普遍の真理を同じ度合で語り得る」(文芸学への一つの反省)などと考えることの非を、指摘している。 「追体験を方法とする形而上学、鑑賞主義の文芸学への抵抗の武器として」(文学と教育・四号P6)“準体験”理論の提唱者は次のような立場に立つ。つまり、芸術的体験とは「人間の主体的な実践活動であり、そのようなものとして、社会的体験」(不可知論と芸術学)なのだという。そのような認識をふまえた上で理論を展開する。 本来の読者ではない読者が、歴史的に高く評価されている、ある作品に対して、たまたま、感動したことがあったとしても、そのことが、そのまま、作品の中に内容が封じこまれているからなのだと、推論するわけにはいかない。 というのは、「コトバの融通性と、読者の体験の融通性とが、鑑賞の可能な範囲を規定し、コトバの規定性と、読者の体験の確かさが、その受けとり方の正しさを保障することになる」(源平盛衰記論序章)からである。 デューイは、鑑賞的・認識的・享受的経験に関連を持つコトバとして、「美的」というコトバを設定している。この限りにおいては、もちろん、問題はない。だが、デューイは鑑賞や認識の成立するそのしくみについて、明確に分析し、説明しつくしているとはいえない。 この問題について、熊谷さんは「作家の内部」という論文(文学と教育・二二号)の中で、創作過程の側面から、作家と読者との関係を明らかにしている。そこでは、作家が作家の中に温められた読者の体験をとおして、読者のすぐれた部分につながっていく過程を、きめ細かに分析している。このことを、熊谷さんは、「創作と鑑賞の弁証法」と呼んでいる。 デューイの場合では、表現の完全性は「作品を享受する人を、暗に予想し、兼ね具えて」いなければならないといっている。暗に予想し、兼ね具えることが、どのようにして成り立つのか、その点をつきつめていっても、「作家の内部」ほどの明確さが出てこない。このことは、デューイの芸術理論の、ひとつの弱さとして考えられないだろうか。 実態と形式の問題についての、デューイの理論の中には、芸術における表現および表現理解の基本的な線が示されている。そして、それは文教研の理論とふれあういくつかの面を持っている。また、「芸術的」と「美的」の二つの語の意味を併せ含むコトバという発想も、デューイの芸術理論の、すぐれた部分として認められよう。だからこそ、デューイのそれが「文芸学への一つの反省」につながる論理を持つことも、できたのである。 けれども、そのように、いくつかのすぐれた面をもちながらも、認識論、創作と鑑賞、あるいは、創造性の問題を、さらに一歩おし進めようとする時に、それらをはっきりさせようとしても、しきれない何かが、そこに残る。それは、デューイへの理解の不足からくるものなのか、それとも、デューイ理論の科学性の弱さとしての結果なのだろうか。 もし、そうだとするならば、「経験としての芸術」が「観念論」へと傾斜していく可能性を、全くはらんでいないとはいえまい。
|
|