| ▼1988/01/09 №365 冬合宿研究会 略報 S氏ノートより まず最初に、熊谷孝先生に感謝の意を表したいと思います。合宿中、三日間通してチューターをして いただきました。ありがとうございました。 初日、二時から始められた研究会では、冒頭、N.T.、Y.A.両氏によるオリエンテーションから始められた。以下、要旨・抜粋。 文学の科学とは〈統一テーマ〉 ・ 文学とは、文学的感動を自他に成り立たせることである。 ――科学とか、概念の網ではこぼれてしまうもの、それを丸ごとつかむこと。 ・ その文学を文学としてつかむ方法は鑑賞においてしかない。 ――歪みや、浅さを自覚し、まっとうな鑑賞を成り立たせるもの、それが〈文学の科学〉である。 ・ だから、鑑賞という操作なしには〈文学の科学〉は成立しない。 ・ 鑑賞を離れて、それとは別の所に〈文学の科学〉が在るとすれば、鑑賞は科学以前ということになる。 ――鑑賞は鑑賞、それとは別に〈文学の科学〉があるとすれば、これは明らかに二元論に陥ってしま う。 ・ ただその〈文学の科学〉も、単独では科学として成立しない。 ――歴史学、経済学(史)、哲学、言語学、心理学、文献学、等々の他の諸科学との支え合いがなくてはならない。このことは、他の科学の場合も同様である。 今回の研究会で、メインの作品を「菊花の約(ちぎり)」(『雨月物語』)に決めたのは、今迄に取り上げたことがなく、各自がまっさらな気持でまず読んでみる、その自他の鑑賞過程をとおして〈文学の科学〉とは何か、を明らかにしていこうということである。 この作品は、熊谷先生の提案によるものである。その理由は、「菊花の約」は『雨月物語』を代表する作品であり、太宰文学につながるものがある、ということ。 予備知識はこれだけであって、いわば各自が思いおもいの羅針盤を手に、『菊花の約』の世界にとび込んでいった、というのが、今回の冬合宿であった。 〈話し合い〉の中から 〔Kg〕 丹治は私だ!、という実感が湧かないと、この作品は読めないのではないだろうか。彼はただの悪玉ではない。 〔熊谷〕 たしかギュヨーだったかしら、同質の感情を持たない人はその作品の鑑賞者たりえない、と。「文学は常に私の鏡である」。これは、むしろ、同質の感情に、自己の感情が組み変えられない限りは――というふうに言ったほうがいいと思うが。 〔Yg〕 左門の自己変革に眼を向けたい。それは単に学問ということではなく。 〔Ys〕 封建武士道といったものではなく、敬愛、愛情といったものの持続的なメンタリティーの中で信義を貫いている人間、それは、何かが起きたときでも、なお貫ける人。――この作品では、それが近世を含み込んだ形で描かれている。 〔Ki〕 ひとりで読んでいたら、この作品、こういうふうに見えてこなかっただろうと思う。自己のメンタリティーを揺さぶっていく、そこにつながっていくという姿勢で作品を追っていく、ということではないか。 〔St〕 ただ概念的につかんでいこうとすると作品はつかめない。ギュヨーの言っている通りだと思う。 〔Td〕 作品の冒頭部分(三行半)の読みで、熊谷先生は「秋成は怒っている」と言われたが、“年表”(昨年夏の全国集会、熊谷先生の講演レジュメ「近代文学における異端の系譜」内の“年表”)の見方を説明していただくことによって、その意味が具体的に分かったような気がする。 〔Ak〕 文体において思索することと「私は丹治だ」という姿勢が鑑賞の基本だと思う。 〔熊谷〕 自分に怒りの感情体験がない人は、冒頭の三行半を単に“結論”として見てしまう。そうではなくて、自己の怒りの対象に向けて、それは最も文学的表現になっているのではないか。「教師が教師でなくなった日」(都高教)が文学になりえているということなのだ。このことは、階級論、階級感情につながっていく。教師が教師でなくなった時、それに怒りを感じない人は、文学に無縁の人である。 ▼1988/01/23 №366 1月第一例会 報告 S .T. ▼1988/02/13 №367 1月第二例会 第37回全国集会プラン検討 S氏ノートより 〈集会テーマ〉鑑賞体験の変革と文学の科学 ――文学教育方法論の直接的な、最重要課題 ○〈鑑賞〉とは〈鑑賞体験〉のことである。その鑑賞体験の深まり、というのは、鑑賞体験の変革のことである。またそれは、自己変革のことであり、相互変革のことである。 ○「文芸学」とか言って、何か出来上がっているみたいに考えている人がいるが、そういう考え方をまずぶちこわしたい。文学のバイブルみたいなものはない。〈文学の科学〉、それはまだ未成熟であり、未完成。だから、同じことなのだが、「文教研理論」ということじゃなくて、自分の理論がどう在るか、というふうに考えてもらいたい。 ○科学を自己の中に成り立たせるために、鑑賞の変革をめざすのだ、ということ。 ○鑑賞の普遍化、それは鑑賞の変化なしにはできない。 ○客体(Gegenstand)―――客体の対象化――→対象(Objekt) この「対象」が〈文学の科学〉の対象である。文学現象(アピアされたもの)として対象化したものであり、客体一般(文字のラレツ)ではない。(英語の「object」では、この両者を区別しにくい。) ○〈世代(Generation)〉――〈階級〉では解決し尽くせないからこそ、この概念を持ってきたのである。 -------------------------------------------------------- ●熊谷先生 激怒! ――仲間だったら、人の書いたものをきちんと読め! ▼1988/02/27 №368 文学の科学とは何か――2月第一例会(2/13)報告 Y.H. (一)全国集会 第2次プランの検討 2月第一例会は、第37回全国集会の第2次プランの検討から始められた。 前回の1次プランの検討が、主に集会テーマの要請する原理論を中心になされたのに対し、今回の検討は、そのテーマを参加者全体のものにするためのプログラム構成にむけられた。その中で特に、第Ⅲ部(注:シンポジウム・文学系譜論への要請――鑑賞体験の自己変革のために/文学史の方法と文学教育の方法との接点)に質問が集中した。[中略] (二)文学の科学とは I.M.報告 ① 「自我の原点への問い直しなしには、芸術の原点への思索というものはない。(熊谷孝『芸術の論理』)ということを今の時点で展開してみると、「鑑賞体験の変革」と「文学の科学」とは別々のものではないというふうに押さえられよう。 ② つまり、鑑賞体験は固定的なものではない。その鑑賞の変革過程の中に「文学の科学」が内包されているのだ。 ③ いいかえれば、自己をはなれて鑑賞体験はないし、概念的整理もない。 ――芸術の論理の問題として、熊谷先生が一貫して追究してきている論理をI さんは整理する。つづけて概念化の問題に入る。 ④ その概念的整理は、ところで、どこの誰にも通じるというようなものではない。文学の原点が違っている者には、概念もまた違ってつかまれてしまうからだ。 ⑤ 例えば、「文学的イデオロギー」という概念一つにしても、熊谷先生のこれまでの文学体験、鑑賞体験のいわば総括が概念化されるわけだから、その概念を理解するということは、同時にその鑑賞体験をも媒介しない限り、成り立たないわけのものだろう。 ⑥ したがって、文学現象を概念的に明らかにするときにも、“普遍的概念整理”と名づけたいような方法が要請されてくるのではないか。 ――I さんは、さらにそうした概念整理を表現する方法についても考えをすすめる。 ⑦ “文学の科学”の文章、例えば研究論文にしても、評論、批評にしても、自己の鑑賞体験がイメージ豊かにみえてくるような文章でなければならないだろう。 ⑧ 客観主義的文章では“文学の科学”が実現していないのだ。 “文学の科学”の成立条件として、以上の諸点をI さんは示した。引きつづいてK.T.さんが「菊花の約」に即して、文学の科学とは何か、を報告された。 (そのK.T.報告と、その後の話し合いの内容は次号のニュースで紹介します。――ニュース部) ▼1988/03/12 №369 2月第一例会報告(つづき) Y.H. 文学の科学とは何か――K.T.報告「菊花の約」に即して ① 今回読みかえすにあたり、素直に読もうと心がけた。言いかえれば、自己の主体をかけて読むことだ。それが文学を文学として読むことになるのだと、あらためて思った。 特に冒頭部分。以前はこれが作品の結論ではないか、とか、道徳訓を示しただけではないかと理解していた。作品に距離をおいていたわけだ。冬合宿で、熊谷孝先生から、「秋成は怒っている」という指摘をうかがい、人間疎外の悪現実が、今の自分の問題とつながってきた。がぜん、作品がおもしろくなってきた。 ② “場面規定”、それは、外側にある「時代背景」ではないと、わかっていたつもりだったが……、自分の現実の問題として、自分の感情においてつながるとき、生きた場面規定となることを、今回実感した。“本来の読者”概念にしても、かつては、当時の一般的読者層を思い浮かべていた。が、今、作品と対話する読者の内側の問題だと理解されてきた。外側に固定した読者一般が存在するのではない。 ③ ここでI 報告につなげてみると、“場面規定”とか“本来の読者”という概念も、相互に高めあう主体、作品と対話し続ける主体でなければ、使えぬ概念なのではないかと思った。冬合宿の際、「丹治は私だ」と発言した。私自身をみつめ、自己を可変的につかもうとすれば、「左門もまた私だ」とも言えるように、今、思っている。 〈話し合い〉の中から ★熊谷さん―― お二人の報告とそれに対する意見の方向に賛成。が、もう一歩踏み込んで、文学の科学を考えあってみたい。『芸術とことば』『芸術の論理』で芸術現象を解明し、“芸術の科学”の視野で“文学の科学”を追求してきた。その焦点を、文学の科学の特殊性に絞っていくとどうなるか。“芸術の科学”から“文学の科学”へ具体化していくキッカケが見えてくる、と思うがどうだろう。 ★I.M. さん―― 熊谷先生が一貫して展開されている言語芸術の特性としての「継時性」の問題ではないか。言語芸術は、ことばの継時性によって喚起されるイメージに支えられる。それは絵に描けるものではない。それでは具体的・具象的でないかといえば、そうでもない。言葉の継時性の中で、素材としての「ことばが消え」て、その肉声が響いてくる。そういうイメージを実現する。 ★K.T. さん―― 私も同様。その上で「とらえ直し」という現象が生まれる芸術ではないかと思う。文学ならではのダイナミックイメージである。 ★A.Y. さん―― 言葉の継時性に即しつつ、自己凝視を深めていくところに、文学の特性が生まれる。遠近法の調節によって、自己の生きている条件と〈文学的現実〉の対比が成立する。場面規定の実現とは、感動において対話が実現したことでもあろう。自分がどう生きているかという問いかけ自体、文体刺激と文体反応とのかかわりの中で、あきらかにされる。それが、“文学の科学”の基本にあると思う。 ★熊谷さん―― 「継時性」という点でいえば、音楽芸術に近いと言えるだろう。違うのは、文学芸術がたいへん、思索する、思考する、ということに密着している点、――それにサッカクを起こし、“解釈”が生じるのだが――その点に大きな特性があるといえよう。 言語という第二信号系をくぐってイメージされる芸術……パブロフではつかみえなかったものが、ランガーにおいて明らかになった部分、これを論理として整理するのは文教研であろう。 研究を深めてほしい。 「平和と民主主義のための研究団体連絡会議」 文教研 15番目に加盟。 第一回会議 3月4日 S出席。 ▼1988/03/27 №370 3月例会 報告 S氏ノートより 鑑賞体験の変革――鴎外『寒山拾得』に即して ○ 〈N.T.報告〉の骨子/★ 〈話し合い〉の中から ○ 鑑賞体験――その変革の契機 「拾得が賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)の像の前」で「向き合っていっしょに食べている」――これ「おもしろい」と私はこの間の全国集会で発言した。これは「拾得が普賢であることがわからぬ俗物大衆」、それに向けての私の視点、つまり上から下をみる、そうした視点からの「おもしろ」さではなかったのか。 ここでの“おもしろさ”ははたしてそういうものなのか、ここが変革のための出発点であった。 ○ 「主人公概念では、つかめない作品」 私は最初、主人公は「寒山」と「拾得」――と思っていたが、それではこの作品はつかめないと思うようになった。だからと言って、それが「閭」というわけではない。 ★ 自然主義文学の中での、従来のいわゆる「主人公」概念によっては、この作品はつかめない。(I ) ★ 従来の「主人公」概念というのは、中世的ロマン(ノベルではなくて)から生まれてきたヒーロー、ヒロインと言っているもののことでしょう。それを採り入れた自然主義をのり越えるかたちで井伏や太宰の文学的追求があった。日本の近代小説の流れで言えば、そういうことです。『寒山拾得』の「閭」にしても、「寒山」や「拾得」にしても、そういう意味でのヒーローというものではない。(熊谷) ○ 「閭のメンタリティーを通して、閭が聞き、見た寒山拾得の人物像」 閭のメンタリティーがていねいに描かれている作品だ。 ★ 寒山、拾得を今まで傍観者的な立場でみていた。読者の一人としての自分の位置が定まっていなかった。これでは、この作品のおもしろさはわからないだろう。(A) ★ 閭は、寒山、拾得を(とらえられなかった、のではなく)つかみそこなった、とういうことだろうか。そのことを読者の視座からみたとき、寒山、拾得の魅力がわかってくる。(熊谷) ○ 「世の中の人の、道とか宗教とかいうものに対する態度に三通りある。」(そのうちの三番め)――「中間人物」「自分のわからぬもの、会得することのできぬものを尊敬することになる。そこに盲目の尊敬が生ずる。」……笑いとばされている閭、それが自分の姿と重なってくる。閭をとらえ直すことで作品がみえてきた。 ★ 1.無頓着な人、2.道を求める人、これらを含めての「三通り」の態度をみると、これが類型論になっていない。だから、それぞれに変わりうる可能性がある。(?) ★ だが、閭はあまり変わる人物とは思えない。それに対して、同じ鴎外の作品でも『高瀬舟』の庄兵衛は変わりうる人物として描かれている。(庄兵衛のメンタリティー――中流意識の幻想性) それに対して、『寒山拾得』の時の鴎外、なんかふっきれていないみたい。(熊谷) 紹介:『文学教育基本論文集』1~4巻(明治図書刊) 1、2、4巻に熊谷先生の論文、2巻に荒川氏の論文が収録されている。 ▼1988/04/09 №371 春合宿研究会 報告 N.H. Ⅰ.「マスコミ時代の芸術家」(『芸術とことば』)の印象の追跡 Ⅱ.西鶴「人には棒振虫同然に思はれ」 二泊三日(3/26-28)の春合宿は、鑑賞体験の変革という角度から、西鶴作品に大きく焦点を絞り込んだ会であった。長時間で内容豊かな会であった。紙面の都合もあり、私がつかめた範囲で主に、熊谷孝先生の発言を中心に、これだけは確認しておきたいと思うものを列記した。 ① 作家はだれのために書くのか。 ――(「芸術家のタクティーク」をめぐって) ※タクティーク=戦略、戦術 本文を確認しつつ話題は西鶴へ進んだ。――「浮世草子」に先行する「仮名草子」の世界。確かに、その中にはすぐれた民衆文学への可能性があった。むろん、「仮名草子」は、それ自体として、読者の要求に応えて変化し推移していく。が、西鶴は、その変化、推移の中に、民衆的視点における鑑賞体験の芽を先取りしていくのである。 ② 現在の私たちから、視聴覚的鑑賞体験をはずして考えることはできない。 ――(「視聴覚的フォーマットと小説の方法」をめぐって) 西鶴の時代に映画やテレビはない。しかし、私たちの持つ鑑賞体験をご破産にして西鶴を読むことはできない。では、今日、西鶴文体を読む意味はどこにあるのか。また、どのように読むことが必要なのか。(報告者グループから『鼠の文づかひ』などを含めつつ、「棒振虫――」の印象の追跡を行なったあと、話し合い。) ③ 「 」という表記の問題。 西鶴の表記には「 」はない。どこからが心の中のつぶやきで、どこからが口にした言葉かの明確な区別はない。音声言語としてよりも、〈心のつぶやき〉を含み込んだものとして、登場人物の言葉がはっきりと記されている文章である。「浮世草子」は「浮世草子」として読まないとおもしろくない。現代表記では書きようがないのだ。(こうした〈心のつぶやき〉として書いていく方法は島尾敏雄などにもつながっていく。秋成とはちがう。) ④ 「浮世草子」は必然性を追っていく文体である。 利左が二十五文を投げ出す必然性、利左と三人のやりとり、さらに、たたみかけるように、利左のどん底生活が描かれる。利左が案内する餌差町の東のはずれを通る時、残された人生をすがすがしく生きようとしている老婆の姿も見えてくる。熊谷先生は、そうした西鶴文体を媒介されながら「一頁で人生をつくしているような文体だ」と話された。 ⑤ “逃亡”の問題。 このような熊谷先生の媒介を通して、さらにそこから逃亡していかざるをえない利左夫婦の姿があらためて浮き彫りにされてきた。 ⑥ 「浮世草子」は講や寄合の中で話されるような調子で描かれている。 「浮世草子」には、旅先などで、おもしろい話を見聞きした町人の話の調子がある。西鶴は、むしろ、自分と異質なメンタリティーの人物に語らせる。それが特徴のひとつと言える。 だから、「棒振虫――」の最後など「大晦日定めなき世の定めかな」という西鶴の俳諧の発想と較べてみたとき、その語り手は、作者・西鶴とはおよそ違う、もっともらしい処世訓の持ち主であることが見えてこよう。(続けて「南部の人が見たも真言(まこと)」(『万の文反古』)について話し合いをした。) ⑦ 食いつなぎの生活をしている手紙の書き手……〈常の町人〉二代目の生活。 「五十両迄ならば」と、何とか今の生活を持ちこたえようとしているのが、又兵衛である。そうした中から、「又当年も弐千両までは請合」う大資本家である「算用の大尽」との対比も見えてくる。 ⑧ 〈常の町人〉二代目なればこそとりえた行動……こよし の行動。 食いつなぎの生活の彼らにとって、「銀が銀を儲ける」世の中である限り、彼らには未来はない。そんな中でこそ形成しえた こよし の姿であった。 ⑨ 西鶴の付けた題名には、彼の主題的発想が出ている。……経験主義への抵抗の世代。 この眼で見たものは「真言(まこと)」である、という経験主義の哲学にすがって生きてきたのが、初代新興町人の姿である。しかし、二代目がそうした経験主義に左右される時、家との一体化しか望めない。西鶴世代としての二代目はそんな経験主義に抵抗していった世代である。「南部の人の――」、そこに悪意の人はいない。しかし、人間としての真実という視点から追跡する時、何が見えてくるのであろうか。 この経験主義の問題と、こんにちの情報主義の問題は重なり合ってこないか、という熊谷先生の問いが胸に響いた。 ▼1988/04/23 №372 4月第一例会 報告 M.T. 西鶴「鼠の文づかひ」 新学年がスタートしたばかりの、新しい学級の生徒たちとの出会い。その新鮮な雰囲気がそのまま持ち込まれた例会だった。 N.H.さんの話題提供――以前の私の読みでは、冒頭のケチな男に、まず興味をひかれたものである。だが、春合宿を経て、「鼠の文づかひ」の印象も大分変わってきた。「塵もほこりもすてぬ随分こまかなる」かたちで生活している人々。「銀が銀を儲くる」世に何とか、今の生活を持ちこたえようと、四苦八苦している中下層町人の姿(「南部の人が見たも真言」)と重なって、厚みを感じるようになってきた。 「十八の時……嫁入り」して、五十三年になる老婆も、『五人女』のお夏の「十六まで男の色好みていまに定まる縁もなく」の表現と比べても、いろんなイメージが浮かんでくる。 〈話し合い〉の中から 熊谷 合宿で得たものが多い。その合宿を受けての今日の例会ではあるけれども、西鶴の作品、何から何まで同じなんてことはない。この「鼠の文づかひ」独特の面白さ、初代の経験主義云々にはないよね、と、さっきの休憩中S.M.さん、K.T.さんと三人で話した。 S.M. この作品のおもしろさは、息子に〈常の町人〉二代目のメンタリティーが感じられない、というところにある。息子が母親と同じやり方で、その母親に立ち向かっている。当然かないっこない。水風呂(すいふろ)にはいっている薬師(くすし)と老婆のやりとりもおもしろい。薬師にはインテリの姿がある。 K.T. この作品の個性は日常的なものの描写にある。「是ほど遠ありきいたす鼠を……」とわめく老婆に対して、年代記でたちむかう薬師にインテリの弱さを感じる。 I .M. 「大願成就のしるし」を見たら信じてしまう老婆、この老婆にも抜けたところがある。息子も同じ土俵で勝負している。 Y.R.息子の「しわさ」、スケールが小さい。 N.T. 同じ土俵で勝負しようとするから、息子は負けてしまう。 S.T. 以前は「この母にしてこの子」と見ていたが、老婆は懸命に生きている。 熊谷 「十八の時から一代一足で……」「銭一文落とさずくらせしに」「盗まれて」「泪をはらはらと」こぼす。身についている、その身につき方のスゴサ。巧まずしてたくんでいる老婆。息子から金をまきあげようとして、しらっぱくれたり、わめいたりしている。その点、医師や息子は観念的(二代目的観念性)。 A.Y. どこまでが老婆の本音か。涙を流すことも計算のうちか。 熊谷 古典を引用する医師の経験主義を老婆は見破っている。勝って意気揚々とひきあげていくが、そうした勝利が、人間として生きることに、はたしてどういう意味があるのか。結果において、老婆も充分に観念的ではないか。 K.K. 「ひとり寝」をする老婆の孤独感が本来の読者の視座にみえてくるのではないか。 熊谷 隠居所に帰ってから、のうのうと寝ているんじゃないの。 S.N. やったやったという老婆の気持。読者の視座において、登場人物はひとりも肯定されていない。 T.M. デフォルメされてはいるが、全面否定されてはいない。ディテールにわたって書かれている。新興町人二代目のパーソナリティー、初代への批判の眼、医師、二代目の観念主義のよい面も……。 熊谷 (S.N.発言に対して)登場する人物全部が否定されるべき人物として、描かれているだろうか。三井の両替店の開業(1683年)をメルクマールとして、新興町人の階級分化は大きな変貌を示す。 ▼1988/05/14 №374 4月第二例会 報告 K.K. 西鶴「人には棒振虫同然におもはれ」(続き) ○ 「人には棒振虫同然におもはれ」についての詳細な印象の追跡が担当者からなされたあと、会場から次のような注文が出された。すなわち、今までの印象の追跡とは目的意識が違うはずだ、今回のは鑑賞体験の相互変革という観点からの印象の追跡でなければならない、ということだ。どういう観点に立ったとき、鑑賞のありようがどう変わったか。私の場合、例えば、その語り手がどういう性質の人間か、そのことを知った時、私の鑑賞のありようは変わったが、そういう意識づけを、まずチューターが示すべきではないのか。変革ということを意識的に、次の「菊花の約」とのつながりで、文学系譜論の観点で、チューターがレールを敷き、報告の位置づけをすべきではないか。―― 休憩後、二度にわたってチューター提案がされた。 チューター提案:A.Y. 西鶴文学の魅力をいくつかの作品とのつながりの中で、特に「人は棒振虫――」を中心に据えて明らかにしていく。そのときに以下のことに眼を向ける。 ① 西鶴文学を今次集会[夏の全国集会]の最初のゼミナールに取り上げたのは、浮世草子が日本における最初の小説の成立にかかわっていることと関係する。『源氏物語』に、ある批評家などは小説の成立を見ているが、私たちは西鶴の浮世草子こそが、小説の成立を示す指標と考えている。例えば、「恨之介」などという作品に見るように、仮名草子では神仏の御加護で男女の恋が成就したりする。また、実用書や教訓書が仮名草子の重要部分をしめたりする。しかし、西鶴の『一代男』に当時の読者が、浮き世を観じて、浮世草子と呼ぶようになったことから明らかなように、西鶴文学は言葉形象を通して、自己の人間回復を志向する探究がはじまっているのである。 ② 西鶴、芭蕉、近松の誕生が鎖国以後にあること、日本の政治史上における鎖国という意味が、単に政治的、経済的な意味にとどまるものでなく、日本民族の運命、文化形成に深くかかわっていた。旧特権門閥町人が自己の今までの権益を保持する形で、経済活動を押し進め掌握していくわけであるが、鎖国現象の中で、海外に、自己の人間としての可能性を探究できなくなった人たちが、自己を新興町人として形成することを通して、問題を解決していく。つまり、新興町人初代は本来なら人間の可能性や自由を追求する手段として、金儲けを志向したのである。しかし、現実の進展の中で、金儲け自体が目的化されていく。そういう悲喜劇を、西鶴は突き離す形で描いている。初代の経験主義的な生き方を、二代目がどのように批判的に継承していったのか、銀(かね)が銀をもうける現実の中で、人間いかに生きるべきか。西鶴文学は、常の町人二代目の文学として創造されていく。 ③ 西鶴文学は近世を生きるさまざまな人間模様を描きつづけた。「鼠の文づかひ」の老婆にも憎めない何かを感じる。十八歳で遅い結婚をした時、異なった人生コースがありえたかもしれない。「南部の人が見たもまこと」の こよし は家のため、親のために、気にそまない結婚をするが、それが人間として、どんな悲劇をもたらしたかを知った時、死ぬことを通して最後の“人間”を守る。このように、西鶴は近世を生きるさまざまな人間の行為の軌跡を描いた。人間喜劇としての文学の誕生である。 ○ 以上のチューター提案に対して、いくつかの注文、補足がなされた。 ・仮名草子から浮世草子への発展と言うとき、仮名草子の説話的なものを、浮世草子がどう克服していったか、という視点で整理してほしい。 ・衰弱した説話文学を克服することで、近世小説の創造が可能になった。それが「菊花の約」へともつながる。 ・説話文学における語り手の問題と西鶴文学の語り手の位置の相違。 ・西鶴世代の問題意識と必ずしも重ならない形で語り手が登場することの意味。 ・寄席における人情話には近代小説の読者とは違う聞き手がいる。人情話と近代小説の間に、近世小説を置いてみると、その性格がよく見えてこよう。 ・浮世草子、例えば「人には棒振虫――」という作品を声に出してみると、読み手の心をとらえる、わかりやすい文体であることに気づく。 ▼1988/05/28 №375 5月第一総会 報告 T.K. 西鶴「菊花の約」 ○ 「文学と教育」№144掲載予定の熊谷論文「文学の科学と鑑賞体験と」の抜き刷り(Nさんのワープロ版)を読み合う。「文学・芸術の創造が鑑賞体験の変革によって動的・過程的なものになる」というところが強調点だ、との指摘が熊谷先生によりなされた。 Ⅰ.チューター提案(S.T.) (1) 上記熊谷論文に「鑑賞は文学の方法だ、文学の方法は鑑賞だ」という指摘がある。鑑賞抜きの文学、文学の科学はありえないのだ、ということを衝撃をもって確認させられた。 (2) その点から自分の鑑賞のあり方を顧みる。たとえば、月夜の利左を通して西鶴の“トカトントン”が聞こえていたのかどうか。それが聞こえてくるような鑑賞でなければ、西鶴を文学として捉えたことにはならないし、又、系譜論的に捉えたことにはならないだろう。 (3) 秋成の「菊花の約」にしても、白話小説の翻案だ、怪異小説だと、外側の知識でわかったつもりになている間は、“トカトントン”は聞こえてこなかった。中国の白話小説に材を求めたものであるにせよ、そこには秋成の鑑賞体験の変革をもたらすような鑑賞がまず息づいていた。鑑賞を通して秋成は材料を資料に高め、フィクションによってそれを自分の文学として創造していく。その過程を見落としたくない。そこにはまた、秋成の“トカトントン”が聞きとれるのだ。 (4) 十八世紀、封建制の解体へ向けての動揺期、“丸腰の武士”化していく上層町人と、他方で本来ありうべき人間らしさとしての町人性、農民性を喪失していく中下層町人、農民。秋成はそうした、人間が人間でなくなっていく現実の状況を教養的新興町人中層者の眼で冷徹に捉えている。そして怒っているのだ。この点がはっきりしてくると衰弱した浮世草子(例えば、言葉遊びに堕し、言葉で思索する姿勢を欠如した西沢一風の『新色五巻書』(しんしきごかんしょ)など、やがていわゆる八文字屋本の主軸となっていく作品群)から読本へという必然性も見えてくる。 (5) 言葉(第二信号系)と第一信号系との隙間が開く一方の生き方に秋成は我慢できなかった。「やっぱり言葉でいこうよ」というときに、西鶴が切り開いた咄(はなし)の世界とは違う形で秋成の文体が生まれてくる。たんに“言(げん)”につくのではなく書き言葉(“文(ぶん)”)からもう一度出なおそう、そして言葉で思索しようという線が明確にでてくる。雅文調、漢文調もその現われと見られる。そこに西鶴を継承しながら秋成的展開を見せる近世小説の大きな特徴があるのではないか。 (6) 最後にもう一つ問題提起を。西鶴の場合、講、寄合をベースに咄を楽しむ、旅人が見てきたものを語るという形で展開されるが、、それに対して秋成はどっしり腰を据えてみているような気がするのだが、どんなものだろうか。 Ⅱ.話し合いの中から チューター提案をめぐっての話し合いの中で、熊谷先生から私たちに、考え方の根底において問い直しを迫るような厳しい助言があった。 ① 西鶴、秋成をそれぞれ固定化して、両者の違いを言うような対比は意味がない。秋成が一本調子で腰が据わっているわけではないし、西鶴もその意味で“一人”ではない。『諸国咄』の西鶴と『胸算用』の彼とか『置土産』『万の文反古』の彼とか、そこには大きな変化があるだろう。問題は、どう変化した西鶴を秋成が受け継いでいくのかということだし、変化の方向は十八世紀的町人・百姓のありようの変化と関わるわけだ。極と極をとって対比するという考え方には疑問を感じる。 ② 戦後派の作家たちが、精神分析の公式で作品の世界を構築し、それを精神分析の方法でもって解明していこうとしたように(『芸術とことば』p.146以下参照)、公式で公式をなぞり返すような誤りを犯したくない。文教研の一員として、仲間だから言うのだが、不満なのは、我々の中にそういう傾向が内在していることだ。自明の公式のような西鶴論を作り出し、それを、用意した公式で解く。見事に解けはするが、それで文学がわかるか。わかるはずがない。時間をつぶし集まって、A+B=CをXとYとZに置きかえて、それで解いていく行き方。むだだ。そうならないことを――。 ③ どうして西鶴が“一人”なのか。秋成がどうして“一人”なのか。そんなはずはないだろう。「忍び扇の長歌」から「人には棒振虫同然におもはれ」、その間に鑑賞体験の変革があったはずだ。作家は自分の鑑賞を書いていくわけだ。変革された鑑賞を。西鶴は突然変異で「棒振虫――」のような大作を書いたわけではない。西鶴自身が、そして西鶴の世代が鑑賞体験を自己変革し、自他変革して、こうなってきているという押さえが必要だ。秋成の「菊花の約」の場合も、『雨月物語』全体を見わたして、ある意味での達成点――鑑賞体験の変革を重ねてきたという達成点――の作品を取り上げているのであって、したがって“二人”の比較という単純な操作にはなるまい。もっとフレキシビリティーに立つ発想で前提条件をおさえ、ダイナミックに考えていきたい。 ワープロ――わたしにもできます 文教研会員の中で、既に何人かの方はお持ちのようですが、ニュース(今号)の冒頭にもあるように、、この度Nさんがワープロを購入しました。おかげで今までとは違ったきれいな印刷物を見られるようになりました。 それもさることながら、「わたしだってできるかもしれない」とまわりの多くの方々に自身と確信を与えたことが、最大の貢献であった、と言っていた人がいました。 ▼1988/06/11 №376 5月第二例会報告 M.M. 熊谷孝論文「文学の科学と鑑賞体験と」の検討 Ⅰ.話題提供(T.M.) ① 昨年の11月に確かにこういう問題提起があった。「最近の自分たちの作品評価の仕方には、停滞というか、一種のステレオタイプ化が見られはしないか」「〈文学の科学〉へのより一層の関心の深まりを」。作品評価がカタにはまっているのを感じる。カンというものを忘れかけていた。“カン”についての話(p.7-8)は解りやすい。あらためて見直しを迫られた。 ② 「〈鑑賞〉〈鑑賞活動〉ということを……〈文学の方法〉だと定位して考えてみる必要がありはしないか」――全国集会のサブタイトルも「文学教育方法論の直接的な最重要課題」となっている。ここから考えていかなければならない大きな問題提起である。動的な、あくまでヒポテーゼなのだ、という提示のされ方であるが、仮説をテーゼにしていく事が求められている。 ③ 「文学・芸術の創造が鑑賞体験の変革によって、動的過程的なものになる……そういう発想が意識の根っこにあって、私のいう〈文学系譜論〉が、そしてまた〈現代史としての文学史〉と私が呼んでいる文学史の方法原理が導かれてまいります」。 焦点はここだというご指摘があった。鑑賞体験の変革が先行しないかぎり、文学の創造の名に価するものにはなりえない。創造主体と鑑賞者との内的な関係・関連を示す〈内なる読者・内なる鑑賞者〉という把握がないと、系譜論は出てこない。そのおさえがぬけおちていた。〈現代史としての文学史〉自体成り立ちようがない。また系譜論というと陥りがちなのは、ちがう作家同士の受け継ぎにだけ目がいく事、同一作家であっても、その中に内在的系譜論がある。時期区分論もこういう視点がないと出てこない。 ④ 二、三歳の子どもでも、玩具の自動車などを見ている時には、鑑賞体験の想起・反応様式の想起がある。そこから鑑賞が始まる、新しい鑑賞体験が呼び起こされた時に、初めて作品がわかり得る条件が整う。作り手(作家)の場合も創作の過程は準体験の極致、と言いきっていいのではないか。 ⑤ 熊谷先生の読者論には、パブロフの第二信号系理論の批判的摂取がある。現在の読者論ブームの中の“読者”は、テキスト構造にくみ込まれている構成概念として静的に捉えられているようである。読者論の違いがはっきり位置付けられた。 ⑥ 「鑑賞――文学の鑑賞を〈文学の科学〉の方法だと考えていいのか」――哲学辞典には、「方法=我々の認識は一つの体系であると同時に、無限に前進する過程であり、従って真理に向って絶えず自己を検討し、確信していく方法を具えていなければならない。方法というのは、理論に対して、その外的な補助手段ではなくて、内容の必然的発展の道筋なのだ」とある。戸坂潤は「方法とは最も確実で目的にかなった道を教えるものだ」という。そこをおさえた時、〈文学の科学〉の方法は鑑賞なのだとピンとくるものがあった。 ⑦ 実践とは臨床的いとなみ。人生の脈搏に触れる事、人間の精神の自由、その鼓動に耳を傾ける事、それなくして文学は語れない。今回の提起に関して、自分の方の誤ちを出しきって新しい事にきっちり耳傾けられる自分にしていくことが必要だ。 Ⅱ.質疑の中で熊谷先生から ① テレビで、黄楊(つげ)の櫛を作っている木曾の職人さんの話をきいた。アナウンサーに「どういうコツがあるんですか」ときかれて、「コツ? コツなんかない、カンだよ」。その職人さんの父親が息子に遺した言葉「技術を云々することが問題ではない、どうやったらいい櫛ができるか“木に教われ”」。我々は、ことばを使って言葉の芸術を追究している。“文学作品に教われ”。――文学とは自分にとって何なのか。それを忘れて、文学の科学とは? 対象は? 方法は? と言ってみても何にもならない。 ② 自分の感動が先にあっての話だが、奮い起こされたその感動は、どのようにして自己の内部に形成されたものなのか、という“反省”が必要。その辺のことを衝くことで〈文学の科学〉の必要性が出てくる。 ③ 〈文学の科学〉の対象とは何か? 目的とは何か? 根本的には切り離せない面もあるが、一応分類して考えてみる必要がある。対象の面からみて〈系譜論〉〈現代史としての文学史〉〈文学的イデオロギー〉、文学の機能と構造の問題などがある。文学教育は、これらにまっとうに結びつかなければ駄目。いわゆる対象だけを問題にして、目的を忘れると、対象論としての有効性を失う。目的論の目的にのみとらわれては、現場主義に陥ってしまう。 ④ 西鶴文学を捉える時の「新興町人」の問題は“外側”でなく、“内側”の問題ではないか。(「新興町人」の概念については『芸術とことば』p.278参照) ⑤ 仮説らしい仮説は“方向感覚のしっかりした”という限定がつく。カンは方向感覚の問題である。それを研くには猛烈な自己訓練(学問的修練)が必要である。 ⑥ 第二信号系と第一信号系の間の関係・関連をどう捉えているか。第一信号系という条件反射を経て、人間のみが持ちうる高度の条件反射として第二信号系が成立したことは確かである。第二信号的条件刺激の媒体としての言語には、形象と概念という二つの基本的な機能がある。しかし、第二信号系が第一信号系につながるという大事な面がぬけると、言語主義に陥る。文学現象において、言葉が消えるということを、ランガーに学んだ。パブロフ理論でも、根本的には、言葉が消える、といっているはず。 ⑦ 文学とは何か? 何が文学であり、何が文学ではないのか? それを〈鑑賞〉という重要な方法をぬきにしてつかめるのか? その〈鑑賞〉はいかにあるべきか、を〈鑑賞体験〉として捉えていく。“体験”という言葉は、日常性・芸術性・科学性の、あの概念で使っている(体験の日常性、体験の芸術性……)。 切り口を変えた言い方をすれば、それはプロセス(過程)ということ。あらゆるものが過程として存在する(マルクス テーゼ)。静止した時は死んだ時。鑑賞が鑑賞でなくなり、文学は文学でなくなる。生き続けたいからこそ〈文学(芸術)の科学〉が必要になるのだ。 ⑧ 主観は大事。主観が狂っていたら、わかるはずはない。肉眼ですべてが見えるわけではない。望遠鏡、顕微鏡を必要とする時がある。しかし、それらがどんなに精巧なものでも、見えるのは、肉眼(主観)を持っているからだ。盲目の人に望遠鏡をついつけても意味がない。 ⑨ 二十代の時の仕事で、暗い谷間の文芸学・鑑賞主義を徹底的に批判した。鑑賞を鍛えていけば、文学という対象が見ぬける、すべては鑑賞だ、という支配的風潮に腹を立てた。あの時と今の論理は、根本精神として少しも変わっていない。どういうふうに〈鑑賞体験〉はあるべきか、私の〈文学の科学〉の対象の問題でもある。 個人の鑑賞がすぐれていても、それを絶対化してしまったら、主観主義、事実主義になる。こういう鑑賞の心理[ママ]でいくのなら、科学は要らない。それに戦きを感じるからこそ、〈文学の科学〉ということを真剣に言うのだ。変革を忘れ、停滞に陥ったら、それは死ぬ。生き続けたいからこそ、〈文学(芸術)の科学〉が必要になるのだ。 ○ 多くの重要なご指摘、発言の交わされた例会であった。未消化のため割愛した部分が多くあることをご了承いただきたい。 ▼1988/06/25 №377 6月第一例会 報告 H.M. 鴎外『寒山拾得』 N.T.さんは、3月例会(そのまとめは、ニュース№370)以後の、自己の印象の追跡過程を中心に報告された。詳しくはレジュメを参照していただくとして、私なりにまとめると次の如くである。 ① 長谷川泉氏に代表されるような研究のありかた、すなわち、原典から作品を解釈するような論はおかしい。鴎外が創造した文体に即して鑑賞することこそ大切だ。鴎外は「寒山子詩集」や「序」を自由に鑑賞し、その自由な精神を作品に結晶させている。この作品に描写文体の極致を感じる。「一冊の参考書を見ずに書いた」という「縁起」の言葉には、原典などをみないで、自分の文章をじっくり鑑賞してほしいという作者の願いが感じられる。 ② 3月例会では、閭の人物像に関して微妙なズレがあった。閭の中に権威主義に陥っていない面を指摘する人と、笑い飛ばすしかない人物とみる人と――。私としては、高位高官ではあるが、門閥によらず、自分の力で地位をかちとった人物、しかし現状に満ち足りていて、倦怠の思いや危機感のない人物として、閭をイメージしている。そして、そういう閭のメンタリティーにおいてつかまれた寒山・拾得であることをおさえ、閭がつかみそこねている寒山・拾得をつかむ事が大切だと思う。 ③ その場合、「縁起」が自作案内になっている、という熊谷先生の指摘を大切にしたい。文殊とか普賢とかの言葉(概念)にとらわれていると、寒山・拾得がつかめない。上にたてまつる存在というのでなく、自由な精神に生きている人を、ある人が見たとき、文殊や普賢に見える、ということだろう。 N.T.報告を受けて、「閭には決してつかめない寒山・拾得。しかし読者にはある見え方で見えてくる」(Ki)、「作中人物には見えず、読者の視座には見えてくるように書かれている作品だ。しかし、どういう読者に見えてくるのか?」 (熊谷)、「読者の視座が変わっていくのでは?」(Sn)、「いや、むしろ深まるのだろう」(St)、といった発言が続いた。そして、閭は「くだらん奴、いない方がいい奴、では決してない。」(熊谷)、「自分と同じだ、と思いながら読む」(St)、そんな人物であること、「(そういう)閭に即して読んでいくうちに、自己の読みが変えられていく、そのプロセスが大事」(St)であること、また、「こういう閭の描き方は芥川の『芋粥』に通じる」(熊谷)こと、などが指摘された。こうした過程の中で、この作品を(レジュメに書いた)“歴史そのまま”の作品だという必要を感じなくなった、との発言が報告者からあった。 〈例会後半のまとめは次号に〉 ▼1988/06/25 №378 6月第一例会 報告(続き) H.M. 例会後半を始めるにあたり、司会の熊谷先生が次のような板書をされた。 ・何をもって〈描写文体の極致〉というのか?その後の話し合いの中で、特に印象に残ったことを以下に記すと――。 ① 「パパアは文殊」というのは、鴎外ならではの発想だ。普賢はメシタキをしているが、文殊は残飯をもらいに来るだけで、労働はしない。手抜きをしている。鴎外はユーモアたっぷりに、自分も手抜きだ、と言っている。高度のユーモア、高度のジョークだ。(熊谷) ② 「極致」とは「非常に高度の」ということであって、「完全」ということではない。完全小説などはない。『寒山拾得』と『高瀬舟』とどちらが上か、というような比較はナンセンス。どちらも高度だ。また、庄兵衛と閭とでは、作品における位置がちがうのだから比較にならない。(熊谷) ③ 『寒山拾得』の第二章(三分類論のところ)などは、説明的だと言われがちだが、むしろこれが小説だと思う。この作品では、文殊や普賢を仏的でなく、人間的に描いている。また、言葉の限界を逆に生かしている高度な言葉操作であり、タモリ的笑いに浸っていては笑えない作品だ。(St) ④ 会話のリズムのおもしろさとともに、全体が喜劇精神に貫かれているのを感じる。閭の表情が目に見えるようだ。(Nm) ⑤ 「縁起」がすばらしい。「パパアは文殊だ」と言う発想が根底にあって、残飯もらいのことが書かれたのだろう。(熊谷) ⑦ 人間への興味や、子どもの可能性に賭ける姿勢が「縁起」にはある。その「縁起」の発想が作品の中に一本通っている。「縁起」を読むと作品がおもしろくなる。そして、自分の印象の変化が楽しめる作品だ。「官僚主義批判」という解説では、そうしたおもしろさがこわれてしまう。(Yg) 何人かの方も語っておられたが、私自身も寒山と拾得の違いに、全く目が向いていなかった。それでいて、「寒山子詩集序」と作品とを対比して、あれこれコウサツしてみたり、一方、森林太郎の退官とこの作品における“官僚批判”との関連を憶測したりして、それを“研究”だと思っていた面がある。作品の表現部分 にまっとうに反応できることと作品に一貫する発想や文章のリズムがつかめることと、決して別のことではないことを痛感した。「鑑賞こそ文学の科学の重要な 方法的側面ではないか」と熊谷先生が強調される理由もこういうところにあるのだろう、と改めて思ったのであった。 ▼1988/07/09 №379 6月第二例会 報告 S.T. 芥川『黄粱夢』――古典の受け継ぎ(中国古典・謡曲) Y.A.さんの報告を聞くことで、今回の全国集会の課題の一端を私なりに掴むことができた。とりわけ熊谷先生のご指摘は、『黄粱夢』が極めて短い作品であることをいいことにして安易に考えていた私に、痛烈に響いてきた。以下、Yさんの提案と熊谷先生のご指摘を、自分なりにまとめることでレポートとしたい。 Y.A.さんの報告から ① Y さんが強調されたことは、〈文学の科学〉を太く貫いていくる〈現代史としての文学史〉の視点的立場に立つことの必要であったように思う。『日本人の自画像』での熊谷先生のご指摘の整理を踏まえながら、「文学との対話・対決を通して、さまざまの作品相互の関連の中に人間の精神の系譜を探る」ことに、『黄粱夢』を読む意味があることを提案された。また、さまざまの作品との対話・対決という営みの中に、「不断に、人間の可能な生き方を問い続ける」ことが、〈現代史としての文学史〉の原点であることが提案されたように思う。 ② 次いで、この営みの中に、現代を生きる自己の課題意識を捉え直していく過程と、〈文学の受け継ぎ〉〈古典の受け継ぎ〉ということが密接に関連していることが指摘された。「狭い自己の課題意識」を、「文学との対話・対決によって見極める営み」の中で、言い換えれば「鑑賞の絶えざる変革・自己変革」の中で、自己の課題意識は「世代に普遍的な課題意識として捉え直されて」いく。その場合、〈場面規定〉、いわば〈鑑賞の場面規定〉を踏まえることが、私たちの鑑賞を「鑑賞主義」に滑らせることなく、「文学を自分のものとし、自分の支え」としていく〈鑑賞の自覚化の過程〉にとって、欠かせぬものとして位置づいていく。だからこそ、文学の鑑賞過程が、「人生の脈拍に触れるという意味で、実践的で臨床的なもの」として位置づいていく。 ③ このように考えていくとき、熊谷先生が「『芸術の論理』で『黄粱夢』を初めとして芥川の初期の作品を取り上げられながら展開されている具体的な方法」を、再度押さえ直していく必要がある。「青年芥川の倦怠と苦悩。そこで人間とは何か、人間はどう生きるべきかを問い続けた流れの中に『黄粱夢』が位置づいていく」ことをYさんは強調された。また『黄粱夢』について、このパートのテーマである「〈古典の受け継ぎ〉という切り口から迫っていく場合、芥川の必要・内的必然性において、中国の古典・謡曲などをどう受け止め、非常に個性的なものへとどう再創造していったかを明らかにする」必要を強調された。 熊谷先生の話から 盧生の見た夢は、青年一般・若者一般の夢ではない。古代末期の斜陽貴族が来世に思いを託した浄瑠璃寺の美しさとも、また、中世が終わろうとしている時点での義政の、何もかもが厭になった人間が見た夢の中の極楽浄土の表現=銀閣寺の美しさとも違っている。 他方、芥川が描いた〈夢〉は、『枕中記』の道教的世界での〈夢〉とも『邯鄲』の仏教的世界での〈夢〉とも違う。それは大正デモクラシーを実現しようとする人々の、あるいは、大正デモクラシーの先頭に立った人間の、可能性に賭けた夢であり、古代にも中世にもない〈夢〉だ。 原田浜人の句 火 取 虫 浩 瀚 に し て 興 薄 し 朝日新聞「折々のうた」(6月23日付)に取り上げられた句。原田浜人は熊谷孝先生の中学生時代の恩師。自ら英訳したドーデの『最後の授業』を教材化して教えたりもした。母国語=母国語文化への愛情に溢れた英語の教師であったという。 ▼1988/07/26 №380 7月例会 報告 Y.R. 「実朝再発見」――『金槐集』における異本の発見 T.M.報告 ここで『金槐和歌集』を取り上げる理由は、『右大臣実朝』における太宰の虚構のあり方、太宰が1940年代に再発見した『金槐集』とは、ということを見極めるためにも、『金槐集』をきちっと位置付ける必要がある、ということであろうか。 1929年(昭和4年)佐佐木信綱博士の定家本発見。1932年(昭和7年)、岩波文庫の増補改訂版、斎藤茂吉校訂本の巻末に、定家本による校訂がつけられた。定家本発見の喜びを我が喜びとしている茂吉の姿が、そこにはあった。その発見によって、『金槐集』をまとめた段階での実朝の年齢は22歳だった、ということ、従って、万葉調の歌も晩年ではなく、22歳までの作であった、ということなどがわかった。 そして、決定的なことは、それまで判断のつかなかった字句がはっきりしてきた、ということである。それによって、それまでの実朝像が、がらりと変わったのだ。その端的な例が、熊谷先生の指摘されている「よそに見ておらではすぎじをみなへし……」(定家本195)の歌である。「餘所に見てをらでや過し女郎花……」(貞享本217)と比べるとき、ひたむきな思い、妥協を知らない魂、情熱、といったものが、強く実朝像として浮き出てくる。古典――『金槐集』の優れた読者である太宰は、そのうような実朝の歌を虚構の眼でとらえ、散文的現実のなかに生かしきった、と言える。 そうした太宰の鑑賞体験をくぐって、『金槐集』を読む楽しさも私たちにはある。そしてなにより、ひとりよがりの鑑賞にならないために、また、人間的真実を発見するためにも、自己の鑑賞をとらえ直し、変革していく、そういう意味において、『金槐集』のことを話題にしていきたい。 話し合いの中から ○ 報告の中でも触れたが、アピアランスとしての文学現象、だから、あくまでも作品形象は未完了なもの。創造の完結者は読者なのだ。そこから、系譜論も、文学教育の必要性も生まれる。私たち読者は、自己の分担課題を見極めるために、違う世代の文学的イデオロギーを発展的に受け継ぐのである。そして、次の世代に媒介していく、そのときどう媒介するのかが問題になる。たえず自己の鑑賞のありようをみつめ、変革していくために、系譜論がどうしても必要になってくる。文学史の方法と文学教育の方法との接点、そこをもっと出していかないと。(Td) ○ 『金槐集』をめぐって真淵―子規―茂吉 の鑑賞体験の系譜がある。そして佐佐木信綱の定家本発見による茂吉の鑑賞体験の変革を、正面から受けてたった太宰。その太宰の鑑賞体験の変革が『右大臣実朝』に結実していったのだ。その過程を、私たちに、また次の世代に媒介することによって、実朝像が違ってみえてこないだろうか。定家本発見という書誌学的な成果をふまえることで、鑑賞が深まる。また、マチ針論の意味なども見えてくる。今度の集会の第Ⅲ部は、その構造が明らかにされるパートなのではないか。(St) ○ 文学史の方法としての文学系譜論、それがそのまま文学教育の方法論と重なってくる。それが熊谷理論の、資料主義・解釈主義などとは一線を画すところなのだ。文教研理論の一つの集約として、今次全国集会のプログラムは構成されている。(Ys) ○ 系譜論ということに関して今回は、同一の創造主体内部における自己変革のありよう、鑑賞体験の変革による創造過程、それを明らかにしていくという課題がある。また、『金槐集』の異本の発見、の位置づけが、資料主義的な関心からではなくて、あくまでも虚構精神・虚構的必然の問題として、私たちの考える文学系譜論の基軸からの要請だ、ということが、『太宰治――「右大臣実朝」試論』の中で強調されているように思う。(Ak) ▼1988/09/24 №382 9月総会 報告 S氏ノートより 9月第一例会は総会ですので、編集、組織の各部の報告、予算の検討などもありましたが、何と言っても研究企画がメインです。それを主として熊谷先生が話されたことを中心に、S氏ノートでまとめました。 〔年間研究テーマの三側面〕 1.鑑賞と創造の基礎理論 ――鑑賞と創造の基礎理論としての文芸認識論 ★ 「創造と鑑賞」ではない。 2.文学史の方法原理 ――文学史の方法原理としての文芸認識論 3.日本の教育と文学教育 ――日本の教育と文学教育へのたえまない関心 ★ これを統一するかたちで〈文学の科学〉がある。 ★ そして、それは実践と深く関わっている。 ※ この三つをあくまでも側面として捉えてほしい。この三側面をつねに視野の中に入れ、深めていかないと、その一をも深めていくことはできない。 〔第一期 月例研究会〕 ○ 『芸術とことば』序 について 何か完成したものがそこに在る、というものではない。 文教研創設当時、こういう仮説に立って考えていたのだ、ということである。 それ以後、〈文学史〉の面で言えば、「現代史としての文学史」「読者中心の文学史」「系譜論」など部分的に深められたものはある。 だから、それといっしょに深められなければならないものがあったはずなのに、そのバランスが今くずれている。たとえば、条件反射学、第二信号系のことなどコロッと忘れてしまっている。今、ほんとに反映論的立場に立っていると言えるだろうか。精神の文化のバランスをもってもらいたい。 ○ 西鶴から秋成へ――封建制下の民衆文学として 文学史の成立を可能とするような歴史認識を持たなければならない。近世文学を扱うから封建制を問題にするのではない。近代・現代文学であっても、封建革命の問題を避けて通ることはできない。 民衆による下からの革命は、信長、秀吉による検地、刀狩りを通して鎮圧され、その封建反動は徳川幕藩体制として結実する。 それに対する民衆の闘い、これが西鶴を先頭とする近世文学である。そうした文学の闘いは、近代文学へとつながっていく。近代文学は個を圧殺する〈封建反動〉(いわゆる“封建的”なもの)と闘うばかりでなく、と同時に封建主義のみを克服の対象とする近代主義との闘いを二重の任務とする。 ○ 『去来抄』はやらないのですか。 当初の原案には入っていたのです。熊谷先生のお体の調子が良くなれば取りあげようと思っています。「熊谷教室」というようなかたちで。 日本の芸術論はヨーロッパよりも低いレベル、という捉え方がある。これは文化植民地主義というのでしょうね。そうじゃない、たとえば『去来抄』などは抜群の芸術論である。 ・古代末期の歌論――これはやはり一種の追体験主義。 ・中世の世阿弥(能楽論)――やはり、ここにもない。 ・近世の本居宣長――ここにもない。近松もやはり……。 それが、いわば突然変異みたいに、かなりフィクショナルな形で、それ自体、文学作品と言っていいような「先師評」(『去来抄』)が現われた。これはみごとな文学論である。 その文学論の方法は、説明という形ではなく、描写という方法がとられている。これだけの文学論を、現代で今どれだけの人が持っているだろうか。 組んずほぐれつやってみたらどうですか。 ▼1988/10/08 №383 9月第二例会(9/24) まとめ Y.H. 文学観・言語観の変革のために――熊谷孝著『芸術とことば』序 から学ぶ 『芸術とことば』序の中から〈観念のひずみ〉の部分を検討した。私たちめいめいが無自覚にみすごしている自己のひずみ を自覚するためである。 報告はA.Y.さん。『芸術とことば』発刊時の、同書への評価を切り口に、同書のもつ新しさを現時点でつかみ直す形で話された。 最初に、『芸術とことば』発刊に当って、諸氏から寄せられた〈推薦のことば〉の紹介があった。 その中で、波田野完治氏は「独創性と正統性とが見事に結合された」著述だと述べ、「パブロフの第二信号系の理論を文学体験の問題としてとらえ、条件反射の“内面化”を企図したことは卓見」と評価していること、また、乾孝氏が「言語の働きがもつ実践的側面を、概念的な伝えの問題にとどめず芸術の伝えにまで照明をあてた」と評価していることなどは、私も含め、おそらく多くの会員の初めて知る資料であったろう。 これは、ある意味で、私たちが『芸術とことば』の核心部分を押さえていくうえで大事な助言になっていると思えた。 次にA.Y.さんは「1963年段階の、この書の〈序〉が提起している問題を受けとめるには、熊谷先生の、これまでの一貫した理論活動をとらえ直す作業を同時的にやらないとむずかしい」と強調した。 それは、「熊谷先生の研究姿勢の中には、かならずそれまでのご自分の研究を、ある切り口から総括して、新しい作業を展開するという方法が貫かれているから」である。――『文体づくりの国語教育』(1970年刊)の序、及び『芸術の論理』(1973年刊)のあとがきを見てほしい、云々。 『芸術とことば』(序)を、これから読みすすめていく上での構えを、そのように述べ〈観念のひずみ〉の項へ報告をすすめた。報告は主に、 ① 主観主義と客観主義の「教室における二つの偏向(p.42-44)を、例えば、教科研の宮崎典男氏は、読み手の主体の外に“正しい読み方”が客観的に厳然と存在するという発想に立って評し、荒木繁氏のするどい批判を受けている。さらに、 ② 伝え・伝え合いの芸術過程(p.44-45) ③ 言語過程・芸術過程(p.45-48) へと話題を展開したが、紙幅の都合で省略する。 討議の中から ○ 「ところで芸術を芸術たらしめる基本モメント、芸術特有の、ある特殊な機能とは何であるか。――文中(p.45)に〈すぐれた感情体験において事物の意味をさぐる行為にほかならない〉とあるが、これはどうか」という熊谷先生の問いがあり、核心的な討議に入った。 ○ 「芸術の表現は単なる事物の指示や再現ではない。」あくまで「感情ぐるみの事物の表現」「感情を培う仕事が芸術過程」だという展開がなされている、そこのところである。「感情ぐるみ」とか「感情をつちかう」ということばばかりに眼が向いていて、「事物の意味をさぐる」という点にはてんで関心が薄かった私などは、「事物の意味」とは「意味形象」のことであり、「象徴」のことである、という指摘で、やっとその部分が見えてきて、課題になってくる。 ○ 熊谷先生は、「芸術体験とは意味形象体験のこと」と押さえ、「象徴(意味形象)の機能が芸術の認識機能の核である」と規定する。ここまで詰めてきてみて、「第二信号系の理論をコミュニケーション理論に組み込むことで、文学・芸術に固有の認識性格」を明らかにしている。この芸術論の新しさが、改めて実感されてきた。 ○ 荒木繁氏は、この書の書評において、「シンボル論はまだ著者の理論体系に十分組み込まれていない」といっているが、「〈ことば〉の規定性に徹する方向での事物の概念的抽象化による意味把握とはディメンジョンの違った感情を軸とする《まるごとの意味体験》が、この象徴化という手段によって、初めて実現される」(p.52)というように、明確に展開されていると思う。(St) ○ 事物の再現にとどまっている芸術観、感情を絶対化した芸術観、この双方を越えたつかみ方が、この「感情体験において事物の意味をさぐる行為」という芸術観ではないのか。(I d) ○ 「事物の意味をさぐる行為」とは、「表現によって喚起されたその事物に対する自己の日ごろの反応様式」ということにつながる。したがって、自己完結的であることはできない。――この芸術観の論理は、当然、ディルタイの〈生の哲学〉に対する批判となり解釈学批判となるものだ。(Nm) ○ 〈序〉に圧縮されている原理論を、その論理の追跡を通して、なんとか主体化していこうとする例会であった。なお、プラグマティズムの歴史的限界を云々するだけでなく、仮説を実証していくその実験精神に学び続ける必要があること、高橋義孝氏の『文学非芸術論』にみるような荒っぽい見解を、芸術コミュニケーションの視点から批判し続ける必要があること、等々。私たち一人ひとりの課題がゆたかに提起された例会でもあった。 ▼1988/11/12 №386 10月第二例会(10/22) 報告 K.K. 熊谷孝著『芸術とことば』序についてのN.T.さんの報告を受けて、話し合いがなされた。報告は熊谷孝著『言語観・文学観と国語教育』76ページ、および『文体づくりの国語教育』100ページに示された図形を基にして、絶えずそれに返る形で行われた。 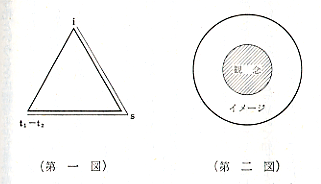 この図のt1,t2,s,i のそれぞれの概念をまず、各自がどれだけ掴んでいたかということで話し合いが始まった。 t1……thing、事物それ自体。例えば“うめぼし”それ自体。 t2……事物の第一信号で、“うめぼし”を見た人の内部に、ある像が結ばれ、ある反応を起こすこと。 t1は一つだが、t2は多様である。例えば、唾液反応。もちろん、そうでない反応を起こす人もあるわけだが、その反応の違いは第二信号系のありようの違いによる。 s ……speech。第一信号の、そのまた信号としての第二信号。例えば、“ウ・メ・ボ・シ”。 i ……image, idea, imagination、人間の神経のかこい を示す。 [ここで詳細は省略します。上記著書を参照してください。] ○ イメージは感覚の内化したものではなくて、運動の内化したものである。ということは、過程的な事物の反映ということである。常に変化の過程にあるということであろうか。 ○ 第一信号系と第二信号系のつなぎとして、イメージが大切なはたらきをする。イメージ体験は、第一信号系を確実にしつつ、これを第二信号系へむすびつける。 ○ t2は主体に反映された事物像、第一次現実 ということができる。これは自己の内部に一人ひとりがどのような仲間をあたためているかによって違う。仲間の体験をどうくぐって、言い換えれば、どのような世代的普遍性において、思索しているかによってt2は変わってくる。t2は、さらにはt3というように、ダイナミックに変わり得るものだ。人間は社会的・歴史的な存在であると言われてきた。その通りであるが、そのことを大前提として、熊谷理論では、さらに生物学などで使われてきた「世代」概念を新しく組み替えて、文学系譜論に導入したのである。 〔特筆大書〕 ○ 実はこの例会での私の一番の感動は、このことであった。「80年代、ほんとうの意味での階級論などなくなっているのではないか。階級的視点において、仲間体験を深めていくという世代論を持ち込むことで、階級論を確実なものにしたかったのだ。」という熊谷先生のお話で、文学というもの、文学的認識ということが、胸に落ちてきた。 世代論、系譜論を抜いては文学は掴めないということ、さらに、メンタリティーを育むということが、何よりも大切なのだ、ということなどがつながってきた。 ○ さらにもう一点。この三角形で示されたことは、言語活動、文学の問題だけでなく、音楽にも絵画にも通じるものである。音楽も絵画も人間の産み出すものであり、良かれ悪しかれ、人間は言語を持っている。従って、言語の方からも、 iや t1、 t2の方向への働きかけがあるというようなことも話された。シャガールの絵と彼の故郷の言葉[イディッシュ]のことなどを思いだした。 ○ この後、象徴と信号、そしてその関係をどうとらえてきたか、という方向へ議論は進んだ。が、十分詰められないで、課題として残ったと思う。ただ、「言語を記号としてとらえているか、信号としてとらえているかで、象徴ということが違ってくる。」ということは確認された。 ○ ここで、〈序〉でも触れられているピアジェの言語観について、S.N.さんがコメントを添えてくれた。レジュメを参照していただきたいが、結論的に言えば、ピアジェは言語を信号としてとらえていない、記号としてとらえている、ということであろうか。象徴概念にしても、「芸術の認識機能の核」としてではなく、非常に低次元のとらえ方だ、という感じである。 残された課題も多かったが、得るものの多い例会であった。 ▼1988/11/26 №387 11月第一例会(11/12) 報告 S氏ノートより この日の例会では「西鶴から秋成へ――封建体制下の民衆文学として」(その1)の報告、話し合いが行なわれました。次回もひき続き同じテーマの例会になっていますので、このテーマの例会の様子は、次回の例会を中心に報告いたします。(ニュース部) 第38回全国集会へ向けて 〔1〕思想史としての文学史――宗教思想、哲学思想、そして文学の対象としての思想 〔2〕教師 の登校拒否の心性 ○ まず、こんな話から始められました。――テレビの番組に国宝への旅」という続きものがある。この間のものは、たしか「斑鳩の微笑」だったか、そんな題名のものであった。哲学者の中村元氏がコメンテーターになって、聖徳太子像の体内像について語られた。「なにかきりっとしているじゃないですか。なにか語りかけてきませんか。日本にもすばらしい思想家がいたものです。」(文責:S) 「和をもって尊しとなす」(聖徳太子十七条憲法) | (これは、こっちのほうじゃないでしょうか) ↓ 和をふみにじるものへの怒り / 闘争! つまり、妥協しないで生きていく、その姿勢 / その姿勢こそ、異端の文学者たちの姿勢ではないか 〈文学者の求めるものは何か〉――こういう角度から、芥川を井伏を太宰を 考えてみようではないですか。 また、教師らしい教師だったら、現在の学校状況に対して、闘うはずでしょう。 | 受験体制、教師を含む管理主義体制…… 日教組教研に参加されたH.M.さんの話 札幌まで行って来ました。教室からとび出した平和教育、ということで、私の学校では、ここ数年間とりくんで来ました。修学旅行で広島に行っています。そのためには、事前に冊子(資料集)づくりをしながら学習をやり、そして、現地。帰ってきたら文章でまとめる。七十余りのリポートが出されます。 平和教育、民族の問題も含めての討論では、柱として次のようなものがありました。 ・被害という観念、加害という観念 ・平和教育と平和運動のかかわり ・Xデー後の対応、あり方について 余話ですが、国語分科会で、広島の方で、花森安治の『戦場」』を持ち込んでいた方がいましたが、誰だったのでしょうか。 ※ その方は、正会員として参加された文教研の地方会員H.S.さんです。(事務局) 最近、文教研に入会のY.H.さんからのたより 夏の全国集会に参加して、熊谷先生の講義に胸を突かれ、心を揺さぶられた。大学の授業では聞くことのできなかった、生きた民衆の文学史を学びたいと思った。蝉時雨の中で、朝から夜遅くまで、会員の方が用意してくださった梅干やレモンジュースをいただきながら、秋成・西鶴・太宰・芥川の作品についての講義と討論に耳を傾け、必死にノートを取り、体の中から力が湧いてくるような気がした。 「生活は弱く文学は強く」というお話が非常に心に残り、文教研は権力に阿ねらず、象牙の塔にもならない文学研究の場であると思った。文学を愛好してきた自分が、文学をどうしても必要とする自分に変わってきたので、この会に参加しようと考えた。西鶴の「人には棒振虫同然に思はれ」を初めて読み、西鶴には、こんな人の生き様を描いた面白い作品があったのかと思った。(討論をきき)一人で把握した狭い作品の世界が、みるみる広がり、正に、自分の内なるものが変革されていくことを感じた。毎日、高校生に古典を教えている自分が、古典を文学として、大勢で読み合うことができるということに驚いた。大学の授業で、四十代半ばの教授が「皆さんにはまだ文学がわからないでしょうね」と、ため息をついていたことを思い出す。ある意味において、当たっていることなのだろう。当時に比べると、作品の中に見え隠れする作者の哀しみや痛みが、しんしんと伝わってくるようになったと思う。だが、その先にある、作家が自己を乗り越えようとする姿がつかみきれない。自分自身がそこまで到達していない甘い人間であるからだと思う。 九月に入ってから、煩瑣な日常に紛れている自分を反省して、心して例会に臨もうと思う。毎回わからないことばかりです。よろしくお願いいたします。 ▼1988/12/10 №388 11月第二例会(11/26) 報告 M.M. 西鶴から秋成へ――封建体制下の民衆文学(2回め) ★ I .M.報告 “町人思想”というと、一般には『町人考見録』(三井高房著)の内容と合致するものを西鶴の文学から取りだしてきて問題にする傾向がある。しかし、序の部分だけをとってみても、「二代目に破る扇の風」「人には棒振虫同然に思はれ」とは根本的な違いが見られる。“家業に励め、家を忘れるな。油断はむしろ太平の世に現われやすい。源実朝は和歌にはしった為に天下を失った”等々。 特権化した新興町人上層の人々のあり方を基準にする限り、「棒振虫――」の利左の生き方は否定されなければならない。 西鶴の視点は、常の町人二代目のもの。自己の世代に対して、厳しい眼を向けると同時に、そのすばらしさを描き出す。利左の、友人たちを拒否する姿勢に代表される視点が、秋成に受け継がれてゆく。「菊花の約」に見られるような人間のさまざまな可能性の追究、そうした自己の世代へのきびしい眼は、『考見録』に見られるものとは異質である。 ○ 以上の報告に対して、熊谷先生から『考見録』の著者の生没年、出版時期が問われた。『考見録』が文学史において、どの段階に位置づくのかをはっきりさせるために、である。出版は享保11年~18年(1726-1733)、八代将軍・吉宗のころ。これは、じつは西鶴の時代ではなく、秋成につながる時期である。 『考見録』は、西鶴のような文学が存在しえないような歴史条件の中で書かれたものであり、秋成の時代の上層町人のプシコイデオロギーがそこに表現されている。その思想は、封建制の解体に向かう動揺期の危機意識、体制迎合意識とつながるものであろう。西鶴から秋成への移行期を語る重要な文献であることが確認された。 ★ K .T.報告 「秋成にとっての悪現実」というのは、あいまいな表現であった。誰にとって、悪現実であるかが問題。この時期、体制側は自らを延命させるために、寄生地主的土地所有を容認する政策を採る。それは、『考見録』の上層町人の発想に通じるものであろう。その結果、民衆は本来の民衆魂を失っていく。世わたり上手、体制順応……そうしなくては生きてゆけない。なろうとしてなるのではないが、人間が生きてゆくうえで、持たざるをえない弱さは、それがたとえ善意からのものであっても、結果は体制を支えるものになってしまう。理想を持って、人間として生きようとするものにとって、その現実は、正に悪現実としてひびいてくるのだ。秋成世代 は、その中で生きている。 人間とは、こうしたものではない、という気持をもつかどうかで、人間 が分かれる。信義を見出しがたい現実にあって、秋成世代にとっての、人間のあるべき姿を明確化したいという模索の過程が、彼の文学活動なのであろう。 「浅茅が宿」の、夫の勝四郎は、素朴で素直、正直な男であるが、理想を欠いた人間。しかし、七年のあいだに、自己変革があったと捉えてよいのではないか。一方、妻の宮木も“完全人間”として描かれているわけではない。ときに迷い、夫を信じる心を自らに確信しながら待ち続ける。人間の微妙なちがいが、決定的な行動選択を左右する。「菊花の約」「浅茅が宿」の両作品とも、舞台は戦国期。戦国の世と自分たちの現実が重層的に表現されている。 報告をめぐる話し合いの中で 報告をめぐる話し合いの中で熊谷先生から以下のような重要なご指摘があった。それに触発されて、私自身の読みも大きく変わっていった。いくつかの問題点を摘記してみたい。 ○ 舞台像と秋成世代の現実――舞台が戦国期であることは、「菊花」よりはっきりしている(……ありけりのけりに注目。伝聞した過去、すくなくとも近世以前の話として語られている)。「物にかゝはらぬ性」「農作をうたてき物に厭ふ」勝四郎の性向は、享保以降、顕著になるものではあるが、その現実を、秋成が描写しているわけではない。当時の読者の感情として 、“百姓は損だ、地主は……”等々が喚起されたのであって、今日(こんにち)の話でないことが大前提になっている。また、そう読ませる表現になっているのではないか。 ○ 宮木のキャラクター――テキストの「宮木」についての注は適切。仮名草子は大衆的読み物。『伽婢子(おとぎぼうこ)』の“遊女宮木野”が多くの人々に読まれていた。貧しくて、人身売買で遊女になる。が、それにもめげず、その枠の中でではあるが、きちんとした教養を身につけ、近世町人社会での理想の女性になっていく。秋成は、宮木というその名をつかうことで、宮木のキャラクターを尽くし、人物を生かしている。 ○ 作品冒頭の描き方、「勝四郎」の設定――「はた家は貧しくなりにけり」とあるが、その原因は勝四郎自身にある。「残る田をも販(う)りつくして」片端から金に換え、「絹素(きぬ)あまた買ひ積みて」全財産を持って、浮きうきして都へ。その一方、妻の宮木には、生活の手段(農民にとっては、それは田畑)さえ何ひとつ 遺しておいてやらない勝四郎。これでは“人でなし”とよぶほかはない。ほんとだったら、その勝四郎は妻・宮木との約束の日より一日でも早く、東海道をハイズリマワッテでも帰ってくるべきであった。 「浅茅が宿」では、その辺りのところを重く書き出している。また「菊花の約」が武家社会を描いたのに対し、「浅茅」では、身分的には、農民・町人を描き、角度を変えて切り込んでいる。 話し合いの中では、「階級が違うから敵になるのではなく、同じ階層の中にも敵がいる。秋成は、ある意味では近世の太宰治といえるのではないか」など、何人かの方から、貴重な発言もあったが、割愛させていただく。 ▼1988/12/26 №389 12月第二例会(12/10) 報告 H.M. 第38回全国集会テーマに関する常任委員会提案 ① 11月第一例会で、次の全国集会に向けて検討したいこととして、(イ)思想史としての文学史 (ロ)教師の登校拒否の心性、のふたつが提案されていた。(イ)も無論大事なことだが、統一テーマとしては降ろしたい。そして、「文学の科学」の「パートⅡ」というかたちで、「リアリズムとは何か」というテーマを設定したい。 ② これまでも、「リアリズム志向のロマンティシズム」ということを口にしてきたが、リアリズムとロマンティシズムとは、どう違うか、必ずしも明確でなく、安易に使ってきた傾向がある。先の全国集会で「文学の科学とは何か」の解明を目指したが、そこでも「リアリズムとは何か」という点の解明は不十分だった。今度はそれを、文学史上の具体的な作品のリアリズムを問題にすることで確かめ合いたい。 ③ 山田洋次監督『幸福(しあわせ)の黄色いハンカチ』について、ある評論家が、「あんなこと(相手を信じて何年も待ち続けること)は実際にはありえないことだ」と非難したのに対して、山田氏は「現実にありえないからこそ描いたのだ」と反論したという。この山田氏の姿勢こそリアリズムではないのか。 ④ たとえば『雨月物語』には、様々な幽霊が出てくる。そのことと秋成文学のリアリズムと、どう関係するか、考え合いたい。また、芥川・井伏・太宰たちの文学の検討を通して、「リアリズムとは何か」を具体的に検討したい。 ⑤ 「鑑賞体験の変革」というと、“変わる”という点だけを考えがちだが、同時に、“持続”ということにも目を向ける必要があろう。井伏の「気無精」や「保守的」(「反動的」ではなく)というようなことについても、リアリズムとの関連において検討すべきではないか。 この提案に対しては異論はなかった。賛成意見のいくつかを以下に――。 ★ 山田洋次氏は、70年安保の状況の中で、“ありえぬこと”を追求したのだ。あの『――黄色いハンカチ』は決してアイデアリズムの世界ではない。(St) ★ 悪現実をリアルに描く(「在ること」を描く)のではなく、それをひっくり返して描く、という現実否定の精神(批判精神)がリアリズムだ。見る側・読む側からすると、作品には“あってほしい世界”が描かれており、その鑑賞の過程で、現実肯定的な自己への批判を感じることになるのだ。(熊谷) [リアル≠リアリスティック。「在ること」を、ではなく、「あり得ること」を描くのがリアリスティックな姿勢。リアリズムは「リアル」ではなく、「リアリスティック」と結びつく概念である。] ★ 「リアリズムとは何か」を深めることで、自分の中にある登校拒否の心性が、多少変わるかもしれない。(Ki) ★ 今、登校拒否の精神を持たない教師は、リアリストではない。いい加減にやっていれば、登校拒否にはならない。(熊谷) ★ 名和秀雄さんの話(「文学と教育」№146、p.13以下参照)に拍手を送っている母親たちが、その子どもたちが大きくなった時に、果たして、もう一度拍手を送るかどうか。そういう問題もごまかさないで、何がリアリズムなのか、文学論の問題として考えてみたい。(熊谷) ★ リアリズムとは何か、を問い直すことは、また、フィクションについて考え直すことでもある。それは、“現代小説”たりえていない「現代の小説」の問題とも関連する。マスコミ用語としてのフィクションとノンフィクションという分け方は、おかしい。リアリズムとは何か、と問うことで、真のフィクションとは何か、をも追求したい。(I d) ★ リアリズムとは何か、イメージぐるみ、感情ぐるみに捉えたい。そのことで、「追体験」や「共体験」などとは異なる「準体験」の機能も明らかになり、作品把握も深まるのではないか。(Ak) このように、リアリズムの問題を、自分の問題として検討していく方向が確認された。タイトルとして、「リアリズムとは何か」を掲げるというのではなく、たとえば、「リアリズムとロマンティシズム」(逆ではない)といったかたちで、位置付けられることになろう。その場合、鑑賞と科学とを別々に考えるのではなく、「鑑賞体験の変革と文学の科学」という視点からのアプローチであることを、決して忘れてはなるまい。 ▼1988/12/26 №390 12月第二例会 報告 つづき H.M. 「浅茅が宿」第1パート(冒頭~「鳥が啼く東を立ち出でて京の方へ急ぎけり。」)の印象の追跡 〔西鶴から秋成へ――封建体制下の民衆文学(3回め)〕 「文教研ニュース」(№388)のまとめを踏まえつつ、自分の言葉で印象を語り合う、というかたちで話し合いは始まった。 初めに、作品の冒頭の部分をきちんと読むことの大切さが語られた。「大切な田を売りつくした金で、“一発逆転”をねらうという、“ヘンな夢”を見ている勝四郎であることがはっきりした。(Dh) 「農村離脱者である私は、勝四郎を身びいきして読んでいた面があったが、冒頭部分から、すでに勝四郎のダメさ加減が描かれていることの指摘に驚いた。(Ak) 「多少の食料を残しておいたとしても、生活基盤のない状態で妻を残して上京したのはひどい、と改めて感じた。(Kg) 「左門のようなすばらしい主人公が登場するものという先入見で読んでいたため、勝四郎の人間像をつかみそこなっていた。(Tg) 「田を売りつくすというところに目が行かず、戻ってきてからの勝四郎を中心にこの作品を考えていた。(Yg)等々。 さらに、「ある研究者(高田衛氏)は、勝四郎の弱点・欠点 が冒頭部分に現われているなどと言っている。そこに上田秋成の人間形象の特徴がある、という。確かに、ここで田畑を全部売りはらい、京でひともうけしようとする勝四郎の無分別が描かれている。が、秋成文学の冒頭部分がいつもこうだ、というのは、作品の個性を無視した意見である。このことは、「菊花の約」の冒頭を想起しただけでも明らかであろう。(St)との発言もあった。 また、秋成の文章のすばらしさも指摘された。「『伽婢子(おとぎぼうこ)』を踏まえて、宮木を描いていることのすばらしさが、教養のある宮木の言葉などに窺える。」(Kg) 「『伽婢子』に比べ、こなれた文章で宮木の人間像が描かれている。また、宮木の言葉には、その思いが自然ににじみ出ている感じだが、勝四郎のそれは浮かれており、教養のひけらかしの感じがある。(St) 話し合いの後半は、“薄紙重ね”による印象の追跡とはどういうものか、を改めて問い直されたかたちになった。そのきっかけを与えたのは、「再興を志した勝四郎の発想――家をダメにしてしまった根本を見ずに、“やってやる!!”と思っている彼の考え方――をどう見るか?」(Sz)という発言であった。 勝四郎の発想は、確かに、「財産を食い潰して親族にもうとまれた人間が“今に見ていろ”という姿勢で考えている、おかしな方向のもの」(Dh)だ。しかし、そういう発想は(自分なども陥りやすいものだが)当時の読者の中にもあったのではないか、そして、そういう現実への批判として、勝四郎像が提示されているのではないか、そこに勝四郎像の必然性があるのではないか、云々―― 「実際に文章として、どう書いてあるのかの検討を!」という熊谷先生の提案に従って、話し合う中で、以下のことが確認された(と思う)。 (中略) 時間をかけて検討することで、私自身も、印象の追跡とは、ほんとうに薄紙重ねだ、と実感した。そして「部分は全体あっての部分」であり、「文章は前から素直に読めばいい」という熊谷先生の指摘に、素直に共感することができた。 冬合宿では、「リアリズムとは何か、を絶えず意識しながら、一行一行を大事にして」(Nm)第二パート以降を読み合うことになる。 |