| むかしの「文教研ニュース」記事抜粋 | ||||||||||||||||
| 1986 *例会ごとに発行されるニュースから、部分を適宜、摘記したものです。 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| ▼1986/1/11 №300 冬合宿研究会報告 I.M. 冬合宿で話題になった問題のいくつかを、箇条書き風にまとめてみたい。 Ⅰ.文学的イデオロギー概念をめぐって 1.プシコ・イデオロギーは、思想である。 思想はただの観念ではなく、実感の体系である。したがってそれは一人ひとりの実践のありようを規制しているものだ。ここで体系というのは、体系づけるという働きを示している。思想は実践を規制するとともに、実践の中で自己を変革していく動的な存在である。 この思想を、メンタリティーとイデオロギーとの関係という側面から、つかみなおしていったとき、そこにプシコ・イデオロギーという概念がうまれる。持続的なメンタリティーとして、また主体化されたイデオロギーとして、つまり、プシコ・イデオロギーとして、思想をつかみなおすことができるのである。 2.文学教育は、思想教育である。 プシコ・イデオロギーは、言語形象的認識機能を内具している。で、その認識機能に注目し、その側面からプシコ・イデオロギーを枠づけていったとき、そこに生まれるのが文学的イデオロギーという概念である。 プシコ・イデオロギーを持たない人間はない。と同様に、文学的イデオロギーを持たない人間もない。だからこそ、文学教育が可能になるのである。文学的イデオロギーをもっとひろげて、芸術的イデオロギーという枠組で考えれば、芸術教育は芸術的イデオロギーの教育であり、又そういう意味での思想教育だということになる。これこそが芸術教育の原点である。 3.上部構造(イデオロギー)としての文学現象は、一般的な現象ではなく、典型的な現象である。 文学的イデオロギーは、プシコ・イデオロギーに属しており、個性的なものである。文学現象が一般性に属するのではなく、普遍の中の個(典型)として、個性に属しているということの根源はそこにある。文学は上部構造であるか、というような論争が戦後なされたが、文学=非上部構造論を克服するための克服するための明確な視点がここに示されている。 4.自己の階級主体(実践主体)をぬきにしては、創造も創造の完結も不可能である。 これは、文学的イデオロギーの特性を考えれば当然の事である。化学も文学も人間の実践とかかわって存在しているわけだが、科学の場合は、自分が実行できないものでも、真実は真実だとして追求する。文学の場合は、あくまで自己(普遍につながる)の実践に密着した思索である。教養的中流下層階級者の視点が、なぜ、すぐれた文学的視点でありえたのか、という問題もそこに深くかかわってくる。 (Ⅱ.略)
▼1986/1/25 №302 1月第一例会報告( T.K.)から ──人生には、あいまいなこと、訳の判らないことが、存外大きなパートを占めている。新しい映画の中には、そういう問題と正面からとり組んだ作品がボツボツ出てきている。映画の未来は、そこに着眼する限り、明るい。 「読解」派、結論を用意して、その結論に向かって読者を追い込んでいく。そこには、わからないからこそ一緒に考え合うという態度が欠けている。結論は一つ、答は必ずある、という姿勢は非芸術的・非文学的だ……。 ▼1986/4/12 №307 春合宿研究会報告(Y.H.)から 今回の春季合宿は、たっぷりと時間をかけて、プログラムの第一部「国語教育・文学教育の原点」を問いかえした。 テキストに指定されていた「イヌに食われろ、共通一次」(「文学と教育」135号所載「私の教室」)を自宅で読んだとき、「入試のありようが、実は、大学文学教育と高校文学教育との直接の、そして決定的な最初の出会いの場にほかならない。」という指摘に、まずぎょっとさせられた。 「けっこう良心的にやっているほうだ」という重いが、どこか心のすみにあって、文学教育にとって「直接の、そして決定的な最初の出会いにほかならない」という自覚が、私にはまったく欠けていたからだ。 今回の春合宿・第一部は、もう最初から自分の理論と実践を問いかえされるかたちではじめられたのである。 この№135の「私の教室」、熊谷先生の報告についての感想を私なりにまとめることで私のリポートとしたい。 さて「イヌに食われろ、……」に例示されている入試問題について、Tさんは「こういうテストなら受けてみたい。やっていて楽しくなる」と発言されたが、同感だった。たしかに、問をたどっていくことが問題文を媒介にして、新しい問題発見の旅になっていくからである。 例えば、問題文にされている新聞のコラムの筆者自身、一茶の俳句についての様々の理解を紹介して、さてしかし、「よく分からなくなりました」といったのに対して熊谷先生は、注意深く配慮された〈注〉を含む問題を提示されて、この場合、どういう理解でなければならないかを、回答者が発見していくしくみにくみたてられている。まったく感動してしまった。(機関誌「文学と教育」135号、p46、問11~13) 生きた文学史である。 読者(解答者)に対して、ことばが信号になりうるように、また「行動選択のための思索」になるように問いかけていくテストなのだ。記号を単に記号に置きかえてすませているような授業と、共通一次に代表されるようなテストのありようを、具体的な形で批判されているのだ。 文学の授業が、そのまま入試問題にまで貫かれているのである。 まさにテストもまた授業展開の一部であり、文学教育であるべきだという熊谷先生の論理・原理がここにある。「文学教育の視点から」の「すじを通」しているのだ。 しかし「すじを通」すことほどむずかしいことはない。自分の中にしっかりした論理を培わないところでは流されるばかりである。 「けっこう良心的にやっているほうだ」というのでは文学教育もおしまいだ。 ▼1986/4/26 №309 4月第一例会 K.K. 今例会のテーマは次の二つでした。 1.『鉄面皮』に見る、その時点における太宰の歴史小説観。(報告 H.M.氏) 2.『右大臣実朝』第一章を中心に。(報告 Y.H.氏) おふたりの報告を中心に話し合われたことを、私は今どう掴んでいるかというようなことで例会報告にかえさせていただきたいと思います。 1.当時流行の歴史小説といわれていたものが、「もっぱら作者自身のけちな日常生活からのみ推して」の人物造形であり、衣装は違っていても、中味は現代人以外ではないことに、太宰は腹を立てている。(『鉄面皮』全集巻六 p.8、12~) このことは苦しい時はいつも実朝を思うという形で以前から抱きつづけていた太宰の実朝像のとらえ直しがあったということではないのか。史実を逸脱しない形での自分の掴み直した実朝像を描こうと考えた。掴み直しとはどういうことだろうか。 太平洋戦争下、誰も彼もが同じような国民服、モンペを着せられている。その時代を生きる太宰とのかかわりに於て過去は問題にされる。その時、太宰は「人間はみな同じものではない」という括弧とした人間観を自分のものにしていた。味方の階級の中に於ても、敵階級の中に於てさえ、個を見据えていこうとする視点の確立である。この視点こそ「〈教養的中流下層階級者〉の文学的イデオロギーに固有の形象的認識の視点」だと、熊谷先生は著書『太宰治』の中で述べておられる。 『右大臣実朝』は「人間みな同じものだなんて、何という浅はかな独りよがりの考え方か……」という視点を獲得した実朝の近習をナレーターとして設定している。このナレーターの設定の意味、性格を考えてみることは、作品を読む上で重要なことである。それは、作中人物と作者との距離を適切にとるためにということにとどまらない。作者自身の生き方は、深い関心と敬愛の対象としての実朝の内面に虚構されていく。内面に虚構された太宰というのは、A氏の言葉をお借りすれば、「精神の原風景の問題」ということになろう。さらに、「ナレーターも実朝も中世の存在性と感覚を持った人物であるが、〈教養的中流下層階級者の視点〉で切り取られた人物像」ということである。 この内面に虚構された、ということを『吾妻鏡』『金槐集』と『右大臣実朝』の関係に見るならば、史実は『吾妻鏡』から、実朝像は『金槐集』の中から探ったというようなことではなく、『吾妻鏡』『金槐集』の表現の意味を、怒濤の葉っぱの世代の発想、フィルターを通して掴んだということになろう。自分にとって意味のある表情を発見していくということがないと、現代小説としての歴史文学にはなり得ない。『吾妻鏡』を読む中でも、ある表情を探り当てていく、そういうことであろう。史実に忠実に、それに現代の問題をダブらせたなどという二元論ではない。この二元論を払拭し、一元的なものにしたということが、虚構(=文学)である。そうなって初めて、現代史としての歴史小説と言えよう。 熊谷先生はこうも言っておられた。「表情が出て初めて文学のリアリズムになる。リアリズム志向のロマンティシズムということは、リアリズムがなければロマンティシズムはあり得ないということでもある。「ロマンティシズムに支えられたリアリズム」、「リアリズム志向のロマンティシズム」、「抽象的思想への情熱」、「文学的現実としての史的現実」、「現代史としての文学史」、これらのことが大きく一つのものとしてつながってきた。 こう考えるとき、『右大臣実朝』は見事に現代史としての歴史小説になり得ている。 1.のテーマである『鉄面皮』にみる、その時点における太宰の歴史小説観というのは、このようなものと考えてよいであろうか。 2.(省略) ▼1986/5/10 №311 4月第二例会(『右大臣実朝』)報告 M.M. チューターの熊谷先生から、『右大臣実朝』の読みに欠かせない事柄のご指摘や問題提起が数多くなされた。二十年戦争下の現実と作品とのかかわりなどにふれて、先生のご体験に基づく貴重なお話もいくつか伺うことができた。不十分な要約でお伝えできない部分が多くあることをおゆるしください。 Ⅰ.前回の補足(熊谷先生) ① レポート、コメントは作品把握に欠かせない所をおさえる。例えば、第一章に出家者の名を列挙した部分がかる。これなどをとばして読んではならない。「武蔵守」(武蔵は上国中の上国)、「隠岐守」(隠岐は下国中の下国)に至るまで、こぞって出家している。彼らの出家は『阿部一族』の場合のように、子孫繁栄をねらったものではない。こういう表現の中に、多様な身分改装の武士、貴族達から敬愛されていた実朝の人間像が伝わってこないだろうか。鴎外文学を受け継いだ太宰の姿がはっきりと感じられるところである。 ② テキストの良否──『吾妻鏡』の訳文には「御所」(ごしょ)とあり、太宰全集には「御ところ」とある。将軍とて「臣民」、当時、太上天皇の住居と同じ御所(ごしょ)という言葉を使ったとしたら、書き換えを求められるのは必至である。政治に舌を縛られている作者の、抵抗の思いをこめたことば選びがなされている事など、コメントする必要があるのではないか。 ③ 『右大臣実朝』から『鉄面皮』へと読み進むのと、逆に『鉄面皮』から『右大臣──』に入るのとでは、『右大臣──』の読みが違ってくるはずである。今回は『鉄面皮』から入る。『鉄面皮』には太宰の歴史小説論が述べられている。当時、流行した歴史小説には、人間が歴史社会的存在=階級的存在であることを無視した、人間みな同じもの、と言わんばかりの人物が登場する。マルキシズム以前の、階級論のない人間観であることを太宰はその『鉄面皮』の中で鋭く批判している。そこをおさえなければ『鉄面皮』から入った意味がない。 ④ ナレーターは十二歳の時は十二歳なりに、四十歳の今は、その年輪の中でつかみ直しを氏ながら、実朝を「融通無碍」な人として語っている。「傷心」を抱き、狂う程の状態になるのをおさえて、実朝は一切を表示 ではなく、表現 で通していく。人間として面白味のある人間とは、「融通無碍」な人間のことではないか。そうふるまうことは難しい。自分は勿論、他の誰にでもできることではないと考える人にして初めて、人間みな同じものではないという捉え方が可能になるのではないか。 鴎外文学の“あそびの精神”が実朝の中に生きている、という事を痛感する。 Ⅱ.第二章をめぐって 熊谷先生が朗読を生かしながら、コメントされたことを列記させていただく。 ★ナレーターの口調、敬語の使い方等から、語っている相手が、相当身分の高い、しかもその人物に敬意を払っている人間であることが想像される。 ★幕府のまつりごとを「決裁」している実朝の姿が──合議の形態をとってはいるが、宿老の悪玉連中の思うがままのやり口の中で、うっ屈した日々を送っている──十二歳のナレーターらしい語り口で、イメージ豊かに語られている。 ★「当て推量」や「したり顔」の穿さくをする人の姿に、戦時下、サーベルをガチャつかせていた軍部、官憲のイメージがダブってこないだろうか。 ★「敬神の念」=「信仰」のある人=現実的(リアル。通俗的・妥協的・日和見的)でない人。鴨長明を「信仰ノナイ人」と言った実朝の言葉につなげて捉えてみてほしい。 ★京の様子、噂への関心は、文化 に対する深い思いのあらわれではないか。 ★朝廷への敬慕=後鳥羽院の正体を見ぬけない十七歳の実朝の、虚像 に対する思いである。こういうところに〈日本ロマン派〉保田与重郎的なもの(『戴冠詩人の御一人者』参照)が重なり合う。日本ロマン派はマゴコロ主義、その意味で“リアル”ではない。彼らは文化を必死に守ろうとした。この時期、文化 を本当に愛し、野蛮であることを嫌悪した人達は、お互いに肩を寄せ合い、温め合い、ある明るさの中に生きていた。そういう“歴史”をイデオロギー主義にならないで、歴史的に見ていく必要がある。……実朝は次第に実像 がつかめる人間に成長していく。 こういう実朝像に、作者・太宰の若い日の姿が重なる。その自己凝視の姿勢や、まら虚構の在り方に一層魅力が感じられてくる。 ★峯王──騎射=登用試験に失敗し、失笑をかい、将来への望みを絶って世間を捨てて逐電する。そのいさぎよさと、変にしつこくない所が素敵である。京女たち(御台所をはじめ侍女達)はそれを観て、「笑い崩れて」(バカ笑い)いる。今まで各自、ここの所をどう読んできていたのだろうか。『徒然草』二二六段の信濃前司行長が楽府の御論議に失敗して嗤われ、「学問 を捨てて道世」したのと、社会状況や人間関係は同じである。どんなときに、何を嗤うのか、その嗤いの中に見られる人間性の一面、当時の学問のありよう等がそこに浮かび上がる、と同時に現在の学問の世界の現実がインプリケートされてくる。 ★「平家ハアカルイ」──ということを、実朝は『平家物語』を通して感じとっている。“文学”が作中人物である「実朝」の中に息づいている。そういう設定のもつ意味はとてつもなく大きいものである。平家がほんとうに明るいかどうかはさておき、実朝は『平家物語』をその面ですくいとり、感動を示している。源氏や義経をも平曲を通して見つめようとしている。歌よみが好きな実朝ではあるが、武人にして歌人の源三位頼政のことには触れていない。父・頼朝の事は文化人、勅撰集にも入集しており、自由を愛する人として敬愛している。それは義家についても同じである。しかし、頼政については触れられていないのである。『平家物語』では次のように記されている。「上るべきたよりなき身は木のもとに椎(四位)を拾ひて世を渡るかな」──このように頼政は出世志向の人として描かれている。実朝から見ればこういう人物は尊敬に値するものとは思われなかったであろう。一方、平曲の中の平知盛は壇ノ浦合戦の場面に見られるように、人間として面白味のある人間の極致に位置づけられている。文学を通して、そういう思索過程をたどる人間として実朝像を形象化している。 ★アカルサと暗さ──この時期の実朝は、まだ暗さを暗さとして十分には感じていない。だからこそ、明るくふるまうことができた。しかし、虚像を、それとして見破れなかった実朝の「ロマンチシズム」は次第に深まりを見せるようになる。じつはそこに、明ルサハ滅ビノ姿……というところにはってんしていくモメントが感じられる。 ▼1986/5/24 №313 5月第一例会報告( H.M.)から 研究会に先立って、熊谷先生の旧著『松宮観山 武学答問書』(昭和17年刊)の紹介があった。当時、執筆を大幅に制限されていた先生は、太平洋戦争下の時流に乗ったふりをして、合理主義的な判断を欠いた当時の日本の指導者への批判を行なった、ということである。義兄[大西一男氏]の名を借りて本書を公刊した経緯についてのお話は『右大臣実朝』を、場面規定をおさえて読む上でも、大いに資するところがあった。 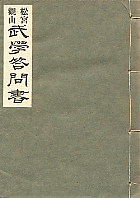 [参考 『武学答問書』表紙] [参考 『武学答問書』表紙]▼1986/6/14 №315 5月第二例会報告( S.F.)から 報告の前提が、機関誌次号の熊谷論文「リアリズム志向のロマンティシズムを解明したもの」であり、論議もそこに集中したので、熊谷先生より講義を受けた。それを略記しておきたい。 リアリズム志向のロマンティシズムについて ① リアリズム志向のロマンティシズムにおいて、リアリズムとロマンティシズムを対立的に扱うのはまちがいである。 ② リアリズムとロマンティシズムは不二の関係にあり、肉体と精神の関係に喩えて言えるもので、リアリズムなくしてロマンティシズムはなく、ロマンティシズムのないリアリズムはないといえるもので、この関係を示す的確な既成の概念がないので、「リアリズム志向のロマンティシズム」と命名したものである。 ③ ロマンティシズム一般はないのであって、個々のロマンティシズムがあるだけである。真にロマンティシズムを志向しているものに対して「リアリズム志向のロマンティシズム」と命名したものである。 ④ ある精神構造から導かれた方法・手段──リアリスティック あるありズムを実現させるための手段──リアリスティック(動的なもの) ⑤ リアルではなく、「リアリスティックな抽象的な思想への情熱」(臼井吉見)=賭け、冒険。 臼井吉見のいうところのものは、マルキシズムないしコミュニズムへの、ソロバン勘定なしのロマンチックな情熱であるが、太宰文学の展開をみた時、『右大臣実朝』などを例にとれば、マルキシズムやコミュニズムだけでは割り切れない、もっとふくらみのある、ゆたかな作品形象となっている。そのようにリアリスティックな抽象的な思想へのロマンチックな情熱がある。 ⑥ 文学史上のいわゆる自然主義(ナチュラリズム)は、a.リアルであることでリアリズムになろうとしたエセリアリズムである。また、b.自然主義のリアリズムは作品においては部分的にリアリスティックになりえているものもある。啄木の批判はそこに向けられている。そこに自然主義のもつ矛盾がある。リアルとリアリスティックとが未分化なところのエセリアリズムである。『破戒』はリアリスティックたろうとすることで矛盾をおこしている作品であり、『新生』はまったくリアルである自然主義作品である。 ▼1986/7/12 №317,№318 6月第一例会『右大臣実朝』最終章の検討-最終章の呼びかけるもの-〈Y.H.記〉 (前略) 例会後半に入って──。 「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ」という、第二章から一貫して響きすづけてきた、この言葉こそ、この作品の文学精神ではないのか、この実朝のつぶやきこそ、「世のなか、ふっと火を消ちたるさまなり」という最後の一行と響きあって、呼びかけつづけているもの、“最終章の呼びかけるもの”ではないか、という熊谷先生の指摘によって、ツゥーと一本、なにかが通った感じがした。 最終章の報告が討論の中で深まり、その発見だけでも、ぼくにはおもしろかったのだが、考えてみれば、その満足は、ぼくの中で、各章がバラバラにしかつかめていなかったということに気付かないでいたせいであったためだろう。 もっとも、一本なにかが通ったといっても、例会当日のぼくは、美しく生ききって敗れたものの高貴な魂といったものが、しきりに感じられ、心が洗われる思いだけで、バクゼンとしたものであった。〈アカルサ〉ということについて、まとまりがつかないでいたのだと思う。 「都ハ、アカルクテヨイ」「平家ハアカルイ」という実朝のことばの中に、「京都文化 への傾倒」や「メンタリティーのすがすがしさ」をみ出している熊谷先生のこれまでのご指摘などが、頭の中をかけめぐっていた。 また、実朝が〈アカルサ〉ということばに託したその思いは、人間精神にとって、暗黒の、ハニカミを知らない無文化・無教養に対置した人間的教養とでもいいうるものではないのか、という理解もきざした。 しかし、それだけではどうも、「都ハ、アカルクテヨイ」「平家ハアカルイ」という点ではつながるのだが、「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ」ということばのもたらす深い印象を──ぼくの中に、なにかが一本通ったという実感はありながら──説明しきれないように思えた。 いま、あの時の「一本通った」というじっかんをついせきしなおしてみると、「アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ」ということばが呼びかけてくる、その響きは、最終章にいたり、それまでの〈アカルサ〉についての理解を内包して、なお、もっと大きいところで、いわば象徴的な次元で、ぼくらの旨を打っていたのではないか、と思うようになった。 つまり、本を閉じてからも響きつづける、あの一句の中の〈アカルサ〉は、この数年、太宰の文学的イデオロギーをつかむ勉強を通して学んだ「何らか抽象的な思想への情熱を内心に掻き立てながら、曲がりなりにも自分の旗を守り抜こうとする」精神につながるそれではないかということである。 その精神がもたらす〈アカルサ〉、つまり、「何らか抽象的な思想への情熱」がなければ、ニヒリズムにおちこむしかない状況のもとで、その情熱を支えに、内心を掻き立て、自分の旗を守ろうとする人間だけがもつ〈アカルサ〉=ロマンティシズムではないかと思われてきたのである。 疎外状況にあって、それでもなお心づくしに努める実朝の、あの美しい生き方にそれはみえてくる。「無理カモ知レマセヌガ、ソレダケガ生キル道デス。」 そしてまた、その繊細な神経がひとり(個において)人間としての気品を崩さず、対峙すべき現実を見すえ、例えば日本脱出の夢──精神の自由を求め、不可能を可能にする夢──に自己を賭けていく実朝の自分の旗を守りつづけ、待ちつづけた生き方にも、それは、みえてくる。 階級疎外のあるところ、この〈アカルサ〉=ロマンティシズムは異端であるほかないのだろう。 待ちつづけた実朝であるが、“待つ”ことにも限界がある。日本脱出にも失敗した後の屈折し崩折れていった実朝であるが、(そうした人間的側面、真実をも、はずさず、描ききったところに、リアリズムの本道をみるわけだが)そのように実朝を追いつめたもの、〈アカルサ〉を打ち砕いたものは何かと、問わないわけにはいかない。いわば疎外の人間的・社会的根源を問い続けることを求める響きとして、この一句がみえてきた。 しかし、それは、例会で熊谷先生から鋭く指摘されてしまったことだが、世俗のアカにまみれて鈍感になっているぼく自身の内側を思いかえさないで、その根源を問うような姿勢ではみえてこないものだということは明かである。 〈アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ〉と、反語にこめて、みずからに問い返す、あのいつまでもぼくの心の底で響きつづける実朝のことばが、最終章の最後の一行「世のなか、ふっと火の消ちたるさまなり」に共鳴し、一本の音になってきいま、ようやくぼくには、〈アカルサ〉を〈ホロビノ姿〉にしない自他のありようをさぐりつづけるほかない、という点がみえてきた。 ▼1986/7/26 №320 6月第二例会報告 続き(T.K.)から リアルとリアリスティックということについて ・手段としてリアリスティックに追うことで、読者にはリアルな印象を与える(リアリティーを感じさせる)。これがリアリズム志向のロマンティシズムである。リアルに追ったものは決してリアルな印象を与えない。 ▼1986/9/13 №321 8月総会 報告〈その1〉 ○この一年をふりかえってみて── ・例会の運営面で大きく変わったことは、第一会場を烏山に変えたこと、それと関連してロング休憩をカットした時間帯の変更。 ・数字でみると、例会18回、合宿3回、集会2回、総会2回。──アナタの数字は! ・そして、私の成果は……(省略) ○編集部総括から ・こういう学術雑誌は日本の中でも唯一じゃないか。──毎号統一テーマのもとに編集していること。そして、編集権を確保していること。編集権を奪われている場合、どうしても版元の意向で、売らんかな、の方向へすべりがち。(編集長) ・原稿の依頼があったら、いのちがけで書きましょう。(A) ・「私の教室」などのプール原稿がほしい。(編集長) ・もしこれ(機関誌「文学と教育」)がなかったらどうなるか。拠りどころを失ってしまうでしょう。研究水準が保てないでしょう。書きましょうね。(熊谷) ▼1986/10/25 №325 9月例会(9/27日)報告 続き〈K.K.〉 鴎外・芥川・井伏・鶴田知也などの歴史小説との連続・非連続面を意識して〈T.M.報告〉 T.M.報告がまずおさえたことは、「自分の主体をかけない読み、作品を解きあかそうという姿勢からは作品は読めない。」ということであった。その意味で、文学は受け継ぎ、系譜から見ていかなければいけないのではないか、と前置きして──。 鴎外の歴史小説と『右大臣実朝』との連続・非連続、芥川の『羅生門』や『雛』について、さらには井伏の『さざなみ軍記』に触れながら、『右大臣実朝』という歴史小説の特性を語られた。 特に、近習の語りという一本線だけでなく、『吾妻鏡』という作品を、虚構意識によって取捨選択を挿入することで、時間の経過、近習には見えてこないものを写し出す。又、近習のおしゃべりをストップさせ、二つのからみあいで展開していく。近習の語りで『吾妻鏡』に関与していく、又、『吾妻鏡』を通じて、近習の語りに多様な人間が描かれていく。さらに鶴田知也『コシャマイン記』に触れて、『右大臣実朝』とのつながりを探られた。 その後の討論から印象強く残ったのは、熊谷先生の『コシャマイン記』から『右大臣実朝』へという文学系譜の指摘であった。討論にでた発言をあげる。 ・『コシャマイン記』という作品は階級の問題、民族の問題が、あの非文明人・コシャマインの眼を通すから見えてくるといった作品である。英雄として死ぬことを期待していた読者は「又も詐し討ちにしたな」と叫んで死んでいったコシャマイン、「その砕けた頭部を、昼は鴉共が、夜は鼠共が啄んで、その脳漿の総てを喰い尽くした」という英雄の最後の姿を見る。(滅びを自覚しなかったというより、滅びのあり様が見えていなかったコシャマインと言うべきではないか。) ・『コシャマイン記』をくぐることで『右大臣実朝』という作品がどう見えてくるか。まさに文学系譜の問題としてとらえることができるのではないか。 ・そして現在我々は、コシャマイン以上に未来が見えているのか、見えていないのか。現代史としての文学史とは、こういうことではないか。 『コシャマイン記』から『右大臣実朝』へという主題的発想のつながりが太い線として私には見えてきた。 ▼1986/10/25 №326 10月第一例会(10/11)報告〈M.M.〉 熊谷 孝著『日本人の自画像』 Ⅰ近代主義の克服 初めに準備会での熊谷先生の提言をうけて、N氏から──。日本の近代文学史を考えるには、日本的近代をどう把握するのかということが問題になる。『日本人の自画像』(以下『自画像』)は講座派の立場に立った平野義太郎氏の『日本資本主義社会の機構』の論理を大前提に、それを文学史として「移調」して書かれたもの。その社会機構や経済的基盤の捉え方が確認されなければ、文学史を考える際にズレが生まれて来る。『日本資本主義社会の機構』の論理を肯定できるのかどうか、けんとうしてほしい──、という問題提起があった。それをめぐって以下の(1)~(3)について討論が行なわれた。 (1) 『自画像』「あとがき」の確認 〈担当者 N.T.〉 文学史を考える場合の基本的姿勢は〈現代史としての文学史〉であること。そのためには系譜論的発想が求められること。また文学史を追究する作業は「究極において、現代の読者相互の現代のテーマに関しての対話の場を用意することである」。“近代主義”の問題は、私達自身の「現代のテーマ」として避けては通れない問題である。又、「あとがき」の冒頭の「文学史と文芸時評との統一」という視点は、文学史を考える上に本質的かつ実践的な問題を含んでいるなど、改めて読み合うことで、今後の課題とその為の方法とを大きく、そして具体的に確認できた。 (2) 『日本資本主義社会の機構』概観 〈担当者 I.M.〉 概観に先だって次のような指摘があった。 ──日本近代文学史把握の前提条件 ① 日本的近代(その経済的土台、国家の階級的本質と政治形態)についての構造的把握。 ② 確かな階級論を自己の内部に用意すること。 (①②はひとつながりの問題であり、これをぬきにしては〈現代史としての文学史〉を構築することが不可能である。 ──日本資本主義論争における講座派 1927年から37年にかけてのいわゆる日本資本主義論争は、日本の近代をどう変革していくのかという革命路線の問題として、すぐれて実践的な論争であり、その核心は日本的近代における前近代の位置づけ、日本的近代の性格をめぐる論争であった。したがって、日本の近代文学史の把握や〈現代史としての文学史〉の視点のもつ意味の問題と密接なつながりを持つ。そこでの労農派の見解は、例えば天皇制絶対主義にしろ、寄生地主制にしろ、単なる封建遺制と捉え、日本的近代を規定する重要な側面とは考えない。一方、講座派は、前近代が日本的近代を支えるものであり、その構造的一環として存在する、と捉える。日本近代文学史の把握はこの講座派的視点からとらえていくことによって、初めて可能になるのであり、実践的課題とのかかわりが見えてくるのではないか。 以上の二点をふまえて、まず日本的近代についての熊谷先生の見解を明らかにすることから始められた。『自画像』において、「天皇制絶対主義──版封建的資本主義として成立した時本的近代」、「前近代との抱合における半封建的資本主義としての日本的近代」、封建制が資本制をささえ、また資本制が封建制をささえるという半封建的資本主義」、「日本的近代のどす黒い前近代性・前近代と近代との抱合におけるその絶対主義」として、くり返し明確におさえられている。 その『自画像』における観点の前提としての平野義太郎氏の見解を“文体的摂取”ということで簡潔に紹介された。短い期間に用意したと言われたが、『自画像』の論理と対応させながら、見事に要約されており、大変有難い媒介の役割を果たして下さったと感謝している。その内容については例会の資料によってご理解いただきたい。 この後『──機構』が提示している問題の今日的意味について検討が行なわれた。 (中略) (3) “近代と教養的近代”概観 〈担当者 I.M.〉(この項№325に戻って掲載) この項は『自画像』の各論が記述された後に書かれたもの、具体を通したうえでの抽象である。“教養的近代”という概念を提起された意味は大きい。文学とは何かを考える時、この概念の有効性に注目したい。『自画像』の中に、教養的近代とは「利潤追求の自由を根本義とする“近代”の一種の自己否定によってつくり出されたもの」云々と明確に規定されている。「一種の 自己否定」ときめ細かな論脈の展開がなされている。その意味をきっちりと捉える必要がある、などの発言があった。そこで熊谷先生から次の提起がなされた。「一種の 自己否定」と書いたのは、不十分な自己否定ゆえに全面的には否定しきれていない、という意味である。それ故にプロ文学の想念としてああいう形のものが生まれ、鴎外、芥川……の文学が必要とされた。異端の文学系譜につながる作家達は近代主義を徹底して否定しきろうとしている。透谷が近代主義と反近代主義の〈結節点〉であった(『自画像』中の透谷論の「結論」の一部)ことを確認してほしい。── 時間の関係で“近代文学の始発点を透谷に求める意味”、および今回予定していた(4)“近代主義における戦前と戦後”については次回に、ということになった。 I氏の豊かな報告を十分にくみ込み得なかったことをお詫びしたい。社会科学の面の不勉強を痛感している。私も『自画像』を納得して読んだ一人であり、その立場を今後自覚的に捉えていきたいと思う。 ▼1986/11/22 №327 『日本人の自画像』 Ⅰ近代主義の克服〈第二回〉 10月第二例会報告 〈T.K.〉 前回の例会にひきつづき「近代主義の克服」の章について検討した。冒頭、熊谷先生から、講座派と労農派を善玉・悪玉式に軽々に割り切って捉えるようなことがあってはならない、との指摘がなされた。 ──『自画像』の視点はむろん講座派のそれである(前回確認済み)。講座派的な視点に立つ以外、どうにもならなぬものがあった。経済の専門でない者がなぜその視点をとることになったかについては、戸坂潤の論理学という“秘密兵器”の存在があった。封建「遺制」という考え方は誤りだ。封建「遺制」があれほどに「生き延びる」には、それなりの必要があって「再生産」されているからだ、との見解を戸坂先生は一貫して持っていた。 ところで、講座派の立場に明確に立つことは、労農派の一切を気って捨てることにはならない。実際、近代主義批判という点では労農派の方が、より徹底していた。講座派(そしてその亜流)は前近代批判は長けていても、近代主義批判への徹底を欠いていたのである。 (なお、この近代主義徒然近代批判を文学的に統一してなし得たのが芥川文学であった。) 「農民文学」三井……考えてみても、いわゆる講座派の作家から真の「農民文学」が生み出されたとは必ずしも言い難い。それは例えば、いわゆる労農派の鶴田知也を思ってみればよい。また、長塚節、和田伝を思ってみればよい。そして『丹下氏邸』(井伏鱒二)派、あるべき農民文学の方向を示したものではないか。講座派・労農派論争以前の成立であるにかかわらず、これこそ講座派的視点に貫かれた作品だといえよう。── 講座派・労農派を善玉・悪玉では言えぬというところから発展して、話は蘆花の『灰燼』に及んだ。この作品に登場する茂は、自由民権運動に参加するが、彼が加わったのは地主的基盤に立つ右派民権運動であったことが確認され、それが、透谷等が参加した民権左派でなかったことをもって、『灰燼』の感動が薄れるわけではないこと、そして、人間を左派・右派というように単純に片づけられないことなどが話された。妥協的・折衷的でない真の柔軟さをもって対象に接していかないかぎり決して「文学」は成り立たないということが改めて胸に落ちた一齣であった。 続く討論の中では、『自画像』の中に私たちは熊谷先生が文学現象を追求する苦闘のプロセスを見るべきであったこと、戸坂理論に学びつつ、それの依拠するマルクスの発想をモノにしていった熊谷先生の理論摂取の仕方にまで溯ってテキストを読み返す必要があることや、それに又、『日本資本主義社会の機構』をよんでわかることの外に文学を通すことではじめてみえてくるものがある、ということ等について話し合われた。 熊谷先生はこの討論の中でも蘆花を軸として話された。『灰燼』『思ひ出の記』についての指摘は、次章「日本的近代の成立」の担当グループの一人としては、前もってここにも一本太いレールを敷いていただいたことになり、とても有難かった。 ――『灰燼』を、マルキシズムをくぐった眼で読んだ場合、そう書かざるを得ぬ必然性をそこに感じる。しかも蘆花はマルキシズム以前の作家である。私たちがこの作品に見るのは文学的イデオロギーの確かさである。プシコ・イデオロギーとはこういう性格のもの、そして、メンタリティーで書いて、書き得たもの、ということを感じさせる作品になっている。茂をみつめ、猛をみつめ、それを人間の問題として書けたということだ。 公式マルキシズム作家には書けない、科学主義では書けない作品だ。マルキシズム以後でないと書けない形だが、実は、そうではない。この段階の蘆花に書けたというのは、非常に貴重なことである。マルキシズム以前の歴史科学にこのような捉え方はできない。文学にしてはじめて可能となったのである。(文学コースと科学コースの問題) 『思ひ出の記』は歴史としての近代はこうしたもの、これが明治だということがよくわかり、歴史の教科書よりは、よほど実になるおもしろい作品だ。「思い出の上澄み」をすくいとって書いたということは、それがニセものであったということではない。それに、ただの「上澄み」では、どうやらないものがある。複数のナレーターを設定していること、近代文学に多く現れる弱々しく青白い人間は、ここには登場しないことなど、この作品が文壇文学に終らず大衆文学になり得た理由は多々ある。文壇の枠を取り払って、このような作品をも位置づけながら、文学史の再構築ができぬものだろうか。── このあとN氏の「近代主義における戦前と戦後」についての報告があった。報告内容については割愛せざるを得ないが、詳細なレジュメが用意されているので、それによってご承知いただきたい。 (以下の部分、№329に続載) 討論は、報告と、熊谷先生から提起された問題、即ち、「戦前の半封建的資本主義は、戦後の農地解放の後どうなったか」ということをめぐって展開された。 天皇制が手段として戦後も温存されたことや、山林地主が土地(山林)の解放を免枯れたことなどが指摘され、また、首都圏の山林地主が自ら小企業経営者となって独占資本の傘下に組み込まれていくといった最近の実態についても具体的事例に即しつつ話し合われた。 平野義太郎の指摘は過去のこととしてだけではなく、まさに現代の問題として私たちは受けとめなければならない。過去が過去になりきっていないのだ。「半封建的な意識の再生産」と「中流意識の再生産」の結びついた状況がますます進行しつつあるのではないか。そう考えてくると、「戦後」を読む視点が定まってくる。1950年代の六全協世代のかかえた問題は、1930年代の太宰治たちの苦しんだ問題と重なりをもつ。その問題は究極的には「個の自覚の欠如」「個の自覚を求める精神の弱さ」ということに尽きよう。(過去のすぐれた文学は、個の自覚に徹しようとする文学であった。)等々。今後の『自画像』検討の足場を強固にし、方向を見定めるには至極有益な報告であり、討論であったが、その豊富な内容を豊富さにおいて掬い上げきれなかったことが残念である。 ▼1986/11/22 №328 『日本人の自画像』 Ⅱ日本的近代の成立 11月第一例会報告 〈S.F.〉から 熊谷先生の発言 ★(『自画像』p.29の『太陽のない街』にかかわって)日本資本主義機構における初代労働者群として、お加代の父親を登場させたところに意味を見つけた。 ★(『浮雲』に続く日本近代文学の展開の中で)内海文三と『舞姫』の太田豊太郎について、それを世代の交替における受け継ぎの問題として、系譜論的に見ることが大切だ。『浮雲』か『舞姫』かという二者択一ではない。「豊太郎の真の心のうずき」が鴎外自身の心のうずきとなって、鴎外は歴史小説を書いていく。それは歴史的社会的発展とプシコ・イデオロギーの深まりによるものである。 ★言文一致について、いわゆる文学史では、そのはじまりを『浮雲』に見ているが、私たちの今までの研究の結果では、そうはなっていない。私たちは以前ホトトギス派の文体の学習をしたが、その点からみて『浮雲』は言文一致の始発点とは言えない。そして、異端の文学の達成点である『右大臣実朝』からみれば、『浮雲』が異端の文学の始発点にならないのは当然である。 ★透谷からみると、『浮雲』のリアリズムは、西欧近代文学のリアリズムであり、だから文三を袋小路に追い込んでしまったわけである。 ★『浮雲』は通俗小説ではないか。それとの対応でいうと、、『金色夜叉』を通俗小説のうちに一把ひとからげにしてしまってはいけない。『金色夜叉』に感動し、そこに近代文学を感じた。苦闘の連続の中で、貫一が出口を探していることは、人間を出口のない袋小路に追い込んだ『浮雲』ちがうではないか。 ★『日本資本主義社会の機構』を文学史において深めるということが、今回の大きなテーマである、という点を忘れてはならない。 ▼1986/12/13 №331 『日本人の自画像』 Ⅱ日本的近代の成立 11月第二例会レポート 透谷から藤村へ・続き 〈S.T.〉から 熊谷先生の発言 ★瀬川丑松がテキサスに行くことは、日本社会からの自己追放であり、その意味では滅びの道を選んだことになる。藤村文学を、オーナメンタルな(飾り立てた)告白文学として批判・否定する見解もあるが、そこからは、敢えて滅びの道を選んだことのまっとうな評価はできない。お志保の描き方に多少の出来すぎのきらいはあっても、そのすばらしさは否定しようもない。 ★「けれど、労働者となった丑松とお志保のその後の闘いの姿を、読者はついにこの作品の中に見出すことはできない。」(『自画像』78ページ)のところは、現実の社会状況の未成熟の中で、それ以外に藤村が書きようもなかったことを、精一杯アピールしたかったところだ。『破戒』は別の経路を辿って成長した透谷の姿を見出すことの出来る作品だが、丑松が、次に他の別個の作品で姿を変えた丑松として現れる(とすれば……)、という文学史意識にもとづいて書いた。 ★(与謝野晶子についての)「前垂掛のリアリズム」という概念は、単なる耽美主義的本能主義者というような、従来の晶子論へのアンチ・テーゼとなる素晴らしい概念である。しかし、彼女の所属する新詩社が、「八分までが前垂掛の集まり」であったことと、加えて晶子自身が「堺の街のあきびと」の家の出であったことも含めて、だからそのリアリズムを新詩社のラショナリズムと同一視し、一義的に理解することは間違い。 ▼1986/12/26 №332 文教研活性化のために(組織部長提案) ──「ニュース」の円滑な発行を期するために、下記はその一部ですが提案が出されています。例会運営にも関りがありますので、掲載いたします。 1.24時間の中に、文教研の思索を位置づける。 2.2週間単位で、研究会の質を追跡し続ける。 3.例会参加に必要な準備量を自己の分担課題としてどう設定するか。 4.報告者、話題提供者が突発事故で欠席しても、いつでもピンチ・ヒッターになれる条件をどうはぐくむか。 5.発言する自由と発言しない自由を「ニュース」はどう保障するか。その固定化へのいましめとして。 6.「人間ミナ同ジモノデハナイ。」という前提のうえに、分担課題に集中し、文教研課題を持続して追跡するために、「ニュース」は何をしたらよいのか。 |