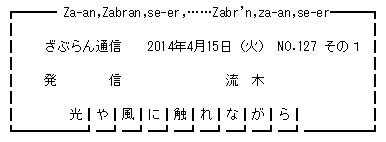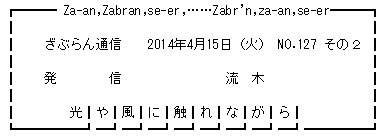| |
|
|
|
| |
≪ リンクされているHP・ブログから ≫
|
|
| |
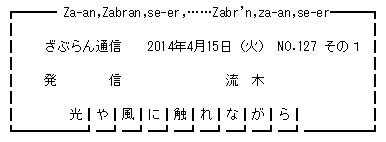 |
|
| |
むくろをはたとなげうちぬ 流木
◆ 「新選・百人一首」から
村上春樹の短編が載っているといって妻が近所のコンビニで「文芸春秋」の2月号を買ってきた。こうした総合月刊誌はたいてい通院している医院の待合室で読み、あまり買うことはない。
この号には<代表的日本人の「新選・百人一首」>という企画誌面があり、これが思いがけなく面白かった。4人の現代歌人が、明治以降の政治家や思想家、作家などいわゆる専門歌人でない百人の、それぞれ一首を選びまとめたものである。
たまたま森鷗外の歴史小説を再読していたこともあって、その中の3首にとりわけ興味を引かれた。鷗外は大逆事件を契機に、過去に材をとった作品を多く残している。それでこの3人の、これらの歌に吸い寄せられたのだった。
* さながらに猟矢(さつや)遁(のが)れし雁ひとつ
二見ヶ浦にわれ落ちてこし 明治42年 幸徳秋水
* 斑駒(ぶちごま)の骸(むくろ)をはたと抛(なげう)ちぬ
Olymposなる神のまとゐに 明治42年 森 鷗外
* 天地(あめつち)をくつがへさむとはかる人
世にいづるまで我ながらへぬ 明治43年 山縣有朋
後に<冬の時代>と呼ばれる明治末年の時代状況を反映したような、それぞれの歌である。
◆ 事件前年、鷗外の歌
大逆事件は、絶対主義天皇制国家のもとで性急な解放を求めた宮下太吉ら数人による天皇暗殺計画を口実に、これとは無関係であった社会主義者や無政府主義者を「大逆罪」に問い、反体制思想を萌芽のうちに摘みとろうとした明治43年の捏造(デッチアゲ)事件であるが、山縣はそれを推し進めた明治の元勲であり、秋水はこの罪を負わされて処刑された思想家であった。
秋水が捕まる前年に詠んだ歌について、選者の馬場あき子は「<猟矢遁れし雁ひとつ>に実感がこもっていますね。単なる比喩として読めません。本当に切羽詰ったときに出てくる表現だと思います」と言っている。
また山縣の歌を、選者の岡井隆は「山縣は当時72歳ぐらいで<自分は維新の功臣としてやってきたのに、秋水みたいな連中が出てくるまで長生きしちゃったよ>と嘆いている」と解説している。
そして鷗外の歌について、岡井は、「Olymposなる神」とは当時文壇の主流であった自然主義文学のことで、その連中への批判をこめて馬の死骸を投げつけたということだ、と述べている。
専門家によれば事実はそうなのかもしれないが、しかし私には単なる文壇批判にとどまらない鷗外の、この時代への苛立ちをそこに感じてしまったのである。
当時社会を覆っていた閉塞状況は、翌年大逆事件を生み出すのだが、鷗外は作家的感覚でその状況を撃ったのではないか、そんなふうに思ったのだ。
さらにまた、舞台はオリンポスだが、日本神話のスサノオがアマテラスへ為したかの乱暴を私にイメージさせたからでもあった。それにしてもこの表現は激しい。
◆ 「かのやうに」での思索
明治43年5月大逆事件の検挙が始まり、6月には秋水が逮捕された。
鷗外、このとき48歳。3年前、陸軍軍医総監の任につき官僚としてその地位を極め、また山縣を中心とする歌会・<常盤会>を設立するなど政府のブレーン的存在のひとりとみられた。
しかしその一方で、自宅において<観潮楼歌会>を主催し、石川啄木や北原白秋、斎藤茂吉などを招いて新しい思想の交わりを見守った。また文芸誌「スバル」には「沈黙の塔」「食堂」など社会主義や無政府主義に触れた作品を載せたりもした。
こうした「二つの顔をもったヤヌスのような」(森山重雄)鷗外について、岡井も、この「文春」の誌面で「なかなか食えない人です」といっている。
食えない人かどうかは別にして、確かに鷗外は、自身その<社会的立場>と<学問で探求して得た認識>とのあいだに、越えることの難しい溝をみていたと思う。それは苦しく自覚せざるを得ない矛盾であった。
この矛盾を小説で思索したひとつが事件2年後執筆の「かのやうに」である。
主人公の秀麿は生涯の仕事として日本の歴史を書こうと考えている。しかし「神話と歴史との限界をはっきりさせずには手がつけられない」のである。
天孫降臨から明治のこの御世までの歴史をどう書くかという問題である。その際、秀麿にとって「神話が歴史でないと言明することは良心の命ずる所」である。
しかし、この良心に従うことは、神話をバックボーンにした天皇制国家の中ではいわゆる「危険思想」につながる。
秀麿は五條子爵家の跡継ぎであり「皇室の藩屏(守護)になるよう」期待されている人間である。その人間が「神話は歴史でない」と言明するのは難しい。
その解決に、秀麿はファイヒンゲルの著書『かのようにの哲学』の考え方を援用しようと考えるのであった。かつてベルリンに留学した折、そこでは学問をした教養人が、信仰がないのにあるふりをしたり、宗教を認めないのに認めるふりをしていることの多いのを知った。「あるかのやうに」ふるまっているのである。
それを理論化したのがファイヒンゲルの哲学だ。その理(ことわり)を秀麿は友人の綾小路にかいつまんで話した。
・・・人生で価値あるものはすべて「意識した嘘」の上で成り立っている。理想だの、自由だの、霊魂不滅だの、義務などは存在しない。その無いものを有るかのように考えなくては、倫理は成り立たない。つまり「かのやうに」という仮定の上に社会は成立しているのだ。
この理論を援用すれば、わが国の「お国柄」と矛盾しない歴史学が構築できるのではないか、というのである。いわば、神話を事実で「あるかのやうに」扱おうというのであった。
ところがこれを聞いた画家は、それは駄目だという。
神話の実在を信じる人々に、神話は「嘘」だが、それを前提に国史を「尊敬しろ」といっても納得しないだろう。「僕のかいた裸体画を一枚遣って、これを生きた女であるかのやうに思へといっても納得しないのと同じだ」と反論される。
いわば、秀麿の歴史学は「お国柄」と矛盾しないどころか、国の統治大系を破壊する、という指摘でもあった。
それではどうするか?
画家は、そんな問題は「思わずにゐる」か、「極めずに置く」のだという。絵を描く上で不自由はないからだ。
しかし、歴史を書く人間である秀麿はそうはいかない。「真面目にやろうとすれば八方塞がりになる職業だ」と嘆く。
その嘆きに、画家から「それならなぜ、突貫して行く積りで遣らない」と激しく批判される。しかし秀麿は、ただ黙して佇んでいるばかりであった。
小説は、次のような描写で閉じられていく。
<・・・二人は目と目を見合はせて、やや久しく黙ってゐる。山の手の日曜日の寂しさが、二人の周囲を依然支配してゐる。>
この秀麿の沈思する姿に、私はこの国のこの時代の閉塞状況を、実になまなましく感じさせられた。秀麿の苦悩と思想が、そのまま鷗外のものではないだろうが、鷗外の胸中、いたく察せられた。
ここには、もう「神のまとゐ」に「斑駒の骸を抛つ」ような激しさはない。
◆ 「歴史小説」・その強靭な作家精神
そうした激しさはないが、しかし鷗外の作家精神はやはり強靭だと思った。
それは作中、主人公の秀麿を矛盾の前で沈黙させてしまった鷗外だったが、
一方明治国家の統治システムを揺るがしかねないような、まことに重大な考え方を秀麿に語らせてしまってもいるからある。
鷗外はこれを、平然と、といったら少し言い過ぎかもしれないが、あえて意識してやっているように、私には感じられたのである。
もしかすると鷗外には、考えあぐねた果てに生じる疑問を、その立場の中に閉じ込めて不問に付してしまうことのできない気質があったのかもしれない。
ただこの<冬の時代>、それを大きな身振りでぶつけることができない中で、鷗外は、身振り小さく、しかししたたかに、作品の中で疑問を問い質していく道を選んだのだと思う。
むしろそれは作家の姿勢として強靭ではないだろうか。
そしてこの強靭な作家姿勢がかずかずのすぐれた歴史小説を結実させていくのを、私たちは見ることができる。
例えば、「最後の一句」に描かれたような、静かではあるが、鋭利な言葉で奉行に対峙する<いち>という少女の造形、また「高瀬舟」の、奉行の決定に疑問を抱く庄兵衛という同心の造形など、まさに「神のまとゐ」にむけて、強靭に問い質していく文学が創作されていったのである。
◆ 陽気のいい4月なのに
今月は、初めて眼にした鷗外などの短歌に興味をもって書き出したら、ついついリキんでしまって、陽気のいい気分のほぐれる4月なのに、ちょっと読むのに骨の折れる、堅苦しい通信にしてしまったようでありました。
|
|
| |
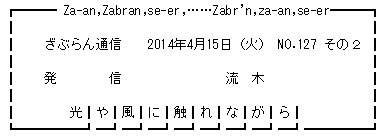 |
|
| |
「ぢいさんばあさん」(鷗外)を読む 流木
◆ 野暮だと知りながら
この「通信」の127号<その1>で、鷗外の短歌にふれた。
ちょうど鷗外作品を読み返していた時だったので、つい力がはいってかたい話になってしまった。
それを気にしていたくせに「ついでだから」とケチな根性が生じてこの号には<その2>まで付け足した。サラッといかない野暮なタチのだ。
で、ふれたかったのは「ぢいさんばあさん」という小品である。
◆ 作品のストーリー
この作品はときどき歌舞伎で上演されるので芝居好きにはよく知られているらしい。「罪を負った夫が許されるまで辛抱強く待ち続けた妻の話です、よね」とか、「37年間も会うことが許されなかった夫婦がそれぞれを思いやり、再会をはたしたという夫婦の情愛話でしょう」と、聞かされている。
鷗外の原作がどう脚色されているのか、あいにく私は見ていない。
芝居好きの方からその話を聞きながら、事柄としてはそうなのだろうが、私が味わっている鷗外のそれとは少々印象が違って感じられた。
鷗外の簡潔な文体にゾクゾクしながら読んだのだが、いまそうした文体の妙には触れないまま筋を語るのはちょっと気が引けるが、気軽な通信、とりあえず私のとらえた内容として、以下に紹介したい。
・・・文化6年の春遅く、麻布のある屋敷に上品な老夫婦が移り住んでくる。
この二人の「仲の好いことは無類である。近所のものは、若しあれが若い男女であったら、どうも平気で見ていることが出来まい」と云われるほど、むつまじい。
その老夫婦の妻るんに、年の暮れになって将軍家から褒賞が下された。世間はおどろく。褒賞の理由は、流配の境遇におかれた「夫のため、貞節を尽くした」ことへの「思し召し」だという。まさに体制を支える儒教道徳の手本となる女として栄誉を授けられたのである。
いま市井の片隅で静かに暮すこの夫婦、実は過去に過酷な運命があったのだ。
るんの夫・美濃部伊織は京都在勤中に刃傷沙汰を起こした。相手の意地悪い態度への立腹とはいえ殺すに至った刃傷は許されない。「心得違いのかどをもって」厳しい処罰が下された。
伊織はこれを覚悟して受けとめた。
しかし、妻のるんの立場からすれば、夫の配流、お家断絶等、この突然の処分はどのようなものだったろう。るんが凛とした覚悟でこれを受けとめたことは伺えるが、夫よりはるかに過酷な結果になったのではなかろうか。
家に残された夫の祖母の介護や死のみとり。とりわけ5歳になる嫡男の病いとその死等々、家を守るその日常の、女のやらなければならないことを忍耐強くよくやり遂げてはいくのだが、これは配流先の夫の苦労の比ではない。
そして彼女は、祖母と息子の死を弔うと、躊躇せず「一生武家奉公しよう」と決意したのである。<自活の道・自立の道>を選ぶのである。
親類に頼んで奉公先を探してもらい黒田家に雇われた。この間、るんは給金の中から寺へ金を納め「美濃部家の墓に香華を絶やさなかった」のである。
彼女は、親類の情けで生きていく道を絶ち、みずからの暮らしを立てていく算段をつけたのだ。
<経済的自立>であった。これはまた<精神の自立>でもあったろう。
そして31年間を黒田家に仕えた後、隠居を許され故郷の安房に帰った。その翌年、夫伊織が罪を解かれ江戸へ帰ることになった。
「それを聞いたるんは、喜んで安房から江戸へ来て、龍土町の家で、37年振に再会したのである」と、この小説は結ばれる。
「ひどく夫を好いて」いるるんの行動は、ここでもためらいがない。
読み終わってみると、このるんという女性の一生を「耐え忍んで待ち続けた女」だとか、「夫に貞節を尽くした女」というイメージだけでくくってしまうのは、どうも落ち着かない。
自活した女性が、やるべきことをきちんとやって、背筋のばして生きた、そういうイメージとしての「るん像」が、私には見えてきたのである。
◆ 女性像の系譜を勝手に想像
この作品は『一話一言』(大田南畝)などをもとに、大正4年『新小説』に発表された作品なのだが、「女は自活よりも良い所へ嫁すことが幸せ」という考えが支配的であった大正期に、こうした女性を見いだして創作したところがおもしろいと思った。
また勝手な想像の楽しみで、るんの精神系譜を他作品の中に探った。
その少女期を、父の助命のために沈着冷静に、しかも敢然と行動を起こした「最後の一句」のいちに重ねてみた。
中年期は、これもまた冷静果敢に腰巻ひとつの裸体で、沸き返る湯を三人の恐喝者に浴びせて、夫の危機を救った「渋江抽斎」の妻・五百(いお)に重ねもした。
鷗外作品の女性像をたどってみるとおもしろい。
陽気のいい4月の、付け足し<その2>の通信です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔ざぶらん通信〕
作 者:流木
編集者:風間加勢
発行日:毎月15日発行
ご意見、ご感想は掲示板「浜辺の語らい」にお寄せ下さい。
http://www.geocities.jp/ryubqu88/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
|
| |
(現在リニューアル進行中)
http://www.geocities.jp/zabran_news/index.html |
|
| |
http://archive.mag2.com/0000119440/index.html |
|
| |
|
|
 ∥リンク集-エッセイ・画像∥リンクされているHP・ブログから∥ ∥リンク集-エッセイ・画像∥リンクされているHP・ブログから∥ |