(「文学と教育」誌上に連載された10回にわたる「国語教育講座」の中から、その第8回の記事を掲載した。)
は じ め に
自分の中にある解釈学の“シッポ”を、どうやって断ち切るか、そんなことを考えながら本誌一三二号掲載の「文芸認識論の諸問題」を読む。冬の合宿研究会に参加しており、話し合いの流れはつかんでいたつもりでいたが、こうして整理されたものを読むことで、あらためて、文芸認識論のかかえている今日的課題の大きさに気付かされる。
私自身の文芸認識論を確実なものにするために、ここで論じられていること、例えば、科学分類論、内容と形式、 科学の対象・文学の対象等々について、解釈学のそれと対比して考えてみることにした。石山脩平『教育的解釈学』の記述に限定してのことであるが、そこに示されている概念を批判できるだろうか。解釈学批判を前提にしたノートの段階に終わるであろうが、とにかくやってみようと思う。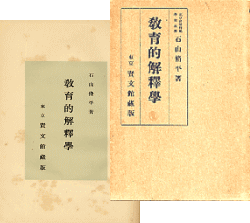
どうして『教育的解釈学』(昭和10年刊、以下『解釈学』と略記する)をとりあげたのか。「解釈学上の諸問題を教育の視点から統整し体系づけると共に、それを教育の実践原理にまで具体化すること」(序言)をめざし、その第三篇に示される三読法の定式化が、長い間、そして今日も、変形した形で国語教育の底流となっているからである。
「序言」から、もう少し引用してみる。「解釈学への関心が私(石山脩平氏)の心に芽生えたのは、約十年前であって、その頃初めて教育に志した私は、当時の流行思想であった精神科学派の所説に先ず接触し、就中ディルタイやシュプランガーに強く惹きつけられた。そして、この学派の中心問題が『理會』という精神科学的認識方法に存することを知り、これを教育の実践領域に適用したいとの念願を心ひそかに抱いた」云々。『解釈学』に、ディルタイ等の生哲学者の諸説の引用が多いのは、こうした理由からであろう。
世代形成過程に、解釈学で訓練されたか否か、その後の“シッポ”と大いに関連してくると思う。世代形成過程に出会う解釈学に、ディルタイ等の生哲学がどのように適用されているのか、私には興味のある問題である。
今、私が手にしているのは、昭和14年版の『教育的解釈学』である。昭和10年に初版発行以来、廿五版を重ねている。
因みに『解釈学』の目次をぬきがきしてみよう。解釈学として、一つの体系を持ったものであることが、うかがえよう。
『教育的解釈学』
第一篇 理會・解釈及び解釈学の意義
第一章 理會の意義/第二章 解釈及び解釈学の意義
第二篇 解釈の対象
第一章 文の表現過程/第二章 文の構造及び性格
第三篇 解釈の方法
第一章 解釈方法上の諸原理 形式主義と内容主義 対象的解釈と心理的解釈 客観主義と主観主義/第二章 解釈の実践過程 解釈過程 本文批評 解釈の補助手段 通読段階の任務 精読段階の任務 味読(鑑賞)段階の任務 批評段階の任務 人格及び文化財一般の理會過程
第四篇 解釈学の可能根拠及び妥当性
第五篇 解釈学略史
第一章 古代・中世解釈学/第二章 近世解釈学・近世前期解釈学 近世後期解釈学 現代解釈学 日本解釈学略史
十数年前、はじめて『解釈学』を手にした私は、第三篇を中心に目を通した記憶が残っている。私の関心・批判の中心は、第三篇の定式化されたものに向いていたようだ。
今回は、この書の冒頭から、一・二篇を中心に考えてみたいと思う。教育的解釈学という一つの体系の、その原理となる部分について、検討する必要を感じているからだ。
まず、気になるのは、科学分類論の上から、「精神科学」という分類についてである。
科学分類論にふれて
「文学と教育」掲載の「文芸認識論の諸問題」で述べられていることを辿ってみよう。 「弁証法的唯物論の視点をとる限り、科学分類論が科学論 として決定的な問題である。」
「われわれは、自然と社会とは対立物だとは考えない。むしろ、自然の発展として人間社会がある。一本の基本のルー卜に立って〈自然科学〉と〈社会科学〉という分類を考える。」
「ところが、リッケルトやディルタイの場合だと、人間の生活、社会は、自然科学の方法では追跡できないから、そこは、別の方法意識で分類しなくてはいけないということで、文化科学や精神科学というジャンルを設定する」云々。
分類のための分類でなく、どういう立場に立つ科学論かを考える上で、科学分類論が重大な意味を持つことに、思いを新たにした。十数年前には、余り気にならなかったのだが、今回読み直したとき、「精神科学」という言葉が、すでにその序言から使用されており、本文中にもしばしば使われていることに気付かされた。
「解釈」は、精神科学という立場に立つことから生まれる概念であろう。解釈について『解釈学』ではどう説明されているのだろうか。
「体験は生命の内化であり、表現はその外化であり、理會は他人によって外化された生命を自己に於て、内化すると共に、自らの内に潜める生命を顕わにすることであって、内化が同時に一種の外化を兼ねた作用――この意味に於いて内化と外化を総合せる作用である。斯く
してディルタイの考えた如く、体験と表現と理會とは精神生活が辿る不断の循環路である。」 「解釈とは、この循環途上の一領域をなせる理會の一種であって、特に永続的に固定させる生活表現、就中文学による表現を理會することであり、解釈学とは解釈の方法を究明し、その可能性を基礎づけ、その普遍妥当性を限界づけることである。」 「理會の言語としての
Verstehen は元来、日用語と しても学術語としても甚だ多義に用いられて来たが、それを特定の一義的な学術用語として用いられるに至ったのは、主としてディルタイの功績である。」 「ディルタイによれば、自然を要素に分析し仮説を媒介として、それ等の要素を因果的関連に構成するのは、自然科学に固有な説明方法であるが、精神科学は精神生活をば、本原的に全一的意味関連に於いて与えられたものとして、直接に追体験するのであって、これが即ち理會である。」 「広義に解釈とは、体験の永続的・固定的表現たる絵画・彫刻・文献等の理會を指す。」 「然しながら、更に厳密には、解釈とは狭く文献の理會のみを意味する。言語は体験の内容を限定し且つ第三者に伝える機能に於て最もすぐれたものであるが、その言語を文学と言う表徴に托して固定化し永続化したものが文献である。」 「ディルタイの言える如く文献のみが人間の内的生活を最も完全に、残りなく且つ客観的に理會し得べき表現であり、ここに精神生活及び歴史の理會に対する文献の測り難き重要性がある。それ故に文献に保存されたる人間生活の遺跡の解釈は理會の技術の中核をなすものである。」 (『教育的解釈学』)
生哲学の諸説が時に羅列的に引用されており、要約がむずかしいので、中心的部分と判断した個所を引用することにした。(引用部分の漢字・かなづかいは現代的用法にあらためた。但し、理會の會はそのまま使用した)また、解釈の言葉による記述の実際を知る上でも、参考になると思ったからで
ある。
やはり、自然科学と精神科学は対立するものとして位置づけられている。精神科学と位置づけることで、決定的マイナスとなることは何か? 自然科学と社会科学に共軛する基本ルートとは何か? 自明の理であるはずなのであるが、私には、やはりノートして確かめる必要がある。戸坂潤の整理に学ぼう。
「精神科学としての哲学は、対象を解釈し理解し、意味づけ性格づける。哲学の対象が、プロパーな意味に於ける実在=現実的存在ではなくて、第二次的な言わば高次の対象である処の表現 であるという見地が横たわっていた。歴史的社会的存在はこの哲学の対象となるとき、凡て表現という資格を有つのである。無論表現は之を説明することはできない。解釈し得るだけである。」 「観念論の根本特色の一つは、それが存在の解釈だけを目的とする哲学体系=方法だということだ。」(戸坂潤『料学論』一)
精神科学は、実在の認識ではない。「歴史的社会的存在は、この哲学の対象となるとき、凡て表現という資格をもつ」という指摘によって、そのことが明確になった。
弁証法的唯物論の視点をとる限り、精神科学という分類をしない。一本の基本ルートに立って〈自然科学〉と〈社会科学〉とに分類する。この場合の、一本の基本ルートとは何か?
「自然と歴史的社会とでは無論別な法則が支配する。だがそれにも拘らず、この二つの世界は自然史的発達の過程を介して、同一なのだ。それ故社会科学に於て正当に使われ得る根本概念=範疇は、自然科学の夫と決して直接に同じでないにも拘らず、一定の約束(いわば翻訳の文法)を介して、相照応せざるを得ないものなのである。(略)唯物論に固有な技術的範疇(唯物弁証法)は、社会科学の範疇と自然科学の範疇とに対して、共軛関係を持つことが出来ればこそ、初めて『技能的』であり得たのだ。」 (前出『科学論』)
自然史的発達の過程について、『科学論』では詳述されているが、ここでは、意識を物資的基礎との関わりで説明 している個所を引用する。「意識は脳髄という生理的物資の未知ではあるが或る一定の状態乃至作用だと考える他に現在道はない。」云々。この仮説がその後実証されたことを私たちは知っている。「第二信号系の理論は、認識の反映論的な機能をそれの大脳生理学的な基礎づけにおいて追求する」(熊谷孝『言語観・文学観と国語教育』)。ここで考えられ
ている反映は「媒体による反映、二重の媒体による反映(信号の信号による反映)」のことである。
このように整理してきたとき、『解釈学』の発想、例えば「体験の永続的・固定的表現たる文献」云々は、第二信号系の理論以前であることがわかる。言葉刺激に対する反応は、受け手の側の主体のありようによって規定されてくることなど、何ら問題にされていない。「記号を記号として受けとめて解読していったときに、送り意図に、より接近していく形で、受け手はわかるのだ、ということ」(本誌一三二号・前掲記録)なのである。第二信号系の理論が究明される以前の理論であるからと言って、それが過去の理論になったということではない。「文芸認識論の諸問題」での次のような指摘を見落すことができない。
「送り内容・受け内容という概念は、心理学者のがわから提起された問題でしたね。最近はまた、情報理論のほうから出て来るわけです。送り内容と受け内容が一致しなければいけないと……。そこでコードがどうのってこと。いつ・ど
こで・だれが・何を・どうした。これがはっきり送られてないから、受けるほうに混乱がおきる。そういうふうに情報理論につながっていく。」云々。
教育と基礎科学
『解釈学』には、五号活字の部分と九ポイント活字の部分があり、前者は「教育的解釈学の理論」、後者は「教育の実践に関する事例」が記述されている。例えば、第一篇第一章の九ポイント活字の部分には、「教育に於ける理會の実践と理論」という見出しで、次のようなことが記されている。
「クリークやペテルゼンが代表する教育科学の所説に従って、教育の本質をば社会の根本契機としての同化・順応に見出すとき、人が他人を理會し、また社会の文化を理會することがなければ、社会的同化順応は不可能であるが故に、理會は教育の根本条件となる。」
「然しながらこの重大な理會作用が旧来の教育に於て、必ずしも至当な方法を以て行われては居らなかった。」 「子弟に教材を学習させる方法が教材の種類に応じて異なるべきであるのに、自然的教材と精神的教材とが同一方法で学習せられたりすることが多かった。教育学が、理會作用に関する最近の心理的・哲学的考究等、新しい基礎科学に支えられることによって、精神科学的教育学としての特徴を発揮し、教育実践に新生面を与えつつある。」
(『教育的解釈学』)
精神科学的教育学は、まさに適応の論理である。そしてその材料となるものが、精神的教材、というわけなのだ。 『解釈学』で精神的教材としてとりあげられているのは、国語読本の本文である。その解釈の一例として、高等科用巻二第一課「農業」をみてみよう。
「『農業』に於ては、『斯く観じ来れば、農業は実に堅実にして幸福な職業である。』という末尾の結語として主題が与えられて居り、それが内容的に展開して、農業の堅実性に於ては第一節に身体の健康が、第二節に精神の健康が説かれてあり、農業のもたらす幸福については第三節に家庭の和楽が、第四節に趣味の豊富さが説かれている。」 (『教育的解釈学』)
昭和十年代に、こうした発想で農業がとらえられ、それをこのように解釈するということ。現実の問題の解決には何ら目が向けられていない。戸坂潤の、精神科学の対象は実在ではなくて、表現されたものである、という指摘が想起される。
それにしても、精神的教材という言葉にはなじめないものを感じる。どうして、このように短絡的にしかも矮小化 されてしまうのであろうか。
内容と形式をめぐって
「形式概念と対比的に用いられている内容概念については、あまりにも不十分なものを感じる。(略)せっかく〈文学的現実〉という概念を生んできた以上、形式概念との対に使われる内容という概念、使うことをやめたほうがよいんじゃないか。」(本誌一三二号、前掲)
内容と形式について、『解釈学』ではどのように記されているのであろうか。
「文は作者の体験を想化した所の個性的なる想内容が、特定の言語集団の一般的規則としての表現形式に於て客観化せられたものであるから、そこには内容と形式の二契機が総合せられている。然るにそれを解釈するに当って、先ず、何よりも形式を尊重する立場と、端的に内容を把えんとする立場の何れかに傾くことによって形式主義と内容主義とが対立する。」
「内容主義・文章法は、若干の難語句や文法的不可解には敢て拘泥せずに解し得た限りの形式を通して文の含む事象と主題と情調――要するに作者の想の全一的構造を端的に把握すべきことを要求する。一読直ちに文の生命に触れる底の『直覚』が尊重せられる。」
「が、直覚主義が卓越せる天才に於てでない限り、当人に於ては多くは独断的解釈に陥り易い。この危険を防ぐために専ら形式を尊重するのが形式主義・語句法である。語句の一義的意味や文法の一般的規約を忠実に辿って文章を解釈する限り、その解釈は普遍妥当性を、それ故にまた客観性を得るであろう。」
「その内容と形式との対立を止揚して、本来の一者に還元することによって、真にその生命を理會し得る。形式主義と内容主義との止揚は、『形象』の理會に究極する。」 (『教育的解釈学』)
芥川龍之介は、すでに大正13年に『文芸一般論』で、「文芸の内容は、言語を通じてのみその正体を示す」ものであること、つまり、内容と形式との不即不離の関係を述べている。それ以後に刊行された『解釈学』において、内容と形式とが、このように整然と二元論的にとらえられているのである。二元論的にとらえた上で、内容主義と形式主義との止揚、云々。論理に飛躍がありすぎる。
しかも、教育の次元では、内容主義――文章法、形式主義――語句法、という対応。どうしてこうした次元の問題になるのか、私にはよくわからない。解釈学の内的必然性において、こうした対応が成立するのだと思うが、文章法と語句法は長い間、国語教育界の論争点の一つであったと言う。
本誌一二四号で山下明氏は、『国語の力』(垣内松三、大正11)で垣内が提唱したセンテンス・メソッドについて今日的立場にたって批判を試みておられる。(「解釈学的国語教育の源流、『国語の力』」参照)そのセンテンス・メソッドに対して、『解釈学』は非常に高く評価して紹介している。「センテンス・メソッドが正しく行われる所では他の諸方法との対立に於てではなく、それ等を含むものとして行われるであろう。文に即して語句を棄てず、内容と形式とを『人格的生命の表現せられる作用の連続』として一元的に見て行かれる根本態度――私(石山)が弁証的止揚の境地として憧れているのもまさしくこれに外ならない。」
というのだ。ここまで論述されても、私には「止揚」の説明がなされた、とは思えない。「人格的生命の表現せられたる作用の連続」云々、に納得が行かないのである。
真に弁証法的な把握として、今、私の頭に浮かんでくるのは、次のような説明である。
「コミュニケーション・メディアの“メディア”のことですけれど、“伝えあい”によるお互いの体験の交換・交流をなかだちとする“媒体”のことです。ときとして、それはまた、そういう媒体を組み立てる材料――“媒材”のことです。たとえば、“ことば”は、人間相互の“伝えあい”のための有力な手段、媒体です。が、詩作品なら詩作品、小説作品なら小説作品というかたちで、つまりひとまとまりの文章表現として“伝えあい”がおこなわれるような場合、その文章の中にある一つのセンテンス、一つの単語などは、むしろ全体としてのその表現を構成する“媒材”だと、そういっていいわけでしょう。つまり、そういう意味での媒材――媒体としてのメディアと、媒材としてのメディアの区別です。」
「けれど、それも、弁証法的な把握による部分と全体という関係での媒材と媒体との違い、ということ以外ではありません。詩の表現というようなものを思ってみたら、その一語、一語が媒材であると同時に、媒体としてのおもみ を持ったものとして考えられることになるのですから。」 (熊谷孝『言語観・文学観と国語教育』)
弁証法的な把握による部分と全体という関係で、媒体と媒材をとらえるとき、国語教育界で長い間争点となっていた文章法、語句法という次元での対立を克服することが可能となる。
解釈学で言うところの内容、形式について考える場合、その汎言語主義としての性格を見おとしてはならないと思う。
「汎言語主義者にとっても、“ことば”は媒体であるが、それがたちまち実体に化ける。“ことば”でとらえたもの 、 “ことば”としてつかみとられたもの は、はやくも事物の等価物に転化し、仮象としての事物をこえた事物の本質、事物そのものに転化してしまう」云々(『言語観・文学観と 国語教育』)。それゆえに、「体験の永続的・固定的表現たる文献」ということになるのであろうか。そして、また、順序をおって、きちんと教えれば、一様に内容を理解させ得る、という考え方が成立するのであろうか。
人間の主体は白紙ではない。体験のありようによって、刺激に対する反応が異なったものとなる。刺激(文体刺激)に対するまっとうな反応を成立させるための、印象の追跡としての総合読みの発想が、私には重みをもって再確認された。
日常的な教室の中で
個々の概念をばらばらにとらえるのではなく、「そこでの中心的問題を見きわめ、基調となる概念(キイ・コンセプト)を確立する」(熊谷孝『芸術の論理』)必要がある。私たちは、このキイ・コンセプトを確立することをめざし、「ドラエモン・ポケット」を合言葉にしている。さまざまな概念をべつべつのポケットにしまったまま例会で発言すると、「ドラエモン・ポケットはどうしました?」と、きび
しく批判される。ノート、というつもりで書いてきたのであるが、ドラエモン・ポケットにする難しさを感じている。
が、毎日、教室での国語教育にたずさわっているはずの私が、授業を矛盾なくやるためには、ドラエモン・ポケットが要求されることになる。今模索している理論が、方法原理として有効であるか、否か、たえず意識的にとらえ直す必要がある。
三年ぶりに中学一年生の国語担当となり、今、『空気がなくなる日』(岩倉政治)をとりあげている。明日はどんな風に、生徒との対話が進展するのか、わくわくする気持でいる。今回の授業を通して、私自身『空気がなくなる日』を再発見することができた。何を再発見したのか、と問われると困るのであるが。それは、すでに文教研の共同研究の中で、指摘されていることなのである。が、今まで私自身は、それをどこか、アタマでとらえていたのだな、と今回気付いたという、それだけのことである。アタマでとらえるのと、感情ぐるみとらえるのとでは、文学の場合、決定的な違いとなろう。
『空気がなくなる日』がどんな作品であるかは本誌一二三号掲載の拙稿を参照願いたい。その中に、私自身『文学序章』(熊谷孝)から、次のことを引用している。『空気がなくなる日』は、「子供相手の創作であるだけに、作者の技術的な苦心にはかえって並々ならぬものがあるのだが、それだけにまた表現そのものはきわめて単純化されているし、子供の実感に訴えてぴんといくような、そういう角度からの、要点をつかんだ問題の捉え方がなされている」云々。
今回の私の再発見というのは、この作品が「子供の実感に訴えてぴんといくような」文体として実現している、と いうことに関わっている。
内容・形式を二元論的にとらえるのではなく、文体刺激に対する文体反応として、読者が再構成することで文学的現実をとらえる。音読しながら、印象の追跡をする。みんなで補いあって、イメージをつくって行く。
第三パート。あいにくの出張で自習となる。第三パートを中心に、第一パートから第三パートまでの印象を記すことを課す。翌日、それに目を通していて、何年か前に授業したとき、こうした反応はあったかしら、と思う。
「うちのものがみんな死んでいくのに、おらだけ、生きのこっておられるかい。」 「子どもは、その日のまえのばんから、母親にしがみついて、あけがたまで、まんじりともしなかった。……それでも、うちじゅうのものが、しっかりとだきあって死ぬんなら、つらいけれど、なんだか、いいような気もするな……。」この個所を引用している生徒が非常に多かった。そして、今の子ども(自分を含めて)と違う、今の子どもは自分のことしか考えないのではないか、ということや、この家族は貧乏だけれど、家族のきずなが感じられる、いい家族だな、という感想がつけ加えられている。「おらだけ、生きのこっておられるかい」という子どもの言葉でなければとらえられないもの、こう言い切った子どもに感動している。
今は家族が何となくばらばらだ、ということを書いている生徒もいた。子どもの言動がイメジャリーにつかめることによって、自分自身の生活がつかみ直されるきっかけが生まれたようだ。自分もきっとこう言うであろうと書いた生徒を含めて、自分の生活に、何かショックを感じたようである。ショックを感じさせるような文体として実現している、と言ってよいのだろうか。「かわいそうにな。おまえら、こんなうちへ生まれずと地主のだんなのところへでも、生まれたらよかったのに」という親の言葉に対する評価は分かれていた。子どものことを思っている親だと、とらえる生徒もいた。地主制度の中の、小作の地主に対する感情は、無媒介では、とらえさせられない。が、この作品では、すぐその後に地主の子ども大三郎が登場する。大三郎に対する子どものくやしい気持は、実感できるようだ。この大三郎の描写を通して、その側面から地主制度の中に生きる人間のメンタリティーが描けている、という気がする。「おらだけ、生きのこっておられるかい」と言った子どもへの感動を軸に、この作品の印家が追跡されていったように思える。うわさだとわかった後、この子ども一家は地主からひどい仕打ちを受けなかったのか、と心配する生徒の発言から、三パート、四パートの印象が、文章に即して再度、追跡される。
授業を通して、何を、どんなふうに、私自身、つかんだのか、記すのが目的であったのに、そこまで行かないうち に筆をおかねばならなくなってしまった。
|