|
筑摩書房刊「国語通信」132 1970年12月号掲載 |
|
| 文章意識をはぐくむために---
|
|
「作文はアタマだ……」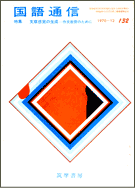 院生だった時分、私立の中学校――一九三〇年代末のことだから、男の子だけの旧制の中学校である――の非常勤講師の口が見つかって、週に二日、文法と作文を教えに行くことになった。この学校では、橋本文法で教えることにしているから、そのつもりで準備してくれ、と初対面の国語漢文科主任の先生が言った。「それから作文だが、これは、ひとつ、きみのやりたいようにやってみてくれたまえ。要するに、ちゃんと文章が書けるような生徒にしてくれればいいんだから。」云々。 ちゃんと文章が書けるような生徒に……そりゃ、そうだろうが、しかしいったい、どうすれば生徒諸君が「ちゃんと文章が書ける」ようになるのか、それが、こちらにはわからないのである。だいいち、わたし自身、文章を書くということが大の苦手で、中学生時代、作文という科目は亀の子方程式――化学が嫌いだったのと同じくらいに嫌いだった。 その、わたしが、選りに撰って作文の教師に――である。 どうしたものか? ……いくら考えても、妙案が浮かばないのである。妙案というとあれだが、方法がつかめないのである。さらに言えば、原理がてんでわからないのだから、方法を探るにも探りようがない、ということなのである。中学生のころ、隔週に行われた作文の時間に原稿用紙が配られるときの、あの憂鬱な気分がよみがえって来て、今度はその用紙を配るのが自分だということになるのかと思うと、「被害者変じて加害者となる」うしろめたさ のようなものが心にうずき始めるのである。 どう見てもウルサ型であるらしいあの教科主任が、作文の場合に限っておまえの自由にやれと言ったのは、それは夫子(ふうし)みずから作文指導には手を焼いているということの結果ではないのか、という下司(げす)の勘ぐりまで心を去来し始めるのである。そこへもってきて、その学校にいる同窓の先輩から情報がはいった。「要するに作文という科目は、国語科教育の中で教師がいちばん負担の大きい科目である。なにしろ、毎週、百人分、二百人分の作文を読んで添削したり批評を書いたりしなければならない。そこで今年度は二人の非常勤を入れて、専任の先生たちは負担の軽減をはかろう、ということになった。きみの役割は、つまりそれさ。」というようなことであった。 うんざりした。就職を見合わせようと思った。せっかく下宿代ぐらいにはなりそうな収入の口を振るのは辛いけれど、しかしいやなこった。推せん状を書いてくださったK教授のお宅へそのことを言いに伺った。 「まあ、やってみるんだね。やっている中に興味が出てくるかもしれないし、方法も見つかって来るだろうよ」と言って、先生は次のような話をしてくださった。 きみも、ただ、文章の書き方を教えるとか、教えなければならないというふうに考えないで、生徒が自分の考えや感じたことを文章にまとめるときの相談相手というか話し相手になるぐらいのつもりで授業に取り組んでみたらどうだ。なにも、書くこと自体を教えなくたっていいんだ。作文も、女の人の家庭料理と同じことでね、娘時代にいくら料理法を仕込んでみたところで、当人のアタマが固いと、実際の家庭生活には役に立たないような、つまり毎度のことで鼻についてしまって食欲の起らないような物しか、こしらえないよ。 反対に、正式に調理法は習わなくとも、当人のアタマが正常なら、結構栄養価も高いし、時おり目先をかえて家族の味覚を楽しませるような料理を作るようになるものだ。作文も、アタマだね。作文教育というのは思想教育だよ。アタマが確かで、筋を通したものの考え方をしている人間は、筋の通らないような文章は書かない。今の学校は生徒のアタマがおかしくなるような教育ばかりやっているというか、やらされているわけだから、きみも、その辺のところを考えて、生徒たちのいい兄貴になってやるんだな、云々。 作文の指導法について決して納得いったわけではなかったけれども、現にわたしたち学生のよき兄貴――いや、よきオヤジであるこのK教授から、「お前も、ひとつ、生徒たちのいい兄貴になる努力をしてみろ。」というふうに言われると、そちらのほうで士気(?)を鼓舞させられてしまって作文教師、というより学校教師になる決心をした。「なにも、書くこと自体を教えなくたっていいんだ。生徒の思考方法に対して責任を持ち、生徒たちが自分の考えや感じたことを文章にまとめるときの親切な相談相手になれればいいのだ。」というK先生のことばが、その時わたしの心のささえであった。 言いたいこと、言うに価すること 最初の授業で、きみたちは作文が好きか、と聞いてみた。三、四人、優等生然とした生徒が手をあげたが、あとは返事に困るという顔をしていた。顔を見合わせてニヤニヤしているのもいる。過去の自分の姿を見る思いだった。「当分、作文はしないから安心したまえ。」と言ったら、わぁーッと歓声があがった。 「その代わり、みんなで交替に感想発表をやる。新聞に書いてあることについてでもいい、本で読んだことでもいい、直接見たり聞いたりしたことでもいい、この学校のことだっていい。むろん、自分のことだっていいし、何でもいいから自分の感じたこと、考えたことを毎週作文の時間に話すんだ。替わり合って、一人残らずそれをやるんだ。意見が違ったら、そこでお互いに討論するんだよ。」と、そう言ったら、また「わぁーッ」と涌いた。 誤解のないよう。二度目に「わぁーッ」と涌いたのは、それは困るというのと、しかし毎回一時間原稿用紙とにらめっこさせられて、六百字、七百字のマス目を埋めさせられるよりはまだましだ、という「わぁーッ」である。読者はすでにお見通しのように、わたしの狙いは、そういう感想や意見の発表、討論などのつみ重ねの上に、自分たちの言いたいこと、書きたいことを見つけて作文する気持を起こさせる、ということだったわけである。書きたいことの発見と言ったらいいのか、書きたいことのある人間に生徒を……というふうなことだったわけである。 太宰治が書いている。「私が綴方へ真実を書き込むと必ずよくない結果が起ったのである。父母が私を愛してくれないという不平を書き綴ったときには、受持訓導に教員室へ呼ばれて叱られた。『もし戦争が起ったなら』という題を与えられて、地震雷火事親爺、それ以上に怖い戦争が起ったらならば先ず山の中へでも逃げ込もう。逃げるついでに先生をも誘おう、先生も人間、僕も人間、いくさの怖いのは同じであろう、と書いた。此の時には校長と次席訓導とが二人かがりで私を調べた。」云々(『思い出』)。 つまり、この「私」の先生たちがやったような、生徒たちの真実を語る意欲、書きたいことを書く意欲を凋(しぼ)ませてしまうようなサクブン指導にだけは陥りたくない、と考えていたわけである。という以上に、書かずにはおれないことを書かせるということ、さらには、書くだけの意味なり価値のあることを見つけて書くようになってくれることを、あまり年の違わないこの弟たちに期待していた、ということである。そのための、感想や意見の発表に続く討論 (話し合い・相互批判)ということだった。 小島信夫も言っている。「私は文章というものを非常に簡単に考えている。つまり、言いたいことが、十分に言えているかどうかということだ。というより、言いたいことがあるかどうか、ということだ。」云々。しかし、その「言いたいことが大したことなければ、十分に言われたとしても、つまらないのだから、結局言いたいことがほんとうにあり、その言いたいことが、言うに価することであるかどうかということが問題となってくる。」云々(『一つのセンテンスと次のセンテンス』)。書かずにはおれないことを書かせる、書くだけの意味のあることを見つけて書けるようになることを期待する、とわたしが言うのは、つまり小島の指摘しているような意味においてだ。 ところで、上記の文に続けて小島は言っている。「それならば、言うに価することとは何であるか。本人がそう思っても、ただそれだけのことで、ハタから見て何でもないこともある。といって言うに価することかどうかは、言われた文章を見てみなければ分らない。」云々。 確かに、その通りなのだ。が、作文指導の方法の問題として、「本人」が有意味(有意義)だと思っていることを“書きことば”に託す前に“口ことば”に託して「言うに価することかどうか」を討論(相互批判)させる、という指導法をわたしの場合とり上げた、ということにほかならない。そういう操作を通すことでまた、ほんとうに言いたいこと、書きたいこと、書くに価することを発見させようとしたわけである。さらに次には、そのようにして身につけることの出来た現実把握の発想を書きことばに託し、書きことばを通す過程において(つまり現実の作文の過程において)自問自答する形で再検討させるというようなことを、やや図式的に考えていたのである。が、こうしたわたしの指導の発想には空洞がポッカリ大きな口を開けていた。 読むことと書くことと 空洞云々というのは、こういうことだ。少なくともわたしの目の前の生徒たちの場合、話すということと書くということとは別のことだ、ということである。何遍か実際に作文をさせてみて痛感させられたことだが、口頭による感想発表なり意見の交換の際に時おり示されるような、生徒たちのフレッシュな発想が、そこに実際に書き上げられた文章の上では凋(しぼ)んでしまっている、ということなのである。そこに実際にあるのは、ご時世向きの――というのは、日中戦争下の至ってご時世向きの――発想のカサカサした文章である。 それは、明らかに、彼らが自分たちの意見や感想をそっちょくに口にしていた時の現実把握の発想・発想法とは別のものである。が、それは、彼らが心にもないことを討論の場で口にしていた、ということではない。また、故意に意識して文章に嘘を書いた、ということでもないのだ。“書きことば”を通すことで(言い換えれば、習慣化された自分たちの書きぐせで書くことによって)またまた習慣化された思考の発想に結びついてしまった、ということのようである。つまり、飼いならされ身についてしまった生徒たちの文章感覚、文章意識のありかたに、一つ、大きな問題があったわけなのである。 彼らのそうした困った書きぐせ――文章感覚をもたらしているものは、さし当たって彼等自身の読書のしかた、文章の読み方、読みぐせだろう。さし当たり、それは国語教育全体の責任だろう。この点について、敗戦直後、大久保正太郎は次のように書いている。 「教室で、国語の時間などに、文学作品の切れはしが教えられることはあった。しかし、その大部分は、少年や青年の若わかしい心をとらえる生きた文学ではなかった。人間の、偽りのない精神や生活をえがいた、ほんものの文学ではなかった。生活する人びとの、なまなましい喜びや悲しみを、そっちょくに訴えた、力づよい文学ではなかった。かびくさい、老人じみた、上品に気取った、そうでなければ、国体の尊厳、日本のありがたさを頭から押しつけるようなものばかりだった。(中略)その上、教えかたもまた、文学のほんとうの読みかたとは、およそ違っていた。ことばの解釈だけに終わってしまったり、なかに盛られている考えかたや感じかたを鵜呑みにさせるだけで、その考え方や感じかたそのものについて自分たちの立場から考え、批評することなど思いもよらなかった。」(『文学への迷信』) 何か現在の国語教育の状況に通じるものがあるようだが、それはともかく、国語科の読みの指導ではまともな文章感覚・文章意識をつちかうような指導が行われていなかった、ということである。言い換えれば、教材の文章が示す発想と読み手(生徒)の発想とを、その文章のありかたに即して対決させるという、主体的な読みの指導がなされていなかった、ということである。つまりは、文体意識において文章感覚をはぐくむ、という文体的発想づくりの意識を欠いていた、ということにほかならない。 で、そういう状況のもとにあっては、ただ討論させたり書かせたりということではどうにもならないので、いつかわたしの作文教室は、岩波文庫や岩波新書所収のエッセイや小説などをテキストにした、読むことで文章意識をはぐくむ、半ば読書会の格好のものに変わって行った。論理的でイメジャリのある文章――そういう文章を通してでなければつかめない、みずみずしい発想、ことばの選択、そういう言表の世界をくぐり抜けることの中で、自分自身に書かずにはおれないことを書く、という営みにおいて「言うに価する」ことも書けるようになって行くのだ、と今でも思っている。
|