|
三省堂刊「国語教育」12-3 1970年2,3月号 掲載 |
|
| イメージの変革をこそ---
|
|
| ■――思考と想像そしてことば 読みの指導で思考力をつけさせるためには説明文を教材に、また情緒(情動)・情操をつちかうためには詩や小説や随筆などの文章を教材として、という考えかたがある。あるどころの話ではない。それが現在の通り相場だ。この、通り相場というか常道を、あなたは疑ってみたことはないだろうか。 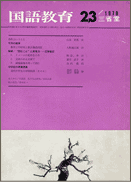 ところで、ここでの課題は、そういう世間なみの常識をこえて、(1)思考力を生徒たちの身につけさせるという目的に関して、文学作品の読みに期待できるのはどういうことなのか、というようなことである。あるいは、(2)文学作品の読みにおいて実現を期待される思考力というのが、どういう性質のものであるのか、というようなことである。さらにまた、(3)文学作品の読みを媒介にして思考力をはぐくむためには、どういう指導の発想がそこに必要になるのか、というようなことである。ここでの課題を、たぶんそんなふうに受けとめていいだろう。 課題をそういうふうに受けとめたうえで、一つ二つあらかじめ指摘しておきたいことがある。そのことがハッキリしさえすれば答えの方向はおのずから明らかになる、というような一、二の前提についてである。 前提の一つは、まず思考力ということについてである。 思考力、これは慣用語である。ことばの日常的な慣用としてそれが世間をまかり通っている、というだけのことにすぎない。個々人の思考が根源をそこに発する、というようなスタティックでサブスタンシャルな思考力というようなものは、どこにもないのである。 無用の――つまり、むだ な――観念論議をひき起こすことをさけて、その道の専門家の解説を引用しておこう。それもごく一般的な、通説にしたがって解説したというかたちのものを引いておこう。「いうまでもなく、思考も、思考力というような、なにか実体的なものから発する独自別個な作用ではない。心的活動の対象として、与えられる材料の種類によって、その刺激に対する反応のしかたが、知覚とよばれ、あるいは記憶といわれ、思考・想像などとよんで、特徴づけられるにすぎない。これらは、すべて、全体としての心的活動の部面であって相互に密接して関連している。したがって、思考を、それだけ別個に発達させることはできない。他の部面が発達することによって思考もまた発達する」うんぬん。(柴山剛「思考と発達」/中山書店刊『現代教育心理学大系』4所収) ここで確認しておきたいことは、次のようなことである。①思考力、思考力一般というようなものは、もともとありはしないのだ、ということ。したがって、②思考力というもの一般を予想して、その思考力をはぐくむにはどうすればいいか、というふうに考える考え方自体が狂っている、ということ。③実際にそこにあるのは、さまざまの次元における個々人の思考活動であり、そうした思考活動の反復によって習慣化され、ある傾向性をもつようになった各人の思考のパターンである、ということ。あるいは、パターン化したある思考の発想・発想法である、ということ。したがって、④指導の対象ないし目的は、どのような発想の思考方法を身につけさせていくか、という一点にしぼって考えられねばならないだろうこと。 前提の二つめは、読みの操作をもふくめてことば操作の機能的性質についてである。 最も up-to-dateなことばの基礎理論である第二信号系の理論のさし示すところにしたがっていえば、ことばがことばとして機能するのは、ことばの系(第二信号系)が運動感覚の系・行動の系(第一信号系)につながったときである。たとえば、ウ・メ・ボ・シという音声なりそれの記号としてのその文字が、ただの音声や記号としてではなく、そこに存在するそのもの を指示し、あるいはそこに存在しないにもかかわらず、梅干というまさにそのもの を視覚的、味覚的なイメージぐるみの観念として喚起して、「おお、酸っぱい」という感覚にみちびく。それは、上記の二つの系がそこにつながり、ことばとして機能した、ということである。で、その場合、この二つの系のつなぎ の役めを果たすのがイメージである、というふうにこの条件反射学の理論では説明しているわけだ。 そこで、この説明を前提にしていえば、イメージを伴い、イメージにささえられなければことばがことばにならない、ということになるのである。あるいは、ことば機能の生産性は保障されない、ということになるのである。したがって、“イメージづくり”という作業を積極的におこなわないことには、ことば操作の指導は生産的なもの、アクチュアルなものになりえない、ということになるのである。イメージづくり、それを読みの指導に即していえば、そこに与えられる教材の文章の文体的性質――文種 ではない文体 である――に対応して学習者のイマジネーション(想像)をかき立て、彼らの知覚を確かなものにし、思考を促す作業である。この作業は、そのことば操作の指導が、ことばの概念的操作に関するものであろうと形象的操作に関するものであろうと必要とされるわけだ。が、直接イメジァリの世界を対象として扱うという意味において、文学作品の読みの授業にあってはこの作業が根幹の作業となるわけである。 ■――かさなり合うイメージ 上記の二つの前提をふまえて課題をつかみなおすと、どういうことになるだろう。 まず、いえることは、文学作品――文学作品の文章――の読みの指導における思考のはぐくみかたは、すぐれた意味において想像(イマジネーション)に媒介されささえられた、思考の発想(発想法)の変革である、ということだろう。いいかえれば、イメージの変革による思考の発想の変革ということである。そこでは、新しいイメージづくり=イメージの変革ということが直接の目的なのであって、思考方法の変革(形成)ということは、いわばそれに伴ってやってくる、という格好になるわけだ。 もっとも、それは必然的、必至的にやってくる 、という意味である。現実や人間に対するイメージのほうだけが変わって、思考のしかたのほうはもとのまま というようなことはありえないのである。イメージが変化すれば、やがて観念のありようが変化するし、思考のはたらきを中心とした現実把握の発想のしかたそのものが変化するのである。むしろ、その意味では、イメージの変革による思考方法の変革というこの道筋が、旧い自己の思考のパターンを主体の内側から根源的に突きくずし突きやぶっていく、ノーマルな道筋だとさえいえるかもしれない。 が、それはともあれ、思考の発想の変革ということは文学作品の読みの場合、“あとからやってくる”という格好になるのである。この点をとりちがえた文学作品の読みや読みの指導は、文学作品を文学作品でないものに、つまり絵解きの対象にしてしまうのである。それを想像の対象としてイメージの世界に分け入ろうとすることの代わりに、妙にギクシャクした“思考”の対象物として文学作品を考えるものだからして、そういうことになってしまうのである。いま、読解指導というかたちで国語教室でおこなわれているような、まずその文章の表の意味 をつかんでから、次にはそこに隠されている裏の意味 をさぐる、というあの読みかたなどがそれだ。そこでは、文学作品を読むということはクイズを解くことである。クイズの答えが内容 で、それを要約したものがその作品の主題 だ、というわけなのである。うまくないな、と思う。 これは、そういうチャチな例ではなくて本格的な評論家の場合だが、岩上順一の『歴史文学論』などにもそれがあるのだ。この評論書というか文学史書というか、この書物の中の『羅生門』(芥川竜之介)論を部分的に引用すると、次のようなものだ。この作品は唯物論批判を課題としたものであって、「芥川は、下人の姿のなかに、当時のアナアキストの思想と行動とを表現」している。「かかるアナルヒスムは、それ自身の論理によって、それみずからを否定せざるを得ないではないか、と芥川は考えた。」この作品の「テェマは明白である。飢の前にはいかなる悪行も許される、という老婆の論理は、下人の行為によって逆用され復讐された。この下人の行為の中には一つの意味が含まれている。即ち、あらゆる人間は、飢の前には暴力的な行為にかり立てられるものであるということである。芥川は、当時の労働運動の根拠をこの下人の行為において設定したのである。それと同時に、老婆の形象の中には、このような暴力的行為の理論に対する否定が含められている」うんぬん。 つまり、完全な絵解きの姿勢である。岩上の眼には、小説・文学というものはすべて寓意によるものであり、したがって、それはおしなべて絵解きの必要があるものだとして映っているような印象なのである。しかし、絵解きの対象となったとき、文学は文学でないものになってしまうのである。 私は思うのだが、下人はけっして下人以外のものではない。しかも、その下人は、後にも先にもこの世にひとりしかいない(いなかった)まさに芥川の創造した下人である、ということなのだ。それは、虚構において初めて可能とされたような一個の新しい個性である。普遍に通じ、しかしそれとして特殊な、そのような人間のビルト(像)でありイメージである。 読者は、この下人のなかに何らか自分自身を感ぜざるをえない。それと同時に、自己の周囲のだれかれをこの下人、この老婆のなかに見つけるだろう。下人や老婆のそのイメージとかさなり合うイメージにおいて、読者はそのことをイマジネートするだろう、という意味である。大正期の、この作品本来の読者にとっては、そこにかさなり合うイメージが自己内心のアナルヒスムや、反アナルヒスムにつながる何かであったかもしれない。自己周辺のアナアキストの思想と行動のことであったかもしれない。 つまり、読者の受け内容におけるかさなり合うイメージというかたちで、岩上の指摘しているようなアナルヒスムの問題にもこの作品の表現はつながりを持ってくる、ということなのである。だが、岩上の語るような「寓意」というような脈絡において(いいかえれば作品の送り意図におけるテーマとして)アナルヒスム批判がおこなわれている、ということではたぶんないだろう。そのことを送り意図におけるテーマだといいはるような人は、「黒洞々たる夜」の闇の中に姿を消し去る、その「行方」については、ついにだれも知るところのない下人の姿を、そのことば、その文章の重みにおいてイメージしえない人である。 紙幅尽き、その点にくわしくふれることはできないが、文学作品の読みの指導を通してイメージを変革し思考の発想を変革していくうえに決定的なのは、作品の文体である、ということをいいそえておく。まあたらしい発想、ショッキングな発想として学習者の心を揺さぶるような、そのような発想につらぬかれた文体の作品でなくては“思考の発想の変革”というようなことは期待できないのである。
|