|
三省堂刊「国語教育」7-7 1965年9月号 掲載 |
|
| 文学教育/その方法と教材について―― 再び 『信号』 をめぐって――-
|
|
| ==特集・文学教材における〝人間像〟をふり返って== 先ごろ本誌では二回にわたって、《文学教材における〝人間像〟》という特集をおこなった。五月号と、それにつづく六月号においてである。「文学教材の中の人間像の扱いを通じて〝文学を文学として教える〟方法を探」ろう(五月号編集後記)、という企画である。  文学を文学として教える方法――つまり文学教育の方法である。 もろもろの現場の教育活動が「道徳」教育への従属を余儀なくされている現在の状況の中でも、とりわけ動きのとれない窮地に追いこまれた格好になっているのが文学教育――国語科文学教育だ。特集は、その文学教育の本来像について方法原理の面から考えてみよう、というのである。 そこでは、八人の中学校の先生方の論文(意見)を中心に編集が組まれている。執筆者は、いずれもこういう問題を深くほり下げて考えておられる方々で、ひとつひとつ読みごたえがある。どの意見にもヴィジョンがあるのだ。すぐれた教育のヴィジョンが、である。大勢順応、現状肯定の構えに立った、通り一遍の紋切り型の発言とは質が違っている。 わたしは、いま、読者のひとりとして自身に学びとったものを書きとめようとしているわけだが、たとえば中山渡氏(五月号)は、こう語っておられる。「文学教育も道徳教育も、究極のところは同じもの」なはずだ云々。「徳目に抽象された教育では人間の精神現況にふれ」えないが、「真の道徳教育は人間にわが存在の深さと、意味の重さを」知らしめる。「文学教育における人間像の追求とて同じことである」云々。 真の道徳教育――道徳教育の本来像を前提とした立論である。このようにして、あるべき道徳教育の姿を前提として語ることで、氏の所論は、その本来像をへだてるほど遠い、特設「道徳」のありかたそのものを批判したものになっている。 中西暘子氏(五月号)もまた、作中人物の「生き方」について考える国語教育(文学教育)のいとなみは、それ自体「広い意味での道徳教育」以外ではない、という見解を示しておられる。しかし、道徳教育の現状が、「文学から手ごろな問題を発見するが早いか、現実の生活に立ち返って、文学をたな上げする」傾向にある、という事実(実態)を指摘することを氏は、忘れてはいない。中西氏の批判は、文学を「手段」視した、その素材主義に向けられている。 そこで、こうした現状・現実を前提とするかぎり、文学的真実と道徳的真実を区別して考えよう、という小原フサ氏(六月号)の提唱も十分意味をもってくるわけだ。また、荒川有史氏(五月号)のように、《現状肯定の道徳教育》というパターンで問題を考えたくなくもなってくるのだ。 と同時に、「国語科に於いても道徳づいた文学の授業」がおこなわれている現状に対して、ある「やりきれない思い」にもなる(吉田克己氏・六月号)わけなのだ。荒川氏流にいえば、反逆の文学教育が現状肯定の道徳教育に転落していることに、国語教師自身気づいていない状況に対してである。 ==作品本来の場面規定== このような現状のひずみに対して、教師はどう対処するのか? 教師その人が、「まず文学を愛し、文学をたいせつにする教師にならなくてはならない」と、吉田氏は指摘される。同じ思いである。これは、文学教育のアルファでありオメガである、ではないだろうか。ところで、文学を愛するとは、文学に信頼をかけることだ。そこで――と中西氏はいう。文学が本来的にもつ「問題意識喚起の機能」を、教師その人がまず信頼してかかることだ。そういう文学の機能への信頼に立って、「作品の叙述の中から」「作品の人間像」に迫ることである云々。 作品の叙述の中から、つまりは「表現に即して自己の〝受け内容〟を修正しながら(中略)まるごとの作品の世界を自己の内面にうちたてる」というののが、この点に関する川越怜子氏(六月号)の意見である。そういう構えが確立したとき、「すぐれた作品であれば、ずしんと重い人間を(読者に)手渡してくれるに違いない」という。 だが、それでは、表現に即して受け内容を修正するとは、具体的にいって、どういうことなのか? その作品が「どんな歴史的時点、どんな場面での表現なのか」という、作品表現本来の場面規定を教師が自分自身に明らかにし、また生徒に媒介して自他の作品の「解き口」そのものを明確に方向づけることだ、と荒川氏はいう。「場面規定のおさえ方のちがい、その解き口のちがいで作品の様相は(読者にとって)一変」してしまうものなのだから、と氏は語っておられる。 ところで、「指導者は自己の鑑賞・批判を心の底に沈め、生徒の問題意識が十分喚起されるように努めたい」と中西氏がいわれ、また倉地宏光氏(六月号)が、「読み手(生徒)の立場をたいせつにして、いつも、どんなことでも、読み手の立場で受けとめさせたい」といわれるのも、むろん、やはり、上記荒川氏のいう、「媒介の視点」を前提としての発想、発言なのだろう。読み手の立場をたいせつにする、ということは、実際の表現内容と無関係に読み手の受け内容をスッポリ是認する、ということではない。「一足飛びに結論へ」向かいがちな生徒の眼を「過程」に向け変えさせた、という倉地氏のすぐれた指導も、現実に氏ご自身の媒介の視点によって保障されているわけなのだから。 ==文学教材としての『信号』== ところで、実はわたしも上記の特集号の執筆者のひとりだったわけだが、そのおりの掲載稿について伊藤貞夫氏から、ご批判いただいた。『信号』は文学教材としてよりは道徳教材に向いている、つまり文学教材としては問題がありはしないか、というわたしの感想に対する反論である。実際に教室で扱ってみた上での話だがこれは適切な文学教材だと言いきれる、というものである。 伊藤氏がそんなふうに断言なさる気持も、実際に授業記録を読ませていただいて、わたしなりによくわかるのである。たとえば、〈授業について〉の項の終わりに近い箇所で、「みんなが戸惑った顔をしている。初めのころは論点がはっきりしていたが、話し合っているうちに焦点がぼやけてしまった」こと、そのぼやけてしまったことが実は「理解が深まった」ことのあらわれなのではないか、という意味のことをいっておられるが、その通りだと思う。文学の指導はこういう過程を生徒に経験させるものでありたい、とわたしは思うのだが、そのことは、つまり『信号』が(そのかぎり)適切な教材になっている、ということだ。 また、〈考察〉の項で、「こういう過程が熊谷氏のいわれる〝文学体験〟だと私は考えるが、どうだろうか」と反問しておられるが、「そうです、その通りです」とお答えしたい。伊藤氏の授業は、つまり非常に充実した〈文学の授業〉なのである。わたしが引っかかるのは、作品表現本来の場面規定のつかみ方というか、それの媒介の仕方である。 たとえば、「初めは、単純にセミョーンの〝まじめさ〟が好きだった生徒も、彼のいろんな面がわかってくるにしたがって、多面的な解釈をするようになっていっ」たというのは、それとしてすばらしいことなのだが、作品そのものは、しかし、けっして〝多面的な解釈〟を成り立たせるようには書かれていない、ということなのである。生徒たちのワシーリィへの共感あるいは同情にもかかわらず、作品の表現自体はそのような共感や同情をみちびくようなものにはなっていない、ということなのである。 少し話を飛躍させるが、『信号』の作者ガルシンは、トルストイの影響などもあったらしく、古いタイプの農奴のもつ従順と無抵抗に人間の理想像というか美徳をみつけているような人だったらしい。そして何よりも(五月号に書いたように)、一八八〇年代のロシアという、あすへの展望をもちえない暗い谷間の時代の作家であった、というハンディを考えなくてはならないだろう。少なくとも、この作品の表現の時点と次元においては、セミョーンは善玉でありワシーリィは悪玉以外ではなさそうだ、ということなのである。 だが、生徒諸君の上記のような人間像の評価は、こんにちの時点の問題としてあくまで正しいだろう。その評価は、そのようにしか人間というものを描けなかった(つかめなかった)ガルシンとガルシンの文学を評価する基礎資料を用意することになるだろう。つまりは、自己の人間のつかみ方とこの作者による人間のつかみ方とを対比させつつ、人間というもの、歴史というもの、そして歴史と人間の関係を人間自身の内側から考えるモメントを作りだすことにもなるだろう。 表現に即して考えた場合、しかしそのようにしか扱うほかない作品だということは、それがはたして中学校段階の文学教材として適切かどうか、あらためて考えてみなくてはならない問題のように思われる。 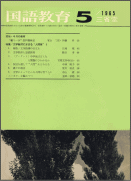
|