| |
| |
|
三省堂刊「国語教育」7-4 1965年5月号 掲載 |
|
| 文学教育と道徳教育――貝塚氏の授業報告から---
|
|
| ……貝塚レポを読んで…… 貝塚斌氏の報告を読んだ。自分では文学の授業のつもりで進めた授業が、見学者の眼には道徳の授業同様のものにしか映らなかった、ということ、また貝塚氏ご自身の反省としても、そうした第三者の批評が〈当たらずとも遠からず〉の感がある、ということなどが、そこに語られている。 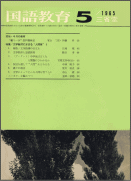 そこで、こうした「失敗」をくり返さないためには、「今後、文学の指導をどのようにしていったらよいか」云々。とくに、「道徳指導との一線を、どこではっきり区別したらよいのか」云々。国語教育や文学教育とかぎらず、学校教育そのものが妙に道徳づいてきているおりから、タイムリーな問題提起だと思う。 が、どうも、かんじんの授業の中身がハッキリしないのである。その授業がどういうところで、どんなふうに道徳教育方式の授業にすべってしまったのか、という点が報告の文章からはつかめないのである。 授業に用いられた教材はガルシンの『信号』であるが、「この作品の社会的背景を理解させる」とか、「セミョーンやワシーリィの性格・行動について考えさせる」というその第二時、第三時の授業設定にしても、それをどういう方向で 理解させ考えさせるかで、授業の内容と次元がまるで違ったものになってくるわけだ。ところが、それが説明されていない。 その日の研究授業の設定にしても、主人公たち二人の「人間像」や「ヒューマニズムについて考えさせる」と、そんなふうに言われただけでは、それを生徒にどう考えさせたのか、教室のイメージが全然わいてこない。考える方向、考えさせ方いかんで、それは文学体験をはぐくむ教育にもなり、また、ただの「道徳」指導にも成り下がってしまうからだ。いきおい、私としては推測でものを言うみたいなことになってしまうわけだけれども、その授業がもし本当に道徳くさいものになったのだとしたら、それは報告者がそこにあげているような理由からでは多分ないだろう。 つまり、七〜八時間かけて指導すべきものを半分の時間で処理したからとか、生徒どうし、あるいは生徒たちと十分に話し合う時間がとれずに、教師の側からの一方的なレクチュア形式の授業になってしまったから、といったことが真実の理由ではあるまい、ということなのだ。 時間が足りないので十分なことができなかった、というのは、わかる。が、不十分にしかできないということと、それが道徳づいたものになってしまう、ということとは、おのずから問題が別だろう。ゼミ形式とレク形式の問題にしても同じことだ。レク形式でやると文学が道徳に変わる、というものではないだろう。つまり、理由は別のところにあるはずだ、ということなのである。 ……『信号』の教材としての問題点…… 『信号』に教材を求めた授業がなぜか道徳くさいものになってしまった、というのは、ひとつにはこの作品の弱さ(文学としての弱さ)によるところがあるのではないか。だいいち、作者その人が――いや、ガルシンという人は不幸な時代に生まれあわせた作家だ。一八八〇年代のロシアという、自由のひとカケラすら見あたらないような専制主義の時代に、若いこの知識人が文学に自己を賭けたということは、故意に自分自身を不幸にする道を選んだようなものだ。三十そこそこの若さで狂い死にするような悲惨な結果になったのも、あながち遺伝という宿命のせいばかりとは言えないだろう。 彼と入れ替わるみたいにして文壇に姿をあらわしたチェーホフが、やがてそこに示したようなあすへの展望は、いまだ彼の時代のものではなかった。ガルシンの文学が示すスケールの狭さと、底の浅さ、つまりは作品としての弱さは、いわば、このようにして文学史的な宿命であった。ガルシンの作家としての不幸を言うのは、そのことなのである。そういう彼の作品の中でも、『信号』は決して良い作品とはいえないのではないか。 もっとも、セミョーンやワシーリィたちの性格的なものや、ものの考え方・行動の中に、私たちは、八〇年代のロシアの農奴たちの典型的な二つのタイプを見つけることができる。時をかして飼いならされた者の、抵抗ということを知らぬあきらめ の姿と、真実の敵がだれであるのか見さだめることのできないまま、ウップンのはけぐち を眼の前の相手に求める、すてばちで八方やぶれな反抗の姿勢。 だが、そのことが作品そのものの〈送り内容〉として実現しているわけではない。いわば〈受け内容〉として、媒介的にそんなふうに読みとれる、というだけのことである。 この作家にとっては、農奴の従順と無抵抗はそれ自体美徳であり、飼いならされた、この骨なしクラゲみたいな人間(セミョーン)は善玉なのである。この反対に、あきらめきれずにあがき のた打ち回っているような人間は、頭から〈仕様のないやつ 〉なのである。『信号』という作品は、ワシーリィというこの仕様のないやつが、セミョーンの献身と自己犠牲の崇高な行為の前に、前非を悔い更生する話である。教訓ばなしとしては、よくできた「お話」ではないか。 「お話」としてうまくできていることで、この作品は現実を裏切ってしまったのではないか。『信号』の論理は、こうだ、理由はどうであろうと、列車転覆を考えるというのは、けしからん。ほんとに仕様のないやつだ。ところで、セミョーンは自己の生命の犠牲において、事故を未然に防止しようとした。見よ、ナイフを自分の腕につきさし、流れ出る血をハンカチーフに染めてレールの上に立つ彼の姿を。 見よ、血にまみれて倒れ伏すセミョーンの姿と、そのかたわらに、血に染んだハンカチーフをふるワシーリィの姿を。 自己の観念を合理化するための、列車転覆という異常な事件の設定。そして、ワシーリィの改悛。それは、問題の本質から自他の目をそむけさせるものでしかない。こういう架空の、こしらえもの の設定では、ワシーリィ自身の問題は解決されないし、セミョーンも救われない。いや、解決へ向けてのいっさいの努力がそこに放棄されてしまっていると思うのだが。 『信号』という作品の中に良さもあることを私は否定しないが、このような、こしらえものの設定こそ、まさに、こんにちの「道徳」教育にとって、おあつらえ向きの設定だという点で、『信号』は教材として問題がありはしないかと思うのである。貝塚氏のその日の授業が、文学の授業をめざしていながら道徳の授業まがいのものになってしまった、というのも一面 では、この教材が文学教材であるよりは道徳教材に向いている、という点に起因しているのではないだろうか。 ……文学の眼、道徳の眼…… 私の言いたいのは、文学教育は、文学精神の背骨をもった文学 作品を通してしかできない教育活動だ、ということなのである。それは、ほかでもない、そのような文学 作品を媒介しつつ、自身に文学を要する教師その人が支えとなっていとなまれる、文学体験をはぐくむ教育活動である。そういういとなみに媒介されて、生徒は、自分たちめいめいの気質に応じた仕方で〈文学の眼〉を自分のものにしていけるようにもなるのである。 文学の眼――それは、たとえば、ジャンヴァルジャンがひと(他人)のパンに手を出したという行動 だけをとり出して、「良い」とか「悪い」と判断する〈道徳の眼〉とはちがう。飢えた、幼い弟や妹たちの姿がまぶた に浮かんだとき、つい手が出てしまっていたジャンの姿に逆に〈人間〉を見つけ、むしろその行為 のもつ人間的な意味を考える、という、そのような〈眼〉のことである。そこでは、つねに〈人間〉が問題なのであり、事件なら事件の全体の場面規定における、その行為の意味が問題なのである。 こんにちの道徳教育が語る「道徳」は、どうやら、あるとりきめ を前提としたルールにすぎないようだ。そのようなルールが矛盾を経験しないですむのは、ゲームにおいてだけである。文学は、むしろ、そのようなとりきめ とルールがつくり出す、もろもろの人間疎外と闘うのである。文学は何よりも人間の実人生のためのものだからである。文学教育が道徳教育の目的の次元をどう異にしているか、もはや説明の要はないかと思う。
|