| 民主教育確立のために たにもと・しげる(熊谷 孝) |
| 宮城県教員組合編集「教師の広場」№3(1949年3月)掲載----- |
|
|
一 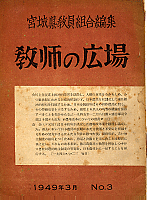 話を具体的にはこぶことにしよう。 生徒のことをしんみになって考え、ほんとうに「生徒のための学校」ということを考えている教師だったら、いま、きっと、こういう一つなやみをなやんでいるに違いない。それは、父親や母親の世代と、生徒がそれにぞくしている子どもたちの世代との、ものの考えかたや感じかたの大きなへだたりのなかに、教師自身、身を置いているということにかんしてだ。 旧(ふる)い「ならわし」や「しきたり」のなかにむしろルーエなもの[気安さ、安穏]を感じ、そういう雰囲気をなるべくそっとその儘(まま)にしておきたいと考える、多くの父や母。そういう父親や母親がその中のひとりである「世間」というもの。だが、その一方には、世間のそういう「ならわし」や「しきたり」を、いやらしく、いとわしいものに感じはじめている子どもたちの世界がある。或(ある)いは、時として、子どもたちのそういう新しい世界にとけ込もうと努力している親たちの群を見かけることもある。それは、いわばくすんだ旧憲法的な感覚と、まあたらしい新憲法的センスとの対立である。 教師のなやみは、こうした二つの対立をどうさばいていくか、という点にかんしてである。いや、どうさばくかという事よりは、自分自身どちらの立場を選ぶか、ということのなやみなのだ。それを、どういうふうにさばくというにしても、教師独自の第三の立場というようなものはありえないからだ。二者択一――そういうぎりぎりのところに自分というものが追い込まれているからなのだ。 ところで、それはつまり、新憲法の立場に立って教育を事とするか、それとも日本人民の憲法をふみにじって反動教育者に成り下がるかという境目なのだから、立場の選択になやむというのは、なやむだけヤボな話だということになりそうだが、事に実際に即していうと、そう簡単にケリのつく事柄ではない。書斎の窓から首だけつきだして、人民の「下情」を遠く眺めやっている人たちや、たとえ効果や実績がどうあろうと、動き回ればそれで気がすむ、まごころ主義者やビラ貼り行動主義者たちの眼には、およそケッタイなこととして映るかも知れないが、しかしこれが世の中の実際なのだ。なげかわしいことだと言うなら、それは確かにその通りだが、なげかわしくともナサケなくとも、現実の事実がそうなのだから致しかたないのだ。事の実際を無視して理論も成り立たなければ、実践もあったものではない。教師のなやみは、ここにある。 試みに、新憲法の精神をそのまま教育の現場に実行してみたまえ。なんらかの圧力が教師の身のうえに及んでくるのは請け合いだから。早い話が、「主権が国民に存する」という憲法の条文にふれて、天皇はもう国家や国民の主人ではなくて、クニのあるじは、誰でもないわたしたち国民自身であるという意味のことを喋(しゃべ)った教師が、「不忠の臣」であり、非国民であるというわけで、地元からボイコットを喰ったというような話もある。また、こんな話も耳にした。社会科の時間に、婚姻のことにかんして、新憲法や改正民法の話を一席やったところ、親不孝をこしらえるようなそんな講義はやめろ、といって怒鳴りこんだオヤジがあるとかないとか。 これはまた、その反対の例だが、憲法は変ったが国体は断じて変らないとか、婚姻にかんする新憲法の規定は、それを額面どおりに受け取るなら、それはわが国古来の家族制度の美風をそこねるものである、というようなことを生徒にたいして「訓話」する教師も、げんにある。これは、生徒の失笑と黙殺を買う代りに、地元の受けはひじょうにいい。生徒の個性を伸ばすとか、新憲法的な性格の民主主義者に生徒をそだてあげるとか、そういうための文化機関として学校を考えていない、一部の教師や学校経営者にとっては、何よりもまず、この地元の気受けというのが問題なのだ。つまり、これらの人々の文脈からすると、学校は一つの商売、それもいっぷう毛色の変った客商売だということになるのだ。それで、世界や日本の世論――それが、つまりほんとうの意味での民主主義の世論というものなのだろうが――にしたがって教育を事とするよりも、地元の「世論」にしたがって、まず直接の取り引き先(?)であろう父母のお気に召すような方策をとる、ということになるらしい。 ここまで書けば、もうわかって頂けると思うが、そんなふうに、自分のかわいい生徒を、一部のかたくなな父親や母親と同じような枠の人間に仕立てることには、すくなくとも良識ある教師はあきたりないものを感じている、ということを訴えたいのだ。学校は工場とちがって、きまりきった規格品をこしらえるところではない。全体主義ではあるまいし、民主主義や民主主義者の規格品なんてもののあるはずはないし、それにまた、規格品のモデルが生徒の親であったりするのでは、お話のほかだろう。学校というところは、若い世代を、親の世代以上のものに向上させるための文化機関だ。それがつまり、「生徒のための学校」ということなのだ。文化機関であることをやめるなら、学校はもはや学校でないものになってしまうだろう。おそらく、それは、半端人足養成機関か、旧憲法型花嫁志願者第一期調教所というようなものになるのほかはあるまい。それは戦前・戦時下の学校が、文化を追放することで兵営と化したのとは、やや趣を異にしているにしても、である。 二 二年兵たちが、初年兵時代に経験したと同じ屈辱感を、まだ「地方」のくさみの抜け切れない新兵たちにしんみり味あわせようとかかるのは、日本の兵隊の悪い趣味(?)だった。夢よ、もう一度――自らの若かりし日に蒙(こうむ)った被害を、こんどは加害者の立場に立って追体験しようとするシウトメのふるまいは、これまた、まことに他人迷惑な話である。親や教師が、自分たちの受けた教育を絶対のものとして、それと同じものを子どもや教え子たちに押し売りするのは、それに輪をかけた悪趣味であり、迷惑この上ない仕打ちだと言わなくてはなるまい。 「しきたり」を「しきたり」として、たんにそれを繰り返えしていたのでは、進歩も向上もありはしない。これは、至極わかり切った話だ。生徒がけっして先生より偉くならないような、また、親まさりの子どもは薬にしたくも見当らないような、そんな民族だったら、明日をまたずに亡びてしまうだろう。前の世代の文化を承けつがないでは新しい文化はつくれない、というようなギロンもあるけれど、しかしそれは、唯単に「しきたり」だから旧い「ならわし」に従がうということではないはずだ。むしろ、今となっては「しきたり」としての意味しか持ち合わせていないような、そんな旧文化の名残りは、きれいさっぱりと拭い去るべきで、過去の文化のもつ文化意識を現代の範疇に翻訳し再生産することで、明日の文化の創造にプラスするということこそ、実は文化遺産の継承ということでなけらばならない。そんなわけで、文化の継承というのは、文化生産のエネルギィーとなったもの――文化意識――を受けつぐということなのだ。文化の継承ではなくて、文化意識の継承、現代のカテゴリィーによるそれの翻訳・再生産ということなのだ。だが、しかしそうであるからといって、翻訳してみたって何のたしにもならないようなものを、いまさら持ち出すのはナンセンスだ。いわんや、封建時代や旧憲法時代の反文化的な文化意識(?)を現代の意識として再生産するにおいてをや、だ。「しきたり」のもつ反動性は、ざっと右のとおりだ。 「しきたり」は、だから、反動的な意識において再生産された過去の文化であるか、過去の反動的「文化」意識の直訳的再生産であるかだ。(たとえば、国学思想の「昭和維新」思想・皇道主義への翻訳などは前の例だし、あとのよい例は、歴史社会的範疇を無視した、儒学思想の現代への直訳的適用だ。)「しきたり」とは、そうしたものだ。それは、文化のすこやかな成長をはばみ、歴史の歯車を逆転させる魔力をもっている。現代の意識・現代の感覚が、「しきたり」にたいして素直でありえないのは、当りまえのことだ。「しきたり」を破ろう、旧い「しきたり」を破ることで、むしろ新しい「しきたり」を自分たちのこの手で作ろうではないか、――いってみれば、そうした意識と実践への情熱が、民主革命のこの時代に若い世代の心を捉(とら)えて放さぬのは、これまた当然過ぎるほど当然のことだろう。 若い世代のそうしたひたむきなおもいを、むしろわが事として感じ得るだけの感覚の若々しさと柔らかさがなかったら、こんにち、ひとは教師となることはできない。こんにちこの時代に「先生らしい先生」となるためには、教師は、この新憲法的感覚をわがものとしなくてはいけない。新憲法をさえも旧憲法的感覚で感覚し、生徒を、学校を、かつての全体主義的・画一主義的な統制のもとにとどめようともくろんだり、すきがあったら学校をもとの秩序に、全体主義的なもとの仕組に引き戻どそうとたくらむような事では、それがいくら口先だけのこととはいえ、ひごろの口ぐせみたいに喋っている「民主主義」が泣くだろう。言うだけヤボな話だが、教師はほんものの民主主義者にならなくてはならない。ヤボは承知の上うえで、あえてこうしたことを口にするのは、言わねばならぬだけのワケが、そこにひそんでいるからなのだ。 三 だが、ひと口に民主主義というのにもいろいろあるらしい。それで、、人民民主主義がどうの西欧民主主義がどうのという、ムズかしい事はぼくにはわからないが、ぼくがここで「ほんもの」の民主主義というのは、新憲法の精神を護持する立場のことだ。それを裏からいうと、ポッダム宣言にそむいたり、憲法に背中を向けたりするような民主主義なんてものは考えられない、ということなのだ。暴力や暴力的な思想を、それがどんな形のものであっても、ぼくらはにくむ。民主主義の立場に立つ限り、そうなるのだ。ぼくらは自由と平和を愛し、合理主義に主義に徹しようとおもう。新憲法は、そのことをおしえている。 だから、教師がいまなお旧憲法的感覚の人であったり、または封建的ボス的旧勢力とヤミ取引きすることで一身の「立身出世」や「身の安全」をねがう、というような事であってはいけないわけだ。それでは学校というものが「生徒のための学校」ではなくなって、たかだか「親のための学校」「教師のための学校」になってしまうからだ。しかも、その「親」とか「教師」というのが、一般の父母教師ではなくて、ボス勢力である旧い型の特殊な父母や教師であるからだ。朝日の論調を借りれば、それはP.T.AでなくてB.T.Aだということになろう。(Bというのは、ボスの頭文字だそうな。)P.T.AがぜんぶB.T.Aだというわけでは、むろんない。だが、そうした顔がものいう旧体制のものも、満更(まんざら)ないわけではない。だからこそ、はじめに述べたような教師のなやみも生れて来ているしだいなのだ。 BをPに切り替えると同時に、TをTらしいTにすることで、PとTを結びつけるということ以外に、ほんとうの意味での生徒のための学校――文化機関としての学校――はつくれない。旧い世代の思想や感覚が否定されなくてはならないからといって、教師が生徒の父母と背中合せになるのは、けっして好ましいことではない。教師は、生徒の教師であると同時に、その意味では父母の教師でなければならぬわけだ。こんにちの教師のつとめは、たんに生徒を啓蒙するということに尽きるのではない。 今のはんとし一年は、昔の五十年百年にも相当する。いや、見ようによっては、もっとテムポが早いと言っていい位のものかも知れない。「歴史の巨歩」という言葉が、きょうこの日ぐらい、しっくりぼくらの胸に響いてきたことはない。歴史の大股なあゆみは、その歩幅の大きいことのために、しみのすくない若い心には、じかに、ゆがみなく反映していくのだが、すり減った、感度のにぶった「経験の深い」人の心には、それが映らぬらしい。映ったにしても、それが妙にゆがんだ形でしか影を投げかけぬもののようだ。「深い」経験がわざわいしており、誤まった経験の仕方がもたらした心のねじくれのせいである。そういう、ものを見る眼のゆがみと心のねじくれは、しかし同時に教師自身のものである。だから、父母を啓蒙するというしごとは、同時にきびしい自己批判が伴なわなくてはならぬわけだ。相手を批判するということは、自分を深くかえりみるということだ。そして、そういう自己批判が、修身道徳的なチョロイものでない限り、そこにきっと相手を啓蒙するという実践的な意欲が生れてくるはずだ。 だが、事の実際・世の中の実際に照らしてみて、これはひじょうにムズかしいしごとだ。ほんとうを言ったら、ひとりやふたりの教師の結びつきでは出来る話ではない。だからこそ、初めに愚痴を並べたように、一片の良心のカケラでも持ち合わせている程の教師は、みんなここのところでなやみ、かつ足踏みしているのだ。そして、たまさか一歩前へあゆみを進めた教師があったとすると、たちまちにして浮き上り、袋叩きにあってしまうわけなのだ。だが、この線を踏み切ることができなかったら、教育の民主化も教育復興も何も出来はしない。だから、結論は踏み切ることだ。踏み切ることなのだが、それには踏み切れるような体制をあらかじめ作らなくてはいけない。そうでなければ、大きい力になることが出来ないからだ。そういう体制、そういうシステムがどうしたら出来るかと言ったら、教員組合が教員組合らしくなるということだ。教師の理想像は「人の師表」となることだろう。だから、教組を「人の師表」の集まりというにふさわしいものにすることだ。 「人の師表」は、進むべきところで尻ごみしたり、戦友をタマよけにして見殺しにしておいて、そのくせ戦利品の分け前だけを当然の権利のような顔をしてもらったりはしないはずだ。また、都合のいい時だけは同志で、わざわいが身に及びそうになるとソッポを向く、なんて事もけっしてないはずだ。 四 あの侵略戦争のさなかにおいてすら、国民のあらゆる層が東条軍閥を支持し、戦争を支持していたわけではない。すくなくとも、知識人の多くは、心ひそかに戦争を呪い、かつ敗戦のこんにちを十分予見しえていたはずである。これが見透せないようなのは、もともとが知識人でなかったのだと言い切っていい。それは知識人ではなくて、たんに学校でムダメシを食ったというにすぎない学歴人――単なる大学・高専の卒業証書所持者であったわけだ。だが、ほんらいの意味での知識人たちだって、あんまり大きな顔は出来ないはずだ。内心反戦的であったというだけで、戦争を喰い止めることができなかったのだし、第一そういう意思表示さえろくろくしなかったわけなのだから。 このことは、こんにち、知識人の自己批判の問題として取り上げられ、自分たちが民衆のひとりであるという自覚を欠いていたことや、民衆と背中合わせになることで、民衆の啓蒙をないがしろにし、その結果、民衆から浮き上ってしまっていたことなどが、ふかく、きびしく内省されはじめている。教師も知識人の端くれだったら、ことに戦時中に身をもって「実践」した戦争協力の罪業の数々をうしろめたく思うなら、今こそぼくらは人民意識にめざめるべきだし、民衆との積極的な結びつきをふかく考えるべきであろう。ぼくらが心ならずも戦争に協力しなければならなかったのは、どうしてか? 或いはまた、この侵略戦争を心から「聖戦」だと信じて大きなミスを仕出かしてしまったのは、どうしてなのか? 前のばあいは、知識人相互の、或いは教師相互の横の結びつきを欠いていたということ、さらにまた、知識人(ないし教師)と一般民衆との関係が背中合わせになっていたという事によるものだ。あとのばあいは、教師たちが理論的精神を欠いていたということ、理論的精神によって構想された実践の人でなかったということを言いあらわす以外のものではない。それはつまり、教師その人が人民意識にめざめない愚衆の一人であったということを示すものだ。 愚衆から民衆へ、人民意識をもった民衆へと自分を変革していくことが、いまだいじなのだ。人民意識をもった人でなくて、人民の子どもを育てることはできない。人民の子のゆがみない素直な心に、もし黒いシミでもつけるような事があったら、何といって申訳(もうしわ)けするつもりなのだ。自身、まず「人民」になることだ。人民意識をもった民衆のひとりになるためには、だが書斎にこもって、百冊の社会科学の文献を退治してみたってダメだ。すくなくとも、その事だけでは自己変革はできない。そういうふうな勉強だったら、これまでの知識人がみんなやって来たことなのだ。そうした、いわば書斎派的な勉強がもたらした知識が、現実の事実として、戦争を防止するうえに三文のたしにもならなかったという点にこそ、こんにちの批判があるのではなかったか。 ぼくらが市民として生き、教師として生活しているということ、そのことが、実はなんらかの実践をおこなっているということなのだ。それがプラスの実践であるか、マイナスの実践であるかは別としてである。それが或いは当の本人には自覚されていないかも知れないが、教師としての自分の日常のふるまいが、結果としては、教育の民主化にブレーキをかけたり、それを促がしたりしている事になっている、というわけのもだろう。ふつう、ぼくらは、ぼくらの行動を、これまで生活の経験からえたところの知識でもって律して来ているわけだが、そういう日常的経験的な知識だけでは、どうふるまってよいのかの判断がつきかねるというような場面に行き当ることも、ままあるわけだ。理論の探究というのは、そういう壁を突き破るためにおこなわれるものだ。どうすれば、もっとも効果的に短時間にこの壁をこわすことができるのか、という実際問題を解決するためには、まず「壁」の造くりや仕組を知らなければなるまい。つまり、そこで、事象の起こりや、それのもとになっているものや、事象の外側と内側からの事象そのものの理解というような事が、客観的・因果的にさぐられなくてはならぬわけだ。それもこれも、事象の探究をとおして現実そのものの秩序(論理)を捉え、そのことによってまた、事象をすきなく解決するという、実践の論理(秩序)をわがものとするためにである。論理が実践のためのものであるなら、論理は現実の秩序に一致しなくてはならない。そして、現実の秩序をさぐるための組織的な認識活動が、ここに理論と呼ばれるものであるわけだ。現実が動的なものである以上、論理も、だからまた理論も、それとして固定したものとしてあるわけにはいかない。 それで、つまりこういう事になるだろう。ぼくらが人民意識にめざめた実践の人となるためには、自分というものを内側から変革していかなくてはいけないわけだが、しかし内部変革という言葉を使ったからといって、それはなにも実践をないがしろにした書斎派になれということではなくて、むしろその反対なのだ。理論は、もともと人間の実践的要求から生れたものだし、実践のためのものだ。実践に役立たないような知識や理論は、理論のまがいものにすぎない。だが、しかし、「理論よりまず実践」という声には、どうもぼくは同調しかねるのだ。理論と実践とを機械的に対立させて考えることで、ビラはり行動主義のオトシアナに片足突っ込んでしまっているからだ。書斎派のインテリどもが観念的であるのと同様に、実践マニアのこれらの行動主義者たちも十分観念的なのだ。内部と外部を、理論と実践とを、こんなふうにバラバラにしてしまったら、もうおしまいだ。ほんらい民衆の一部であるはずの知識人が、民衆自身と対立するという奇妙な現象が、第一こうしたバラバラ事件の産物であったわけなのだから。 事のついでに、知識人と民衆との対立の話にちょっと戻どるが、かつて知識人の人民意識を眠りこませた魔薬にハイデッガー流の存在論哲学のあったことを、ここで想い起こすことにしよう。火に油をではなく、水に油を注ぐように、このハイデッガーにマルクスをこね合わせて作られたのが、あの「中間者」の哲学――三木哲学だった。三木清の死が、人民解放の前夜を背景として、きわめてドラマティックなものであったということも手伝って、きょうこの頃では、一部には、反人民的なこの中間者の論理が、人民哲学の論理そのものであるかのように考えられている向きもあるらしい。けれど、三木哲学のプラスの面は別のところにあるのであって、中間者の論理そのものは、あえて言えば修正主義の悪い見本みたいなものだ。パトスとロゴスの中間者としての人間彫像を刻むことで、実質的には階級者としての人間規定をなし崩しに取り除き、人間を歴史の枠の外にほうり出すことで人間を人間でないものにしてしまう、という役割を演じたものだった。これが、三木清の「歴史哲学」であり「人間学的基礎」による人間の自己省察であったわけだ。このようにして、人間らしい人間というのは、超歴史的・超階級的なこの中間者の自覚に達した人間のことであって、知識人こそは、まさにそのような自覚に至る唯一のひとであるということになるのだ。インテリは、第三階級にも第四階級にもぞくしない中間者――単なる知識人ではなくて知識「階級」――であるから、というしだいだ。 だから、つまり、ひと世代まえの文化青年たちにこうした迷信を植えつけた当のものが、「中間者」の哲学、三木哲学であったということになるのだ。(すなおに白状すると、ぼくもまた、当時、三木哲学の影響下にあったひとりなのだ。)それで、きょうこの頃、実存哲学や実存主義的気分の横溢・流行という現象とあいまって、またそれが若い世代の一部にずい分もてはやされているらしいが、もてかたそのものに何か問題がありそうな気がするのだ。 五 これは、木村禧八郎氏が書いて居られたことなのだが(世界評論・十月号)、社会党のある参議が松本治一郎氏に向って、「あなたは、いったい右派なのか左派なのか」と訊(たず)ねたというのだ。すると、「わたしは右派でも左派でもない。わたしは、社会党の精神に生きるものだ。」と答え、「わたしを左派だという党員は、社会党立党の精神を忘れて右へ行ってしまった人たちだ。わたしを左派扱いするのは勝手だが、それは、そういうことを口にする当人が立党の精神を忘れて右傾したという事を白状しているようなものだ。」といって相手を極めつけたというのだ。「言葉はおだやかだったが、内容には筋金が入っていた。」そう木村氏は付け加えておられたが、ぼくらやぼくらの組合に欠けているものは、松本さんのこのセンスでありこの筋金である。 だが、教員ひとりびとりについて言えば、それは欠けているのではなくて、教員相互の横のつながりと結びつきが弱いために、効果的に力が発揮できないでいると言ったほうが当っているだろう。ここで教師の横の結びつきというのが、教員組合のことであり、また、組合員相互のつながりをバラバラなものにすることで組合そのものの力を弱め、教育復興ということを掛け声だけのものにしてしまっている当のものが、松本氏に「立党の精神を忘れ」といって極めつけられたような、「組合設立の精神を忘れた」ひと握りの力であることなどは、いまさら口にするのもヤボな話かも知れない。〔民主主義科学者協会会員〕 |
|
|