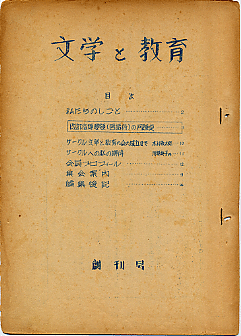| 「文学と教育」掲載記事 対象別一覧 |
| 学習指導要領問題と どう取り組んできたか。 |
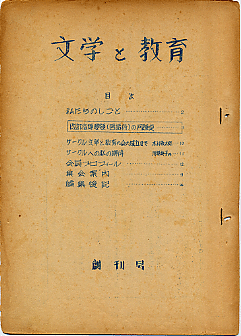 |
記事全文、または部分
|
| ■改定・学習指導要領(国語科)の問題点──熊谷孝氏をかこんで─………編集部(「文学と教育」創刊号 1958.10) |
| ■改訂指導要領と国語教育………(「文学と教育」第2号 1958.11) |
| ■改訂学習指導要領をめぐって………(「文学と教育」第2号 1958.11) |
| ■今日の課題──国語教育の側面から………(「文学と教育」第3号 1958.12) |
| ■原則的と現実的と………熊谷 孝(「文学と教育」第6号 1959.4) |
| ■抵抗論は正しいか──改訂指導要領反対闘争をめぐって………小沢(「文学と教育」第7号 1959.5) |
| ■道徳教育と文学教育………小沢雄樹男(「文学と教育」第9号 1959.7) |
| ■第八回全青教別府集会報告………福田隆義(「文学と教育」第10号 1959.9) |
| ■文学教育は子供の認識をどう育てるか………熊谷 孝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
| ■改訂指導要領の文学観………荒川有史、鈴木 勝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
| ■集団の自己紹介………鈴木 勝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
| ■《声明》灘尾文相「国防発言」に抗議する………(「文学と教育」第49号 1968.1) |
| ■国防意識に結びつく改訂学習指導要領の問題点(座談会)………熊谷 孝 ほか(「文学と教育」第49号 1968.1) |
| ■指導要領改悪史………福田隆義(「文学と教育」第52号 1968.6) |
| ■私たちの立場と課題………福田隆義(「文学と教育」第59号 1969.8) |
| ■国語教育課程の新改訂に思う………夏目武子(「文学と教育」第99号 1977.1) |
| ■「教育課程の基準の改善について」を読んで………T.N.(「文学と教育」第99号 1977.1) |
| ■文学の創造と文学教育──テスト体制下の国語教育と文学教育………熊谷 孝(「文学と教育」第101号 1977.8) |
| ■改訂「学習指導要領」批判の質を問う………福田隆義(「文学と教育」第103号 1978.2) |
| ■文学教育と教師の鑑賞体験………夏目武子(「文学と教育」第104号 1978.5) |
| ■文教研二〇周年に思う………福田隆義(「文学と教育」第105号 1978.8) |
| ■第30回全国集会を迎えるにあたって――今こそ文学教育を………福田隆義(「文学と教育」第117号 1981.8) |
| ■教科書はだれのものか――学習指導要領について………樋口正規(「文学と教育」第150号 1989.11) |
| ■文教研創立の思い出………福田隆義(「文学と教育」第151号 1990.3) |
| ■「文学教育の復権」を訴える………委員長 福田隆義(「文学と教育」第179号 1997.11) |
| ■黙ってはいられない――『21世紀の国語科学習指導要領』を読んで………山口りか(「文学と教育」第180号 1998.3) |
| ■真の伝え合いとは何か――「学習指導要領」における「伝え合う力」批判………井筒 満(「文学と教育」第197号 2003.7) |
| ■学習指導要領の改訂に想う――変わらぬ言語技術主義の横行………夏目武子(「文学と教育」第208号 2008.7) |
|
 ‖「どう取り組んできたか。」目次‖機関誌「文学と教育」‖ ‖「どう取り組んできたか。」目次‖機関誌「文学と教育」‖ |
|
文教研の「学習指導要領」批判、その軌跡
(上記標題記事の全文、または部分を、以下に掲載します。発表年代順。) |
|
| ■改定・学習指導要領(国語科)の問題点──熊谷孝氏をかこんで──………編集部(「文学と教育」創刊号 1958.10) |
《君が代》と《国民的自覚》
A 九月例会と十月例会の二回のゼミナールにおいて、国語科学習指導要領改定案の検討をやりましたが、問題点として指摘されたことを一つ一つ拾っていきましょうか。
熊谷 Fさんのほうから指摘されたことだが、学習素材の選択の基準として、現行指導要領には十四項目あげられているのが、今度は一〇項目に減っている。何が削られたのかというと、「自由・平等・博愛・正義・寛容の思想の理解と発達を助けるもの」といった項目であって、反対に、新しく(1)「道徳性を高め、教養を身につけるに役立つもの」を選ぶようにとか、(2)「国土や文化などについて理解と愛情を育て、国民的自覚を養うのに役立つもの」を選べ、という二項目が加えられている、ということ。この辺のところから、改定案のねらいがつかめやしないか、というFさんの意見でしたね。(…)
A 「道徳性」だの、「国土への理解」だの、「国民的自覚」だのという、新しく付け加えられた項目に問題がある。そんなふうにみんなの意見が、なったのでしたね。
C そうでした。「国民的自覚を養う」というんだが、問題はその実質的な内容ですね。一方で《君が代》を必修歌唱にしておいて「国民的自覚」をうんぬんするからには、これは《国粋主義》の線での国民的自覚と理解するほかない、という熊谷(孝)先生のご意見でした。
熊谷 戦前の国粋主義とイコールではないですけれど……、ファシズムのニュー・ルック政策というところですか。(…)
「道徳」の特設との関連
C (…)「道徳」を特設した意味と、改定のねらいとの関連・関係……
B 天野文相以来の「修身」復活のねらいが、両者の密接な関連のもとで一おう成功した、ということ。
A もう少し具体的に……。
熊谷 家を建てるのには土地が必要だ、ということ。「修身」という家を建てるための地所が「道徳」という名の空地だった、ということが一つ。
C 杭は打ってあるが目下空地だということなんですな。そいつをカヴァーするために各教科の内容のほうを「修身」の方向に改定する必要があった。音楽科では《君が代》を必修にするという調子で……
A そういう一環としての国語科の改訂というわけですね。(…)
授業時数の増加と毛筆習字
B 戦前の教育では、国語・算数がだいじにされていた。一通り読み・書きができて、数の勘定も間違えないような、詔書必謹の臣民をつくるための……
熊谷 こんどは、どこの国の臣民になればいいのかね?(笑声)
A 国語の授業時数が増えたらいい、というものではない。それが、さっき出された意味での「国民的自覚」を促がすための時間増加であったり、というのでは困る、というのが、Oさんや、Fuさんや、Fさん方みんなの意見でした。(…)
経験主義、系統性、発達段階
A 次に経験主義と系統学習の問題ですね、系統性を持たせた指導要領というけれども、実際はどうだろう、という点……
B 何が系統学習だ、これで系統性を持たせたといえるかい、とOさんリキんでいたそうだね。
熊谷 あれはOさんのいう通りですよ。文学教育のほうと関係してくるが、ふたことめには「経験を広め心情を豊かにするための」文学学習だ、というんですものね。こっちにいわせると、文学を読むのは《経験の仕方を変革する》ためなんであって、たんに「経験を広める」ためじゃない。
C そうだと思いますね。あれは、経験領域のただの拡大です。(…)
C 今度のは系統性を持たせた、というが、たとえば「目標」のところで、一年生では「文字をていねいに書くことができるようにする」とあり、二年では「文字を正しく書くことができるようにする。」三年になると「文字をいっそう正しく書くことができるようにする」というぐあいですね。
A 「ていねいに」の次が「正しく」、その次が「いっそう正しく」ですか。作文ですね、まるで。(笑声)
熊谷 こういう作文を書いていればつとまるのなら、僕にだって指導要領作成委員の資格は十分あるな。(笑声)
C いや、それだけじゃダメですよ。心を入れ替えませんと。(爆笑)
文学教育の側面から
A 文学教育の面から話題にしたことを、ふり返ってみませんか、この辺で。
C そうですね。
B さっきもでましたが、改訂案による文学教育も、やはり経験主義学習だということが一つ。改訂案は「経験を広める」ための文学作品の読み、ということに終始している。
C さっきの系統性につながる問題ですが、Ogさんも指摘していたように、一年生では「童話、説話、詩などを読む」とあるのが、三年では「童話、物語、伝記、脚本」と種類をふやしていっているだけで、系統性を持たせたみたいな印象を与えているんですよ。ただの印象にすぎないんですがね。
B 「経験を広め心情を豊かにする」文学作品の読みというのは、熊谷先生でしたか教養主義の臭みが強い、と批判されていましたね。
A 情操教育として文学教育をおさえていく行き方だ、ということでしたね。
熊谷 と同時に、前にでた「道徳性を高め、教養を身につける」国語教育や文学教育というのは、一本テコ入れが行われているわけですよ。そこで身につける教養なり情操というのは、例の逆コースの意味での国民的目標に裏打ちされたものでなければならない、という但し書きつきのものなわけですね。
B 中学校の改訂指導要領になると、文学作品全体の認識とか表現の理解ということの指針は全然ないですね。この点は小学校の場合も同じですが。その「構成や修辞に注意して、味わって読むこと」というふうなことになっている。第一回のゼミで、このところが問題になりましたね。
熊谷 方向としてそれが問題になったが、しかしそこのところまで割り切った結論へは到達していなかったんじゃありませんか。
A でしたね。話がそれちゃった、あのとき……。
C 中学校の面で、もう一つ大きな話題を呼んだのは、改訂案の「指導計画作成および学習指導方針」の項の3で、「読みものは、文学作品に片寄らないで」とあって、その次のセンテンスで「古典にたいする関心を持たせるように留意」せよ、とある点でした。
B 古典は文学でないのかね。(笑声)
熊谷 底意地の悪いいい方になるけど、文学性を疎外して考えられる古典、例の国民的自覚と結びつけて考えられる古典というのは、未来形における戦犯候補みたいなコテンですね。もっとも、これは古典のほうの罪ではなくて、悪用するほうの側に100パーセント罪があるのだけれど。この間は、その点が問題になったのでした、たしか。(…)
課 題
C 国語教育のなかで文学教育をどう位置づけるか、ということですが、それと同時に国語教育の指導体系というか、国語教育とは何かということですね、Oさんがさかんに問題にしていましたね。
A そのことの追求が、次回からの課題になるわけですよ。
B こちら側で実際に役に立つ指導要領をつくろう、というわけでしたね。
熊谷 Fuさんが、前から強く主張されてることですね。
A では、今夜はこの辺で。先生どうも遅くまでお世話さまでした。
|
|
| ■改訂指導要領と国語教育………(「文学と教育」第2号 1958.11) |
| 十一月十一日(火)、杉並区荻窪中学校で、月例の国語教育研究会があった。ちょうど十一月は私たちの“サークル・文学と教育の会”の熊谷孝先生が講師として参加されたので、編集部から、O、Aの二名が同行させて頂いた。以下の報告は、当日のメモをくりながらの話しあいを、Oがまとめたものである。なお、杉並国教研は、私たちのサークルの仲間であるFu氏が、中心となって運営されているものである。 |
ファシズム教育のニュー・ルック
新指導要領が、単にお粗末だ、というだけではなくて、ファシズム教育のニュー・ルックとして登場した、というのが、先生の講演の御主旨ではなかったろうか。特に、国語科として問題をしぼることなしに、他教科、中でも特設道徳(「太陽系の太陽自体が特設道徳である」と文部当局の担当官が発言して、学校教育の中心におこうとしている)との関連において、国語科改訂もまた、その真のネライは、ファシズム教育への改訂である事を示してくださった。
これを前提として、細部の批判にうつられたわけであるが、第一に、経験主義批判を話された。従来からの活溌な経験主義批判をうけながら、文部省は本質的に経験主義を変えなかったこと、また中学校の場合、部分的に言語主義への移行が見られるが、言語主義と経験主義とは、同じ一つの本質の二つの現象形態にすぎないこと、しかも、言語主義への移行は、戦前教育への逆行である事等である。教育は、その本質は経験の仕方の変革 である。ところが、単に、経験を広める ことに教育の仕事をすりかえている。その文部省の経験主義を、鋭く批判された。
幼児語の否定
次いで、文部省の言う所の、“系統性”が、いかに形式的で内容が空疎なものであるかを話された。例えば、小学校一年の指導事項に、「発音に気をつけ、幼児語を使わないこと」というのがあるが、一体どういう幼児語を否定しているのかわからない。これなど、“お の字の過剰”等というのならばわかる。さなきだに動きの少ない日本語なのであるから、動詞・助動詞・形容詞などを大切に育てて行かなければならないのに、「おあそび」などと、本来動詞として表現されるべきコトバを、それにお をつける事によって名詞化して使用するなど、ますます動きの少ないものにして行きつつある現状、これら即ち、日本語の充実発展に対する反動的な用語例をこそ具体的に否定すべきであるのに、単に「幼児語をなおせ」式の表現にとどまっている形式性に、強い不満をのべられた。
形象理論の復活について
更に話題は、文学教育の側面からの批判に移られたわけであるが、文部省の意図する所謂道徳科文学教育は、全くナンセンスであること、これに反して、国語科文学教育は、今まで、本来アモーラルな立場に立つ文学の、その文学的感動を中心として育てられて来たこと、即ち、作品全体の認識を中心として、人間の生き方を内面からさぐって行く方向であること。しかるに「改訂」によれば、それが、部分的修辞の鑑賞に逆もどりする傾向であり、表現のコマ切れを問題にする方向であることを指摘された。
これは明らかに形象理論 の復活であり、移行の動きを見せつつある言語主義とのつながりがここにあり、しかも、修身教育の復活への、国語的賛同がここにあることを指摘されたわけである。
その他、指導要領の文学観は、こんにちの文学研究の水準からは、あまりに蒙昧にすぎるという事実。また、国語教育の領域を〈話す・聞く〉〈読む〉〈書く〉という言語領域のみにおさえるおさえ方の問題、特に、コトバによる認識の二つの極として科学と文学を考えられるのが当然であるのに、その文学の国語科における重要性が全くないがしろにされている事、等々を豊富に提出してくださったわけである。
特に結語は、現在、国語教育や文学教育の各種団体が作られているが、それを逆用してあらぬ方向へ方向づけていこうとするのが戦後ファシズムの新しい形態であり、その力が強く働いている現在、それを明確に把握して、今こそ意識的に民主教育を守らなければ、いつの日にそれを守る時があろうか、という、きわめて感動的なものであったことを報告いたします。
|
|
| ■改訂学習指導要領をめぐって………(「文学と教育」第2号 1958.11) |
[改訂学習指導要領をめぐる論調を広く新聞・雑誌からリストアップしたもの。]
|
|
| ■今日の課題──国語教育の側面から………(「文学と教育」第3号 1958.12) |
十二月二十七、二十八日の二日間にわたって、日本生活教育連盟の第十回総会・研究集会が、東京・九段会館でもたれました。
第四部会「教科による生活教育の問題を──新指導要領の検討を中心として」の第一分科会には、助言者として熊谷孝先生、提案者としてK.K.さんが参加されました。また、私たちのサークルからも、この分科会には、S.M.、S.Y.、M.M.、T.K.、A.Y.、O.I.のみなさんが参加しました。
K.K.さんは、国語科による生活教育がいったいなりたつのかどうかという疑問から出発し、国語科には国語科としての任務、方法、目的があること、したがって生活一般にけっして解消されはしないこと、またどの学科も生活指導的側面はもっているけれども、あくまで各教科独自の機能によって世界観の形成につながるのであって、理論と実践の問題を媒介にして“生活”と“教育”との関連を明らかにしていきたいことを、実に厳密に批判・検討されました。その上で、新指導要領批判が簡潔に行われました。今までは、裏口営業といった形で「要領」をネグレクトしてきたが、今後はそうした形さえ圧迫されようとしており、「新指導」へのうむことない批判が必要だ、と力説されました。
熊谷先生は、生活教育の“生活”があいまいな言葉であることをまず指摘し、私たちは“生活”をどう把握するか、国語生活という側面にしぼって生活をどう考えるか、現実の子どもだちは、どういう観点からみて“弱い”のか、子供たちを民族の子として育てるために私たちはどういう言語観文学観をもたねばならないか、と問題の焦点を指示された。
|
|
| ■原則的と現実的と………熊谷 孝(「文学と教育」第6号 1959.4) |
(…)
改訂指導要領は返上しよう
ところで、さきごろの警職法反対闘争ですが、あのときの、すさまじい盛りあがり方には、予期せぬものがあって、相手も首をすくめたに違いありません。が、しかし同時に、笑いが止まらなくて困る、というふうな一面が相手方にあったことも、見のがしえません。というのは、警職法に国民の目が一せいにそそがれることで、警職法とじつは表裏一体の関係にある一連の法案が、国民の監視の目をまぬがれて、悠々と通過しそうな見とおしを用意しえたからであります。
つまり、それと同じことが、勤評と「道徳」の特設との関係、そして学習指導要領の改訂との関係においても見られるわけであります。
現実という名の既成事実を、まず、どこかの一点で作りあげる。正面からではダメなら裏側から回る、というわけです。で、表なり裏なり側面なり、そのいずれかの一点で作りあげた既成事実に立って、第二、第三の既成事実をつぎつぎと作りあげていく、というのが、いつも変わらぬ相手の常套手段のようです。つまり、警察予備隊という既成事実の上にたって、それをアメリカ人たちからは、カントリー・アーミイ(土民軍)と呼ばれている、「戦力なき軍隊」自衛隊にまで仕上げていく、あの手口であります。
いまさら言うまでもないことですが、「道徳」の時間特設は修身復活への第一歩であります。作成委員某氏の意見によれば、それは純粋に倫理学的要請にもとずく時間特設なのだそうですが、そうした学者の意図とは別個に、「道徳」という名の空地は、「修身」という家屋を建てるための、建築用敷地として用意されたもの、と考えるほかありません。
それが空地であることをカヴァーするためにこそ、こんどの指導要領の改訂です。音楽科で《君が代》を必修歌唱として歌わせ、国語科では、国粋主義的な意味での《国民的自覚》を促がす――たとえば古典を、文学としてではなくて、右の国民的自覚を促がす道徳教材として使え、といった調子です。教科課程の改訂は、ですから、勤評を実施しようとするモクロミと同一のモクロミで立案されたもの、と考えざるをえません。
だから、勤評闘争を軸としていえば、改訂指導要領返上闘争は、勤評闘争の重要な一環であります。今は勤評問題で忙しいから、このほうは後回し、という性質のものではないのであります。
ところが、さきごろの第八次教研でありますが、朝日新聞の報道を額面どおり受けとるとすると、ちょっと不安になるのです。福島・和歌山・高知の教組から出された、改訂指導要領返上論に対して、「それは原則論であって容易ではない。」という「反論」が出て、うやむやに終ったらしい模様なのです。原則的には正しいが現実的でない、という例の論法によってであります。これでは、まるで、原則に忠実であることが、つねに非現実的な態度に陥ることであるみたいな印象を受けてしまうのですが、討議の実際は、新聞の報道とは、かなりニュアンスの違ったものであったろうことを、私は信じたいのであります。
ただ、いささか危惧するのは、(朝日の報道にしたがえば)反論した側の論拠が「勤評闘争といった権力闘争なら職場の中はまとまるが、教科ごとに上からびっしりおしつけられた場合は、不安だ。」というふうなことである点です。
それは、まるで、改訂指導要領返上闘争を権力闘争として考えていないみたいな口ぶりです。加えて教科指導や教科論の面においてこそ、教師は専門家として、自信をもって起ちあがれるはずであるのに、それが闘えない、そこのところで足並みが乱れてしまうというのでは、理論の裏づけをもち、理論的な反省を伴なって教科指導をおこなっているような教師は少ないと言っているようなものだからです。もしも、それが現状であり事実であるとしたら?……私が危惧するといったのは、その点であります。
が、すくなくとも私の見ききしているかぎりの現場の実際は、科学的な教育の場であります。そして、現場の教科指導が、現に理論的・科学的にいとなまれているという点にこそ、この返上闘争の揺がぬ拠点が見いだされるのであります。(…)
|
|
| ■抵抗論は正しいか──改訂指導要領反対闘争をめぐって………小沢(「文学と教育」第7号 1959.5) |
都教組の四月中央委員会の席上、ある委員が大要次のような発現をした。
私達は、改訂指導要領に反対して斗っている。しかし、実際にこの四月、教科課程を組むに当って、私達の主張は《反対の為の反対》だとして校長あたりから片づけられることが多かった。いくら改訂要領の悪質さを言っても、それだけでは斗う力とはならない。この現状を救う為にも、日教組はその力をあげて真の民主主義教育のプログラムをつくるべきではないか。
これに対して日教組副委員長であった藤山執行委員の答は、
日教組としてそういうものを出せば、文部省が出すものを日教組で対抗上出すという妙なことになって、我々の反対斗争の意味がなくなる。我々が反対しているのは、文部省のそれの「基準性」というもので、本来職場にあるべき教育過程の編成権を、文部省あたりで集権的に取りあげてしまうことにあるのである。だから、我々は今、改訂指導要領の基準に抵抗し、自主的な教科課程編成権を守り、我々が行って来た民主教育を守る為に斗わねばならない。民主教育とは、各地域、各現場に応じた教育の謂であって、文部省に対して日教組が教育課程を出せというのは自ら民主教育を捨てるものである。
この藤山答弁は正しいだろうか。私は正しくないと決せざるをえない。
第一に、この抵抗論では、教育の原則が無視されている。アナーキーではないか。要するに抵抗すればいいというのでは、敵が明確な目標に向って、組織的に系統的に教育を利用しようとしているのに、民主教育の目標自体が混乱している今日、民主教育とは各地域、各現場に応じた教育をいうのであって、要は基準性に抵抗すればいいというのでは、《反対の為の反対》から一歩も出てはいない。
第二に、戦後教育の実状把握と反省に欠けている。戦後の民主教育といっても、それは、文部省発行の指導要領の線に従って実施されていたに過ぎないということ、我々の現場から積みあげていったものではなかったという事実。これをどう把えるのか。また、戦後文部省の民主教育(我々がやった民主教育)のその反民族性、その経験主義、その非能率生等々は、我々自体の苦い経験からの反省として現在批判されているではないか。この批判をどうするか。
第三に、従って、全国的な勤評下での、また貧困の中におかれての、日教組員個々人の力量に対する判断の甘さが目立つ。日教組五十万人の大部分は、現在文部省の指導要領を否定し、自らの教育課程を組み得る力量を持ち得ない状態に置かれている。だからこそ当初のの如き発言も生まれて来るというこの現状で、藤山のこの答弁は、遂に答弁にならないのである。
どうも、場違いなことを書いたが、この藤山流の抵抗論が、まだまだたくさん、進歩的だといわれる教師の中にあるように思われてならない。我々が今これを突き破らなければ、日教組の斗いは自殺に等しいものとなるだろう。
我々の階級の為の教育、その目標とプログラムをこそ、今、明確にうち立てる必要がある。それがなければ、改訂指導要領は大手をふって日本中に浸透するだろう。
|
|
|
| ■道徳教育と文学教育………小沢雄樹男(「文学と教育」第9号 1959.7) |
(…)
私たちはこう考える
私たちのサークルは、その発足以来、最初の三回のゼミを改訂指導要領・国語科編の検討に当てました。そのなかで、この特設「道徳」と国語科との関連を問題にした際に、次のようなことが話題になりました。「理論的な理由も法的な根拠も考えらえないのに、道徳の時間を特設するについては、十分政治的意図があり、それが修身科を復活させる一過程であることは疑いない。それがいずれ改悪されて、いっそう修身化することは必然だ。いかなる形でも特設道徳を認めることは、そうした、政治プログラムに組み入れられることになる。」
この特設道徳はけっして認めないという立場の考え方をもう少し整理していえば、一貫していることは、この立場の教師は、人間の主体性の確立を道徳教育の根拠と見なしている、ということであります。
第一に、この立場に立つ教師は勤評[勤務評定]と道徳教育とは全く内的に結びつく、と考えています。勤評に対して、主体的な抵抗を示さない人間が、道徳教育をやれるはずがない。勤評という人間の主体性と自由を奪いとろうとする力に抗して、人間の品位──自由と主体性を守ろうとする抵抗の精神なくしては、人間を前進させるべき道徳の教育はなりたたない、と考えるのであります。ですから、特設「道徳」を既成事実としては受取らない。また、道徳教育は、人間の主体性の確立の教育である、という意識は、必然的に組合運動・政治運動との結びつきを持ってくることになります。
第二に、一方、こうした考え方は当然人間疎外の条件への深い憤りとなり、その条件の排除のために、まず人間そのものをきわめて人間的に育て上げようと志向する。だから、ここでは既成の徳目のワクに子供をはめこむとか、あるいは、ある階級のためにのみ有利な階級社会の道徳、既成道徳は否定され、それぞれの階級に固有な道徳を自ら創造してゆくために、まず、人間が人間としての〈主体性〉を回復することが要求されるのであります。
この次元において、はじめて文学教育は、人間回復の教育として道徳教育に結合されるわけであります。
しかるに、特設道徳実施以来の一年余、道徳教育と文学教育は、まことに奇妙な関係をつくりつつあるように思われます。
文部省の要求としての「道徳教育への文学作品の利用」という要求と、それに応えての「道徳教育のための童話何年生」式の本の流行。それを追い求める教師、これに手をかす児童文学者、あるいは文学教育者と自称する人々もかなり見うけられます。ここには、原則性を無視して末梢技術化した、道徳教育と文学教育のそれぞれに功利的な、利害関係からの野合とも言うべき結びつきが見られます。こうした野合から何が生まれるかは、言うをまたないでありましょう。
文学教育とは何かということが、ここで重要な問題になってきます。私たちの《サークル・文学と教育の会》で話し合って来たことは、文学の本質的機能は何か、そして、それに即して文学と教育との結びつきはどこに求められるべきか、という点でした。それを認識論的に探究し、それを各々が実践して裏づける、という学習の方法をつづけて来たのであります。(…)
|
|
| ■第八回全青教別府集会報告………福田隆義(「文学と教育」第10号 1959.9) |
[東京サークル報告と指導要領批判]という一章があります。
|
|
| ■文学教育は子供の認識をどう育てるか………熊谷 孝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
1.学習指導要領と文学教育
文学教育のいとなみを、たんに情操陶冶の手段として考えるとき、それは国語教育にとって第二義的なものとならざるをえません。
第二義的なもの……つまり、付属品です。アクセサリーです。
しかし、アクセサリーもまた一種、生活の必需品であるという意味で、それは珍重され、同様にしょせんはツケタリにすぎないとい意味で貶められます。ともあれ、「経験を広め心情を豊かにする」情操教育としての文学学習は、国語教育にとってアクセサリー以外(あるいは以上)のものではありません。
そういうつかみ方、おさえ方をするものですから、学習指導要領では、文学教育を文学教育としてではなく、たんに文学学習 としてしか考えておりません。
いいかえれば、それは、数多くの国語学習領域のなかの一領域――いや、さらにその領域のなかの従属的な一小部分にすぎないというわけです。本筋において、それは文学教育の否定にほかなりません。というのは、文学教育がそれ自身、一まとまりの体系をもった教育活動であることが、そこでは否定されていることになるのですから。(…)
|
|
| ■改訂指導要領の文学観………荒川有史、鈴木 勝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
改訂指導要領にたいする批判は、その発表後、さまざまな角度からなされてきました。しかし、それらの批判は、指導要領のワク組をすっぽり肯定したうえでの、部分的な、表面的な修正に終っているようです。
たとえば、国語教育を、「聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの学習」の四領域から成りたつと規定しますと、文学の学習はその四つのうちの「読むこと」のなかに限定されてしまいます。そのうえ、伊藤整氏がいうように、現存の秩序を否定しよりよき未来への展望を明示するという文学特有の機能は完全に無視されてしまいます。みにくい現実には目をつむり、あたえられた秩序のなかで生きていく人間、そういう人間に慰さみとなるような教養としてのみ、文学はその生存権を許されているようです。このワクのなかだけで、思考力をどのように伸ばすか論じてみてもあまり意味はないと考えます。
また、すでに多くの人が指摘しているように、読みものは、文学作品に片よってはいけないが、古典には関心をもたせるように、という指示などに、根本的な疑問を感じます。
古典は、文学としてではなく、教訓のために、つまり道徳教育の素材として活用せよ、というわけでありましょう。それはさらに“君が代”の復活と見あう国民的自覚、ニュールックの国粋主義を核心とする国民的自覚の尊重へとつながっていくのでありましょう。
人間変革とはなんらふれあうところのない国民的自覚。それに奉仕することを要請されている国語教育。これが改訂指導要領の基本線です。ですから人間のしあわせをねがい、人間を無気力と停滞からときはなす文学教育が、「要領」の国語教育に正当な位置を与えられていないのも当然なことかもしれません。
実践面での計画設計にも、古い文学感覚と照応する児童観がハバをきかせております。ここに登場してくる児童生徒は、全国共通の顔をもっており、一年ごとに、同一歩調で成長していきます。成長の方向も進度もあらかじめ決定されているのです。それぞれの社会における人間関係や家庭環境のゆがみが、全国的にも年齢的にもはなはだしい落差をうみだしていることを捨象し、予定調和の机上プランを提出しているわけであります。
弁証法的な思考による以外、この複雑な現場を処理できないはずなのに、例えば、英語の原級、比較級、最上級といった作文上の表現だけで処理された指導プランが、はたしてどんな役に立つというのでしょうか。
こうしたさまざまな不合理を根底から是正するためにも、指導要領の文学観の批判をとおして、国語教育のなかに文学教育を明確に位置づけていきたいと考えます。読解ブームといわれる奇妙な現象も、その地点で同時に批判できるのではないかと考えます。
|
|
| ■集団の自己紹介………鈴木 勝(「文学と教育」第15号 1960.4) |
私たちの《文学教育研究者集団》は、一九六〇年二月二六日に出発した。が、その母胎は、すでに五八年の夏に出来上っていた。勤務評定・道徳教育実施要項・改訂学習指導要領等々一連の文教政策が次々とうちだされた時期においてである。私たちは、《サークル・文学と教育の会》に結集し、次の仕事を設定した。
──「とくに、学校教育の面において文学教育がおしゆがめられようとしている、こんにち、私たちは、まず《国語教育のなかに文学教育を位置づける》ことから、仕事をはじめていきたい。当面の課題をそこに求めて学習活動をつづけると同時に、一方では、たえず、学校教育のワクを越えたところで活動をおし進めることで、《明日の民族文学創造の基盤》を確かなものにしよう、と考えるのである。」
──「サークル文学と教育の会は、よりよい文学教育の実践をめざした《文学と教育の学習》のための集いである。他のサークルとの交流や、文書その他による対外的な活動も、先に予想している。」
私たちが最初にとりあげた仕事は、改訂学習指導要領(国語科)への批判である。改訂が国民的自覚という視点からとりあげられているにもかかわらず、それが国粋主義につながるものであること、発達段階に即した系統性といっても人間を固定した角度から生物学主義的にとらえる基準にしかすぎないこと、したがって、こうした視点、こうした論理のもとでは、文学教育は片すみへ追いやられ、人間形成、人間変革といういとなみは完全に無視されてしまうこと、等々が真剣に検討された。
指導要領批判をきっかけとして、“国語教育の機能的本質と役割”“国語教育としての文学教育”“道徳教育と文学教育”“古典教育の視点”などのテーマで、《国語教育のなかに文学教育を明確に位置づける》仕事を追求しつづけてきた。また、文学と科学におけるそれぞれの認識表現の機能にまでわけいって教育のあり方を反省した。
この活動の成果は、その都度、十四号まで発行された、ガリ版刷りの機関誌“文学と教育”に発表された。さらに、文学教育の会理論部会、全国青年教師連絡協議会文学教育部会、日本生活教育連盟国語教育部会などにサークルとして参加し、多数のナカマとの話しあいのなかで、わたしたちの理論を普遍化することに努力した。それらの参加報告は、『文学教育』『カリキュラム』『生活教育』『広場』に、あるいは『講座文学教育』『生活教育の系譜と課題・第八集』に、正確にまとめられている。
これらの報告に一貫していることは、文学研究の水準が文学教育実践を豊かにもし、ひからびたものにもするという姿勢であろう。サークルを構成するメンバーの一人一人が利害をはなれて研究し実践したことが、サークルのこの姿勢を保障したと考えられる。
が、さいきん、私たちは、自分たちの『純粋さ』について、深刻な、私たちの全存在をゆさぶらずにはおれないような、疑問を感ずるにいたった。
私たちは、文学教育運動の統一のために、文学教育の会に積極的に参加していたのであるが、講座刊行後の質的な発展を期待して、一九六〇年三月に、“文学教育と芸術的認識”のテーマのもとに、文学教育研究集会をもつことを提案した。サークルの共同提案は、常任委員会・集会準備委員会によるさまざまの修正をふくみながらも、今年の一月末には可決された。ところが、私たち自身に行動性というか、機動力を欠いていたことと、(私たちの側にあったところの)非生産的な感情とがあいまって、せっかくのこのプランを流産させてしまった。
さらに、流産の共同責任を分ち合うべき常任委員会では、「初めから、こんなプランは実現させるつもりはなかった。言葉として賛成はしたけれど、だから適当に掻き回したり、いなしたりサボタージュしていたわけだ」という、聞き捨てならない侮辱的な言辞をさえ浴びせられた。
その瞬間、私たちはこの会に見切りをつけた。というより、こうした人々と行動を共にともにして会を盛りたてていく自信を、そこに求めえなかった。
そして、この敗北の体験を、いかにもしてプラスに転化させたいと考えた。マイナスをプラスに転化する手がかりを、ナカマとの体験の交換・交流という、この四月集会に求めた。
文学教育研究者集団
これが、私たちの新しい出発に対して、みずから与えた名まえである。(…)
|
|
| ■《声明》灘尾文相「国防発言」に抗議する………(「文学と教育」第49号 1968.1) |
昨年末、一二月二九日「国防意識の養成を」(朝日)「小学生にも国防意識を」(毎日)など、各新聞が一斉にトップ記事として扱った、灘尾文相の発言は、教育の軍国主義への意図を露骨に示したことを意味する。われわれは、日本の将来のために、厳重に抗議する。
戦後、日本の教育が、大きく曲がったのは、一九五〇年である。この年、朝鮮事変が勃発し、警察予備隊が創設され、第二次米国教育使節団が来日した。それと呼応し、文相の「君が代」についての通達、修身復活が世論をわかせた。
その後、日本の再軍備、そして、軍国主義への傾向は急速にたかまった。そのなかでも特筆すべきは、一九五三年、池田・ロバートソン会談である。アメリカの再軍備要請に答え「日本政府は教育と広報を通して愛国心と自衛のための自発的精神を養う空気をつくることに第一の責任を持つものである。」と約束をして帰ってきた。
その発想に基づいて、一九五八年、学習指導要領の全面改訂が行われた。「愛国心」を「国民的自覚」とか「国土や文化に愛情を云々」と表現した。いわゆる三三年度学習指導要領である。
さらに、昨年一一月、佐藤首相が、安保改定への下ごしらえにアメリカに行った。そしてジョンソンと話しあい「みずからの国をみずからの手で守る気慨をもて」というみやげをもって帰った。今回の灘尾文相発言「国防意識云々」は、たんに文相個人の放言ではない。一九七〇年安保再改定へむけての、政府と自民党の段階的、組織的な文教政策の一つのあらわれである。その証拠に、一九六五年から、極秘裡に国防意識をふくめた教育課程の改訂が進行してきたし、それに伴う教科書検定が予定されている。
まさに、昭和初年、満州事変前夜の様相を呈してきた。
我々は、一九四六年「日本国憲法」を制定し、独立、平和、民主主義を民族の課題として再出発をした。今回の灘尾発言は、それとまっこうから対立し、アメリカのアジア政策に従属した日本の再軍備を直接教育の場にもちこむものである。我々は、政府と自民党、そして、その端的なあらわれである灘尾発言に厳重に抗議する。と同時に、進行中の「学習指導要領」改訂の方向に反対であることを声明する。
一九六八年一月一日
|
文学教育研究者集団委員長 福 田 隆 義------
|
|
| ■国防意識に結びつく改訂学習指導要領の問題点(座談会)………(「文学と教育」第49号 1968.1) |
歴史の決定的瞬間
熊谷 今日の座談会のテーマは、〈政治と教育〉というようなことです。といっても、何も政治と教育の問題一般について抽象論議をやるために僕たち集まったわけじゃないので、非常に切迫した具体的な問題をかかえているわけです。学校教育に安全保障の問題を、小学生のうちから国防意識を、という灘尾文相の発言です。出来れば学習指導要領にもそれを織りこみたい、という自民党右派政権の移行をストレートに代弁した、あの「政治」的な発言です。これに、しんそこ から怒りをおぼえて、「相手がその気なら、よし、こちらもやるぞ」という気持で、きょうここに集まったということですね。先年の安保闘争のとき、若い友人が口にしていた言葉なんだけれども、あと七,八年もするとウチの子どもも高校へ行くようになる。その子に、「安保のとき、パパは何してたの?」と聞かれてヘドモドしないように、今度はやるよ。親として恥ずかしいからな。それで、傍観者の見本みたいだったこの友人が行動にふみ切ったのですが、そのとき 行動にふみ切れなかったら悔いを後々に残すに違いないような、そういう歴史の決定的瞬間 というのがあるんだ、と思います。今がそういう瞬間なんだ、と僕は思いますね。とくに、教師である人間にとってはね。そういうわけできょうの話し合いは僕たちが具体的にどういう行動を選びとるか、という実践的課題に関して現実認識、あるいは現状分析をたしかなものにし、自分たち自身の足場を見さだめるための会合だ、ということになります。自分たちの持ち場と任務をハッキリさせるため、といってもいいんですが。(…)
“ある朝、突然に”ではない灘尾発言
F こんどの指導要領の改訂は、七〇年の安保の年へ向けての改訂だと思いますが、これまでの何回かにわたる改訂にしたって、日本の対外従属、再軍備の動きと結びついたものだったのですね。そしてそのつど、謳い文句をじわじわ、たとえば〈愛国心〉から〈国防意識〉へ、というぐあいにエスカレートしてきた。〈君が代〉を必修歌唱にしたかと思うと、〈日の丸〉を学校行事に、国民行事に掲げるようにする。そして、オリンピックだ、明治百年だ、万国博だと既成事実の積み上げとムードづくりをやる。そのあげくの、こんどの灘尾発言ですよ。文教研の冬季合宿研究会から帰った翌朝、十二月二十九日でしたね、朝刊であれを目にしたときは本当にショックでした。Nさんが最初かな、つぎつぎに文教研のメンバーから電話がありまして、「さっそく抗議運動をやろう」とか、「機関誌の次号を“抗議特集”といこう」とか、「歳末だが明日にでも集って抗議の方法を考え合おう」という電話なのです。思いは、だれも同じだなと、文教研のナカマたちへの信頼感を深めましたよ。
N 灘尾発言はショックだった、とおっしゃったけど、確かにそうなんですけど、でも私としては何だかハッキリして、かえってよかったみたい。相手の本心はこうなんだろうと、今までは憶測のかたちでしか言えなかったことが、これからはハッキリ言えるでしょう。指導要領でいう〈国民性の育成〉だの〈愛国心〉というのが実は〈国防意識〉のことなんだ、ということをズバリ向うから種あかし してくれたわけですもの。現場の弱い部分にはマイナスに影響するでしょうし、問題の一つはその辺のところにありますけれどもね。……教育課程審議会の答申がなされたのは去年の十月三十日で、この三月に新指導要領が発表されることになっているようですが、そのちょうど間(あいだ)を縫って灘尾発言があったわけですね。まだ間(ま)があることですし、あきらめないで、今からでも発言の実際の内容がどんなに怖しいものか、その危険性を明らかにして反対運動を盛りあげていったら、〈国防〉がどうのこうのということを指導要領に書きこむような、憲法違反の教育体制への道を阻むことも不可能ではないし、少なくとも現場における教育活動の実際面で防げるわけでしょう。
A 指導要領改悪阻止の運動はむろんやらなければならないし続けなければならないけれど、たとえ不幸にして改訂が実現したとしても、やはり反対運動は続行しなければならない、ということじゃないですか。悪法も法なり、ではいけないのであって、悪法はやはり撤回させるまで否定しつづけないといけない。それのどこがおかしいのか、そのおかしな点を明確にしてそれと闘いつづける、という姿勢が必要だと思います。
F 賛成。灘尾発言にしたって、偶然にあの日の朝に行なわれたってなものじゃなくて、長い年月をかけて、あんな恥しらずなことをヌケヌケと発言できるだけの土台づくりを、ちゃんとやっているわけですからね。アチラさんのそういう粘り強さを、僕らも見習う必要がありますね。(…)
|
|
| ■指導要領改悪史………福田隆義(「文学と教育」第52号 1968.6) |
1.指導要領との出あい
昭和二十二年、それは、わたしが初めて給料をもらった年である。“終戦”という開放感もてつだってか、ある種の期待と希望をもって、田舎の小学校につとめた。が、そこでわたしが、まず狩りだされたのが「再教育講習会」であった。アメリカの占領政策による、洗脳講習会である。
わたしは、そこで、たいへんめんくらった。「コース・オブ・スタディ」とか、「カリキュラム」あるいは、「ユニット」だの「ガイダンス」などなど、敵国語であったはずの、片仮名の氾濫に、である。
それら、片仮名の意味は、今だによくわからない。が、なんとなく、そうしたウズの中にまきこまれていった。そして、なんとなく、自分の視野が広まっていったように思えた。と同時に、アメリカという国が、すばらしい国のようにさえ思った。まさか、ベトナムで、あれほど非人道的な行為をしようなど、夢にも思っていなかった。
ところで、その頃の教育思潮が、アメリカから直輸入した、プラグマチズムによるものである、ということを知ったのは、十年もたってからのことである。つまり、文教研機関誌『文学と教育
創刊号』に、「改訂学習指導要領(三十三年版)批判」を特集したときである。そのとき、「二十六年版」と「三十三年版」とを、たんねんに比較検討した。しかし、わたしが初めて給料をもらった年にでた、いわゆる「二十二年版」は、つい、きょうまで、批判という視点では読まなかった。
そして、二十年たった今は、資料にさえこと欠く。以下、国語科学習指導の目標にしぼり、資料という意味もふくめ、順をおって紹介しよう。
2.国語科学習指導の目標(資料一)
(1) 昭和二十二年版(試案)
(…)
(2) 昭和二十六年版(試案)
(…)
(3) 昭和三十三年版
(…)
(4) 昭和四十三年版
(…)
3.「国語教育」アメリカ版
戦後の教育、ないし、国語教育について、波多野完治氏は、次のように説明している。
「戦後の日本の教育は、国語教育をも含めて、アメリカ教育思想のもとに成立したわけですが、言語技術、すなわちランゲイジ・アートの考えは、アメリカ初等教育における国語教育のあり方からきています。アメリカでは、国語(英語)の教育も、アメリカニゼーションの立場からとり扱われてきました。アメリカ国民を形成する現実の民衆は、外国からきたものと考えて、彼らを、アメリカ国民として最小限の実生活をいとなみうる程度にまでしあげていく。ここに、教育の目的と必要を見いだしたわけであります。こうして、言語政策および言語教育がアメリカニゼーションの重要な役割をになうことになったのでした。」(『第二信号系理論と国語教育』)
昭和二十二年版の「あらゆる環境におけることばのつかいかたに熟達させるような経験を与えること」という目標は、国語教育のアメリカ版といえないだろうか。わたしたちは、かつて、この考え方を「場面言語の技術主義」と批判した。つまり、「あらゆる環境」に適応できるような、言語技術を、というのである。したがって、国語科の学習領域も、「話す・聞く・読む・書く」という、言語現象からの設定、ということになる。
わたしはかつて、「電話ごっこ」や「お客様ごっこ」で、国語教育をしたつもりになっていた。「ごっこあそび」で、実生活のヒナ型を、と考えていたらしい。それは、電話をかけるという場面の、あるいは、来客・訪問という場面での言語技術の指導でしかなかった。
多民族国家であるアメリカでは、「最小限の実生活をいとなむため」に、こうした言語技術と経験を、子どもに与える必要があったであろう。が、この言語技術主義・実用主義からは、しっかりした、考える子どもは育たない、ということは明かである。そこには、変革の姿勢がまったくない。生活に適応し、大勢に流され、体制に順応する人間しか育たない。このプラグマティズムのなれの果が、「夢にも思わなかった、ベトナムでの非人道的な行為」となったといえないだろうか。
ところで、この技術主義・実用主義は、二十六年版には、「ことばを効果的に使用する」技能と能力というかたちで受け継がれ、さらに、三十三年版、四十三年版にも一貫している考え方である。
4.ファシズムのニュー・ルック
ところで、「あらゆる環境におけることばのつかいかたに熟達させるような経験を与える」国語教育では、大勢に流される人間しか育たない、といった。体制に順応する人間しか育たない、ともいった。というのは、独占資本の体制下という環境になれば、それに順応し、さらに、その終末段階であるファシズム体制下では、また、それに順応する、という結果になるからである。
いつ、誰がつかいはじめたかは知らないが、国語科に、「価値目標」というのがあるらしい。それは、言語技術や能力面からの目標に対してのいい方だそうである。たとえば、三十三年版の「思考力を伸ばし、心情を豊かにする」とか、今回、四十三年版び中教審答申にあった「国民性の育成云々」などが、それになる、というのである。
そして、その「国民性」は、「最近の政治的・経済的情勢に応じて、『国民性』という形で打ちだされてきたものであると、わたしには思われる。」(現代教育科学、一九六八年一月号)他人ごとのようなかきぶりだが、今回の改訂の理論的指導者であるといわれる輿水氏の論考からの引用である。
一方では、言語技術主義の教育を、そして、他方では、「価値目標」と称して、政治的・経済的要請に応じた内容を、ということになる。それが、ごく巧妙に軍国主義へとエスカレートしているのが現実である。
しかし、こうした動きは、今、はじまったことではない。わたしたちは、すでに、三十三年版「改訂指導要領」の、こうした動きに対して、「ファシズムのニュー・ルック」と批判した。また、それ以前の、二十六年版・二十二年版にも、こうした方向への可能性が内包されていたわけである。
次に、この「価値目標」の具体的内容となって、教科書に強い制約を加えている、話題・題材選定の観点を列記してみる。資料という意味をふくめ、二十二・二十六年版は、全文を引用する。
5.話題・題材選定の観点
(1) 昭和二十二年版(試案)
(…)
(2) 昭和二十六年版(試案)
(…)
(3) 昭和三十三年版
(…)
(4) 昭和四十三年版
(…)
6.現実はもっと厳しい
二十二年版・二十六年版が、試「案」であったのに対し、三十三年版以後は、「基準性」をもたせ、より強力な制約を教科書に加えてきた。さらに、いわゆる「価値内容」といわれるものからみても、「自由」とか「平和」という、最も基本的な理念が消され、それにかわって、「道徳性」とか「国民的自覚」(三十三年版)あるいは、「日本人としての自覚」とか「愛国心」(四十三年版)が、うちだされてきた。が、ここで、わたしが、いちばん強調したいことは、そうした、ことばのうえの変化より以上に、現実はファッショ化の方向へ進行している、ということである。
文相の「国防発言」、農相の「原爆発言」、さらに、防衛庁長官の訓辞、等々、その裏付け資料にはこと欠かない。
いっぽう、「今後の国語指導法は、いわば、もっと、戦前の形象理論的、あるいは解釈学的な指導過程を取り入れることになるだろう。」(前記、現代教育科学)という、輿水発言を媒介して考えるとどういうことになるのだろうか。
解釈学による指導過程、それは、あの戦前、戦中の国語教育界を支配した、追体験方式の指導過程である。(この点については、黒川氏の論考参照)「国防意識」を追体験によって昂揚しようというのである。
戦後、国語科学習指導要領の変遷をたどってみて、わたしは、次のような結論をえた。
「あらゆる環境におけることばのつかいかたに熟達させるような経験を与える」ことで出発した、言語技術主義も、「電話のかけかた」などという、場面に限定して考える範囲では、まだ、罪はあさかったといえよう。が、しかし、この理論は、根なしぐさである。ひとたび、その環境が、独占資本の支配体制、そして、ファッショ体制へと、エスカレートしたばあい、そのエスカレートした環境にも適用できる論理である。そして、適応する言語技術を身につけることになる。
それが、指導要領の改悪というかたちで具体化してきた。つまり、体制側の「価値」を追体験によって昂揚させようというのである。そして、指導要領の表現より、現実は、ずっとずっと先を突っ走っている。
さらに、その方向を裏側でコントロールしているのが、アメリカの世界政策である、ということをつけ加えなければならない。
|
|
| ■私たちの立場と課題………福田隆義(「文学と教育」第59号 1969.8) |
【文教研第18回全国集会特集号 巻頭言】
今回の学習指導要領・国語科編の改訂は、戦後の国語教育を一貫している、言語技術主義・実用主義の立場に、はっきり「国民性の育成」という方向を与えたといえます。それは、国語教育を「国防意識高揚」の手段とする発想であり、明らかに七〇年以後を想定した改訂であるといえます。そこでは、言葉は「お上」のもの、そして、上意下達の道具になってしまいます。上意下達の道具、それは、戦前・戦中の発想そのものであり、「人間破壊」「人間喪失」の教育を復活させることになります。
こうした体制側の露骨な反動化に対して、わたしたちはどう対処したらいいのでしょうか。ある人たちは、直接行動で対決しようとしています。またある人たちは、指導要領とイデオロギー主義的な対決をしようとしています。が、果してそれが有効な方法であり、適切な批判であるかどうか、今この時点でもう一度、真剣に考えなおす必要を痛感します。
文教研は、創立以来十一年間、一貫して指導要領を批判し続けてきました。それは、部分修正意見などではありません。また、たんにイデオロギー主義的な批判でもありません。いつも、その根底にある言語観・文学観を問題にしました。そこが狂っていたのでは、まともな国語教育が実現するはずがないからです。そうした観点から指導要領を批判する一方、わたしたちは、わたしたち自身の言語観・文学観を変革し確立する学習を続けました。そして、理論的にも、論理的にも、さらに実践的にも、指導要領と対決できる自信を深めました。
わたしたちは、言葉を「お上」のものから、自分のもの、あるいは、自分たちのものに取り戻さなければならないと考えます。というより、言葉はもともと、わたしたち民衆のものであります。生産・労働の過程で、民衆の連帯・民族のあすの創造を保障してきたのが母国語であったはずです。自分の言葉に、あるいは、自分たちの言葉に、──これが文教研年来の主張である「文体づくり」ということであります。
今次集会[文教研 第18回全国集会]も、そういう発想で立案しました。つまり、あすに生きる民族の子を育てるために、今、国語教育は何をすべきかを、言葉の機能・文学の機能に即して突きつめてみようというのです。
第一部「私の大学」では、わたしたちめいめいの言語観・文学観の変革・確立をというわけです。そのうえにたって、文学教育の構造化を考えてみました。さらに、第二部「国語教育で何をするか」では、国語教育のなかで文学教育をどう展開するかを、具体的に提案し、ご批判をいただきたいと思います。
|
|
| ■国語教育課程の新改訂に思う………夏目武子(「文学と教育」第99号 1977.1) |
【巻頭言】
(…)「教育課程基準の改善と新国語教育の課題」(「国語教育」臨時増刊'76.12/明治図書)を手にした。何らかの意味で、国語教育に関して一家言をもっておられる41氏が意見を寄せられている。「こんどの改善で、理解・表現という国語科の伝統的な考え方に立ち戻った」という全面評価もあれば、二領域・一事項という教科構造を認めた上での部分的批判はあったが、「文学教育」と表題に明示することで、文学教育を問題にされたのは、41氏中、熊谷孝氏だけであった。氏は、国語教育は「母国語に関しての言語操作の仕方の教育」であり、「典型という意味での言語形象以外のものではない文学にかかわる教育活動──文学教育」は、当然、国語教育の体系的一環であると、テーゼを出すことで審議会まとめを批判されている。
教師も生徒も自分のことば=文体をとりもどすために、私たちは自主編成という形で文学教育に取り組んできた。神奈川県教研で、今年やっと、小学校でも教師が文学教育意識をもつ必要性が確認された。第26次全国教研では、大前提である教科構造論について討議する場がほしい。参加者全員で、文学教育が国語教育にどう位置づくのか、考え合いたいのだ。指導要領改定期には、便乗主義が横行する。自分の人間を失わないためにも、改めて自己の言語観、文学観を問いなおす、そんな機会にしたいと思う。
|
|
| ■「教育課程の基準の改善について」を読んで………(「文学と教育」第99号 1977.1) |
10月7日の朝刊に教育課程審議会の「教育課程の基準の改訂について」のまとめが発表された。朝の職員室はこの話題でにぎわう。新聞に発表されたのは要点だけであり、まとめの全文を見たいという声が多かったが、学校中どこをさがしてもそれはなかった。第一線で教育にたずさわっている教員が知らないところで、教育内容が決められる、という感が強い。市販の11月号の教育雑誌(10月刊)にまとめの全文がのっており、それを入手することで全貌を知ったという次第だ。
全文を読んでの感想。なぜ改善しなければならないかの理由が明確でない。従来のものでは、どういう欠陥があるのか、この方向に改めた場合、それが克服できるのか、こういう方向をとったのは、たとえば、民間教育研究の成果をとり入れた結果なのか、周辺諸科学、国語教育の基礎となる学問の新しい成果をとり入れたのか、児童、生徒そのものの変容に対応させるものなのか、その辺を明示する必要があるのではないか。
指導要領が変わるたびに、教師が納得しないままに、もし自分の教育のあり方を変えるのだとするなら、教育不在と言わなければならない。教師の主体性ぬきに教育は考えられないのではないか。
そのことと関連するのだが、指導要領はもっと大まかなものでよい。このことだけは落とさないようにという留意事項というか重点事項だけを示せば事足りると思う。ここの教師の言語観を一方的に規定してしまうことは、教師の意欲をなくすだけで、教育効果は上がらないと思う。
そうした前提に立ってのことであるが、そして、審議のまとめだけではよくわからないことが多々あるが、現時点で私なりに考えたことを何点か記してみる。(…)(T.N.)
|
|
| ■文学の創造と文学教育──テスト体制下の国語教育と文学教育………熊谷 孝(「文学と教育」第101号 1977.8) |
(…)
5.テスト教育方式の新学習指導要領案
文部省の新学習指導要領案は、もともとテスト体制の胎内から生まれたテスト教育方式のカリキュラム案、指導案なのですから、一つの正解は出しにくいような(もしも出したら自壊作用を結果するような)公害問題などについての学習指導は、触らぬ神で避けて通る、というカリキュラムを打ち出しています。直接、国語科についていえば、文学教育は敬遠です。敬遠 かどうかわかりませんが、用語としても“文学教育”というような言葉を使うことは避けて、また用語の問題としてだけではなしに、実質的にも、主題が何、感動点はここ、と一つの正解が出せる(?)読み方指導(読解指導)方式の文学の授業の採用を提示(=指示)しております。
先生も気の毒なら、生徒諸君も気の毒です。以前もそうだったけれども今後とも、文学の授業は一向に「改善」されないのです。扱う文学作品に関して、教師は、到達目標を明確にするという大義名分に縛られて、一つの正解を用意してそこへ生徒の理解を、落ちこぼれなく 追い込まなくてはなりません。生徒の方はまた、なぜ自分の実感を自己否定しなければならないのか納得のいかないまま、教師の言いなりに、「この作品のここのところは、すごく感動的でえーす」というふうに答えないと、いい点が貰えません。内申書のことを考えると、自分の実感をぐっと抑えて、ということになります。どうも、大へんなブンガクの授業です。
もっとも、これは、先生方が学習指導要領に順応してたてまえ 通りにやればの話です。たてまえと本音(ほんね)は別、というのが一般ですが、本音イコールたてまえという形で、“一つの正解”を生徒に押しつけるような教師も、数多い教師の中にはいないこともないようです。文学教育を否定して、文学作品の読み方指導を主張する一群の教師たちです。自分の政治的・教育的イデオロギーと、自分自身の実際の教育理論や教育実践との矛盾、自己矛盾です。
何でこんな指導要領改訂案が評判がいいのか、僕には全く理解がつきません。いけないのは、君が代を国歌だといっている点だ、公害問題をはずしたことだ、あとは大体まあまあだ、といった見解や意見が民間教育の側でも通り相場になっているというのは、僕にとっては解(げ)せないことの一つです。(7月27日校正の折り加筆。/世論に押され公害問題復活の由。指導要領の声価、倍増か。)
決して文学教育セクトで言うんじゃありません。国語科における文学教育疎外──このことを何とも感じないというセンスは、狂ってる。テスト体制の論理を、頭で否定しながら、それに胸をむしばまれ足を食われて、動きがとれなくなっている状態としか思われません。何年にも[わたって]、〈文学教育・文学作品の読み方指導〉という柱が日教組全国教研の討議の柱立てとして行なわれていることなども、水と油どころか、火に油、あるいは火に水みたいなものでして、ヘンな燃え方をするか、せっかく燃え上がろうとする火を消してしまうか、奇妙きてれつ な組み合わせだと思うのです。(…)
|
|
| ■改訂「学習指導要領」批判の質を問う………福田隆義(「文学と教育」第103号 1978.2) |
【巻頭言】
「ゆとりのある充実した学校」をキャッチフレーズに、改訂「学習指導要領」が告示されたのは、昨年七月二三日であった。以降、文部省側はマスコミを動員し、権力によって講習会を組織して、宣伝・伝達に狂奔した。そして、今すでに、移行措置をどうするかという具体性をもった問題で現場教師を拘束しはじめた。
今回の改訂が、国家主義的傾向をさらに強化したことは、「君が代」を「国歌」と規定したことに象徴される。この危険な方向は、世論の厳しい批判をあびた。けれども、国語科という教科に、その危険な方向がどう具体化しているかにまで言及した批判は少ない。組合教研の場でさえ、配当漢字は逆に増えている、「ゆとり」どころではない、あるいは「言語教育の立場を一層明確にした」といいながら、科学的・体系的知識を確実に与えようとする意欲がみられないなど、いわば指導要領の枠内での修正意見にとどまっている。われわれの批判は、たんに危険な方向を指摘するにとどめてはならない。指導要領の枠内の修正意見であってはならない。
文教研の前身である〈サークル・文学と教育の会〉設立第一回研究例会は、33年版指導要領の批判検討であった。そこで確認し合ったことは、字句の入れ替えや修正ではまにあわない、その根底にある言語観・文学観を問い直すべきだということだった。以降、43年、52年と改訂するたびに、指導要領の言語観は危険な方向に変質してきた。言葉を一方通行、つまり上意下達の道具とする危険な方向にである。
そうした指導要領を批判しきるということは、めいめいの言語観・文学観を確立すること以外ではない。伝達講習でもたじろがない主体の確立なしに、真の母国語教育は実現しない。この機会に、文教研の初心を確認しあいたい。
|
|
| ■文学教育と教師の鑑賞体験………夏目武子(「文学と教育」第104号 1978.5) |
【巻頭言】
本誌100号に、編集部の整理による文教研略年史が掲載されており、全国集会のテーマが一覧できる。それによると、第1回集会は一九六〇年、「文学教育理論の確立とよりよい実践をめざして」というテーマ。第20回集会までは同様に、文学教育、国語教育に関するいわば教育づいた 名前が付けられている。文学とは何かを問い続けることが、文学教育の原理・原則を実践的に考える原点であり、集会の内容もその精神に貫かれたものであったが、テーマの設定は教育面が前面に出されていた。が、一九七二年第21回集会から「文学史を教師の手に」という新たな発想で、基本過程としての作品把握が前面に出されるようになった。指導過程を含んだり、多少のジグザグはあったが、「芥川竜之介から太宰治へ」「文学史の中の井伏鱒二と太宰治」というように、教師その人の〈私の文学〉を求める場に、ひとりひとりの自己の鑑賞体験を実践的に確立する場に、集会は変ってきた。八月五日から四日間の暑い最中での、芥川文体、太宰文体、井伏文体との格闘・対話に、べつな汗を流したことが想起される。今回[文教研第22回全国集会]は長編小説との取り組みでまた汗を流すことになろう。
もう、文教研は教育のことを問題にしないのか? とんでもない。文学教育を否定する「表現と理解」という指導要領の二元論の立場からの声が大きい昨今である。私たちは文学教育研究者集団であり、今こそ文学教育の旗印を鮮明にする必要がある。が、問題は、その鮮明にする仕方にある。集会で他の鑑賞体験にぶつかり、自己の文体反応がいかにそっぽであったかに気付かされ、うちのめされることもあれば、眼前が明るくなることもある。その作品の新たなおもしろさの発見。他者との対話を通しての自己の発見でもあり、こうした自己変革なしに、相手の発想を変えることはできない。教師の場合、とくにそれが必要ではないかと、あらためて痛感している。
|
|
| ■文教研二〇周年に思う………福田隆義(「文学と教育」第105号 1978.8) |
【巻頭言】
文学教育研究者集団(文教研)の創立は、一九六〇年二月二六日である。が、文教研の前身〈サークル・文学と教育の会〉の発足は、一九五八年一〇月だった。一九五八年一〇月を起点にするなら、文教研はこの秋、二〇周年を迎える。
この二〇年間を一口でいうなら、着実に研究をすすめ、確実に成果をあげてきたといえる。私たちの究極の目的は、私たち自身が文学のわかる人間になることである。私たちめいめいが、母国語教育・文学教育と、子供たちの未来に責任のもてる教師になるためにである。しかし、それは容易なことではない。この二〇年間も、そこへ向けての自己変革の過程であった。ふり返ってみると、楽しい二〇年間であり、苦しい二〇年間でもあった。
私たちは、そういう研究の場を、ゴーリキーの言葉を借りて、文教研“私の大学”と呼んできた。修業年限もなければ、卒業もない大学である。“私の大学”では、ある時は文学教育という実践課題に即して研究をすすめた。またあるときは、一見教育現場を離れたかたちの研究をすすめることで、めいめいの文学と、その基礎理論を問い直してきた。教師としての主体性の確立をめざしてである。
ところで、教育界の反動化は、そのテンポを一層はやめた。主任の「制度化」の強行とともに、やたら「講習会」ばやりである。昨年は改訂された「学習指導要領」の伝達講習会。今年度になってからは、○○教育助言者講習会というのが、半強制的に行なわれている。教師の主体を剥奪し、上意下達の道具にしようというのである。
文教研は研究団体であると同時に、運動団体である。私たちには、こうした動向との対決が迫られている。二〇年の成果を総括し、広く訴えていくことが急務である。文教研二〇周年の課題にしたい。
|
|
| ■第30回全国集会を迎えるにあたって――今こそ文学教育を………福田隆義(「文学と教育」第117号 1981.8) |
【巻頭言】
戦後の国語教育は、その始発点に問題があった。47年(昭和22年)『学習指導要領・試案』には、国語科学習指導の目標を「児童・生徒に対して、聞くこと、話すこと、読むこと、つづることによって、あらゆる環境におけることばのつかいかたに熟達させるような経験を与えることである」と規定している。アメリカから直輸入した、いわゆる経験主義である。「あらゆる環境」に適応できる、言語技術の指導をというのである。こうした適応の論理のなかには、変革の論理にたつ文学教育は、位置づかないし、位置づけようがない。この指導要領の考え方は、当時、子どもを守る文化運動の一環として盛りあがりつつあった、文学教育運動とは相容れなかった。したがって、この民間の文学教育運動は、当然、指導要領批判でもあった。が、51年(昭和26年)指導要領の改訂には、残念ながらこの運動は反映されなかった。
ところで、子どもたちをとりまく「環境」は、50年朝鮮事変を契機に大きく変わった。52年警察予備隊の創設。54年自衛隊の発足と、アメリカ軍事戦略のなかに日本は組みこまれていった。。そうした既成事実の積み重ねによって作られた「環境」に適応させるための文教政策が、あの悪名たかい教職員の勤務評定であり、58年(昭和33年)指導要領の改悪であった。この改悪で、指導要領から「試案」の文字が削除され、法的拘束力をもって現場を縛りはじめた。ここでは文学教育どころか、小学校編からは「文学」という言葉さえ一切消し去った。体制側は順応し適応することを拒否する文学教育を恐れていたのである。文学のもつ人間解放・人間形成への機能を、感覚的にではあるがつかんでいたのであろう。それに代わって強調し強制されたのが「愛国心」の涵養であり、特設「道徳」であった。この改悪で、物語や伝記も「愛国心」や「道徳」教育のための手段とされてしまった。これらの施策は、いうまでもなく、60年安保改定へ向けての布石であり、締めつけであった。
こうした時代の動向、子どもたちをとりまく反動化の波から、子どもたちと文学教育を守り抜こうと決意して結成したのが、わが文学教育研究者集団である。以来、二十三年、一貫して子どもたちの未来と、文学教育を守り抜くための研究と運動をつづけてきた。しかし、それは容易なことではなかった。まさに闘いであった。体制側が拒否しつづけたばかりではない。日教組教研でさえ、文学教育という発想を公認しなかった。指導要領まがいの「文学作品の読みかた指導」という柱だてのなかに、われわれの主張を解消してしまった。この論理からは、有効な指導要領批判はうまれない。
さらに時代は反動化の一途をたどった。それに応じて、68年(昭和43年)と、77年(昭和52年)に指導要領が改訂された。改訂されるたびに右寄り路線、反動化路線と呼応し、それに適応するよう組変えられてきた。今や国語教育も、戦前・戦中とは違った、より巧妙なかたちで国防教育の一環に組みこまれてしまった感さえある。
そして、今回の自民党と、その御用「学者」による教科書攻撃は、その総しあげのつもりではなかったのか。ここでも、彼らの攻撃の矛先の一つは文学作品に向けられている。教科書から文学を抹消し、教室から文学を閉め出してしまわない限り、彼らは不安なのであろう。が、ここではもはや理不尽というより、狂気としかいいようがない。第一彼らは文学を文学として読んでいない。読めていない。われわれが批判しつづけたイデオロギー主義的な読みしかできないようだ。いうなら「鑑賞上の盲人」(芥川)である。文学教育をうけて育たなかった証拠といえよう。
こうみてくると、体制側は一貫して教育・国語教育から、文学教育を排除しつづけてきた。そして今や、文学教育をこうした反動化の攻撃から守り抜くことは、日本の平和と民主主義を守ることでもある。初心忘るべからず。第30回全国集会を迎えるにあたって“今こそ文学教育を”と訴えずにはおられない。
|
|
| ■教科書はだれのものか――学習指導要領について………樋口正規(「文学と教育」第150号 1989.11) |
(…)
今年の三月十五日に新学習指導要領が告示されました。多くの問題点を含むものですが、ここでは国語科に絞って考えることにします。
指導要領の文章というのは、おもしろくないし、わかりにくい。そこで解説書が出る。本屋さんには何種類もの解説書が並んでいますね。改訂の意義やら歴史やらが実に細かく説明してあります。大分売れているそうですが、一体誰が読むんでしょうか。――まあ、私も読みましたが(笑い)、多分、伝達講習会などで使われるんでしょうね。
国語科の目標を見ますと、小学校は「国語を正確 に理解し適切に表現する能力を育てる」とあり、中学校は「(同)能力を高める」となっています。それが高校では「こくごを的確 に理解し適切に表現する能力を身に付けさせる」となっているんですね。「正確」と「的確」都道違うのか、伝達講習会でもあったら質問してみたいと思います(笑い)、高校はもう「正確」でなくていいんですか、と。
今度の改訂で一番問題なのは、「教材選定の観点」ですね。小学校では復活、中・高では新たに加えられたわけですが、先ほどの教科書検定の「基準」と関連しますので、少し詳しく見ておくことにします。
(…)
ここで求められているのは“適応”の能力です。今の日本の社会のあり方をよしと認めた上で、それにうまく『対応』できる人間、どんなにひどい世の中でも「たくましく」生きていける人間、それが求められているわけです。なにか、あの入江進二郎(石川達三『熔岩』)みたいな(笑い)、社会の矛盾の根源に目を向けることをしない人間の育成がめざされているようです。つまり、臨教審以来おなじみの「国際化」という日本の現実、それにどう対応するかというところからの、教育課程の「改善」なわけです。
この「改善のねらい」は、当然、教科の内容に及んできます。国語の「「改善の基本方針」では、「特に、情報化などの社会の変化に対応するため」に国語の諸能力を養うのだと言い、「教材については、……道徳性を養うことにも資するよう配慮する。その際、特に、……たくましく生きる態度を育てること、……我が国の文化と伝統に対する関心や態度を深めること、……」と、教材選定の観点を示しています。これが、先ほどあの学習指導要領の記述に直結し、教科書選定の「基準」の拘束によって、教科書内容を大きく規定することになるわけですね。
国語の学習指導要領の基本的性格は、言語技術主義と道徳主義の抱き合わせと言ってよいと思いますが、その根底にある論理や国家主義に対して、厳しい批判の目を向ける必要があると思います。
(…)
教課審答申にも学習指導要領にも、「文学教育」という言葉は一度も出て来ません。そういう発想が全くないからです。しかし私たちは、「文学の人間回復の機能に賭けて、若い世代の“魂の技師”たろう」として、実践を積み重ねて来ました。国語教育としての文学教育の実現を当面の緊急課題として、自己の言語観・文学観を絶えず問い直しながら、共同の研究を進めて来ました。生徒たちの現実把握の発想を鍛えうるような、文体ある作品の教材化を抜きにして文学教育は始まりません。しかもそれは、教科書教材をひとつふたつ差し替えて自主教材を“投げ込む”といったやり方で実現できるものでもありません。
文教研は結成以来、学習指導要領を根底から批判し、文学教育を軸にした国語教育を提唱し続けて来ました。また、教科書教材の批判的検討、自主教材の発掘と教材化、文学教育の構造化に取り組んで来ました。教科書の改悪がますます強化されようとしている今、統制に反対する様々な運動とともに、自主編成意識に裏打ちされた研究・教育活動の広がりが強く求められていると思います。
(…)
|
|
| ■文教研創立の思い出………福田隆義(「文学と教育」第151号 1990.3) |
私に与えられた課題は、表記「文教研創立の思い出」である。文教研一九八九年度は〈明日へ向けて──文教研理論の形成過程をさぐる〉をテーマにスタートした。その第一回、九月例会では、集団創立のいきさつから、その前史にまで話がおよんだ。文教研の初心を確かめる必要からだった。が、ここでは、第一回全国集会(一九六〇年四月二三〜二四日・都下小金井市浴恩館)を中心に思い出をたどってみる。
文教研前史──サークル文学と教育の会
とはいっても、前史なしには語れない。文教研の前身として「サークル文学と教育の会」(一九五八年結成)がある。このサークルは、同じ目的をもつ二つの流れが合流し結集されたといえよう。その人的構成を時期的にいうなら、まず、熊谷孝編『十代の読書』(河出書房一九五四年刊)出版を機にうまれた「サークル広場の会」があった。そのメンバーと、熊谷氏が講師として参加されていた「全国青年教師連絡協議会」(全青教)文学部会の若い教師たちとが合流した。
ところで、同じく熊谷孝著『文学教育』(国土社一九五六年刊)出版記念会を機に、「文学教育の会」(後の文学教育連盟)が結成された。当然のことながら、熊谷氏をはじめ「サークル広場の会」の会員は、この会の会員にも登録。主要メンバーは常任委員に推薦され、主として理論部会を担当し、精力的に研究活動を推進していた。この時期、前記「全青教」の若手教師が加わって「サークル文学と教育の会」誕生ということになる。
その後も「サークル文学と教育の会」は、独自の研究会をもつ一方、「文学教育の会」理論部会と積極的に提携、共催の研究会も組織した。またあるときは、理論部会に提起した問題を、サークルでさらに深める、というような例会もあった。ともかく、そうした友好的な関係が、両者の間に約一年半つづいた。
集団の結成──一九六〇年二月二六日
正確を期すために、記録紹介からはじめよう。機関誌「文学と教育」一五号に、当時のいきさつがつぎのように記されている。
私たちは、文学教育運動の統一のために、文学教育の会に積極的に参加していた。〈略〉 一九六〇年三月に、“文学教育と芸術的認識”のテーマのもとに、文学教育研究集会をもつことを提案した。サークルの共同提案は、常任委員会・集会準備委員会によるさまざまの修正をふくみながらも、今年の一月末には可決された。ところが、私たち自身に行動性というか、機動力を欠いていたことと、(私たちの側にあったところの)非生産的な感情とがあいまって、せっかくのこのプランを流産させてしまった。
さらに、流産の共同責任を分ち合うべき常任委員会では、「初めから、こんなプランは実現させるつもりはなかった。言葉として賛成はしたけれど、だから適当に掻き回したり、いなしたりサボタージュしていたわけだ」という、聞き捨てならない侮辱的な言辞をさえ浴びせられた。
その瞬間、私たちはこの会に見切りをつけた。というより、こうした人々と行動を共にともにして会を盛りたてていく自信を、そこに求めえなかった、云々。 |
理論部会担当の私たちが提起した“文学教育と芸術的認識”というテーマでは、時期尚早(?)というのが表向きの理由だった。が、そういう問題意識が他の委員にはなかったのだと思う。
直接的には、右のようないきさつで「文学教育の会」の常任委員であったサークルの会員は、常任委員を辞任。たとえ少人数でもいい、もっと研究に徹しようではないか、研究に徹することで、文学教育運動を見直そう、そういう思いをこめて、サークルを「文学教育研究者集団」と改称して再出発したのは、一九六〇年二月二六日だった。
話は前に戻るが、この時期「サークル文学と教育の会」では、すでにあの悪名高い三三年版「学習指導要領」の問題点を洗い出し、根底からの批判を加えていた。そのうえで〈国語教育の機能的本質と役割〉へと研究をすすめた。また、熊谷氏の〈国語教育としての文学教育〉が提唱され、その路線にそって、〈仲間の体験をくぐるということ──科学と文学の二つの側面から〉さらには〈文学における典型の問題〉と、論理的な筋道だった追求をすすめていた。そうした積み重ねをふまえた上での“文学教育と芸術的認識”というテーマ設定であり、提案だった。
他方「文学教育の会」は、多様な考え方の人たちの寄り集りだった。後に“だれにでもできる文学教育”という主張に結びつく要因をふくんだ、現場主義的な姿勢が強かったように思う。そうしたくい違いに、私たちがもどかしさを感じていたことは確かだ。これが遠因といえよう。
文教研・第一回全国集会
それなら、われわれだけでやろうと燃えた。いうなら、「文学教育研究者集団」の旗あげ。だが、二月に発足したばかりの集団が、四月に全国集会をもとうというのである。しかも、可動人員は熊谷氏ほか七名。当然、講師や助言者として、集団外の方にお手伝いをお願いした。その交渉から準備は始まった。それでも提案・報告・司会・進行は八人で担当しなければならない。ダブルキャストどころか、三役も四役も分担、その準備におわれた。また、案内のチラシはできても配布ルートがない。遠い方には郵送。手わけをして教組の支部をまわって、協力を依頼した。今からふり返ると、考えられない強行スケジュールだった。
その甲斐あって、申し込みが八十名になったときには、ホッとした。が、集会当日、八名ではとても手がまわらない。熊谷氏ご一家が総出で、受付・接待を引き受けてくださった。そうした協力によって、第一回全国集会をなんとか成功させることができた。
といっても、後遺症は当分つづく。申し込んでおきながら不参加が続出。私たちの不馴れから、というより教師という肩書を信用し、参加費を事前に集めなかったことが、最大の原因でありミスだった。たいへんな赤字である。カンパと、それ以降の文教研会員への依頼原稿の稿料の一割は無条件に取りたてるという強行手段とで、穴うめをしていった。いうまでもなく、いちばんの被害者は熊谷氏である。暮しむきの楽な人はいなかった。が、“グチはいうまい、こぼすまい”を合言葉にして切り抜けた。(…)
|
|
| ■「文学教育の復権」を訴える………委員長 福田隆義(「文学と教育」第179号 1997.11) |
【巻頭言】
(…)
今ここで「文学教育の復権」を掲げなければならないことを残念に思います。と同時に、今だからこそ、積極的に私たちの主張をという、決意の表明でもあります。
というのは、最近、国語教育から文学教育を抹殺しようとする動きが目立つからです。といっても「学習指導要領」に、文学教育という発想があったわけではありません。読むことの、そのまた一部分として教科書に文学作品があったにすぎません。それをさえ非難し排除しようとした、自民党の教科書攻撃(『いま、教科書は……』自由民主党・一九八〇年刊)は、記憶に新しいと思います。が、あまりにも稚拙であり、論理のなさに執筆者も出版社もあきれたのでしょう。それらの作品は、今も教科書に健在です。
ところがここにきて、中央教育審議会や、教育課程審議会に注文をつけたり、それを支持する学会の動きが出てきております。たとえば、日本言語技術教育学会が要請した、中央教育審議会あての提言です。「『国語科』教育の抜本的改革――次期学習指導要領改定へ向けての緊急提言」(一九九六年四月二八日)がその一つ。どうやら、外国人にわかる言語技術の訓練を日本語教育の中心課題にせよということのようです。中教審答申でいう「国際化・情報化」に対応しています。その提言の趣旨が「教育科学国語教育・五月臨時増刊号『二一世紀の国語科学習指導要領』」(明治図書刊)に詳述されております。文学作品に関する個所でいうなら「例えば『読者論』による文学作品の解釈を自由に楽しむ仕事は、クラブ活動の受け持ちにしたらよい。すると『この教材の面白さはどうやって教えたらよいか』という難題はなくなる。めでたいではないか』といった調子です。が、冗談ではないようです。自民党の稚拙な個々の作品非難とは違って、教科書から文学作品を抹殺する「指導要領」に改定せよというのでしょう。この提言に、別の論者は賛成意見を述べ「文学的な文章を排除するのではありません。当然『情報』の一種として扱います」といい添えている。文学的文章の読みは「情報を客観的に読みとる」ことの一部分だというのです。
ところで、文学作品を「客観的に読みとる」とは、どういうことでしょうか。ここに「教材研究の定説化2『ごんぎつね』の読み方指導」(明治図書刊)という本があります。「科学的『読み』の授業研究シリーズ」のなかの一冊です。「科学的で客観的な読み」を「言語技術教育としてそれを方法化し体系化」しようと研究を進めている団体の著書。この一冊があれば誰にでも一定水準の授業ができる、というふれこみの本です。
読みには「表層よみ」と「深層よみ」(裏を読む)がある。その深層読みを読みの技術として子どもたちの身につけさせよう。そのためには、完成された教材研究、つまり「教材研究の定説化」が必要だといいます。定説化された教材を一定の手順に従って指導すれば、主題をつかませることができる。その手順を「授業の定式化」と呼んでいます。
『ごんぎつね』に即していうなら、主題は「理解しえなかった愛の悲劇」。この定説、つまり主題をつかませるために「構造読み」「形象読み」「主題読み」の、三段階の読みを設定します。「授業の定式化」です。
(…)
こうした読みでは、読者である子どもの主体は位置付かない。また、教師の主体はどうなるのでしょう。教師の主体を通さない教育は教育の名に値しない。この発想は文教研の基本姿勢を示します。ここでいう授業の定式化は、文学作品の読みではない。主体の変革を促す契機はありません。今次集会のテーマに「文学教育の復権」を掲げた理由です。
(…)
|
|
| ■黙ってはいられない――『21世紀の国語科学習指導要領』を読んで………山口りか(「文学と教育」第180号 1998.3) |
(…)
・文学教育への攻撃
次に引用したのは、一九八一年八月に刊行された「文学と教育」の巻頭言で、福田隆義氏の執筆によるものである。
(引用文略 上掲参照)
そして次に、十六年たった一九九七年秋号「文学と教育」の巻頭言を見ていただきたい。執筆は、福田隆義氏である。
(引用文略 上掲参照)
戦後の国語教育、国語科教育に対する体制側の一貫した文学教育排除の姿勢、そして一貫しながらも社会情勢を反映して表情を変えてきていることが明確に示されている。
今年の文教研全国集会のテーマは〈「文学教育の復権」を訴える――読者論の立場から〉というものであった。その集会を準備する例会で、福田氏が『21世紀の国語科学習指導要領』を問題にされ、私たちの課題をさらに明確にすべきではないかと提案され、全国集会でも報告された。
・『21世紀の国語科学習指導要領』
「生きる力」「国際化・情報化」というような意見反論の余地のないような言葉を使いながら、民衆のよってたつところの母国語の、連帯への思索や発想をつちかう対話の機能を「抹殺」しようとする動き。それを支持している人々の論理が端的に現れているのが『21世紀の国語科学習指導要領』における、いくつかの提言、提案である。そして、その方向性を支持し、推進しているのは、外ならぬ、明治と書編集部の江部満氏なのである。
(引用文略)
これがこの臨時増刊号の原稿依頼の文章の一部、ということらしいのだ。「編集後記」で紹介されている。中教審の答申のまとめかた、お見事、である。しかし、この文章には、決定的な欠陥がある。それは、答申の方向性、目的が、意図的に削除されていることである。「生きる力」や「ゆとり」を失わせていっているのは、一体誰なのか。競争社会、管理社会に適応することを子どもたちに強要し続け、窒息させてきているおおもとはどこなのか。中教審答申、臨教審そしてそれを導き出している文教政策なのではないのだろうか。そうした問題意識を喚起させない文章である。いや、あえてネグレクトして、お上のいうことにはまちがいない、とでも思わせたいとしか感じられないのだ。
(…)
「文学と教育」一五〇号で、樋口正規氏が「教科書はだれのものか――学習指導要領について」で、「……ここで求められているのは“適応”の能力です。今の日本の社会のあり方をよしと認めた上で、それにうまく『対応』できる人間、どんなにひどい世の中でも『たくましく』生きていける人間、それが求められているわけです。(…)」と一九八七年における教科課程審議会の答申について述べられている。
一貫しているのは「適応」の論理なのだ。言語技術主義もまた、である。そして、過去の路線と違ってきているのは、道徳主義的に文学教材を使う、といったやりかたで国家主義をおしつけてくるのではない、という点だろう。多国籍化する世界経済へ適応する日本人を必要とする財界。その要求に応えるための国語教育なのである。例えば海外で、現地の人を雇用し労務管理する日本人として、そのための表現技術を身につけさせよう、ということである。「発信型」としてのディベート技術を磨くことで、日本人としての「誇り」をもって、自己主張や他を説得することのできる子ども――日本人づくり、をめざしているわけである。そのためには、あからさまな国家主義はかえってじゃまにもなる。対外的に前面からはさげたかっこうで、変革への思索を促す文学教育を徹底的に排除し、そうすることで、まさに「国家」に殉じる人間を作り出そうということなのである。
(…)
・今こそ連帯のとき
『こんな教科書あり? ――国語と社会科の教科書を読む』(一九九七、十二、岩波書店)で、谷川俊太郎氏、佐藤学氏、斎藤治郎氏が対談している。一年生から六年生までの教科書を読み通した上で、意見を出し合っている。
「谷川 ……いま文体という観点がまったくないんです。だから一年生のは、すごくチープな日本語からはじまっているんです。骨董屋の丁稚が修業するには、とにかく一流のものをみなきゃいけない。ずっと見続けていれば自然に偽物がわかるようになるという一種の教育論があるわけじゃない。それと同じで、どんなに小さい子どもでも、いい日本語をまず教えていかなきゃいけないと思うんだけど、小学校に入っていちばんはじめの日本語が、「はるの はな/あおい あおい/はるの そら/うたえ うたえ/はるの うた」(『こくご
1上』 教育出版)。無味乾燥といえばいいか、なんの表現にもなっていない。こういうのではじまるというのはねえ。」
「谷川 言語観みたいなものがまちがっているというか、ないんですよ。つまり言葉とは何かということを考える視点がまったくないんだと思う。ぼくなんか、『にほんご』(安野光雅・大岡信・谷川俊太郎・松居直編、岩波書店、一九七九年)という教科書的な本をつくったときに考えた基本点の一つですが、小学校の一年生の子どもはけっこう言語の体験をしているわけでしょ。そういうことを前提にして、まだ未分化な言語観を整理していくというふうに考えたほうがいいというのが基本的な考え方なんだけど、この教科書は白紙からはじめている。子どもの現実から見て実際に白紙ということはありえないですよ。
(中略)
佐藤 光村の一年の教科書で、「すきな もの おしえて」(『こくご 一上 かざぐるま』 光村図書)というのがありますね。「せんせい、すきな たべものを おしえて ください。」そのつぎは、「ようこちゃん、すきな あそびを おしえて ください。」これが日本人に対する日本語教育かと思いますね。まるで外国人に対する日本語教育ではありませんか、といいたくなる。」
(…)
|
こうしたいきいきした論議に私たちも加わっていきたいのだ。言語観、文学観が大事だよね、じゃあその言語観とは? 文学観とは? 一流のものを見せておけば自然に偽物がわかるようになる……じゃあ一流のものってどういうものなのか。自然に、というけれど、それじゃあ教育は必要ないの? 等々、聞いてみたい。文教研が約四十年かけて提案し続け、論理を深めてきたことも、きちんとふまえてもらいたい。いまこそ文学教育なのだ。バラバラに言いたいことを言っているのではなく、手をつないで、反動路線に抗していくべきなのだと思う。
(…)
|
|
■真の伝え合いとは何か――「学習指導要領」における「伝え合う力」批判………井筒 満(「文学と教育」第197号 2003.7)
|
(…)
「学習指導要領」における「伝え合う力」とは、情報化などの社会の変化に適応し、環境不適応現象をおこさないために必要な技能なのである。だが、現代の日本社会(日本型現代市民社会)においては、「3」で話題にした「合意のでっちあげ」が「情報化」を手段として強力に推し進められている。したがって、そのような「合意のでっちあげ」によって飼い馴らされないような豊かで自由な思考活動・想像活動・瑞々しい感情を、生徒たちの中に培っていくことが教育――国語教育の中心課題であるはずだ。そして、そのような認識活動・認識の構えとしての感情は、伝え合うという過程(教師・生徒・教材化された様々な作品との間で行われる)を通して培われるのである。
それは、また、伝え合いによる相互変革を通して、「えせ民主主義」が支配する現状を変革し、真の民主主義を実現する主権者としての資質・メンタリティーを培っていくことでもある。
ところが、「学習指導要領」の「伝え合う力」は、現状への適応能力に過ぎず、現状変革・相互変革という契機が全く抜けおちている。これでは、「伝え合う」という言葉を使う意味がない。現状変革・相互変革という契機を示すために使ってkそ「伝え合う」という言葉は生きるのである。
(…)
教育基本法改正論者たちの主張には、「子どもと教育の危機的状況の原因を戦後改革と教育基本法に求めるという短絡的主張が目立」[(堀尾輝久氏、以下同じ)]つが、「戦後史をたどれば、教育基本法は教育荒廃の原因などではなく、逆に、その精神が不当に軽視され、ゆがめられてきたことこそが問題であり、それが根づくことを妨げてきた政策にこそ、その原因の一端がある」といえる。彼等の主張は、「二一世紀をアメリカを軸とするグローバリゼーションと国際緊張を避けがたい所与のものとして前提し、そこでの生き残りをかけた大競争(メガ・コンペティション)の時代として捉え、経済の世界だけではなく教育の世界においても競争の原理と能力主義を徹底し、強者を良しとし、弱者を切り捨てる考えで徹底させようとするもので」ある。それは、「大競争にうち克つための人材養成を目標」とし、「一般大衆には有事に際して公=国家に奉仕する愛国心教育を強調する」という特徴をもっている。
(…)
このような「教育改革」を実現するために、国語教育の果すべき目標として登場してきたのが「伝え合う力」なのである。大競争に打ち克ち、大企業の利潤獲得に最も貢献できる人材になるために必要な「発信−受信」能力、また、低賃金や無権利状態が押しつけられても環境不適応現象をおこさず耐え続ける人間になるための「発信−受信」能力、それが「伝え合う力」なのである。
学習指導要領的な「伝え合う力」の正体は、「愛国心教育」の実態をみることでも明かになる
(…)
文部科学省は、という大成を一方では教師を処分で黙らせるという体制を強化しながら、国語の授業では、生徒が「伝え合う力」を身につけられるように指導せよと教師に要求しているわけである。こうした現状が存在するにもかかわらず、学習指導要領が目標としている「伝え合う力」は、相手の苦しみや悲しみを理解できる想像力や思考力によって支えられた能力(川本氏)だなどと言っても、何の説得力も持たないだろう。偽装していても、「伝え合う力」が目指しているのは命令型のコミュニケーションに他ならない。
相談型コミュニケーションの担い手は、真の民主主義・民主教育を実現するための様々な実践の中でこそ形成されるのである。
|
|