| 第57回全国集会(2008.8) | 文学史を教師の手に | ||
| 【統一テーマ】 “自分”を切り拓く“笑い”の文学――太宰治「畜犬談」とケストナー「一杯の珈琲から」 |
(第31回と同文) | ||
私たちは、全国集会で、これまで一貫して“笑い”の文学――すぐれた喜劇精神に根ざす“笑い”の文学を取り上げてきた。それは、個々人を分断し、人間らしさを奪い取ろうとする圧力が充満している現代の日本社会の中で、自分自身を見失わないために、また、そのような圧力に負けないで、真の仲間づくりを実現していく対話精神を私たち一人一人の内部に培うために、“笑い”の文学と対話することが不可欠だと考えたからである。 今回も、そのような課題意識からこの二作品を取り上げた。 『一杯の珈琲から』は、ナチスによってケストナー作品のドイツ国内での出版が禁止されていたため、1938年にスイスで出版された。(原作の題名は「ゲオルクと突発事件」、49年の戦後版は『小さな国境往来』と改題された。)また、太宰の「畜犬談」は1939年に発表された作品である。ファシズムが支配するドイツと日本――二人の作家は、自分が生きている現実の中でどのように闘っているか。そこで発揮される喜劇精神の共通性とそれぞれに固有なものとは何か。ゼミの中で検討していきたい。 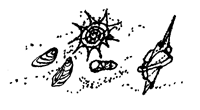 なお、『一杯の珈琲から』は、去年の秋季集会(07年11月23日)でも取り上げた作品であるが、作品の検討が不十分であった。その後、例会で検討を続け、全国集会で再度とりあげようということになった。今回は、最新刊「文学と教育」208号に、私たちが共同で作成したこの作品に関する〈注〉が掲載されている。この〈注〉に関しても今回の集会でぜひ検討していただきたい。 |
|||